1. はじめに
パルスオキシメーター管理は、患者さんの呼吸状態を継続的に監視する重要な看護技術の一つです。実習現場では「SpO2が下がっています」という報告をよく耳にしますが、単に数値を読み取るだけでなく、患者さんの全身状態を総合的にアセスメントする力が求められます。
この技術は、酸素療法を受けている患者さんや呼吸器疾患のある方、手術前後の患者さんなど、幅広い対象に実施される基本的でありながら専門性の高い技術です。正確な測定と適切な判断により、患者さんの安全を守り、早期の異常発見につながります。
近年の医療現場では、パルスオキシメーターによる監視は24時間体制で行われることが多く、看護師は測定値の変化を敏感に察知し、患者さんの状態変化に迅速に対応することが期待されています。また、在宅医療の普及により、患者さん自身や家族への指導も看護師の重要な役割となっています。
この記事で学べること
• パルスオキシメーターの原理と正確な装着方法
• 測定値の正常範囲と異常時の対応方法
• 測定に影響する因子とその対策
• 患者さんの個別性に応じた管理方法
• 実習で遭遇しやすいトラブルシューティング
2. パルスオキシメーター管理の基本情報
定義
パルスオキシメーター管理とは、専用の機器を用いて経皮的に動脈血酸素飽和度(SpO2)と脈拍数を非侵襲的に測定し、患者の呼吸・循環状態を継続的に監視する技術
技術の意義と目的
パルスオキシメーター管理の最大の意義は、患者さんの酸素化状態をリアルタイムで把握できることです。従来は動脈血ガス分析という侵襲的な検査でしか正確な酸素化状態を知ることができませんでしたが、この技術により痛みを伴わずに継続的な監視が可能となりました。
患者さんにとっては、呼吸困難感がある際の客観的な評価や、酸素療法の効果判定において安心感を得られます。「息苦しいです」という訴えに対して、具体的な数値で状態を把握し、適切な対応を受けることができるのです。
看護師にとっては、呼吸状態の悪化を早期に発見し、医師への報告や緊急時対応のタイミングを適切に判断するための重要な指標となります。また、酸素療法中の患者さんの安全管理や、リハビリテーション時の活動耐性評価にも欠かせません。
実施頻度・タイミング
手術後や重篤な疾患のある患者さんでは24時間持続監視を行います。一般病棟では、バイタルサイン測定時(通常1日3-4回)や処置前後、歩行訓練時などに測定することが多いです。呼吸器疾患のある患者さんでは、症状に応じて随時測定を行い、酸素療法を受けている場合は酸素流量変更前後での評価が重要です。
3. 必要物品と準備
基本的なパルスオキシメーター管理用品
パルスオキシメーター本体は、携帯型と据え置き型があります。携帯型は回診や処置時の一時的測定に適しており、据え置き型は持続監視に使用します。センサープローブは測定部位に応じて指用、耳用、足用などがあり、患者さんの状態や年齢に応じて選択します。
電源関連では、バッテリー式の場合は充電状態の確認が必要で、電池式では予備電池の準備も重要です。アラーム設定機能がある機器では、患者さんの状態に応じた適切な上下限値の設定が求められます。
センサープローブは使い捨て(ディスポーザブル)タイプと再利用(リユーザブル)タイプがあり、感染管理の観点から使い分けが必要です。
状況別対応用品
感染対策用品として、センサープローブの消毒に使用するアルコール綿やディスポーザブルワイプが必要です。血液や体液で汚染される可能性がある場合は、使い捨て手袋の着用も検討します。
マニキュアや汚れで測定が困難な場合に備えて、除光液やアルコール綿、爪ブラシなどの清拭用品を準備します。測定部位の循環不良がある場合は、温めるためのホットパックや血流改善のためのマッサージ用品も用意しておくと良いでしょう。
小児や不穏な患者さんの場合は、センサープローブを固定するためのテープや包帯、センサープローブを保護するための保護カバーが必要になることがあります。
物品準備のポイント
患者さんの個別性を考慮した物品選択が重要です。高齢者では皮膚の脆弱性を考慮してテープ類は低刺激性のものを選び、小児では装着感の少ない小児用センサーを選択します。循環障害のある患者さんでは、測定部位を複数準備し、定期的な部位変更ができるよう配慮が必要です。
4. パルスオキシメーター管理の実施手順
事前準備とアセスメント
まず患者さんの全身状態を観察し、意識レベル、呼吸状態、皮膚色、冷感の有無を確認します。測定予定部位の皮膚状態、循環状態、マニキュアの有無、浮腫の程度などを評価し、最適な測定部位を選択します。
機器の動作確認では、電源の投入、バッテリー残量、センサープローブの接続状態を確認し、必要に応じてセルフテストを実施します。患者さんには測定の目的と方法を説明し、「指に小さなクリップのような器具を付けて、血液中の酸素の量を測らせていただきます」といった分かりやすい表現で理解を得ます。
環境整備として、強い光源(手術用照明、赤外線ランプなど)の影響を避け、電気的干渉を起こす可能性のある機器から離れた場所で測定を行います。
基本手順
センサープローブの装着では、指用センサーの場合、爪が上になるよう装着し、光源と受光部が爪を通して対向するよう位置を調整します。装着の強さは、センサーが外れない程度で、かつ循環を阻害しない程度とし、指先の色調変化がないことを確認します。
測定部位は第2指(人差し指)が最も適しており、次に第3指(中指)を選択します。拇指は動きやすく、小指は細すぎるため避けることが一般的です。循環不良や浮腫がある場合は、耳朶や足指での測定も検討します。
機器の設定では、患者さんの状態に応じてアラーム範囲を設定します。一般的にSpO2の下限は95%、脈拍数は50-120回/分程度に設定しますが、慢性呼吸器疾患のある患者さんでは個別に調整が必要です。
実施中の観察ポイント
測定中は波形の安定性を確認し、良好な脈波が得られていることを波形表示で確認します。数値の変動が大きい場合は、体動や不整脈、循環不良などの原因を検索し、必要に応じて測定部位の変更や再装着を行います。
持続監視中は定期的(2-4時間ごと)に測定部位の皮膚状態を観察し、圧迫による皮膚障害の予防を行います。特に循環不良のある患者さんでは、測定部位の変更を1-2時間ごとに行うことが推奨されます。
患者さんの自覚症状と測定値の関係を観察し、「息苦しい」という訴えと数値の変化が一致しているかを評価します。また、酸素療法を行っている場合は、酸素流量や酸素濃度と測定値の関係も継続的に観察します。
5. 特殊な状況でのパルスオキシメーター管理
循環不良・ショック状態の患者
末梢循環不良やショック状態では、指先での測定が困難になることがあります。このような場合は、より中枢に近い部位である耳朶や前額部での測定を検討します。測定部位を温めることで血流を改善し、測定精度を向上させることも有効です。
血管収縮剤を使用している患者さんでは、特に末梢循環が悪化しやすいため、測定値の信頼性を慎重に評価し、必要に応じて動脈血ガス分析での確認を医師に相談することが重要です。
小児・新生児への対応
小児では成人用センサーが大きすぎる場合があるため、専用の小児用センサーを使用します。新生児では足指や手指での測定が一般的で、センサーの重さで指が下がらないよう体位に注意が必要です。
活発に動く小児では、センサーが外れやすいため、適切な固定方法を検討し、保護者の協力を得ながら測定を継続します。また、小児は成人よりも酸素飽和度が高めに維持されることが多く、正常値は97-100%とされています。
慢性呼吸器疾患患者への対応
慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの患者さんでは、平常時の酸素飽和度が健常人より低いことがあります。このような患者さんでは、通常90-95%程度が目標値となることが多く、個々の患者さんの平常値を把握しておくことが重要です。
急激な酸素投与により炭酸ガス貯留(CO2ナルコーシス)を起こす危険性があるため、酸素療法中の観察では意識レベルの変化にも注意を払い、SpO2の急激な上昇も警戒する必要があります。
手術中・麻酔中の監視
手術中は体動がないため安定した測定が可能ですが、体位変換や手術操作により測定部位の循環が阻害される場合があります。手術体位に応じて測定部位を選択し、術中の体位変換時には測定値の変化を注意深く観察します。
麻酔薬や筋弛緩薬の影響で呼吸抑制が起こりやすいため、SpO2の変化は呼吸状態悪化の早期発見に重要な指標となります。術後の覚醒過程では、患者さんの体動により測定値が不安定になりやすいため、波形の質も含めて総合的に評価します。
6. パルスオキシメーター管理中の観察とアセスメント
測定中に得られる情報は、SpO2値と脈拍数だけでなく、脈波の波形や変動パターンも重要な観察項目です。良好な脈波は規則的で振幅が安定しており、この波形の変化から循環状態や測定の信頼性を評価できます。
SpO2値の評価では、単一の数値ではなく経時的な変化パターンを重視します。急激な低下は呼吸器系の異常を示唆し、徐々に低下する場合は慢性的な呼吸機能低下や心機能低下の可能性があります。また、酸素療法中にも関わらずSpO2が改善しない場合は、肺炎や無気肺などの重篤な病態を疑う必要があります。
脈拍数の観察では、頻脈や不整脈の検出が可能です。SpO2の低下と同時に頻脈が認められる場合は、呼吸不全に対する代償反応として心拍数が増加している可能性があります。逆に、重篤な低酸素血症では徐脈が認められることもあり、この場合は緊急度が非常に高い状態です。
患者さんの自覚症状との関連性も重要な観察ポイントです。「息が苦しい」「胸が痛い」といった訴えとSpO2値の変化が一致している場合は、測定値の信頼性が高いと判断できます。しかし、高齢者や意識レベルの低下した患者さんでは、自覚症状がない場合もあるため、客観的な測定値により病状判断を行う必要があります。
7. 看護のポイント
主な看護診断 • ガス交換障害 • 非効果的呼吸パターン • 活動耐性低下 • 知識不足
ゴードンの機能的健康パターン別観察項目
活動・運動パターンでは、日常生活動作時のSpO2の変化を観察し、患者さんの活動耐性を評価します。歩行や階段昇降、入浴などの活動時にSpO2が著明に低下する場合は、活動制限や酸素療法の適応を検討する必要があります。安静時と活動時のSpO2の差が大きい患者さんでは、段階的な活動量増加や適切な休息間隔の設定が重要です。
睡眠・休息パターンでは、睡眠時無呼吸症候群の患者さんにおいて、睡眠中のSpO2変動を観察することが診断や治療効果判定に役立ちます。夜間の酸素飽和度低下は、日中の眠気や疲労感の原因となることがあり、患者さんの生活の質に大きく影響します。
認知・知覚パターンでは、低酸素血症による意識レベルの変化や認知機能の低下を早期に発見することが重要です。特に高齢者では、軽度の酸素飽和度低下でも認知機能に影響を与えることがあり、せん妄の原因となる場合もあります。
ヘンダーソンの基本的欲求からみた看護
呼吸の欲求に対しては、パルスオキシメーターによる監視を通じて患者さんの呼吸機能を支援します。効果的な呼吸法の指導、適切な体位の保持、酸素療法の管理など、科学的根拠に基づいた呼吸ケアを提供し、患者さんが自立して呼吸機能を維持できるよう支援します。
安全の欲求については、SpO2の異常値を早期に発見し、適切な医学的介入につなげることで患者さんの生命の安全を守ります。また、酸素療法中の安全管理、転倒予防、活動制限の適切な判断により、二次的な事故の予防も重要な看護介入です。
学習の欲求に対しては、患者さんや家族に対してパルスオキシメーターの意味や正常値について分かりやすく説明し、在宅での自己管理能力を向上させます。慢性呼吸器疾患の患者さんでは、自己監視により病状変化を早期に察知し、適切な医療機関受診につなげる能力の習得を支援します。
具体的な看護介入
最も優先度が高いのは、SpO2低下時の迅速な原因検索と対応です。気道分泌物の増加、気道閉塞、肺水腫、気胸などの可能性を系統的に評価し、吸引、体位変換、酸素流量調整、医師への報告など適切な初期対応を行います。この際、患者さんの不安軽減のために、状況説明と安心感を与える声かけも重要な看護介入です。
次に重要なのは、個別性を考慮した測定方法の選択と環境調整です。患者さんの病態、年齢、皮膚状態、循環状態に応じて最適な測定部位とセンサータイプを選択し、正確な測定値を得られるよう環境を整備します。測定部位の定期的な変更により皮膚障害を予防し、患者さんの快適性を保持します。
三番目として、患者さんと家族への教育と自己管理支援があります。パルスオキシメーターの意義と正常値について説明し、異常時の対応方法を指導します。在宅療養に向けては、機器の操作方法、測定のタイミング、記録方法、緊急時の連絡方法などを具体的に指導し、安全な在宅管理を支援します。
最後に、多職種連携による包括的なケアの調整も重要な看護介入です。医師、理学療法士、薬剤師、医療ソーシャルワーカーなどと連携し、患者さんの呼吸機能改善と生活の質向上を目指した総合的なケアプランを立案・実施します。
8. よくある質問・Q&A
Q:SpO2が一時的に90%を下回りました。すぐに酸素投与をするべきでしょうか?
A: まず患者さんの全身状態を迅速に観察し、意識レベル、呼吸状態、皮膚色を確認してください。測定値の信頼性をチェックするため、センサーの装着状態や患者さんの体動の影響がないかも確認が必要です。
酸素投与の判断は医師の指示に従いますが、緊急時には看護師も初期対応として酸素投与を開始することがあります。その際は、患者さんの既往歴(特にCOPD)を確認し、適切な酸素流量から開始します。同時に、医師への報告と指示受けを速やかに行うことが重要です。
Q:マニキュアをしている患者さんで測定値が不正確のようです。どうすれば良いでしょうか?
A: マニキュアは光の透過を妨げるため、測定精度に影響を与えます。可能であれば除光液で除去することが最も確実ですが、患者さんの了解が得られない場合は別の測定部位を選択します。
足指での測定や耳朶用センサーの使用を検討してください。また、マニキュアが薄い色の場合は、センサーを横向きに装着する方法(側面測定)で測定可能な場合もあります。どの方法でも安定した測定ができない場合は、医師に動脈血ガス分析の必要性について相談することをお勧めします。
Q:小児の患者さんでセンサーがすぐ外れてしまいます。良い固定方法はありますか?
A: 小児専用の小さなセンサーを使用することが基本です。固定には医療用テープを使用しますが、皮膚に直接貼らず、センサー部分のみを軽く固定する方法を試してください。
包帯や弾性包帯で優しく巻く方法も効果的です。ただし、循環を妨げないよう、指先の色調変化がないことを頻繁に確認してください。保護者に協力を求め、お子さんの気をそらすような遊びや話し相手になってもらうことも、測定継続に役立ちます。どうしても困難な場合は、医師と相談して測定の必要性と頻度を再検討することも重要です。
Q:夜勤中にアラームが頻繁に鳴りますが、患者さんに異常はないようです。どう対応すれば良いでしょうか?
A: まず、アラーム設定値が患者さんの状態に適切かを確認してください。慢性呼吸器疾患の患者さんでは、平常時のSpO2が健常人より低いことがあり、個別に設定調整が必要です。
センサーの装着状態も再確認し、緩い装着や体動による影響がないかチェックしてください。睡眠中は体位変換により一時的に数値が変動することもあります。患者さんの睡眠を妨げないよう、適切なアラーム範囲の設定について医師と相談し、必要に応じて夜間のアラーム設定を調整することを検討してください。ただし、安全性を損なわない範囲での調整であることが重要です。
9. まとめ
パルスオキシメーター管理は、非侵襲的でありながら患者さんの生命に直結する重要な情報を提供する看護技術です。単純に数値を読み取るだけでなく、患者さんの全身状態と関連付けて総合的にアセスメントする能力が求められます。
覚えるべき重要数値・基準
- 正常なSpO2値:95-100%(健常成人)
- 慢性呼吸器疾患患者の目標値:90-95%
- 小児の正常値:97-100%
- 測定部位変更の間隔:1-2時間ごと(循環不良時)
- 一般的なアラーム設定:下限95%、脈拍数50-120回/分
実習・現場で活用できるポイント
実習では、患者さんの個別性を重視したアセスメント力の向上を心がけてください。同じSpO2値でも、患者さんの基礎疾患や平常時の数値、自覚症状の有無により対応が異なることを理解し、常に根拠に基づいた看護判断を行うことが重要です。また、測定技術の正確性だけでなく、患者さんへの説明や不安軽減への配慮も忘れずに実践してください。
技術習得においては、正確な測定方法の確実な実施と、異常時の迅速な対応能力を身につけることを目標とし、多職種連携の重要性も常に意識して患者ケアに取り組んでください。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
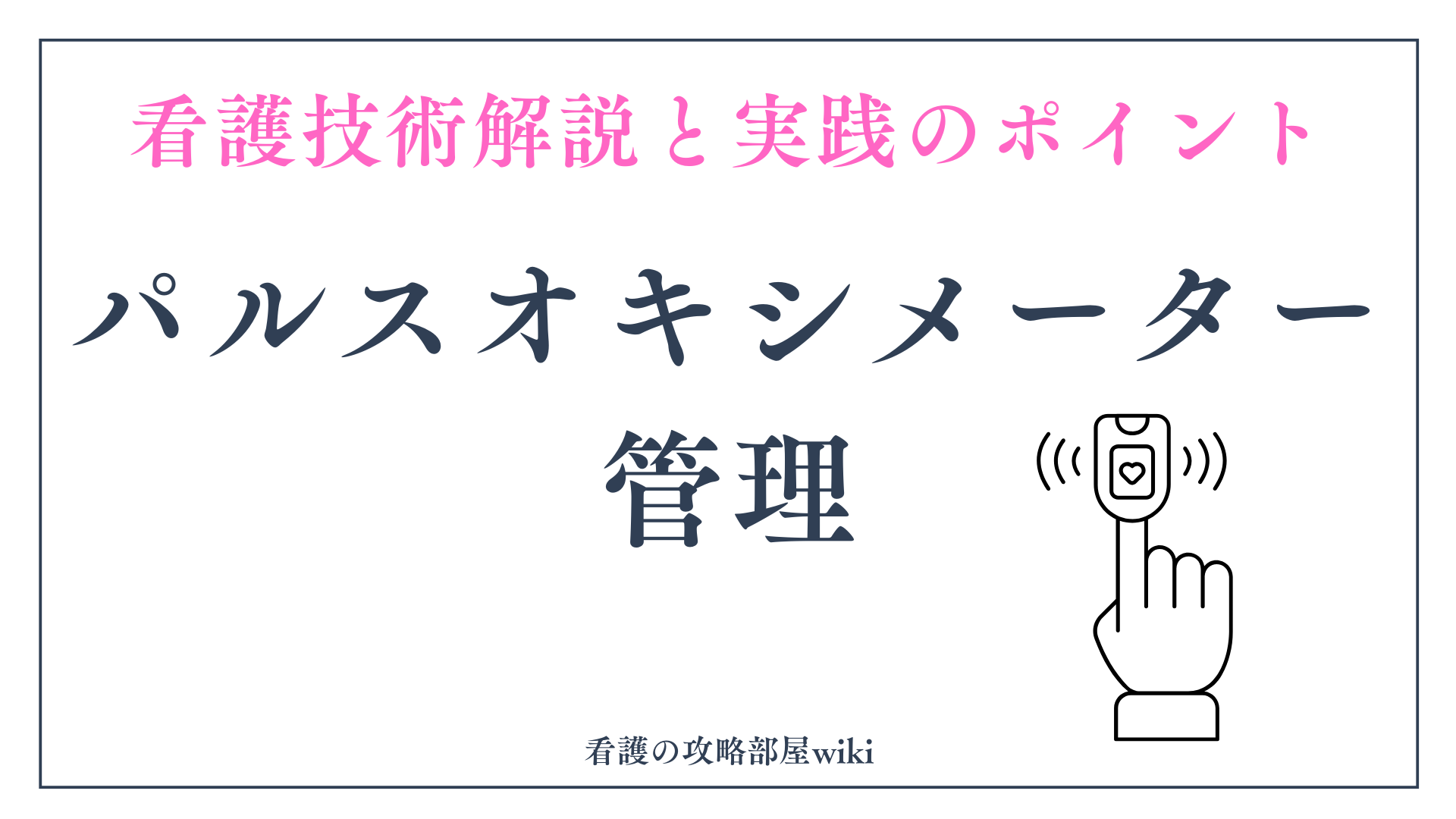


コメント