1. はじめに
実習初日、患者さんのベッドサイドに立った瞬間の緊張感を覚えていますか?「バイタルサインを測らせていただきます」と声をかけるその一言から、看護師としての実践が始まります。バイタルサイン測定は、看護技術の中でも最も基本的でありながら、患者さんの生命に直結する重要な技術です。
バイタルサイン測定は単なる数値の記録ではありません。患者さんの「今」を知り、変化を察知し、適切な看護介入につなげるための貴重な情報収集の場です。体温計の冷たさに身を縮める患者さんの反応から、血圧測定時の表情の変化まで、すべてが看護アセスメントの材料となります。
実習では毎日のように行うこの技術だからこそ、正確で安全な方法を身につけ、患者さんとのコミュニケーションの機会として活用していくことが大切です。
この記事で学べること
- バイタルサイン測定の正確な手技と正常値・異常値の判断基準
- 患者さんの状態に応じた測定方法の選択と個別性への配慮
- 測定中の観察ポイントと異常時の対応方法
- ゴードンとヘンダーソンの理論を活用したアセスメント技術
- 実習や現場で自信を持って実践できる具体的なコツとポイント
2. バイタルサイン測定の基本情報
定義
バイタルサイン測定とは、体温・脈拍・呼吸・血圧の4項目を測定し、患者の生命徴候を客観的に評価する基本的な看護技術
技術の意義と目的
バイタルサイン測定は、患者さんにとって健康状態の客観的な指標となり、体調変化の早期発見や治療効果の判定に欠かせない情報を提供します。「なんとなく調子が悪い」という患者さんの訴えを、具体的な数値として可視化できる重要な手段でもあります。
看護師にとっては、患者さんの全身状態を総合的に把握し、適切な看護計画を立案するための基礎データとなります。また、医師や他職種との情報共有においても、共通言語として機能する重要な役割を担っています。
実施頻度・タイミング
一般的には入院時、1日3~4回(朝・昼・夕・眠前)の定期測定に加え、患者さんの状態変化時や医師の指示に応じて随時測定を行います。手術前後、薬剤投与前後、症状出現時など、患者さんの状況に応じて測定頻度を調整することが重要です。
3. 必要物品と準備
基本的なバイタルサイン測定用品
体温計(電子体温計・耳式体温計)、血圧計(手動式・自動式)、聴診器、秒針付き時計またはストップウォッチ、記録用紙または電子カルテ端末、ペン、消毒用アルコール綿、ディスポーザブル体温計カバー
感染対策・安全管理用品
手指消毒剤、使い捨て手袋、マスク、体温計プローブカバー、血圧計カフの消毒用品、聴診器用消毒綿
特殊状況対応用品
小児用血圧計カフ、大型血圧計カフ、水銀柱式血圧計(手動測定用)、パルスオキシメーター、体温計用潤滑剤(直腸測定時)
物品準備のポイント
患者さんの年齢、体格、意識レベル、基礎疾患を考慮して適切な測定器具を選択することが重要です。例えば、不整脈のある患者さんには聴診器を用いた手動血圧測定が適している場合があり、意識レベルの低い患者さんには耳式体温計が安全で迅速な測定を可能にします。
4. バイタルサイン測定の実施手順
事前準備とアセスメント
患者さんの現在の状態を観察し、測定に影響する要因(食事、運動、入浴、薬剤投与など)がないかを確認します。測定環境を整え、プライバシーに配慮した空間を作ります。患者さんに測定の目的と方法を説明し、協力を得ることで、より正確な測定が可能になります。
体温測定手順
腋窩測定の場合、腋窩部の汗を清拭し、体温計を腋窩の最深部に当て、上腕で体温計をしっかりと固定します。測定時間は電子体温計で約1~2分、水銀体温計で約10分間保持します。測定中は患者さんの表情や発汗状態を観察し、正常値36~37℃を基準に評価します。
脈拍測定手順
橈骨動脈に人差し指、中指、薬指の3本の指腹を軽く当て、15秒間測定し4倍して1分間の脈拍数を算出します。不整脈が疑われる場合は1分間の完全測定を実施します。正常成人の脈拍数は60~100回/分で、リズム、強弱、緊張度も同時に評価します。
呼吸測定手順
患者さんに気づかれないよう、脈拍測定に続いて胸郭の上下動を観察します。正常成人の呼吸数は12~20回/分で、1分間測定を基本とします。呼吸の深さ、リズム、努力性の有無、呼吸音の異常についても観察します。
血圧測定手順
適切なサイズのカフを上腕に巻き、カフの下縁を肘窩部より2~3cm上方に位置させます。聴診器を上腕動脈上に当て、カフを収縮期血圧予想値より20~30mmHg高く加圧します。2~3mmHg/秒のペースでゆっくりと減圧し、コロトコフ音の出現点を収縮期血圧、消失点を拡張期血圧として記録します。
実施中の観察ポイント
測定中は患者さんの表情、皮膚色、発汗状態、呼吸パターンの変化を継続的に観察します。測定値だけでなく、患者さんの主観的な訴えや非言語的なサインにも注意を払い、総合的な状態評価を行います。
5. 特殊な状況でのバイタルサイン測定
意識レベル低下患者への対応
意識レベルが低下している患者さんには、耳式体温計の使用や自動血圧計による測定が安全で効率的です。体位変換が困難な場合は、側臥位での測定方法を選択し、測定中の体動による誤差を最小限に抑えます。
不整脈患者への配慮
不整脈のある患者さんには、自動血圧計よりも聴診器を用いた手動測定が正確な値を得やすくなります。脈拍は必ず1分間の完全測定を行い、不整脈の種類や頻度についても記録します。
小児患者での測定のコツ
小児の場合、年齢に応じた正常値の把握が重要です。測定時は保護者の協力を得て、遊びの要素を取り入れながら恐怖感を軽減します。小児用カフの使用や、短時間での迅速な測定を心がけます。
発熱患者への対応
発熱時は発汗による体温計の滑りや、悪寒戦慄による測定困難が予想されます。測定前の清拭を丁寧に行い、必要に応じて測定間隔を短縮して経時変化を把握します。
6. バイタルサイン測定中の観察とアセスメント
測定中に得られる重要な観察項目として、皮膚の色調と温度感、発汗の程度と部位、呼吸パターンと呼吸困難の有無、意識レベルと反応性があります。体温38℃以上の発熱時には感染の可能性を考慮し、脈拍100回/分以上の頻脈では心疾患や脱水を疑います。
収縮期血圧90mmHg未満、拡張期血圧60mmHg未満の低血圧や収縮期血圧140mmHg以上、拡張期血圧90mmHg以上の高血圧は、循環器系の異常や薬物の影響を示唆する重要なサインです。これらの異常値は単独で判断せず、患者さんの基礎疾患、症状、他のバイタルサインとの関連性を総合的に評価することが重要です。
7. 看護のポイント
主な看護診断
- 体温調節異常:発熱・低体温に関連した体温調節機能の変調
- 心拍出量減少:循環器疾患や脱水による心機能低下
- 非効果的呼吸パターン:呼吸器疾患や疼痛による呼吸機能障害
- 感染リスク状態:免疫力低下や侵襲的処置による感染の危険性
ゴードンの機能的健康パターン別観察項目
栄養・代謝パターンでは、体温調節機能と発熱パターンを重点的に評価します。発熱時の食事摂取量、水分摂取状況、皮膚の状態変化を観察し、脱水症状の早期発見に努めます。活動・運動パターンでは、脈拍数と血圧値から心機能と循環動態を評価し、活動時の息切れや動悸の有無を確認します。睡眠・休息パターンでは、夜間の体温変動や安静時のバイタルサインから、患者さんの回復力と身体的ストレスの程度を判断します。
ヘンダーソンの基本的欲求からみた看護
正常に呼吸するという基本的欲求に対しては、呼吸数と呼吸パターンの観察を通じて、呼吸困難の早期発見と適切なポジショニングによる呼吸支援を提供します。適切に飲食するという欲求では、発熱時の水分需要増加や食欲不振に対応し、適切な栄養・水分管理を行います。体温を正常範囲内に保つという欲求に対しては、発熱時の冷却や保温による体温調節支援と、快適な環境調整を実施します。
具体的な看護介入
最優先となるのは、異常値を認めた際の迅速な報告と医師との情報共有です。体温38.5℃以上、脈拍120回/分以上、血圧収縮期180mmHg以上または80mmHg未満の場合は、速やかに医師へ報告し、必要に応じて追加の検査や治療介入を検討します。
継続的なモニタリングでは、患者さんの状態変化を早期に察知するため、定期的な測定スケジュールの遵守と、患者さんの主観的症状との照らし合わせを行います。測定間隔の調整や測定方法の変更についても、患者さんの状態に応じて柔軟に対応します。
患者・家族への教育支援として、自宅でのセルフモニタリング方法の指導や、異常値の意味と対処方法について分かりやすく説明します。特に慢性疾患を持つ患者さんには、日常生活での注意点と受診のタイミングについて具体的にアドバイスします。
8. よくある質問・Q&A
Q:血圧測定で左右の腕で値が違うのですが、どちらを記録すればよいですか?
A: 初回測定時は両腕で測定し、高い方の値を基準値として採用するのが一般的です。左右差が10mmHg以上ある場合は医師に報告しましょう。継続的な測定では、常に同じ側で測定することで経時変化を正確に把握できます。
Q:患者さんが「いつもより血圧が高い」と心配されています。どう説明すればよいですか?
A: 血圧は一日の中でも変動があることを説明し、測定前の活動、食事、排泄、精神的緊張などが影響することを伝えます。単回の測定値だけでなく、継続的な観察が重要であることを強調し、心配な点は医師に相談するよう促します。
Q:体温測定で腋窩と耳式で値が異なる場合、どちらが正確ですか?
A: どちらも正確な方法ですが、測定部位による生理的な差があります。腋窩温は体表温、耳式は鼓膜温を反映するため、耳式の方が0.5℃程度高く出ることがあります。同一患者さんでは一貫して同じ方法で測定することが重要です。
Q:脈拍が不規則な患者さんの場合、どのように測定すればよいですか?
A: 不整脈がある場合は、15秒測定ではなく1分間の完全測定を行います。脈拍の強弱やリズムの変化も記録し、可能であれば聴診器で心音も聴取して、心拍数と脈拍数の違い(脈拍欠損)がないかを確認しましょう。
9. まとめ
バイタルサイン測定は看護の基本中の基本でありながら、患者さんの生命と直結する重要な技術です。正確な測定技術を身につけることはもちろん、測定値の意味を理解し、患者さんの全体像と照らし合わせながら適切な看護判断を行うことが求められます。
覚えるべき重要数値・基準
- 体温:36~37℃(腋窩)
- 脈拍:60~100回/分(成人)
- 呼吸:12~20回/分(成人)
- 血圧:収縮期90~139mmHg、拡張期60~89mmHg
- 緊急報告基準:体温38.5℃以上、脈拍120回/分以上、血圧収縮期180mmHg以上または80mmHg未満
実習・現場で活用できるポイント
実習では、測定技術の習得だけでなく、患者さんとのコミュニケーションの機会として活用しましょう。「今日は調子いかがですか?」という声かけから始まる会話は、貴重な情報収集の時間となります。異常値を発見した際は、慌てずに再測定を行い、患者さんの状態と照らし合わせながら、指導者や医師への報告を行うことが大切です。バイタルサイン測定を通じて得られる情報を、ゴードンの機能的健康パターンやヘンダーソンの基本的欲求と関連付けて考察することで、より深い看護アセスメント能力を身につけることができます。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。


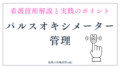
コメント