1. はじめに
実習先で「患者さんの口唇が乾燥している」「皮膚のツルゴールが悪い」「尿量が少ない」という場面に遭遇したことはありませんか?これらは脱水の典型的なサインです。
脱水は、体内の水分と電解質のバランスが崩れた状態で、あらゆる医療現場で頻繁に遭遇する病態です。特に高齢者や小児、慢性疾患を持つ患者さんでは、軽微な原因でも急速に進行し、生命に危険をもたらすことがあります。
私たちの体は約60%が水分で構成されており、この水分バランスの維持は生命維持の基本中の基本です。看護師には、脱水の発生メカニズムを理解し、早期発見・早期対応により患者さんの安全を守ることが求められています。
この記事で学べること
- 脱水の分類と各タイプの特徴
- 体液バランスの調節メカニズム
- 脱水の早期発見のための観察ポイント
- 適切な水分・電解質補給の方法
- 予防的なケアと患者・家族への指導
2. 病態の基本情報
定義
体内の水分と電解質の喪失により、体液量が正常範囲を下回った状態
疫学
脱水は入院患者の約20-30%に認められ、特に65歳以上の高齢者では40%以上に何らかの脱水症状が見られます。救急外来を受診する高齢者の約15%が脱水を主訴としており、夏季には熱中症に伴う脱水で搬送される患者が急増します。小児では下痢・嘔吐による脱水が多く、年間約10万人が脱水で医療機関を受診しています。
分類・病型
脱水は浸透圧の変化により3つのタイプに分類されます。高張性脱水(水欠乏性脱水)は水分の喪失が電解質の喪失を上回る状態で、発熱や発汗過多で見られます。等張性脱水(混合性脱水)は水分と電解質が同程度に失われる状態で、下痢・嘔吐や出血で起こります。低張性脱水(塩類欠乏性脱水)は電解質の喪失が水分の喪失を上回る状態で、利尿薬の使用や大量発汗時の水分のみの補給で生じます。
重症度別では、軽度脱水(体重減少3-5%)、中等度脱水(体重減少6-9%)、重度脱水(体重減少10%以上)に分類され、重度では生命に危険が及びます。
原因別分類では、摂取不足(経口摂取困難、意識障害)、喪失過多(下痢、嘔吐、発汗、利尿薬)、第三間隙への移行(腹水、浮腫)に分けられます。
3. 病態生理
基本メカニズム
体液バランスは、まるで精密に調整された家の給水システムのような仕組みで維持されています。正常な成人では、毎日約2-2.5Lの水分を摂取し、同量を排泄することでバランスを保っています。
この調節には視床下部、下垂体後葉、腎臓が重要な役割を果たします。体内の水分が不足すると、血液の浸透圧が上昇し、視床下部の浸透圧受容器が感知します。すると抗利尿ホルモン(ADH)が分泌され、腎臓での水分再吸収が促進されます。同時にレニン・アンジオテンシン・アルドステロン系が活性化し、ナトリウムと水分の保持が図られます。
また、口渇中枢が刺激されて喉の渇きを感じ、水分摂取行動を促します。これらの機構により、正常時は体液量が厳密に調節されています。
進行過程
脱水の進行は、まるで水槽の水が徐々に減っていくような段階的な変化を示します。
軽度脱水(体重減少3-5%)では、代償機構が働き始めます。患者さんは「のどが渇く」と感じ、腎臓では尿濃縮が起こり尿量が減少します。この段階では、日常生活にはほとんど支障がありません。
中等度脱水(体重減少6-9%)では、循環血液量の減少により循環動態に変化が現れます。「立ちくらみがする」「だるい」「頭痛がする」という訴えが聞かれ、皮膚の乾燥や弾力性の低下も明らかになります。高齢者では軽度の意識レベルの低下も見られることがあります。
重度脱水(体重減少10%以上)では、循環不全により生命に危険が及びます。血圧低下、頻脈、意識障害、乏尿・無尿が出現し、緊急の輸液治療が必要となります。患者さんは「気分が悪い」「息苦しい」と訴え、時として意識を失うこともあります。
病型別の違い
高張性脱水では、細胞内から細胞外への水分移動により、相対的に循環血液量が保たれやすく、循環症状は軽度です。しかし、脳細胞の脱水により意識障害や痙攣が起こりやすくなります。
等張性脱水では、細胞内外の浸透圧が保たれるため、循環血液量の減少が顕著に現れ、ショック症状を起こしやすいのが特徴です。
低張性脱水では、細胞外から細胞内への水分移動により脳浮腫が生じ、頭痛、嘔気、意識障害、痙攣などの症状が現れやすくなります。
合併症・併発する病態
脱水による主な合併症として急性腎障害があります。腎血流量の減少により糸球体濾過率が低下し、老廃物の排泄ができなくなります。血清クレアチニン値の上昇(正常値:男性0.65-1.07mg/dL、女性0.46-0.79mg/dL)や尿量減少(400mL/日以下)として現れます。
血栓症も重要な合併症で、血液濃縮により血液粘度が上昇し、深部静脈血栓症や脳梗塞のリスクが高まります。電解質異常(高ナトリウム血症、低ナトリウム血症、高カリウム血症)も頻繁に併発し、不整脈や筋力低下の原因となります。
高齢者ではせん妄や転倒のリスクが増加し、小児では熱性痙攣や意識障害を起こしやすくなります。
看護に活かすポイント
脱水の看護で重要なのは「見た目だけでは判断できない」ということです。特に高齢者では、口渇感が鈍麻しているため自覚症状が乏しく、また皮膚の弾力性も加齢により低下しているため、従来の観察項目だけでは不十分です。
複数の観察項目を組み合わせた総合的な評価と、患者さんの普段の状態との比較が重要になります。また、脱水は予防可能な病態であるため、リスクファクターを持つ患者さんに対する予防的なケアが極めて重要です。
4. 症状・検査・治療
代表的な症状・徴候
脱水の症状は、まるで植物が水不足で萎れていくような全身の変化として現れます。
初期症状として最も重要なのは口渇ですが、高齢者では口渇感が鈍麻していることが多く、「のどが渇く」という訴えがない場合も多いです。皮膚・粘膜の変化では、口唇の乾燥、口腔粘膜の乾燥、皮膚のツルゴール(弾力性)の低下が観察されます。
循環器症状として、軽度では起立性低血圧(立位時の収縮期血圧20mmHg以上または拡張期血圧10mmHg以上の低下)が現れ、進行すると安静時の血圧低下、頻脈、末梢循環不全による四肢冷感が見られます。
泌尿器症状では、尿量減少(正常成人:1日1000-1500mL)、尿の濃縮による色調の変化(濃黄色)が特徴的です。神経症状として、軽度では倦怠感、頭痛、めまいが見られ、重度では意識レベルの低下、見当識障害、痙攣も起こります。
患者さんからは「だるい」「頭がぼーっとする」「立つとふらつく」「尿の色が濃い」といった訴えが聞かれることが多いです。
主要な検査・診断
脱水の診断には血液検査が重要で、血清ナトリウム値(正常値135-145mEq/L)、血清浸透圧(正常値280-290mOsm/kg)、BUN/クレアチニン比(正常20:1以下、脱水では20:1以上)を評価します。
尿検査では、尿比重(正常値1.010-1.025)、尿浸透圧(正常値50-1200mOsm/kg)により腎臓の濃縮能力を評価します。脱水時は尿比重1.025以上、尿浸透圧800mOsm/kg以上となることが多いです。
ヘマトクリット値(男性40-48%、女性35-42%)や血清アルブミン値の上昇も血液濃縮の指標となります。
体重測定は脱水の程度を評価する最も簡便で確実な方法で、普段の体重との比較により脱水の程度を判定できます。中心静脈圧(正常値2-8mmHg)の測定により、より正確な循環血液量の評価も可能です。
治療の基本
脱水の治療は原因の除去と水分・電解質の補給が基本となります。軽度脱水では経口補水液(OS-1、アクアソリタなど)による経口補給が第一選択で、1日1000-1500mLを目安に少量ずつ頻回に摂取させます。
中等度から重度の脱水では静脈内輸液が必要となります。等張性脱水では生理食塩水や乳酸リンゲル液、高張性脱水では5%ブドウ糖液、低張性脱水では生理食塩水が選択されます。
輸液速度は患者の状態により調整しますが、一般的には最初の1-2時間で不足水分量の1/3-1/2を補給し、残りを24時間かけて補給します。急激な補正は脳浮腫や心不全のリスクがあるため、慎重な管理が必要です。
電解質異常の補正も同時に行い、ナトリウム、カリウム、マグネシウムなどの適切な補給を行います。
5. 看護のポイント
主な看護診断
- 体液量不足
- 体液量不足リスク状態
- 口腔粘膜障害
- 転倒リスク状態
ゴードンの機能的健康パターン別観察項目
栄養代謝パターンでは、水分摂取量と排泄量のバランス、体重変化、皮膚・粘膜の状態を詳細に観察します。特に、24時間の水分出納バランスの正確な記録が重要で、摂取量(経口摂取、輸液)と排泄量(尿量、便、発汗、不感蒸泄)を記録します。
排泄パターンでは、尿量、尿の性状(色調、比重)、排尿回数、便秘の有無を観察します。正常成人の1日尿量は体重1kgあたり1mL以上(例:60kgの人で1440mL以上)が目安となります。
活動運動パターンでは、循環動態の変化(血圧、脈拍、起立性低血圧の有無)、活動耐性、転倒リスクを評価します。特に起立性低血圧の評価は、臥位から立位への体位変換時の血圧・脈拍変化を測定することが重要です。
認知知覚パターンでは、意識レベル、見当識、頭痛やめまいの有無を観察し、脱水による神経症状の早期発見に努めます。
ヘンダーソンの基本的欲求からみた看護
適切な食物と水分の摂取への支援が最も重要です。患者さんの嗜好に合わせた水分の提供、摂取しやすい形態(ゼリー、アイスクリーム、果物など)の工夫、定期的な水分摂取の促進を行います。脱水リスクの高い患者さんには、時間を決めた定期的な水分摂取を習慣化させることが重要です。
排泄する欲求への支援では、適切な尿量の確保、便秘による水分喪失の防止、必要に応じた排泄の介助を行います。下痢や嘔吐がある場合は、喪失量の正確な測定と適切な補給を行います。
身体の清潔と身だしなみを整え、皮膚を保護するでは、皮膚の乾燥に対するスキンケア、口腔ケアによる粘膜の保護を行います。特に口腔内の乾燥は感染リスクを高めるため、定期的な口腔ケアが重要です。
正常な体温を保持するでは、発熱による水分喪失の防止、適切な環境温度の維持、発汗過多の予防を行います。
病態に応じた具体的な看護介入
軽度脱水では、経口での水分補給を中心とした予防的ケアを行います。1日の必要水分量(体重1kgあたり30-35mL、例:60kgの人で1800-2100mL)を目安に、少量ずつ頻回に摂取させます。水分摂取記録表を作成し、患者さんと一緒に摂取量を確認することも効果的です。
中等度脱水では、輸液管理と並行して経口摂取の促進を図ります。輸液ポンプによる正確な輸液速度の管理、血管外漏出の観察、電解質データの継続的な評価を行います。患者さんの循環動態を定期的に評価し、輸液効果を判定します。
重度脱水では、集中的な観察と治療が必要となります。バイタルサインの頻回測定、時間尿量の正確な測定、意識レベルの評価、中心静脈圧の監視などを24時間体制で実施します。急激な輸液による心不全や脳浮腫のリスクにも注意が必要です。
予防・悪化防止のポイント
脱水の予防には環境要因の管理が重要です。室温の適切な調整(22-26℃)、湿度の維持(50-60%)、直射日光の回避などにより、過度の発汗を防ぎます。
定期的な水分摂取の習慣化も効果的で、起床時、食事時、入浴前後、就寝前など、決まったタイミングでの水分摂取を促進します。高齢者では口渇感が鈍麻しているため、時間を決めた水分摂取が特に重要です。
薬剤管理では、利尿薬、下剤、発汗を促進する薬剤の適切な使用と副作用の観察を行います。また、感染症の早期発見・治療により、発熱による水分喪失を最小限に抑えることも重要です。
6. よくある質問・Q&A
Q:高齢者の脱水で特に注意すべき点はありますか?
A: 高齢者の脱水には多くの特徴があり、特別な注意が必要です。まず、口渇感の鈍麻により、脱水が進行しても「のどが渇く」という自覚症状が現れにくいです。また、腎機能の低下により尿濃縮能力が低下し、脱水の代償機構が働きにくくなっています。皮膚の弾力性も加齢により低下するため、皮膚ツルゴールテストの信頼性が下がります。さらに、認知機能の低下により水分摂取を忘れたり、トイレが近くなることを嫌って意図的に水分摂取を控えたりすることもあります。このため、定期的な水分摂取の声かけ、環境整備、家族への指導が特に重要になります。
Q:皮膚ツルゴールテストはどのように実施し、どう判定しますか?
A: 皮膚ツルゴールテストは、皮膚の弾力性を評価する簡便な方法です。実施方法は、手背や前胸部、鎖骨下部の皮膚を親指と人差し指でつまみ上げ、2秒間保持した後に離します。正常では皮膚は即座に元の状態に戻りますが、脱水では戻るのに時間がかかります。判定基準は、2秒以内に戻る場合は正常、2-4秒で戻る場合は軽度脱水、4秒以上かかる場合は中等度以上の脱水を疑います。ただし、高齢者では加齢による皮膚の弾力性低下があるため、他の観察項目と合わせて総合的に判断することが重要です。
Q:経口補水液と普通の水やスポーツドリンクの違いは何ですか?
A: 経口補水液(ORS)は、WHOが推奨する組成に基づいて作られており、ナトリウム濃度が普通の水やスポーツドリンクより高く設定されています。具体的には、ナトリウム40-80mEq/L、ブドウ糖20-25g/Lの濃度で、腸管での水分・電解質の吸収が最も効率的になるよう調整されています。普通の水では電解質が補給できず、大量摂取により低ナトリウム血症のリスクがあります。一般的なスポーツドリンクはナトリウム濃度が10-20mEq/Lと低く、糖分が多いため、脱水時の補給には不適切です。脱水の治療には、医療用の経口補水液(OS-1、アクアソリタなど)を使用することが重要です。
Q:1日の必要水分量はどのように計算しますか?
A: 1日の必要水分量は、年齢や活動レベルにより異なります。成人の基本計算式は、体重1kgあたり30-35mLです(例:60kgの人で1800-2100mL)。より詳細な計算では、体重別計算法を使用します:体重10kgまでは100mL/kg、11-20kgは50mL/kg、21kg以上は20mL/kgを加算します(例:70kgの人では1000mL+500mL+1000mL=2500mL)。体表面積による計算法では、1500mL/㎡/日となります。発熱時は体温1℃上昇につき10-15%増加、発汗過多時はさらに追加が必要です。高齢者では腎機能低下により1日1500-2000mL程度が目安となりますが、心不全などがある場合は制限が必要なこともあります。
7. まとめ
脱水は予防可能でありながら、見過ごされやすい病態です。特に高齢者や慢性疾患を持つ患者さんでは、軽微な要因でも急速に進行する可能性があるため、看護師の継続的な観察と予防的なケアが極めて重要です。
重要なのは、複数の観察項目を組み合わせた総合的な評価と、患者さんの個別性を考慮したケアを提供することです。日常的な水分摂取の促進から緊急時の対応まで、幅広い知識と技術を身につけて、患者さんの安全を守る看護を実践していきましょう。
覚えるべき数値
- 成人の体重に占める水分の割合:約60%
- 1日の基本的水分需要量:体重1kgあたり30-35mL
- 正常1日尿量:体重1kgあたり1mL以上
- 軽度脱水:体重減少3-5%
- 中等度脱水:体重減少6-9%
- 重度脱水:体重減少10%以上
- 血清ナトリウム正常値:135-145mEq/L
- 血清浸透圧正常値:280-290mOsm/kg
- 尿比重正常値:1.010-1.025
- BUN/クレアチニン比(脱水時):20:1以上
実習・現場で活用できるポイント
実習では、患者さんの水分出納バランスを正確に記録し、24時間の総合的な評価を行うことが重要です。単一の観察項目だけでなく、複数の指標を組み合わせて脱水の程度を判断する能力を身につけましょう。
特に高齢者では、従来の観察項目の信頼性が低下するため、より注意深い観察が必要です。患者さんの普段の状態を知り、わずかな変化も見逃さない観察力を養ってください。予防的視点を持ち、リスクの高い患者さんには積極的な水分摂取の促進を行える看護師を目指しましょう。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
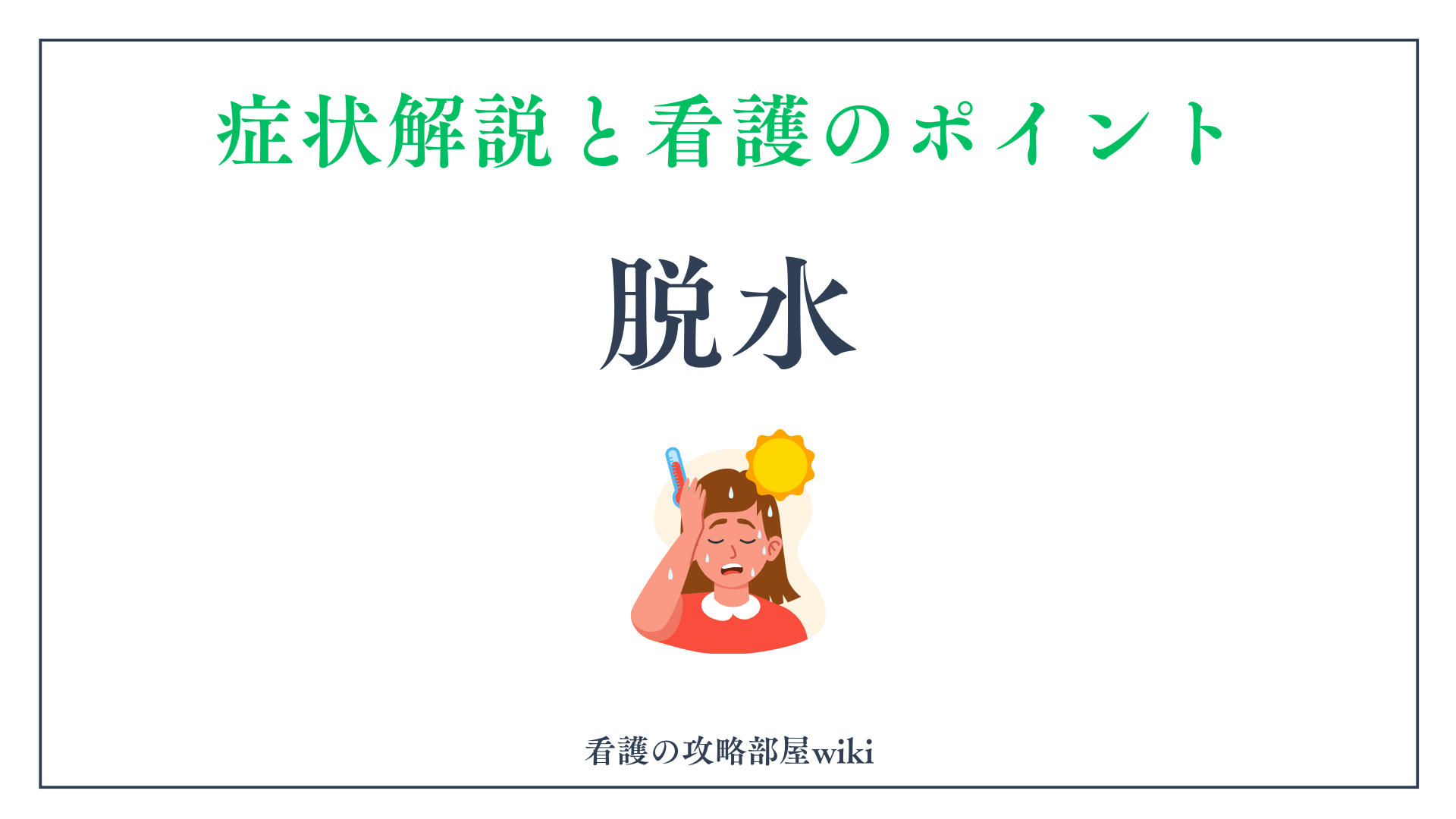


コメント