1. はじめに
腹痛と腹部膨満は、実習現場で最も頻繁に遭遇する症状の一つです。患者さんが「お腹が痛い」「お腹が張って苦しい」と訴えられた時、看護師として適切な観察と判断ができることは、重篤な疾患の早期発見や患者さんの苦痛軽減において極めて重要です。
腹痛は軽度の消化不良から生命に関わる腹膜炎まで、その原因は多岐にわたります。また、腹部膨満も単純な便秘から腸閉塞まで、緊急度の異なる様々な病態が隠れています。実習では、患者さんの表情、体位、腹部の視診・聴診・触診を系統的に行い、症状の変化を継続的に観察することが求められます。
この記事で学べること
- 腹痛と腹部膨満の定義・分類と発生メカニズムの理解
- 部位別の腹痛の特徴と鑑別のポイント、緊急度の判断
- 系統的な腹部観察技術と異常所見の見つけ方
- ゴードンとヘンダーソンの理論に基づいた個別性のある看護展開
- 症状に応じた具体的な看護介入と悪化防止のための継続観察
2. 病態の基本情報
定義
腹痛:腹腔内臓器の炎症、痙攣、伸展、虚血などにより生じる腹部の疼痛感覚 腹部膨満:腹腔内のガスや液体貯留により腹部が異常に拡張した状態
疫学
腹痛は全救急外来受診者の約10-15%を占める症状で、入院患者では約20-25%が何らかの腹痛を経験します。腹部膨満は消化器疾患患者の40-50%で認められ、特に高齢者では便秘による腹部膨満が60%以上で見られます。
急性腹症として緊急手術が必要となるケースは腹痛患者の5-10%ですが、早期診断により予後が大きく左右されるため、適切な初期対応が重要です。慢性腹痛は成人の約15-20%が経験し、生活の質に大きな影響を与える症状です。
分類・病型
腹痛は発症様式により急性腹痛と慢性腹痛に分類されます。急性腹痛は24時間以内に発症する激しい痛みで、虫垂炎、胆石症、腸閉塞、消化管穿孔などが原因となり、緊急性が高い状態です。慢性腹痛は3か月以上続く痛みで、過敏性腸症候群、慢性胃炎、機能性ディスペプシアなどが原因となります。
痛みの性質による分類では、内臓痛が臓器の伸展や炎症による鈍い痛みで部位が曖昧、体性痛が腹膜刺激による鋭い痛みで部位が明確、関連痛が内臓の病変が体表に投射される痛みとなります。
腹部膨満は原因によりガス性膨満、液体貯留性膨満、腫瘤性膨満に分類されます。ガス性膨満は腸閉塞や便秘で見られ、液体貯留性膨満は腹水や腸液貯留で生じ、腫瘤性膨満は腫瘍や臓器腫大によるものです。
3. 病態生理
基本メカニズム
腹痛の発生を家庭の配管システムに例えて考えてみましょう。正常な状態では、配管(消化管)を通って水(消化物)がスムーズに流れています。腹痛は、この配管のどこかに詰まり(腸閉塞)、破裂(穿孔)、炎症(腹膜炎)が生じた状態といえます。
内臓痛は、消化管の平滑筋の痙攣や伸展により生じ、交感神経を介して伝達されます。痛みは鈍く、部位が曖昧で、悪心・嘔吐を伴うことが特徴です。体性痛は、腹膜や後腹膜の刺激により生じ、体性神経を介して伝達されます。痛みは鋭く、部位が明確で、体動により増強します。
腹部膨満は、消化管内のガス貯留、腸液や腹水の貯留、腫瘤による圧迫などにより生じます。ガス貯留は腸管の蠕動低下や通過障害により起こり、腹腔内圧の上昇により呼吸困難や循環障害を引き起こすことがあります。
進行過程
軽度の腹痛では、患者さんは「なんとなくお腹が重い」「食後に軽い痛みがある」程度の症状を訴えます。この段階では日常生活への影響は軽微で、体位変換や温罨法により症状が軽減することがあります。
中等度になると、「はっきりとした痛み」を感じるようになり、患者さんは特定の体位を取りたがるようになります。膝を曲げて横向きになったり、前かがみになったりする姿勢が見られます。食欲不振や軽度の発熱を伴うことがあります。
重度では、「耐え難い痛み」となり、患者さんは安静を保てなくなります。冷汗、顔面蒼白、頻脈、血圧低下などのショック症状を呈することがあり、緊急手術が必要な状態です。この段階は、家の水道管が破裂して大洪水になった緊急事態に相当します。
腹部膨満も同様に進行し、軽度では「お腹が張る感じ」から始まり、中等度では「苦しくて横になれない」、重度では「息苦しくて動けない」状態となります。
病型別の違い
- 内臓痛: 鈍い痛み、部位不明確、悪心・嘔吐を伴う(胃炎、腸炎など)
- 体性痛: 鋭い痛み、部位明確、体動で増強(腹膜炎、虫垂炎など)
- 関連痛: 原因部位と異なる場所の痛み(胆嚢炎での右肩痛など)
- ガス性膨満: 腹部全体の膨隆、金属音様腸雑音(腸閉塞など)
- 液体性膨満: 腹囲増大、波動感(腹水、腸液貯留など)
合併症・併発する病態
腹痛が持続すると、脱水や電解質異常を引き起こします。特に嘔吐を伴う場合は、ナトリウムやカリウムの喪失により重篤な電解質バランスの崩れが生じます。また、強い痛みによるストレス反応により、血糖値の上昇や免疫機能の低下が起こることがあります。
腹部膨満が進行すると、横隔膜の挙上により呼吸困難が生じ、静脈還流の減少により循環不全を引き起こすことがあります。また、腸管の拡張により腸管壊死や穿孔のリスクが高まります。
慢性的な腹痛・腹部膨満は、うつ状態や不安障害などの精神的な問題を引き起こし、患者さんの生活の質を著しく低下させることがあります。
看護に活かすポイント
なぜ体位を観察するのでしょうか?腹膜炎では仰臥位で膝を曲げた体位を取り、胆石発作では前かがみの体位を好むなど、疾患により特徴的な体位があるからです。なぜ腸雑音を聴取するのでしょうか?腸閉塞では金属音様の亢進した腸雑音が、腹膜炎では腸雑音の減弱や消失が見られるからです。なぜ反跳痛を確認するのでしょうか?腹膜刺激症状の有無により、外科的治療の緊急度が判断できるからです。
4. 症状・検査・治療
代表的な症状・徴候
急性腹痛では、患者さんは「突然激しい痛みが始まった」「刃物で刺されるような痛み」と表現することが多くあります。虫垂炎では「最初はみぞおちが痛かったが、だんだん右下腹部に移ってきた」、胆石症では「背中まで突き抜けるような痛み」、尿路結石では「腰から下腹部にかけての激痛」といった特徴的な訴えが聞かれます。
腸閉塞による腹部膨満では、「お腹がパンパンに張って苦しい」「ガスも便も出ない」と訴え、間欠的な腹痛と嘔吐を繰り返します。腹水による膨満では、「お腹だけが大きくなってきた」「息苦しくて仰向けに寝られない」といった症状が現れます。
慢性腹痛では、「いつもお腹の調子が悪い」「ストレスがかかると痛くなる」「食後に決まって痛む」など、症状の周期性や誘因との関連を訴えることが多くあります。
随伴症状として、発熱、悪心・嘔吐、下痢、便秘、食欲不振などが見られ、これらの組み合わせが診断の手がかりとなります。
主要な検査・診断
血液検査では、白血球数の増加(正常値4,000-9,000/μl、炎症時10,000/μl以上)、CRP上昇(正常値0.3mg/dl以下、炎症時3.0mg/dl以上)により炎症の程度を評価します。アミラーゼ値(正常値40-130U/l)は膵炎の診断に有用です。
腹部X線検査では、腸閉塞の際に見られる鏡面像(ニボー)や腸管の拡張、腹腔内遊離ガス(消化管穿孔)の有無を確認します。
腹部CT検査は最も有用な画像診断で、臓器の形態異常、炎症の範囲、腹水の有無などを詳細に評価できます。腹部超音波検査は胆石、腹水、腸管の状態を非侵襲的に観察できます。
腹囲測定は腹部膨満の評価に重要で、基準値(男性85cm未満、女性80cm未満)を超える場合は注意が必要です。
治療の基本
急性腹症では、原因に応じた迅速な対応が必要です。外科的疾患では緊急手術、内科的疾患では保存的治療が選択されます。疼痛管理、輸液療法、感染制御が治療の基本となります。腸閉塞では胃管による減圧、腹水では穿刺排液などの対症的治療も重要です。
5. 看護のポイント
主な看護診断
- 急性疼痛 炎症過程に関連した
- 慢性疼痛 持続する病理学的過程に関連した
- 体液量不足 嘔吐・下痢による体液喪失に関連した
- 栄養摂取低下 腹痛・嘔吐による経口摂取不良に関連した
ゴードンの機能的健康パターン別観察項目
健康知覚-健康管理パターンでは、患者さんの症状に対する理解と対処方法を評価します。「いつから症状が始まったか」「どのような時に痛みが強くなるか」「今まで同じような症状はあったか」「市販薬を服用しているか」といった詳細な病歴聴取が重要です。
栄養-代謝パターンは腹痛・腹部膨満患者にとって極めて重要な観察領域です。食事摂取量の変化、嘔吐の有無と性状、体重変化、脱水の徴候を系統的に評価します。「食欲はあるか」「何を食べると症状が悪化するか」「水分は取れているか」といった具体的な情報を収集します。
排泄パターンでは、排便状況の詳細な観察が必要です。便の性状、回数、色調、血液の混入、最終排便日時、ガスの排出状況などを確認します。特に腸閉塞の早期発見には、「ガスが出ているか」「便が出ているか」の確認が重要です。
活動-運動パターンでは、腹痛による活動制限の程度を評価します。痛みのために取る体位、歩行時の痛みの変化、日常生活動作への影響を観察し、患者さんの活動耐性を把握します。
ヘンダーソンの基本的欲求からみた看護
適切に飲食する欲求において、腹痛・腹部膨満により食事摂取が困難な患者さんに対し、症状に応じた食事調整を行います。急性期には絶食が必要な場合もありますが、回復期には段階的な食事再開を支援します。「お粥から始めて様子を見ましょう」「少量ずつ食べて、痛みがないか確認してください」といった具体的な指導を行います。
正常に排泄する欲求では、便秘による腹部膨満の改善や、下痢による脱水の予防が重要です。排便パターンの観察、必要に応じた排便コントロール、適切な水分摂取の支援を行います。浣腸や下剤の使用については、腸閉塞などの器質的疾患を除外した上で慎重に検討します。
身体を清潔に保つ欲求では、腹痛により活動が制限された患者さんの清潔保持を支援します。特に嘔吐がある場合は、口腔ケアを頻回に行い、気分不快を軽減します。また、発熱を伴う場合は、適切な体温調節と発汗後の更衣を支援します。
休息と睡眠欲求では、腹痛により睡眠が妨げられる患者さんに対し、安楽な体位の工夫や環境調整を行います。痛みの軽減により良質な睡眠が得られるよう、薬物療法と非薬物療法を組み合わせて支援します。
病態に応じた具体的な看護介入
急性期では、疼痛の評価と管理を最優先とします。NRS(Numerical Rating Scale)やフェイススケールを用いて疼痛の程度を定量的に評価し、疼痛の部位、性質、持続時間、増悪・軽快因子を詳細に観察します。「1から10までの数字で、痛みの強さを教えてください」「どのような痛みですか?刺すような痛み?重い痛み?」といった質問により、痛みの特徴を把握します。
バイタルサインの監視では、疼痛による頻脈、血圧上昇、発熱の有無を確認し、ショック症状の早期発見に努めます。特に腹部の観察では、視診(膨隆、陥凹、皮膚色調)、聴診(腸雑音の性状)、触診(圧痛、反跳痛、筋性防御)を系統的に行います。
回復期には、段階的な食事再開を支援します。医師の指示に従い、水分摂取から開始し、流動食、軟食へと段階的に進めます。各段階で腹痛や嘔吐の有無を確認し、患者さんの状態に応じてペースを調整します。「少し食べてみて、30分後に痛みがないか確認しましょう」といった声かけを行います。
慢性期では、生活習慣の改善とセルフケア能力の向上を支援します。ストレス管理、規則正しい食事、適度な運動の重要性を説明し、患者さんが継続できる具体的な方法を一緒に考えます。
予防・悪化防止のポイント
腹痛・腹部膨満の予防には、規則正しい食習慣の確立が重要です。暴飲暴食を避け、食物繊維を適度に摂取し、十分な水分摂取を心がけるよう指導します。また、ストレス管理も重要で、リラクゼーション技法や適度な運動を取り入れることを勧めます。
早期受診の指導も大切で、「激しい腹痛」「血便」「持続する嘔吐」「発熱を伴う腹痛」などの症状が現れた場合は、速やかに医療機関を受診するよう説明します。
6. よくある質問・Q&A
Q:腹痛を訴える患者さんの観察で、最も重要なポイントを教えてください
A: まず緊急度の判断が最重要です。激しい腹痛、反跳痛、筋性防御、ショック症状がある場合は緊急対応が必要です。観察のポイントは、疼痛の部位(右下腹部痛は虫垂炎、心窩部痛は胃・十二指腸疾患を疑う)、疼痛の性質(突然発症の激痛は穿孔や結石を疑う)、随伴症状(発熱・嘔吐の有無)、患者さんの体位(特定の体位を好む場合は特定疾患を示唆)です。また、腸雑音の聴取は必須で、亢進は腸閉塞、減弱・消失は腹膜炎を示唆します。
Q:腹部膨満の患者さんへの看護で注意すべき点は?
A: 呼吸状態の観察が最も重要です。腹部膨満により横隔膜が押し上げられ、呼吸困難を引き起こすことがあります。腹囲測定を定期的に行い、膨満の程度を客観的に評価します。排便・排ガス状況の確認も重要で、「最後に便が出たのはいつか」「ガスは出ているか」を必ず確認します。体位は半座位を基本とし、呼吸を楽にします。脱水の予防も大切で、経口摂取が困難な場合は輸液管理を適切に行います。腸閉塞が疑われる場合は、浣腸や下剤の使用は禁忌であることを覚えておいてください。
Q:夜間に腹痛を訴える患者さんへの対応方法を教えてください
A: まず疼痛の評価を速やかに行います。NRSスケールで疼痛の程度を確認し、部位、性質、持続時間を聴取します。バイタルサインを測定し、全身状態を把握します。安楽な体位を取ってもらい、「楽になる姿勢はありますか」と声をかけます。医師への報告が必要な症状(NRS 7以上の激痛、新たな症状の出現、バイタルサインの異常)を判断し、必要に応じて速やかに連絡します。患者さんには「一緒にいるので安心してください」「痛みの様子を見させてください」と声をかけ、不安を軽減することも重要です。
Q:便秘による腹部膨満の患者さんに、いつ浣腸を実施すべきでしょうか?
A: 浣腸実施前に必ず器質的疾患の除外を行います。腸閉塞、腸管穿孔、急性腹症が疑われる場合は浣腸は禁忌です。実施の判断基準は、3日以上の排便なし、腹部膨満感、排ガスの減少、器質的疾患の除外、医師の指示があることです。実施前には腹部の観察(腸雑音、圧痛、膨満の程度)を行い、実施中は患者さんの状態変化(腹痛の増強、血圧変動)を注意深く観察します。実施後は排便状況と腹部症状の改善を評価し、効果が不十分な場合は医師に報告することが重要です。
7. まとめ
腹痛・腹部膨満は日常的に遭遇する症状ですが、軽微なものから生命に関わるものまで幅広い原因があります。系統的な観察と適切な判断により、患者さんの安全を確保し、苦痛を軽減することができます。緊急度の判断と継続的な観察が、良好な患者アウトカムにつながります。
覚えるべき数値
- 白血球数正常値:4,000-9,000/μl
- 炎症時白血球数:10,000/μl以上
- CRP正常値:0.3mg/dl以下
- 炎症時CRP:3.0mg/dl以上
- アミラーゼ正常値:40-130U/l
- 腹囲基準値:男性85cm未満、女性80cm未満
- 体温正常値:36.0-37.0℃
- 発熱基準:37.5℃以上
実習・現場で活用できるポイント
実習では、腹痛・腹部膨満を訴える患者さんに対し、系統的な腹部観察を身につけることが重要です。視診・聴診・触診の順序を守り、異常所見を正確に把握できるよう練習しましょう。患者さんの苦痛に共感しつつ、冷静な判断力を持って観察を行うことが大切です。
ゴードンの機能的健康パターンやヘンダーソンの基本的欲求を活用した看護展開により、個々の患者さんの状態に応じたケアが提供できます。特に、疼痛管理と生活援助のバランスを取りながら、患者さんの回復を支援することを心がけてください。緊急時の判断基準を明確に持ち、迅速かつ適切な対応ができる看護師を目指しましょう。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
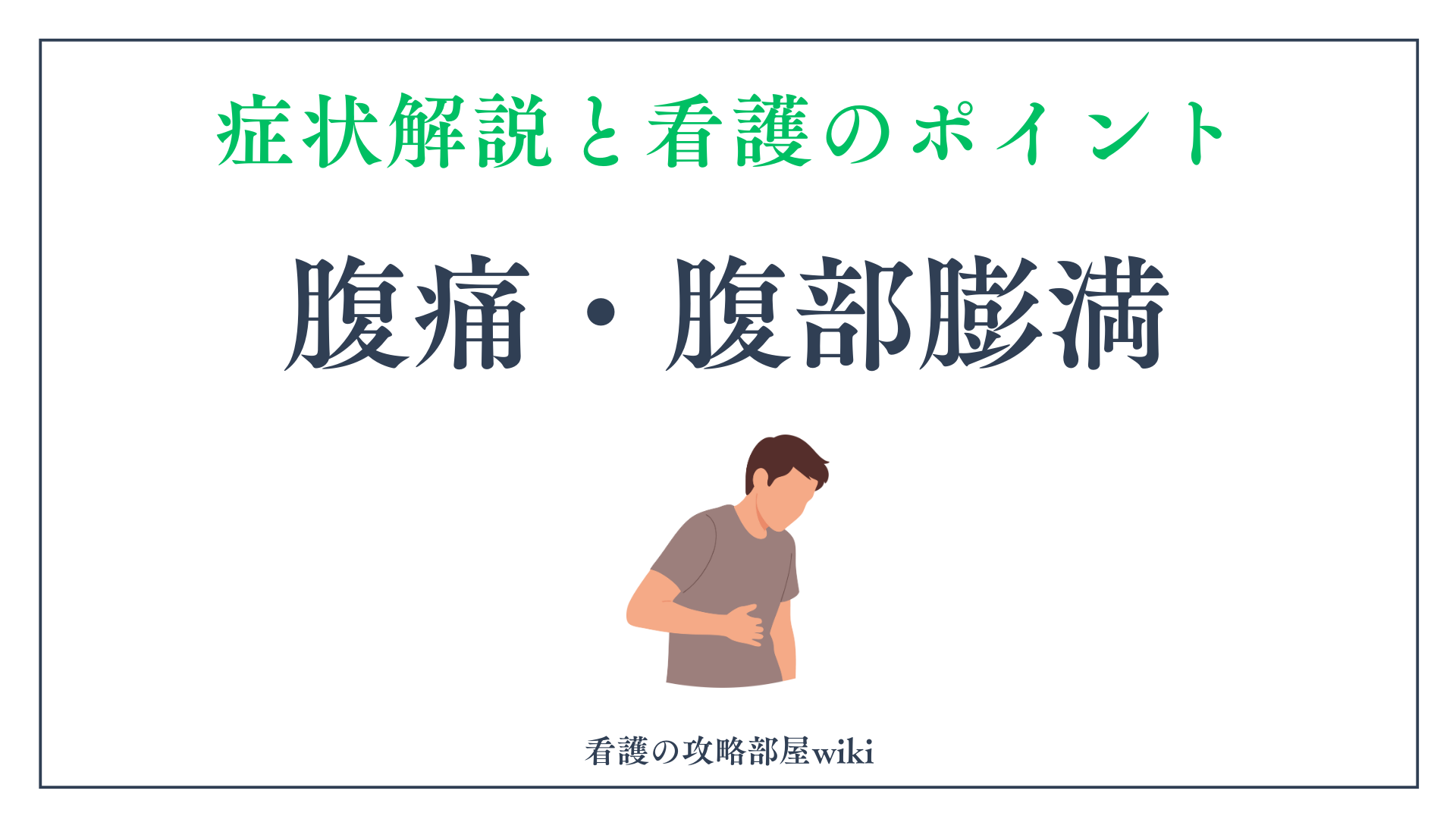
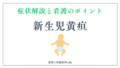
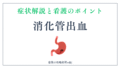
コメント