1. はじめに
実習中に「胸が痛い」「ドキドキする」と訴える患者さんに出会ったことはありませんか?胸痛と動悸は日常的によく遭遇する症状でありながら、緊急性の高い疾患から比較的軽微なものまで幅広い原因が考えられる重要な症状です。看護師として、これらの症状を適切にアセスメントし、迅速かつ的確な対応をとることは患者さんの生命を守る上で極めて重要です。
この記事で学べること
• 胸痛・動悸の基本的なメカニズムと分類
• 緊急性の判断基準と優先度の考え方
• 症状に応じた観察ポイントと根拠
• ゴードンとヘンダーソンの理論を活用した看護展開
• 実習で活用できる具体的な看護介入方法
2. 病態の基本情報
定義
胸痛は胸部に感じる不快感や痛み、動悸は心拍動を自覚する症状で、心疾患から心因性まで多様な原因により生じる
疫学
胸痛を主訴とする救急外来受診者は全体の約5-10%を占め、そのうち約15%が心筋梗塞などの緊急性の高い疾患です。動悸については成人の約16%が経験し、特に女性に多く見られます。高齢化に伴い、心房細動による動悸は65歳以上で約5%の有病率を示しています。
分類・病型
胸痛は発生機序により心原性胸痛、血管原性胸痛、呼吸器性胸痛、消化器性胸痛、心因性胸痛に分類されます。心原性胸痛は心筋虚血や心膜炎によるもので、特に急性心筋梗塞では生命に直結するため最優先で鑑別が必要です。血管原性では大動脈解離や肺塞栓症が代表的で、いずれも緊急性が高い疾患です。
動悸は不整脈の有無により器質的動悸と機能的動悸に大別されます。器質的動悸は心房細動、心室頻拍などの不整脈が原因で、心電図で異常を認めます。機能的動悸は構造的心疾患がなく、ストレスや薬物、甲状腺機能亢進症などが原因となることが多いです。
3. 病態生理
基本メカニズム
胸痛の発生は、胸部の様々な組織にある痛覚受容器が刺激されることで起こります。これは家の火災報知器のようなもので、異常を感知すると警報(痛み)を発します。心臓の場合、酸素不足になると心筋細胞が「助けて!」のサインとして痛みを発するのです。
動悸は正常では意識しない心拍動を感じる状態です。普段は静かに動いている心臓が、何らかの理由で「ドンドン」と大きく、または速く拍動することで自覚症状として現れます。これは普段は気づかない時計の針の音が、静かな夜に急に大きく聞こえるのと似ています。
進行過程
急性期では症状が突然出現し、患者さんは強い不安を感じます。「胸を締め付けられるような痛み」「心臓が飛び出しそう」といった表現をされることが多く、交感神経が活性化され冷汗や血圧上昇を伴います。
代償期では身体が症状に慣れようとし、軽度の症状であれば日常生活への影響は限定的です。しかし根本原因が解決されていない場合、症状は繰り返し出現します。
悪化期では症状の頻度や強度が増し、日常生活に著しい支障をきたします。心原性の場合は心不全症状を併発し、呼吸困難や浮腫などの症状も現れます。
病型別の違い
• 心筋梗塞:締め付けるような持続性の胸痛、左肩や顎への放散痛 • 狭心症:労作時の圧迫感、安静で軽快 • 大動脈解離:突然の引き裂かれるような背部痛 • 肺塞栓症:突然の呼吸困難を伴う胸痛 • 心房細動:不規則で速い動悸、脈の乱れ • パニック障害:発作性の動悸、窒息感、強い不安
合併症・併発する病態
心原性胸痛では心不全、心原性ショック、不整脈を併発するリスクがあります。特に急性心筋梗塞では心筋壊死により心機能が低下し、全身への血液供給が困難になります。動悸が持続する場合は頻脈性心筋症や血栓塞栓症のリスクが高まります。
看護に活かすポイント
症状の観察は「いつ、どこで、どのような」痛みかを詳細に聞くことが重要です。なぜなら、心筋梗塞の胸痛は「朝方に突然始まった締め付けるような痛み」という特徴があり、これを見逃すと生命に関わるからです。また、動悸の際は脈拍の確認が必須で、不整脈の早期発見につながります。
4. 症状・検査・治療
代表的な症状・徴候
心原性胸痛の患者さんは「胸の真ん中が重苦しい」「象に踏まれているような感じ」と表現されることが多く、しばしば左肩や顎、左腕への放散痛を伴います。一方、呼吸器性では「息を吸うと痛い」「咳をすると響く」といった呼吸との関連を訴えます。
動悸では「心臓がバクバクする」「脈が飛ぶ感じがする」「首の血管がドクドクと拍動する」などの表現が聞かれます。器質的な不整脈では脈拍の不規則性が特徴的で、機能的動悸では比較的規則正しい頻脈を認めることが多いです。
随伴症状として、心原性では冷汗、悪心・嘔吐、呼吸困難を、肺塞栓症では突然の呼吸困難とチアノーゼを、パニック障害では強い不安感と窒息感を伴うことが特徴的です。
主要な検査・診断
心電図は最も重要な検査で、ST上昇型心筋梗塞では特徴的なST上昇を、不整脈では異常なリズムを確認できます。正常値は洞調律でR-R間隔が規則的、心拍数60-100回/分です。
心筋逸脱酵素では、トロポニンTが0.1ng/ml以上(正常値0.1ng/ml未満)で心筋梗塞を強く疑います。CK-MBは心筋特異性が高く、正常値は25IU/L未満です。
胸部X線では心拡大(心胸郭比50%以上で異常)や肺うっ血の有無を確認し、心エコーでは壁運動異常や弁膜症、心機能(左室駆出率正常値55%以上)を評価します。
血液ガス分析では、肺塞栓症でPaO2低下(正常値80-100mmHg)とA-aDO2開大を認めることがあります。
治療の基本
急性心筋梗塞では再灌流療法(PCI:経皮的冠動脈インターベンション)が第一選択で、発症から90分以内の実施が推奨されます。薬物療法では抗血小板薬、β遮断薬、ACE阻害薬が標準的です。
不整脈による動悸では原因となる不整脈に応じた治療を行い、心房細動では抗凝固療法による血栓予防が重要です。機能的動悸ではβ遮断薬や不安に対する心理的サポートが効果的です。
5. 看護のポイント
主な看護診断
• 急性疼痛:胸部の疼痛に関連した • 不安:症状や予後への恐怖に関連した
• 活動耐性低下:心機能低下や症状に関連した • 非効果的対処:症状への理解不足に関連した
ゴードンの機能的健康パターン別観察項目
健康知覚‐健康管理パターンでは、患者さんが症状をどのように捉え、対処しようとしているかを観察します。「いつもと違う胸の痛み」を感じても「年のせい」と軽視していないか、適切な医療機関受診ができているかを確認します。既往歴として狭心症や心筋梗塞の有無、服薬状況、特に抗凝固薬の内服歴は血栓リスクの評価に重要です。
活動‐運動パターンでは症状と活動の関連性を詳細に観察します。労作性狭心症では階段昇降や重い物を持つなどの労作時に症状が出現し、安静で軽快するのが特徴です。安静時痛は不安定狭心症や心筋梗塞を疑う重要なサインです。また、動悸の場合は体位変換や起立時の症状変化も重要な観察ポイントです。
対処‐ストレス耐性パターンでは症状に対する不安の程度と対処方法を評価します。胸痛や動悸は患者さんに強い不安を与えやすく、この不安がさらに交感神経を刺激し症状を悪化させる悪循環を形成することがあります。
ヘンダーソンの基本的欲求からみた看護
安全の欲求に対しては、症状の早期発見と適切な対応が最優先です。胸痛の場合は症状出現時の迅速な心電図モニタリングと医師への報告、動悸では脈拍チェックと不整脈の早期発見が重要です。患者さんには「症状が出現したらすぐにナースコールを押してください」と説明し、一人で我慢しないよう指導します。
休息と睡眠の欲求では、症状による睡眠への影響を評価し、安眠できる環境を整えます。夜間の動悸で眠れない患者さんには、適切な体位(セミファーラー位など)の調整や、就寝前のリラクセーション技法の指導が効果的です。
不安からの解放の欲求に対しては、症状の原因や治療方針について分かりやすく説明し、患者さんの不安を軽減します。「心臓の検査でははっきりした異常は見つからなかったので、ストレスが原因の可能性が高いです」といった具体的な説明が安心感につながります。
病態に応じた具体的な看護介入
急性期では生命徴候の継続的な観察が最優先です。血圧、脈拍、呼吸状態、意識レベルを15分毎に測定し、異常の早期発見に努めます。酸素飽和度が95%未満の場合は酸素投与を検討し、胸痛が持続する場合は医師と連携して鎮痛薬の使用を検討します。
安定期では症状の誘発因子を特定し、生活指導を行います。労作性狭心症の患者さんには「階段は一段ずつゆっくりと上がり、息切れを感じたら立ち止まって休憩してください」と具体的に説明します。また、硝酸薬の正しい使用方法についても指導が必要です。
回復期では退院後の生活管理と再発予防に重点を置きます。定期的な外来受診の重要性、症状再発時の対応方法、緊急時の連絡先を明確に伝えます。また、心臓リハビリテーションの必要性についても説明し、段階的な運動療法の開始を支援します。
予防・悪化防止のポイント
生活習慣の改善指導では、禁煙、適度な運動、塩分制限、体重管理の重要性を説明します。特に喫煙は冠動脈の攣縮を誘発しやすく、狭心症患者さんには絶対禁煙を指導します。ストレス管理では、深呼吸法やリラクセーション技法を指導し、日常生活でのストレス軽減方法を一緒に考えます。
服薬管理では、抗血小板薬や抗凝固薬の重要性と副作用について説明し、定期的な血液検査の必要性を伝えます。また、市販薬との相互作用についても注意喚起が必要です。
6. よくある質問・Q&A
Q:胸痛と動悸が同時に起こる場合、どちらを優先して観察すべきでしょうか?
A: どちらも重要な症状ですが、まず生命に直結する可能性の高い胸痛の性状を確認します。締め付けるような持続性の胸痛があれば心筋梗塞を疑い、直ちに心電図測定と医師への報告が必要です。動悸については脈拍を確認し、不整脈の有無をチェックします。両症状が急性心筋梗塞や不整脈による場合は緊急性が高いため、迅速な対応が求められます。
Q:患者さんが「いつもの胸の痛み」と言っている場合、様子を見ても良いでしょうか?
A: 「いつもの痛み」であっても、必ず症状の詳細を確認してください。痛みの性状、持続時間、誘発因子が本当にいつもと同じかを慎重に評価します。狭心症の患者さんでも、安静時痛や痛みの持続時間が長くなっている場合は不安定狭心症への移行を疑います。また、硝酸薬を使用しても症状が改善しない場合は緊急性が高いと判断し、医師に報告することが重要です。
Q:動悸を訴える患者さんで、脈拍は正常範囲内の場合はどのように対応しますか?
A: 脈拍数が正常でも、患者さんが動悸を自覚している場合は詳細な観察が必要です。不整脈による脈の不規則性、血圧変動、随伴症状の有無を確認します。また、甲状腺機能亢進症や貧血、薬物の副作用なども動悸の原因となるため、これらの可能性も考慮します。心電図モニタリングで不整脈の有無を確認し、患者さんの不安に対するサポートも同時に行います。
Q:夜勤中に胸痛を訴える患者さんがいる場合、どのような準備をしておくべきでしょうか?
A: まず心電図装置と酸素、救急カートの場所を確認しておきます。症状出現時は直ちに心電図を測定し、バイタルサインをチェックします。医師への連絡体制を整え、必要に応じて救急外来や循環器医への相談ができるよう準備します。また、患者さんの既往歴、服薬状況、アレルギー歴を事前に把握しておくことで、緊急時の対応がスムーズになります。硝酸薬の処方がある場合は、使用方法と注意点も確認しておきましょう。
7. まとめ
胸痛・動悸は看護師が日常的に遭遇する症状でありながら、適切なアセスメントと迅速な対応が患者さんの予後を大きく左右します。症状の性状を詳細に観察し、緊急性を的確に判断することが最も重要です。また、患者さんの不安に寄り添いながら、根拠に基づいた看護介入を行うことで、安全で質の高いケアを提供できます。
覚えるべき数値
• 心拍数正常値:60-100回/
• 血圧正常値:収縮期120mmHg未満、拡張期80mmHg未満
• 酸素飽和度:95%以上
• トロポニンT:0.1ng/ml未満(正常)
• 左室駆出率:55%以上(正常)
• 心胸郭比:50%未満(正常)
実習・現場で活用できるポイント
症状出現時は「PQRST」(Provocation誘発因子、Quality性状、Radiation放散、Severity重症度、Time時間経過)を用いた系統的なアセスメントを行いましょう。また、患者さんの表情や言動からも重要な情報が得られるため、言語的・非言語的コミュニケーションの両方を大切にしてください。実習では指導者や医師への報告のタイミングと内容を事前に確認し、チーム医療の一員として適切な連携を心がけることが重要です。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
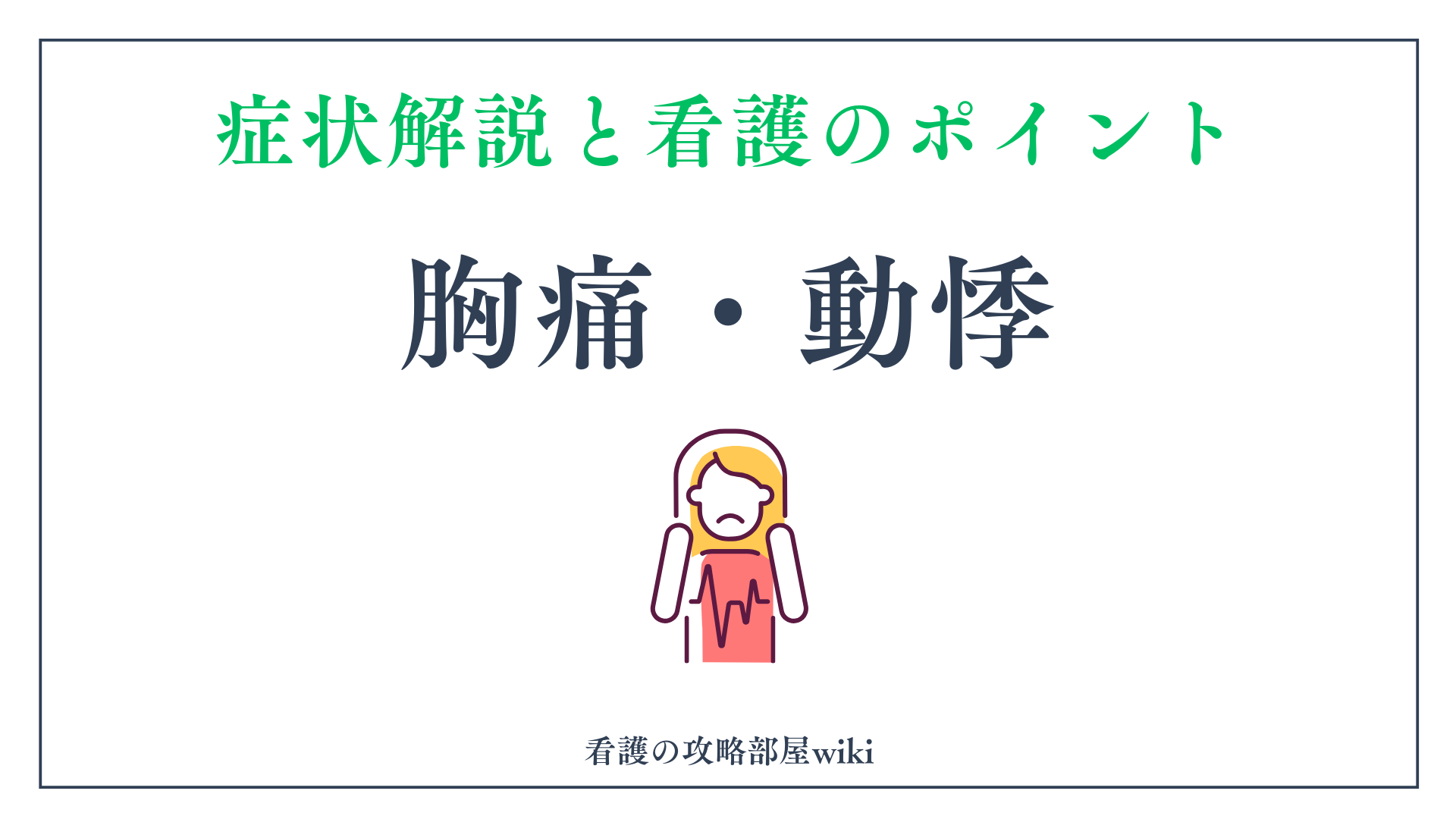


コメント