1. はじめに
ショックは看護師として最も緊急性の高い病態の一つです。患者さんの生命に直結する病態であり、迅速で適切な判断と看護介入が求められます。実習で出会う可能性も高く、正しい知識と観察技術を身につけることで、患者さんの救命に大きく貢献できます。
この記事で学べること
- ショックの基本的な病態生理と進行過程の理解
- 心原性・出血性・敗血症性ショックそれぞれの病態メカニズムの違い
- 代償期から非代償期への移行過程と観察ポイント
- 病態に応じた理論に基づく具体的な看護介入方法
- 実習で遭遇した際の対応と多職種連携のポイント
2. 病態の基本情報
定義
ショックとは、全身の組織や臓器に十分な酸素や栄養を運ぶことができなくなった病態で、細胞レベルでの酸素需要と供給のバランスが崩れ、組織の機能不全を引き起こす状態です。
疫学
日本では年間約20万人がショック状態で救急搬送されており、院内死亡率は心原性ショックで約30-50%、敗血症性ショックで約25-40%と高い数値を示しています。しかしゴールデンタイム(発症から1時間以内)での適切な介入により救命率は大幅に改善するため、看護師の役割は極めて重要です。
分類・病型
ショックは循環動態の異常パターンにより4つに分類されますが、臨床で最も頻度が高いのが今回取り上げる3つです。心原性ショックは心臓のポンプ機能低下により心拍出量が減少するタイプで、急性心筋梗塞や重篤な不整脈が原因となります。出血性ショックは循環血液量の急激な減少により起こるタイプで、外傷や消化管出血、手術時の大量出血が主な原因です。敗血症性ショックは血管の異常拡張により血圧が維持できなくなるタイプで、感染による全身性炎症反応が引き金となります。これらは原因が異なるため、病態の進行過程や治療アプローチも大きく異なります。
3. 病態生理
基本メカニズム
ショックを理解するために、体の循環システムを「水道システム」に例えて考えてみましょう。心臓がポンプ、血管がパイプ、血液が水です。正常な状態では、ポンプ(心臓)が十分な圧力で水(血液)をパイプ(血管)に送り出し、末端の蛇口(各臓器)まで適切な水圧が保たれています。ショックはこのシステムのどこかに問題が生じた状態で、心原性ショックはポンプの故障、出血性ショックは水の大量流出、敗血症性ショックはパイプの異常拡張により、末端まで十分な水圧が届かなくなります。
進行過程
ショック病態は代償期→非代償期→不可逆期の3段階で進行します。代償期では、体は血圧低下を感知すると交感神経を活性化させ、心拍数増加と末梢血管収縮により血圧を維持しようとします。この段階では患者さんは「なんとなく調子が悪い」「疲れやすい」と訴える程度で、血圧は正常に保たれていることも多いのです。しかし代償機能の限界を超えると非代償期に移行し、血圧低下、尿量減少、意識レベル低下などの明らかな症状が現れます。さらに進行すると不可逆期となり、多臓器不全により救命が困難となります。
病型別の違い
- 心原性ショック: ポンプ(心臓)の機能低下型、心拍出量↓、左心房圧↑、肺うっ血による呼吸困難
- 出血性ショック: 容量(血液)不足型、循環血液量↓、静脈還流↓、代償性頻脈と末梢血管収縮
- 敗血症性ショック: 血管拡張型、末梢血管抵抗↓、初期は心拍出量↑、後期は心機能も低下
合併症・併発する病態
ショック病態では複数の臓器が同時に機能低下を起こします。腎血流減少による急性腎障害(尿量0.5ml/kg/時未満)、脳血流減少による意識障害、肝血流減少による肝機能障害、消化管血流減少による消化管出血や腸管壊死などが主要な合併症です。また、組織の酸素不足により代謝性アシドーシスが進行し、さらに循環状態を悪化させる悪循環を形成します。
看護に活かすポイント
なぜ血圧だけでなく、皮膚の色や温度、尿量、意識レベルを継続的に観察するのでしょうか。それは血圧は代償機能により一時的に保たれるため、病態の早期発見には不十分だからです。体は生命維持のため、皮膚や腎臓への血流を最初に制限するため、皮膚の冷感・蒼白や尿量減少は血圧低下より早く現れる重要な早期サインなのです。
4. 症状・検査・治療
代表的な症状・徴候
代償期では患者さんから「なんとなく気分が悪い」「立ちくらみがする」「疲れやすい」といった非特異的な訴えが聞かれます。病型別では、心原性ショックで「胸が締め付けられる」「息が苦しい」、出血性ショックで「のどが渇く」「冷や汗が出る」、敗血症性ショックで「悪寒がする」「熱っぽい」といった特徴的な訴えがあります。非代償期に進行すると、患者さんは「意識がもうろうとする」「話すのがしんどい」と訴え、最終的には訴えることもできなくなるため、客観的な観察がより重要になります。
主要な検査・診断
血圧は収縮期90mmHg未満または普段より30mmHg以上の低下が診断基準です。心拍数は代償的に100回/分以上に増加し、尿量は0.5ml/kg/時未満に減少します。血液検査では血中乳酸値の上昇(2mmol/L以上)が組織の酸素不足を示す重要な指標で、4mmol/L以上では予後不良となります。また、血液ガス分析では代謝性アシドーシス(pH<7.35、HCO3-<22mEq/L)が特徴的です。看護師は数値の変化と患者さんの全身状態を総合的に判断することが重要です。
治療の基本
心原性ショックでは心機能改善を目的とした強心薬(ドパミン、ドブタミン)や、心臓の負担軽減を図る血管拡張薬が使用されます。出血性ショックでは迅速な輸血・輸液による循環血液量の回復と出血源の確実な止血が最優先となります。敗血症性ショックでは感染源に対する適切な抗菌薬投与と、血管作動薬(ノルアドレナリン)による血圧維持が治療の柱です。いずれも時間との勝負であり、多職種チームによる迅速かつ的確な対応が患者さんの予後を決定します。
5. 看護のポイント
主な看護診断
- 心拍出量減少
- 体液量不足
- 組織灌流量減少
- ガス交換障害
ゴードンの機能的健康パターン別観察項目
活動・運動パターンが最も重要な観察対象となります。循環機能の評価として、血圧・脈拍・心音・末梢循環の状態を15-30分毎に継続的に観察します。皮膚の色調(蒼白・紅潮・チアノーゼ)、温度(冷感・温感)、毛細血管再充満時間(正常2秒以内)は末梢循環の状態を直接反映する重要な指標です。排泄パターンでは腎血流量の減少を反映する尿量の変化を厳重に監視し、時間尿量30ml未満は緊急事態のサインとして医師に即座に報告します。栄養・代謝パターンでは体温の変動(敗血症性ショックでは発熱、出血性ショックでは体温低下傾向)、水分バランス、血糖値の変化に注意を払います。認知・知覚パターンでは意識レベルや見当識の変化を通じて脳血流の状態を評価し、GCSスケールやJCSスケールを用いた客観的評価を行います。
ヘンダーソンの基本的欲求からみた看護
循環の基本的欲求に対しては、病型に応じた適切な体位管理(出血性ショックでは下肢挙上位、心原性ショックでは半坐位)を行い、静脈還流や心負荷の最適化を図ります。循環動態の継続的モニタリングを通じて、わずかな変化も見逃さないよう注意深く観察します。呼吸の基本的欲求では酸素療法の実施と効果の評価、SpO2の継続監視により組織への酸素供給を最大化します。特に心原性ショックでは肺うっ血による呼吸困難に対する適切な体位と酸素投与が重要です。水分・電解質平衡の基本的欲求に対しては、医師の指示に基づく適切な輸液管理と、正確な水分バランスの記録・評価を行います。過剰輸液は心原性ショックで心負荷を増大させ、不十分な輸液は出血性ショックで循環不全を悪化させるため、病態に応じた慎重な管理が必要です。体温調節の基本的欲求では、敗血症性ショックにおける発熱管理や、出血性ショックにおける体温低下への対応を通じて、患者さんの生理機能の安定化を図ります。
病態に応じた具体的な看護介入
最優先は循環動態の継続的監視と早期発見です。血圧・脈拍・SpO2・尿量・意識レベルを定期的に測定し、トレンドグラフを作成して変化の傾向を把握します。第二に病態に応じた適切なポジショニングを行います。心原性ショックでは呼吸困難軽減と心負荷軽減のため半坐位、出血性ショックでは静脈還流促進のため下肢挙上位、敗血症性ショックでは患者さんの快適性を重視した体位を基本とします。第三に酸素療法の実施と効果判定で、SpO2を95%以上に維持できるよう酸素流量を調整し、動脈血ガス分析結果と併せて評価します。第四に輸液・薬物療法の確実な実施として、点滴ルートの確保と維持、投与速度の正確な管理、副作用や効果の継続的な観察を行います。第五に患者さんと家族への心理的支援として、不安軽減のための適切な説明と声かけ、安全で清潔な療養環境の提供、家族への状況説明と精神的サポートを心がけます。
予防・悪化防止のポイント
ショック病態の進行を防ぐため、代償期での早期発見が最も重要です。定期的なバイタルサイン測定に加え、患者さんの主観的な訴えや表情の変化にも注意を払います。感染予防対策の徹底により敗血症性ショックの発症を予防し、適切な水分管理により循環血液量の維持を図ります。また、転倒・転落防止により外傷性出血を予防し、薬物の副作用監視により医原性ショックの発生を防ぎます。多職種との密な連携により、早期の治療介入につなげることが患者さんの予後改善に直結します。
6. よくある質問・Q&A
Q:ショック患者の血圧が測定できない時はどのように対応すればよいですか?
A: 血圧測定困難な場合は、まず測定部位を変更します(上腕→大腿部)。それでも困難な場合は、脈拍の触知部位により血圧を推定できます。橈骨動脈が触知できれば収縮期血圧約80mmHg以上、大腿動脈のみ触知可能なら約70mmHg以上、頸動脈のみなら約60mmHg以上と判断します。同時に皮膚色調、毛細血管再充満時間、尿量、意識レベルなどの間接的指標を総合的に評価し、緊急度を判断して医師に報告します。
Q:心原性ショックと出血性ショックの病態の違いを教えてください
A: 最も重要な違いは血管内容量と心負荷の状態です。心原性ショックでは心機能低下により血液が心臓に戻ってきても十分に送り出せないため、中心静脈圧が上昇し肺うっ血による湿性ラ音が聴取されます。一方、出血性ショックでは循環血液量そのものが減少するため、中心静脈圧は低下し肺音は清明です。また病態の進行速度も異なり、出血性ショックは急激に悪化する傾向があるのに対し、心原性ショックは比較的緩徐に進行することが多いです。
Q:敗血症性ショックの初期段階(warm shock)で注意すべき病態変化は?
A: 敗血症性ショックは他のショックと異なり、初期には血管拡張により皮膚が温かく紅潮した「warm shock」を呈します。この段階では心拍出量は増加し血圧も保たれているため、一見すると状態は安定しているように見えます。しかし血管拡張により相対的循環血液量不足が生じており、急激に「cold shock」へ移行する可能性があります。そのため感染徴候がある患者では、血圧正常でも頻呼吸、頻脈、体温変化、意識レベル変化に注意深く観察し、早期発見につなげることが重要です。
Q:実習でショック患者を受け持つ際の学習ポイントを教えてください
A: まず病態生理の理解を深めることが重要です。なぜその観察項目が必要なのか、なぜその看護介入を行うのかを常に「根拠」と結び付けて考えます。観察では数値だけでなく患者さんの全体像を捉え、時系列での変化を読み取る力を養います。また緊急事態だからこそ基本に忠実に、正確な観察と記録を心がけます。分からないことは積極的に質問し、チームの一員として多職種連携の重要性を学びます。患者さんや家族の不安に共感し、温かい声かけを忘れずに行うことも大切な学習ポイントです。
7. まとめ
ショックは生命に直結する緊急病態ですが、病態生理の理解と適切な観察技術により早期発見・早期対応が可能です。心原性・出血性・敗血症性それぞれの病態メカニズムを理解し、進行段階に応じた理論に基づく看護介入を行うことで、患者さんの救命に貢献できます。
覚えるべき数値
- 収縮期血圧:90mmHg未満または30mmHg以上の低下
- 心拍数:100回/分以上(代償性頻脈)
- 尿量:0.5ml/kg/時未満(腎血流量減少の指標)
- 毛細血管再充満時間:2秒以上(末梢循環障害)
- SpO2:95%以上維持が目標
- 乳酸値:2mmol/L以上(組織酸素不足)、4mmol/L以上(予後不良)
実習・現場で活用できるポイント
病態の進行段階(代償期→非代償期→不可逆期)を意識した観察を行い、早期発見に努めます。「なぜこの病態でこの症状が現れるのか」を常に考えながら看護を実践し、根拠に基づいたケアを心がけます。数値だけでなく患者さんの全体像を捉え、変化の傾向を読み取る力を養います。緊急時こそ基本に忠実に、チームワークを大切にした看護を実践してください。ショック患者の看護経験は、循環動態の理解を深め、将来どの分野に進んでも必ず活かされる貴重な学習機会となります。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
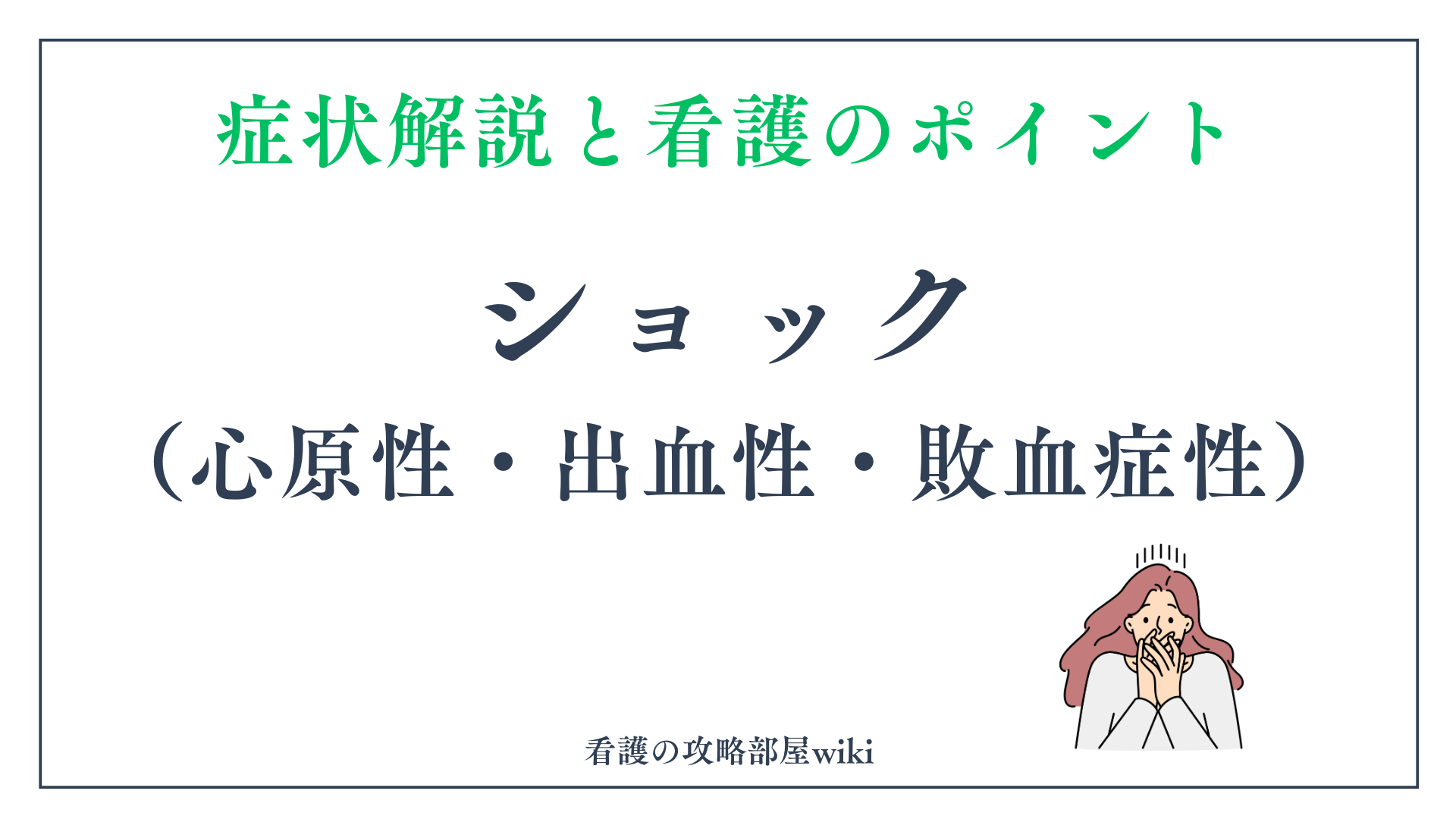


コメント