1. はじめに
実習中に「最近歩くのが遅くなった」「握力が弱くなった」「体重が減ってきた」という高齢の患者さんに出会ったことはありませんか?これらはフレイルやサルコペニアの重要なサインかもしれません。
フレイルとサルコペニアは超高齢社会の日本において極めて重要な概念で、要介護状態に至る前段階として注目されています。看護師が早期に発見し、適切な介入を行うことで、患者さんの自立した生活の維持と健康寿命の延伸を支援することができる、可逆性のある病態です。
この記事で学べること
- フレイルとサルコペニアの定義と相互関係の理解
- 身体的・認知的・社会的フレイルの包括的アセスメント方法
- 筋肉量・筋力・身体機能の評価と判定基準
- 栄養・運動・社会参加を柱とした多面的介入アプローチ
- 入院によるフレイル進行の予防と早期回復に向けた看護
2. 病態の基本情報
定義
フレイル:加齢に伴う予備能力低下により、ストレスに対する回復力が減弱した状態 サルコペニア:加齢や疾患により筋肉量と筋力または身体機能が低下した状態
疫学
65歳以上の日本人におけるフレイルの有病率は7-12%、プレフレイルは約50%と報告されています。サルコペニアは65歳以上で男性12-18%、女性8-13%に認められ、85歳以上では30%以上に達します。入院患者ではフレイルが30-40%、サルコペニアが25-50%と有病率が高く、入院による廃用症候群の進行が問題となります。フレイル高齢者の要介護認定率は健常高齢者の約5倍で、死亡リスクは1.8-2.3倍高いことが知られています。
分類・病型
フレイルは身体的フレイル、認知的フレイル、社会的フレイルの3つの側面から評価されます。身体的フレイルは筋力低下、歩行速度低下、体重減少、疲労感、活動性低下が特徴で、最も客観的に評価しやすい領域です。認知的フレイルは認知機能の軽度低下を伴うフレイルで、将来の認知症発症リスクが高い状態とされています。社会的フレイルは社会的つながりの低下、経済的困窮、社会参加の減少が特徴で、特に日本の高齢者では重要な問題となっています。
サルコペニアは原因により一次性(加齢性)サルコペニアと二次性サルコペニアに分類されます。二次性サルコペニアはさらに活動関連性(廃用、無重力)、疾患関連性(炎症、悪性腫瘍、内分泌疾患)、栄養関連性(摂取不足、吸収不良)に細分されます。
3. 病態生理
基本メカニズム
フレイルとサルコペニアの発症は「体の貯金が少なくなった状態」に例えることができます。若い頃から蓄えてきた身体的・認知的・社会的な「貯金」が加齢とともに徐々に減少し、ある閾値を下回ると日常生活に支障をきたすようになります。これは銀行口座の残高が減って、少しの出費でも家計が苦しくなる状況に似ています。
筋肉においては、加齢により筋タンパク質の合成低下と分解促進のバランスが崩れ、年間1-2%の筋肉量減少が生じます。特に速筋線維(瞬発力に関わる筋肉)の減少が著しく、これが転倒リスクの増加につながります。
進行過程
フレイル・サルコペニアの進行は段階的です。健常期では予備能力が十分にあり、ストレスに対して適切に対応できます。プレフレイル期では予備能力の低下が始まり、軽度のストレスでも回復に時間がかかるようになります。この時期は「疲れやすくなった」「以前より時間がかかる」といった主観的な変化として現れます。
フレイル期では明らかな機能低下が現れ、日常生活に支障をきたすようになります。さらに進行すると要介護状態に至り、基本的な日常生活動作にも介助が必要となります。重要なのは、フレイル期までは適切な介入により改善が可能な可逆的な状態であることです。
身体的変化の特徴
筋肉量の減少は全身に及びますが、特に下肢筋群と体幹筋群の減少が顕著です。これにより歩行能力、バランス能力、起立動作能力が低下し、転倒リスクが増加します。また、呼吸筋の筋力低下により咳嗽力が減弱し、誤嚥性肺炎のリスクも高まります。
内分泌系では成長ホルモン、IGF-1、テストステロンの分泌低下により筋タンパク質合成が減少し、インスリン抵抗性の増加により糖代謝も悪化します。
合併症・併発する病態
フレイル・サルコペニアは様々な有害事象のリスクを増加させます。転倒・骨折のリスクは健常高齢者の3-5倍に増加し、特に大腿骨近位部骨折は要介護状態への直接的な原因となります。感染症に対する抵抗力も低下し、軽微な感染でも重篤化しやすくなります。心血管疾患、糖尿病、認知症の発症リスクも高く、入院期間の延長や再入院率の増加も認められます。
看護に活かすポイント
「なぜ入院により急激に機能低下するのか」を理解することで、入院中の予防的ケアの重要性を認識できます。また、「なぜ栄養だけでは改善しないのか」を知ることで、運動と栄養の組み合わせた介入の必要性を理解できます。
4. 症状・検査・治療
代表的な症状・徴候
患者さんからよく聞かれる訴えとして、「階段を上がるのがきつくなった」「買い物袋が重く感じる」「歩くのが遅くなったと言われる」「疲れやすくなった」「食欲がない」「体重が減った」などがあります。家族からは「動作が緩慢になった」「外出を嫌がるようになった」「食事量が減った」といった変化の指摘があります。
身体所見では握力低下(男性28kg未満、女性18kg未満)、歩行速度低下(1.0m/秒未満)、体重減少(6ヶ月で2-3kg以上)、下腿周囲径減少(男性34cm未満、女性33cm未満)がみられます。起立歩行テストでは椅子からの立ち上がりに時間がかかり、片脚立位保持時間が短縮します。
主要な検査・診断
フレイルの評価にはCHS基準(Cardiovascular Health Study)やJ-CHS基準が用いられ、①体重減少、②疲労感、③活動性低下、④緩慢性、⑤筋力低下の5項目のうち3項目以上でフレイル、1-2項目でプレフレイルと判定されます。
サルコペニアの診断ではAWGS2019基準(Asian Working Group for Sarcopenia)が推奨され、①筋力低下(握力:男性28kg未満、女性18kg未満)、②筋肉量低下(DXA法、BIA法で評価)、③身体機能低下(歩行速度1.0m/秒未満、SPPB≤9点)を総合的に評価します。
栄養評価ではMNA-SF(Mini Nutritional Assessment-Short Form)、血清アルブミン値(3.5g/dl未満で低栄養のリスク)、BMI(22kg/㎡未満で低体重)を確認します。
治療の基本
フレイル・サルコペニアの治療は多面的介入が基本となります。運動療法では有酸素運動と筋力トレーニングの組み合わせが効果的で、週2-3回、1回30-60分程度の実施が推奨されます。栄養療法ではタンパク質摂取量1.2-1.6g/kg/日を目標とし、特に必須アミノ酸の摂取が重要です。
薬物療法は限定的ですが、男性ではテストステロン補充療法、栄養不良ではアミノ酸製剤の使用が検討されます。社会参加の促進も重要で、地域のサロン活動や体操教室への参加を支援します。
5. 看護のポイント
主な看護診断
- 活動耐性低下
- 転倒リスク状態
- 栄養摂取不足
- 社会的孤立
ゴードンの機能的健康パターン別観察項目
活動-運動パターンが最も重要な観察項目となります。歩行速度、歩幅、歩行の安定性、階段昇降能力、起立動作の様子を詳細に観察し、日常生活動作の自立度を継続的に評価します。転倒歴や転倒に対する恐怖感の有無も重要な情報です。
栄養-代謝パターンでは食事摂取量、体重変化、BMI、血清アルブミン値を定期的に評価し、栄養状態の悪化を早期に発見します。認知-知覚パターンでは認知機能の評価とともに、気分の変化や意欲の低下についても観察します。
役割-関係パターンでは社会的つながりの状況、家族関係、地域活動への参加状況を把握し、社会的フレイルの評価を行います。
ヘンダーソンの基本的欲求からみた看護
運動の欲求に対しては、患者さんの身体機能に応じた適切な運動プログラムの提供と継続支援を行います。安全性を確保しながら、可能な限り自立した活動を促進し、廃用症候群の進行を防ぎます。ベッド上安静が必要な場合でも、関節可動域訓練や等尺性収縮運動を実施します。
食事と水分の欲求については、十分なタンパク質とエネルギーの摂取を支援し、食事の楽しみを維持しながら栄養改善を図ります。摂食嚥下機能の評価も重要で、安全で効率的な栄養摂取を支援します。
社会参加の欲求に対しては、入院中であっても他患者との交流機会を設け、退院後の社会復帰に向けた準備を支援します。
病態に応じた具体的な看護介入
入院時のアセスメントでは入院前の生活機能を詳細に聴取し、フレイル・サルコペニアの程度を評価します。ADL評価(Barthel Index、FIM)、IADL評価(Lawton Scale)、認知機能評価(MMSE、HDS-R)を実施し、包括的な機能評価を行います。
入院中の機能維持では早期離床を促進し、可能な限りベッド上安静を避けます。日中の活動性向上のため、リハビリテーション以外の時間でも座位保持や歩行を促進します。栄養管理では管理栄養士と連携し、個別の栄養計画を立案・実施します。
退院準備では退院後の生活環境評価、介護サービスの調整、家族指導を行い、在宅での機能維持・改善を支援します。
予防・悪化防止のポイント
入院関連機能低下の予防には「動かない時間」を最小限にすることが重要です。検査や処置以外では可能な限り離床し、食事は食堂で摂取することを促します。感染予防により不要な安静期間を避け、せん妄予防により認知機能の維持を図ります。
継続的な運動習慣の確立に向けて、患者さんが取り組みやすい運動プログラムを提案し、退院後も継続できるよう指導します。社会参加の継続支援として、地域の健康教室や介護予防事業への参加を促進します。
6. よくある質問・Q&A
Q:フレイルとサルコペニアの違いがよく分からないのですが、どう説明すればよいでしょうか?
A: サルコペニアは主に「筋肉」に焦点を当てた概念で、筋肉量・筋力・身体機能の低下を評価します。一方、フレイルはより包括的な概念で、身体機能だけでなく認知機能や社会的つながりも含めた「全体的な虚弱状態」を表します。つまり、サルコペニアはフレイルの身体的側面の一部と考えることができます。患者さんには「筋肉の衰え(サルコペニア)が、体全体の弱り(フレイル)の重要な要因の一つです」と説明すると理解しやすいでしょう。
Q:入院中の患者さんのフレイル進行を防ぐために、具体的にどのような看護を行えばよいですか?
A: 早期離床が最も重要で、医師の許可があれば入院翌日から離床を開始します。食事は食堂で摂取し、トイレ歩行を促進して「動く理由」を作ります。ベッド上でも運動を継続し、足関節の背屈運動、膝の屈伸、深呼吸などを定期的に行います。栄養管理では食事摂取量を正確に記録し、不足時は補食や栄養補助食品を提供します。認知刺激として新聞を読んでもらったり、他患者との会話を促したりすることも重要です。
Q:高齢の患者さんに運動を勧めても「もう年だから」と消極的な場合、どう関わればよいでしょうか?
A: まず患者さんの気持ちを受け止め、「年齢を重ねることで心配になるお気持ちはよく分かります」と共感を示します。その上で、フレイルの可逆性について説明し、「適切な運動と栄養により、何歳からでも改善が期待できます」と希望を伝えます。小さな目標から始め、「今日は廊下を端まで歩いてみましょう」といった達成可能な活動を提案します。成功体験を積み重ね、「昨日より歩けるようになりましたね」と変化を一緒に喜ぶことで、患者さんの意欲向上を図ります。
Q:実習でフレイル・サルコペニアの患者さんを受け持った時、どのような観察項目を重点的に記録すればよいですか?
A: 身体機能(歩行速度、歩行距離、起立動作の安定性、階段昇降の可否)、筋力(握力、下肢筋力、起立テストの結果)、栄養状態(体重、BMI、食事摂取量、血清アルブミン値)を継続的に記録します。活動量(離床時間、歩行回数、リハビリテーションへの参加状況)、認知機能(見当識、注意力、記憶力)、気分・意欲(表情、発言内容、活動への積極性)も重要な観察項目です。数値だけでなく、「階段昇降時に手すりを両手で支持する必要がある」「食事摂取に30分以上要する」といった具体的な機能状態を記録することが大切です。
7. まとめ
フレイル・サルコペニアは高齢者において極めて頻度が高く、要介護状態への移行を予防する上で重要な概念です。看護師の適切なアセスメントと多面的な介入により、患者さんの身体機能と生活の質の維持・改善を図ることができる可逆的な病態であることを理解することが大切です。
覚えるべき数値
- フレイル有病率:65歳以上で7-12%
- プレフレイル:約50%
- サルコペニア有病率:65歳以上で男性12-18%、女性8-13%
- 握力基準値:男性28kg未満、女性18kg未満
- 歩行速度基準値:1.0m/秒未満
- 下腿周囲径:男性34cm未満、女性33cm未満
- 推奨タンパク質摂取量:1.2-1.6g/kg/日
- 年間筋肉量減少率:1-2%
実習・現場で活用できるポイント
フレイル・サルコペニアの患者さんへの関わりでは、「できないこと」ではなく「できること」に焦点を当て、患者さんの強みを活かしたケアプランを立案してください。入院による機能低下は予防可能であることを念頭に置き、積極的な早期離床と活動促進を心がけます。運動と栄養の両面からのアプローチが重要で、リハビリテーション部門や栄養部門との連携を密にとってください。また、退院後の生活を見据えた包括的な支援により、患者さんの自立した生活の継続を支援することができます。小さな変化や改善も見逃さず、患者さんと一緒に喜び、継続的な取り組みへの動機づけを行うことが重要です。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
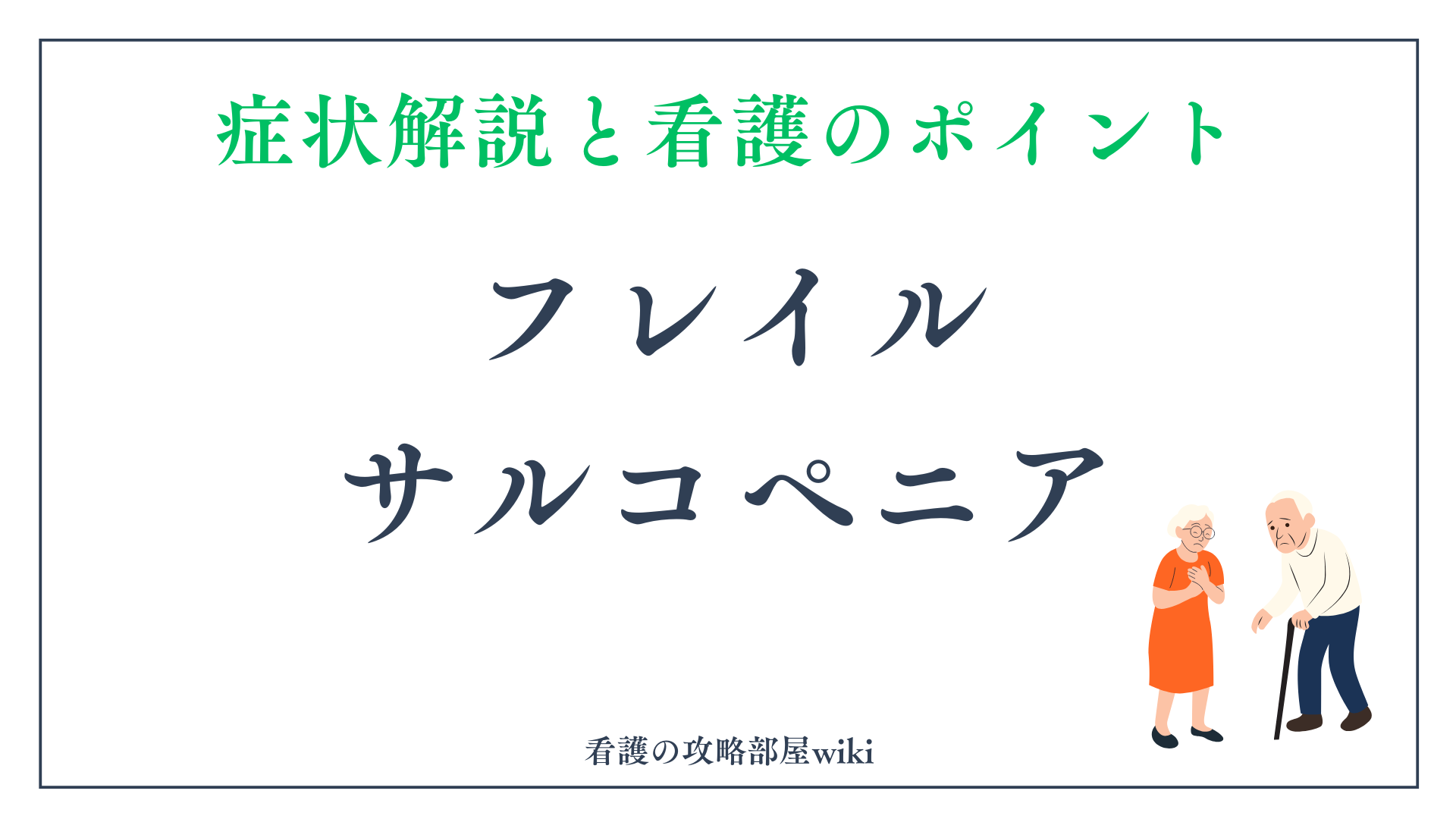


コメント