1. はじめに
「患者さんの尿量が急に減った…」「1日に何リットルも尿が出ている…」実習中にこのような状況に遭遇したことはありませんか?尿量の異常は、腎機能や全身状態を反映する重要なバイタルサインの一つです。適切な観察と迅速な対応が患者さんの生命に直結することもあります。
この記事で学べること
- 実習現場で活用できる具体的な観察技術と記録方法
- 乏尿・無尿・多尿の定義と正常範囲の理解
- 原因別の病態生理メカニズムと鑑別ポイント
- ゴードンとヘンダーソンの理論に基づいた系統的な看護アプローチ
- 緊急度に応じた優先順位の高い看護介入方法
2. 病態の基本情報
定義
乏尿は1日尿量が400ml未満、無尿は100ml未満、多尿は3000ml以上の状態
疫学
急性腎障害の約50-60%で乏尿が認められ、入院患者の約5-10%が何らかの尿量異常を経験します。乏尿の死亡率は約30-50%と高く、早期発見・早期対応が生命予後を大きく左右します。多尿は糖尿病患者の約40-60%で見られ、特に血糖コントロール不良例で顕著です。高齢者では生理的な腎機能低下により、軽度の乏尿(400-600ml/日)を呈することも珍しくありません。
分類・病型
尿量異常は発生メカニズムによって分類されます。腎前性は腎臓への血流が減少することで起こり、脱水や心不全、ショックが原因となります。腎性は腎臓自体の障害によるもので、急性腎炎や薬剤性腎障害が代表的です。腎後性は尿路の閉塞によるもので、結石や腫瘍による尿管・尿道閉塞が原因となります。多尿については浸透圧利尿(糖尿病など)と水利尿(尿崩症など)に大別され、それぞれ異なる対応が必要です。
3. 病態生理
基本メカニズム
尿量のコントロールを家庭の水道システムで例えてみましょう。腎臓は「浄水場」、糸球体は「フィルター」、尿細管は「再利用システム」の役割を果たします。正常では1日約180Lもの原尿が作られますが、99%以上が再吸収され、最終的に約1500mlの尿として排出されます。この精密なシステムのどこかに問題が起きると、尿量に異常が現れるのです。
進行過程
正常な尿量は1000-2000ml/日(約0.5-1.0ml/kg/時)です。初期段階では軽度の尿量減少(600-800ml/日)が見られ、この時期は代償機能により症状が現れにくいことがあります。代償期を過ぎると明らかな乏尿(400ml/日未満)となり、浮腫や呼吸困難などの体液貯留症状が現れ始めます。さらに進行すると無尿状態となり、数時間から数日で生命に危険が及ぶ状態になります。一方、多尿では初期は軽度の多飲・多尿から始まり、進行すると脱水症状や電解質異常が顕著になります。
病型別の違い
• 腎前性乏尿:尿の濃縮能は保たれており、尿比重は高く(1.020以上)、尿中ナトリウムは低値
• 腎性乏尿:濃縮能が障害され、尿比重は低く(1.010前後)、尿中ナトリウムは高値
• 腎後性乏尿:閉塞部位により異なるが、完全閉塞では急激な無尿、部分閉塞では尿量の変動
• 浸透圧利尿性多尿:尿比重は高く、尿中糖や電解質が多量に含まれる
• 水利尿性多尿:尿比重は低く(1.005以下)、薄い尿が大量に産生される
合併症・併発する病態
乏尿・無尿では体液貯留による肺水腫や心不全が生命に直結する合併症となります。電解質異常では特に高カリウム血症(6.0mEq/L以上)が危険で、致死的不整脈を引き起こす可能性があります。また、老廃物の蓄積により尿毒症を呈し、意識障害や消化器症状が現れます。多尿では脱水と電解質異常(特に低ナトリウム血症、低カリウム血症)が主要な合併症で、重篤な場合は意識障害や不整脈を引き起こします。
看護に活かすポイント
尿量の観察で最も重要なのは「なぜその尿量なのか?」を考えることです。単に数値だけでなく、尿の性状(色調、混濁、泡立ち)、患者の水分摂取量、全身状態を総合的に評価します。また、尿量の変化は時間単位で急激に変化することもあるため、継続的な監視が不可欠です。特に手術後や薬剤投与後、造影剤使用後は腎機能が急激に悪化する可能性があるため、より注意深い観察が必要です。
4. 症状・検査・治療
代表的な症状・徴候
乏尿・無尿の患者さんは「足がむくんできて、靴がきつい」「息苦しくて横になれない」といった体液貯留症状を訴えることが多くあります。進行すると「気持ちが悪くて食べられない」「頭がぼーっとする」という尿毒症症状も現れます。多尿の患者さんは「のどが渇いて水ばかり飲んでいる」「1時間おきにトイレに行く」と訴え、夜間も頻繁な排尿で睡眠が妨げられます。また、「立ちくらみがする」「力が入らない」といった脱水や電解質異常による症状も重要です。
主要な検査・診断
尿量測定が基本となり、正確な時間尿量(ml/時)の把握が重要です。尿検査では尿比重(正常値:1.015-1.025)、尿中ナトリウム、尿浸透圧から原因を推定できます。血液検査では血清クレアチニン(正常値:男性0.65-1.07mg/dl、女性0.46-0.79mg/dl)、BUN(正常値:8-20mg/dl)の上昇程度から腎機能を評価します。血清電解質では特にカリウム(正常値:3.6-4.8mEq/L)の値に注意が必要で、6.0mEq/L以上では緊急対応が必要です。看護師は検査値の変動パターンと症状の関連性を理解し、異常値を早期に発見することが重要です。
治療の基本
腎前性乏尿では適切な輸液による循環血液量の回復が最優先で、心原性の場合は強心薬や利尿薬が使用されます。腎性乏尿では原因疾患の治療とともに、腎代替療法(血液透析、腹膜透析)が検討されます。腎後性乏尿では緊急的な尿路ドレナージが必要で、膀胱留置カテーテルや腎瘻造設が行われます。多尿では原疾患の治療とともに、適切な水分・電解質補給が重要で、糖尿病性の場合はインスリン治療も並行して行われます。
5. 看護のポイント
主な看護診断
• 体液量過多(乏尿・無尿による体液貯留) • 体液量不足リスク状態(多尿による脱水) • 電解質バランス異常(高カリウム血症、低ナトリウム血症) • 活動耐性低下(浮腫、脱水による身体機能低下)
ゴードンの機能的健康パターン別観察項目
排泄パターンが最重要な観察領域となります。1時間ごとの正確な尿量測定と、尿の性状(色調、混濁、泡立ち、臭い)を継続的に評価します。排尿時間や排尿困難感の有無も詳細に観察し、膀胱留置カテーテル使用時は閉塞や感染兆候にも注意します。栄養代謝パターンでは水分出納バランスを正確に把握し、体重変化(1日0.5kg以上の変動は要注意)を毎日同条件で測定します。浮腫の程度は圧痕の深さと持続時間で段階評価し、特に下腿、仙骨部、眼瞼の観察が重要です。活動運動パターンでは呼吸困難の程度、起座呼吸の有無、日常生活動作への影響を具体的に評価します。
ヘンダーソンの基本的欲求からみた看護
正常な排泄の欲求では、尿量異常の原因や治療について患者・家族に分かりやすく説明し、排尿に関する不安を軽減します。膀胱留置カテーテル管理では、患者の自立度に応じてセルフケア指導を行い、感染予防の重要性を理解してもらいます。適切な栄養と水分摂取の欲求では、病態に応じた水分制限や塩分制限を、患者のライフスタイルに合わせて実践可能な方法で指導します。多尿患者では適切な水分補給方法と、脱水兆候のセルフチェック方法を教育します。正常な呼吸の欲求では、体液貯留による呼吸困難に対する体位の工夫や、環境調整による呼吸楽化を支援します。
病態に応じた具体的な看護介入
軽度の尿量異常期では、正確な水分出納バランスの測定と記録が最優先となります。患者・家族に尿量測定の重要性を説明し、可能な範囲でセルフモニタリングを促進します。中等度異常期では、浮腫や脱水症状の詳細な観察とともに、活動制限の必要性を患者の理解度に応じて説明します。体位変換時の注意点や、浮腫による皮膚トラブル予防策も具体的に指導します。重度異常期では、生命に直結する合併症(肺水腫、高カリウム血症)の早期発見が最重要で、バイタルサインの頻回測定と異常時の迅速な報告体制を確立します。
予防・悪化防止のポイント
腎機能悪化を防ぐためには、まず薬剤性腎障害のリスクを最小限にすることが重要です。NSAIDsや造影剤、抗菌薬などの腎毒性薬剤使用時は、事前の水分負荷と使用後の腎機能監視を徹底します。また、感染症や脱水の予防も重要で、適切な手洗いと口腔ケア、十分な水分摂取(病状に応じて)を指導します。高血圧や糖尿病などの基礎疾患管理の重要性も説明し、定期的な検査受診の必要性を患者・家族と共有します。早期受診の目安となる症状(尿量の急激な変化、浮腫の増悪、呼吸困難)を具体的に教育します。
6. よくある質問・Q&A
Q:尿量はどのくらいの頻度で測定すればよいですか?
A: 病状の重篤度によって異なりますが、基本的には1時間ごとの測定が推奨されます。特に急性期や治療開始直後は、尿量の変化が治療効果や病状悪化の重要な指標となるため、正確な時間測定が不可欠です。安定期では4-6時間ごとでも可能ですが、1日総量だけでなく時間尿量(ml/時)も記録し、0.5ml/kg/時未満が続く場合は医師への報告が必要です。
Q:膀胱留置カテーテルの患者で尿量が急に減った場合、まず何をチェックしますか?
A: まずカテーテルの閉塞を疑い、チューブの屈曲やクランプの確認、尿バッグ内の血塊や沈渣の有無をチェックします。カテーテル周囲からの尿漏れがないか、膀胱部の膨隆がないかも観察します。これらに問題がなければ、腎前性(脱水、血圧低下)、腎性(薬剤性、感染性)、腎後性(カテーテル以外の閉塞)の原因を順次検討し、バイタルサイン測定と医師への報告を行います。
Q:多尿の患者さんの水分管理で注意すべき点は何ですか?
A: 多尿患者では過度な水分制限は危険です。脱水を防ぐため、尿量に応じた適切な水分補給が必要で、一般的には尿量の80-100%程度の水分摂取が目安となります。電解質入りの経口補水液の使用も有効です。ただし、心疾患や腎疾患がある場合は医師の指示に従い、体重や浮腫の程度を指標として調整します。患者には喉の渇きに応じた適度な水分摂取の重要性を説明し、一度に大量摂取せず少量頻回摂取を勧めます。
Q:高カリウム血症の患者で最も注意すべき症状は何ですか?
A: 最も危険なのは不整脈です。血清カリウム値が6.0mEq/L以上になると、心電図変化(テント状T波、QRS幅拡大)や致死的不整脈のリスクが高まります。患者の症状では、筋力低下、しびれ感、悪心・嘔吐などが現れますが、これらは主観的症状のため、心電図モニターでの継続監視と定期的な血液検査による客観的評価が不可欠です。異常を発見した場合は緊急対応が必要です。
7. まとめ
尿量異常は腎機能や全身状態を反映する重要なバイタルサインです。看護師として正確な観察と迅速な対応により、患者の生命予後を大きく改善できます。特に時間尿量の継続的な監視と、原因に応じた系統的なアセスメントが重要です。
覚えるべき数値 • 正常尿量:1000-2000ml/日(0.5-1.0ml/kg/時) • 乏尿:400ml/日未満(0.5ml/kg/時未満) • 無尿:100ml/日未満 • 多尿:3000ml/日以上 • 危険な高カリウム血症:6.0mEq/L以上
実習・現場で活用できるポイント
尿量測定は単なる数値記録ではなく、患者の全身状態を把握する重要な観察です。正確な時間測定と尿性状の観察、水分出納バランスの把握を基本とし、異常値を発見した際の迅速な報告・対応が患者の生命を守ります。また、患者・家族への教育により、退院後も継続的な自己管理が可能となり、再入院の予防にもつながります。病態に応じた個別性のある看護実践により、患者のQOL向上と早期回復を支援することが、質の高い看護につながります。厳を支える看護を提供しましょう。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
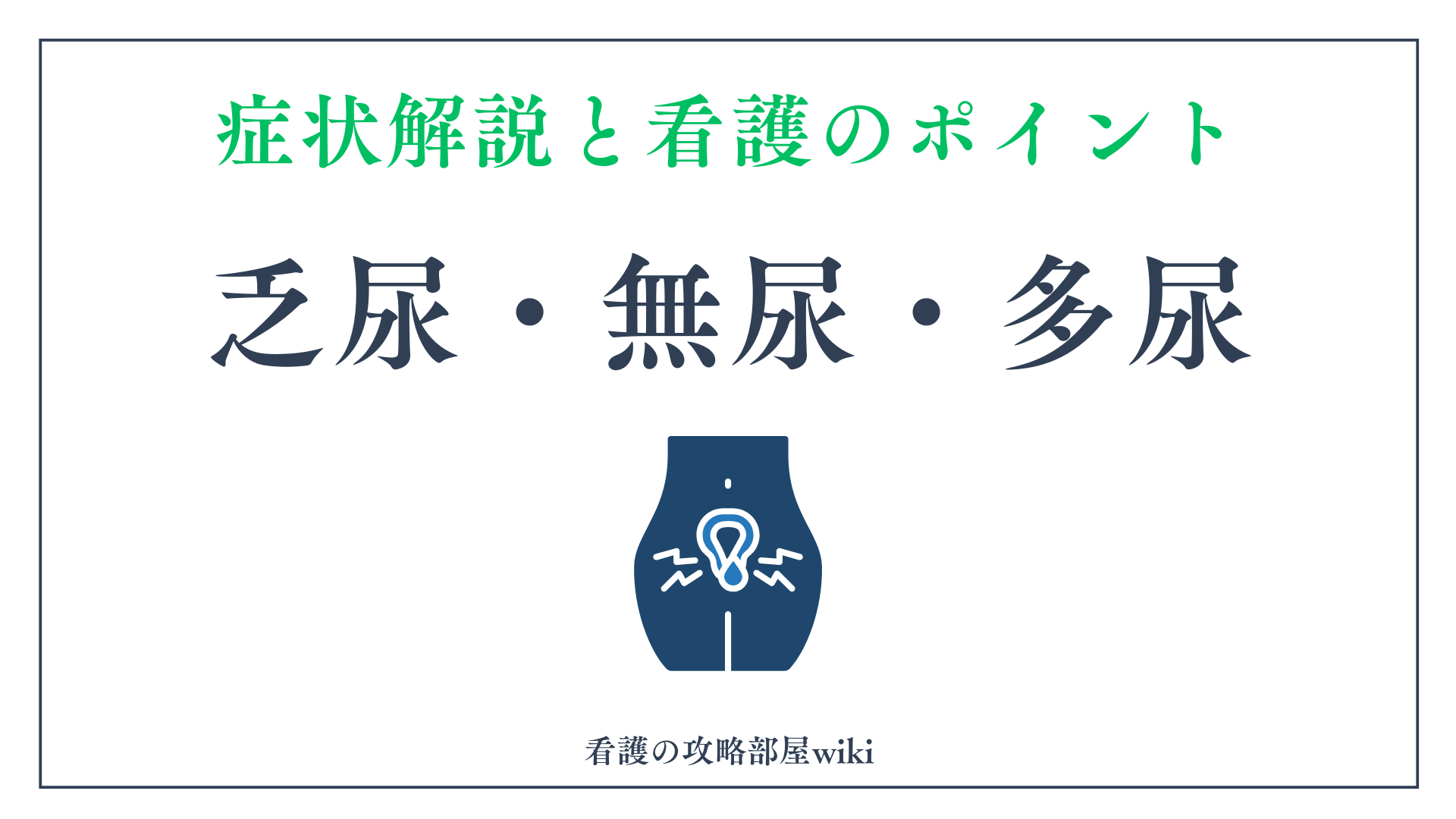


コメント