1. はじめに
実習で患者さんの尿検査結果を見て、「血尿+」や「蛋白尿+2」という表記に戸惑った経験はありませんか?血尿や蛋白尿は、腎・泌尿器系の疾患だけでなく、全身の健康状態を反映する重要なサインです。これらの症状を正しく理解することで、患者さんの病態を的確にアセスメントし、適切な看護ケアを提供できるようになります。
この記事で学べること
・血尿
・蛋白尿の発生メカニズムと分類
・各種検査値の読み方と看護師が注目すべきポイント
・ゴードンの機能的健康パターンに基づいた観察項目
・ヘンダーソンの基本的欲求からみた看護介入
・実習で活用できる具体的なアセスメント方法
2.病態の基本情報
定義
血尿は尿中に赤血球が異常に混入した状態、蛋白尿は尿中に蛋白質が異常に排泄された状態
疫学
健康診断での血尿検出率は約3-5%、蛋白尿検出率は約2-7%とされています。特に高齢者では腎機能低下により蛋白尿の頻度が高くなります。慢性腎臓病(CKD)患者数は日本で約1,330万人(成人の8人に1人)と推計されており、血尿・蛋白尿はその重要な早期発見指標となっています。
分類・病型
血尿は見た目による分類で肉眼的血尿(目で見て赤い尿)と顕微鏡的血尿(検査でのみ発見される)に分けられます。蛋白尿は程度により微量アルブミン尿(30-300mg/g・Cr)、顕性蛋白尿(300mg/g・Cr以上)に分類されます。発生部位では糸球体性(腎臓内の濾過装置の問題)と非糸球体性(尿路の問題)に分けられ、糸球体性では赤血球の形が変形し、蛋白質も多く漏れる特徴があります。原因による分類では一過性(運動後、発熱時など)と持続性(慢性疾患による)があり、持続性の場合は詳しい検査が必要になります。
3. 病態生理
基本メカニズム
腎臓は体の「浄水器」のような働きをしており、糸球体という細かい網目状のフィルターで血液を濾過します。正常な状態では、赤血球や蛋白質のような大きな分子はこのフィルターを通過しません。しかし、糸球体に炎症や損傷が起こると、「網の目が粗くなった状態」になり、本来通らないはずの赤血球や蛋白質が尿中に漏れ出てしまいます。これは家庭用の浄水器のフィルターが古くなって、本来取り除かれるべき不純物が通り抜けてしまう状況と似ています。
進行過程
正常期では糸球体の構造が保たれており、尿検査で異常は認められません。代償期に入ると軽度の糸球体損傷により微量の血尿や蛋白尿が出現しますが、腎機能は正常範囲を保ちます。この段階では患者さんに自覚症状はほとんどありません。進行期では糸球体の損傷が拡大し、血尿や蛋白尿が持続的に認められ、血清クレアチニンの上昇も見られるようになります。非代償期では腎機能が著しく低下し、浮腫や高血圧、貧血などの症状が現れ、最終的には透析療法が必要になる場合もあります。
病型別の違い
・糸球体性血尿・蛋白尿:赤血球が変形(円盤形→いびつな形)し、蛋白尿を同時に認める
・非糸球体性血尿:赤血球の形状は正常で、蛋白尿は軽度または認めない
・一過性血尿・蛋白尿:運動後や発熱時に一時的に出現し、安静により改善する
・持続性血尿・蛋白尿:慢性疾患により継続的に認められ、進行性である
合併症・併発する病態
長期間の蛋白尿により低蛋白血症が生じ、血液中の蛋白質が減少することで血管内の水分が組織に漏れ出し、浮腫を引き起こします。また、高血圧は腎機能低下の原因であると同時に結果でもあり、悪循環を形成します。貧血は腎臓から分泌されるエリスロポエチンの減少により生じ、電解質異常(カリウム、リンの蓄積)も腎機能低下に伴って出現します。
看護に活かすポイント
血尿・蛋白尿の観察では「なぜその症状が起こるのか」を常に考えることが重要です。例えば、浮腫が見られる患者さんでは蛋白尿による低蛋白血症を疑い、血圧上昇があれば腎機能との関連を考える必要があります。また、検査値の変化だけでなく、患者さんの日常生活動作への影響や心理的負担も含めて総合的にアセスメントすることが大切です。
4. 症状・検査・治療
代表的な症状・徴候
肉眼的血尿では「尿が赤茶色になった」「コーラのような色の尿が出た」という患者さんの訴えがよく聞かれます。顕微鏡的血尿では自覚症状はなく、健康診断で偶然発見されることが多いです。蛋白尿に伴う症状として「朝起きると顔がむくんでいる」「靴下の跡がなかなか消えない」「体重が急に増えた」といった浮腫症状の訴えがあります。進行した場合には「息切れがする」「疲れやすい」「食欲がない」といった腎機能低下に伴う全身症状も現れます。
主要な検査・診断
尿定性検査では蛋白尿の程度を(-)から(4+)まで、血尿の程度を(-)から(3+)まで評価します。正常値は蛋白(-)、潜血(-)です。尿沈渣検査では顕微鏡で尿中の赤血球数(正常:男性1個/HPF以下、女性5個/HPF以下)や赤血球の形態を観察し、糸球体性か非糸球体性かを判断します。24時間蓄尿検査や随時尿での蛋白/クレアチニン比(正常:0.15g/g・Cr未満)により正確な蛋白排泄量を測定します。血液検査では血清クレアチニン(正常:男性0.65-1.07mg/dl、女性0.46-0.79mg/dl)、推定糸球体濾過量(eGFR)(正常:60ml/min/1.73㎡以上)により腎機能を評価します。
治療の基本
原因疾患の治療が最優先となります。糸球体腎炎にはステロイド治療や免疫抑制剤、高血圧性腎症にはACE阻害剤やARB(アンジオテンシン受容体拮抗薬)による血圧管理、糖尿病性腎症には血糖管理と血圧管理を行います。生活習慣の改善として減塩(6g/日未満)、蛋白制限(0.6-0.8g/kg/日)、適度な運動、禁煙が重要です。進行した慢性腎臓病では透析療法や腎移植が検討されます。
5. 看護のポイント
主な看護診断
・体液量過剰 水分・電解質バランス異常に関連した
・活動耐性低下 貧血・心機能低下に関連した
・感染リスク状態 免疫機能低下
・侵襲的処置に関連した
・不安 疾患の予後・治療に対する知識不足に関連した
ゴードンの機能的健康パターン別観察項目
栄養・代謝パターンでは浮腫の程度と分布を詳細に観察します。顔面浮腫は起床時に最も強く、下肢浮腫は夕方に増強する傾向があります。体重測定は毎日同一条件で行い、急激な増加(2-3日で2kg以上)は体液貯留を示します。食事摂取量と水分バランスの観察も重要で、蛋白制限食への適応状況や塩分制限の理解度を確認します。
排泄パターンでは尿量・尿色・尿の性状を継続的に観察し、特に乏尿(400ml/日未満)や無尿(100ml/日未満)の出現に注意が必要です。排尿時の痛みや頻尿、夜間尿の有無も確認し、尿路感染症の合併を早期発見します。
活動・運動パターンでは労作時呼吸困難や易疲労感の程度を評価し、貧血や心機能への影響を判断します。血圧測定は体位変換時の変動も含めて観察し、起立性低血圧の有無を確認します。
ゴードンの機能的健康パターン別観察項目
栄養・代謝パターンでは浮腫の程度と分布を詳細に観察します。顔面浮腫は起床時に最も強く、下肢浮腫は夕方に増強する傾向があります。体重測定は毎日同一条件で行い、急激な増加(2-3日で2kg以上)は体液貯留を示します。食事摂取量と水分バランスの観察も重要で、蛋白制限食への適応状況や塩分制限の理解度を確認します。
排泄パターンでは尿量・尿色・尿の性状を継続的に観察し、特に乏尿(400ml/日未満)や無尿(100ml/日未満)の出現に注意が必要です。排尿時の痛みや頻尿、夜間尿の有無も確認し、尿路感染症の合併を早期発見します。
活動・運動パターンでは労作時呼吸困難や易疲労感の程度を評価し、貧血や心機能への影響を判断します。血圧測定は体位変換時の変動も含めて観察し、起立性低血圧の有無を確認します。
ヘンダーソンの基本的欲求からみた看護
正常な排泄の欲求に対しては、尿量測定の重要性を患者さんに説明し、排尿日誌の記録を支援します。尿の性状変化(色調、混濁、泡立ちなど)に気づけるよう観察方法を指導し、異常時の報告を促します。排尿に関する不安や羞恥心に配慮し、プライバシーを保護した環境を整備します。
体液・電解質バランスの保持では、水分制限がある場合の具体的な管理方法(コップの大きさを変える、氷を利用するなど)を一緒に考え、患者さんが実践しやすい方法を見つけます。塩分制限についても、調味料の使い方や食材選択のコツを具体的にアドバイスし、家族の協力も得られるよう調整します。
学習の欲求に対しては、病態について分かりやすい言葉で説明し、患者さんの理解度に合わせた教育資料を準備します。治療の意義や生活管理の必要性について、患者さん自身が納得できるまで繰り返し説明し、セルフケア能力の向上を支援します。
病態に応じた具体的な看護介入
急性期では厳密な水分出納バランスの管理が最優先となります。1時間ごとの尿量測定を行い、乏尿や無尿の早期発見に努めます。浮腫の程度を客観的に評価するため、下腿周囲径の測定や圧痕浮腫の確認を定期的に行います。呼吸状態の観察も重要で、肺水腫の兆候(起座呼吸、湿性ラ音、咳嗽)に注意します。
慢性期では患者さんの生活習慣改善への支援が中心となります。食事療法の継続に向けて、栄養士との連携により個別性のある食事プランを作成し、家族も含めた指導を実施します。運動療法については、患者さんの腎機能や心機能に応じた適切な運動量を医師と相談して決定し、段階的に活動量を増加させます。定期的な検査結果の説明を通じて、治療への動機を維持できるよう支援します。
予防・悪化防止のポイント
感染予防は腎機能保護において極めて重要です。特に尿路感染症は腎機能を急速に悪化させる可能性があるため、清潔なトイレ環境の維持、適切な陰部洗浄の指導、十分な水分摂取(制限がない場合)を行います。血圧管理も継続的に必要で、家庭血圧測定の方法を指導し、目標血圧値(通常130/80mmHg未満、蛋白尿がある場合125/75mmHg未満)の維持を支援します。薬物療法のアドヒアランス向上のため、服薬カレンダーの活用や家族の協力体制を整備し、副作用の早期発見にも注意を向けます。
6. よくある質問・Q&A
Q:血尿があっても痛みがない場合、緊急性は低いのでしょうか?
A: 痛みがない血尿こそ注意が必要です。膀胱炎による血尿では排尿時痛を伴いますが、腎炎や腫瘍による血尿は無痛性のことが多いです。特に肉眼的血尿では、痛みの有無に関わらず早急な検査が必要になります。「痛くないから大丈夫」ではなく、「痛くない血尿は重篤な疾患の可能性がある」と考えましょう。
Q:蛋白尿が出ていても自覚症状がない患者さんに、なぜ食事制限が必要なのですか?
A: 蛋白尿は腎臓のSOSサインです。症状がなくても腎臓の糸球体では確実に損傷が進行しており、放置すると不可逆的な腎機能低下につながります。食事制限は腎臓への負担を軽減し、残された腎機能を保護するための重要な治療法です。患者さんには「今の努力が将来の透析回避につながる」ことを具体的に説明し、モチベーション維持を支援することが大切です。
Q:運動後の血尿・蛋白尿と病的な血尿・蛋白尿の見分け方は?
A: 運動後の血尿・蛋白尿は通常24-48時間以内に消失し、程度も軽度です。一方、病的なものは持続性があり、安静にしても改善しません。判断に迷う場合は、運動を控えて数日後に再検査を行います。また、運動強度に比べて血尿・蛋白尿の程度が強い場合や、軽い運動でも出現する場合は病的である可能性が高いです。
Q:透析導入の判断基準について患者さんから聞かれた場合、どう説明すればよいですか?
A: 透析導入は血清クレアチニン値だけでなく、患者さんの症状や生活の質も総合的に判断します。一般的にはeGFRが15ml/min/1.73㎡未満で導入を検討しますが、浮腫や呼吸困難、食欲不振などの尿毒症症状が強い場合は、もう少し早い段階で導入することもあります。「数値だけでなく、患者さんの生活の質を最も重視して医師が判断する」ことを伝え、不安があれば主治医との面談の機会を設けることが大切です。
7. まとめ
血尿・蛋白尿は腎臓から発信される重要な警告サインです。看護師として最も大切なことは、検査値の変化を敏感に察知し、患者さんの全身状態と関連付けて包括的にアセスメントすることです。また、慢性疾患としての特徴を理解し、患者さんが長期にわたって治療を継続できるよう、個別性を重視した支援を提供することが求められます。
覚えるべき数値
・正常尿蛋白:0.15g/g・Cr未満 ・正常血清クレアチニン:男性0.65-1.07mg/dl、女性0.46-0.79mg/dl
・正常eGFR:60ml/min/1.73㎡以上 ・透析導入検討:eGFR 15ml/min/1.73㎡未満 ・乏尿:400ml/日未満、無尿:100ml/日未満 ・減塩目標:6g/日未満
実習・現場で活用できるポイント
実習では患者さんの検査データを経時的に追うことで、腎機能の変化を実感できます。特に入院時と退院時の比較、治療前後の変化に注目しましょう。浮腫の観察では、触診による圧痕浮腫の確認方法を実際に体験し、患者さんの日常生活への影響を具体的にアセスメントしてください。また、患者さんとの会話の中で「尿の色や量の変化に気づいているか」「食事制限をどのように工夫しているか」などを聞き、患者教育のポイントを学び取ることが大切です。多職種カンファレンスでは、看護師の視点から患者さんの生活面での課題を積極的に提案し、チーム医療における看護の役割を実践してください。アセスメントを行い、多職種と連携しながら患者さんの自立と尊厳を支える看護を提供しましょう。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
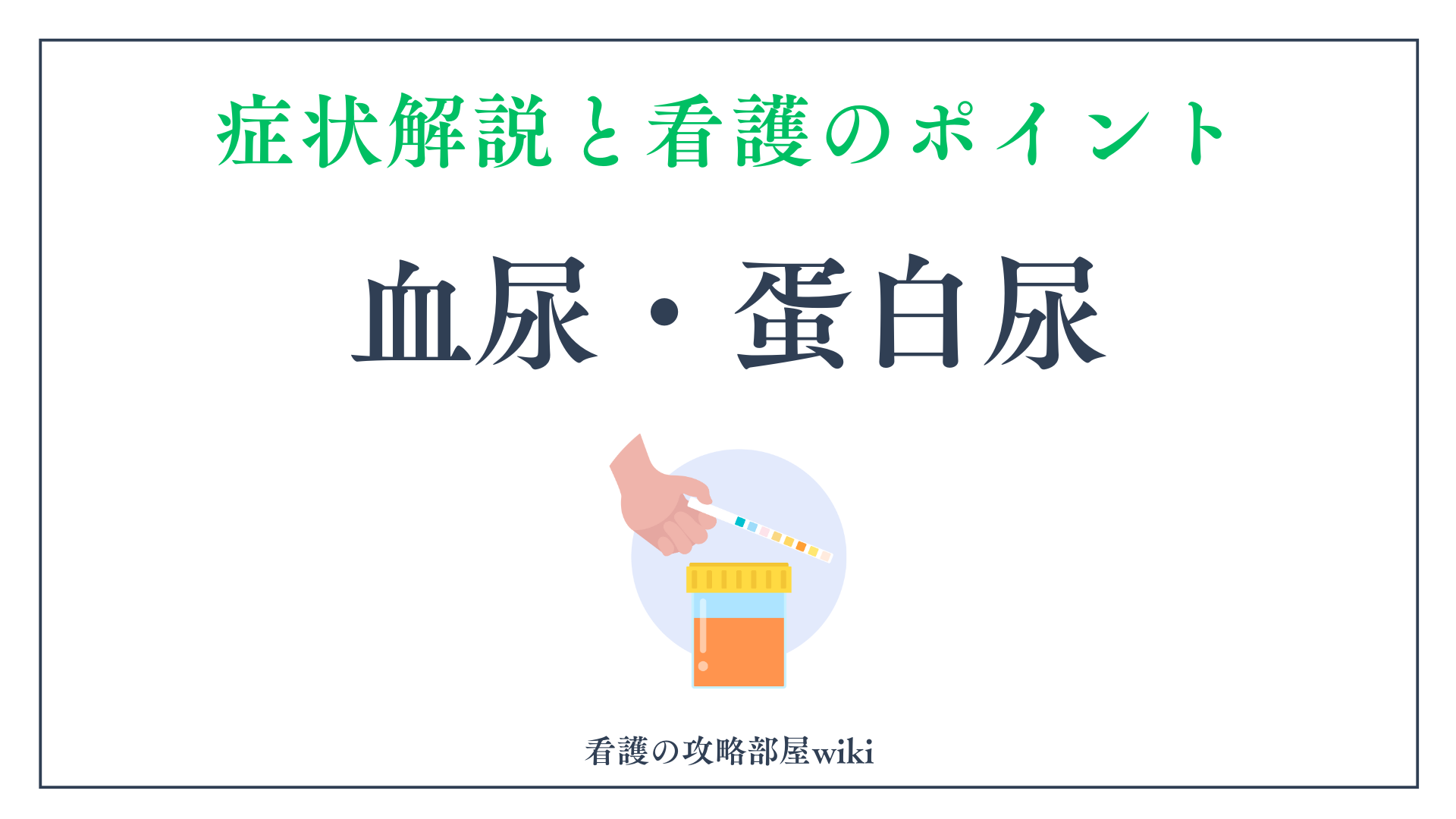


コメント