症状概要
定義
悪心とは、吐き気や胃部の不快感を自覚する主観的な症状で、患者は「気持ち悪い」「むかむかする」「吐きそう」などと表現します。嘔吐とは、胃内容物が食道を逆流して口から排出される現象です。悪心は嘔吐の前段階として出現することが多いですが、必ずしも嘔吐に至るわけではありません。これらの症状は非常に頻度が高く、消化器疾患だけでなく、中枢神経系、代謝性、薬剤性、心因性など多様な原因により生じます。中には頭蓋内圧亢進や腸閉塞など緊急対応が必要な疾患も含まれます。
疫学
悪心・嘔吐は日常的に経験される非常に頻度の高い症状です。急性胃腸炎による嘔吐は救急外来受診理由の上位を占めます。また、化学療法を受けるがん患者の約70〜80%が悪心・嘔吐を経験し、QOLに大きな影響を与えます。妊娠初期のつわり(妊娠悪阻)は妊婦の約50〜80%に見られ、そのうち約1〜2%は入院治療が必要な重症妊娠悪阻となります。術後の悪心・嘔吐(PONV)も約20〜30%の患者に発生し、回復を遅らせる要因となります。
原因
嘔吐・悪心の原因は非常に多岐にわたります。消化器疾患では、急性胃腸炎、食中毒、胃潰瘍、胃炎、腸閉塞、虫垂炎、胆石症、膵炎、肝炎などが挙げられます。中枢神経系疾患では、脳腫瘍、頭蓋内圧亢進、くも膜下出血、脳炎・髄膜炎、片頭痛、めまい症(メニエール病)などがあります。代謝性・内分泌疾患では、糖尿病性ケトアシドーシス、尿毒症、肝不全、電解質異常、甲状腺機能異常などが原因となります。薬剤性では、抗がん剤、麻薬、ジギタリス、抗菌薬などが有名です。その他、妊娠、心筋梗塞、緑内障発作、心因性(ストレス、不安障害)なども原因となります。
病態生理
嘔吐・悪心は延髄にある嘔吐中枢が刺激されることで生じます。嘔吐中枢への刺激経路は主に4つあります。第一に、消化管からの迷走神経を介した刺激、第二に、第四脳室底の化学受容器引金帯(CTZ)を介した刺激(薬物、代謝産物、毒素など)、第三に、大脳皮質からの刺激(視覚、嗅覚、記憶、不安など)、第四に、前庭器官からの刺激(めまい、動揺病)です。嘔吐反射が起こると、横隔膜と腹筋が収縮し、腹腔内圧が上昇すると同時に、食道下部括約筋が弛緩して胃内容物が逆流します。頻回の嘔吐により、脱水、電解質異常(低カリウム血症、代謝性アルカローシス)、栄養障害を引き起こし、重症化すると全身状態の悪化につながります。
原因疾患・評価・対応
主な原因疾患
緊急対応が必要な疾患として、腸閉塞、消化管穿孔、虫垂炎、急性膵炎、胆石症・胆嚢炎、頭蓋内圧亢進(脳腫瘍、くも膜下出血)、髄膜炎・脳炎、急性心筋梗塞、糖尿病性ケトアシドーシス、薬物中毒などがあります。頻度の高い疾患として、急性胃腸炎、食中毒、胃炎・胃潰瘍、片頭痛、めまい症、妊娠悪阻、薬剤性(抗がん剤、麻薬など)、術後悪心・嘔吐などが挙げられます。慢性的な悪心・嘔吐の原因として、胃がん、消化管通過障害、慢性腎不全、肝不全、機能性ディスペプシア、神経性食思不振症などがあります。高齢者では非典型的症状を呈することが多く、心筋梗塞でも悪心・嘔吐のみで現れることがあります。
評価とアセスメント
嘔吐・悪心の評価では、まず緊急性の判断が重要です。バイタルサイン(血圧、脈拍、体温、呼吸数、SpO2、意識レベル)を測定し、全身状態を評価します。危険なサインとして、ショック徴候(血圧低下、頻脈、冷汗、顔面蒼白)、意識障害、激しい頭痛、激しい腹痛、腹膜刺激症状、吐血・下血、脱水症状(皮膚ツルゴールの低下、尿量減少)があれば緊急対応が必要です。吐物の性状は重要な情報で、食物残渣、胆汁性(黄緑色)、糞便臭(腸閉塞)、血性(鮮血または coffee ground様)などを観察します。OPQRSTを用いて、発症時期、誘因(食事、薬剤)、嘔吐の回数と量、随伴症状(腹痛、下痢、発熱、頭痛、めまい)を確認します。脱水の程度を評価するため、口渇、尿量、皮膚ツルゴール、粘膜の湿潤度、体重減少も確認します。
対応と治療
嘔吐・悪心への対応は原因により異なりますが、共通する初期対応として、まず誤嚥予防のため側臥位をとらせ、脱水補正のため静脈ルートを確保し輸液を開始します。経口摂取が可能な場合は少量頻回の水分摂取を試みます。制吐薬は原因に応じて使用し、消化管運動促進薬(メトクロプラミド、ドンペリドン)、抗ヒスタミン薬、5-HT3受容体拮抗薬(オンダンセトロン)、NK1受容体拮抗薬などがあります。原因疾患の治療が最も重要で、腸閉塞では絶飲食と経鼻胃管挿入、急性胃腸炎では補液と整腸薬、化学療法による嘔吐では予防的制吐薬投与などを行います。頻回の嘔吐による電解質異常(特に低カリウム血症)の補正も重要です。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 体液量不足:頻回の嘔吐による体液・電解質喪失
- 栄養摂取消費バランス異常:悪心・嘔吐による食事摂取不良
- 誤嚥リスク:嘔吐による気道内への吐物吸引のリスク
ゴードン機能的健康パターン
栄養-代謝パターンでは、最終飲食時刻、食事内容、食欲、嘔吐の回数・量・性状、水分摂取量、体重変化を評価します。脱水徴候(口渇、尿量減少、皮膚ツルゴール低下)や電解質異常の症状(脱力感、不整脈)も確認します。排泄パターンでは、尿量と性状(濃縮尿)、排便状況(下痢、便秘、血便)を評価します。脱水により尿量が減少し、濃縮尿となります。活動-運動パターンでは、悪心・嘔吐により活動が制限され、安静を要することが多いです。長期化すると筋力低下や深部静脈血栓症のリスクも考慮します。認知-知覚パターンでは、悪心の程度をNRSなどで評価し、随伴する頭痛、腹痛、めまいなども確認します。
ヘンダーソン14基本的ニード
食べる・飲むニードが最も直接的に障害されています。嘔吐により経口摂取が困難となり、栄養と水分の補給が課題となります。症状が軽快してからの食事再開のタイミングと方法(少量頻回、消化の良いもの)の指導が重要です。正常に呼吸するニードでは、嘔吐時の誤嚥による窒息や誤嚥性肺炎のリスクを評価します。意識レベルが低下している場合や高齢者では特に注意が必要です。安全なニードでは、脱水による転倒リスク、電解質異常による不整脈リスク、嘔吐時の転倒・転落リスクを評価します。また、嘔吐による食道・胃粘膜損傷(Mallory-Weiss症候群)のリスクにも注意します。
看護計画・介入の内容
- 嘔吐・悪心の継続的評価:悪心の程度(NRS)、嘔吐の回数・量・性状・タイミングの記録、バイタルサインの継続的モニタリング、脱水徴候の観察(口渇、尿量、皮膚ツルゴール、粘膜の湿潤度、バイタルサイン変化)、電解質異常の症状(脱力感、不整脈、テタニー)の観察
- 誤嚥予防と安全確保:側臥位の保持、嘔吐時の介助(吐物受け、背部摩擦)、口腔ケア、ベッド周囲の環境整備(吐物受けの準備、ナースコールの配置)、転倒予防(ベッド柵の使用、移動時の付き添い)
- 症状緩和と水分・栄養管理:制吐薬の投与と効果判定、輸液管理と効果評価、可能であれば少量頻回の水分摂取(氷片、経口補水液)、食事再開時の段階的進め方の指導、環境調整(換気、不快な臭いの除去、静かな環境)、リラクセーション法の提供
よくある疑問・Q&A
Q: 嘔吐と吐血の違いは何ですか?
A: 嘔吐は胃内容物が排出される現象で、内容物には食物残渣や胆汁が含まれます。吐血は消化管(主に食道、胃、十二指腸)からの出血が口から排出される現象で、鮮紅色の血液または暗赤色〜黒色のcoffee ground様(コーヒー残渣様)の血液が見られます。吐血は上部消化管出血を示し、緊急対応が必要です。一方、下血は下部消化管出血を示し、肛門から排出されます。
Q: 嘔吐が糞便臭がするのはなぜですか?
A: 嘔吐物から糞便臭がするのは腸閉塞を強く疑う重要なサインです。腸管が閉塞すると内容物が停滞し、腸内細菌により発酵・腐敗して糞便様の臭いを発します。特に下部腸閉塞では、長時間停滞した腸内容物が逆流して嘔吐され、糞便臭を伴います。この場合、緊急対応が必要です。
Q: 化学療法の悪心・嘔吐はいつ起こりますか?
A: 化学療法による悪心・嘔吐は、急性(投与後24時間以内)、遅発性(投与後24時間以降、通常2〜5日目)、予期性(過去の経験から次回の化学療法前に生じる)に分類されます。使用する抗がん剤により催吐性リスクが異なり、シスプラチンなどは高リスク、パクリタキセルなどは低リスクです。予防的制吐薬の使用が重要です。
Q: つわりはいつからいつまで続きますか?
A: つわり(妊娠悪阻)は通常妊娠5〜6週頃から始まり、妊娠12〜16週頃にピークを迎え、その後徐々に軽快します。多くは妊娠16〜20週までに消失しますが、個人差が大きく、妊娠後期まで続く人もいます。水分も摂取できない、体重が著明に減少する、尿中ケトン体陽性などの場合は妊娠悪阻として入院治療が必要です。
Q: 嘔吐後の食事再開のタイミングと方法は?
A: 嘔吐が落ち着いてから2〜4時間程度は絶飲食とし、胃腸を休ませます。その後、まず少量の水分(白湯、麦茶、経口補水液)から開始し、問題なければ消化の良い食品(おかゆ、うどん、バナナ、りんごのすりおろし)を少量ずつ摂取します。一度に大量に摂取すると再び嘔吐を誘発するため、少量頻回が原則です。脂っこいもの、刺激物、冷たすぎるものは避けましょう。
Q: 嘔吐している人にはどのような体位をとらせればよいですか?
A: 側臥位(横向き)が基本です。仰臥位では吐物が気道に流れ込み、誤嚥や窒息のリスクがあります。意識レベルが低下している場合は特に注意が必要で、顔を横に向け、やや頭部を低くした回復体位をとらせます。嘔吐後は口腔内を清潔にし、誤嚥がないか呼吸状態を観察します。座位がとれる場合は、やや前傾姿勢で吐物受けを持たせると患者も楽です。
まとめ
嘔吐・悪心は非常に頻度の高い症状であり、多くは急性胃腸炎など軽症の疾患が原因ですが、中には腸閉塞や頭蓋内圧亢進など緊急対応が必要な疾患も含まれます。看護師の重要な役割は、緊急性を判断し、原因疾患を推測するための情報を収集することです。
特に、吐物の性状(糞便臭、血性、胆汁性)、随伴症状(激しい腹痛、頭痛、意識障害)、脱水徴候は重要な観察ポイントです。頻回の嘔吐は脱水と電解質異常を引き起こし、全身状態の悪化につながるため、水分・電解質バランスの評価と補正が必要です。
嘔吐時は誤嚥予防が最優先であり、側臥位の保持、嘔吐時の介助、口腔ケアが基本的な看護介入となります。また、患者にとって嘔吐は非常に不快で苦痛な症状であるため、共感的な態度で接し、安楽を提供することも重要です。
実習では、嘔吐・悪心を訴える患者に対して、吐物の性状を正確に観察・記録し、脱水徴候や電解質異常の症状を見逃さないよう継続的に観察しましょう。また、食事再開時には段階的で適切な方法を指導し、患者のセルフケア能力を高める支援を行うことが大切です。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
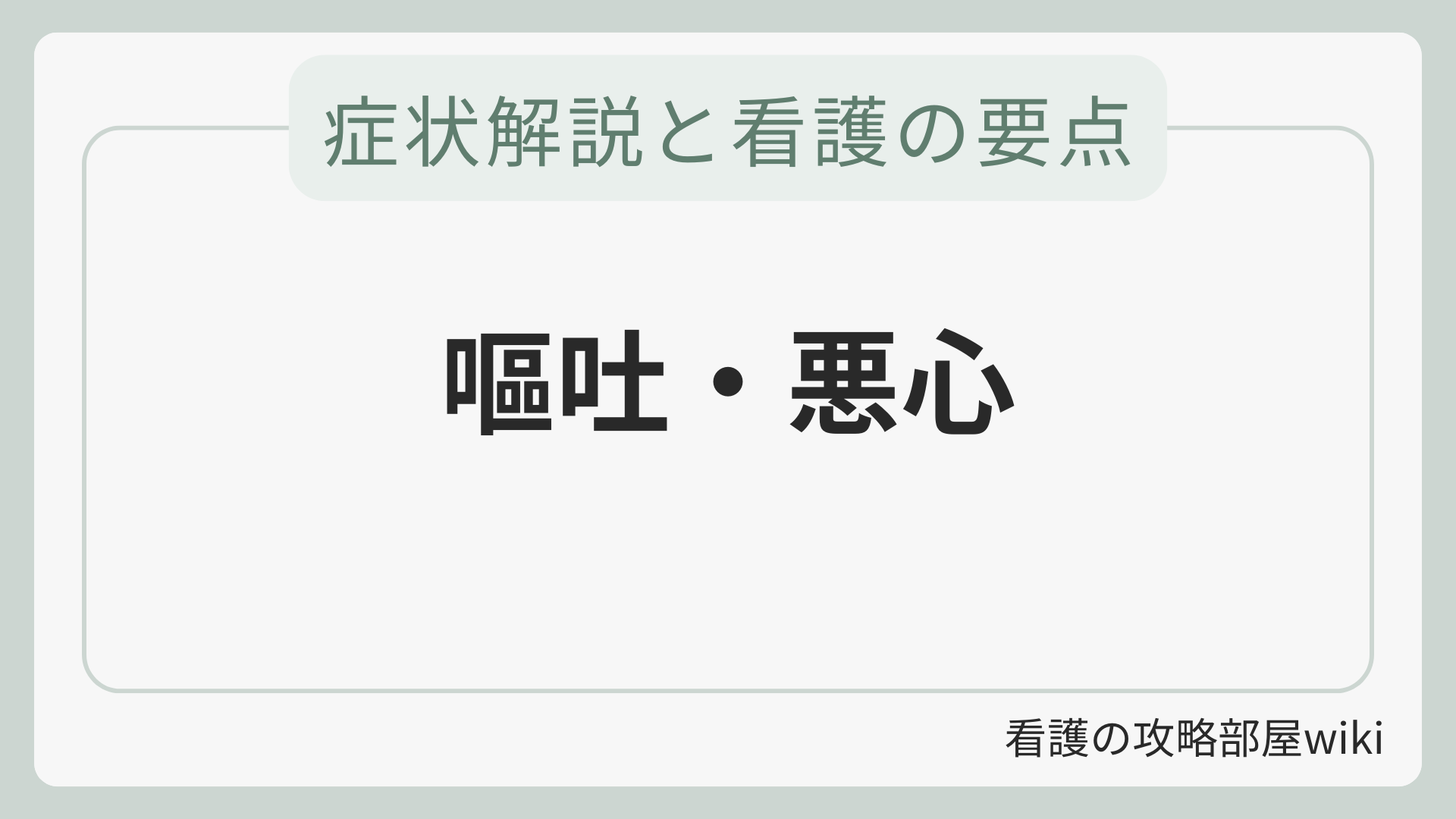
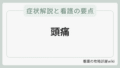
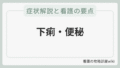
コメント