本記事では、看護師の思考プロセスを詳しく解説します。
実際の臨床では患者さんごとに状況が異なりますが、「わたしならどう考えるか」を具体的に示すことで、あなた自身の考える力を育てることを目指します。
この記事を参考に思考プロセスを学び、看護過程が得意になってもらえたら嬉しいです。
それでは、見ていきましょう。
看護学習や実習に役立つブログも運営しています✨️
ぜひ参考にしてみてくださいね!
https://kango-kouryaku.com/
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。事例は完全なフィクションであり、個別の診断・治療の根拠ではありません。実際の看護実践は患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください。本記事をそのまま課題として提出しないでください。内容の完全性・正確性は保証できず、本記事の利用により生じた損害について一切の責任を負いません。
今回の情報
基本情報
A氏は55歳の女性で、身長158cm、体重52kg(入院前58kg)である。夫(60歳)との2人暮らしで、長男・長女は別居している。キーパーソンは夫である。温厚で協調性があり、几帳面な性格である。会社員として経理課の主任を務めており、現在は休職中である。感染症とアレルギーは特になく、認知力に問題はない。
病名
胃癌 stageⅡA(T2N1M0)に対して、7月8日に胃全摘術及びルーY法を施行した。
既往歴と治療状況
高血圧は5年前から認められ、アムロジピン5mgを朝食後に内服中である。脂質異常症は3年前から認められ、アトルバスタチン10mgを夕食後に内服中である。入院を機に喫煙(20本/日×45年)は禁煙となり、飲酒(ビール350ml/日)は中止している。
入院から現在までの情報
X年5月の職場健診で上部消化管造影検査により胃体中部に陰影欠損を指摘された。その後、上部消化管内視鏡検査を実施した結果、胃体中部後壁に2.5cm大の2型進行胃癌を認め、生検の結果は中分化型管状腺癌と診断された。術前検査(CT、MRI)では遠隔転移や重要臓器への浸潤は認めず、cStageⅡA(T2N1M0)と診断された。手術適応と判断され、X年7月1日に当院外科を紹介受診し、7月6日に入院した。入院前は食欲低下や体重減少などの自覚症状はなかったが、後から振り返ると軽度の心窩部不快感を自覚していたとのことである。
7月8日に全身麻酔下にて開腹術による胃全摘術及びルーY法を施行した。術後1日目は全身状態が安定し、絶食継続のもと点滴管理を行い、創部痛に対して鎮痛薬を使用した。離床指導を開始し、ベッドサイドでの座位を促した。術後2日目から病棟内歩行訓練を開始し、腹部症状は認めず疼痛コントロールは良好であった。術後3日目に胃管を抜去し、腸蠕動音は確認できたが排ガスはなかった。術後4日目に排ガスを認め、腹部膨満は認めず創部の炎症徴候もなかった。術後5日目から氷片摂取を開始し、摂取後も腹部症状なく経過は良好で、腸蠕動音の回復を確認した。センノシド(下剤)の処方を開始した。術後6日目に軟便の排便があり、創部ガーゼ交換を実施してドレーンを抜去した。術後7日目(現在:7月15日)から流動食(1食150ml)を開始し、摂取状況は良好で嘔気・腹部症状はなく、歩行はふらつきなく自立している。
点滴内容は、術後1日目はソルアセトF 1000ml/日と抗生剤CEZ 1g×2回/日を投与した。術後2~7日目はソルアセトF 1000ml/日を継続し、術後8日目より食事開始に備えて500ml/日に減量し、現在も継続中である。食事量の増加に応じて漸減・終了予定である。
バイタルサイン
入院時と比較して、体温は36.8℃から36.5℃へ低下し、脈拍は76回/分(整)から82回/分(整)へ上昇、血圧は138/82mmHgから126/78mmHgへ低下している。呼吸数は16回/分から18回/分へ若干上昇し、SpO2は98%から97%へ低下しているが、いずれも許容範囲内である。
食事と嚥下状態
入院前は普通食を1食約8割摂取していたが、現在は流動食を1食150mlで開始したばかりである。いずれも1日3食で、自立摂取が可能である。嚥下機能に問題はなく、嘔気・腹部症状はない。術後5日目から氷片を開始し、上体挙上30度以上の指導を受けている。患者は食事量の増加に不安があると表出している。喫煙は入院を機に禁煙し、飲酒(ビール350ml/日)は現在中止している。
排泄
入院前は排便回数1日1~2回で、性状は普通便であり自立していた。現在、術後5日目に初回排便があり、性状は軟便である。排泄は自立しており、腸蠕動音はやや低下している。下剤は術後6日目よりセンノシド2T眠前を使用している。
睡眠
入院前は午後11時~午前6時の睡眠時間で、睡眠の質は良好であった。現在は断続的睡眠であり、創部痛により中途覚醒がある。眠剤は頓用でゾルピデム10mg眠前を使用している。
視力・聴力・知覚・コミュニケーション・信仰
視力は矯正視力で両眼1.0(眼鏡使用)、聴力は正常、知覚に異常はない。コミュニケーション能力は良好であり、医療者の説明を理解し、質問も適切である。信仰は特にない。
動作状況
入院前は歩行・移乗・排泄・入浴・衣類の着脱はいずれも自立しており、転倒歴はなかった。現在、歩行は術後5日目より病棟内歩行を開始し、ふらつきなく自立している。移乗は自立しており、排泄はトイレまで歩行可能である。入浴はシャワー浴許可待ちであり、衣類の着脱は自立している。転倒歴はない。
内服中の薬
- アムロジピン5mg 1T 朝食後
- アトルバスタチン10mg 1T 夕食後
- センノシド2T 眠前
- ゾルピデム10mg 眠前(頓用)
内服薬は現在、看護師管理である。
検査データ
検査データ推移(入院時→術後7日目(現在))
Hb:13.2→11.8 g/dL 低下
Ht:39.2→35.4% 低下
WBC:6,800→8,200/μL 上昇
PLT:22.5→19.8万/μL 低下
TP:7.0→6.5 g/dL 低下
Alb:4.0→3.5 g/dL 低下
CRP:0.3→2.1 mg/dL 上昇
入院時と比較して、ヘモグロビン、ヘマトクリット、総蛋白、アルブミンの低下が認められ、これは手術による出血と栄養摂取量の低下を反映している。WBCの上昇とCRPの上昇は手術侵襲に対する炎症反応と考えられる。
今後の治療方針と医師の指示
今後の治療方針は、合併症予防と早期発見を最優先に経過観察を継続する。術後10日目に血液検査による全身評価を実施し、活動範囲の拡大とシャワー浴開始を検討する。食事は確実な経口摂取の確立を目指し、消化器症状に留意しながら段階的に量を増やしていく予定である。医師の指示として、安静度は現在病棟内歩行可能で、8日目以降は院内歩行、退院時は制限なしとする。食事は現在流動食150ml×3回で、10日目に三分粥、12日目に五分粥、退院時に全粥へと段階的に進める予定である。30分以上かけて摂取することを指示している。創部処置は1日1回のガーゼ交換を継続し、感染徴候時は報告するよう指示されている。疼痛管理はロキソプロフェン60mgを頓用で、状態により調整し、1日3回まで、4時間以上の間隔を空けることとされている。清潔ケアは現在清拭可能で、10日目以降シャワー浴を開始し、創部は濡らさないよう指示されている。バイタルサインは1日3回測定し、術後10日目に採血、退院前にCTを実施する予定である。
退院は術後14日目を予定しており、退院までに基本的ADLの自立を目標とする。退院1週間後の外来診察で術後補助化学療法の必要性を検討し、その後は定期的な画像・血液検査による経過観察と段階的な職場復帰計画を進めていく予定である。
本人と家族の想いと言動
患者は術後の回復に前向きで、早期の社会復帰への意欲が高く、「できるだけ早く仕事に戻りたい。部下たちに心配をかけているから」と話している。一方で、胃全摘後の食事に関して「どのくらい食べられるようになるのか」「体重は戻るのか」と不安を表出している。リハビリには積極的で、「一日でも早く元の生活に戻れるよう頑張りたい」と意欲的に取り組んでいる。
夫は妻の回復を最優先に考えており、非常に協力的な姿勢を示している。「妻の体調が一番大事。仕事のことは焦らなくていい」と本人をサポートする発言が多い。特に退院後の食事管理に関心が高く、「少量ずつ何回かに分けて食べさせた方がいいのか」「食材の選び方や調理法で気をつけることは」など、具体的な質問を積極的にしている。毎日の面会時には妻の様子を細かく観察し、看護師に質問するなど、情報収集に熱心である。
ゴードン11項目アセスメント解説
1. 健康知覚-健康管理パターンのポイント
このパターンでは、A氏が自分の健康状態や疾患、治療をどのように認識し、管理しようとしているかを評価します。胃癌という診断と胃全摘術という大きな治療を受けた患者が、自身の状態をどう理解し、今後の健康管理にどう向き合おうとしているかを捉えることが重要です。
どんなことを書けばよいか
健康知覚-健康管理パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 疾患についての本人・家族の理解度(病態、治療、予後など)
- 疾患や治療に対する受け止め方、受容の程度
- 現在の健康状態や症状の認識
- これまでの健康管理行動(受診行動、服薬管理、生活習慣など)
- 疾患が日常生活に与えている影響の認識
- 健康リスク因子(喫煙、飲酒、アレルギー、既往歴など)
疾患発見の経緯と健康管理行動
A氏は職場健診で胃癌が発見されており、これは定期的な健康診断を受けていたことを示しています。会社員として経理課の主任を務める几帳面な性格が、健康管理行動にも反映されていた可能性があります。入院前は明確な自覚症状がなかったものの、後から振り返ると軽度の心窩部不快感があったと述べている点を踏まえて、症状に対する気づきと報告のタイミングについて考慮するとよいでしょう。
既往歴と服薬管理の状況
高血圧5年、脂質異常症3年という既往歴があり、それぞれアムロジピン、アトルバスタチンを継続内服していることから、慢性疾患の管理を継続できていたことがわかります。現在は看護師管理となっていますが、入院前は自己管理していたと考えられ、服薬アドヒアランスの評価や退院後の自己管理能力を考える上で重要な情報となります。
生活習慣とリスク因子
喫煙20本/日×45年、飲酒ビール350ml/日という長期の生活習慣があり、入院を機に禁煙・禁酒となっています。これらは胃癌のリスク因子であると同時に、術後の創傷治癒や合併症予防の観点からも重要です。入院を契機に生活習慣を変更できたことは、健康管理への意識が高まっている可能性を示しており、退院後の生活習慣改善への動機づけを考える際の強みとなります。
疾患と治療に対する認識と受容
A氏は「できるだけ早く仕事に戻りたい。部下たちに心配をかけているから」と話しており、社会復帰への強い意欲が認められます。一方で「どのくらい食べられるようになるのか」「体重は戻るのか」と食事に関する不安を表出しています。これは胃全摘という治療の影響を理解しつつも、今後の生活への具体的なイメージが持てていない状態を示しており、疾患や治療の受容過程を支援する必要性を考慮するとよいでしょう。
家族の理解と協力体制
夫は「妻の体調が一番大事。仕事のことは焦らなくていい」と述べ、退院後の食事管理について具体的な質問を積極的にしています。これは家族の疾患理解と協力的な姿勢を示しており、退院後の健康管理において重要なサポート資源となることがわかります。毎日の面会時に細かく観察し質問する行動は、家族の情報収集能力と学習意欲の高さを示しています。
アセスメントの視点
A氏は几帳面な性格と職場健診の受診歴から、基本的な健康管理能力を持っていると考えられます。胃全摘術という大きな治療を受け、今後の生活に不安を抱えながらも、早期社会復帰への意欲を示しています。長期の喫煙・飲酒歴という健康リスク因子を持っていましたが、入院を機に中止できており、生活習慣改善への動機づけのタイミングと捉えることができます。家族の協力的な姿勢と学習意欲の高さは、退院後の健康管理における大きな強みとなるでしょう。
ケアの方向性
胃全摘後の生活変化について、具体的で実践可能な情報提供を行い、A氏と家族の不安を軽減することが重要です。これまでの健康管理能力と几帳面な性格を活かし、段階的な食事管理や服薬管理の方法を一緒に考えていくことが効果的でしょう。早期社会復帰への意欲を尊重しつつ、無理のないペースでの回復を支援し、家族の協力体制を活用した退院後の生活設計を共に検討していくことが求められます。
2. 栄養-代謝パターンのポイント
このパターンでは、胃全摘術後のA氏の栄養状態と今後の栄養管理の方向性を評価します。手術により胃が失われたことで、栄養摂取方法が大きく変化しており、現在の状態から段階的に経口摂取を確立していく過程を支援する必要があります。
どんなことを書けばよいか
栄養-代謝パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 食事と水分の摂取量と摂取方法
- 食欲、嗜好、食事に関するアレルギー
- 身長・体重・BMI・必要栄養量・身体活動レベル
- 嚥下機能・口腔内の状態
- 嘔吐・吐気の有無
- 皮膚の状態、褥瘡の有無
- 栄養状態を示す血液データ(Alb、TP、RBC、Ht、Hb、Na、K、TG、TC、HbA1c、BSなど)
術前術後の体重変化と栄養状態
A氏の身長は158cm、体重は入院前58kgから現在52kgへと6kg減少しています。BMIは入院前23.2から現在20.8へ低下しており、標準範囲内ではあるものの短期間での体重減少が認められます。血液データではTP7.0→6.5g/dL、Alb4.0→3.5g/dL、Hb13.2→11.8g/dLと低下しており、手術侵襲と栄養摂取量の低下を反映しています。これらの変化を踏まえて、現在の栄養状態と今後の必要栄養量を考慮するとよいでしょう。
経口摂取の再開と段階的な食事の進め方
術後7日目から流動食150ml×3回が開始され、摂取状況は良好で嘔気・腹部症状は認められていません。術後5日目から氷片摂取を開始し、上体挙上30度以上の指導を受けている点は、誤嚥予防と消化管機能の回復を考慮した適切な管理がなされていることを示しています。医師の指示では、10日目に三分粥、12日目に五分粥、退院時に全粥へと段階的に進める予定であり、30分以上かけて摂取することが指示されています。この段階的な食事の進め方と、ゆっくりとした摂取の必要性について、その理由を含めて理解を促すことが重要です。
水分管理と点滴補液の状況
術後8日目より点滴はソルアセトF500ml/日に減量され、食事量の増加に応じて漸減・終了予定となっています。現在の経口摂取量は流動食450ml/日と少量であり、点滴による水分・電解質補給が継続されています。腸蠕動音はやや低下しているものの、排ガス・排便が確認されており、消化管機能は回復傾向にあることがわかります。水分・電解質バランスと消化管機能の回復状況を併せて評価するとよいでしょう。
胃全摘後の食事に対する不安
A氏は「どのくらい食べられるようになるのか」「体重は戻るのか」と食事量や体重への不安を表出しています。胃全摘により一度に摂取できる食事量が制限されること、栄養吸収の変化があることを理解しつつも、具体的な見通しが持てていない状態と考えられます。夫も「少量ずつ何回かに分けて食べさせた方がいいのか」「食材の選び方や調理法で気をつけることは」と具体的な質問をしており、退院後の食事管理への関心の高さが窺えます。
創傷治癒と皮膚の状態
術後7日目で創部ガーゼ交換が継続されており、感染徴候は認められていません。Hb、Alb、TPの低下は創傷治癒に影響を与える可能性があり、栄養状態の改善が創部の治癒促進につながることを意識して記述するとよいでしょう。また、体重減少と活動量の低下により、褥瘡のリスクも考慮する必要があります。
アセスメントの視点
A氏は胃全摘術により栄養摂取方法が大きく変化し、現在は流動食から段階的に食事を進めている段階です。摂取状況は良好で消化器症状もなく、消化管機能は順調に回復していると評価できます。一方で、体重減少と血液データの低下から栄養状態の改善が必要であり、今後の経口摂取の確立が重要な課題となります。A氏と家族は食事管理に関する不安と関心を持っており、具体的で実践可能な情報を求めている状態です。
ケアの方向性
段階的な食事の進め方について、消化管機能の回復状況を観察しながら慎重に進めていくことが必要です。胃全摘後の食事の特徴(少量頻回食、ゆっくりとした摂取、ダンピング症候群の予防など)について、A氏と家族が理解し実践できるよう、具体的な指導を行うことが重要です。体重減少への不安に対しては、長期的な視点での体重管理の見通しを示し、栄養状態の改善に向けた支援を継続していくことが求められます。
続きはnoteで公開中です✨️
ゴードンの続きとヘンダーソン・関連図・看護計画について解説しています😊
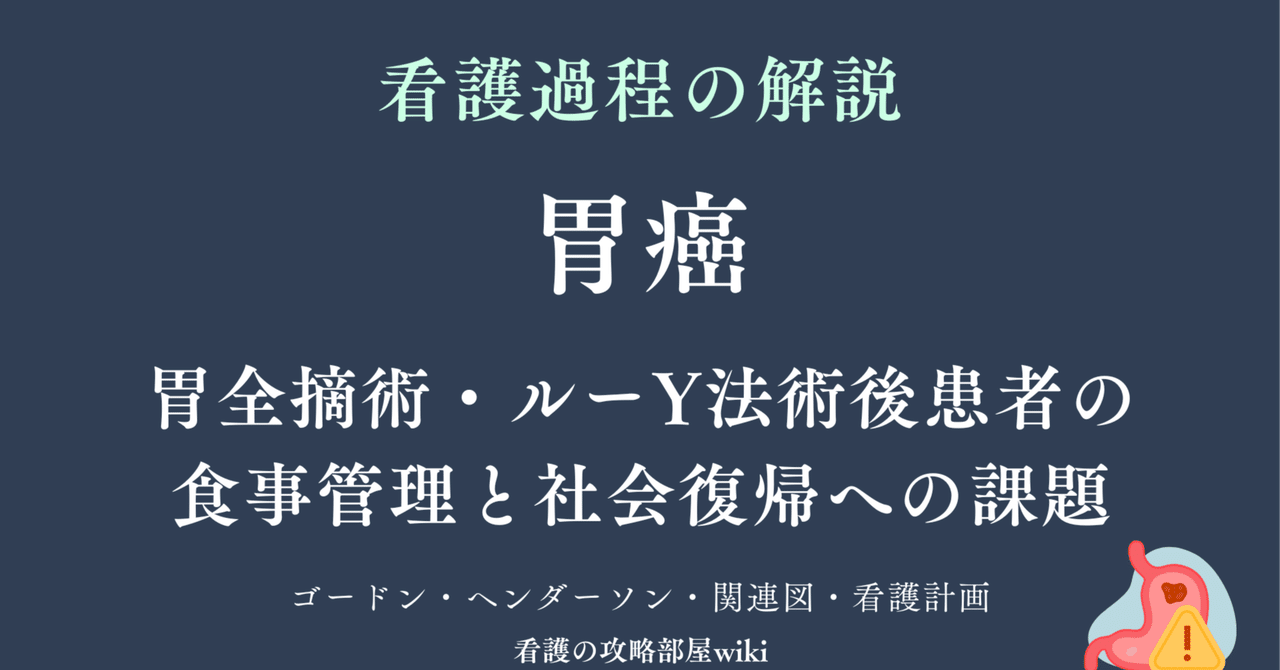
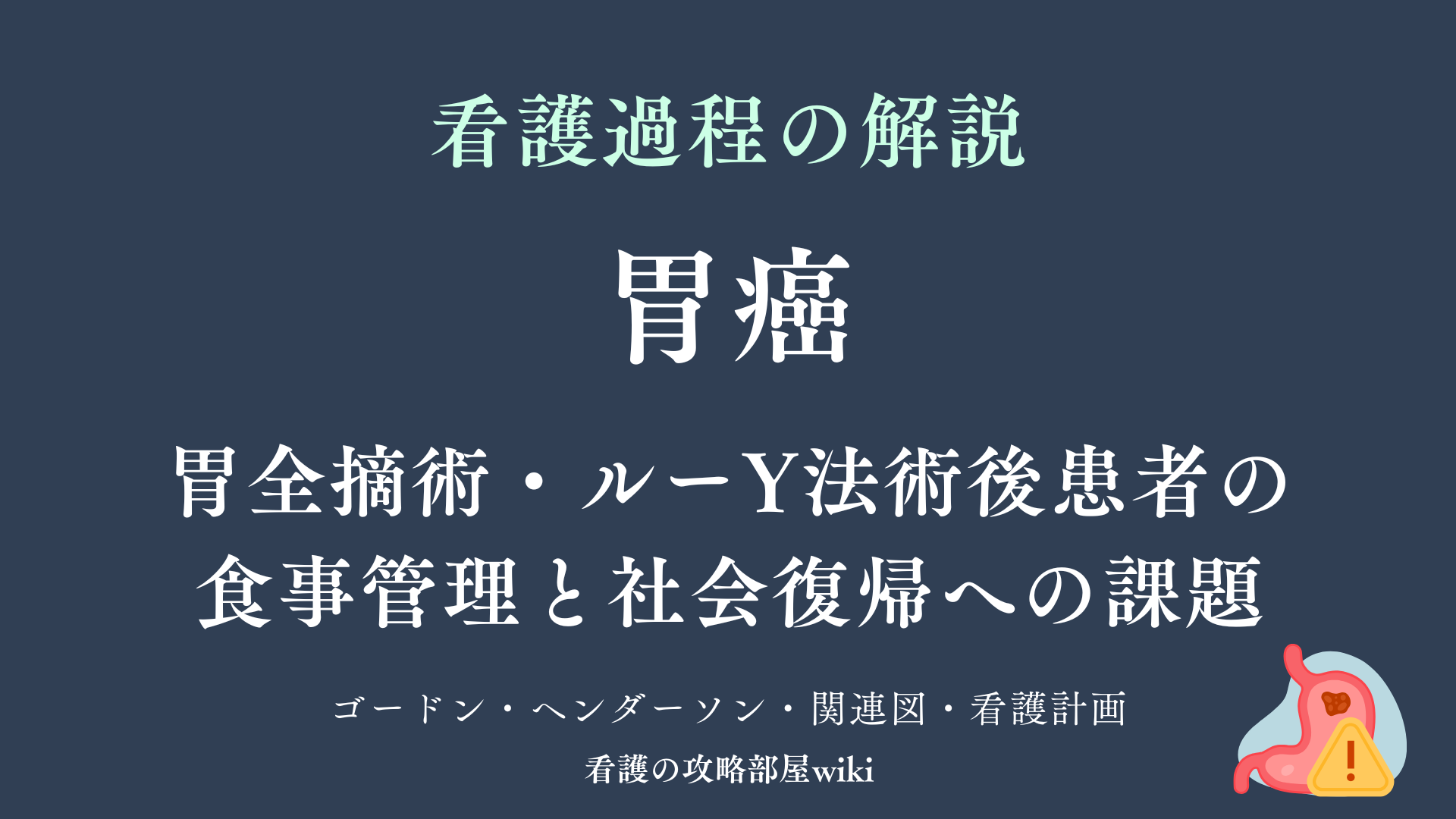

コメント