本記事では、看護師の思考プロセスを詳しく解説します。
実際の臨床では患者さんごとに状況が異なりますが、「わたしならどう考えるか」を具体的に示すことで、あなた自身の考える力を育てることを目指します。
この記事を参考に思考プロセスを学び、看護過程が得意になってもらえたら嬉しいです。
それでは、見ていきましょう。
看護学習や実習に役立つブログも運営しています✨️
ぜひ参考にしてみてくださいね!
https://kango-kouryaku.com/
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。事例は完全なフィクションであり、個別の診断・治療の根拠ではありません。実際の看護実践は患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください。本記事をそのまま課題として提出しないでください。内容の完全性・正確性は保証できず、本記事の利用により生じた損害について一切の責任を負いません。
今回の情報
基本情報
A氏、45歳、男性。身長175cm、体重90kg(BMI 29.4)である。IT企業の中間管理職として勤務しており、デスクワークが中心の仕事に従事している。既婚で妻(42歳)と高校生の長男(16歳)、中学生の長女(13歳)との4人暮らしで、キーパーソンは妻である。
性格は几帳面で仕事熱心である一方で、自身の健康管理については楽観的な傾向がある。多忙な業務を優先し、不規則な食生活や運動不足となっている。新型コロナウイルスのワクチン接種は3回完了しており、その他の感染症や特記すべきアレルギー歴はない。日常生活動作は自立しており、認知機能に問題はない。コミュニケーションは良好で、医療者の説明は十分に理解できている。
病名
- 2型糖尿病
- 肥満症
- 高血圧症
既往歴と治療状況
急性虫垂炎を15歳時に発症し、虫垂切除術を施行している。高血圧症については20XX年12月より内服加療中で、アムロジピン5mgを1日1回朝食後に服用している。また、42歳時に腰椎椎間板ヘルニアを発症したが、現在は症状なく保存的治療により軽快している。
入院から現在までの情報
20XX年12月の定期健康診断で空腹時血糖235mg/dL、HbA1c 9.8%と高値を指摘され、精密検査目的で近医を受診した。2型糖尿病と診断され、食事療法と運動療法の指導を受けるも、仕事の多忙を理由に生活習慣の改善が進まなかった。その後、外来でメトホルミン500mgの内服を開始したが、確実な服薬ができておらず、3ヶ月後の外来受診時にHbA1c 10.2%とさらなる上昇を認めた。主治医より糖尿病教育入院を勧められ、仕事の調整がついた時期に合わせて入院となった。
入院後は糖尿病教育プログラムに則り、1日目から食事療法(1600kcal/日)を開始した。2日目より、血糖測定の手技指導と運動療法の導入を開始している。血糖値は入院時280mg/dLであったが、食事療法開始後は緩やかな改善傾向にある。運動療法については、腰椎椎間板ヘルニアの既往があることから、理学療法士による評価のもと、個別のプログラムを作成中である。
バイタルサイン
来院時の体温は36.8℃、脈拍84回/分・整、血圧148/92mmHg、呼吸数16回/分、SpO2 98%(室内気)であった。
現在(入院3日目)の体温は36.6℃、脈拍78回/分・整、血圧138/88mmHg、呼吸数16回/分、SpO2 98%(室内気)である。規則的な生活リズムと食事療法の開始により、血圧値は緩やかに改善傾向にある。
食事と嚥下状態
入院前は朝食を時間がないことを理由に欠食が多く、昼食は外食やコンビニ弁当が中心であった。夜は仕事の付き合いによる外食が週3-4回あり、それ以外の日は帰宅が遅く、妻が用意した夕食を一人で食べることが多かった。食事の量や時間は不規則で、特に夜間の過食傾向があった。また、仕事中のコーヒーには砂糖を多めに入れ、午後は菓子類を頻繁に摂取していた。嚥下機能に問題はない。
現在は入院後、病院食(糖尿病食1600kcal、塩分6g/日)を提供されている。規則的な時間での食事摂取ができており、食事量は8-10割程度である。現在の食事に対しては「思ったより食べられる量がある」と話している。嚥下機能は良好で、食事摂取に問題はない。
喫煙歴なし。飲酒は機会飲酒で、仕事の付き合いによる飲酒が週3-4回(ビール500ml 1-2本程度/回)である。甘い物を好み、特にチョコレートやケーキなどの洋菓子をよく摂取していた。コーヒーは1日4-5杯摂取し、砂糖を2個ずつ入れる習慣があった。
排泄
入院前の排尿は日中5-6回、夜間1-2回であった。頻尿の自覚はあるが、医療機関は未受診である。排便は1日1回、普通便であった。不規則な食生活の影響で、時々便秘(2-3日排便なし)があった。下剤の使用経験はない。
現在の排尿は日中6-7回、夜間1回で、混濁や排尿時痛なしである。排便は規則的な食事と水分摂取により、毎朝1回の排便がある。便性状は普通便で、下剤は使用していない。トイレまでの移動や排泄動作は自立している。
睡眠
入院前は平日、仕事の都合で23時以降の就寝が多く、睡眠時間は5-6時間程度であった。休日は疲労回復のため、午前中まで睡眠を取ることが多かった。入眠障害や中途覚醒の訴えはなく、睡眠薬の使用歴はない。
現在は病棟の消灯時間(21時)に合わせて就寝し、6時の起床まで良眠できている。日中の活動性が上がり、夜間の良好な睡眠が取れていると本人も実感している。睡眠薬は使用していない。
視力・聴力・知覚・コミュニケーション・信仰
視覚機能については軽度の近視(-2.0D)があり終日メガネを使用しているが、白内障や糖尿病性網膜症の所見は認められていない。聴覚機能は正常で、会話に支障なく補聴器の使用も必要としていない。知覚については、四肢末梢の痺れや冷感の訴えはなく、足底の触覚・痛覚も正常に保たれている。
コミュニケーション面では、言語理解・表出ともに良好である。医療者との意思疎通は円滑で、自身の質問や要望も適切に表現できている。職場においても良好なコミュニケーションが保てているとのことである。信仰は特にない。
動作状況
日常生活動作は全般的に自立しており、介助を必要とする項目はない。歩行は安定しており、院内の移動もスムーズに行えている。階段の昇降も問題なく可能である。過去に転倒したエピソードはなく、現在も転倒リスクは低い。ただし、腰椎椎間板ヘルニアの既往があるため、長時間の歩行や急な動作時に軽度の腰部違和感を自覚することがある。
病室とトイレ、浴室間の移動や移乗動作は安定している。排泄動作は自立しており、トイレでの下衣の着脱もスムーズである。入浴は一般浴槽を使用し、洗体や洗髪も含めて自力で行えている。更衣に関しても、病衣や私服の着脱を問題なく行うことができる。靴下の着脱時にも、腰部への負担は少ない姿勢で実施できている。
肥満があるものの、これによるADLへの明らかな支障は認められていない。ただし、運動療法を開始するにあたり、腰部への負担を考慮した適切な運動方法の指導が必要な状態である。
内服中の薬
【内服薬】
- メトホルミン錠(500mg):1回1錠 1日2回 朝・夕食後
- アムロジピン錠(5mg):1回1錠 1日1回 朝食後
【持参薬】
- ロキソプロフェン錠(60mg):腰部痛時 頓用(腰椎椎間板ヘルニアによる腰痛時)、入院前は月に2-3回程度使用
【服薬状況】
入院前は仕事の忙しさを理由に、特にメトホルミンの服薬を忘れることが多かった。アムロジピンは比較的規則的に服用できていた。入院後は全ての内服薬について自己管理が許可されており、服薬カレンダーを使用して管理している。現在は看護師の声かけのもと、確実に内服できている。看護師は毎日の内服確認と週1回の残薬確認を実施している。糖尿病教育プログラムの中で、服薬の重要性についても学習中である。入院後はロキソプロフェンの使用はない。
検査データ
| 検査項目 | 基準値 | 入院時 | 現在(3日目) |
|---|---|---|---|
| 空腹時血糖 | 70-109 mg/dL | 280 | 198 |
| HbA1c | 4.6-6.2 % | 10.2 | 10.2 |
| 総コレステロール | 130-219 mg/dL | 242 | 238 |
| 中性脂肪 | 30-149 mg/dL | 195 | 182 |
| HDL-C | 40-90 mg/dL | 38 | 39 |
| LDL-C | 70-139 mg/dL | 165 | 162 |
| AST | 10-40 U/L | 38 | 35 |
| ALT | 5-45 U/L | 42 | 40 |
| γ-GTP | 12-87 U/L | 86 | 82 |
| BUN | 8-20 mg/dL | 18 | 17 |
| Cr | 0.60-1.10 mg/dL | 0.82 | 0.80 |
| eGFR | ≧60 mL/min/1.73m² | 75.4 | 76.2 |
尿検査
| 検査項目 | 基準値 | 入院時 | 現在(3日目) |
|---|---|---|---|
| 尿糖 | (-) | (3+) | (2+) |
| 尿蛋白 | (-) | (±) | (±) |
| 尿ケトン体 | (-) | (-) | (-) |
血圧
| 検査項目 | 基準値 | 入院時 | 現在(3日目) |
|---|---|---|---|
| 収縮期血圧 | ≦139 mmHg | 148 | 138 |
| 拡張期血圧 | ≦89 mmHg | 92 | 88 |
身体計測
| 項目 | 基準値 | 入院時 | 現在(3日目) |
|---|---|---|---|
| 体重 | – | 90.0 kg | 89.2 kg |
| BMI | 18.5-24.9 | 29.4 | 29.1 |
| 腹囲 | ≦85 cm | 98 cm | 97 cm |
今後の治療方針と医師の指示
現在の治療方針は、2週間の教育入院プログラムを通じて、適切な血糖コントロールと生活習慣の改善を図ることである。具体的には、食事療法(1600kcal/日)の継続と、運動療法の段階的な導入を行う。運動療法については、腰椎椎間板ヘルニアの既往を考慮し、理学療法士による個別プログラムを作成中である。
薬物療法に関しては、現在のメトホルミン500mg 1日2回の内服を継続し、血糖値の推移を見ながら用量調整を検討する。また、高血圧に対するアムロジピンの内服も継続する。血糖値が200mg/dL以上の場合は、速やかに主治医に報告する指示が出ている。
教育プログラムは第1週目に糖尿病の基礎知識、運動療法評価と指導、服薬指導、栄養指導を実施し、第2週目にフットケア指導、生活習慣の振り返り、外出訓練、最終評価と退院準備を行う予定である。毎日の内服確認と食事・運動記録を実施し、水曜日には糖尿病教室(集団指導)を行う。
退院後は2週間毎の外来通院とし、3ヶ月後に眼科受診を予定している。
本人と家族の想いと言動
本人は「仕事が忙しくて、食事の時間も不規則になってしまう。健康のために気をつけなければと思うが、仕事を優先してしまう」と話す。特に残業の多い日は、コンビニ弁当や菓子類で済ませることが多かったと振り返る。また、「このまま放っておくと重症化するのではないか」という不安を抱えているものの、具体的な生活改善の方法がわからず戸惑っている様子である。
妻は「主人の健康が心配。夕食は作っているのですが、帰りが遅くて冷めたものを食べることが多いんです」と話す。休日は家族で外食することが多く、食事内容や量の調整が難しい状況にある。「家族でできることは協力したい」という思いはあるが、具体的な支援方法についての知識が不足している。
長男(16歳)と長女(13歳)は父親の病気を心配しているが、学業が忙しく、平日は家族全員で食事をする機会が少ない状況である。
ゴードン11項目アセスメント解説
1. 健康知覚-健康管理パターンのポイント
このパターンでは、A氏が自身の健康状態をどのように認識し、どのような健康管理行動をとってきたか、そして今回の入院や治療をどう受け止めているかを評価します。特に生活習慣病の管理においては、本人の疾患理解と自己管理能力が治療の成否を左右するため、このパターンの丁寧なアセスメントが重要となります。
どんなことを書けばよいか
健康知覚-健康管理パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 疾患についての本人・家族の理解度(病態、治療、予後など)
- 疾患や治療に対する受け止め方、受容の程度
- 現在の健康状態や症状の認識
- これまでの健康管理行動(受診行動、服薬管理、生活習慣など)
- 疾患が日常生活に与えている影響の認識
- 健康リスク因子(喫煙、飲酒、アレルギー、既往歴など)
疾患の認識と受容の程度
A氏は健康診断で空腹時血糖235mg/dL、HbA1c 9.8%という著明な高値を指摘され、2型糖尿病と診断されています。「このまま放っておくと重症化するのではないか」という不安を抱えていることから、疾患の重大性については一定の認識があると考えられます。しかし、「仕事が忙しくて、食事の時間も不規則になってしまう。健康のために気をつけなければと思うが、仕事を優先してしまう」という発言からは、健康管理の必要性は理解しているものの、実際の行動変容には至っていない状況が読み取れます。この点を踏まえて、疾患の受容段階や行動変容のステージについてアセスメントするとよいでしょう。
これまでの健康管理行動
A氏の健康管理行動を振り返ると、いくつかの課題が明らかになります。まず、服薬管理について、メトホルミンの内服を「仕事の忙しさを理由に忘れることが多かった」という状況があり、3ヶ月後の外来でHbA1cが10.2%とさらに上昇しています。これは服薬アドヒアランスの低下が血糖コントロール不良に直結していることを示しており、入院前の自己管理能力に課題があったことを意味します。一方、高血圧に対するアムロジピンは「比較的規則的に服用できていた」ことから、服薬管理能力が全くないわけではないという点も押さえておくとよいでしょう。
定期健康診断を受診し、異常値を指摘された後に医療機関を受診している点は、受診行動としては適切です。しかし、外来で食事療法と運動療法の指導を受けたにもかかわらず、「仕事の多忙を理由に生活習慣の改善が進まなかった」という経過から、外来レベルでの自己管理が困難であったことが分かります。この点から、入院による集中的な教育と生活習慣の見直しの必要性が高かったという医療者側の判断の妥当性を考えるとよいでしょう。
健康リスク因子の存在
A氏には複数の健康リスク因子が存在します。肥満症(BMI 29.4)、高血圧症(20XX年12月より内服加療中)という既往歴があり、これらは2型糖尿病と相互に関連し、心血管疾患のリスクを高める要因となります。また、42歳時に腰椎椎間板ヘルニアを発症した既往があり、現在は症状なく軽快しているものの、運動療法を導入する際には配慮が必要な状態です。
飲酒については「機会飲酒で、仕事の付き合いによる飲酒が週3-4回(ビール500ml 1-2本程度/回)」という状況があり、頻度としては決して少なくありません。喫煙歴はないという点はリスク因子の一つが除外できる要素として捉えることができます。これらの情報を総合して、A氏の持つ健康リスクの全体像を把握することが重要です。
入院後の変化と学習意欲
入院後3日目の時点で、A氏は糖尿病教育プログラムに則り、規則的な生活リズムと食事療法を開始しています。血糖値は入院時280mg/dLから198mg/dLへと改善傾向を示しており、「思ったより食べられる量がある」という発言からは、食事療法に対する前向きな受け止めが感じられます。また、服薬カレンダーを使用した自己管理が許可されており、看護師の声かけのもとで確実に内服できている状況は、適切な支援があれば服薬管理が可能であることを示しています。
「具体的な生活改善の方法がわからず戸惑っている様子」という記載から、A氏は改善の意欲はあるものの、方法論が不足していると考えられます。この点を踏まえて、教育的介入の必要性と効果が期待できる状況にあることをアセスメントするとよいでしょう。
家族の健康管理への関与
妻は「主人の健康が心配」と話しており、「家族でできることは協力したい」という思いを持っています。しかし、「具体的な支援方法についての知識が不足している」という状況があります。キーパーソンである妻の協力意欲は高いものの、糖尿病の食事管理や生活習慣改善に関する知識や技術が不足していることから、家族を含めた教育的アプローチが必要な状態です。また、「休日は家族で外食することが多く、食事内容や量の調整が難しい状況」という発言からは、家族全体の生活パターンの見直しが必要であることも読み取れます。
アセスメントの視点
A氏の健康知覚-健康管理パターンをアセスメントする際は、疾患の重大性は認識しているが行動変容に至っていないという「認識と行動のギャップ」に着目することが重要です。仕事を優先してしまう価値観や多忙な業務環境が、健康管理行動の障壁となっている可能性を考慮する必要があります。また、入院後の良好な血糖コントロールは、適切な環境と支援があれば自己管理が可能であることを示唆しており、退院後の生活をどう設計するかが鍵となります。家族の協力意欲も強みとして捉え、本人と家族への教育的アプローチを統合的に考えることが求められます。
ケアの方向性
このパターンから導かれるケアの方向性としては、まず糖尿病の病態・治療・合併症についての正確な知識の提供が必要です。特に、血糖コントロール不良が引き起こす具体的なリスクを理解できるような教育が重要となります。また、仕事と健康管理を両立させるための具体的な方法論(時間管理、食事の工夫、服薬管理の仕組みづくりなど)を一緒に考え、実行可能な自己管理計画を立案することが求められます。家族、特にキーパーソンである妻への教育も同時に進め、退院後の生活における家族のサポート体制を構築する必要があります。入院中の良好な変化を本人にフィードバックし、自己効力感を高めながら、退院後も継続可能な健康管理行動の習慣化を支援することが重要です。
2. 栄養-代謝パターンのポイント
このパターンでは、A氏の食事摂取状況、栄養状態、代謝機能を評価します。2型糖尿病と肥満症を抱えるA氏にとって、栄養管理は治療の中核をなすものであり、入院前の食生活の問題点と入院後の変化を丁寧にアセスメントすることが重要です。
どんなことを書けばよいか
栄養-代謝パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 食事と水分の摂取量と摂取方法
- 食欲、嗜好、食事に関するアレルギー
- 身長・体重・BMI・必要栄養量・身体活動レベル
- 嚥下機能・口腔内の状態
- 嘔吐・吐気の有無
- 皮膚の状態、褥瘡の有無
- 栄養状態を示す血液データ(Alb、TP、RBC、Ht、Hb、Na、K、TG、TC、HbA1c、BSなど)
入院前の食生活パターンと問題点
A氏の入院前の食生活には、いくつかの重大な問題が存在します。朝食は「時間がないことを理由に欠食が多く」、昼食は「外食やコンビニ弁当が中心」、夜は「仕事の付き合いによる外食が週3-4回」という状況です。外食以外の日も「帰宅が遅く、妻が用意した夕食を一人で食べることが多かった」ことから、家族と共に食事をする機会が限られています。この点を踏まえて、食事の質だけでなく、食事を取り巻く環境や時間的な問題についても考慮するとよいでしょう。
特に注目すべきは「食事の量や時間は不規則で、特に夜間の過食傾向があった」という点です。朝食欠食により日中のエネルギー不足が生じ、夜間に過剰摂取するという悪循環が形成されていたと考えられます。また、「仕事中のコーヒーには砂糖を多めに入れ、午後は菓子類を頻繁に摂取していた」という習慣も、血糖値の変動を大きくし、HbA1cの上昇に寄与していた要因として捉えることができます。コーヒーを1日4-5杯、砂糖を2個ずつ入れる習慣があったことから、単純計算でも砂糖による摂取カロリーが相当量に上ることが分かります。
身体計測値と代謝状態
A氏の身長175cm、体重90kg、BMI 29.4は肥満(BMI≧25)に該当します。腹囲98cmは内臓脂肪型肥満の基準(男性≧85cm)を大きく超えており、メタボリックシンドロームの診断基準の一つを満たしています。デスクワークが中心の仕事であることから、身体活動レベルは低く、消費エネルギーに対して摂取エネルギーが過剰な状態が長期間続いていたことが推測されます。現在の食事療法として1600kcal/日が設定されていることから、この値を基に必要栄養量との関係を考えるとよいでしょう。
入院3日目の時点で体重は90.0kgから89.2kgへと0.8kg減少しており、腹囲も98cmから97cmへと1cm減少しています。これは適切な食事療法の効果が早期に現れていることを示しており、今後の継続的な体重管理の重要性を本人に伝える良い機会となります。
血液データからみる代謝異常
血糖関連のデータとして、空腹時血糖は入院時280mg/dLから現在198mg/dLへと改善傾向にありますが、依然として著明な高値です。HbA1c 10.2%は過去2-3ヶ月の平均的な血糖コントロール状態を反映しており、長期にわたる高血糖状態が続いていたことを示しています。尿糖も入院時(3+)から現在(2+)へと改善傾向にありますが、まだ陽性であることから、血糖値が腎臓の再吸収閾値を超えている状態です。
脂質代謝についても、総コレステロール242mg/dL(基準130-219)、中性脂肪195mg/dL(基準30-149)、LDL-C 165mg/dL(基準70-139)といずれも高値を示しており、HDL-C 38mg/dL(基準40-90)は低値です。これらは動脈硬化を促進する因子であり、すでに高血圧症を合併していることを考えると、心血管疾患のリスクが高い状態にあることをアセスメントする必要があります。
肝機能については、AST 38U/L、ALT 42U/L、γ-GTP 86U/Lといずれも基準値内ないし軽度上昇程度であり、現時点では脂肪肝などの明らかな肝障害は認められていません。しかし、肥満と糖尿病があることから、今後の経過観察が必要な項目として捉えるとよいでしょう。
入院後の食事摂取状況
入院後、A氏は病院食(糖尿病食1600kcal、塩分6g/日)を提供されており、規則的な時間での食事摂取ができています。食事量は8-10割程度と良好で、「思ったより食べられる量がある」という発言からは、糖尿病食に対する抵抗感が少なく、むしろ量的な満足感を得られていることが分かります。この前向きな反応は、今後の食事療法継続への意欲につながる可能性があり、教育的介入の好機として捉えることができます。
嚥下機能は良好で、食事摂取に問題はなく、嘔吐や吐気の訴えもありません。口腔内の状態についても特記すべき問題は記載されていませんが、糖尿病患者では歯周病のリスクが高いことから、口腔ケアの重要性についても意識を向けるとよいでしょう。
食嗜好と生活習慣
A氏は「甘い物を好み、特にチョコレートやケーキなどの洋菓子をよく摂取していた」という嗜好があります。洋菓子は糖質だけでなく脂質も多く含むため、血糖値の上昇と体重増加の両方に影響を与えます。この嗜好を完全に禁止するのではなく、適切な量と頻度、代替品の活用などについて、具体的な指導が必要な点として考えるとよいでしょう。
また、機会飲酒が週3-4回あり、ビール500ml 1-2本程度/回ということは、アルコールからの摂取カロリーも相当量になります。ビール500mlは約200kcalであり、週3-4回で1-2本となると、週に1200-1600kcal程度のアルコール由来のエネルギー摂取があったことになります。さらに、飲酒時には食事量も増える傾向があることを考慮すると、アルコール摂取が体重増加と血糖コントロール不良に寄与していた可能性が高いことをアセスメントする必要があります。
アセスメントの視点
A氏の栄養-代謝パターンをアセスメントする際は、仕事中心の生活様式が不規則な食生活を生み出し、それが肥満と糖尿病の発症・悪化につながっているという構造を理解することが重要です。朝食欠食、外食中心、夜間過食、間食習慣という複数の問題が絡み合っており、どの問題から優先的に取り組むべきかを本人と一緒に考える必要があります。入院後わずか3日間で血糖値と体重に改善が見られることは、適切な栄養管理の即効性を示しており、本人の自己効力感を高める材料として活用できます。一方で、退院後に職場環境に戻った際、どのように食生活を維持するかが最大の課題となることを見据えたアセスメントが求められます。
ケアの方向性
このパターンから導かれるケアの方向性としては、まず糖尿病食1600kcalの食事内容を具体的に学習し、退院後も実践可能な食事プランを作成することが必要です。特に、朝食を確実に摂取する習慣づけ、昼食の外食やコンビニ利用時の選択方法、間食の適切な取り方、アルコール摂取のコントロールなど、A氏の生活スタイルに即した具体的な方法を一緒に考えることが重要です。栄養士による個別指導を活用し、カロリー計算だけでなく、実際の食品選択や調理方法についても学べるようにすることが求められます。また、妻への栄養指導も並行して行い、家庭での食事環境を整えることも必要です。入院中の良好な変化を数値で示しながら、適切な栄養管理が血糖コントロールに直結することを実感してもらい、退院後の継続的な実践を支援することが重要です。
続きはnoteで公開中です✨️
ゴードンの続きとヘンダーソン・関連図・看護計画について解説しています😊
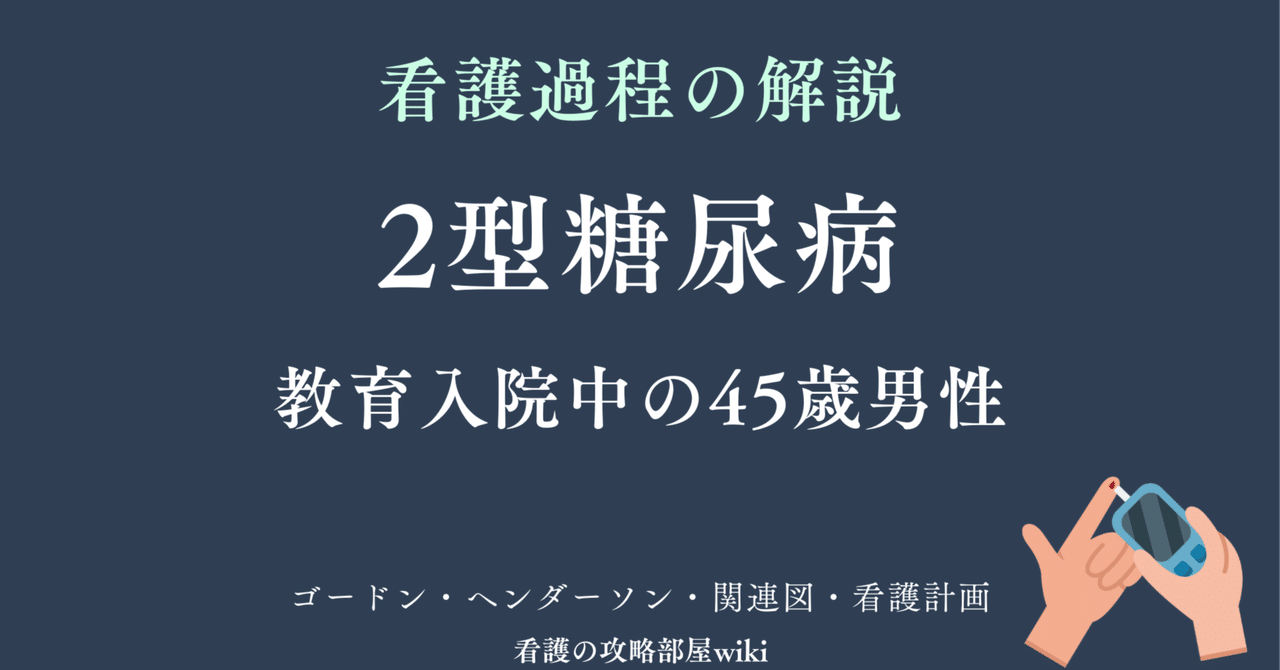
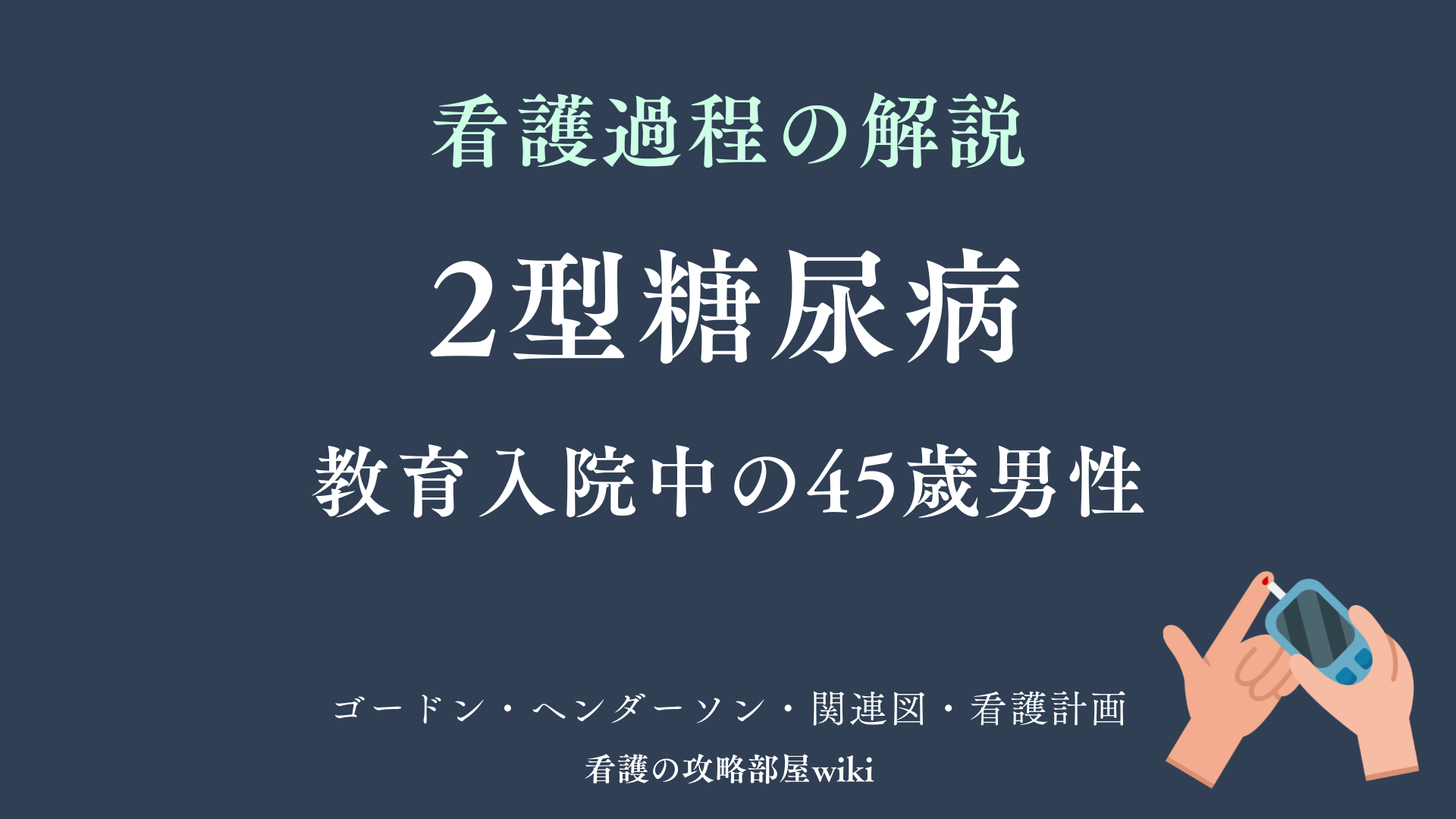


コメント