本記事では、看護師の思考プロセスを詳しく解説します。
実際の臨床では患者さんごとに状況が異なりますが、「わたしならどう考えるか」を具体的に示すことで、あなた自身の考える力を育てることを目指します。
この記事を参考に思考プロセスを学び、看護過程が得意になってもらえたら嬉しいです。
それでは、見ていきましょう。
看護学習や実習に役立つブログも運営しています✨️
ぜひ参考にしてみてくださいね!
https://kango-kouryaku.com/
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。事例は完全なフィクションであり、個別の診断・治療の根拠ではありません。実際の看護実践は患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください。本記事をそのまま課題として提出しないでください。内容の完全性・正確性は保証できず、本記事の利用により生じた損害について一切の責任を負いません。
基本情報
A氏は28歳の女性で、身長160cm、体重は妊娠前52kg、分娩時63kg、現在60kgである。夫(32歳)と二人暮らしで、キーパーソンは夫である。職業は小学校教諭で現在は産休中である。性格は几帳面で計画性があり、物事を事前に準備しておくことを好む。感染症はなく、アレルギーは猫アレルギーのみである。認知力に問題はない。
病名
正常経腟分娩後、産褥3日目
既往歴と治療状況
既往歴として23歳時に左卵巣嚢腫で腹腔鏡下左卵巣嚢腫摘出術を受けている。妊娠中は妊娠性貧血があり、鉄剤を服用していた。また、妊娠32週から妊娠高血圧症候群と診断され、安静と塩分制限が指示されていたが、投薬治療はなかった。
入院から現在までの情報
妊娠40週1日に陣痛発来し、自然破水後に入院した。入院後12時間の分娩経過で、3152gの女児を経腟分娩で出産した。分娩所要時間は初産婦としては比較的短く、会陰切開はあったが裂傷はなかった。出血量は350mlであった。新生児のApgarスコアは1分後8点、5分後9点と良好であった。産後は母子同室で、授乳は3時間ごとに行っている。授乳時に乳頭痛を訴え、正しい授乳方法に不安を抱えている。母乳分泌は開始しているが、児の体重は出生時より5%減少している。会陰部の痛みに対してはシッツバスと消炎鎮痛剤が処方されている。産後の子宮収縮は良好で、悪露も正常経過である。
バイタルサイン
来院時のバイタルサインは体温36.8℃、脈拍88回/分、血圧132/84mmHg、呼吸数20回/分であった。分娩時は一過性の血圧上昇(150/92mmHg)がみられたが、分娩後は安定した。現在のバイタルサインは体温36.6℃、脈拍76回/分、血圧118/74mmHg、呼吸数16回/分と安定している。
食事と嚥下状態
入院前は1日3食の規則正しい食事習慣で、妊娠中は栄養バランスを意識した食事を心がけていた。嚥下状態に問題はなく、喫煙歴はない。飲酒は妊娠判明後から完全に控えていた。現在は産褥食を提供されており、食欲は良好で1日3食+間食を摂取している。授乳のため水分摂取量を増やすよう意識しているが、十分な水分が取れているか不安を感じている。授乳中のため禁酒中である。
排泄
入院前は1日1回の排便習慣があり、便秘傾向はなかった。妊娠後期には時折便秘を自覚することがあったが、食物繊維の摂取で調整していた。現在は分娩後2日目に初回排便があったが、会陰切開部の痛みがあり排便時に恐怖心がある。排便は軟便で、量は少量であった。下剤の使用はないが、便秘予防のため食物繊維を多く含む食品を摂るよう指導されている。排尿は問題なく行えている。
睡眠
入院前は妊娠後期に頻尿と腰痛のため睡眠の質が低下していたが、日中の仮眠を取ることで対応していた。眠剤の使用歴はない。現在は新生児のケアと授乳のため睡眠が断続的となっている。夜間は3時間おきの授乳で起床し、日中も休息を十分に取れていない状態である。眠気を感じているが、児のケアへの不安から熟睡できていない。眠剤は使用していない。
視力・聴力・知覚・コミュニケーション・信仰
視力は両眼とも正常で、聴力も問題はない。知覚に異常はなく、コミュニケーションは良好である。特定の宗教的信仰はない。
動作状況
分娩後1日目から歩行を開始し、現在は病棟内を自力で歩行できている。移乗動作も問題なく行えている。排尿・排便は自力で行えているが、会陰切開部の痛みがあるため、座位での痛みを訴えている。シャワー浴は分娩後2日目から許可され、自力で行っているが、立位での疲労を訴えている。衣類の着脱は自立しているが、屈曲動作時に腹部の違和感を感じることがある。転倒歴はない。
内服中の薬
- 硫酸鉄(フェロ・グラデュメット錠) 105mg 1日1回 朝食後
- ロキソプロフェンナトリウム(ロキソニン錠) 60mg 1日3回 毎食後(頓服)
- センノシド(プルゼニド錠) 12mg 1日1回 就寝前(頓服)
- 酸化マグネシウム(マグミット錠) 330mg 1日3回 毎食後
服薬は自己管理で行っている。硫酸鉄は妊娠中から継続して服用しており、適切に管理できている。ロキソプロフェンナトリウムは会陰部痛に対して必要時に服用しており、1日1回程度の使用頻度である。センノシドは排便コントロール用に処方されているが、まだ使用していない。酸化マグネシウムは便秘予防のため処方されており、毎食後に服用している。
検査データ
検査データ
| 検査項目 | 基準値 | 入院時 | 最近 (産褥3日目) |
|---|---|---|---|
| 赤血球数 (RBC) | 386-492 × 10⁴/μL | 352 × 10⁴/μL | 368 × 10⁴/μL |
| ヘモグロビン (Hb) | 11.6-14.8 g/dL | 10.4 g/dL | 10.8 g/dL |
| ヘマトクリット (Ht) | 35.1-44.4% | 32.5% | 33.2% |
| 白血球数 (WBC) | 3300-8600 /μL | 12500 /μL | 8200 /μL |
| 血小板数 (PLT) | 15.8-34.8 × 10⁴/μL | 28.6 × 10⁴/μL | 26.8 × 10⁴/μL |
| 総蛋白 (TP) | 6.6-8.1 g/dL | 6.8 g/dL | 6.7 g/dL |
| アルブミン (ALB) | 4.1-5.1 g/dL | 3.9 g/dL | 3.8 g/dL |
| AST (GOT) | 13-30 U/L | 22 U/L | 20 U/L |
| ALT (GPT) | 7-23 U/L | 18 U/L | 16 U/L |
| 血糖値 | 73-109 mg/dL | 96 mg/dL | 88 mg/dL |
| CRP | 0-0.14 mg/dL | 0.32 mg/dL | 0.28 mg/dL |
| フェリチン | 5-157 ng/mL | 4.2 ng/mL | 4.5 ng/mL |
| 尿蛋白 | (-) | (+) | (-) |
今後の治療方針と医師の指示
産褥経過は順調であり、貧血の改善と母乳育児の確立を目標に治療方針が立てられている。産褥5日目での退院が予定されており、それまでに母乳育児の技術獲得と育児不安の軽減を図る。医師からは以下の指示が出されている。硫酸鉄の内服を継続し、授乳状況の確認と乳頭ケアの指導、会陰部の消毒継続、適度な休息を取ることが指示されている。また、産後2週間健診と1ヶ月健診の予約確認と、退院後の育児サポート体制の確認が必要とされている。退院後の生活指導として、無理のない範囲での活動と十分な水分・栄養摂取、異常症状(発熱、悪露増加・異臭、乳房の腫脹・発赤・疼痛)があれば速やかに受診するよう指導されている。
本人と家族の想いと言動
A氏は初めての出産と育児に対して不安と期待が入り混じった感情を抱えている。「母乳だけで赤ちゃんが十分育つのか心配」「乳頭が痛くて上手く授乳できているか分からない」と繰り返し発言している。また、退院後の生活について「仕事に早く復帰したいけれど、育児との両立ができるか不安」と話している。夫は仕事の都合で面会時間が限られているが、休日は終日付き添い、熱心に育児書を読んだり、看護師の指導を熱心に聞いたりしている。「妻の負担を少しでも減らせるように育児を手伝いたい」と意欲的な発言がある。また、A氏の母親が産後1週間ほど自宅に滞在して家事や育児の手伝いをする予定で、A氏は「母に助けてもらえるのは安心だけど、自分のやり方と違うかもしれないことが心配」と複雑な思いを抱えている。
ゴードン11項目アセスメントの解説
1. 健康知覚-健康管理パターンのポイント
このパターンでは、A氏が自身の産後の健康状態をどのように認識し、母子ともに健康的な生活を送るために必要な健康管理行動を実践できているかを評価します。初産婦として新しい役割に適応する過程で、自身の回復と育児の両立についてどのような認識を持っているかが重要な視点となります。
どんなことを書けばよいか
健康知覚-健康管理パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 疾患についての本人・家族の理解度(病態、治療、予後など)
- 疾患や治療に対する受け止め方、受容の程度
- 現在の健康状態や症状の認識
- これまでの健康管理行動(受診行動、服薬管理、生活習慣など)
- 疾患が日常生活に与えている影響の認識
- 健康リスク因子(喫煙、飲酒、アレルギー、既往歴など)
妊娠期から産褥期にかけての健康管理行動
A氏は妊娠中、栄養バランスを意識した食事を心がけ、妊娠判明後から飲酒を完全に控えるなど、母児の健康を守るための行動を主体的に実践してきました。喫煙歴がないことも、良好な健康管理意識を反映しています。また、妊娠32週から妊娠高血圧症候群と診断された際には、安静と塩分制限の指示を守っていたことが推測されます。これらの情報から、A氏はもともと健康管理に対する意識が高く、医療者の指示に従う力を持っていると考えることができます。このような背景を踏まえて、産後の健康管理行動への適応能力をアセスメントするとよいでしょう。
既往歴と周産期合併症の理解
A氏には23歳時に左卵巣嚢腫で腹腔鏡下手術を受けた既往があります。この経験により、手術や入院に対する心理的な準備があった可能性を考慮するとよいでしょう。また、妊娠中は妊娠性貧血と妊娠高血圧症候群という二つの合併症を経験しています。分娩時に一過性の血圧上昇(150/92mmHg)がみられたものの、分娩後は安定しており、現在の血圧は118/74mmHgと正常範囲内です。A氏がこれらの合併症についてどの程度理解しているか、また産後も注意が必要な点を認識しているかを確認することが重要です。
現在の健康状態の認識と服薬管理
A氏は現在、硫酸鉄、ロキソプロフェン、酸化マグネシウムを服用しており、服薬は自己管理で適切に行えています。妊娠中から継続している鉄剤の服用を適切に管理できていることは、服薬コンプライアンスが良好であることを示しています。几帳面で計画性のある性格は、退院後の服薬継続や健康管理にも良い影響を与える可能性があります。一方で、A氏は「母乳だけで赤ちゃんが十分育つのか心配」「乳頭が痛くて上手く授乳できているか分からない」と繰り返し発言しており、授乳に関する不安が大きいことがわかります。これは初産婦として当然の反応ですが、母乳育児の確立に向けた正しい知識の習得が必要であることを示唆しています。
健康リスク因子の把握
A氏には猫アレルギーがあることが記載されています。自宅で猫を飼育しているかどうかの情報はありませんが、退院後の環境においてアレルギー症状が産後の回復に影響しないかを確認することも重要です。また、妊娠高血圧症候群の既往は、将来的な高血圧発症リスクとも関連するため、退院後の定期的な血圧チェックの必要性についてA氏が理解しているかを確認するとよいでしょう。
退院後の健康管理に対する認識
医師からは、産後2週間健診と1ヶ月健診の予約確認、異常症状(発熱、悪露増加・異臭、乳房の腫脹・発赤・疼痛)があれば速やかに受診するよう指導されています。A氏がこれらの異常症状を認識し、適切なタイミングで受診できるかどうかは、産後の健康管理において重要な要素です。小学校教諭という職業柄、知識の習得や理解力には長けていると考えられますが、初めての育児に追われる中で自身の体調変化に注意を向けられるかどうかを考慮する必要があります。
アセスメントの視点
A氏の健康知覚-健康管理パターンをアセスメントする際は、もともとの健康管理能力の高さを強みとして捉えながら、産後特有の健康管理課題に対する認識と実践能力を評価することが重要です。妊娠中は適切な健康管理行動がとれていましたが、産後は育児という新たな責任が加わり、自身の回復と児のケアを両立させる必要があります。A氏は授乳に関する不安を言語化できており、これは問題認識ができていることの表れとして肯定的に捉えることができます。一方で、不安が強いことで適切な判断や行動が妨げられる可能性もあるため、心理的なサポートと正しい知識の提供を組み合わせた支援が必要かどうかを検討するとよいでしょう。
ケアの方向性
A氏の健康管理能力を活かしながら、産後の回復過程と母乳育児に関する正しい知識を提供することが重要です。授乳技術の習得に向けた具体的な指導を行い、成功体験を積み重ねることで自己効力感を高める支援が必要です。また、退院後に注意すべき異常症状について具体的に説明し、A氏が自身で判断できるようセルフモニタリングの視点を育てることも大切です。産後2週間健診や1ヶ月健診の重要性を伝え、継続的な健康管理への動機づけを行うことも、退院に向けた準備として重要なケアの方向性となります。
2. 栄養-代謝パターンのポイント
このパターンでは、産後の身体回復と母乳分泌を支えるための栄養・水分摂取状況、および貧血の改善状況を評価します。A氏が授乳婦として必要な栄養を適切に摂取できているか、また代謝に関連する検査データの推移を踏まえて栄養状態を総合的にアセスメントすることが重要です。
どんなことを書けばよいか
栄養-代謝パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 食事と水分の摂取量と摂取方法
- 食欲、嗜好、食事に関するアレルギー
- 身長・体重・BMI・必要栄養量・身体活動レベル
- 嚥下機能・口腔内の状態
- 嘔吐・吐気の有無
- 皮膚の状態、褥瘡の有無
- 栄養状態を示す血液データ(Alb、TP、RBC、Ht、Hb、Na、K、TG、TC、HbA1c、BSなど)
体重変化と栄養必要量
A氏の身長は160cm、妊娠前体重52kg、分娩時63kg、現在60kgです。妊娠前のBMIを計算すると20.3kg/m²で標準体型であったことがわかります。妊娠中の体重増加は11kgで、標準体型の妊婦における推奨増加量(10-13kg)の範囲内です。産褥3日目で分娩時より3kg減少していますが、これは分娩による児・胎盤・羊水の娩出、出血、利尿による生理的な体重減少と考えられます。授乳婦の付加エネルギー量は1日あたり約350kcalとされており、産後の回復と母乳分泌を維持するために十分なエネルギー摂取が必要であることを踏まえてアセスメントするとよいでしょう。
食事摂取状況と水分バランス
A氏は現在、産褥食を提供されており、食欲は良好で1日3食+間食を摂取しています。嚥下状態に問題はなく、嘔吐や吐気の記載もありません。これらは栄養摂取において良好な状態を示しています。一方で、A氏は「授乳のため水分摂取量を増やすよう意識しているが、十分な水分が取れているか不安を感じている」と述べています。母乳分泌には十分な水分摂取が重要であり、授乳婦は1日2000-2500ml程度の水分摂取が推奨されます。A氏が実際にどの程度の水分を摂取できているか、具体的な量を確認することが必要です。
貧血と鉄欠乏の状態
検査データに着目すると、ヘモグロビンは入院時10.4g/dLから産褥3日目に10.8g/dLへとわずかに改善していますが、依然として基準値(11.6-14.8g/dL)を下回っています。赤血球数も368×10⁴/μL(基準386-492)と低値であり、ヘマトクリットも33.2%(基準35.1-44.4%)と低い状態です。さらに重要なのは、フェリチンが4.5ng/mL(基準5-157)と低値を示しており、貯蔵鉄の枯渇した鉄欠乏状態であることがわかります。妊娠中から鉄剤を服用していることを踏まえると、長期間の鉄欠乏が続いていた可能性があります。産後は授乳により鉄の需要がさらに高まるため、貧血の改善が産後の回復や母乳育児の継続に重要な意味を持つことを意識してアセスメントするとよいでしょう。
栄養指標としての血液データ
総蛋白は6.7g/dL(基準6.6-8.1)で基準値内ですが、アルブミンは3.8g/dL(基準4.1-5.1)とやや低値です。産後は血液希釈の影響もありますが、授乳による蛋白需要の増加を考慮すると、良質な蛋白質の摂取が重要です。血糖値は88mg/dL(基準73-109)と正常範囲内で、妊娠糖尿病の徴候はありません。CRPは0.28mg/dL(基準0-0.14)とやや高値ですが、入院時の0.32mg/dLから改善傾向にあり、分娩後の生理的な炎症反応の収束過程と考えられます。これらのデータを総合的に解釈し、栄養状態と産後の回復過程を関連づけて考えるとよいでしょう。
母乳分泌と栄養の関連
母乳分泌は開始していますが、児の体重は出生時より5%減少しています。新生児の生理的体重減少は出生時体重の5-10%程度とされており、5%の減少は許容範囲内です。しかし、A氏は「母乳だけで赤ちゃんが十分育つのか心配」と不安を抱えています。母乳の産生量は産後日数とともに増加し、児の吸啜刺激によっても促進されます。A氏が適切な栄養と水分を摂取し、休息をとることが母乳分泌の確立に寄与することを踏まえて、栄養面からの支援を考えるとよいでしょう。
アセスメントの視点
A氏の栄養-代謝パターンをアセスメントする際は、産後の回復と母乳育児の確立という二つの目標を達成するための栄養摂取状況を評価することが重要です。食欲は良好で食事摂取はできていますが、貧血と鉄欠乏が継続していることは産後の回復を遅らせる要因となりえます。また、水分摂取に対する不安を抱えていることから、具体的な指導と安心感の提供が必要です。妊娠前から栄養バランスを意識した食生活を送っていたことは強みであり、退院後も継続できるよう支援することが重要です。検査データの推移を追いながら、貧血の改善状況を評価していく視点を持つとよいでしょう。
ケアの方向性
貧血改善のため、鉄剤の確実な服用を継続しながら、鉄分を多く含む食品(レバー、赤身肉、小松菜、ひじきなど)やビタミンCを含む食品(吸収を促進)の摂取について具体的な情報提供を行うことが重要です。授乳婦として必要な水分量を具体的に伝え、実践しやすい水分摂取の方法を一緒に考えることで、A氏の不安軽減につなげることができます。また、母乳分泌と栄養・水分・休息の関連についてわかりやすく説明し、A氏が自信を持って母乳育児に取り組めるよう支援することが求められます。
続きはnoteで公開中です✨️
ゴードンの続きとヘンダーソン・関連図・看護計画について解説しています😊
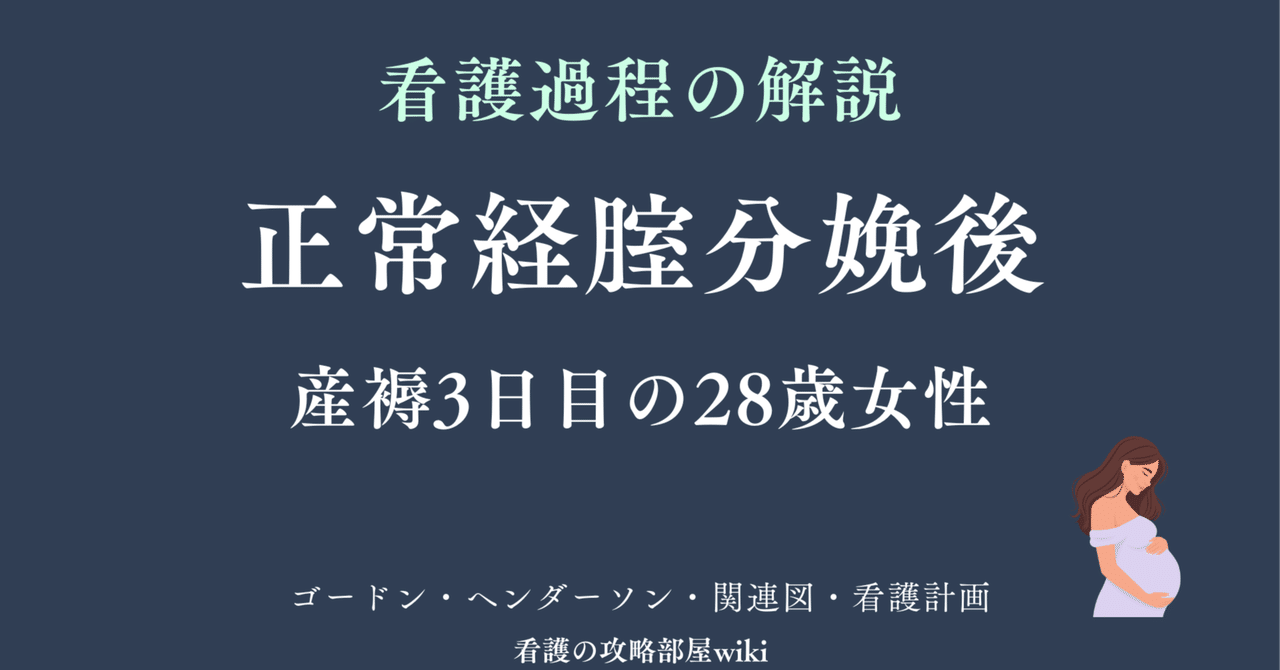
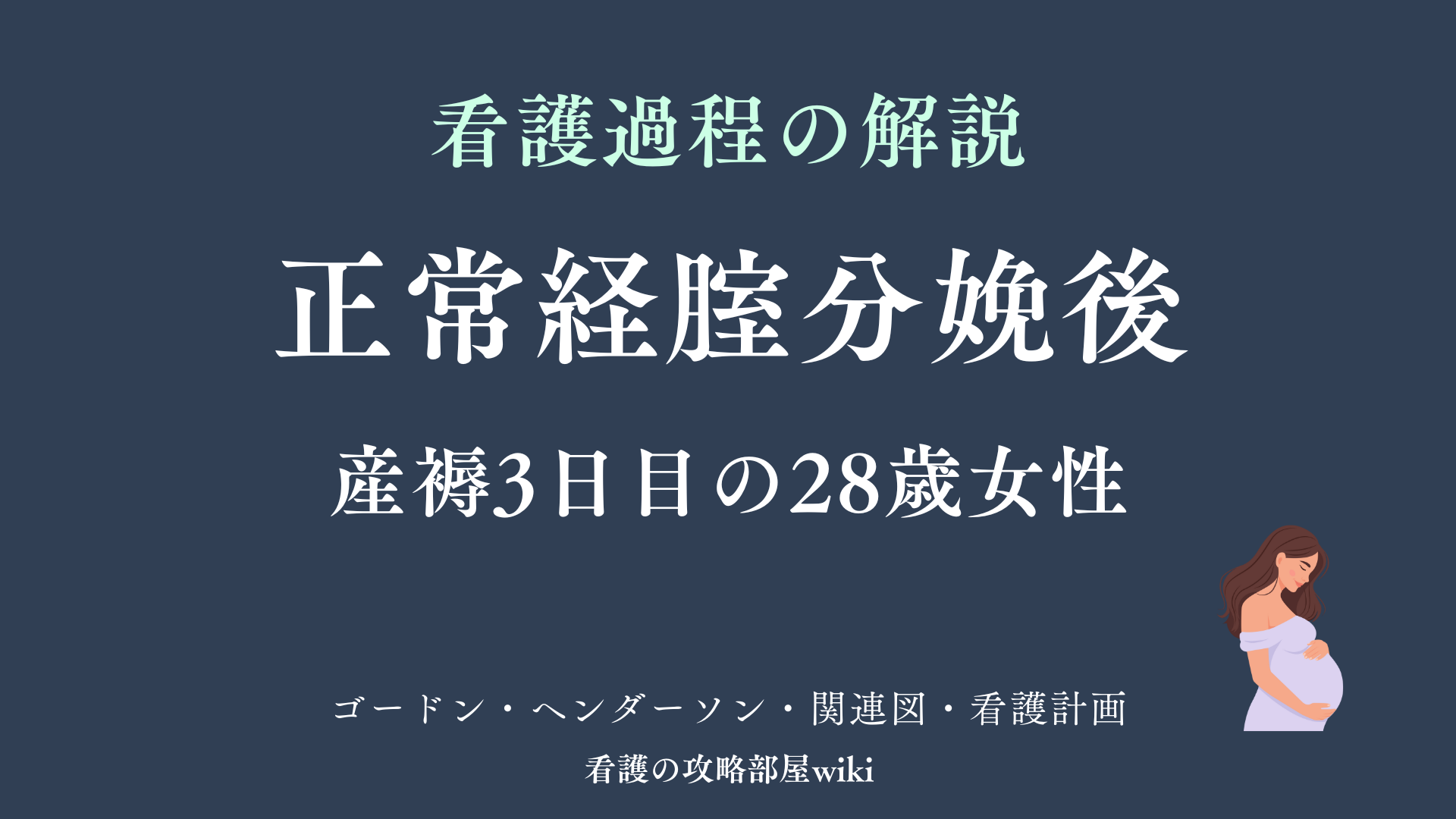
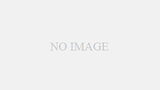

コメント