本記事では、看護師の思考プロセスを詳しく解説します。
実際の臨床では患者さんごとに状況が異なりますが、「わたしならどう考えるか」を具体的に示すことで、あなた自身の考える力を育てることを目指します。
この記事を参考に思考プロセスを学び、看護過程が得意になってもらえたら嬉しいです。
それでは、見ていきましょう。
看護学習や実習に役立つブログも運営しています✨️
ぜひ参考にしてみてくださいね!
https://kango-kouryaku.com/
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。事例は完全なフィクションであり、個別の診断・治療の根拠ではありません。実際の看護実践は患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください。本記事をそのまま課題として提出しないでください。内容の完全性・正確性は保証できず、本記事の利用により生じた損害について一切の責任を負いません。
今回の情報
基本情報
A氏は72歳の男性で、身長165cm、入院時の体重は68kgである。妻との二人暮らしで、近所に長男家族が在住しており、キーパーソンは妻である。職業は元電気工事士として40年間勤務し、5年前に退職している。性格は穏やかであるが、病気に関してはやや心配性な面がある。感染症の既往はなく、薬剤や食物に対するアレルギーも認めていない。認知機能は正常で、日常生活に支障をきたすような認知機能の低下は認めていない。
病名
慢性心不全の急性増悪
既往歴と治療状況
A氏は10年前に慢性心不全と診断され、以降外来で経過観察されていた。治療開始当初は塩分制限や水分制限を遵守していたが、症状が安定していたことで次第に制限が緩くなっていた。その他の既往歴は特記事項がない。
入院から現在までの情報
入院の契機は1週間前からの両下肢浮腫の増悪と起座呼吸である。体重が1週間で5kg急増し、夜間の呼吸困難が強くなり眠れない状態となったため救急受診となった。心エコー検査では左室駆出率35%と低下しており、中等度の僧帽弁閉鎖不全を認めた。胸部レントゲンでは、心胸郭比65%、両側肺うっ血像、胸水貯留を認めた。
入院後の治療として、フロセミドの静注(20mg×2回/日)による積極的な利尿を開始し、心不全の基本治療としてβ遮断薬とACE阻害薬の内服を継続している。塩分制限(6g/日)、水分制限(1000mL/日)を徹底した結果、入院3日目で体重は2kg減少し、呼吸困難感は軽減している。尿量は2000~2500mL/日と良好な利尿が得られており、起座呼吸は改善し、1~2枕での臥床が可能となっている。両下肢の浮腫は残存しているものの、圧痕の改善が認められている。入院3日目からは理学療法士による病室でのベッドサイドリハビリを開始している。
バイタルサイン
入院時のバイタルサインは、血圧148/92mmHg、脈拍92回/分と頻脈を認め、呼吸数24回/分と頻呼吸であった。SpO2は室内気で94%と軽度の低酸素血症を認め、体温は36.7℃であった。
現在(入院3日目)のバイタルサインは、血圧130/75mmHg、脈拍78回/分、呼吸数18回/分、SpO2は室内気で96%と改善を認めている。体温は36.5℃で経過しており、意識レベルは清明である。
食事と嚥下状態
入院前は妻が食事を全面的に管理していたが、以前から甘いものや塩辛いものを好む傾向があり、妻の目を盗んで間食やインスタント食品を摂取することがあった。嚥下機能に問題はない。飲酒は日本酒を2合/日摂取していたが、今回の入院を機に禁酒を決意している。喫煙歴はない。現在は心不全食(塩分6g/日制限)が提供され、水分制限(1000mL/日)も実施しており、食事摂取量は7~8割程度である。
排泄
入院前は自立しており、1日6~7回程度の排尿があり、便通は1日1回で規則的であった。下剤の使用はなかった。現在は利尿剤の使用により尿量が2000~2500mL/日と増加しており、夜間も2~3回のトイレ歩行がある。便通は入院後2日目にあり、性状は普通便であった。下剤の使用は不要である。
睡眠
入院前は1週間ほど前から呼吸困難感により夜間の睡眠が妨げられており、起座位での睡眠を強いられていた。眠剤の使用はなかった。現在は呼吸困難感が改善し、1~2個の枕を使用して仰臥位での睡眠が可能となっており、入眠は良好で眠剤は使用していない。ただし、夜間の排尿のため2~3回程度の覚醒がある。
視力・聴力・知覚・コミュニケーション・信仰
視力は軽度の老眼があり、新聞を読む際には老眼鏡を使用しているが、遠方視力は問題なく、日常生活に支障はない。聴力は正常で、普通の会話音量でのコミュニケーションが可能である。知覚に関しては、四肢の感覚障害はなく、温度覚・痛覚ともに正常である。コミュニケーションは良好で、言語理解力も表現力も問題ない。穏やかな性格で、医療者とのコミュニケーションも円滑である。信仰は特になく、宗教上の制限や希望は認めていない。
動作状況
入院前の動作状況として、歩行は自立しており補助具は使用していなかったが、呼吸困難感により連続歩行距離は50m程度に制限されていた。移乗動作は自立していており、排泄動作も自立しており、トイレまでの移動も問題なく行えていた。入浴は自宅での一般浴を自立して行っており、介助は不要であった。衣類の着脱も自立していた。転倒歴はない。
現在の動作状況は、病棟内の歩行は見守りで行っており、トイレまでの移動時には看護師が付き添っている。これは心不全による活動制限のためである。ベッドからの起き上がりや移乗動作は自立しているが、動作時の息切れに注意が必要である。排泄動作は自立している。入浴は現在未実施であり、清拭で対応している。衣類の着脱は時間をかければ自立して行えるが、上着の着脱時に軽度の息切れがみられる。病棟内での転倒は発生していない。
内服中の薬
- カルベジロール 5mg 1錠 朝食後
- エナラプリル 2.5mg 1錠 朝食後
- フロセミド 20mg 1錠 朝食後
- スピロノラクトン 25mg 1錠 朝食後
- フロセミド 20mg 静注 朝・夕(医師の指示で投与中)
検査データ
| 検査項目 | 基準値 | 入院時 | 入院3日目 |
|---|---|---|---|
| WBC | 4.0-8.0×10³/μL | 9.2 | 7.8 |
| RBC | 4.2-5.5×10⁶/μL | 4.5 | 4.4 |
| Hb | 13.0-17.0 g/dL | 12.5 | 12.3 |
| Ht | 40.0-50.0 % | 38.5 | 37.8 |
| Plt | 15.0-35.0×10⁴/μL | 22.5 | 23.1 |
| TP | 6.7-8.3 g/dL | 6.2 | 6.8 |
| Alb | 3.8-5.2 g/dL | 2.8 | 3.1 |
| AST | 13-33 IU/L | 28 | 25 |
| ALT | 8-42 IU/L | 32 | 30 |
| LDH | 119-229 IU/L | 245 | 215 |
| γ-GTP | 10-47 IU/L | 55 | 52 |
| BUN | 8-20 mg/dL | 28 | 24 |
| Cre | 0.6-1.1 mg/dL | 0.9 | 0.8 |
| Na | 138-146 mEq/L | 135 | 140 |
| K | 3.6-4.9 mEq/L | 4.2 | 4.0 |
| Cl | 99-109 mEq/L | 96 | 102 |
| BNP | <18.4 pg/mL | 850 | 650 |
| CRP | <0.14 mg/dL | 0.85 | 0.42 |
| BS | 70-109 mg/dL | 115 | 98 |
| HbA1c | 4.6-6.2 % | 6.5 | 6.5 |
入院前は妻が薬の管理を行っており、内服の確認も妻が行っていた。自宅での内服コンプライアンスは良好であった。入院中は看護師管理とし、配薬カートを使用して看護師が内服の確認を行っている。内服の拒否はなく、確実に内服できている。今後も心不全の再発予防のため継続した服薬管理が必要な状態である。
今後の治療方針と医師の指示
心不全の安定化を目標に、現在の薬物療法を継続しながら、心不全の増悪兆候がないか慎重に観察を続ける。利尿剤の静注は症状の改善に応じて漸減していく予定である。水分制限(1000mL/日)と塩分制限(6g/日)は継続とし、管理栄養士による食事指導を実施予定である。また、理学療法士によるリハビリテーションを段階的に進め、活動範囲の拡大を図っていく。心不全手帳を用いた自己管理指導を実施し、退院後の生活管理についても指導を行う。地域包括支援センターと連携し、退院後の生活支援体制の整備を進めていく方針である。医師からは、バイタルサインの継続的な観察、体重の毎日の測定、尿量の測定、心不全症状の観察が指示されている。
本人と家族の想いと言動
A氏は「息苦しさが良くなってきて、少し楽になった」と症状の改善を実感している。また、「今回の入院を機に、きちんと管理していきたい」と、治療や生活改善に対して前向きな姿勢を示している。一方で、「また症状が悪くなるのではないか」という不安も口にしており、病気の再発に対する心配性な側面がうかがえる。妻は「長男家族の支援も得られそうなので、頑張って夫の療養を支えていきたい」と協力的な姿勢を示している。ただし、塩分制限食の調理に対する不安も表出しており、「具体的な調理方法を教えてほしい」と希望している。長男家族も定期的な訪問を約束しており、家族による支援体制は整いつつある。
ゴードンの11項目のアセスメント解説
1. 健康知覚-健康管理パターンのポイント
このパターンでは、患者が自身の健康状態をどのように認識し、これまでどのように健康管理を行ってきたか、そして今後の療養に向けてどのような理解と姿勢を持っているかを評価します。特に慢性疾患を持つ患者の場合、疾患管理の継続性と再発予防の視点が重要となります。
どんなことを書けばよいか
健康知覚-健康管理パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 疾患についての本人・家族の理解度(病態、治療、予後など)
- 疾患や治療に対する受け止め方、受容の程度
- 現在の健康状態や症状の認識
- これまでの健康管理行動(受診行動、服薬管理、生活習慣など)
- 疾患が日常生活に与えている影響の認識
- 健康リスク因子(喫煙、飲酒、アレルギー、既往歴など)
疾患管理行動の変遷
A氏は10年前に慢性心不全と診断されて以降、外来で経過観察を受けていました。治療開始当初は塩分制限や水分制限を遵守していましたが、症状が安定していたことで次第に制限が緩くなっていたという経過があります。この点は、慢性疾患における自己管理の難しさを示しており、症状が安定している時期にこそ継続的な管理が必要であるという認識が不足していた可能性を考慮するとよいでしょう。
入院前の食生活に関して、妻が食事を全面的に管理していたにもかかわらず、妻の目を盗んで間食やインスタント食品を摂取することがあったという情報は重要です。これは単なる食事管理の問題ではなく、疾患管理における本人の主体性や理解度の問題として捉える必要があります。また、日本酒を2合/日摂取していたという飲酒習慣も、心不全管理の観点からリスク因子として評価するとよいでしょう。
症状認識と受診行動
今回の入院の契機となった症状について、A氏は1週間前からの両下肢浮腫の増悪と起座呼吸を認識していました。体重が1週間で5kg急増し、夜間の呼吸困難が強くなり眠れない状態となったことで救急受診に至っています。この経過から、A氏は症状の悪化を認識できていたものの、早期の段階で医療機関に相談できなかった可能性を考える必要があります。心不全の増悪兆候をどの段階で医療者に相談すべきかという判断基準が明確でなかった可能性を踏まえて、アセスメントするとよいでしょう。
疾患と治療への姿勢
入院後、A氏は「息苦しさが良くなってきて、少し楽になった」と症状の改善を実感しており、「今回の入院を機に、きちんと管理していきたい」と治療や生活改善に対して前向きな姿勢を示しています。この発言は、現在の健康状態への認識と今後の療養への意欲を示すものであり、セルフケア能力向上への重要な基盤となることを意識して記述するとよいでしょう。
一方で、「また症状が悪くなるのではないか」という不安も口にしており、性格として心配性な面があることも記載されています。この不安は、適切な疾患管理の知識と技術を獲得することで軽減できる可能性がありますが、過度な不安が療養生活の質を低下させる要因にもなり得るという両面から考える必要があります。
家族の健康管理への関与
妻が食事管理や服薬管理を全面的に担っていたという情報は、家族のサポート体制を示す一方で、A氏自身の疾患管理への主体的な参加が不十分であった可能性も示唆しています。入院前の内服コンプライアンスは良好であったとされていますが、これは妻による管理の成果であり、A氏自身の理解に基づくものかどうかを評価する必要があります。
妻は「長男家族の支援も得られそうなので、頑張って夫の療養を支えていきたい」と協力的な姿勢を示している一方で、塩分制限食の調理に対する不安も表出しており、「具体的な調理方法を教えてほしい」と希望しています。この点から、家族も含めた疾患管理教育の必要性を考慮するとよいでしょう。
アセスメントの視点
A氏の健康管理行動を評価する際には、これまでの管理が妻主導で行われており、本人の主体的な参加が不十分であった可能性を考える必要があります。症状安定期に制限が緩くなった経緯、妻の目を盗んでの間食、増悪兆候出現から受診までに1週間を要した点などから、疾患管理の重要性や増悪兆候の早期発見に関する知識が不足している可能性を評価するとよいでしょう。
同時に、現在は前向きな姿勢を示しており、症状の改善を実感できていることは、今後の自己管理能力向上への動機づけとして重要な要素となります。この変化への準備性を踏まえて、どのような支援が効果的かを考えることが大切です。
ケアの方向性
心不全の病態、増悪因子、日常生活での注意点について、本人と家族が正しく理解できるよう支援する必要があります。特に、症状が安定している時期こそ継続的な管理が重要であることを理解してもらうことが再発予防につながります。心不全手帳を活用した自己管理指導を計画的に実施し、体重測定や症状観察など、本人が主体的に行える管理方法を具体的に示していくことが重要です。また、妻の不安にも対応しながら、家族全体で療養を支える体制を構築していく視点が必要となります。
2. 栄養-代謝パターンのポイント
このパターンでは、栄養摂取状況と代謝機能を評価します。心不全患者の場合、塩分・水分制限が治療の根幹となるため、これまでの食生活と現在の制限への適応状況、そして今後の継続可能性を慎重に評価する必要があります。
どんなことを書けばよいか
栄養-代謝パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 食事と水分の摂取量と摂取方法
- 食欲、嗜好、食事に関するアレルギー
- 身長・体重・BMI・必要栄養量・身体活動レベル
- 嚥下機能・口腔内の状態
- 嘔吐・吐気の有無
- 皮膚の状態、褥瘡の有無
- 栄養状態を示す血液データ(Alb、TP、RBC、Ht、Hb、Na、K、TG、TC、HbA1c、BSなど)
体格と栄養状態の評価
A氏は身長165cm、入院時体重68kgであり、BMIは約24.9kg/m²となります。この値は標準的な範囲内にありますが、入院前1週間で5kgの急激な体重増加があったことを考えると、実際の体重は63kg程度であった可能性を考慮する必要があります。この急激な体重増加は体液貯留によるものであり、心不全の増悪を示す重要な指標となっています。
血液データからは、Alb 2.8→3.1 g/dL(基準値3.8-5.2)、TP 6.2→6.8 g/dL(基準値6.7-8.3)と、低栄養状態を示す所見が認められます。Hb 12.5→12.3 g/dL(基準値13.0-17.0)、Ht 38.5→37.8%(基準値40.0-50.0)も軽度の低値を示しており、これらのデータから栄養状態を総合的に評価することが重要です。ただし、入院時のAlbやTPの低値は、心不全による体液貯留に伴う希釈の影響も考えられるため、利尿後のデータと合わせて評価するとよいでしょう。
入院前の食生活と嗜好
入院前は妻が食事を全面的に管理していましたが、A氏には甘いものや塩辛いものを好む傾向があり、妻の目を盗んで間食やインスタント食品を摂取することがあったという情報は極めて重要です。この行動パターンから、塩分過剰摂取が今回の心不全増悪の主要な原因となった可能性を考える必要があります。インスタント食品は一般的に塩分含有量が高く、心不全患者にとって大きなリスク因子となることを踏まえて評価するとよいでしょう。
また、日本酒を2合/日摂取していたという飲酒習慣も、水分摂取量の増加要因として考慮する必要があります。ただし、今回の入院を機に禁酒を決意しているという発言は、生活習慣改善への動機づけがあることを示しており、ポジティブな要素として捉えることができます。
現在の食事摂取状況
入院後は心不全食(塩分6g/日制限)が提供され、水分制限(1000mL/日)も実施されています。食事摂取量は7~8割程度であり、嚥下機能に問題はなく、嘔吐や吐気も認められていません。この摂取量をどう評価するかが重要なポイントとなります。制限食への適応過程にあることを考えると、7~8割の摂取は決して悪くない状況ともいえますが、必要栄養量が確保できているかという観点からの評価も必要となります。
嗜好の変化や味付けの違和感など、制限食に対する本人の感じ方についての情報があれば、今後の継続可能性を予測する材料となります。現時点で食事摂取量が8割程度に留まっている理由が、味付けの問題なのか、食欲の問題なのか、あるいは量の問題なのかを評価することが、退院後の食事管理を支援する上で重要となります。
水分・塩分管理の状況
入院後、水分制限1000mL/日、塩分制限6g/日が徹底された結果、入院3日目で体重は2kg減少し、BNPも850→650pg/mLと改善傾向を示しています。この治療反応から、適切な水分・塩分管理が心不全の改善に直結することが実証されており、今後の自己管理の重要性を本人に理解してもらう貴重な機会となることを意識するとよいでしょう。
Na 135→140 mEq/L(基準値138-146)と改善していることも、体液管理が適切に行われていることを示しています。K 4.2→4.0 mEq/L(基準値3.6-4.9)は正常範囲内で推移しており、利尿薬使用下でも電解質バランスが保たれていることを評価するとよいでしょう。
血糖コントロール
BS 115→98 mg/dL(基準値70-109)、HbA1c 6.5%(基準値4.6-6.2)という結果から、軽度の耐糖能異常を認めます。これは心不全患者において心血管リスク因子となる可能性があり、今後の栄養管理を考える上で考慮すべき点となります。ただし、現時点では糖尿病の診断基準は満たしておらず、食事療法でコントロール可能な範囲と考えられるため、心不全食に加えて糖質管理の視点も必要となることを意識して記述するとよいでしょう。
家族の調理スキルと不安
妻が「具体的な調理方法を教えてほしい」と塩分制限食の調理に対する不安を表出していることは、退院後の食事管理を考える上で重要な情報です。これまで妻が食事管理を担ってきたものの、本格的な塩分制限食の調理経験がない可能性を示唆しています。妻の不安に対応し、実践可能な調理方法を具体的に提示することが、退院後の食事管理の継続性を確保する上で不可欠となります。
アセスメントの視点
A氏の栄養・代謝状態を評価する際には、入院前の塩分過剰摂取が今回の心不全増悪の主要因となった可能性を考える必要があります。甘いものや塩辛いものを好む嗜好、妻の目を盗んでの間食習慣は、単なる食生活の問題ではなく、疾患管理における認識不足を示している可能性があります。
一方で、入院後の制限食への適応状況は比較的良好であり、治療効果も明確に現れていることから、適切な指導と支援があれば自己管理が可能になる可能性を評価するとよいでしょう。血液データからは軽度の低栄養状態が示唆されますが、利尿後のデータ改善傾向も認められており、体液管理の効果と真の栄養状態を区別して評価することが重要です。
ケアの方向性
塩分制限・水分制限の重要性について、本人と家族が具体的に理解できるよう支援する必要があります。管理栄養士による食事指導を効果的に活用し、妻の不安に対応しながら、実践可能な調理方法を具体的に示していくことが重要です。退院後も継続可能な食事管理方法を本人・家族とともに検討し、嗜好を考慮しながら塩分制限を継続できる工夫を一緒に考えていく姿勢が求められます。また、体重測定を日課とし、急激な体重増加を早期に発見できる自己管理能力を育成していくことが再発予防につながります。
3. 排泄パターンのポイント
このパターンでは、排尿・排便の状況とIn-Outバランスを評価します。心不全患者の場合、利尿薬による治療効果の判定や体液管理の状況を評価する上で、排泄機能の観察が極めて重要となります。
どんなことを書けばよいか
排泄パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 排便と排尿の回数・量・性状
- 下剤やカテーテル使用の有無
- In-Outバランス
- 排泄に関連した食事・水分摂取状況
- 安静度、活動量
- 腹部の状態(腹部膨満、腸蠕動音など)
- 腎機能を示す血液データ(BUN、Cr、GFRなど)
続きはnoteで公開中です✨️
ゴードンの続きとヘンダーソン・関連図・看護計画について解説しています😊
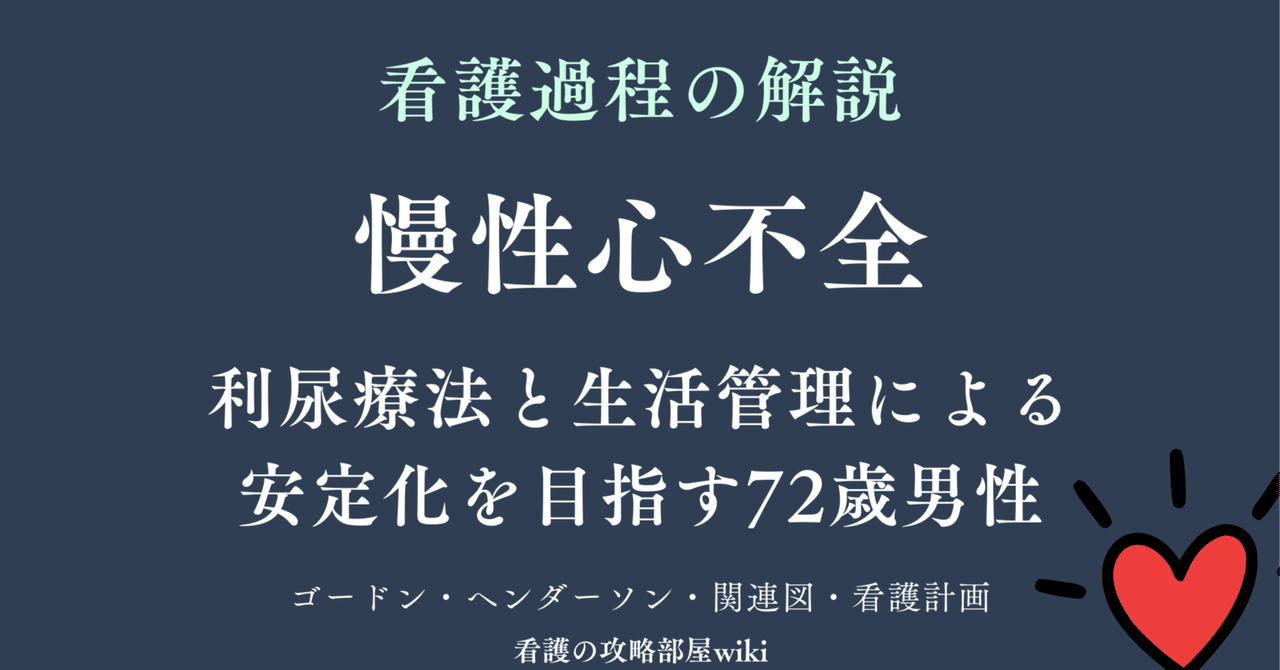
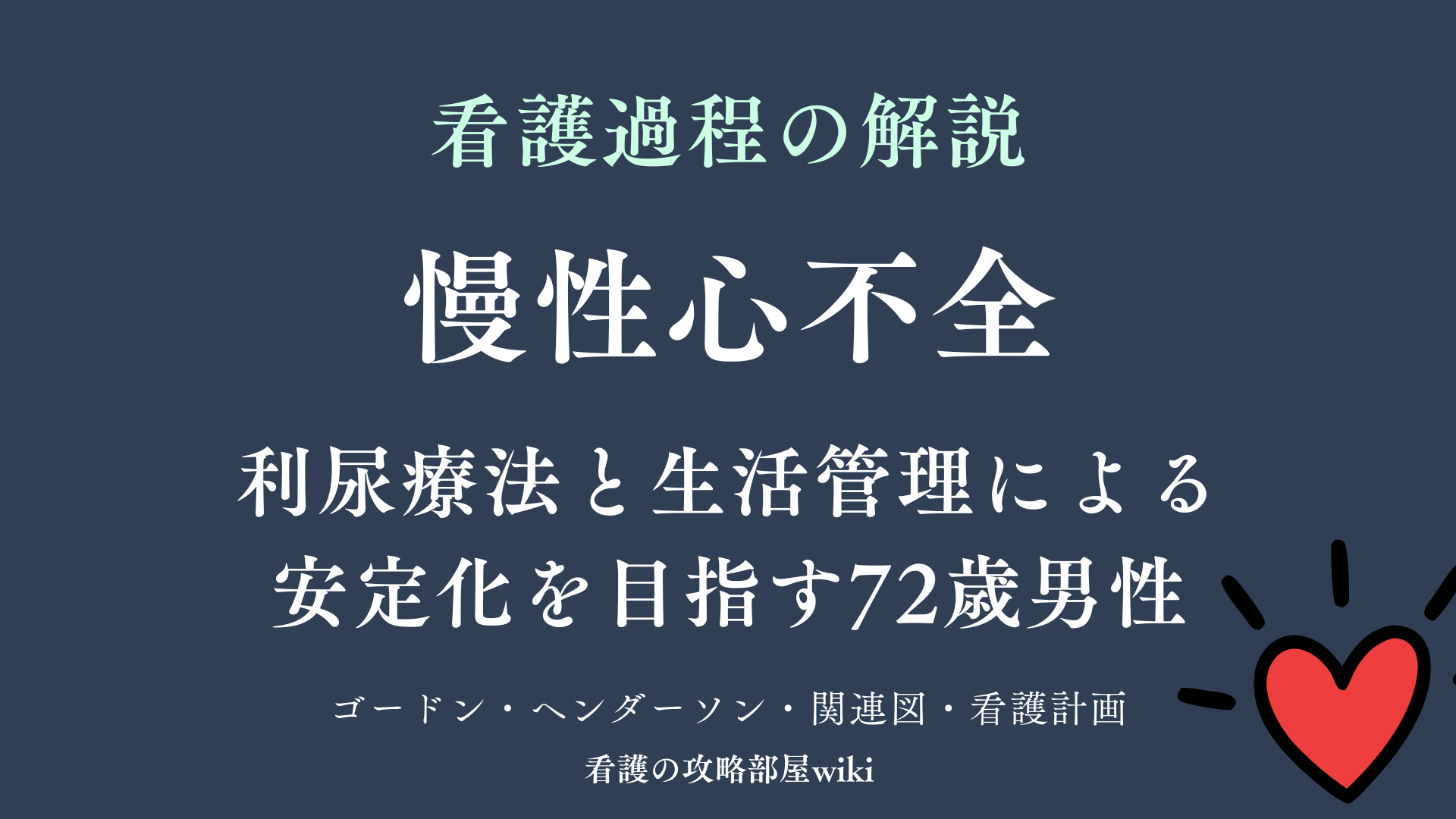


コメント