本記事では、看護師の思考プロセスを詳しく解説します。
実際の臨床では患者さんごとに状況が異なりますが、「わたしならどう考えるか」を具体的に示すことで、あなた自身の考える力を育てることを目指します。
この記事を参考に思考プロセスを学び、看護過程が得意になってもらえたら嬉しいです。
それでは、見ていきましょう。
看護学習や実習に役立つブログも運営しています✨️
ぜひ参考にしてみてくださいね!
https://kango-kouryaku.com/
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。事例は完全なフィクションであり、個別の診断・治療の根拠ではありません。実際の看護実践は患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください。本記事をそのまま課題として提出しないでください。内容の完全性・正確性は保証できず、本記事の利用により生じた損害について一切の責任を負いません。
基本情報
A氏、40歳、女性、身長158cm、体重52kg。夫(43歳)と長女(15歳)、長男(12歳)の4人家族で、キーパーソンは夫である。職業は事務職として勤務していたが、症状悪化により1ヶ月前から休職中である。性格は真面目で几帳面、責任感が強く周囲への気遣いを優先する傾向がある。感染症はなく、アレルギーは花粉症のみである。認知機能に問題はなく、見当識は保たれている。
病名
全般性不安障害
既往歴と治療状況
既往歴として35歳時にパニック障害の診断を受け、約半年間通院治療を行い寛解していた。現在は全般性不安障害に対して薬物療法と精神療法を併用した治療を行っている。
入院から現在までの情報
3ヶ月前から仕事や家庭のことで過度に心配する症状が出現し、動悸、めまい、発汗、手の震えなどの身体症状を伴うようになった。近医を受診し全般性不安障害と診断され外来通院していたが、日常生活に支障をきたすほど症状が増悪し、不安のコントロールが困難となったため、10月8日に精神科病棟へ入院となった。入院時は表情が硬く、落ち着きのない様子で、「このまま治らないのではないか」「家族に迷惑をかけている」と涙ぐみながら訴えていた。入院後、薬物療法の調整と環境調整を行い、徐々に不安症状は軽減傾向にある。現在は病棟内での活動には参加できるようになり、他患者との交流も少しずつ見られるようになっている。
バイタルサイン
入院時のバイタルサインは、体温36.8℃、血圧138/88mmHg、脈拍102回/分(整)、呼吸数24回/分、SpO2 98%(室内気)であった。**現在のバイタルサインは、体温36.5℃、血圧122/76mmHg、脈拍78回/分(整)、呼吸数18回/分、SpO2 99%(室内気)**で、入院時と比較して安定している。
食事と嚥下状態
入院前は食欲不振があり、1日2食程度で摂取量も5割程度であった。嚥下機能に問題はないが、不安が強い時は食事が喉を通らないと訴えていた。現在は常食で3食摂取しており、摂取量は8割程度まで改善している。喫煙習慣はなく、飲酒は社交的な場で月に1-2回程度ビールを1杯飲む程度である。
排泄
入院前は便秘傾向で3-4日に1回の排便であり、便性状は硬便であった。排尿は日中8-10回程度で夜間も2-3回覚醒していた。現在は緩下剤の内服により2日に1回の排便があり、便性状は普通便となっている。排尿回数は日中6-8回、夜間1回程度に減少している。
睡眠
入院前は不安のため入眠困難があり、入眠まで2-3時間かかることが多く、中途覚醒も頻回であった。睡眠時間は実質4-5時間程度で、日中の眠気と倦怠感を訴えていた。現在は睡眠導入剤の内服により、入眠までの時間は30分程度に短縮し、睡眠時間も6-7時間確保できるようになっている。中途覚醒は1回程度に減少している。
視力・聴力・知覚・コミュニケーション・信仰
視力は両眼とも矯正視力で1.0、眼鏡を使用している。聴力は正常で会話に支障はない。知覚に異常はなく、幻覚や妄想は認めていない。コミュニケーション能力は良好であるが、不安が強い時は言葉が詰まったり早口になったりする傾向がある。特定の信仰はないが、正月には神社へ参拝する程度である。
動作状況
歩行、移乗、排泄、入浴、衣類の着脱はすべて自立している。転倒歴はない。不安が強い時は動作が緩慢になったり、手が震えて細かい作業がしにくくなったりすることがある。現在は日常生活動作に支障はない。
内服中の薬
- エスシタロプラム(レクサプロ)10mg 1日1回朝食後
- アルプラゾラム(ソラナックス)0.4mg 1日3回毎食後
- ゾルピデム(マイスリー)5mg 1日1回就寝前
- 酸化マグネシウム 330mg 1日3回毎食後
検査データ
| 項目 | 入院時(10/8) | 最近(10/13) | 基準値 |
|---|---|---|---|
| WBC | 6800 /μL | 6500 /μL | 3300-8600 |
| RBC | 425 万/μL | 432 万/μL | 386-492 |
| Hb | 13.2 g/dL | 13.5 g/dL | 11.6-14.8 |
| Ht | 39.8 % | 40.5 % | 35.1-44.4 |
| Plt | 24.5 万/μL | 25.2 万/μL | 15.8-34.8 |
| AST | 22 U/L | 20 U/L | 13-30 |
| ALT | 18 U/L | 16 U/L | 7-23 |
| BUN | 12.5 mg/dL | 11.8 mg/dL | 8-20 |
| Cre | 0.65 mg/dL | 0.63 mg/dL | 0.46-0.79 |
| Na | 139 mEq/L | 140 mEq/L | 138-145 |
| K | 4.1 mEq/L | 4.0 mEq/L | 3.6-4.8 |
| Cl | 102 mEq/L | 103 mEq/L | 101-108 |
| CRP | 0.08 mg/dL | 0.05 mg/dL | 0-0.14 |
薬剤は現在看護師管理下にあり、配薬時に内服確認を行っている。
今後の治療方針と医師の指示
今後は薬物療法を継続しながら、認知行動療法やリラクゼーション技法を取り入れた精神療法を実施していく方針である。不安のコントロールが安定し、日常生活への適応が可能と判断された段階で外来通院に移行する予定である。医師からは、不安症状の観察を継続し、症状の変動があれば報告すること、また段階的に病棟外への外出訓練を実施し、社会復帰に向けた準備を進めていくよう指示が出ている。
本人と家族の想いと言動
A氏は「少しずつ落ち着いてきた気がしますが、また不安が強くなったらどうしようと考えてしまいます」「家族に心配をかけていることが申し訳なくて、早く元気になりたいです」と話している。また「仕事に復帰できるのか不安です。職場の人に迷惑をかけているのではないかと思うと胸が苦しくなります」とも述べている。夫は週に2回面会に訪れており、「妻が無理をしすぎていたことに気づいてあげられなかった。これからはもっとサポートしていきたい」と話している。長女と長男も週末に面会に来ており、「お母さんが元気になって家に帰ってきてほしい」と言葉をかけている。
ゴードン11項目アセスメント解説
1. 健康知覚-健康管理パターンのポイント
このパターンでは、A氏が自身の疾患をどのように認識し、どのように健康管理を行ってきたか、そして現在の治療に対してどのような姿勢を持っているかを評価することが重要です。特に、過去のパニック障害の経験が現在の疾患認識にどう影響しているか、また真面目で責任感が強い性格特性が健康管理行動にどう関連しているかを考える必要があります。
どんなことを書けばよいか
健康知覚-健康管理パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 疾患についての本人・家族の理解度(病態、治療、予後など)
- 疾患や治療に対する受け止め方、受容の程度
- 現在の健康状態や症状の認識
- これまでの健康管理行動(受診行動、服薬管理、生活習慣など)
- 疾患が日常生活に与えている影響の認識
- 健康リスク因子(喫煙、飲酒、アレルギー、既往歴など)
既往歴からの健康認識
A氏は35歳時にパニック障害の診断を受け、約半年間の通院治療で寛解した経験を持っています。この経験は、A氏が精神疾患の治療に一定の理解があることを示していますが、同時に「このまま治らないのではないか」という訴えから、過去の寛解経験が必ずしも今回の不安の軽減につながっていない可能性も考えられます。前回の経験と今回の症状の違い、あるいは症状の重症度の差異についてA氏がどのように認識しているかを踏まえて記述するとよいでしょう。
疾患に対する受け止め方
入院時にA氏が「このまで治らないのではないか」「家族に迷惑をかけている」と涙ぐみながら訴えていた点は、疾患に対する不安と罪悪感が混在していることを示しています。また「仕事に復帰できるのか不安です。職場の人に迷惑をかけているのではないか」という発言からは、疾患が社会的役割に与える影響を強く意識していることが読み取れます。これらの発言が示す心理状態と、真面目で几帳面、責任感が強いという性格特性との関連を考慮しながら、疾患受容の程度をアセスメントすることが重要です。
症状の認識と受診行動
A氏は3ヶ月前から症状が出現した際に近医を受診し、外来通院を継続していました。症状が増悪し日常生活に支障をきたすようになった段階で入院治療を受け入れていることから、適切な受診行動がとれていると評価できます。この点を踏まえて、A氏の健康管理に対する意識や行動をどのように記述するか検討するとよいでしょう。
健康リスク因子の管理
喫煙習慣はなく、飲酒も社交的な場で月に1-2回程度ビールを1杯飲む程度と、健康リスクとなる生活習慣は見られません。アレルギーは花粉症のみで、感染症もありません。これらの情報は、A氏が基本的な健康管理ができていることを示しており、今後の健康管理行動を考える上での強みとなります。
治療への協力姿勢
現在、薬剤は看護師管理下にあり配薬時に内服確認を行っていますが、A氏は治療に対して協力的な姿勢を示しています。「少しずつ落ち着いてきた気がします」という発言からは、治療効果を自覚し始めていることが読み取れます。ただし「また不安が強くなったらどうしよう」という予期不安も持っているため、この両面性を考慮したアセスメントが必要です。
アセスメントの視点
健康知覚-健康管理パターン全体を通して、A氏は自身の健康状態を適切に認識し、必要な医療を受ける行動がとれている一方で、疾患に対する不安や罪悪感が強く、これが疾患受容を妨げている可能性があります。過去のパニック障害の経験、真面目で責任感が強い性格特性、家族や職場への配慮といった要素が、現在の健康認識にどのように影響しているかという視点でアセスメントすることが重要です。
ケアの方向性
A氏の適切な受診行動や治療への協力姿勢という強みを活かしながら、疾患に対する正確な理解を深め、過度な不安や罪悪感を軽減するための心理教育を行っていく必要があります。また、症状の改善を実感できるような関わりを通して、治療への肯定的な認識を強化していくことが求められます。
2. 栄養-代謝パターンのポイント
このパターンでは、A氏の食事摂取状況が不安症状とどのように関連しているか、また入院後の改善がどのような要因によるものかを評価することが重要です。精神的な状態が食欲や摂取量に与える影響を考慮しながら、栄養状態の変化を捉える必要があります。
どんなことを書けばよいか
栄養-代謝パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 食事と水分の摂取量と摂取方法
- 食欲、嗜好、食事に関するアレルギー
- 身長・体重・BMI・必要栄養量・身体活動レベル
- 嚥下機能・口腔内の状態
- 嘔吐・吐気の有無
- 皮膚の状態、褥瘡の有無
- 栄養状態を示す血液データ(Alb、TP、RBC、Ht、Hb、Na、K、TG、TC、HbA1c、BSなど)
入院前の食事摂取状況
入院前のA氏は食欲不振があり、1日2食程度で摂取量も5割程度でした。「不安が強い時は食事が喉を通らない」という訴えは、精神的ストレスが身体症状として現れ、食事摂取に直接影響を与えていたことを示しています。この時期の摂取量の低下が、3ヶ月という期間でA氏の栄養状態や体力にどの程度影響を与えていたかを考慮してアセスメントするとよいでしょう。
身体計測値と栄養状態
A氏の身長は158cm、体重は52kgで、BMIは約20.8と標準範囲内にあります。入院時の血液データでは、Hb 13.2 g/dL、RBC 425万/μL、Ht 39.8%といずれも基準値内であり、著明な栄養障害は認められません。最近の検査データでもHb 13.5 g/dL、RBC 432万/μL、Ht 40.5%と、わずかに改善傾向を示しています。これらのデータから、入院前の摂取量低下があったものの、短期間であったため重度の栄養障害には至っていないと考えられます。この点を踏まえて、現在の栄養状態を記述するとよいでしょう。
嚥下機能と食事形態
嚥下機能に問題はなく、現在は常食を摂取しています。嚥下機能が保たれていることは、食事摂取を促進する上での重要な強みとなります。食事形態に制限がないことで、十分な栄養摂取が可能な状態にあることを意識して記述するとよいでしょう。
入院後の改善状況
現在は3食摂取しており、摂取量は8割程度まで改善しています。入院時と比較して食事摂取量が大幅に改善していることは、環境調整と薬物療法により不安症状が軽減した結果と考えられます。「少しずつ落ち着いてきた気がします」というA氏の発言とも一致しており、精神状態の安定が食事摂取の改善につながっていることを示しています。
水分・電解質バランス
血液データでは、Na 139→140 mEq/L、K 4.1→4.0 mEq/Lと電解質バランスは保たれています。排尿回数が入院前は日中8-10回、夜間2-3回と頻回でしたが、現在は日中6-8回、夜間1回程度に減少していることから、水分バランスも改善傾向にあると考えられます。これらの情報を統合して、水分・電解質管理の状況を記述するとよいでしょう。
アセスメントの視点
栄養-代謝パターン全体を通して、A氏は精神状態の変化に伴い食事摂取量が大きく変動していますが、基本的な栄養状態は保たれています。入院後の食事摂取量の改善は、不安症状の軽減と密接に関連していることを示しており、今後も精神状態の安定が栄養状態の維持・改善につながるという視点でアセスメントすることが重要です。
ケアの方向性
現在の食事摂取量8割程度を維持し、さらに10割に近づけていくために、食事環境の調整や食事時間の確保を継続することが必要です。また、不安症状の再燃が食事摂取に与える影響を観察し、早期に対応できる体制を整えることが求められます。退院後の食生活についても、ストレス状況下での食事摂取の工夫について考える機会を持つことが重要です。
続きはnoteで公開中です✨️
ゴードンの続きとヘンダーソン・関連図・看護計画について解説しています😊
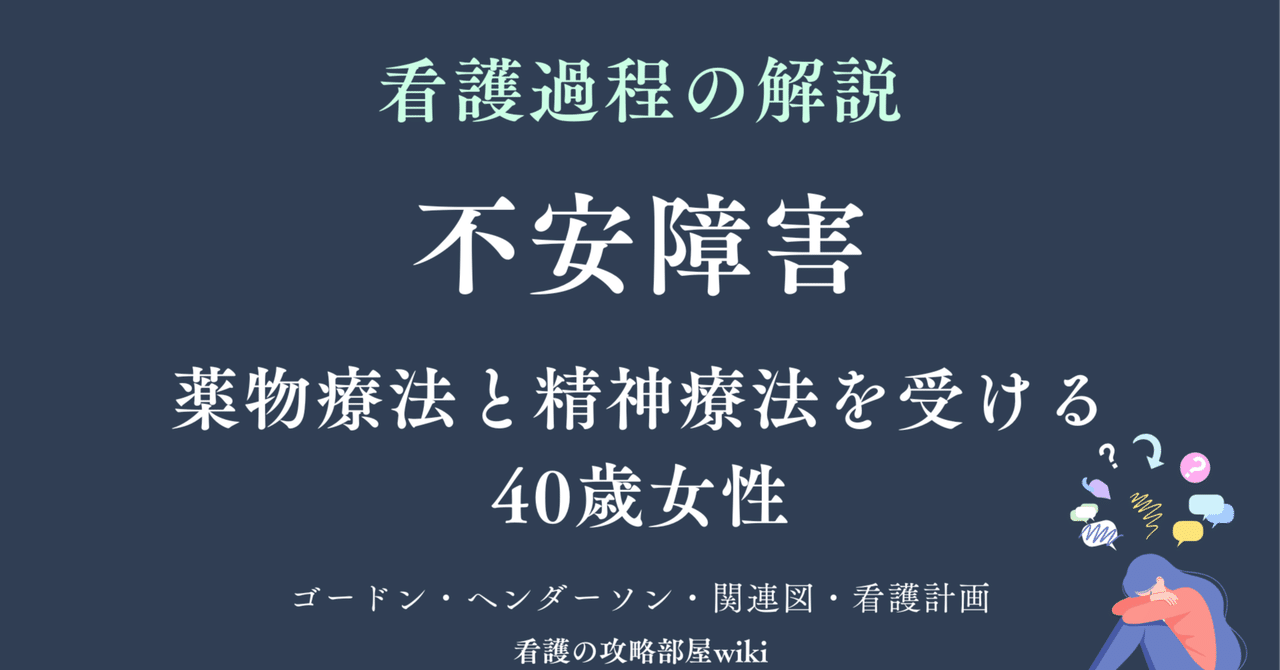
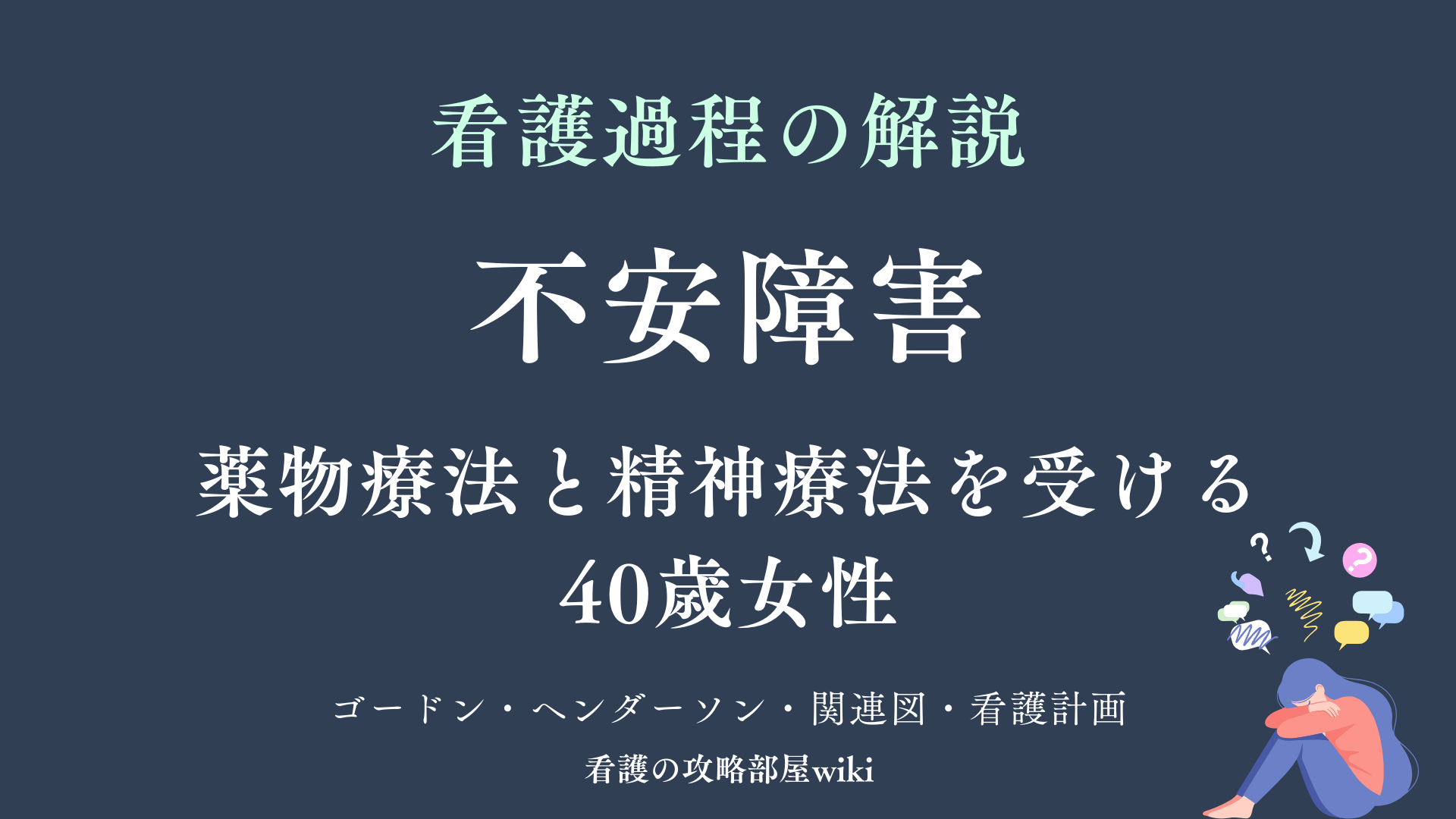


コメント