今回の情報
基本情報
A氏は85歳の男性で、身長165cm、体重58kgである。元高校数学教師であり、現在は退職している。温厚で几帳面な性格の持ち主である。82歳の妻と3世代同居しており、家族構成は妻のほか、45歳の長男、42歳の長男の妻、および中学生と小学生の孫2人との5人家族である。キーパーソンは妻であり、発症前から服薬管理を含めたA氏の健康管理に積極的に関わっている。感染症やアレルギーの既往はない。認知機能の評価では、脳梗塞発症後にMMSE 26点、HDS-R 25点であり、軽度の認知機能低下が認められている。主に見当識と記憶の項目で減点が見られるが、これは環境の変化や睡眠障害の影響も考えられる。時間の見当識は時折曖昧になることがあるが、人物の認識や場所の理解は保たれており、医療者の指示理解も良好である。
病名
右中大脳動脈領域の脳梗塞
既往歴と治療状況
A氏は高血圧を15年間罹患しており、アムロジピン5mg/日の内服により継続的に治療を受けている。また、10年前から糖尿病の診断を受けており、メトホルミン500mg/日を内服して血糖コントロールを行っている。いずれの疾患についても、妻が服薬管理を担当し、治療が継続されていた。
入院から現在までの情報
発症当日、A氏は庭の手入れをしている最中に突然の左半身の脱力感と言語障害を自覚した。家族により直ちに救急要請され、搬送時の意識レベルはJCS Ⅰ-2で、左上下肢の麻痺が顕著であった。救急搬送後のMRI検査により右中大脳動脈領域の脳梗塞と診断され、発症から2時間以内であったため、直ちに血栓溶解療法(rt-PA療法)が開始された。発症前は、趣味の盆栽の手入れと1日4000歩程度の散歩を日課とし、週に1回は地域の将棋サークルに参加するなど活動的な生活を送っていた。また、地域の学習支援ボランティアとしても活動していた。
入院後、rt-PA療法を実施した後、現在は抗凝固療法(クロピドグレル75mg/日)を継続している。言語機能は徐々に改善し、発語明瞭度は3/5まで回復したが、左半身の麻痺は残存しており、ブルンストロームテストでは上肢Ⅲ、手指Ⅲ、下肢Ⅳと評価されている。嚥下機能の低下(MWST:3点)により、現在はとろみ食を摂取している。排泄はポータブルトイレを使用しているが、移乗時には介助を要する。環境の変化による不眠を訴えることが多く、夜間の不穏も時折見られ、睡眠時間は4~5時間程度で断続的である。日中は1~2回/日の個別リハビリテーションを意欲的に実施している。現在のFIMは運動項目45点、認知項目25点である。
バイタルサイン
入院時のバイタルサインは血圧178/98mmHg、脈拍88回/分、体温36.8℃、SpO2 96%であった。現在(入院7日目)は血圧142/82mmHg、脈拍72回/分、体温36.7℃、SpO2 97%と安定している。
食事と嚥下状態
入院前はA氏は常食を自力で摂取し、食事量も良好であった。現在は嚥下機能の低下(MWST:3点)により、誤嚥予防のためとろみ食を摂取している。食事時は体幹を30度挙上し、頸部を軽度屈曲位にして、ゆっくりと摂取するよう促されている。水分摂取時はとろみ剤を使用し、現在の食事量は7~8割程度である。
喫煙の習慣は20歳から60歳までの間、1日20本程度あったが、定年退職を機に禁煙し、現在は喫煙していない。飲酒は機会飲酒程度であり、将棋サークル後の懇親会で缶ビール1本程度を飲む習慣があったが、入院後は禁酒している。
排泄
入院前のA氏は、トイレまで自力歩行し、排泄は完全に自立していた。現在は左半身麻痺により、ポータブルトイレを使用しているが、移乗時には介助を要する。排尿は日中6~7回、夜間2~3回程度であり、排便は1日1回の規則的な排泄パターンを維持している。下剤の使用は現在のところ必要としていない。
睡眠
入院前は21時から翌朝6時まで良眠でき、日中の活動も活発であった。現在は環境の変化による不眠を訴えることが多く、夜間の不穏も時折見られる。睡眠時間は4~5時間程度で断続的であり、特に夜間のトイレ介助の際に覚醒してしまうことが多い。眠剤等の使用については、本人と相談の上、現在は使用していない状況である。
視力・聴力・知覚・コミュニケーション・信仰
視力は軽度の老眼があり、新聞を読む際は老眼鏡を使用している。聴力は左右ともに会話に支障のない程度である。知覚については、左半身の感覚鈍麻があり、特に左上肢の表在感覚と深部感覚の低下が顕著である。温冷覚も左半身で低下が認められている。
コミュニケーションについては、脳梗塞発症直後は失語症状が認められたが、現在は発語明瞭度3/5まで改善している。簡単な日常会話は可能で、質問への応答も概ね問題なく行えるが、複雑な内容を話す際は時間を要する。声量は十分で、表情も豊かである。理解力は保たれており、医療者の指示も適切に理解できている。
信仰は仏教であり、自宅には仏壇があり、毎朝神棚に向かって拝むことを日課としていた。入院中も枕元に小さな仏像を置き、心の安寧を得ている。
動作状況
入院前のA氏は自立歩行が可能で、1日4000歩程度の散歩を日課としていた。現在は左半身麻痺により、歩行は平行棒内での介助歩行を行っている段階である。移乗動作は看護師の見守りと軽介助を要し、特にポータブルトイレへの移乗時は安全確保のため介助を必要としている。
排尿・排便動作は左手の麻痺により下衣の上げ下ろしに介助を要する。入浴は週3回、シャワー浴を実施しているが、バランス低下のため看護師2名で介助を行っている。衣類の着脱は、上衣は前開きのものを使用し、麻痺側から着て健側から脱ぐよう指導されているが、ボタンの掛け外しには介助を要する。下衣の着脱は全介助を必要としている。
転倒歴については、入院前は特になく、入院後も病棟スタッフの見守りと介助により、現在まで転倒の既往はない。ベッド柵やナースコールを適切に使用し、安全な療養環境の確保に努めている。
内服中の薬
- アムロジピン5mg(降圧剤):1回1錠、1日1回、朝食後
- メトホルミン500mg(糖尿病薬):1回1錠、1日1回、朝食後
- クロピドグレル75mg(抗血小板薬):1回1錠、1日1回、朝食後
※内服管理は入院中は看護師が行っている。
検査データ
| 検査項目 | 基準値 | 入院時 | 入院7日目 |
|---|---|---|---|
| TP | 6.5-8.2g/dL | 5.8g/dL | 6.2g/dL |
| ALB | 3.8-5.2g/dL | 3.2g/dL | 3.4g/dL |
| BUN | 8-20mg/dL | 25mg/dL | 22mg/dL |
| Cr | 0.6-1.1mg/dL | 1.2mg/dL | 1.0mg/dL |
| Na | 135-145mEq/L | 140mEq/L | 138mEq/L |
| K | 3.5-5.0mEq/L | 4.2mEq/L | 4.0mEq/L |
| 血糖値 | 70-110mg/dL | 165mg/dL | 132mg/dL |
| HbA1c | 4.6-6.2% | 7.2% | 6.8% |
| WBC | 4,000-9,000/μL | 9,800/μL | 7,200/μL |
| RBC | 400-550万/μL | 420万/μL | 415万/μL |
| Hb | 13-17g/dL | 13.2g/dL | 13.0g/dL |
| PLT | 15-35万/μL | 22.5万/μL | 21.8万/μL |
| AST | 10-40U/L | 45U/L | 32U/L |
| ALT | 5-45U/L | 48U/L | 35U/L |
| CRP | 0.3mg/dL以下 | 2.8mg/dL | 0.8mg/dL |
今後の治療方針と医師の指示
現在、抗凝固療法(クロピドグレル75mg/日)を継続しながら、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による包括的なリハビリテーションを実施している。主な治療目標は、左半身の麻痺の改善、嚥下機能の回復、そして自宅退院に向けた日常生活動作の向上である。
病棟内のADLは看護師の見守りと介助のもと許可されており、平行棒内での歩行訓練も理学療法士の指導のもと実施可能である。食事は誤嚥予防のため、とろみ食とし、水分にはとろみ剤を使用する。摂取時は30度のギャッジアップが必要である。リハビリテーションは理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による介入を1~2回/日実施し、離床時間の拡大を図っている。
バイタルサインの測定は1日3回(朝・昼・夕)とし、血圧160/90mmHg以上、SpO2 95%以下での報告指示がある。頓用薬として、発熱時(38℃以上)にはカロナール(200)1錠、不眠時にはレンドルミン(0.25)1錠(深夜0時まで)、血圧180/100mmHg以上の場合はアダラートCR(10)1錠の使用が指示されている。検査は1週間毎の血液検査と週2回の朝食前血糖値測定を行う。
転倒・転落予防のため、ベッド柵3点使用とし、シャワー浴は看護師2名での介助により実施可能である。退院に向けて週1回の担当者カンファレンスを開催し、ケアマネージャーと連携しながら介護保険サービスの調整を進めている。また、基礎疾患である高血圧と糖尿病の管理を継続し、再発予防に努める方針である。
本人と家族の想いと言動
A氏は「こんな状態では家族に迷惑をかけるばかりだ」と自身の状態を気にかけており、特に夜間のトイレ介助を申し訳なく思っている。リハビリテーションには意欲的に取り組んでいるが、左半身の麻痺による動作制限に対するストレスを感じており、「早く家に帰って盆栽の世話がしたい」と自宅での生活への思いを語っている。
妻は「私たち家族がいるから心配しないで」と声をかけ、介護への参加意思を示しており、医療者の指導を熱心に聞き、介助方法の習得に意欲的である。長男家族も「父のことは家族で支えていきたい」と話すなど、家族全体でA氏の回復を支援する姿勢が見られている。
基本情報
A氏は85歳の男性で、身長165cm、体重58kgである。元高校数学教師であり、現在は退職している。温厚で几帳面な性格の持ち主である。82歳の妻と3世代同居しており、家族構成は妻のほか、45歳の長男、42歳の長男の妻、および中学生と小学生の孫2人との5人家族である。キーパーソンは妻であり、発症前から服薬管理を含めたA氏の健康管理に積極的に関わっている。感染症やアレルギーの既往はない。認知機能の評価では、脳梗塞発症後にMMSE 26点、HDS-R 25点であり、軽度の認知機能低下が認められている。主に見当識と記憶の項目で減点が見られるが、これは環境の変化や睡眠障害の影響も考えられる。時間の見当識は時折曖昧になることがあるが、人物の認識や場所の理解は保たれており、医療者の指示理解も良好である。
病名
右中大脳動脈領域の脳梗塞
既往歴と治療状況
A氏は高血圧を15年間罹患しており、アムロジピン5mg/日の内服により継続的に治療を受けている。また、10年前から糖尿病の診断を受けており、メトホルミン500mg/日を内服して血糖コントロールを行っている。いずれの疾患についても、妻が服薬管理を担当し、治療が継続されていた。
入院から現在までの情報
発症当日、A氏は庭の手入れをしている最中に突然の左半身の脱力感と言語障害を自覚した。家族により直ちに救急要請され、搬送時の意識レベルはJCS Ⅰ-2で、左上下肢の麻痺が顕著であった。救急搬送後のMRI検査により右中大脳動脈領域の脳梗塞と診断され、発症から2時間以内であったため、直ちに血栓溶解療法(rt-PA療法)が開始された。発症前は、趣味の盆栽の手入れと1日4000歩程度の散歩を日課とし、週に1回は地域の将棋サークルに参加するなど活動的な生活を送っていた。また、地域の学習支援ボランティアとしても活動していた。
入院後、rt-PA療法を実施した後、現在は抗凝固療法(クロピドグレル75mg/日)を継続している。言語機能は徐々に改善し、発語明瞭度は3/5まで回復したが、左半身の麻痺は残存しており、ブルンストロームテストでは上肢Ⅲ、手指Ⅲ、下肢Ⅳと評価されている。嚥下機能の低下(MWST:3点)により、現在はとろみ食を摂取している。排泄はポータブルトイレを使用しているが、移乗時には介助を要する。環境の変化による不眠を訴えることが多く、夜間の不穏も時折見られ、睡眠時間は4~5時間程度で断続的である。日中は1~2回/日の個別リハビリテーションを意欲的に実施している。現在のFIMは運動項目45点、認知項目25点である。
バイタルサイン
入院時のバイタルサインは血圧178/98mmHg、脈拍88回/分、体温36.8℃、SpO2 96%であった。現在(入院7日目)は血圧142/82mmHg、脈拍72回/分、体温36.7℃、SpO2 97%と安定している。
食事と嚥下状態
入院前はA氏は常食を自力で摂取し、食事量も良好であった。現在は嚥下機能の低下(MWST:3点)により、誤嚥予防のためとろみ食を摂取している。食事時は体幹を30度挙上し、頸部を軽度屈曲位にして、ゆっくりと摂取するよう促されている。水分摂取時はとろみ剤を使用し、現在の食事量は7~8割程度である。
喫煙の習慣は20歳から60歳までの間、1日20本程度あったが、定年退職を機に禁煙し、現在は喫煙していない。飲酒は機会飲酒程度であり、将棋サークル後の懇親会で缶ビール1本程度を飲む習慣があったが、入院後は禁酒している。
排泄
入院前のA氏は、トイレまで自力歩行し、排泄は完全に自立していた。現在は左半身麻痺により、ポータブルトイレを使用しているが、移乗時には介助を要する。排尿は日中6~7回、夜間2~3回程度であり、排便は1日1回の規則的な排泄パターンを維持している。下剤の使用は現在のところ必要としていない。
睡眠
入院前は21時から翌朝6時まで良眠でき、日中の活動も活発であった。現在は環境の変化による不眠を訴えることが多く、夜間の不穏も時折見られる。睡眠時間は4~5時間程度で断続的であり、特に夜間のトイレ介助の際に覚醒してしまうことが多い。眠剤等の使用については、本人と相談の上、現在は使用していない状況である。
視力・聴力・知覚・コミュニケーション・信仰
視力は軽度の老眼があり、新聞を読む際は老眼鏡を使用している。聴力は左右ともに会話に支障のない程度である。知覚については、左半身の感覚鈍麻があり、特に左上肢の表在感覚と深部感覚の低下が顕著である。温冷覚も左半身で低下が認められている。
コミュニケーションについては、脳梗塞発症直後は失語症状が認められたが、現在は発語明瞭度3/5まで改善している。簡単な日常会話は可能で、質問への応答も概ね問題なく行えるが、複雑な内容を話す際は時間を要する。声量は十分で、表情も豊かである。理解力は保たれており、医療者の指示も適切に理解できている。
信仰は仏教であり、自宅には仏壇があり、毎朝神棚に向かって拝むことを日課としていた。入院中も枕元に小さな仏像を置き、心の安寧を得ている。
動作状況
入院前のA氏は自立歩行が可能で、1日4000歩程度の散歩を日課としていた。現在は左半身麻痺により、歩行は平行棒内での介助歩行を行っている段階である。移乗動作は看護師の見守りと軽介助を要し、特にポータブルトイレへの移乗時は安全確保のため介助を必要としている。
排尿・排便動作は左手の麻痺により下衣の上げ下ろしに介助を要する。入浴は週3回、シャワー浴を実施しているが、バランス低下のため看護師2名で介助を行っている。衣類の着脱は、上衣は前開きのものを使用し、麻痺側から着て健側から脱ぐよう指導されているが、ボタンの掛け外しには介助を要する。下衣の着脱は全介助を必要としている。
転倒歴については、入院前は特になく、入院後も病棟スタッフの見守りと介助により、現在まで転倒の既往はない。ベッド柵やナースコールを適切に使用し、安全な療養環境の確保に努めている。
内服中の薬
- アムロジピン5mg(降圧剤):1回1錠、1日1回、朝食後
- メトホルミン500mg(糖尿病薬):1回1錠、1日1回、朝食後
- クロピドグレル75mg(抗血小板薬):1回1錠、1日1回、朝食後
※内服管理は入院中は看護師が行っている。
検査データ
| 検査項目 | 基準値 | 入院時 | 入院7日目 |
|---|---|---|---|
| TP | 6.5-8.2g/dL | 5.8g/dL | 6.2g/dL |
| ALB | 3.8-5.2g/dL | 3.2g/dL | 3.4g/dL |
| BUN | 8-20mg/dL | 25mg/dL | 22mg/dL |
| Cr | 0.6-1.1mg/dL | 1.2mg/dL | 1.0mg/dL |
| Na | 135-145mEq/L | 140mEq/L | 138mEq/L |
| K | 3.5-5.0mEq/L | 4.2mEq/L | 4.0mEq/L |
| 血糖値 | 70-110mg/dL | 165mg/dL | 132mg/dL |
| HbA1c | 4.6-6.2% | 7.2% | 6.8% |
| WBC | 4,000-9,000/μL | 9,800/μL | 7,200/μL |
| RBC | 400-550万/μL | 420万/μL | 415万/μL |
| Hb | 13-17g/dL | 13.2g/dL | 13.0g/dL |
| PLT | 15-35万/μL | 22.5万/μL | 21.8万/μL |
| AST | 10-40U/L | 45U/L | 32U/L |
| ALT | 5-45U/L | 48U/L | 35U/L |
| CRP | 0.3mg/dL以下 | 2.8mg/dL | 0.8mg/dL |
今後の治療方針と医師の指示
現在、抗凝固療法(クロピドグレル75mg/日)を継続しながら、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による包括的なリハビリテーションを実施している。主な治療目標は、左半身の麻痺の改善、嚥下機能の回復、そして自宅退院に向けた日常生活動作の向上である。
病棟内のADLは看護師の見守りと介助のもと許可されており、平行棒内での歩行訓練も理学療法士の指導のもと実施可能である。食事は誤嚥予防のため、とろみ食とし、水分にはとろみ剤を使用する。摂取時は30度のギャッジアップが必要である。リハビリテーションは理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による介入を1~2回/日実施し、離床時間の拡大を図っている。
バイタルサインの測定は1日3回(朝・昼・夕)とし、血圧160/90mmHg以上、SpO2 95%以下での報告指示がある。頓用薬として、発熱時(38℃以上)にはカロナール(200)1錠、不眠時にはレンドルミン(0.25)1錠(深夜0時まで)、血圧180/100mmHg以上の場合はアダラートCR(10)1錠の使用が指示されている。検査は1週間毎の血液検査と週2回の朝食前血糖値測定を行う。
転倒・転落予防のため、ベッド柵3点使用とし、シャワー浴は看護師2名での介助により実施可能である。退院に向けて週1回の担当者カンファレンスを開催し、ケアマネージャーと連携しながら介護保険サービスの調整を進めている。また、基礎疾患である高血圧と糖尿病の管理を継続し、再発予防に努める方針である。
本人と家族の想いと言動
A氏は「こんな状態では家族に迷惑をかけるばかりだ」と自身の状態を気にかけており、特に夜間のトイレ介助を申し訳なく思っている。リハビリテーションには意欲的に取り組んでいるが、左半身の麻痺による動作制限に対するストレスを感じており、「早く家に帰って盆栽の世話がしたい」と自宅での生活への思いを語っている。
妻は「私たち家族がいるから心配しないで」と声をかけ、介護への参加意思を示しており、医療者の指導を熱心に聞き、介助方法の習得に意欲的である。長男家族も「父のことは家族で支えていきたい」と話すなど、家族全体でA氏の回復を支援する姿勢が見られている。
ゴードン11項目のアセスメント解説
1. 健康知覚-健康管理パターンのポイント
このパターンでは、A氏とその家族が脳梗塞という疾患をどのように理解し、受け止めているか、また発症前の健康管理行動がどうであったかを評価します。特に85歳という高齢者の急性期疾患に対する認識と、今後の健康管理への意欲や能力を見極めることが重要です。
どんなことを書けばよいか
健康知覚-健康管理パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 疾患についての本人・家族の理解度(病態、治療、予後など)
- 疾患や治療に対する受け止め方、受容の程度
- 現在の健康状態や症状の認識
- これまでの健康管理行動(受診行動、服薬管理、生活習慣など)
- 疾患が日常生活に与えている影響の認識
- 健康リスク因子(喫煙、飲酒、アレルギー、既往歴など)
発症前の健康管理行動
A氏は高血圧15年、糖尿病10年という長期にわたる慢性疾患を抱えており、妻が服薬管理を担当して継続的な治療を受けていました。この点は、家族による健康管理体制が確立されていたことを示しており、退院後の療養生活を考える上で重要な強みとなります。また、喫煙については定年退職を機に禁煙しており、健康意識に基づいた行動変容ができていた点も評価できます。これらの情報を踏まえて、発症前の健康管理能力と家族のサポート体制について記述するとよいでしょう。
疾患と症状の認識
A氏は「こんな状態では家族に迷惑をかけるばかりだ」と述べており、自身の状態を認識していることがうかがえます。特に夜間のトイレ介助を申し訳なく思っているという発言からは、麻痺による生活動作の制限を自覚し、それが家族の負担になっているという認識があることがわかります。この認識は、疾患による機能障害を受け止めつつある過程と捉えることができ、リハビリテーションへの意欲にもつながっていると考えられます。一方で、「早く家に帰って盆栽の世話がしたい」という発言からは、回復への希望と具体的な目標を持っていることも読み取れます。これらの言動から、A氏の疾患受容の段階や心理状態をアセスメントすることが大切です。
健康リスク因子の評価
既往歴として高血圧と糖尿病があり、これらは脳梗塞の重要な危険因子です。特に高血圧は15年間という長期にわたって心血管系に負担をかけており、糖尿病も10年の罹患期間があることから、血管障害のリスクが高い状態であったことを考慮する必要があります。喫煙歴については20歳から60歳まで1日20本程度と長期間ありましたが、25年前に禁煙しているため、現在の直接的なリスクとしては軽減されていると考えられます。飲酒は機会飲酒程度で缶ビール1本程度と節度ある範囲内でした。検査データでは入院時にBUN 25mg/dl、Cr 1.2mg/dl、血糖値165mg/dl、HbA1c 7.2%と、腎機能や血糖コントロールに課題があったことが示されています。これらのリスク因子を踏まえて、再発予防のための健康管理の重要性を記述するとよいでしょう。
家族の健康管理能力
妻がキーパーソンとして発症前から服薬管理を含めた健康管理に積極的に関わっており、入院後も「私たち家族がいるから心配しないで」と声をかけ、医療者の指導を熱心に聞いて介助方法の習得に意欲的です。長男家族も「父のことは家族で支えていきたい」と話しており、家族全体でA氏の回復を支援する姿勢が見られます。この家族の健康管理能力の高さと支援意欲は、退院後の療養生活において非常に重要な資源となることを意識して記述することが大切です。
アセスメントの視点
A氏の健康知覚-健康管理パターンを評価する際は、発症前の良好な健康管理体制と家族のサポート、現在の疾患認識と受容の過程、そして複数の健康リスク因子という多角的な視点から捉えることが重要です。特に、A氏の「家族に迷惑をかけている」という思いと「家に帰りたい」という希望のバランスをどう支援していくか、また家族の介護意欲を維持しながら適切な健康管理を継続していくための支援をどう展開するかを考える必要があります。
ケアの方向性
疾患と治療についての理解を深めるための教育的支援、再発予防のための生活習慣の見直し(特に基礎疾患の管理)、家族を含めた退院指導の実施、そしてA氏の心理的負担を軽減しながら回復への意欲を支えていく関わりが必要です。家族の健康管理能力を活かしながら、過度な負担にならないよう社会資源の活用も視野に入れた支援を考えるとよいでしょう。
2. 栄養-代謝パターンのポイント
このパターンでは、脳梗塞による嚥下機能の低下がA氏の栄養摂取にどのような影響を与えているか、また現在の栄養状態と代謝機能を評価します。高齢者の急性期における栄養管理は、回復力や合併症予防に直結する重要な要素です。
どんなことを書けばよいか
栄養-代謝パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 食事と水分の摂取量と摂取方法
- 食欲、嗜好、食事に関するアレルギー
- 身長・体重・BMI・必要栄養量・身体活動レベル
- 嚥下機能・口腔内の状態
- 嘔吐・吐気の有無
- 皮膚の状態、褥瘡の有無
- 栄養状態を示す血液データ(Alb、TP、RBC、Ht、Hb、Na、K、TG、TC、HbA1c、BSなど)
嚥下機能と食事形態
A氏は脳梗塞により嚥下機能が低下しており、MWST:3点という評価結果から誤嚥のリスクが高い状態にあることがわかります。そのため現在はとろみ食を摂取し、水分摂取時にはとろみ剤を使用しています。食事時は体幹を30度挙上し、頸部を軽度屈曲位にしてゆっくりと摂取するよう促されており、誤嚥性肺炎予防のための適切なポジショニングが行われています。現在の食事量は7~8割程度であり、発症前は常食を自力で摂取し食事量も良好であったことと比較すると、やや減少していることに着目する必要があります。この食事量の減少が、嚥下機能低下による食べにくさからくるものなのか、環境の変化や心理的要因が影響しているのかを考察することが重要です。
体格と栄養必要量
身長165cm、体重58kgであり、BMIを計算すると約21.3となります。85歳の高齢者としては標準的な範囲内ですが、入院前後での体重変化の情報があればさらに詳細な評価ができるでしょう。高齢者は予備能力が低いため、わずかな体重減少でも栄養状態の悪化につながりやすいことを意識する必要があります。また、現在はリハビリテーションを1~2回/日実施しており、身体活動レベルがやや高まっていることから、十分なエネルギー摂取が回復のために必要であることを考慮するとよいでしょう。
栄養状態を示す検査データ
入院時のTP 5.8g/dl、ALB 3.2g/dlは基準値を下回っており、低栄養状態であったことを示しています。入院7日目にはTP 6.2g/dl、ALB 3.4g/dlと改善傾向にありますが、依然として基準値には達していません。この低栄養状態は、急性期の治療やリハビリテーションの効果に影響を与える可能性があり、創傷治癒や感染抵抗力、筋力の回復にも関わってきます。また、Hbは13.2→13.0g/dlと基準値内ではあるものの軽度低下しており、貧血傾向がないか注意が必要です。血糖値は165→132mg/dl、HbA1c 7.2→6.8%と改善傾向にありますが、糖尿病の既往があることを踏まえ、適切な血糖コントロールを継続していく必要があります。
水分・電解質バランス
Naは140→138mEq/L、Kは4.2→4.0mEq/Lと基準値内で推移しています。水分摂取はとろみ剤を使用しながら行っており、脱水のリスクと誤嚥のリスクのバランスを取りながら管理されていることがわかります。高齢者は口渇感が鈍くなっているため、意識的な水分摂取を促す必要があることを考慮するとよいでしょう。
代謝機能と合併症リスク
肝機能を示すAST 45→32U/L、ALT 48→35U/Lは入院時にやや高値でしたが改善傾向にあります。これは急性期のストレスや治療による一時的な上昇と考えられますが、継続的なモニタリングが必要です。CRPは2.8→0.8mg/dlと炎症反応が改善していますが、依然として基準値を上回っており、身体にストレスがかかっている状態が続いていることを意識して記述するとよいでしょう。
アセスメントの視点
A氏の栄養-代謝パターンを評価する際は、嚥下機能低下による誤嚥リスクと栄養摂取量のバランス、低栄養状態の改善の必要性、糖尿病管理の継続という複数の課題を統合的に捉えることが重要です。現在の食事量7~8割という状態が、回復に必要な栄養量を満たしているかどうかを判断し、必要に応じて栄養補助の方法を検討する視点も必要でしょう。
ケアの方向性
安全な食事摂取のための嚥下訓練と適切なポジショニングの継続、栄養状態の改善を目指した食事量の確保、糖尿病管理を考慮した食事内容の調整、そして誤嚥性肺炎予防のための口腔ケアの徹底が必要です。また、言語聴覚士と連携しながら嚥下機能の回復を促し、段階的に食事形態を上げていくことも視野に入れるとよいでしょう。家族への退院後の食事指導も重要な支援となります。
3. 排泄パターンのポイント
このパターンでは、脳梗塞による左半身麻痺がA氏の排泄行動にどのような影響を与えているか、また腎機能を含めた排泄機能全体を評価します。排泄の自立度は患者の尊厳やQOLに直結する重要な要素です。
どんなことを書けばよいか
排泄パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 排便と排尿の回数・量・性状
- 下剤やカテーテル使用の有無
- In-Outバランス
- 排泄に関連した食事・水分摂取状況
- 安静度、活動量
- 腹部の状態(腹部膨満、腸蠕動音など)
- 腎機能を示す血液データ(BUN、Cr、GFRなど)
排泄パターンと自立度
入院前のA氏はトイレまで自力歩行し、排泄は完全に自立していました。現在は左半身麻痺によりポータブルトイレを使用していますが、移乗時には介助を要する状態です。排尿は日中6~7回、夜間2~3回程度、排便は1日1回と規則的な排泄パターンを維持しています。この規則的なパターンは、A氏の身体機能が一定のリズムを保っていることを示しており、排泄ケアの計画を立てやすい点として評価できます。特に排便が1日1回規則的であることは、腸蠕動が保たれており、現在のところ下剤の使用を必要としていないという点で重要です。これは食事や水分摂取、活動量が適切に保たれていることの表れとも考えられます。
移乗動作と介助の必要性
左半身麻痺により、ポータブルトイレへの移乗時に介助を要し、左手の麻痺により下衣の上げ下ろしにも介助が必要です。A氏は「夜間のトイレ介助を申し訳なく思っている」と述べており、排泄における依存状態が心理的負担となっていることがわかります。夜間2~3回の排尿があり、その都度覚醒してしまうことが不眠の一因にもなっています。この点は、排泄パターンと睡眠-休息パターンの相互関係として捉える必要があります。移乗動作は看護師の見守りと軽介助を要しますが、ブルンストロームテストで下肢がⅣと評価されていることから、リハビリテーションの進展により自立度が向上する可能性があることを考慮するとよいでしょう。
続きはnoteで公開中です✨️
ゴードンの続きとヘンダーソン・関連図・看護計画について解説しています😊
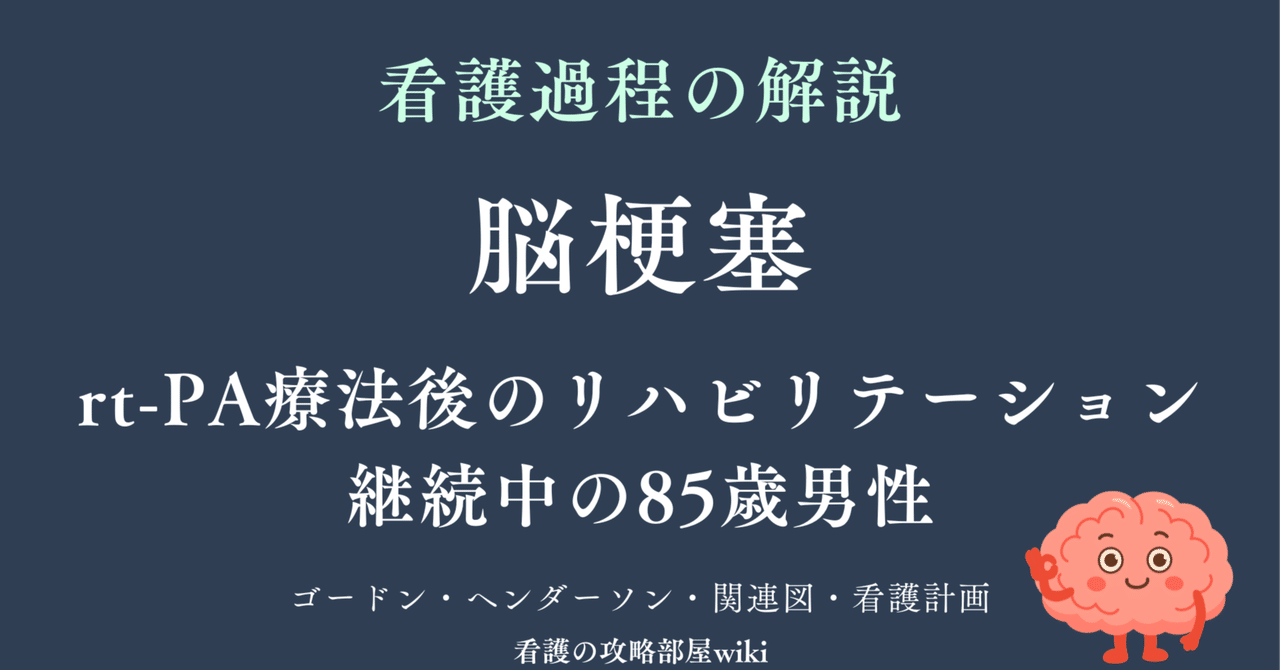
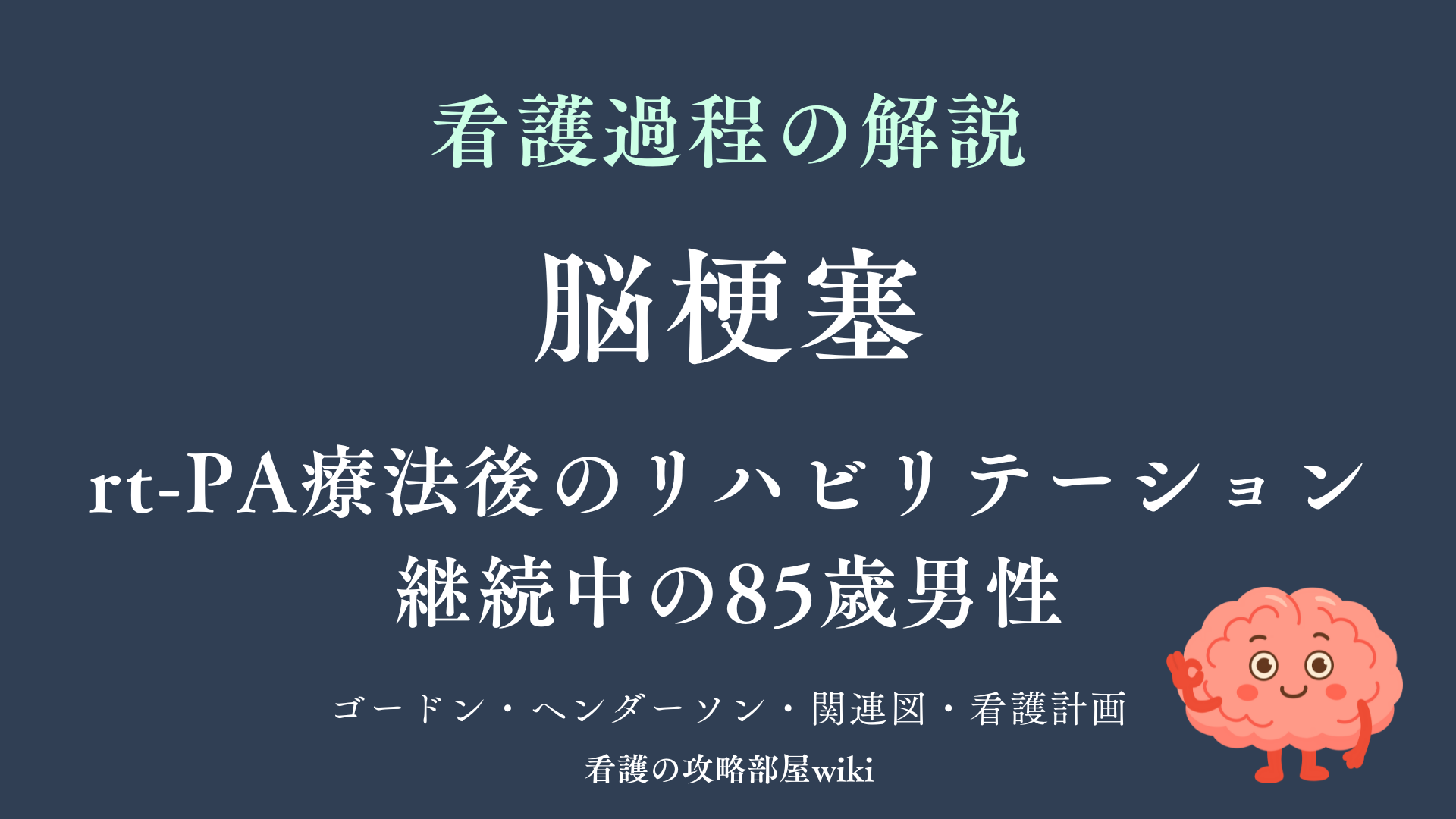


コメント