基本情報
A氏は78歳の男性であり、身長165cm、入院前の体重は62kgであったが、入院後は58kgまで減少している。都内の持ち家で妻(75歳)と2人暮らしをしており、キーパーソンは月1回訪問する長男(50歳)である。次男(47歳)は大阪に在住しており、2ヶ月に1回の頻度で帰省している。職業は大手電機メーカーで40年間製造ラインの管理職として勤務し、65歳で定年退職している。性格は几帳面で社交的であるが自己主張は控えめであり、体調不良時でも周囲に相談せず無理をする傾向がみられる。薬剤および食物アレルギーはない。認知機能は年相応であり、MMSEは27点である。
病名
誤嚥性肺炎
既往歴と治療状況
A氏は高血圧症でアムロジピン5mgを1日1回内服管理している。また胃潰瘍の予防としてラベプラゾール10mgを1日1回内服している。入院前は自己管理により確実に内服できていた。
入院から現在までの情報
20XX年1月21日頃から食事でのむせが増加し、23日夜から微熱が出現した。24日夜間に39.2℃の発熱と呼吸困難を認め救急搬送された。救急外来での胸部X線・CTで両肺下葉に浸潤影を認め、血液検査でCRP 15.2mg/dL、WBC 12800/μLと炎症反応の著明な上昇を認めたため、誤嚥性肺炎の診断で即日入院となった。
入院後、ABPC/SBTによる抗生剤治療を開始した。第2病日の嚥下評価で重度の嚥下機能低下を認めたため、経鼻経管栄養(1500ml/日)を開始した。第3病日には解熱傾向となったが、第4病日夜間から「仕事に行かなければ」「会社の資料を作らないと」などの発言を伴うせん妄を発症し、ハロペリドール0.75mgの投与を開始した。
現在の第5病日では、呼吸状態は改善傾向にあり、炎症反応も低下傾向(WBC 9200/μL、CRP 8.4mg/dL)を示している。一方でせん妄による夜間不穏が継続しており、日中も傾眠傾向がみられるが、声かけにより覚醒し会話可能である。嚥下訓練を実施しており、リハビリテーション開始を予定している。
バイタルサイン
来院時は体温39.2℃、脈拍98回/分・整、血圧146/88mmHg、呼吸数24回/分、SpO₂ 92%(室内気)、意識レベルJCS I-1であった。
現在(第5病日)は体温36.8℃、脈拍82回/分・整、血圧132/78mmHg、呼吸数18回/分、SpO₂ 97%(酸素1L/分投与下)であり、日中の意識レベルはJCS I-1である。ただし夜間はせん妄の影響で見当識障害がみられる。
食事と嚥下状態
入院前、A氏の食事は3食とも妻の手作りを自力摂取していた。半年前から咀嚼力の低下があり、食事時間が延長していた。水分摂取は1日1000ml程度で緑茶を好んで飲用していた。軽度の嚥下機能低下があり、月1~2回程度のむせこみがあったが、医療機関は未受診であった。喫煙歴は1日20本を40年間継続していたが55歳で禁煙した。飲酒は週1~2回の地域の友人との集まり時のみでビール350ml程度の機会飲酒である。
現在、嚥下機能の重度低下により経鼻経管栄養(1500ml/日)を実施中である。嚥下訓練を開始している段階であり、経管栄養の継続と並行しながら機能改善に応じた経口摂取への移行を検討する予定である。
排泄
入院前は自立しており、排尿・排便ともに問題なく、下剤の使用歴はなかった。
現在、尿意・便意は維持されている。せん妄による不穏時は看護師の誘導を要するが、日中はポータブルトイレを自力で使用可能である。排尿回数は6~7回/日で黄色透明であり、排便は2日に1回程度で普通便である。下剤の使用はない。
睡眠
入門前は21時就寝、6時起床と規則正しい生活リズムを維持しており、睡眠導入剤等の使用はなかった。
現在、第4病日夜間からのせん妄により、夜間不眠と不穏状態が出現している。日中も傾眠傾向がみられるが、声かけにより覚醒し会話可能である。生活リズムの調整と昼間の覚醒を促す取り組みが実施されている。
視力・聴力・知覚・コミュニケーション・信仰
視力は軽度の老眼があり、読書時には老眼鏡を使用している。聴力は日常会話に支障がない。四肢の感覚障害はみられない。
コミュニケーション能力について、日中は意識清明で医療者に対して礼儀正しく穏やかな態度で接しているが、夜間はせん妄により見当識障害がみられ、仕事に関連した発言が続く。信仰は特にない。
動作状況
入院前、A氏の日常生活動作は概ね自立していた。毎朝、近所の公園まで30分程度の散歩を日課としており、歩行は安定していた。移乗、排泄、入浴、衣類の着脱もすべて自立していた。転倒歴はなかった。
現在、日中はベッド上での座位保持が可能で、看護師見守りのもとポータブルトイレへの移乗が可能である。歩行は未実施であり、衣類の着脱は声かけと一部介助を要する。清拭対応中である。夜間はせん妄による不穏時に転倒リスクが高く、ベッド柵を使用し、頻回な観察が実施されている。現時点での転倒歴はない。
内服中の薬
- アムロジピン 5mg 1日1回 朝食後(高血圧症)
- ラベプラゾール 10mg 1日1回 朝食前(胃潰瘍予防)
- ハロペリドール 0.75mg 不穏時(せん妄に対して)
入院後は看護師管理とし、経鼻経管栄養チューブより投与している。アムロジピン、ラベプラゾールは粉砕して投与し、ハロペリドールは不穏時に看護師が投与を判断している。
検査データ
| 検査項目 | 基準値 | 入院時(1/24) | 現在(1/28) |
|---|---|---|---|
| WBC | 4000~8000/μL | 12800 | 9200 |
| RBC | 410~530万/μL | 432 | 428 |
| Hb | 13.0~16.5g/dL | 13.2 | 12.8 |
| Ht | 40~50% | 39.8 | 38.6 |
| Plt | 15~35万/μL | 22.4 | 21.8 |
| CRP | 0~0.3mg/dL | 15.2 | 8.4 |
| TP | 6.7~8.3g/dL | 6.8 | 6.6 |
| Alb | 3.8~5.2g/dL | 3.6 | 3.4 |
| AST | 10~40U/L | 28 | 25 |
| ALT | 5~45U/L | 32 | 30 |
| BUN | 8~20mg/dL | 18.2 | 17.8 |
| Cr | 0.6~1.1mg/dL | 0.9 | 0.8 |
| Na | 135~145mEq/L | 138 | 140 |
| K | 3.5~5.0mEq/L | 4.2 | 4.0 |
| Cl | 98~108mEq/L | 102 | 103 |
| BS | 70~110mg/dL | 126 | 108 |
入院時と比較して、WBC、CRP、血糖値は低下傾向を示しており、炎症反応の改善が認められる。一方、アルブミン値の低下が続いており、栄養状態の改善が課題である。
今後の治療方針と医師の指示
現在の誤嚥性肺炎に対して、抗生剤(ABPC/SBT)による治療を継続する。炎症反応の推移を確認するため3日ごとの採血検査を実施し、SpO₂が95%以上維持できれば酸素投与量を漸減していく方針である。
嚥下機能の改善に向けては、言語聴覚士による評価と訓練を毎日実施し、経鼻経管栄養(1500ml/日)を継続しながら、機能改善に応じて経口摂取を検討する。必要に応じて嚥下造影検査(VF)も予定している。
呼吸状態の改善に伴い、理学療法士による呼吸リハビリテーションと運動機能維持のためのリハビリテーションを開始する。状態をみながら段階的な離床を進め、作業療法士による日常生活動作訓練も実施予定である。
せん妄に対しては、ハロペリドール0.75mgを不穏時に使用し、日中の覚醒を促して夜間の良眠が得られるよう生活リズムを整えていく。バイタルサインは1日2回観察する。転倒予防のための環境整備と観察も継続する。
予定されている長男との家族カンファレンスにて、今後の治療方針と退院後の生活について検討する予定である。なお、これらの治療方針は患者の状態に応じて適宜見直しを行う方針である。
本人と家族の想いと言動
A氏は入院当初「管を入れるのは嫌だが、早く良くなりたい」と治療に協力的であった。しかし現在はせん妄により「仕事に行かなければ」などの発言が続いている。入院前から「息子たちは忙しいから、あまり頼りたくない」と周囲への遠慮がみられ、体調不良時でも相談せずに我慢する傾向が根強い。
妻は毎日面会に訪れ「早く家に帰れるように頑張ってね」と声をかけているが、せん妄症状に対して「主人らしくない。早く元気になってほしい」と不安を表出している。
長男は仕事の都合をつけて来院予定であり、次男も電話で状況を確認するなど関心を寄せている。両親の今後の生活支援について、家族での話し合いを希望している。
ゴードン11項目アセスメント解説
1. 健康知覚-健康管理パターンのポイント
健康知覚-健康管理パターンでは、A氏が自身の健康状態や疾患をどのように認識し、これまでどのような健康管理行動をとってきたかを評価します。特に、誤嚥性肺炎という急性疾患の発症に至った経緯と、その背景にある健康管理の課題を捉えることが重要です。
どんなことを書けばよいか
健康知覚-健康管理パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 疾患についての本人・家族の理解度(病態、治療、予後など)
- 疾患や治療に対する受け止め方、受容の程度
- 現在の健康状態や症状の認識
- これまでの健康管理行動(受診行動、服薬管理、生活習慣など)
- 疾患が日常生活に与えている影響の認識
- 健康リスク因子(喫煙、飲酒、アレルギー、既往歴など)
入院前の健康管理行動と疾患認識
A氏は高血圧症に対してアムロジピン5mg、胃潰瘍予防としてラベプラゾール10mgを自己管理により確実に内服できていました。この点は、処方された薬剤については責任をもって管理できる能力があることを示しており、基本的な健康管理能力は備わっていると考えられます。一方で、半年前から咀嚼力の低下があり食事時間が延長していたこと、軽度の嚥下機能低下により月1~2回程度のむせこみがあったにもかかわらず医療機関を未受診であった点に着目する必要があります。A氏の性格として「几帳面で社交的であるが自己主張は控えめであり、体調不良時でも周囲に相談せず無理をする傾向がみられる」という記載があり、これが早期受診行動を妨げた可能性を考慮するとよいでしょう。
症状出現時の対応と受診行動
1月21日頃から食事でのむせが増加し、23日夜から微熱が出現していたにもかかわらず、救急搬送されたのは24日夜間に39.2℃の発熱と呼吸困難を認めてからでした。この経過から、A氏が症状の重大性を十分に認識できていなかった可能性、あるいは認識していても「息子たちは忙しいから、あまり頼りたくない」という思いから家族への相談や受診を躊躇していた可能性を考える必要があります。体調不良時でも周囲に相談せず我慢する傾向が、症状悪化と救急搬送という結果につながったという視点でアセスメントすることが重要です。
疾患と治療に対する受け止め方
A氏は入院当初「管を入れるのは嫌だが、早く良くなりたい」と発言しており、経鼻経管栄養という侵襲的な処置に対する抵抗感を示しながらも治療に協力的な姿勢がみられます。この発言から、A氏は治療の必要性を理解し受容しようとしている一方で、身体的・心理的な負担を感じていることが読み取れます。現在はせん妄により「仕事に行かなければ」などの発言が続いており、現在の状況を正確に認識できていない状態にあることを踏まえてアセスメントする必要があります。
健康リスク因子の評価
喫煙歴として1日20本を40年間継続し55歳で禁煙したという情報は、BI(Brinkman Index)が800という重度喫煙歴を示しています。これは誤嚥性肺炎のリスク因子であり、呼吸器系への長期的な影響を考慮する必要があります。また、高血圧症の既往があり長期間の内服管理を継続していること、胃潰瘍の予防内服をしていることから、複数の慢性疾患を抱えながら生活してきた背景を理解することが大切です。飲酒は週1~2回でビール350ml程度の機会飲酒であり、現時点での健康リスクとしては低いと考えられます。
家族の健康管理への関与
妻が毎日面会に訪れており「早く家に帰れるように頑張ってね」と声をかけていること、長男が仕事の都合をつけて来院予定であること、次男も電話で状況を確認していることから、家族のサポート体制は良好であると考えられます。しかし、A氏が「息子たちは忙しいから、あまり頼りたくない」と周囲への遠慮を示している点は、今後の在宅療養における健康管理や症状出現時の対応を考える上で重要な情報となります。
アセスメントの視点
A氏の健康知覚-健康管理パターンをアセスメントする際は、基本的な服薬管理能力は保たれている一方で、自覚症状があっても医療機関を受診しない傾向、周囲に相談せず我慢する性格特性が、疾患の重症化を招いた可能性を考慮することが重要です。また、現在はせん妄により現状認識が困難な状態にあることから、せん妄改善後に改めて疾患や治療についての理解度を確認する必要があります。家族の関心は高いものの、A氏自身が家族への遠慮から支援を求めにくい傾向がある点も、退院後の健康管理を考える上で重要な課題となります。
ケアの方向性
せん妄が改善した段階で、A氏が誤嚥性肺炎の病態、嚥下機能低下のリスク、今後の予防策について正しく理解できるよう支援することが必要です。また、症状出現時に早期に相談・受診する重要性を理解してもらうとともに、家族への遠慮から我慢してしまう傾向に対しては、家族も含めた話し合いの場を設け、支援を求めることの大切さを伝えていく必要があります。妻や息子たちも、A氏の性格特性を理解した上で、日常的な健康状態の観察や変化への気づきを共有できる体制を整えることが重要です。
2. 栄養-代謝パターンのポイント
栄養-代謝パターンでは、A氏の栄養摂取状況と代謝機能を評価します。誤嚥性肺炎により経口摂取が困難となり、経鼻経管栄養に移行している現状と、入院後の体重減少、栄養状態の変化を捉えることが重要です。
どんなことを書けばよいか
栄養-代謝パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 食事と水分の摂取量と摂取方法
- 食欲、嗜好、食事に関するアレルギー
- 身長・体重・BMI・必要栄養量・身体活動レベル
- 嚥下機能・口腔内の状態
- 嘔吐・吐気の有無
- 皮膚の状態、褥瘡の有無
- 栄養状態を示す血液データ(Alb、TP、RBC、Ht、Hb、Na、K、TG、TC、HbA1c、BSなど)
入院前の栄養摂取状況
A氏は入院前、3食とも妻の手作りを自力摂取していました。この点は、家庭内で適切な食事環境が整っていたこと、妻が食事準備を担っていたことを示しています。一方で、半年前から咀嚼力の低下があり食事時間が延長していたという情報に着目する必要があります。咀嚼力の低下は食事摂取量の減少や栄養バランスの偏りにつながる可能性があり、この時点で食事形態の調整や歯科受診などの対応が必要であった可能性を考えるとよいでしょう。水分摂取は1日1000ml程度で緑茶を好んで飲用していたとのことですが、高齢者の推奨水分摂取量を考慮すると、やや少ない可能性もあります。
体重変化と栄養状態の評価
A氏の身長は165cm、入院前の体重は62kgでしたが、入院後は58kgまで減少しています。BMIを計算すると、入院前が22.0、現在が21.3となり、標準的な範囲内ではありますが、短期間での4kgの体重減少は栄養状態の悪化を示唆しています。第5病日という短期間での体重減少には、発熱や炎症による異化亢進、絶食期間、脱水などが関与していると考えられます。血液データでは、アルブミン値が入院時3.6g/dLから現在3.4g/dLへと低下傾向を示しており、総蛋白も6.8g/dLから6.6g/dLへと低下しています。アルブミン値3.4g/dLは基準値3.8-5.2g/dLを下回っており、低栄養状態にあることを示しています。この点を踏まえて、栄養状態の改善が重要な課題であることをアセスメントに含めるとよいでしょう。
嚥下機能の重度低下と経管栄養
第2病日の嚥下評価で重度の嚥下機能低下を認め、経鼻経管栄養1500ml/日を開始しています。入院前から軽度の嚥下機能低下があり月1~2回程度のむせこみがみられていたことから、もともと嚥下機能の低下傾向があったところに、誤嚥性肺炎による全身状態の悪化が加わり、嚥下機能がさらに低下したと考えられます。現在、嚥下訓練を開始している段階であり、経管栄養の継続と並行しながら機能改善に応じた経口摂取への移行を検討する予定となっています。嚥下機能の回復状況、嚥下訓練の進捗、経口摂取再開の可能性について、継続的に評価していく必要があります。
炎症と代謝への影響
入院時のCRPは15.2mg/dL、WBCは12800/μLと著明な炎症反応の上昇を認めており、現在は改善傾向(CRP 8.4mg/dL、WBC 9200/μL)にありますが、依然として高値が続いています。炎症反応の持続は異化亢進を引き起こし、体蛋白の分解が進むため、栄養状態の悪化につながります。血糖値は入院時126mg/dLから現在108mg/dLへと改善傾向を示していますが、ストレスや炎症による血糖上昇の可能性も考慮する必要があります。電解質バランスは概ね正常範囲内に保たれていますが、経管栄養による栄養管理が適切に行われているか、継続的にモニタリングすることが重要です。
皮膚の状態と褥瘡リスク
事例には皮膚の状態について詳細な記載がありませんが、A氏は現在、日中はベッド上での座位保持が可能で、ポータブルトイレへの移乗が可能である一方、夜間はせん妄による不穏時に転倒リスクが高くベッド柵を使用し頻回な観察が実施されています。活動量の低下、栄養状態の低下、アルブミン値の低下は褥瘡リスクを高める要因となるため、皮膚の観察と予防的ケアが必要です。特に仙骨部や踵部など圧迫を受けやすい部位の皮膚状態を注意深く観察することが重要です。
アセスメントの視点
A氏の栄養-代謝パターンをアセスメントする際は、入院前から咀嚼力の低下や嚥下機能の低下があったこと、誤嚥性肺炎により嚥下機能がさらに悪化し経口摂取が困難となったこと、短期間で4kgの体重減少とアルブミン値の低下がみられることから、栄養状態の改善が急務であることを明確にすることが重要です。現在、経鼻経管栄養1500ml/日で栄養投与されていますが、この量が必要栄養量を満たしているか、水分バランスは適切か、電解質異常はないかを継続的に評価する必要があります。また、嚥下訓練の進捗に応じて経口摂取再開の可能性を見据え、食事形態や栄養補給方法についても検討していく視点が大切です。
ケアの方向性
経鼻経管栄養による適切な栄養管理を継続し、アルブミン値や体重の推移をモニタリングしながら栄養状態の改善を図る必要があります。嚥下訓練を継続的に実施し、嚥下機能の回復状況を評価しながら、段階的な経口摂取再開を目指すことが重要です。経口摂取再開時には、嚥下機能に応じた適切な食事形態(とろみ調整、軟菜食など)を選択し、安全に摂取できるよう支援することが必要です。また、退院後の食生活について、妻を含めた栄養指導を行い、嚥下機能に配慮した食事準備の方法や、咀嚼力低下に対応した食材選択などについて具体的に指導していくことが大切です。
続きはnoteで公開中です✨️
ゴードンの続きとヘンダーソン・関連図・看護計画について解説しています😊
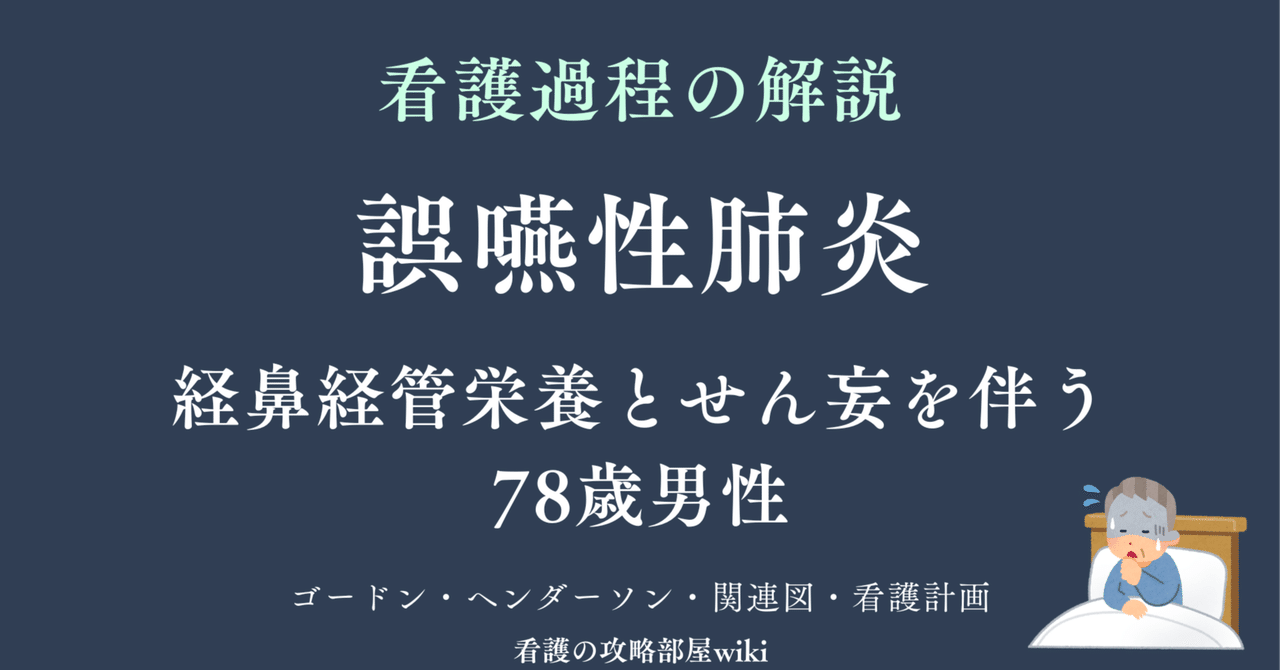
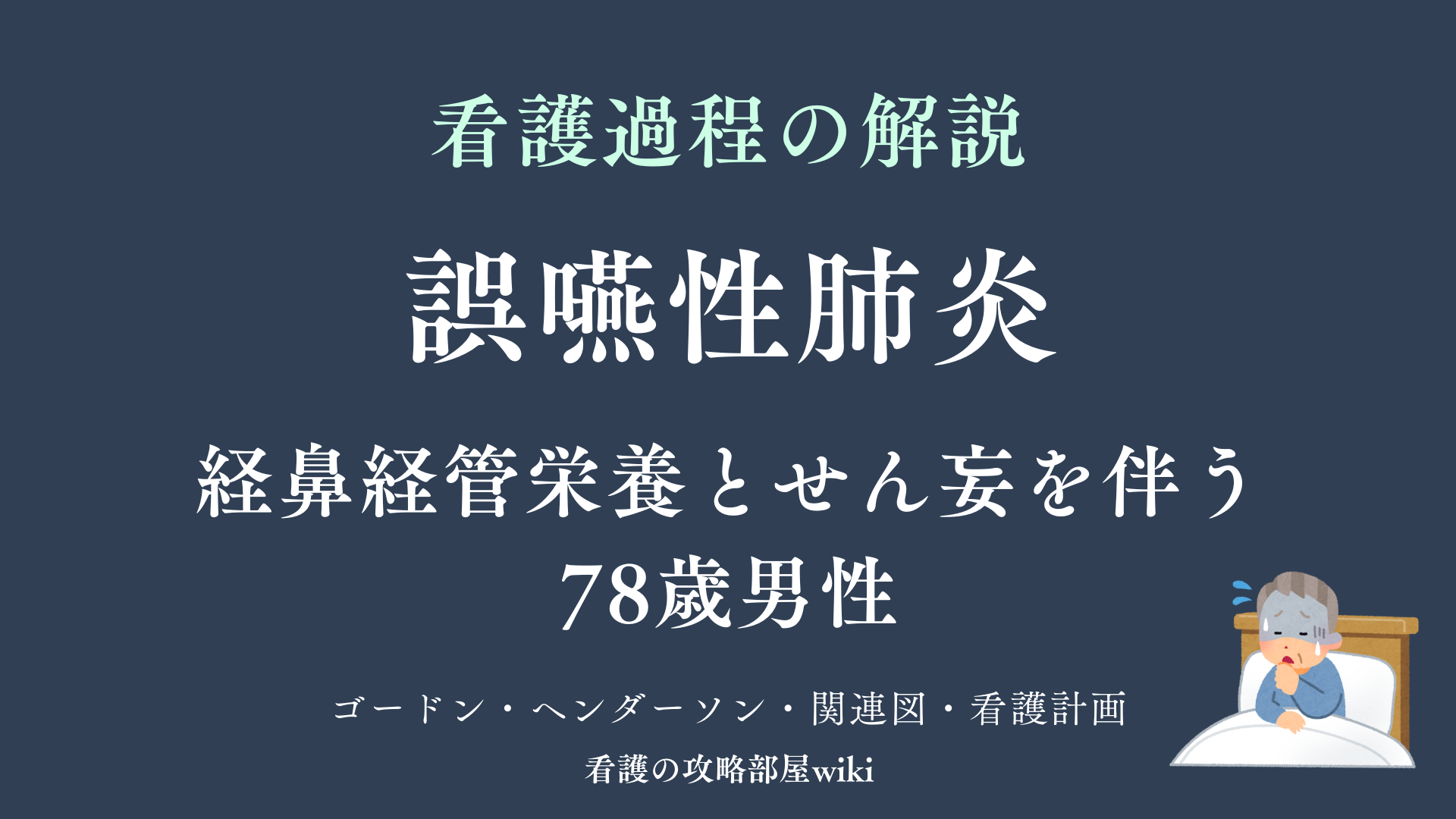


コメント