本記事では、看護師の思考プロセスを詳しく解説します。
実際の臨床では患者さんごとに状況が異なりますが、「わたしならどう考えるか」を具体的に示すことで、あなた自身の考える力を育てることを目指します。
この記事を参考に思考プロセスを学び、看護過程が得意になってもらえたら嬉しいです。
それでは、見ていきましょう。
看護学習や実習に役立つブログも運営しています✨️
ぜひ参考にしてみてくださいね!
https://kango-kouryaku.com/
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。事例は完全なフィクションであり、個別の診断・治療の根拠ではありません。実際の看護実践は患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください。本記事をそのまま課題として提出しないでください。内容の完全性・正確性は保証できず、本記事の利用により生じた損害について一切の責任を負いません。
基本情報
A氏は93歳の女性で、身長152cm、体重34kgである。家族構成は次女夫婦と曾孫1人の3人家族で、キーパーソンは次女である。A氏は元和裁師で、真面目で我慢強い性格である。感染症はなく、食物アレルギーも特記すべきものはない。認知力は軽度低下しており、MMSE 22点、HDS-R 20点で、日常会話は可能であるが短期記憶の低下が見られる。
病名
肺腺癌(右上葉)StageⅣ、脳転移、骨転移(胸椎・腰椎)
既往歴と治療状況
既往歴として、68歳時に高血圧症、75歳時に脂質異常症を指摘され内服治療を継続してきた。82歳時に変形性膝関節症で保存的治療を受けている。現在の肺癌は10か月前に診断され、高齢であることと本人の希望により化学療法は施行せず、当初から緩和ケアを中心とした治療方針となった。5か月前に脳転移が判明し、放射線治療を施行したが効果は限定的であった。3か月前から在宅療養を開始し、疼痛管理と呼吸困難感の緩和を目的とした治療を継続している。
訪問看護開始から現在までの情報
9月12日に訪問看護を開始した。開始当初は、軽度の呼吸困難感と背部痛を訴えていたが、室内の移動は可能であり、日中は居間で過ごすことができていた。しかし、9月下旬頃から全身倦怠感が増強し、臥床時間が徐々に増加してきた。10月に入ってからは呼吸困難感が著明となり、安静時でも呼吸苦を訴えるようになった。10月6日頃からは食事摂取量も著しく減少し、水分摂取も困難になってきている。10月9日現在では、意識レベルはJCS I-2程度で、呼びかけには開眼し短い言葉で応答するが、傾眠傾向が顕著である。
バイタルサイン
訪問看護開始時(9月12日)のバイタルサインは、体温36.5℃、血圧136/82mmHg、脈拍88回/分・整、呼吸数20回/分、SpO2 94%(室内気)であった。現在(10月9日)のバイタルサインは、体温37.4℃、血圧92/54mmHg、脈拍116回/分・不整、呼吸数28回/分・努力様呼吸、SpO2 87%(酸素2L/分投与下)である。頻脈と低血圧、呼吸数の増加と酸素化の悪化が認められる。
食事と嚥下状態
入院前は普通食を1日3食摂取しており、嚥下機能に問題はなかった。訪問看護開始時は、食事摂取量は約60%程度で、軟飯と煮物を中心とした食事を摂取していた。しかし、10月に入ってからは食欲が著しく低下し、現在は経口摂取がほとんどできず、少量の水分を口に含む程度となっている。嚥下反射は保たれているが、むせ込みが時々見られる。喫煙歴はなく、飲酒歴もない。
排泄
入院前は自立してトイレで排泄していた。訪問看護開始時も、日中はトイレ歩行が可能で、夜間はポータブルトイレを使用していた。排便は1日1回程度で、やや硬めの便であった。しかし、10月5日以降はおむつを使用しており、排尿は1日3〜4回、1回80〜100ml程度と尿量の減少が著明である。排便は4日前が最終で、ごく少量の軟便であった。緩下剤を使用しているが、腸蠕動音は微弱である。
睡眠
入院前は22時頃に就寝し、6時頃に起床する生活リズムであった。訪問看護開始時は、夜間に呼吸苦や疼痛で3〜4回覚醒することがあったが、合計で4〜5時間程度の睡眠は確保できていた。現在は傾眠と覚醒を繰り返す状態で、昼夜の区別が不明瞭となっている。呼吸困難感により浅い睡眠が続いており、落ち着かない様子が見られる。睡眠薬は使用していないが、不穏時にはミダゾラムを使用している。
視力・聴力・知覚・コミュニケーション・信仰
視力は白内障があり、視力低下が見られるが、日常生活に大きな支障はなかった。聴力は中等度の難聴があり、補聴器を使用していた。知覚は正常で、疼痛の訴えも可能である。コミュニケーション能力は、現在は傾眠傾向が強く、簡単な質問に「はい」「いいえ」で答えられる程度となっている。信仰は仏教(曹洞宗)で、念仏を唱えることを日課としていた。
動作状況
訪問看護開始時は、歩行は不安定で杖を使用していたが、室内の移動は可能であった。移乗は見守りで可能、排泄はトイレ使用可能、入浴は週1回の訪問入浴サービスを利用していた。衣類の着脱は一部介助が必要であった。転倒歴は訪問看護開始前に1回あり、その際に軽度の打撲を負った。しかし、現在は体動がほとんどなく、寝返りも介助が必要となっている。移乗は全介助、排泄はおむつ使用、入浴は清拭のみ、衣類の着脱も全介助となっている。
内服中の薬
- モルヒネ徐放錠 30mg 1日2回(朝・夕食後)
- モルヒネ速放錠 10mg 疼痛時・呼吸困難時頓用(1日6回まで)
- デキサメタゾン 4mg 1日1回(朝食後)
- アムロジピン 5mg 1日1回(朝食後)
- アトルバスタチン 10mg 1日1回(夕食後)
- 酸化マグネシウム 1.5g 1日3回(毎食後)
- ゾルピデム 5mg 1日1回(就寝前・不眠時)
- ミダゾラム口腔用液 10mg 呼吸困難感・不穏時頓用
検査データ
| 項目 | 単位 | 訪問看護開始時(9月12日) | 現在(10月6日) |
|---|---|---|---|
| WBC | /μL | 7,200 | 5,100 |
| RBC | ×10⁴/μL | 332 | 268 |
| Hb | g/dL | 9.8 | 7.6 |
| Plt | ×10⁴/μL | 16.2 | 10.8 |
| TP | g/dL | 5.8 | 4.7 |
| Alb | g/dL | 2.6 | 1.9 |
| AST | U/L | 42 | 68 |
| ALT | U/L | 38 | 52 |
| BUN | mg/dL | 28.3 | 52.6 |
| Cr | mg/dL | 1.1 | 1.8 |
| Na | mEq/L | 136 | 130 |
| K | mEq/L | 4.3 | 5.2 |
| CRP | mg/dL | 4.8 | 12.3 |
内服薬は現在、家族が管理しており、服薬時には看護師または家族が介助している。現在は経口摂取が困難なため、必要な薬剤のみを少量の水で服用させている。
今後の治療方針と医師の指示
主治医からは、予後は数日程度と説明されている。治療方針としては、延命を目的とした処置は行わず、苦痛の緩和を最優先とする。具体的な指示としては、呼吸困難感や疼痛に対してモルヒネ速放錠を適宜使用すること、不穏や苦悶様表情が見られる場合にはミダゾラム口腔用液を使用すること、酸素投与は継続すること、輸液等の延命処置は行わないこととされている。また、本人と家族の希望により、最期まで自宅で過ごす方針が確認されており、看取りの準備を整えるよう指示されている。
本人と家族の想いと言動
A氏は訪問看護開始時に「家で最期を迎えたい。娘たちには世話になりっぱなしで申し訳ないけれど」と涙を浮かべながら話していた。また、「長く生きてきたから、もう十分。苦しまずに逝けたら」と穏やかな表情で語っていた。現在は傾眠傾向が強いが、時折目を開けて家族の顔を見ると、わずかに微笑む様子が見られる。
次女は「母の希望を叶えてあげたい。家で看取りたい」と強く希望している。しかし、「呼吸が苦しそうで、見ているのが本当に辛いです。これでいいのか不安になります」とも訴えており、精神的な負担が大きい様子である。次女の夫も協力的で、「義母が安らかに過ごせるように、できることは何でもしたい」と話している。曾孫は6歳で、「ひいばあちゃん、がんばって」と小さな声で励ましており、時々A氏の手を優しく握っている。
ゴードン11項目アセスメント解説
1. 健康知覚-健康管理パターンのポイント
このパターンでは、A氏と家族が終末期の状態をどのように認識し、緩和ケア中心の治療方針をどのように受け止めているかを評価することが重要です。93歳という高齢で、本人の希望により化学療法を選択せず緩和ケアを中心とした治療方針を取っていることの意味を考える必要があります。
どんなことを書けばよいか
健康知覚-健康管理パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 疾患についての本人・家族の理解度(病態、治療、予後など)
- 疾患や治療に対する受け止め方、受容の程度
- 現在の健康状態や症状の認識
- これまでの健康管理行動(受診行動、服薬管理、生活習慣など)
- 疾患が日常生活に与えている影響の認識
- 健康リスク因子(喫煙、飲酒、アレルギー、既往歴など)
疾患と治療方針の理解
A氏は肺腺癌StageⅣで脳転移・骨転移を伴う終末期の状態にあります。10か月前に診断された際、高齢であることと本人の希望により化学療法は施行せず、当初から緩和ケアを中心とした治療方針が選択されました。A氏自身が「家で最期を迎えたい。娘たちには世話になりっぱなしで申し訳ないけれど」「長く生きてきたから、もう十分。苦しまずに逝けたら」と語っていることから、自身の予後や状態をある程度理解し、受容していることが推測されます。このような本人の言葉を踏まえて、疾患受容の程度と心理状態を丁寧にアセスメントするとよいでしょう。
家族の理解と受け止め
次女は「母の希望を叶えてあげたい。家で看取りたい」と強く希望する一方で、「呼吸が苦しそうで、見ているのが本当に辛いです。これでいいのか不安になります」と訴えています。この発言から、家族は在宅看取りの方針を理解し支持しているものの、実際に苦しむ姿を目の当たりにして精神的な葛藤を抱えていることがわかります。家族の理解度と心理的負担の両面から状況を捉え、家族支援の必要性についても考慮するとよいでしょう。
既往歴と健康管理行動
A氏には68歳時からの高血圧症、75歳時からの脂質異常症があり、内服治療を継続してきました。82歳時には変形性膝関節症で保存的治療を受けています。喫煙歴・飲酒歴がなく、これまで適切な健康管理行動をとってきたことが推測されます。元和裁師という職業歴と「真面目で我慢強い性格」という情報から、自己管理能力が高い方であったと考えられ、このような背景が現在の意思決定にどのように影響しているかを考察するとよいでしょう。
現在の健康状態の認識
主治医からは予後は数日程度と説明されており、延命処置は行わず苦痛の緩和を最優先とする方針が確認されています。現在のA氏は傾眠傾向が顕著でJCS I-2程度の意識レベルであり、自身の状態を明確に認識・表現することは困難になっています。しかし、時折目を開けて家族の顔を見るとわずかに微笑む様子が見られることから、家族の存在を認識できている可能性があります。このような反応を観察し、本人の安楽と尊厳を守るケアにつなげる視点が重要です。
アセスメントの視点
このパターンでは、終末期における本人と家族の疾患受容、在宅看取りという意思決定の背景、そして現在の苦痛管理に対する認識を統合的に捉えることが求められます。A氏は自らの意思で緩和ケアを選択し、在宅での最期を希望しており、家族もその意思を尊重しようとしています。一方で、家族は実際の看取りの過程で不安や葛藤を抱えており、この点への支援が重要な課題となります。本人の「苦しまずに逝けたら」という願いが達成されているか、家族が安心して看取りに臨めているかという視点からアセスメントを深めるとよいでしょう。
ケアの方向性
A氏の「苦しまずに逝きたい」という願いを尊重し、疼痛や呼吸困難感に対する適切な症状マネジメントを継続することが最優先となります。同時に、家族が抱える不安や葛藤に寄り添い、「これでいいのか」という問いに対して支持的に関わることが重要です。家族が看取りの過程で後悔を残さないよう、ケアへの参加を促し、本人との時間を大切にできるよう支援することが求められます。
2. 栄養-代謝パターンのポイント
このパターンでは、終末期における栄養状態の著しい悪化と、経口摂取困難な状態をどのように捉え、緩和ケアの観点からどのようなアプローチが適切かを考えることが重要です。延命目的の輸液は行わない方針であることを踏まえた栄養管理の考え方を理解する必要があります。
どんなことを書けばよいか
栄養-代謝パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 食事と水分の摂取量と摂取方法
- 食欲、嗜好、食事に関するアレルギー
- 身長・体重・BMI・必要栄養量・身体活動レベル
- 嚥下機能・口腔内の状態
- 嘔吐・吐気の有無
- 皮膚の状態、褥瘡の有無
- 栄養状態を示す血液データ(Alb、TP、RBC、Ht、Hb、Na、K、TG、TC、HbA1c、BSなど)
栄養摂取状況の経時的変化
訪問看護開始時(9月12日)には食事摂取量は約60%程度で、軟飯と煮物を中心とした食事を摂取していました。しかし10月に入ってから食欲が著しく低下し、10月6日頃からは食事摂取量が著しく減少、現在(10月9日)は経口摂取がほとんどできず、少量の水分を口に含む程度となっています。この約1か月間での急激な摂取量低下は、疾患の進行に伴う全身状態の悪化を反映しており、終末期における自然な経過として理解することが重要です。
栄養状態を示す検査データの変化
検査データでは、TP 5.8→4.7g/dL、Alb 2.6→1.9g/dLと、約1か月で著明な低下を示しています。Alb 1.9g/dLは高度の低アルブミン血症であり、著しい低栄養状態を示しています。また、Hb 9.8→7.6g/dLと高度貧血の悪化も認められます。これらのデータは癌の進行と摂取量低下による栄養状態の悪化を示しており、終末期特有の悪液質の状態と考えられます。このような検査データの推移と臨床症状を関連づけてアセスメントするとよいでしょう。
体格と栄養必要量の考え方
A氏は身長152cm、体重34kgで、BMIは約14.7と著しい低体重です。しかし終末期においては、通常の栄養必要量の計算や積極的な栄養補給は必ずしも適切ではありません。延命目的の輸液は行わない方針が確認されており、経口摂取困難な状態での無理な栄養介入は本人の苦痛を増す可能性があることを理解する必要があります。緩和ケアにおける栄養管理の考え方を踏まえ、本人の安楽を最優先とした視点でアセスメントすることが大切です。
嚥下機能と口腔の状態
嚥下反射は保たれているものの、むせ込みが時々見られる状態です。傾眠傾向が強く意識レベルがJCS I-2程度であることから、嚥下機能の低下と誤嚥リスクの増大が考えられます。少量の水分を口に含む程度の摂取であっても、誤嚥性肺炎のリスクについて考慮する必要があります。一方で、口腔内の乾燥や不快感を軽減するための口腔ケアの重要性についても考えるとよいでしょう。
皮膚の状態と褥瘡リスク
低栄養状態(Alb 1.9g/dL)、高度貧血(Hb 7.6g/dL)、体動がほとんどなく寝返りも介助が必要な状態は、いずれも褥瘡発生の高リスク因子です。現在の事例には皮膚の状態についての詳細な記載がありませんが、このような全身状態を踏まえると褥瘡リスクは極めて高いと考えられます。終末期においても皮膚の保護と褥瘡予防は安楽の維持に重要であり、この点についてアセスメントに含めるとよいでしょう。
電解質異常
Na 136→130mEq/Lと低Na血症、K 4.3→5.2mEq/Lと高K血症の傾向が認められます。これらは腎機能低下(BUN 28.3→52.6mg/dL、Cr 1.1→1.8mg/dL)や摂取量低下、全身状態の悪化に伴う変化と考えられます。電解質異常は意識レベルや全身状態に影響を与える可能性があり、現在の傾眠傾向との関連についても考察するとよいでしょう。
アセスメントの視点
終末期の栄養管理においては、一般的な「栄養状態を改善する」という目標ではなく、「苦痛を最小限にしながら自然な経過を支える」という視点が重要となります。経口摂取がほとんどできない状態であっても、輸液等の延命処置は行わない方針が確認されており、この決定を尊重したケアが求められます。低栄養・脱水による苦痛の評価、口腔内の快適さの維持、褥瘡リスクへの対応など、安楽の視点から統合的にアセスメントするとよいでしょう。
ケアの方向性
無理な経口摂取の促しは行わず、本人が望む場合に少量の水分や好みのものを口に含む程度の対応とすることが適切です。口腔内の乾燥や不快感を軽減するための口腔ケアを丁寧に行い、口腔の清潔と潤いを保つことが重要です。また、低栄養・循環不全に伴う褥瘡リスクに対して、体圧分散と皮膚の保護を継続することが求められます。家族に対しては、食べられないことへの不安や罪悪感を軽減するための説明と支援が必要です。
続きはnoteで公開中です✨️
ゴードンの続きとヘンダーソン・関連図・看護計画について解説しています😊
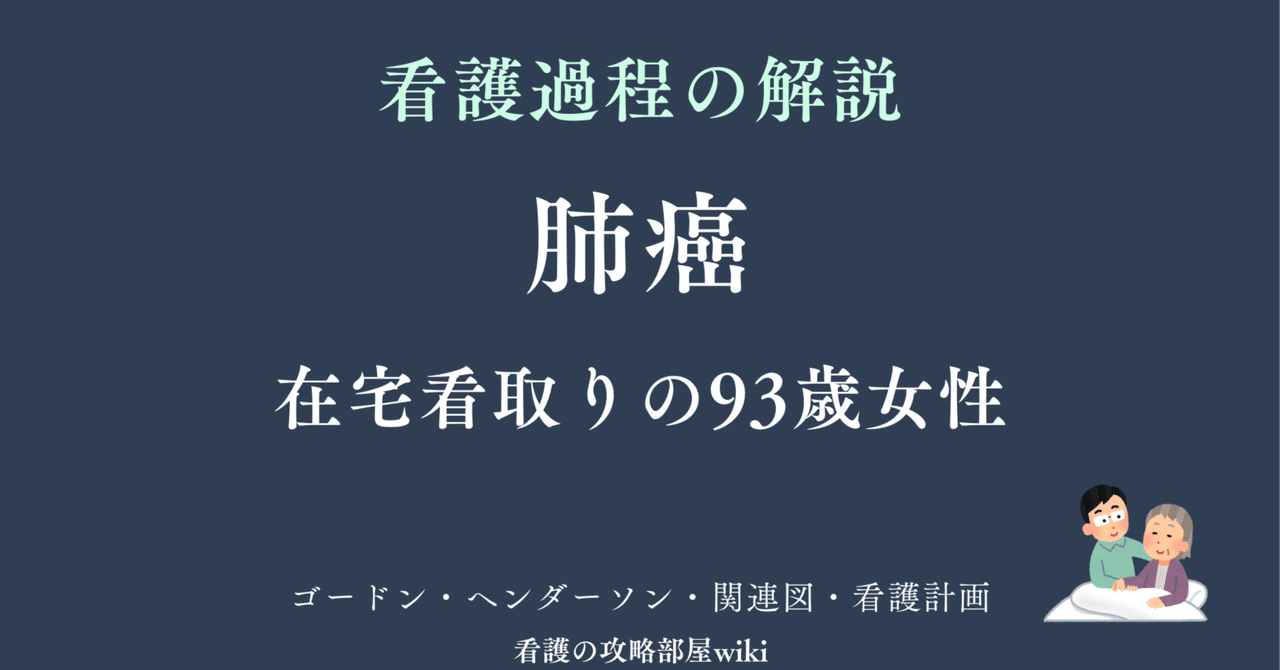
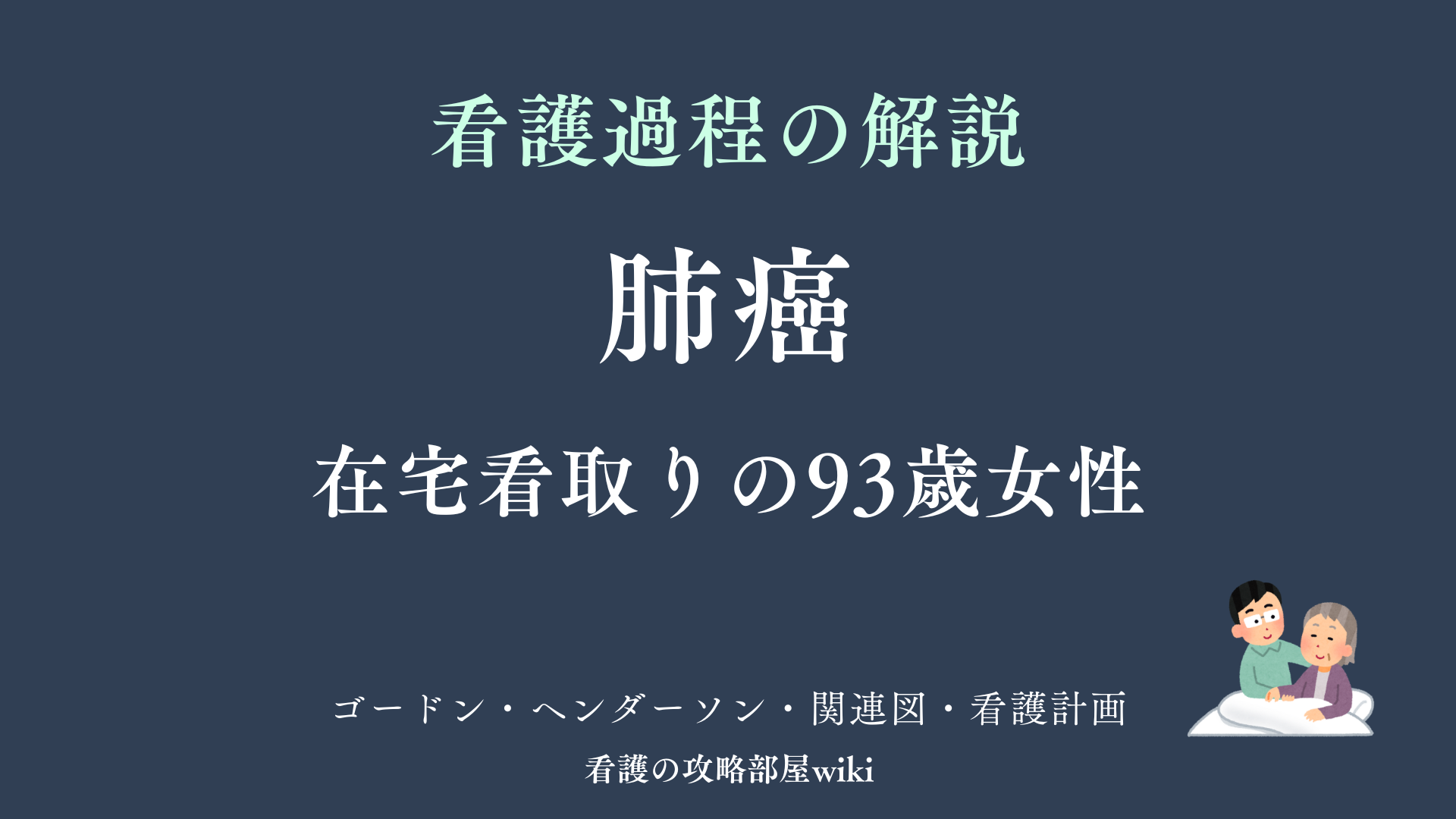


コメント