本記事では、看護師の思考プロセスを詳しく解説します。
実際の臨床では患者さんごとに状況が異なりますが、「わたしならどう考えるか」を具体的に示すことで、あなた自身の考える力を育てることを目指します。
この記事を参考に思考プロセスを学び、看護過程が得意になってもらえたら嬉しいです。
それでは、見ていきましょう。
看護学習や実習に役立つブログも運営しています✨️
ぜひ参考にしてみてくださいね!
https://kango-kouryaku.com/
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。事例は完全なフィクションであり、個別の診断・治療の根拠ではありません。実際の看護実践は患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください。本記事をそのまま課題として提出しないでください。内容の完全性・正確性は保証できず、本記事の利用により生じた損害について一切の責任を負いません。
基本情報
A氏、30歳、女性、身長158cm、体重52kg。家族構成は両親と本人の3人暮らしで、キーパーソンは母親である。職業は入院前までパート勤務をしていたが、症状悪化により3か月前から休職中である。性格は几帳面で真面目、他者への配慮が強い傾向がある。感染症はなし、アレルギーは食物・薬物ともになし。認知力は見当識に軽度の混乱が見られるが、日常会話は概ね可能である。
病名
統合失調症(妄想型)
既往歴と治療状況
22歳時に統合失調症と診断され、以降外来通院にて抗精神病薬による治療を継続していた。過去2回の入院歴があり、いずれも服薬中断後の症状悪化によるものである。現在は再発予防と症状コントロールを目的とした薬物療法と精神療法を実施中である。
入院から現在までの情報
9月下旬頃から「誰かに監視されている」「悪口を言われている」という訴えが増え、徐々に服薬を自己中断するようになった。入院3日前からは幻聴が顕著となり、「死ね」「消えろ」という命令性の幻聴に苦しむようになった。入院前日には興奮状態となり、自室に閉じこもって大声で叫ぶ様子が見られたため、母親が精神科救急に連絡し、10月1日に医療保護入院となった。入院時は著明な不安と緊張が認められ、看護師や他患者への警戒心が強く、「あなたたちも敵なのか」と訴える場面があった。入院後は隔離室での治療が開始され、抗精神病薬の調整と環境調整により徐々に落ち着きを取り戻している。入院7日目から一般病室へ移動となり、現在は病棟内での生活に慣れつつある段階である。しかし、依然として幻聴は残存しており、時折不安そうな表情で独語が見られる。
バイタルサイン
入院時のバイタルサインは、体温36.8℃、血圧138/92mmHg、脈拍98回/分、呼吸数22回/分、SpO2 98%(室内気)であった。現在(10月14日)のバイタルサインは、体温36.5℃、血圧122/78mmHg、脈拍72回/分、呼吸数18回/分、SpO2 99%(室内気)と安定している。
食事と嚥下状態
入院前は自宅で普通食を摂取しており、特に問題はなかった。しかし症状悪化後の1週間は食欲が低下し、1日1食程度しか食べられない状況であった。現在は病院食の常食を提供されており、食事摂取量は約7割程度である。「毒が入っているかもしれない」という思いから食事を拒否する場面もあるが、看護師の声かけにより摂取できることが多い。嚥下状態に問題はなし。喫煙歴なし、飲酒は社交的に少量のみ。
排泄
入院前は自立して排泄していたが、症状悪化後は自室にこもりがちとなり、排泄回数が減少していた。現在は病棟のトイレを使用し、排尿・排便ともに自立している。排便は2~3日に1回で、やや便秘傾向がある。性状は硬めである。下剤は使用していないが、水分摂取を促す声かけを実施中である。
睡眠
入院前は不眠傾向が強く、1日2~3時間程度の睡眠であった。幻聴により覚醒することが多く、夜間も警戒心から眠れない状況が続いていた。現在は睡眠導入剤の使用により、1日5~6時間程度の睡眠が確保できている。しかし、中途覚醒が時折見られ、「声が聞こえる」と訴えることがある。睡眠の質は改善傾向だが、まだ十分とは言えない。
視力・聴力・知覚・コミュニケーション・信仰
視力と聴力に器質的な問題はない。知覚面では幻聴が持続しており、特に夕方から夜間にかけて増強する傾向がある。また、被害妄想により周囲の言動を悪意あるものと解釈しやすい状態である。コミュニケーションは可能だが、看護師との会話中も幻聴に反応して中断することがある。信仰は特になし。
動作状況
歩行、移乗、排泄、入浴、衣類の着脱はすべて自立している。転倒歴はなし。しかし、幻聴や不安により動作が急に止まることや、周囲を警戒しながらゆっくりと移動する様子が見られる。入浴は週2回実施しているが、看護師の声かけが必要である。
内服中の薬
- リスペリドン錠 3mg 1日2回(朝・夕食後)
- クエチアピン錠 100mg 1日1回(就寝前)
- ビペリデン塩酸塩錠 1mg 1日2回(朝・夕食後)
- ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 1日1回(就寝前)
- 酸化マグネシウム錠 330mg 1日3回(毎食後)
服薬は看護師管理で実施されており、配薬時に確実に内服できていることを確認している。
検査データ
| 検査項目 | 入院時(10月1日) | 現在(10月14日) | 基準値 |
|---|---|---|---|
| 白血球数 | 7800 /μL | 6500 /μL | 3300~8600 /μL |
| 赤血球数 | 420 万/μL | 435 万/μL | 386~492 万/μL |
| ヘモグロビン | 13.2 g/dL | 13.8 g/dL | 11.6~14.8 g/dL |
| 血小板数 | 24.5 万/μL | 26.8 万/μL | 15.8~34.8 万/μL |
| 総蛋白 | 7.0 g/dL | 7.2 g/dL | 6.6~8.1 g/dL |
| アルブミン | 4.2 g/dL | 4.3 g/dL | 4.1~5.1 g/dL |
| AST | 22 U/L | 20 U/L | 13~30 U/L |
| ALT | 18 U/L | 16 U/L | 7~23 U/L |
| 血糖値 | 112 mg/dL | 98 mg/dL | 73~109 mg/dL |
| HbA1c | 5.6 % | – | 4.9~6.0 % |
| CRP | 0.2 mg/dL | 0.1 mg/dL | 0.00~0.14 mg/dL |
服薬状況は看護師管理である。
今後の治療方針と医師の指示
今後の治療方針として、抗精神病薬による薬物療法を継続し、幻聴や妄想の軽減を図る。症状が安定すれば、作業療法や集団精神療法への参加を促し、社会生活技能の回復を目指す。退院後の服薬継続が重要であるため、服薬の必要性について心理教育を実施する方針である。家族への疾患理解促進と支援体制の構築も並行して進める。医師からの指示として、幻聴や妄想の内容・頻度の観察、睡眠状況の観察と記録、食事摂取量の記録、服薬確認の徹底が出されている。
本人と家族の想いと言動
A氏は「声が聞こえなくなってほしい。でも薬を飲んでも完全には消えない」と訴えており、幻聴に対する苦痛と不安を強く感じている。また「みんなが私のことを悪く言っている気がする。信じていいのか分からない」と話し、対人関係への不信感が強い。一方で「早く退院して仕事に戻りたい」という気持ちも表現しており、回復への意欲も持っている。母親は「また入院になってしまって申し訳ない。今度こそちゃんと薬を飲ませないといけないと思うが、どうしたらいいか分からない」と話し、疾患管理への不安と自責の念を抱えている。父親は「娘のことは心配だが、仕事があるのであまり面会に来られない。母親に任せている」と述べている。
ゴードン11項目アセスメント解説
1. 健康知覚-健康管理パターンのポイント
健康知覚-健康管理パターンでは、患者自身と家族が疾患をどのように理解し、どのように健康管理を行ってきたかを評価します。特に統合失調症のような慢性疾患では、服薬管理や症状の自己認識が再発予防に直結するため、このパターンのアセスメントは極めて重要です。
どんなことを書けばよいか
健康知覚-健康管理パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 疾患についての本人・家族の理解度(病態、治療、予後など)
- 疾患や治療に対する受け止め方、受容の程度
- 現在の健康状態や症状の認識
- これまでの健康管理行動(受診行動、服薬管理、生活習慣など)
- 疾患が日常生活に与えている影響の認識
- 健康リスク因子(喫煙、飲酒、アレルギー、既往歴など)
疾患管理の現状と課題
A氏は22歳時に統合失調症と診断され、8年間の治療歴があります。過去2回の入院歴がいずれも服薬中断後の症状悪化によるものであることを踏まえて記述するとよいでしょう。このパターンは、A氏にとって服薬管理が最大の課題であることを示しており、なぜ服薬中断が繰り返されるのか、その背景要因を考察することが重要です。今回の入院も9月下旬から徐々に服薬を自己中断したことが症状悪化の引き金となっている点に着目して、服薬に対するA氏の認識や困難さを探る必要があるでしょう。
症状に対する本人の認識
A氏は「声が聞こえなくなってほしい。でも薬を飲んでも完全には消えない」と訴えています。この発言から読み取れることとして、A氏は幻聴が苦痛であることを認識しているものの、薬物療法の限界を感じている可能性があります。薬を飲んでも症状が完全には消えないという現実に直面し、それが服薬継続への意欲を低下させている可能性について考えるとよいでしょう。また、「みんなが私のことを悪く言っている気がする。信じていいのか分からない」という発言は、被害妄想による症状の自己認識を示していますが、同時に自分の認識が正しいのか疑問を持っている部分もあり、この点は支援の手がかりになる可能性があります。
家族の疾患理解と管理能力
母親は「また入院になってしまって申し訳ない。今度こそちゃんと薬を飲ませないといけないと思うが、どうしたらいいか分からない」と述べています。この発言を踏まえると、母親には服薬管理の重要性は理解しているものの、具体的な方法がわからず困惑している状況が読み取れます。自責の念を抱えている点も含めて記述するとよいでしょう。一方、父親は「仕事があるのであまり面会に来られない。母親に任せている」と述べており、家族内での役割分担や支援体制の偏りについても考慮する必要があります。
健康リスク因子の評価
アレルギーや感染症がなく、喫煙歴もないことは、身体的な健康リスクが比較的低いことを意味します。しかし、症状悪化時には食事摂取が1日1食程度まで低下していた点や、几帳面で真面目という性格特性が、かえってストレス対処を困難にしている可能性について考えてみるとよいでしょう。
アセスメントの視点
このパターンでは、疾患の慢性性と再発を繰り返している事実、そして服薬中断が主要な悪化要因であることを総合的に捉えることが重要です。A氏本人の症状認識と薬物療法への期待と失望、家族の疾患理解と支援能力のギャップ、これらを統合して健康管理上の課題を明確化することが求められます。
ケアの方向性
服薬継続を支援するための心理教育、A氏が抱える薬物療法への疑問や不安に寄り添った対話、家族への具体的な疾患管理方法の教育、そして再発予防のための支援体制の構築が必要となるでしょう。
2. 栄養-代謝パターンのポイント
栄養-代謝パターンでは、食事摂取状況だけでなく、精神症状が栄養摂取に与える影響を評価することが重要です。統合失調症患者では、妄想や幻覚が食行動に直接影響を及ぼすことがあるため、その関連性を丁寧に観察する必要があります。
どんなことを書けばよいか
栄養-代謝パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 食事と水分の摂取量と摂取方法
- 食欲、嗜好、食事に関するアレルギー
- 身長・体重・BMI・必要栄養量・身体活動レベル
- 嚥下機能・口腔内の状態
- 嘔吐・吐気の有無
- 皮膚の状態、褥瘡の有無
- 栄養状態を示す血液データ(Alb、TP、RBC、Ht、Hb、Na、K、TG、TC、HbA1c、BSなど)
現在の栄養摂取状況
A氏の現在の食事摂取量は約7割程度であり、病院食の常食を提供されています。BMIを計算すると約20.8(52kg÷1.58²)となり、標準範囲内であることを確認するとよいでしょう。しかし、症状悪化時には1日1食程度しか食べられない状況であったことを踏まえると、精神症状と食事摂取量の関連性について注目する必要があります。
精神症状と食行動の関連
「毒が入っているかもしれない」という思いから食事を拒否する場面があることは、被害妄想が直接的に食事摂取を阻害していることを示しています。この点を踏まえて、妄想の内容や程度が栄養摂取にどのように影響しているかを記述するとよいでしょう。一方で、看護師の声かけにより摂取できることが多いという事実は、支援的な関わりによって食事摂取が改善する可能性を示唆しており、信頼関係構築の重要性を考えるきっかけとなります。
栄養状態の客観的評価
検査データでは、総蛋白7.0→7.2g/dL、アルブミン4.2→4.3g/dL、ヘモグロビン13.2→13.8g/dLと、いずれも基準値内で入院後にわずかながら改善傾向を示しています。これらのデータから、現時点での栄養状態は比較的良好であると評価できますが、症状悪化時の食事摂取量低下が長期化すれば栄養状態の悪化リスクがあることを意識して記述するとよいでしょう。
水分摂取と便秘の関連
排便が2〜3日に1回で硬めの便であることから、水分摂取が不足している可能性があります。妄想による食事拒否があることを考えると、水分摂取も同様に阻害されている可能性について考慮する必要があるでしょう。
アセスメントの視点
栄養摂取における最大の課題は、精神症状が直接的に食行動に影響している点です。現在の栄養状態は保たれているものの、症状の変動によって摂取量が大きく左右される不安定さがあることを統合的に捉えることが重要です。
ケアの方向性
信頼関係を基盤とした声かけの継続、妄想の軽減に向けた薬物療法の効果判定、食事環境の調整、水分摂取促進による便秘予防などが必要となります。
続きはnoteで公開中です✨️
ゴードンの続きとヘンダーソン・関連図・看護計画について解説しています😊
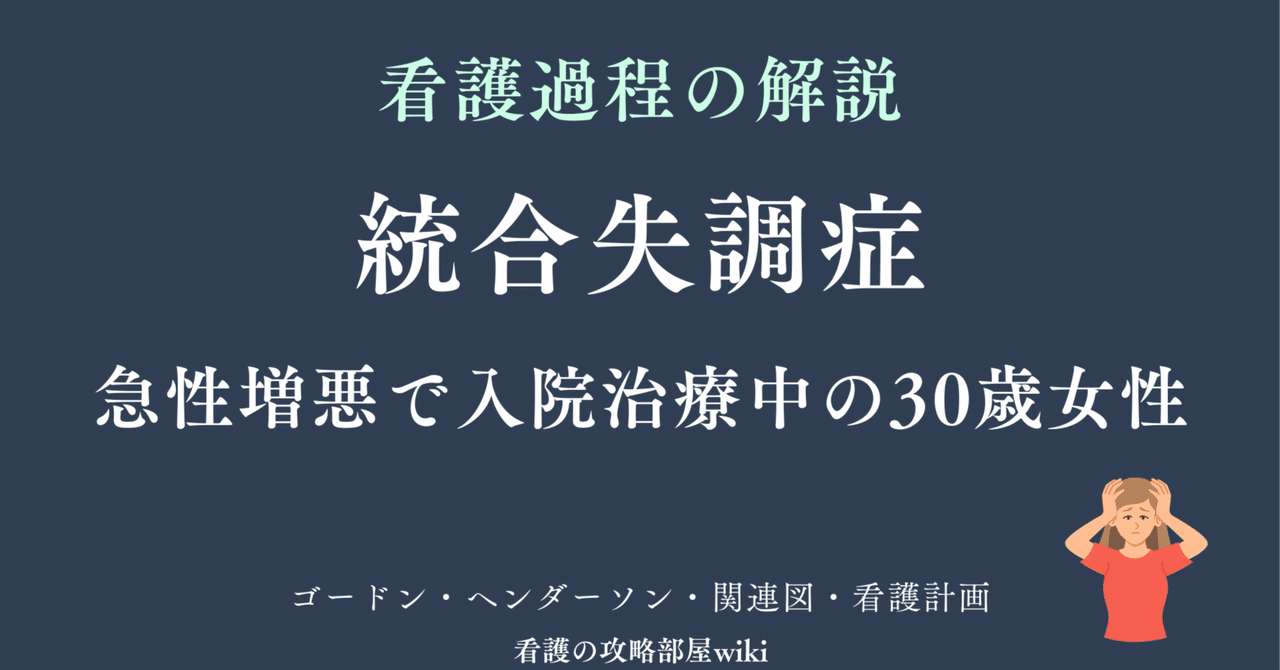
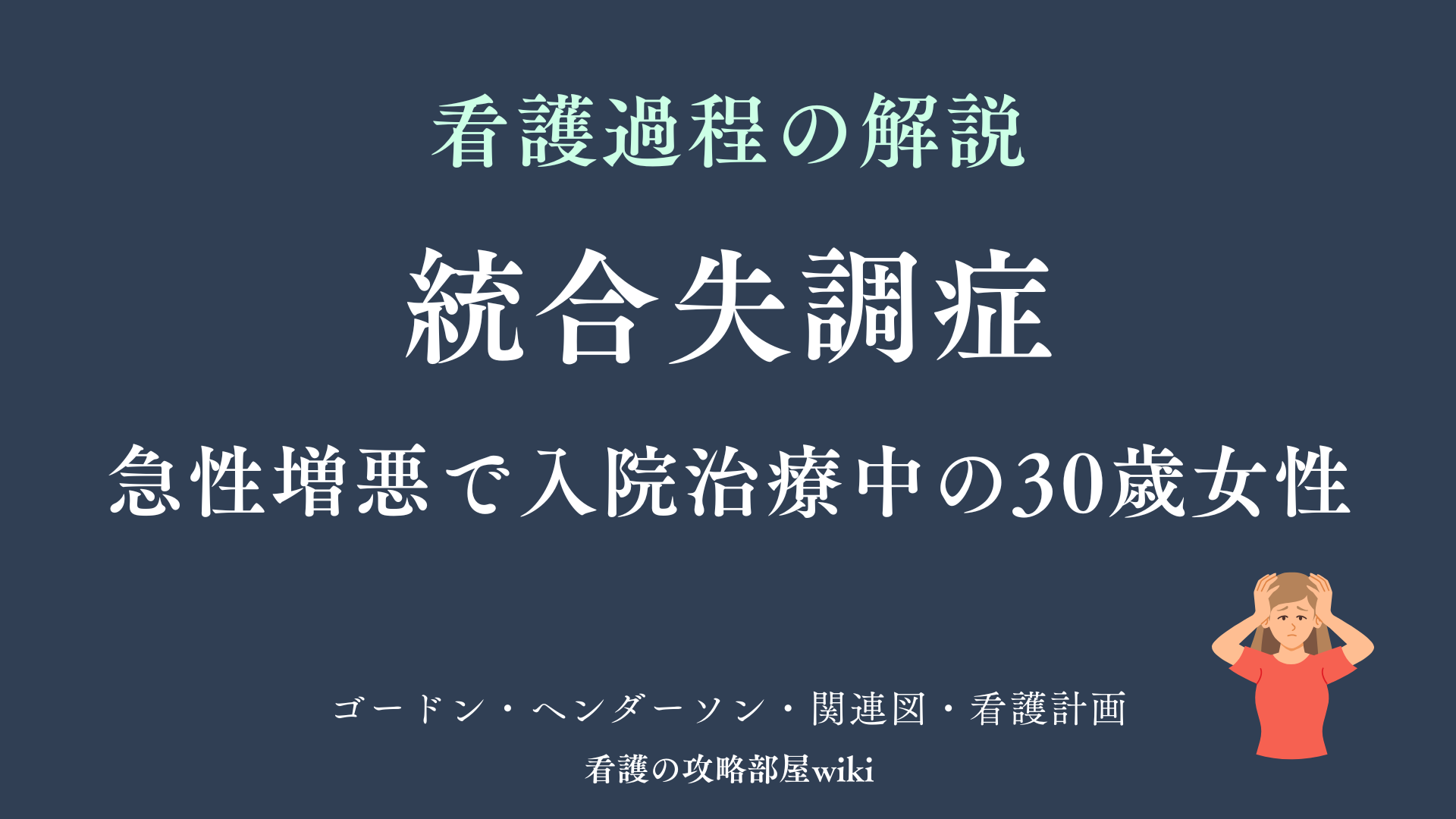


コメント