本記事では、看護師の思考プロセスを詳しく解説します。
実際の臨床では患者さんごとに状況が異なりますが、「わたしならどう考えるか」を具体的に示すことで、あなた自身の考える力を育てることを目指します。
この記事を参考に思考プロセスを学び、看護過程が得意になってもらえたら嬉しいです。
それでは、見ていきましょう。
看護学習や実習に役立つブログも運営しています✨️
ぜひ参考にしてみてくださいね!
https://kango-kouryaku.com/
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。事例は完全なフィクションであり、個別の診断・治療の根拠ではありません。実際の看護実践は患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください。本記事をそのまま課題として提出しないでください。内容の完全性・正確性は保証できず、本記事の利用により生じた損害について一切の責任を負いません。
基本情報
患者はA氏、生後2日の男児である。出生時体重は3,120g、身長49cm、在胎週数39週2日の正期産児として正常分娩で出生した。家族構成は両親と本児の3人家族で、キーパーソンは母親(26歳、主婦)である。父親は29歳の会社員で、第1子である。新生児期のため性格の評価は困難だが、刺激に対する反応は活発で啼泣も力強い。感染症検査は陰性、アレルギーの既往はない。認知機能については新生児反射(吸啜反射、把握反射、モロー反射等)が正常に確認されている。
病名
正常新生児(生理的体重減少経過観察中)
既往歴と治療状況
母体に特記すべき疾患はなく、妊娠経過は順調であった。妊娠中の感染症検査はすべて陰性で、分娩時の異常もなく自然分娩で出生している。
入院から現在までの情報
出生直後の状態は良好で、Apgarスコアは1分値9点、5分値10点と正常であった。生後24時間以内に胎便の排出を確認し、生後48時間で初回排尿も確認された。現在は生理的体重減少により体重が2,980gとなっているが、減少率は4.5%と正常範囲内である。皮膚色は良好でチアノーゼは認めず、活動性も良好である。
バイタルサイン
来院時の体温は36.7℃、心拍数148回/分、呼吸数42回/分であった。現在の体温は36.5℃、心拍数142回/分、呼吸数40回/分と安定している。
食事と嚥下状態
入院前は胎児として母体から栄養供給を受けていた。現在は母乳栄養を基本とし、1回あたり10-15ml程度を3時間ごとに授乳している。吸啜力は良好で、嚥下も問題なく行えている。哺乳後の嘔吐はなく、体重減少も正常範囲内である。
排泄
入院前は胎児として羊水中で過ごしていた。現在は1日6-8回の排尿と2-3回の排便があり、正常な排泄パターンを示している。胎便は生後24時間以内に排出され、現在は移行便から母乳便への変化が見られている。下剤の使用はない。
睡眠
入院前は胎児として子宮内で過ごしていた。現在は新生児期特有の睡眠パターンで、1日18-20時間程度の睡眠をとっている。授乳時間以外はほぼ睡眠状態で、睡眠と覚醒のリズムは未確立である。眠剤等の使用はない。
視力・聴力・知覚・コミュニケーション・信仰
視力は明暗の区別程度で、聴力は正常に反応を示している。痛覚刺激に対する反応も正常である。コミュニケーションは啼泣による意思表示が主で、母親の声に反応を示すことがある。信仰については該当しない。
動作状況
歩行、移乗、自立した排泄、入浴、衣類の着脱はすべて介助が必要な状態である。原始反射(吸啜反射、把握反射、モロー反射、歩行反射等)は正常に確認されている。転倒歴はないが、常に安全な環境での管理が必要である。
内服中の薬
・ビタミンK2シロップ 1ml 生後1日目、4-5日目、1か月健診時に経口投与
服薬状況 看護師管理による投与である。
検査データ
検査データ
| 項目 | 入院時(生後6時間) | 現在(生後48時間) | 基準値 |
|---|---|---|---|
| 血糖値(mg/dl) | 65 | 72 | 40-100 |
| ビリルビン(mg/dl) | 2.8 | 6.2 | <5.0 |
| ヘマトクリット(%) | 52 | 48 | 45-65 |
| 白血球(/μl) | 18,000 | 15,000 | 10,000-30,000 |
今後の治療方針と医師の指示
現在の状態は正常新生児として経過良好である。生理的黄疸の経過観察を継続し、ビリルビン値の推移を注意深く観察する。母乳栄養の確立を図り、体重減少が10%を超えないよう体重測定を毎日実施する。生後3-4日目での退院を予定しており、退院前に新生児マススクリーニング検査と聴覚スクリーニング検査を実施する予定である。
本人と家族の想いと言動
母親は「初めての出産で不安だったが、赤ちゃんが元気に生まれてくれて本当に嬉しい」と喜びを表現している。一方で「授乳がうまくできるか心配で、泣いている理由がわからない時がある」と育児に対する不安も訴えている。父親は「仕事を調整して付き添いたいが、妻と赤ちゃんのために何ができるかわからない」と戸惑いを見せている。両親ともに「健康に育ってほしい」「良い親になりたい」という強い想いを持っており、積極的に育児指導を受け入れている。
ゴードン11項目アセスメント解説
1. 健康知覚-健康管理パターンのポイント
このパターンでは、新生児本人の健康状態の維持と、養育者である両親の健康管理能力について評価します。新生児期は本人による健康管理が不可能であり、両親がその役割を担うため、両親の理解度や受け止め方が重要な評価対象となります。
どんなことを書けばよいか
健康知覚-健康管理パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 疾患についての本人・家族の理解度(病態、治療、予後など)
- 疾患や治療に対する受け止め方、受容の程度
- 現在の健康状態や症状の認識
- これまでの健康管理行動(受診行動、服薬管理、生活習慣など)
- 疾患が日常生活に与えている影響の認識
- 健康リスク因子(喫煙、飲酒、アレルギー、既往歴など)
新生児の健康状態
本事例のA氏は在胎週数39週2日の正期産児として出生し、Apgarスコアは1分値9点、5分値10点と良好な出生時適応を示しています。現在は生理的体重減少の経過観察中であり、減少率4.5%は正常範囲内です。これは正常な新生児の生理的変化であることを踏まえ、病的な状態との区別を明確にしてアセスメントを記載するとよいでしょう。
母体の健康管理と妊娠経過
母体に特記すべき疾患はなく、妊娠中の感染症検査はすべて陰性、分娩時の異常もなく自然分娩で出生しています。この情報は、妊娠期間中の適切な健康管理が行われていたことを示唆しており、両親の健康に対する意識や受診行動を評価する際の重要な基盤となります。
両親の理解と受け止め方
母親は「初めての出産で不安だったが、赤ちゃんが元気に生まれてくれて本当に嬉しい」と述べており、出産に対する肯定的な受け止めがうかがえます。一方で「授乳がうまくできるか心配」「泣いている理由がわからない時がある」という発言からは、初めての育児に対する不安も認められます。この両面を捉えて、両親が現在どのような段階にあるのかをアセスメントすることが大切です。
健康リスク因子の評価
感染症検査陰性、アレルギーの既往なしという情報は、現時点での健康リスク因子が低いことを示しています。また、ビタミンK2シロップの投与が計画されていることから、新生児出血症の予防という観点での健康管理が適切に行われていることも踏まえて記述するとよいでしょう。
アセスメントの視点
新生児期の健康知覚-健康管理パターンでは、新生児自身ではなく養育者である両親の健康管理能力が中心となります。両親が新生児の正常な状態と異常な徴候を理解し、適切に対応できる能力を持っているか、また育児に対する準備状態はどうかという視点で統合的にアセスメントすることが重要です。両親ともに「健康に育ってほしい」「良い親になりたい」という想いを持ち、積極的に育児指導を受け入れている姿勢は、今後の健康管理を担う上での強みとして捉えることができます。
ケアの方向性
両親の育児に対する不安を軽減しながら、新生児の正常な生理的変化や観察のポイントについての知識を提供し、退院後も適切な健康管理が継続できるよう支援することが重要です。特に初産婦である母親に対しては、授乳技術の習得支援や新生児の泣きの意味についての教育的関わりが求められます。
2. 栄養-代謝パターンのポイント
このパターンでは、新生児の栄養摂取状況と代謝機能、成長に必要な栄養が適切に確保されているかを評価します。新生児期は胎内栄養から経口栄養への移行期であり、哺乳確立の過程と生理的体重減少の推移が重要な評価項目となります。
どんなことを書けばよいか
栄養-代謝パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 食事と水分の摂取量と摂取方法
- 食欲、嗜好、食事に関するアレルギー
- 身長・体重・BMI・必要栄養量・身体活動レベル
- 嚥下機能・口腔内の状態
- 嘔吐・吐気の有無
- 皮膚の状態、褥瘡の有無
- 栄養状態を示す血液データ(Alb、TP、RBC、Ht、Hb、Na、K、TG、TC、HbA1c、BSなど)
哺乳状況と栄養摂取方法
本事例では母乳栄養を基本とし、1回あたり10-15ml程度を3時間ごとに授乳しています。生後2日目の新生児として、この哺乳量は生理的な範囲内であると考えられます。吸啜力は良好で嚥下も問題なく行えており、哺乳後の嘔吐もないことから、経口摂取機能は正常に発達していると評価できます。母親が「授乳がうまくできるか心配」と述べていることも踏まえ、母乳栄養確立の過程という視点でアセスメントを行うとよいでしょう。
体重変化と生理的体重減少
出生時体重3,120gに対し、現在の体重は2,980gで、体重減少率は4.5%です。新生児の生理的体重減少は通常5-10%程度であり、本事例は正常範囲内の経過を示しています。医師の指示でも体重減少が10%を超えないよう毎日の体重測定が指示されていることを踏まえ、今後の推移を予測しながらアセスメントを記載することが大切です。
代謝機能と検査データ
血糖値は65→72mg/dlと改善傾向にあり、基準値内で安定しています。新生児の低血糖リスクという観点から、この推移は良好な糖代謝機能を示していると考えられます。一方、ビリルビン値は2.8→6.2mg/dlと上昇しており、基準値(5.0mg/dl未満)を超えています。これは生理的黄疸の進行を示すものですが、この上昇傾向が今後どのように推移するかを注視する必要があることを踏まえてアセスメントするとよいでしょう。
皮膚の状態
皮膚色は良好でチアノーゼは認めないとされています。新生児の皮膚状態は栄養状態や循環動態を反映する重要な指標であり、黄疸の進行に伴う皮膚色の変化についても観察が必要です。
アセスメントの視点
栄養-代謝パターンでは、哺乳の確立状況、生理的体重減少の推移、代謝機能(特にビリルビン代謝と糖代謝)を統合的に評価することが重要です。現時点では哺乳機能は良好で体重減少も正常範囲内ですが、ビリルビン値の上昇傾向があるため、生理的黄疸の経過観察が必要な状態にあります。母乳栄養の確立が黄疸の経過や体重回復にどう影響するかという視点も含めて考察するとよいでしょう。
ケアの方向性
母乳栄養の確立に向けた授乳支援を継続しながら、体重減少と黄疸の経過を注意深く観察することが重要です。母親の授乳技術の向上を支援するとともに、哺乳量の増加が体重回復や黄疸軽減にどうつながるかを説明し、母親の不安軽減を図ることも大切な看護の方向性となります。
続きはnoteで公開中です✨️
ゴードンの続きとヘンダーソン・関連図・看護計画について解説しています😊
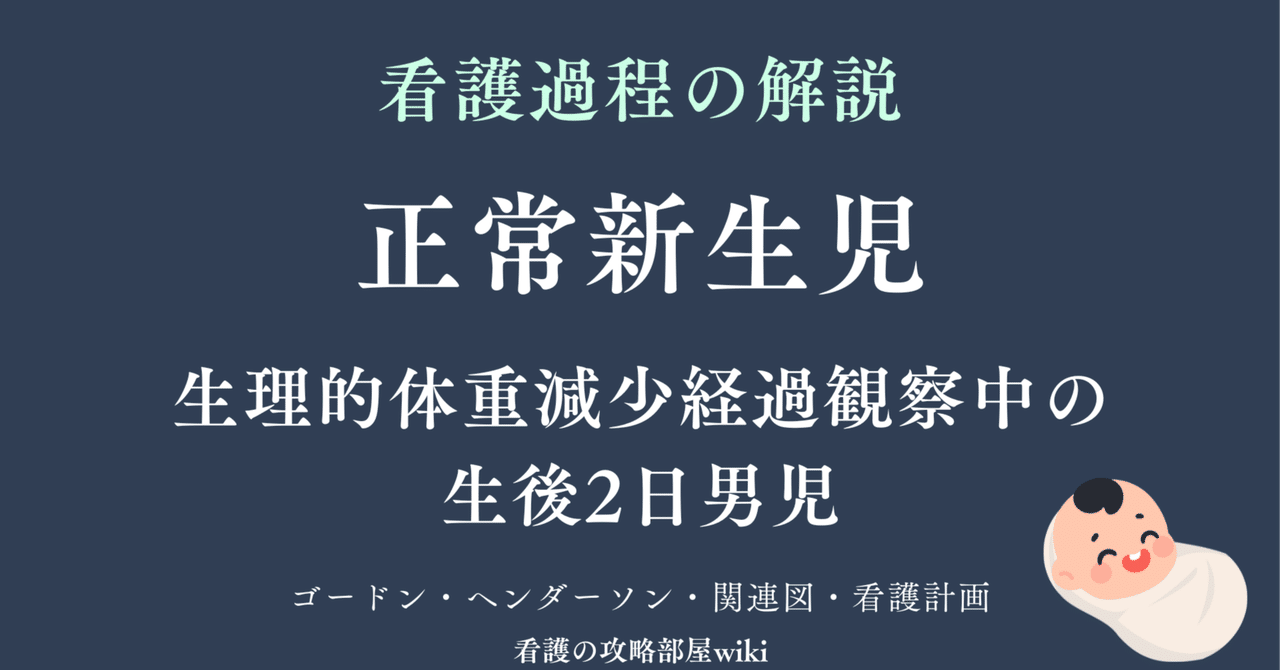
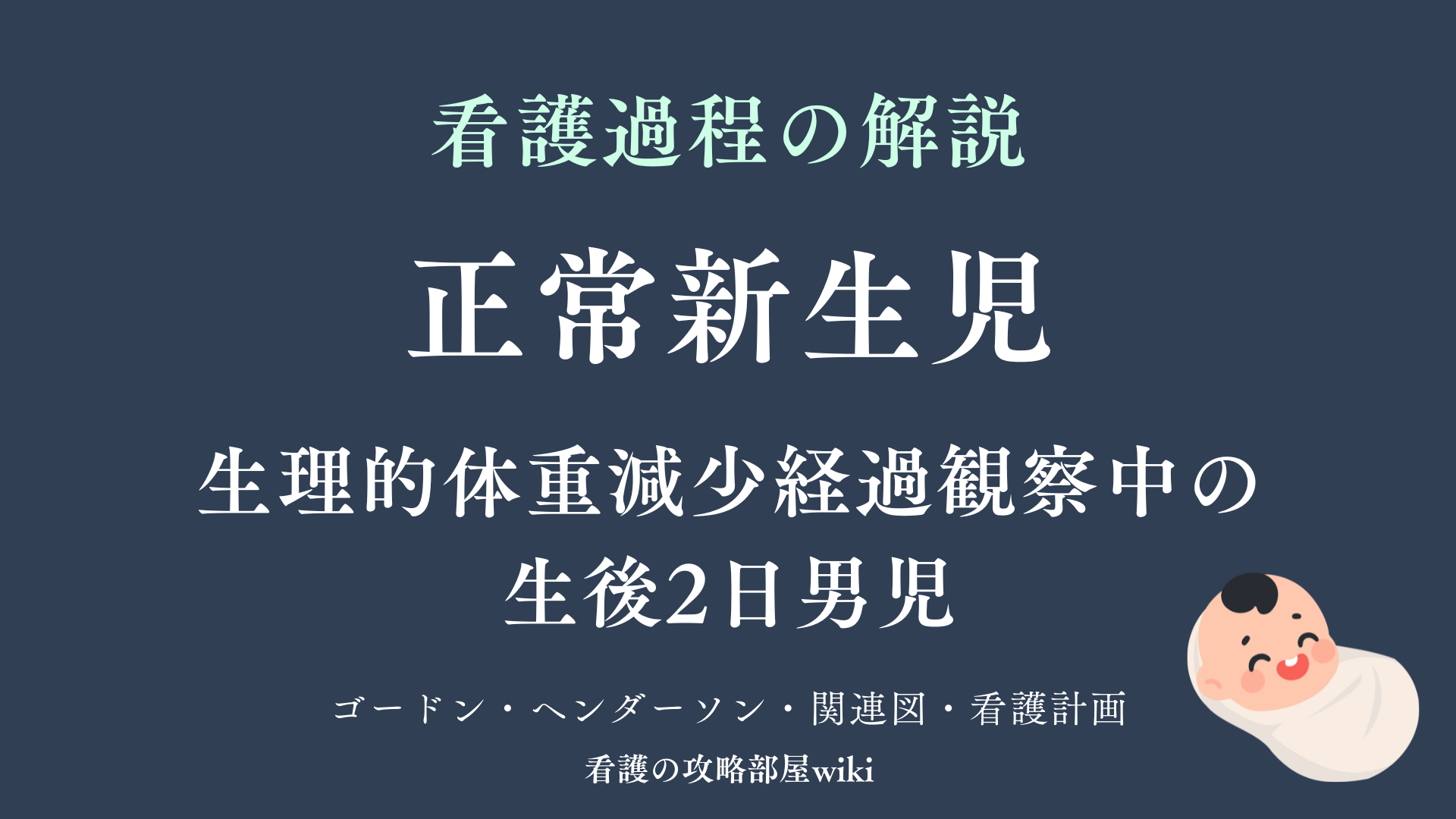

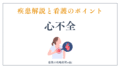
コメント