疾患概要
定義
心不全とは、心臓のポンプ機能が低下して、全身の組織に必要な血液量を送り出すことができなくなった状態です。単一の疾患ではなく、多くの基礎心疾患が最終的に到達する症候群といえます。
心不全は、急性心不全(突然に症状が悪化する)と慢性心不全(症状が徐々に進行する)に分類されます。また、左心不全(左心室のポンプ機能が低下し、肺に血液が逆流)と右心不全(右心室のポンプ機能が低下し、全身に血液が逆流)に分類されることもあります。
心不全の進行は進展的であり、適切な治療がなされなければ、やがて多臓器不全に至り、生命が脅かされます。しかし、現代の医学的管理により、多くの心不全患者さんは良好な生活の質を保ちながら、長く生存することが可能になっています。
疫学
心不全は、高齢化に伴い患者数が急速に増加しており、日本では約100万人以上が心不全を有すると推計されています。特に70代以上の高齢者で発症率が高く、高齢化社会とともに心不全患者さんは年々増加しています。
心不全は、死亡原因としても上位を占める重要な疾患です。一度、進行した心不全の診断を受けると、1年生存率は約80~90%、5年生存率は約50%程度とされており、がんと同程度の予後を有する疾患です。
発症の性別差は疾患の種類により異なります。例えば、心筋梗塞後の心不全は男性に多く、高血圧に伴う心不全は女性に多い傾向があります。
原因
心不全をもたらす基礎疾患は多様です。大きく分類すると以下のようになります。
冠動脈疾患(心筋梗塞、狭心症):心筋への血流低下により、心筋が傷つき、ポンプ機能が低下します。これが最も一般的な原因です。
高血圧:長期間の高血圧により、左心室が肥厚し、やがて拡張機能障害を来たし、心不全に進行します。
弁膜症:弁の狭窄や閉鎖不全により、心臓に過度な負荷がかかり、心筋が疲弊して心不全に進行します。
心筋症:心筋そのものが障害される疾患(拡張型心筋症、肥大型心筋症、限局性心筋症など)により、直接的にポンプ機能が低下します。
心房細動などの不整脈:心房細動による心房の収縮喪失や、長期の頻脈により、心筋が疲弊して心不全に進行します。
肺高血圧症:肺血管の抵抗が増加し、右心室が負荷を受け、右心不全に進行します。
その他:糖尿病、甲状腺機能異常、腎疾患、感染症(特に心筋炎)、毒性物質(アルコール、化学療法薬剤など)、加齢に伴う変化などが原因となります。
病態生理
心不全の発症メカニズムは複雑ですが、基本的には心筋のポンプ機能低下→心拍出量減少→代償機構の発動→やがて代償機構が追いつかなくなり心不全が明らかになるという流れです。
第1段階:心筋ダメージと初期のポンプ機能低下
冠動脈疾患、高血圧、弁膜症などの基礎疾患により、心筋が傷つき、その収縮力が低下します。すると、心拍出量が減少します。
第2段階:代償機構の発動
心拍出量が減少すると、体内の組織や臓器への血流が低下します。これを感知して、身体は複数の代償機構を発動させます。
交感神経系が活性化され、ノルアドレナリンが分泌され、心拍数が増加し、末梢血管が収縮して血圧を保とうとします。これにより、一時的に心拍出量が保たれます。
同時に、レニン-アンジオテンシン-アルドステロン系(RAAS)が活性化され、アンジオテンシンⅡが分泌され、血管が収縮し、アルドステロンが分泌されて水と塩分が保持され、血液量が増加します。これにより、心拡張末期容量が増加し、フランク・スターリングの法則に基づいて、心筋の収縮力が一時的に改善されます。
また、利尿ペプチド系(BNPやANP)が活性化され、血管拡張と利尿が起こり、血液量が調整されます。
これらの代償機構により、初期段階では心拍出量がある程度保たれ、患者さんは無症状であることが多いです。
第3段階:代償機構の不十分さと心室リモデリング
しかし、基礎疾患が続くと、心筋ダメージが進行し、代償機構だけでは心拍出量が保たれなくなってきます。
また、代償機構自体が有害な副作用をもたらします。交感神経の過度な活性化は、心筋を消耗させます。アンジオテンシンⅡは、血管収縮だけでなく、心筋と血管に線維化を促進させ、心筋は硬くなり、血管の柔軟性が失われます。
さらに重要なのが、心室リモデリングという現象です。心筋ダメージにより、心室が拡大し、その形態が球形に近づいていきます。球形になった心室は、収縮効率が低下し、ポンプ機能がさらに悪化するという悪循環が生じます。
第4段階:代償機構の破綻と心不全症状の出現
やがて、代償機構が完全に破綻すると、心不全の症状が顕在化します。
左心不全では、左心室が血液を駆出できず、左心房内に血液が貯留し、その圧が肺静脈に逆流して、肺毛細血管圧が上昇し、肺に血液が貯留します(肺うっ血)。その結果、患者さんは呼吸困難、起坐呼吸、夜間発作性呼吸困難を自覚します。
右心不全では、右心室が血液を肺に駆出できず、右心房内に血液が貯留し、その圧が大静脈に逆流して、全身に血液が貯留します。その結果、患者さんは末梢浮腫、肝腫大、腹水などを示します。
同時に、全身への血液供給が低下するため、腎臓への血流も低下し、腎臓がこれを察知して、さらにアルドステロンの分泌を促進し、水と塩分がさらに保持され、状態がさらに悪化するという悪循環が加速します。
第5段階:多臓器不全への進行
心不全が進行して、心拍出量が著しく低下すると、全身の臓器への血流が不十分になり、多臓器不全に進行します。腎不全、肝不全、脳機能障害など、多くの臓器が傷つき、最終的には生命が脅かされます。
症状・診断・治療
症状
心不全の症状は、どの心室が障害されているか、症状の進行段階により異なります。
左心不全の症状:呼吸困難は最も典型的な症状です。特に労作時呼吸困難(運動や労働で息切れが起こる)が初期症状です。進行すると、起坐呼吸(仰臥位では呼吸困難となり、座位になると改善)が起こります。さらに進行すると、夜間発作性呼吸困難(夜間、睡眠中に激しい呼吸困難で目が覚める)が起こります。
また、咳嗽(咳)が起こり、特に夜間に悪化することが多いです。咳が続くと、ピンク色の泡沫状の痰(ピンク痰)が出ることもあり、これは肺浮腫が高度であることを示す危険な兆候です。
その他の症状として、倦怠感、疲労感、労作不耐性(ちょっとした活動で疲れてしまう)があります。
右心不全の症状:末梢浮腫(足首や下肢の浮腫)が典型的です。仰臥位で長時間いると、仙骨部浮腫も起こります。
肝腫大により、腹部に違和感を感じたり、食欲不振が起こったりします。さらに肝機能が低下すると、黄疸(皮膚や白眼が黄色くなる)が出現します。
頸静脈怒張(首の静脈が膨らむ)が起こります。これは、右心房圧が上昇して、大静脈内の圧が上昇している証拠です。
腹水が貯留すると、腹部が膨張し、嘔気や食欲不振が悪化します。
急性心不全の症状は、より劇的です。突然の激しい呼吸困難、喘鳴(ゼーゼーという音)、ピンク痰、冷汗、不安などが起こります。これは肺水腫の状態であり、生命を脅かす緊急事態です。
診断
心不全の診断には、症状、身体所見、検査所見が組み合わせられます。
身体所見:聴診で、両側肺底部にラ音(バチバチという音)が聴取されます。また、心尖拍動が左下方に移動し、心膜摩擦音が聴取されることもあります。頸静脈怒張、肝腫大、末梢浮腫、肝頸静脈逆流圧の上昇などが認められます。
胸部X線検査:肺うっ血を示す特徴的な所見として、肺血管陰影の増強、Kerley B線(肺野の下部に見られる横方向の線)、心拡大(心胸郭比の増大)、胸水が認められます。
心電図検査:左心室肥大、心房細動などの所見が認められます。ただし、心不全の診断に特異的ではありません。
心臓超音波検査:心不全診断において最も重要な検査です。左心室駆出率(LVEF)の測定により、収縮機能の程度を評価し、心不全を以下のように分類します。
- HFrEF(心不全 with reduced EF):LVEF ≤40%
- HFmrEF(心不全 with mildly reduced EF):LVEF 41~49%
- HFpEF(心不全 with preserved EF):LVEF ≥50%(拡張機能障害が主体)
また、心室のサイズ、弁の状態、壁運動異常の有無なども評価されます。
血液検査:BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)またはNT-proBNPの測定が重要です。これは、心不全の重症度を反映するバイオマーカーであり、心不全の診断と治療効果の評価に用いられます。また、電解質(特にカリウム)、腎機能、肝機能も評価され、治療方針の決定に役立ちます。
冠動脈造影検査:心筋梗塞が原因と疑われる場合に行われます。
心臓MRI検査:心筋症や心筋炎が疑われる場合に、診断に役立ちます。
治療
心不全の治療は、基礎疾患の治療と、心不全症状の軽減の二つの柱からなります。
基礎疾患の治療:冠動脈疾患、高血圧、弁膜症などの基礎疾患を治療することが、心不全の進行を遅延させる最重要課題です。
薬物療法は心不全治療の中心です。
ACE阻害薬またはアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB):血管を拡張させ、心臓への負荷を軽減し、心室リモデリングを抑制します。ほぼすべての心不全患者さんに推奨されます。
ベータ遮断薬:心筋の過度な交感神経刺激を抑制し、心筋を保護し、心不全の進行を遅延させます。ほぼすべての心不全患者さんに推奨されます。
ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MRA):アルドステロンの作用を遮断し、心室リモデリングを抑制し、死亡率を低下させます。
利尿薬:特に症状のある患者さんで、肺うっ血や末梢浮腫を改善させるために使用されます。ただし、過度な利尿は、血液量の減少と腎機能悪化を招くため、注意が必要です。
強心薬:急性心不全や、重篤な心原性ショック患者さんに、一時的に使用されます。ただし、長期使用は死亡率を増加させるため、短期間の使用が原則です。
SGLT2阻害薬:比較的新しい薬剤であり、心不全患者さんの予後を改善することが報告されており、最近の治療ガイドラインで推奨度が高まっています。
その他の薬剤:抗凝固薬(心房細動がある場合)、抗血小板薬(冠動脈疾患がある場合)などが必要に応じて使用されます。
非薬物療法:
ICD(植え込み型除細動器)やCRT(心臓再同期療法装置)などのデバイス治療は、重篤な不整脈のリスクがある患者さんや、心室間の電気的非同期がある患者さんに検討されます。
機械的補助循環装置(大動脈バルーンパンピング、人工心肺、左心室補助装置)は、重篤な急性心不全や、心原性ショック患者さんに、一時的または長期的に使用されます。
心臓移植は、すべての内科的治療に反応しない末期心不全患者さんに対する最終手段です。ただし、ドナー不足が大きな課題です。
生活習慣改善:
塩分制限(1日6g未満)、水分制限(症状に応じて)、禁煙、適度な運動、ストレス管理、体重管理などが重要です。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 知識不足:疾患、危険因子、治療、生活管理について
- 呼吸困難に伴う不安
- 身体活動制限に対する心理的苦痛
- 薬物療法と生活管理の継続困難
- 塩分制限食の受け入れ困難
- 心不全悪化に対する不安
- 死への恐怖
- 社会的役割喪失に伴う抑うつ症状
- 性的機能障害
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚-健康管理パターンでは、患者さんが心不全をどの程度重大な問題と認識しているか、また治療と自己管理の必要性をどの程度理解しているかが重要です。無症状の段階では治療の必要性を感じない患者さんもいますが、心不全は進行性疾患であり、継続的な管理が生命を守ることを理解させることが重要です。
栄養-代謝パターンでは、塩分摂取が心不全の悪化を直接招くため、詳細な食生活聴取と塩分制限の理解が極めて重要です。また、体重管理も重要です。
活動-運動パターンでは、心不全により身体活動が制限される患者さんが多いため、現在の活動量と、患者さんが感じる活動制限の程度を評価することが重要です。
認識-認知パターンでは、患者さんが呼吸困難や倦怠感をどのように受け止めているか、また将来への不安や絶望感がないか把握することが重要です。
ストレス-対処パターンでは、ストレスが心不全の悪化を招く可能性があるため、患者さんのストレス源と対処方法を評価します。
睡眠-休息パターンでは、夜間発作性呼吸困難により睡眠が阻害されていないか、あるいは過度に睡眠をとっていないか把握します。
値値-信念パターンでは、患者さんが治療の受け入れ可能性と、人生における優先順位をどのように考えているか評価します。
ヘンダーソン14基本的ニード
呼吸は心不全患者さんにおいて最も重要なニードです。呼吸困難の程度、起坐呼吸の有無、咳嗽の有無などを継続的に評価し、呼吸困難が増悪していないか監視することが、心不全悪化の早期発見につながります。
栄養と水分では、塩分制限が最優先です。患者さんの食習慣を詳細に理解し、実行可能な塩分制限目標を立てることが重要です。また、利尿薬を使用している患者さんでは、電解質異常(特にカリウム低下)に注視する必要があります。
排泄では、利尿薬の効果により排尿量が増加するため、排尿パターンの評価が重要です。また、便秘による過度な力みが、心不全を悪化させる可能性があるため、排便管理も重要です。
活動と運動では、医師の指示に基づいた段階的な運動が心機能の改善につながることを患者さんに理解させ、過度に活動を制限しないよう支援することが重要です。一方で、症状が悪化している時期には、安静が指示される場合もあります。
個人の衛生と身だしなみでは、体重測定が毎日、同じ時間に行われることが重要です。急激な体重増加(1~2kg/日以上)は、水分貯留を示し、心不全悪化の警告信号です。
危機的状況への安全として、激しい呼吸困難、ピンク痰、胸痛などの症状が出現した場合は、緊急対応が必要です。
看護計画・介入の内容
- 心不全の疾患概要と進行性に関する教育:患者さんが心不全の本質を理解することが、治療と自己管理への協力につながります。「心不全は、心臓のポンプ機能が低下した状態であり、継続的な医学的管理がなければ進行する可能性がある」ということを、図や動画を用いてわかりやすく説明します。
- 呼吸困難時の対処方法の教育:呼吸困難が起こった場合、座位または半座位になることで症状が改善することを説明し、患者さんが主体的に対応できるよう支援します。夜間に呼吸困難が起こるリスクがある患者さんには、複数の枕を用意するなど、半座位が保たれるようにすることが重要です。
- 塩分制限食への具体的支援:心不全患者さんにおいて、塩分制限は薬物療法と同等かそれ以上に重要です。患者さんの現在の食塩摂取量を詳細に把握し、実行可能な塩分制限目標を立てます。具体的には、「毎日食べている味噌汁の量を減らす」「外食の頻度を減らす」「調味料の量を計る」など、日常生活の中で実現可能な小さな改善を積み重ねることが重要です。栄養士との連携が有効です。
- 体重管理と日々の体重測定の習慣づけ:毎日同じ時間(朝の起床後、排尿・排便後)に、同じ体重計で体重を測定し、記録する習慣をつけることが重要です。「1日で1~2kg以上の体重増加」は、水分貯留を示し、塩分摂取の増加や利尿薬の不十分さを示す警告信号です。患者さんが体重変化を「数値」で認識できるようになることで、自己管理への動機づけが高まります。
- 薬物療法の継続支援:ACE阻害薬、ARB、ベータ遮断薬、利尿薬などの心不全治療薬は、長期的な継続が予後を左右する最重要因子です。「症状がないから」「副作用がある」という理由で患者さんが勝手に中止することのないよう、各薬剤の役割と継続の重要性を繰り返し説明することが重要です。
- 利尿薬の役割と効果の理解:利尿薬は、肺うっ血と末梢浮腫を改善させる重要な薬剤です。「薬を飲むと尿が増えて不便」という理由で中止する患者さんもいますが、利尿薬の役割と重要性を理解させることが重要です。
- 定期受診の重要性の強調:心不全患者さんは、定期的に医師の診察を受け、症状の変化、体重変化、検査所見により、治療方針を調整する必要があります。患者さんが自己判断で受診を中止することがないよう、定期受診の必要性を強調します。
- 適度な運動と活動の段階的復帰支援:心不全患者さんが過度に活動を制限することは、却って心機能の悪化につながります。医師の指示に基づいた、患者さんが安全に行える運動を提案し、段階的な運動習慣の確立を支援します。
- ストレス管理と瞑想・リラクゼーション技法の提案:ストレスは心不全の悪化を招く可能性があるため、患者さんが実践可能なストレス軽減法を提案することが重要です。
- 電解質異常(特にカリウム低下)の認識と食事療法:利尿薬使用中の患者さんでは、電解質異常、特にカリウム低下が起こりやすいため、血液検査の定期的な監視が必要です。必要に応じて、カリウム補給薬やカリウム保持利尿薬の調整が行われます。患者さんには、カリウムを含む食品(バナナ、アボカド、野菜など)の摂取を勧めることができます。
- 心不全悪化の早期警告信号の認識:患者さんが「呼吸困難の増悪、夜間発作性呼吸困難の出現、体重の急激な増加(1日で1~2kg以上)、下肢浮腫の増加、倦怠感の増加」などの警告信号を認識し、これらの症状が出現した場合に医師に報告することの重要性を強調します。
- 心房細動がある患者さんへの抗凝固薬管理教育:心房細動がある心不全患者さんは、脳梗塞のリスクが高いため、抗凝固薬の継続が重要です。患者さんに薬の役割と継続の重要性を説明します。
- ICD(植え込み型除細動器)やCRT(心臓再同期療法装置)などのデバイス治療に対する心理的サポート:デバイス治療を勧められた患者さんは、不安を感じることが多いため、治療の必要性と予後について、わかりやすく説明することが重要です。
- 心理的サポートと抑うつ症状への対応:心不全患者さんの中には、疾患の慢性性と身体活動の制限により、心理的な落ち込みと抑うつ症状を示す患者さんが多くいます。精神保健専門家の介入が重要です。
- 家族への教育とサポート体制の構築:心不全患者さんの家族も、患者さんと同様に大きなストレスを経験します。食事準備における塩分制限への協力、患者さんの心理的サポート、症状悪化時の対応などについて、家族全体での支援体制を構築することが重要です。
よくある疑問・Q&A
Q: 心不全と診断されたのですが、これは治る病気ですか?
A: 心不全は、残念ながら「完全に治る」病気ではなく、「コントロールすることができる慢性疾患」です。ただし、「治らない=死に至る」という意味ではありません。適切な医学的管理と生活習慣改善により、多くの心不全患者さんは良好な生活の質を保ちながら、長く生存することが可能です。重要なのは、生涯にわたって医学的管理と自己管理を継続することです。
Q: 心不全があると、運動をしてはいけませんか?
A: 医師の許可があれば、適度な運動は、むしろ心機能の改善に有益です。長期間の研究により、心不全患者さんが定期的な運動プログラムに参加することで、運動耐容能が改善し、症状が軽減されることが報告されています。重要なのは、「息切れしない程度」「症状が悪化しない程度」という個人の身体反応を指標に活動することです。医師に「どの程度の運動が安全か」を確認することをお勧めします。
Q: 塩分をゼロにしなければいけませんか?
A: いいえ。完全に塩分をゼロにする必要はありません。1日6g未満が推奨目標です。これは、通常の一般人の塩分摂取量(約10g/日)より少ないですが、「塩辛い食事を避ける」「調味料の量を計る」「加工食品を避ける」などの工夫により、達成可能な目標です。完全な塩分除去は、生活の質を著しく低下させ、かえって患者さんのアドヒアランス(治療継続)を損なうため、現実的で継続可能なレベルの塩分制限が推奨されます。
Q: 利尿薬を飲むと尿が増えて、頻繁にトイレに行かなければいけません。仕事の支障になります。
A: 利尿薬による頻尿は、多くの患者さんが経験する課題です。ただし、利尿薬は肺うっ血と末梢浮腫を改善させ、心不全症状を軽減させる重要な薬剤です。医師に相談すれば、利尿薬の用量や用法を調整することで、症状軽減と日常生活への影響のバランスを取ることが可能な場合もあります。また、早朝に利尿薬を服用することで、夜間の頻尿を減らす工夫も可能です。医師や薬剤師に相談することをお勧めします。
Q: 体重が1kg増えました。これは危険ですか?
A: 1日単位での1kg程度の体重変動は、通常範囲内です。重要なのは、「短期間(数日)での急激な体重増加(1日で1~2kg以上)」です。このような体重増加は、水分貯留を示し、塩分摂取の増加や利尿薬の不十分さ、あるいは心不全の悪化を示す可能性があります。毎日体重を測定し、体重の変化の傾向を把握することが重要です。
Q: 心不全があると、妊娠・出産はできませんか?
A: 心不全の程度により異なります。軽度の心不全で、心機能が比較的保たれている場合は、医師の厳密な管理下での妊娠・出産が可能なことがあります。しかし、重篤な心不全や、心機能が著しく低下している場合は、妊娠による追加の心臓への負荷が危険になるため、妊娠が勧められないこともあります。妊娠を希望する場合は、心臓内科医と産婦人科医の両者による慎重な事前相談が必須です。
Q: 心不全があると、飛行機に乗ることができますか?
A: 安定した軽度~中等度の心不全であれば、医師の許可があれば飛行機搭乗は可能です。ただし、気圧低下により酸素供給が若干低下するため、症状が重い患者さんや、不安定な心不全患者さんは避けるべきです。長時間フライトでは、深部静脈血栓症のリスクもあるため、定期的な足首の運動や歩行が勧められます。旅行前に医師に相談し、緊急時の対応方法を確認することが重要です。
Q: 心不全があると、性的活動はできませんか?
A: 安定した心不全患者さんであれば、医師の許可があれば、多くの場合性的活動は可能です。ただし、呼吸困難が激しい時期には、避けるべきです。患者さんや配偶者が性的活動について不安を感じている場合は、医師に相談することをお勧めします。
Q: 心不全の患者さんが仕事に戻ることはできますか?
A: 多くの場合、可能です。ただし、心不全の程度と、患者さんの職業の性質により異なります。肉体的に軽い仕事(デスクワークなど)であれば、比較的早期に復帰が可能なことが多いです。一方、肉体的に重い仕事や、ストレスが極めて多い仕事の場合は、復帰がより遅れることもあります。医師と相談して、患者さんの心臓の状態と職業の性質に基づいた、現実的な職場復帰計画を立てることが重要です。
Q: 心不全の患者さんが呼吸困難で目が覚めました。何をしたらよいですか?
A: これは夜間発作性呼吸困難の症状である可能性があります。患者さんを座位または半座位にすることが最優先です。複数の枕を使用して、半座位が保たれるようにします。また、新鮮な空気を吸わせることも重要です。症状が改善しない場合や、激しい呼吸困難が続く場合は、躊躇なく119番通報することが重要です。これは医学的緊急事態を示す可能性があります。
まとめ
心不全は、最初は無症状で進行し、気づいた時には生活の質が大きく低下している可能性のある、進展性で慢性的な疾患です。一度診断されたら、生涯にわたって医学的管理と自己管理が必要になります。
看護の最大の課題は、患者さんが心不全の慢性性を理解し、継続的な医学的フォローアップと生活習慣改善を受け入れるよう支援することです。特に、初期段階で無症状の患者さんには、治療と管理の必要性を理解させることが難しいことが多いため、丁寧で繰り返しの教育が重要です。
塩分制限は、薬物療法と同等かそれ以上に重要です。患者さんのライフスタイルと食習慣を理解し、実行可能で継続可能な小さな改善を一緒に進めることが、長期的な心不全管理の成功を左右します。
体重測定の習慣づけにより、患者さんが「数値」で自分の体の変化を認識できるようになることで、自己管理への動機づけが高まり、心不全の悪化を早期に発見できるようになります。
呼吸困難や倦怠感により、患者さんの身体活動が大きく制限される場合が多いです。この身体活動の制限が、患者さんの心理的な落ち込みと抑うつ症状につながることがあります。看護師は、患者さんの心理的なサポートと同時に、医師の指示に基づいた段階的な運動復帰により、患者さんが心機能の改善と、心理的な自信の回復を経験できるよう支援することが重要です。
心不全患者さんの家族も、患者さんと同様に大きなストレスを経験します。食事準備における塩分制限への協力、患者さんの心理的サポート、症状悪化時の緊急対応など、家族全体での支援体制を構築することが、患者さんの長期的な予後と生活の質を大きく左右します。
実習では、様々な症状を呈する心不全患者さんと向き合い、呼吸困難のある患者さんへの対応、塩分制限を受け入れ難い患者さんへの教育、そして生活の質を保ちながら病と向き合う患者さんをサポートすることの本質を学ぶ貴重な機会になるでしょう。
免責事項
・本記事は教育・学習目的の情報提供です。 ・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません。 ・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください。 ・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります。 ・本記事を課題としてそのまま提出しないでください。 ・正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
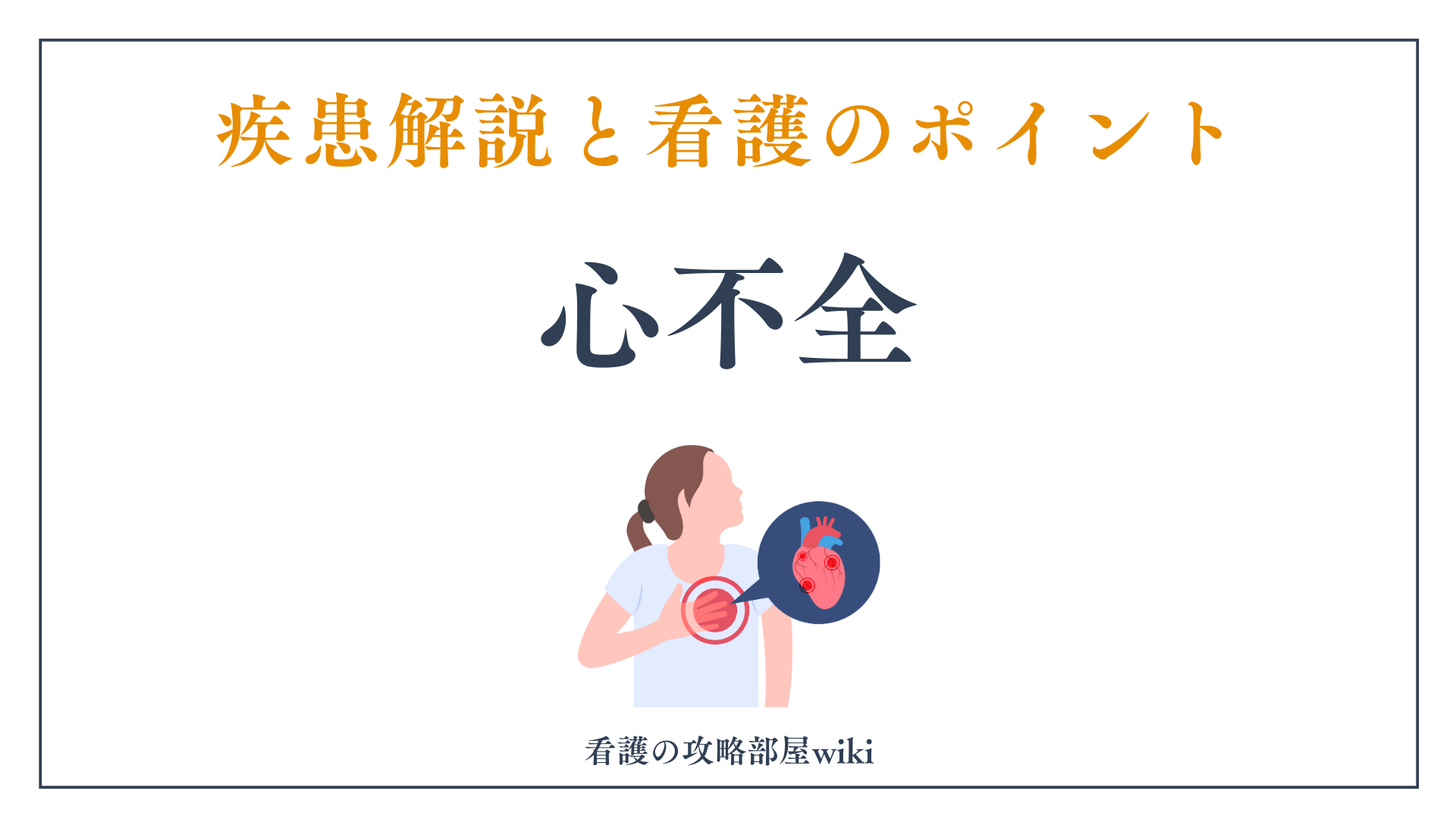

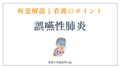
コメント