疾患概要
定義
深部静脈血栓症(Deep Vein Thrombosis: DVT)は、主に下肢の深部静脈内に血栓が形成される疾患です。血栓は通常、ふくらはぎの静脈から始まり、膝窩静脈、大腿静脈、さらには腸骨静脈や下大静脈へと進展することがあります。
この疾患の最も重大な合併症は肺血栓塞栓症(PE: Pulmonary Embolism)です。形成された血栓が血流に乗って肺動脈に運ばれ、肺動脈を閉塞することで突然死を引き起こす可能性があります。深部静脈血栓症と肺血栓塞栓症を合わせて静脈血栓塞栓症(VTE: Venous Thromboembolism)と呼び、予防と早期発見が極めて重要な疾患です。
疫学
日本における深部静脈血栓症の年間発症率は、人口10万人あたり約10〜20人とされていますが、高齢化に伴い増加傾向にあります。特に整形外科手術(人工股関節置換術、人工膝関節置換術など)や婦人科手術、がん手術などの術後に発症リスクが高まります。
発症年齢は幅広く、若年者から高齢者まで見られますが、加齢とともに発症率は上昇します。性別では、若年者ではエストロゲン製剤の使用や妊娠・出産の影響で女性にやや多く、高齢者では男女差は少なくなります。
近年、長時間同じ姿勢でいることによる発症(いわゆる「エコノミークラス症候群」)も注目されており、長距離フライトだけでなく、災害時の車中泊や長時間のデスクワークでも発症することが知られています。
原因
深部静脈血栓症の発症メカニズムは、Virchow(ウィルヒョウ)の三徴として知られる3つの要因で説明されます。
血流のうっ滞は、長期臥床、長時間の同一姿勢(手術中、長距離移動、車椅子使用など)、下肢の麻痺、心不全などで生じます。血流が停滞することで血液が凝固しやすくなります。
血管内皮の障害は、外傷、手術、カテーテル留置、静脈炎などによって引き起こされます。血管内皮が傷つくと、そこに血小板が集積し血栓形成の引き金となります。
血液凝固能の亢進は、先天性凝固異常症、悪性腫瘍、妊娠・産褥期、経口避妊薬やホルモン補充療法の使用、脱水、炎症性疾患などで生じます。
これらの要因が単独または複合的に作用することで血栓が形成されます。特に手術患者では、手術侵襲による凝固能亢進、術中・術後の長時間臥床による血流うっ滞、血管損傷という3要因が揃うため、高リスクとなります。
その他の危険因子として、高齢、肥満、喫煙、深部静脈血栓症の既往、静脈瘤、下肢外傷や骨折なども挙げられます。
病態生理
深部静脈血栓症の発症は、静脈内での血栓形成から始まります。
まず、血流のうっ滞や血管内皮の障害が起こると、その部位で血小板の活性化と凝固因子の活性化が連鎖的に起こります。これによりフィブリン網が形成され、赤血球や血小板が取り込まれて血栓が成長していきます。
血栓は通常、下腿の深部静脈(ヒラメ筋静脈、腓腹筋静脈など)で形成されることが多く、これを末梢型DVTと呼びます。この段階では無症状のこともありますが、血栓が膝窩静脈や大腿静脈に進展すると症状が顕著になります。
血栓によって静脈が閉塞すると、その末梢側で静脈還流が障害されます。これにより、下肢に血液が貯留し、静水圧が上昇して組織間液が増加します。その結果、下肢の腫脹、疼痛、発赤、熱感などの炎症徴候が出現します。
形成された血栓には、器質化(線維化して血管壁に固着)する血栓と、遊離しやすい浮遊血栓があります。特に新鮮な血栓は血管壁への付着が弱く、血流に乗って剥がれやすい状態です。この遊離した血栓が静脈系を通って右心房、右心室を経て肺動脈に到達すると、肺血栓塞栓症を発症します。
肺動脈が血栓で閉塞されると、肺での酸素交換が障害され、低酸素血症や呼吸困難が生じます。さらに、閉塞の程度が大きいと右室への負荷が増大し、循環不全やショック状態に陥ることがあります。大きな血栓が主肺動脈や両側肺動脈を閉塞した場合、心停止や突然死に至ることもあります。
慢性期には、血栓が器質化して静脈弁が破壊されると、静脈還流障害が持続し深部静脈血栓後症候群(PTS: Post-Thrombotic Syndrome)を発症することがあります。これにより慢性的な下肢腫脹、疼痛、皮膚色素沈着、難治性潰瘍などが生じ、QOLが大きく低下します。
症状・診断・治療
症状
深部静脈血栓症の症状は、血栓の部位や範囲によって異なり、無症状のこともあります。
典型的な症状としては、片側下肢の腫脹が最も特徴的です。左右の下腿周囲径を比較すると、患側が明らかに太くなっています。腫脹は急激に出現することもあれば、徐々に進行することもあります。
疼痛も重要な症状で、ふくらはぎの痛みや圧痛、足関節の背屈時痛(Homans徴候)が見られることがあります。ただし、Homans徴候は感度が低く、必ずしも陽性になるとは限りません。
皮膚の変化として、患側下肢の発赤、熱感、表在静脈の怒張などが見られます。広範囲の血栓では、皮膚がチアノーゼ様に暗紫色になることもあります。
下肢の緊満感や重だるさを訴える患者も多く、特に立位や歩行時に症状が増強します。
重症例では、股関節から足先まで全体が腫脹し、皮膚が白色または青紫色になる有痛性白股腫や有痛性青股腫と呼ばれる状態になることがあります。これは緊急性の高い状態です。
注意すべきは、無症状例も多いということです。特に末梢型の小さな血栓では症状が軽微で見過ごされやすく、突然の肺血栓塞栓症で初めて診断されることもあります。
肺血栓塞栓症を合併した場合は、突然の呼吸困難、胸痛、動悸、冷汗、失神などが出現します。これらの症状が見られた場合は直ちに医師に報告する必要があります。
診断
深部静脈血栓症の診断は、臨床症状、血液検査、画像検査を組み合わせて行われます。
臨床評価では、Wells スコアなどの臨床予測ルールを用いてDVTの可能性を評価します。下肢の腫脹、疼痛、圧痛の有無、危険因子の有無などをスコア化し、検査前確率を判定します。
Dダイマーは、血栓が形成され溶解される際に産生されるフィブリン分解産物で、DVTのスクリーニング検査として有用です。陰性的中率が高く、Dダイマーが正常値であればDVTの可能性は低いと判断できます。ただし、手術後、外傷、感染症、悪性腫瘍など、血栓以外の原因でも上昇するため、特異度は低く、陽性の場合は必ず画像検査で確認する必要があります。
超音波検査(下肢静脈エコー)は、非侵襲的で繰り返し実施できるため、第一選択の画像検査です。血栓の有無、部位、範囲を評価でき、圧迫法で静脈が圧迫されない場合は血栓の存在が示唆されます。カラードップラー法では血流の評価も可能です。
造影CT(CT静脈造影)は、腸骨静脈や下大静脈など、超音波検査で評価しにくい中枢側の血栓の診断に有用です。また、同時に肺血栓塞栓症の有無も評価できます。
静脈造影は、造影剤を静脈内に注入してX線撮影を行う検査で、診断の gold standard とされていますが、侵襲的であるため現在ではあまり行われていません。
診断確定後は、血栓の範囲を正確に評価し、治療方針を決定します。また、肺血栓塞栓症の合併がないかも必ず確認します。
治療
深部静脈血栓症の治療目標は、血栓の進展防止、肺血栓塞栓症の予防、深部静脈血栓後症候群の予防です。
抗凝固療法が治療の中心となります。急性期には、ヘパリン(未分画ヘパリンまたは低分子量ヘパリン)の静脈内投与または皮下注射を開始します。ヘパリンは即効性があり、血栓の進展を迅速に抑制します。同時に、ワルファリンなどの経口抗凝固薬の投与も開始し、効果が得られるまでヘパリンを併用します。
近年では、直接経口抗凝固薬(DOAC)が使用されることも増えています。DOACには、リバーロキサバン、アピキサバン、エドキサバン、ダビガトランなどがあり、ワルファリンと異なり定期的な血液検査や用量調整が不要で、食事制限も少ないという利点があります。
抗凝固療法の期間は、通常3〜6ヶ月以上ですが、血栓の原因や再発リスクによって個別に決定されます。手術などの一時的な危険因子による場合は3ヶ月程度、原因不明や再発例では長期投与が検討されます。
弾性ストッキング(段階的圧迫ストッキング)の着用は、下肢の腫脹を軽減し、深部静脈血栓後症候群の予防に有効です。ただし、急性期で血栓が不安定な場合や動脈閉塞性疾患がある場合は禁忌となることがあります。
下大静脈フィルターは、抗凝固療法が禁忌または無効な場合、または広範囲の近位部血栓で肺血栓塞栓症のリスクが非常に高い場合に留置されます。下大静脈内にフィルターを留置することで、血栓が肺動脈に到達するのを物理的に防ぎます。
血栓溶解療法は、広範囲の腸骨大腿静脈血栓で重症循環障害がある場合に検討されます。カテーテルを血栓部位まで挿入し、血栓溶解薬を直接投与する方法もあります。ただし、出血のリスクがあるため、適応は慎重に判断されます。
早期離床と運動は、かつては禁忌とされていましたが、現在では抗凝固療法開始後の早期離床が推奨されています。適切な圧迫療法と抗凝固療法を行えば、早期離床によって肺血栓塞栓症のリスクが増加することはなく、むしろ症状の改善が早まるとされています。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 非効果的組織灌流(末梢性):深部静脈の血栓形成による静脈還流障害に関連
- 急性疼痛:血栓形成による静脈の炎症と組織腫脹に関連
- 活動耐性低下:下肢疼痛、腫脹、および安静指示に関連
- 出血リスク状態:抗凝固療法による凝固機能の変化に関連
- 非効果的健康管理:疾患、治療、予防方法に関する知識不足に関連
- 不安:肺血栓塞栓症や突然死への恐怖に関連
ゴードン機能的健康パターン
深部静脈血栓症の患者をアセスメントする際、以下のパターンが特に重要になります。
健康知覚-健康管理パターンでは、DVTの危険因子(手術歴、長期臥床、がん、ホルモン剤使用、深部静脈血栓症の既往など)を詳しく聴取します。患者が疾患の重大性、特に肺血栓塞栓症のリスクを理解しているかを確認します。抗凝固療法中の患者では、服薬アドヒアランスや出血傾向への注意についても評価します。
活動-運動パターンでは、発症前の活動レベル、最近の長時間の同一姿勢(長距離移動、手術、臥床など)の有無を確認します。現在の下肢症状(腫脹、疼痛)が日常生活動作にどの程度影響しているかを評価します。また、弾性ストッキングの着用状況や足関節の運動実施状況も確認します。
栄養-代謝パターンでは、脱水の有無を評価します。水分摂取量や尿量、皮膚の乾燥状態などを確認します。ワルファリン服用中の場合は、ビタミンK含有食品(納豆、青汁、クロレラなど)の摂取状況も重要です。また、抗凝固療法による出血傾向の徴候(歯肉出血、鼻出血、皮下出血、血尿、血便など)を詳細に観察します。
認知-知覚パターンでは、下肢の疼痛の評価が重要です。疼痛の部位、性質、程度、増悪・軽減因子を詳しく聴取します。突然の胸痛や呼吸困難など、肺血栓塞栓症を疑う症状の有無も確認します。
睡眠-休息パターンでは、下肢疼痛による睡眠障害の有無、不安による睡眠の質の低下などを評価します。
コーピング-ストレス耐性パターンでは、突然の発症や入院、肺血栓塞栓症への恐怖などによる心理的ストレスを評価します。患者の不安のレベルや対処方法、サポートシステムの有無を確認します。
役割-関係パターンでは、活動制限や入院による社会的役割への影響、家族のサポート体制を評価します。特に長期の抗凝固療法が必要な場合、通院や内服管理における家族の協力体制も重要です。
ヘンダーソン14基本的ニード
深部静脈血栓症の患者では、以下のニードへの援助が特に重要です。
正常な呼吸に関しては、肺血栓塞栓症の早期発見が最優先です。呼吸困難、頻呼吸、胸痛、チアノーゼなどの徴候を見逃さないよう、定期的に観察します。深呼吸や咳嗽を促し、肺合併症の予防も図ります。
適切な飲食では、抗凝固療法中の食事指導が重要です。ワルファリン服用中の場合、納豆、青汁、クロレラなどビタミンKを多く含む食品は効果を減弱させるため避けるよう指導します。また、脱水予防のため十分な水分摂取を促します。ただし、心不全などの合併症がある場合は水分制限も考慮します。
身体の排泄については、抗凝固療法中は血便や血尿などの出血徴候を確認します。便秘によるいきみは静脈圧を上昇させるため、排便コントロールも重要です。
身体の位置の保持と動作では、急性期の安静と早期離床のバランスが重要です。医師の指示に基づいて適切な時期に離床を開始し、下肢の筋ポンプ作用を促進します。ベッド上では患側下肢を挙上し、静脈還流を促進します。足関節の屈伸運動や膝の曲げ伸ばしなど、ベッド上でできる運動を指導します。
睡眠と休息では、疼痛コントロールや患側下肢の挙上などにより、快適な睡眠環境を整えます。不安が強い場合は傾聴し、必要に応じて医師と相談して睡眠薬の使用も検討します。
適切な衣類の選択では、弾性ストッキングの正しい着用方法を指導します。サイズが適切か、しわができていないか、つま先が圧迫されていないかなどを確認します。また、締め付けの強い衣類や下着は静脈還流を妨げるため避けるよう指導します。
身体を清潔に保ち、皮膚を保護するでは、弾性ストッキング着用中の皮膚トラブル(発赤、水疱、潰瘍など)に注意します。毎日ストッキングを脱いで皮膚の状態を観察し、保湿を行います。
危険を避けるでは、抗凝固療法による出血リスクへの対応が重要です。転倒による外傷を避けるため、環境整備や歩行時の注意喚起を行います。また、肺血栓塞栓症の徴候を早期に発見し、緊急対応できるよう準備します。
他者とのコミュニケーションでは、患者の不安や恐怖を傾聴し、疾患や治療についての正しい理解を促します。突然の発症や予期せぬ入院により戸惑っている患者に寄り添い、心理的支援を提供します。
看護計画・介入の内容
- 下肢の観察とモニタリング:患側と健側の下腿周囲径を測定し、左右差を評価します。皮膚色、温度、表在静脈の怒張、浮腫の程度を観察します。疼痛の部位や程度も定期的に評価し、症状の変化を早期に発見します
- 肺血栓塞栓症の徴候の監視:呼吸状態(呼吸数、呼吸困難、胸痛、チアノーゼ)、バイタルサイン(頻脈、血圧低下、SpO2低下)を頻回に観察します。突然の呼吸困難、胸痛、動悸、冷汗、意識レベル低下などが出現した場合は、肺血栓塞栓症の可能性を考え、直ちに医師に報告し緊急対応します
- 抗凝固療法の管理:処方された抗凝固薬を確実に投与します。ヘパリン投与中はAPTTを、ワルファリン投与中はPT-INRを定期的にモニタリングし、目標値内にコントロールされているか確認します。過剰投与による出血リスクと過少投与による血栓進展リスクのバランスを考慮します
- 出血徴候の観察:皮下出血、歯肉出血、鼻出血、血尿、血便、喀血、吐血、性器出血などの出血徴候がないか全身を観察します。検査データ(ヘモグロビン、ヘマトクリット)の変化もモニタリングします。出血が認められた場合は速やかに医師に報告します
- 患側下肢の挙上と体位管理:患側下肢を心臓より高い位置に挙上し、静脈還流を促進して浮腫の軽減を図ります。膝下にクッションを入れる際は、膝窩部を圧迫しないよう注意します。長時間同じ体位を避け、適宜体位変換を行います
- 弾性ストッキングの着用支援:医師の指示に基づき、適切な圧迫圧とサイズの弾性ストッキングを選択します。朝、起床時(浮腫が軽度のとき)に着用し、就寝時は脱ぐよう指導します。着用方法を実演し、しわができないよう丁寧に着用することの重要性を説明します。着用中の皮膚トラブルがないか定期的に確認します
- 下肢運動の促進:ベッド上で足関節の背屈・底屈運動、膝の屈伸運動を定期的に行うよう指導します。これらの運動は下肢の筋ポンプ作用を促進し、静脈還流を改善します。離床可能になったら、医師の指示のもと段階的に歩行を開始し、長時間の立位や座位は避けるよう指導します
- 疼痛管理:鎮痛薬を適切に使用し、疼痛をコントロールします。ただし、抗凝固療法中は非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の使用が出血リスクを高めることがあるため、医師と相談して使用します。患側下肢の挙上や冷罨法も疼痛緩和に有効です
- 脱水予防:十分な水分摂取を促し、脱水を予防します。ただし、心疾患などで水分制限がある場合は医師の指示に従います。尿量や皮膚の状態も観察し、脱水の徴候がないか確認します
- 患者教育:疾患の病態、肺血栓塞栓症のリスク、抗凝固療法の重要性と出血リスクについて説明します。ワルファリン服用中の食事制限(納豆、青汁など)や、DOAC服用中の注意点も具体的に指導します。退院後も定期受診と内服継続の必要性を強調します
- 出血予防指導:転倒予防のための環境整備、髭剃りは電気シェーバーを使用する、歯ブラシは柔らかいものを使用する、鼻を強くかまない、便秘を避けるなど、日常生活での出血予防策を指導します
- 深部静脈血栓症再発予防指導:長時間の同一姿勢を避ける、適度な運動を続ける、脱水を避ける、弾性ストッキングの継続着用(必要に応じて)などを指導します。長距離移動時は適宜休憩して歩く、機内では足関節運動を行うなど、具体的な予防策を提案します
- 心理的支援:突然の発症や肺血栓塞栓症への恐怖、長期の抗凝固療法への不安などに対して傾聴し、患者の気持ちを受け止めます。正確な情報提供により不安を軽減し、前向きに治療に取り組めるよう支援します
- 家族への支援:家族にも疾患や治療について説明し、患者の服薬管理や出血徴候の観察を支える体制を整えます。緊急時の対応方法や連絡先も明確にします
よくある疑問・Q&A
Q: 深部静脈血栓症と表在静脈血栓症の違いは何ですか?
A: 深部静脈血栓症(DVT)は筋肉の深層を走る静脈(深部静脈)に血栓ができる疾患で、肺血栓塞栓症の原因となるため重大です。一方、表在静脈血栓症は皮膚の表面近くを走る表在静脈に血栓ができる状態で、一般的には肺血栓塞栓症のリスクは低く、DVTほど重篤ではありません。ただし、表在静脈血栓症が深部静脈に進展することもあるため、注意深い観察が必要です。臨床的には、DVTでは下肢全体の腫脹や深部の疼痛が見られるのに対し、表在静脈血栓症では表在静脈に沿った索状の硬結や圧痛、発赤が特徴的です。実習では、血栓がどの静脈系に存在するかによってリスクが大きく異なることを理解しておきましょう。
Q: 抗凝固療法中の患者が転倒した場合、どのように対応すべきですか?
A: 抗凝固療法中の患者は出血リスクが高いため、転倒時は特に注意深い観察が必要です。まず、患者の意識レベル、バイタルサイン、外傷の有無を確認します。特に頭部を打撲した場合は、頭蓋内出血のリスクがあるため、頭痛、吐き気、意識レベルの変化、瞳孔の異常などの徴候を注意深く観察し、直ちに医師に報告します。外傷部位の腫脹や皮下出血の程度も経時的に観察します。軽微な転倒でも、時間が経過してから出血が顕在化することがあるため、数時間から24時間程度は慎重にモニタリングを継続します。また、転倒の原因を分析し、再発防止策を講じることも重要です。
Q: 弾性ストッキングを嫌がる患者にはどう対応すればよいですか?
A: 弾性ストッキングは締め付け感や暑さから、患者が着用を嫌がることがあります。まず、なぜストッキングが必要なのか、その効果(静脈還流の促進、浮腫の軽減、深部静脈血栓後症候群の予防)を丁寧に説明します。ストッキングを着用しないことで生じる長期的なリスク(慢性的な浮腫、疼痛、皮膚の変色、難治性潰瘍など)についても理解してもらいます。着用感を改善するために、サイズが適切か再確認し、素材や種類の変更を検討します。最近では履き心地の良い製品も増えています。また、着用時間を段階的に延ばす、暑い時期は冷房を活用するなど、工夫を提案します。皮膚トラブルが生じていないか確認し、問題があれば医師と相談します。患者の気持ちに共感しながら、継続の重要性を繰り返し伝えることが大切です。
Q: 肺血栓塞栓症を疑ったとき、最初に何をすべきですか?
A: 肺血栓塞栓症は致命的になり得る緊急事態です。突然の呼吸困難、胸痛、頻脈、血圧低下、SpO2低下、意識レベル低下などの徴候が見られたら、直ちに医師をコールし、応援を呼びます。患者を安静にし、ベッドを挙上して呼吸を楽にします。すぐに酸素投与を開始し、バイタルサインとSpO2を継続的にモニタリングします。静脈ルートが確保されていない場合は確保し、緊急薬剤投与の準備をします。心電図モニターを装着し、不整脈の出現に注意します。患者には落ち着くよう声をかけ、不安を軽減します。医師の到着後は、指示に従って検査(血液ガス分析、Dダイマー、造影CT)や治療(抗凝固療法の強化、血栓溶解療法など)の準備を迅速に行います。このような緊急事態では、冷静かつ迅速な対応が患者の予後を左右します。
Q: 術後患者の深部静脈血栓症予防で、看護師が実施できることは何ですか?
A: 術後の深部静脈血栓症予防は看護師の重要な役割です。まず、早期離床を促進します。医師の許可が出たら、できるだけ早く離床し、ベッド上でも頻繁に体位変換を行います。足関節の背屈・底屈運動や下肢の筋肉を使う運動を指導し、定期的に実施してもらいます。間欠的空気圧迫法(IPC)や弾性ストッキングが処方されている場合は、適切に使用されているか確認します。脱水を予防するため、十分な水分摂取を促します。下肢の観察を定期的に行い、腫脹、疼痛、発赤などのDVTの徴候を早期に発見します。予防的抗凝固薬が処方されている場合は確実に投与し、出血徴候も観察します。また、患者にDVTのリスクと予防の重要性を説明し、自己管理を促します。これらの予防策を組み合わせることで、術後DVTの発症リスクを大きく減らすことができます。
まとめ
深部静脈血栓症は、主に下肢の深部静脈に血栓が形成される疾患で、その本質は血流のうっ滞、血管内皮の障害、血液凝固能の亢進というVirchowの三徴によって説明されます。最も恐ろしい合併症は肺血栓塞栓症であり、血栓が肺動脈を閉塞することで突然死に至る可能性があります。
病態の核心は、静脈内での血栓形成と、その血栓が遊離して肺動脈に到達するリスクです。特に術後、長期臥床、がん患者などはハイリスクであり、予防と早期発見が極めて重要です。
看護の要点は、下肢症状の観察による早期発見、肺血栓塞栓症の徴候の監視、抗凝固療法の適切な管理と出血徴候の観察、弾性ストッキングや下肢運動による予防、患者教育です。特に突然の呼吸困難、胸痛などが出現した場合は、肺血栓塞栓症を疑い直ちに対応する必要があります。
患者教育では、疾患の理解、抗凝固療法の重要性と出血リスクの認識、食事制限(ワルファリンの場合)、再発予防策(長時間の同一姿勢を避ける、脱水予防など)を具体的に指導します。長期の抗凝固療法が必要な場合も多く、継続的な服薬管理と定期受診の重要性を強調します。
実習では、患者の下肢の左右差(腫脹、皮膚色、温度)、疼痛の有無と程度、動脈拍動の確認、呼吸状態、抗凝固療法中の出血徴候の観察を丁寧に行いましょう。予防的ケアの実施状況も確認し、患者が自分でできる予防策を指導することも重要な学びとなります。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。

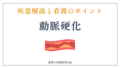
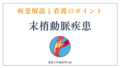
コメント