疾患概要
定義
イレウスとは、腸の内容物が正常に肛門側へ移動できなくなった状態のことです。「腸閉塞」とも呼ばれます。腸の機械的な閉塞(腸が詰まっている状態)と、腸の運動機能が低下している機能的なイレウスに分類されます。実習で出会う機会が多い急性疾患のひとつですね。
疫学
イレウスは全年代で発症しますが、高齢者での発症率が高い傾向にあります。特に70歳以上の高齢者では、癒着や腸捻転による発症が増加します。入院患者における急性腹部疾患の中では比較的頻度の高い疾患で、医療現場で対応する機会は多いでしょう。男女差はほぼありません。
原因
イレウスの原因は大きく分けて二つです。機械的イレウスは腸管内腔が物理的に狭窄・閉塞している状態で、腹部手術後の癒着、ヘルニア嵌頓、腫瘍、腸捻転などが該当します。一方、機能的イレウス(麻痺性イレウス)は腸管の蠕動運動が低下・消失している状態で、術後、腹膜炎、電解質異常、薬剤の影響などが原因となります。
病態生理
イレウスの発症メカニズムを理解することで、患者の症状変化や検査結果の意味が見えてきます。
腸管内容物が通過できなくなると、その閉塞部の口側(肛門に近い反対側)で腸液が貯留し始めます。腸は内容物を肛門側へ進めようとして活発に蠕動運動をしますが、やがて腸管内圧が上昇していきます。この圧の上昇によって、腸粘膜の血流が悪くなり、粘膜が虚血状態に陥ります。さらに進行すると、腸壁全層が障害を受け、腸壁の透過性が亢進して、腸内の細菌や毒素が腹腔内へ漏出します。これが腹膜炎や敗血症へと進行する危険な状態です。
また、腸管内に貯留した液体とガスは、腸管の膨満を招き、さらに蠕動運動を阻害します。脱水が進行し、電解質バランスが崩れることで、全身状態が急速に悪化するのが特徴です。
症状・診断・治療
症状
イレウスの症状は発症から時間経過とともに変化します。初期には腹痛、嘔吐、腹部膨満が三大症状として現れます。腹痛は間欠的(波のように来たり去ったりする)で、患者は「痛くなったり楽になったり」と表現することが多いでしょう。嘔吐は繰り返す傾向があり、嘔吐物の性状も進行とともに変わります。初期は食事内容が混じった嘔吐物ですが、進行すると腸液の逆流により緑黄色やコーヒー色の嘔吐物が見られるようになります。腹部は張っており、排便・排ガスがなくなることが特徴です。進行すると意識レベルの低下、頻脈、血圧低下など全身状態の悪化がみられ、これは腹膜炎や敗血症への移行を示唆します。
診断
診断には臨床症状に加えて、腹部エックス線検査が最も基本的な検査です。イレウスでは「鏡面像(きょうめんぞう)」という小腸内のガス・液体レベルが階段状に見える特徴的な画像所見が得られます。腹部CT検査はより詳細な情報が得られ、閉塞部位の特定や腸壁の虚血の有無、腹膜炎の存在を評価できるため、緊急時には重要な検査です。血液検査では、脱水による電解質異常(ナトリウム、カリウムの低下)、白血球上昇、代謝性アルカローシス(初期)や代謝性アシドーシス(進行時)などが見られます。身体診察では腹部膨満、蠕動音の変化(初期は活発、進行時は消失)、圧痛などを確認します。
治療
治療は保存的治療と手術療法に分かれます。保存的治療は、まず禁食にして腸管を安静にし、鼻から胃管を挿入して腸液を減圧排出させます。同時に点滴で脱水と電解質異常を補正し、全身状態を改善させることが重要です。多くの単純イレウス(腸が詰まっているが腸壁に障害がない状態)は数日の保存的治療で改善します。しかし、絞扼性イレウス(腸が捻れたり血流が遮断されている状態)や保存的治療に反応しない場合、腹膜炎の兆候がある場合には、手術療法が必要になります。手術では閉塞の原因を除去し、壊死した腸があれば切除します。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 急性疼痛
- 体液量減少のリスク状態
- 栄養摂取量の不足
ゴードン機能的健康パターン
栄養・代謝パターン
イレウス患者では嘔吐による栄養摂取の低下と脱水が著明です。禁食中の患者のニーズアセスメントが重要です。点滴ラインの管理、電解質バランスの把握、嘔吐の程度と嘔吐物の性状観察が看護の要点になります。また、胃管から排出される腸液の色・量・性状を記録することで、イレウスの進行度を評価できます。嘔吐による口腔内の不快感に対する対応(含漱など)も患者の快適性を保つうえで大切です。
排泄パターン
イレウスでは排便・排ガスの停止が診断の鍵になります。患者に「排便や放屁はありましたか」と丁寧に聴取することが重要です。保存的治療中に排ガス、排便が見られ始めたことは、イレウスの改善を示す重要なサインとなります。また、尿量の低下は脱水の指標になるため、尿量・尿色の観察も忘れずに行いましょう。
認知・知覚パターン
腹痛は患者にとって大きなストレスです。痛みの部位・性質・程度を定期的に評価し、医師に報告する必要があります。痛みが増悪している場合は腹膜炎への進行を疑い、迅速に対応することが重要です。患者の不安を軽減するため、治療方針や経過についての説明と心理的サポートが必要です。
ヘンダーソン14基本的ニード
栄養と水分の摂取
禁食期間中は栄養・水分の摂取が完全に断たれます。点滴による補液管理が生命維持の基本となります。電解質異常(特にカリウム低下)や脱水の進行度を把握し、必要な輸液内容が適切に実施されているか確認しましょう。嘔吐がある場合はH2ブロッカーやプロトンポンプ阻害薬が投与されることもあります。
排泄
胃管の管理は極めて重要な看護技術です。胃管が正確に位置しているか、クリンケットテストで確認し、排液が良好に行われているか観察します。腹部膨満の程度、排ガス・排便の有無を毎日評価し、改善の兆候を見逃さないことが大切です。排液の性状変化(色が濃くなる、血性になる)は腸壊死の危険信号となる場合があるため、迅速に報告する必要があります。
身体の清潔・衣生活
禁食中で体力が低下している患者が多いため、口腔ケアや部分浴など、患者の状態に合わせた清潔保持が重要です。口腔内が乾燥していれば含漱で湿潤を保ち、口臭予防にもつながります。胃管が挿入されている場合、その周囲の皮膚を清潔に保つことで褥瘡や肌荒れを予防できます。
身体の安全と安楽
腹痛がある患者は動きが制限されます。ベッド周囲に物を置かない、転倒転落予防、ナースコールの位置確認など、安全環境の整備が必要です。またラッセル体位(半座位)など、患者が少しでも楽な体位を工夫することで苦痛の軽減につながります。
看護計画・介入の内容
- 腹部症状の観察と記録:腹部膨満度、腹痛の部位・性質・程度、排ガス・排便の有無、腹部触診所見を定期的に評価し、経過を把握します
- 胃管管理の確実な実施:挿入位置の確認、排液の性状観察、チューブの屈曲・脱落防止、鼻部の皮膚管理を行い、適切な減圧を維持します
- 輸液管理と電解質バランスの監視:点滴ラインの確保、輸液速度の調整、採血結果(特にカリウム、ナトリウム、クロール)の把握と医師への報告を行います
- 疼痛管理:痛みの評価と医師への報告、指示に基づいた鎮痛薬の投与と効果判定を実施します
- 排泄状況の把握:尿量・尿色の記録、排ガス・排便出現の確認により、イレウス改善の兆候を早期に発見します
- 口腔ケアと口腔内の快適性保持:定期的な含漱、嘔吐物の処理による清潔保持で患者の不快感を軽減します
- 患者・家族への説明と心理的サポート:治療経過、回復の見通し、日常生活への影響について分かりやすく説明し、不安軽減を図ります
よくある疑問・Q&A
Q: 胃管から排出される液の色が進行とともに変わるのはなぜですか?
A: イレウスが進行して閉塞部より口側の腸内圧が高まると、腸液が逆流して胃管から排出されるようになります。初期は消化物を含む薄黄色ですが、小腸からの胆汁や膵液が混じるにつれて緑黄色になり、さらに進行して腸壁の血流が悪くなると、腸内細菌の増殖や腸液の停滞によってコーヒー色の嘔吐物(古い血液の色)が見られるようになります。この色の変化は腸管の障害程度を示す大切なサインです。
Q: イレウスと便秘は何が違いますか?
A: 最も大きな違いは腹痛の有無と全身状態です。便秘では一般に腹痛がなく、全身状態も良好です。一方、イレウスでは間欠的な激しい腹痛、嘔吐、腹部膨満があり、脱水や電解質異常による全身状態の悪化が見られます。また、イレウスでは排ガスも完全に停止します。臨床実習では、排便がないからといってすべてが便秘ではないということを意識することが重要です。
Q: 保存的治療で改善しないイレウスの判断基準は何ですか?
A: 一般的には72時間から96時間の保存的治療で症状の改善が見られない場合が手術適応の目安とされています。ただし、以下の場合は早期の手術適応が検討されます:腹膜炎の兆候(発熱、腹部板状硬化)、血液検査での著しい電解質異常、意識レベルの低下、血圧低下などの敗血症兆候、CT検査で腸壊死が疑われる所見です。つまり、単純に時間経過だけでなく、患者の全身状態を総合的に評価することが大切なのです。
Q: 術後イレウスの予防法について教えてください
A: 術後イレウスの予防には、早期離床、段階的な食事摂取開始、適切な疼痛管理が重要です。また、腸蠕動を促進する薬剤(プロキネティック薬)の投与や、医学的に許可される範囲での飲水・流動食の早期開始が行われます。看護では、患者の活動度の段階的な拡大をサポートし、腹部症状の観察を継続することが予防につながります。
Q: イレウスで絶食中、患者から水が飲みたいと言われました。どう対応しますか?
A: 医師の指示に従うことが原則です。絶食指示がある場合は、患者に「今は腸を休める必要がある」という理由を説明し、理解を得ることが重要です。ただし、口腔内の乾燥が著しい場合は、医師に相談して含漱や氷片の使用許可を得るなど、患者の快適性を損なわない工夫ができます。患者教育的なアプローチで、治療の必要性を理解してもらうことが看護師の役割です。
まとめ
イレウスは、腸内容物の通過が阻害される疾患で、腹痛、嘔吐、腹部膨満という三大症状を呈します。看護の要点は、症状の変化を敏感に察知し、迅速に医師に報告すること、そして点滴管理と胃管管理を確実に実施することです。
特に重要なのは、患者観察の中で腸壊死や腹膜炎への進行を早期に発見する能力を養うことです。腹痛の増悪、嘔吐物の色の変化、全身状態の悪化は危険信号です。また、イレウスは保存的治療で改善する場合が多いため、治療経過を根気強く観察し、回復の兆候を見逃さないことも大切です。排ガスや排便の出現は患者にとって大きな喜びとなります。
実習では、患者が不安や恐怖を感じていることを理解し、丁寧な説明と心理的サポートを心がけましょう。イレウス患者の看護を通じて、急性期患者の全身状態管理、アセスメント能力、そして患者とのコミュニケーションという看護の基本が学べます。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
- 一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
- 実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
- 記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
- 本記事を課題としてそのまま提出しないでください
- 正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません
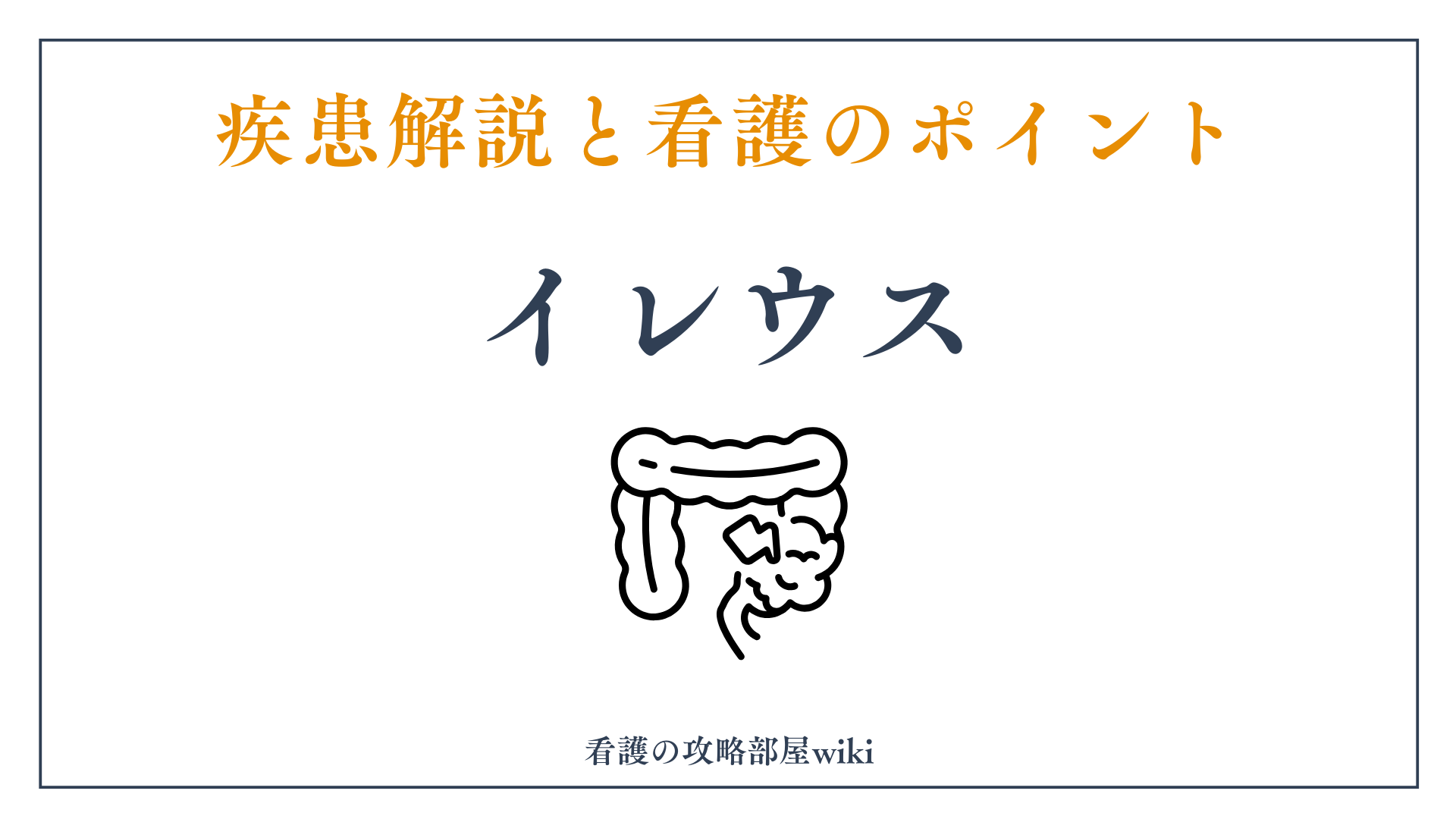
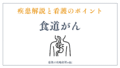
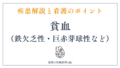
コメント