疾患概要
定義
脳梗塞は、脳の血管が血栓や塞栓によって閉塞され、脳組織への血流が悪くなり、酸素と栄養が供給されなくなることで、脳細胞が壊死に至る疾患です。脳卒中の約80%を占め、高い致死率と後遺症発生率を有する重大な脳血管障害です。発症後の治療時間が極めて重要で、「Time is brain(時間が脳)」というスローガンの下、数時間以内の迅速な医学的介入が患者の予後を大きく左右します。
疫学
日本における脳梗塞の年間発症率は人口10万人あたり約70~100人であり、脳血管疾患の中で最も頻度が高いです。発症年齢は60歳以上が大多数を占めますが、若年者の発症例も少なくありません。男性がやや多く、季節では冬季に多い傾向があります。日本は脳梗塞の高リスク国の一つであり、特に塩分摂取量が多い地域では発症率が高くなっています。生存者の約70%に何らかの後遺症が残り、要介護状態となる患者も多いため、公衆衛生上の重要な課題です。
原因
脳梗塞は発症機序により3つの型に分類されます。アテローム性脳梗塞は、脳の大血管にアテロームプラーク(粥状硬化巣)が形成され、段階的に血管が狭窄する型で、脳梗塞全体の約50%を占めます。心原性脳塞栓症は、心臓内に形成された血栓が脳血管に流れてくる型で、特に心房細動がある患者で多く、脳梗塞全体の約20~30%です。小血管病変による脳梗塞(ラクナ梗塞)は、脳の細い血管が閉塞する型で、約25%を占めます。危険因子には高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙、心房細動、肥満などが挙げられます。
病態生理
脳梗塞の発症と進行は段階的かつ時間に依存した過程です。
虚血の初期段階では、脳血管が閉塞すると、その領域への血流が急激に低下します。脳は体重の約2%でありながら体の酸素消費量の約20%を担うため、血流の低下にきわめて敏感です。血流が途絶えた領域の中心部(虚血コア)では、数分以内にATP(エネルギー物質)が枯渇し、神経細胞が機能を失い始めます。同時に、周辺の血流がある程度保たれている領域(ペナンブラ:虚血半影)では、神経細胞はまだ生存していますが、機能が低下した状態にあります。
時間の経過と不可逆的変化:虚血コアは時間の経過とともに拡大し、数時間後には神経細胞が壊死に至ります。一方、ペナンブラは治療により血流が回復すれば救済される可能性がありますが、血流回復のないまま時間が経過すると、虚血コアへと変わってしまいます。この過程が約4.5時間以内に起こることが、t-PA(組織プラスミノーゲン活性化因子)などの血栓溶解療法が発症後数時間以内の投与に限定される理由です。
二次的障害が続きます。梗塞領域周辺では、神経炎症、酸化ストレス、グルタミン酸毒性などが起こり、神経細胞死が拡大します。脳浮腫が発生し、頭蓋内圧が上昇します。また、虚血領域の血管が再開通する際(再灌流)には、活性酸素が大量に発生し、むしろ神経細胞にダメージを与えることもあります。
症状・診断・治療
症状
脳梗塞の症状は突然に発症することが特徴であり、症状は梗塞部位と領域の大きさにより異なります。
運動機能障害:片側の上肢・下肢の脱力や麻痺が生じます。軽度では力が入りにくい程度ですが、重篤な場合は完全な運動麻痺に至り、患者は動けなくなります。顔面の表情筋が侵されると、口角が下がり、笑った時に顔が歪みます。
言語機能障害:優位半球の中大脳動脈領域が梗塞した場合、失語症が生じます。患者は言葉を理解できなくなったり、話そうとしても言葉が出なくなったりします。劣位半球が侵されると、発話は可能でも音の高低や抑揚が失われる構音障害が生じます。
感覚機能障害:片側の顔面・上肢・下肢の感覚が低下または消失します。
視覚障害:後大脳動脈領域の梗塞では、両眼の同側半盲(視野の半分が見えなくなる)が生じます。
小脳梗塞では、めまい、嘔吐、運動失調(体がふらつき、動きが不正確になる)が見られます。
その他、頭痛、めまい、意識障害なども起こります。発症直後は症状が軽くても、数時間~数日で悪化することもあります。
診断
頭部CT検査が第一段階です。脳梗塞の急性期では、一般的なCTでは異常が見られないことが多いですが、出血がないことを確認することは、血栓溶解療法の適応判断に不可欠です。
頭部MRI(特にDWI画像)は、超急性期の脳梗塞を検出する最も感度の高い検査で、発症数時間後には梗塞領域が高信号で映ります。
脳血管造影(カテーテル検査またはCTA/MRA)により、血管の閉塞部位と程度を把握します。
脳血流検査では、血流の低下領域を可視化できます。
血液検査では、凝血異常、心原性塞栓症のスクリーニング(心房細動の有無)、危険因子の評価(血糖、コレステロール値)などが行われます。
心電図とときに心エコーにより、心房細動や心疾患の有無を確認します。
臨床的には、NIH脳卒中スケール(NIHSS)を用いた神経学的重症度の評価が行われます。
治療
急性期治療では、発症から4.5時間以内に来院した患者に対して、t-PA静脈内血栓溶解療法が検討されます。これは、血栓を溶かすことで血流を再開通させ、ペナンブラを救済する治療ですが、出血のリスクがあるため、厳密な適応基準に基づいて行われます。
機械的血栓除去術は、発症から数時間以内(施設によっては24時間以内)の患者を対象に、カテーテルを用いて血栓を物理的に取り除く治療です。大血管領域の梗塞で特に有効とされています。
対症療法と危険因子管理では、脳浮腫の軽減のため脳圧低下薬が投与され、体温管理(発熱を避ける)、血糖管理、血圧管理が行われます。二次的脳梗塞を防ぐため、抗血小板薬(アスピリンなど)や抗凝固薬が投与されます。
慢性期治療では、再発予防のため、危険因子の管理(高血圧、糖尿病、脂質異常症の治療)、生活習慣改善(禁煙、減塩、適度な運動)、抗血小板薬の継続投与などが行われます。心房細動がある患者には抗凝固薬が推奨されます。
リハビリテーションは、急性期からできるだけ早期に開始され、麻痺の回復、機能の回復を支援します。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 脳血流低下に関連した脳組織灌流圧低下の危険性
- 麻痺に関連した運動機能障害
- 失語症に関連したコミュニケーション障害
- 嚥下機能低下に関連した誤嚥・窒息の危険性
- 脳梗塞の再発に関連した危険性
- 後遺症に関連した自己概念の変容・抑うつ
ゴードン機能的健康パターン
知覚・認知パターン
患者の意識レベルと神経学的徴候を継続的に評価することが最優先です。NIHSS等の神経学的スケールを用いた客観的評価により、微細な変化を検出します。失語症や高次脳機能障害により、患者の理解度が低下している場合があるため、簡潔で繰り返しの説明が必要です。患者の認知機能回復の可能性を信じ、言語刺激や認知リハビリを支援することが大切です。
活動・運動パターン
片麻痺により患者は自力での運動が困難になります。寝たきり状態を避けるため、早期の離床と段階的な活動拡大が重要です。理学療法・作業療法と連携し、患者の安全を確保しながら、可能な限り自力での活動を促します。転倒リスクが高いため、環境整備と見守りが必須です。拘縮予防のための関節可動域運動も継続的に行う必要があります。
排泄パターン
脳梗塞により脳の排泄中枢が侵されると、排尿・排便のコントロールが困難になることがあります。排尿困難に対しては導尿管理や間欠的自己導尿が行われることもあります。便秘は脳圧上昇につながるため、適切な水分摂取と食物繊維、必要に応じて下剤により、毎日の排便を確保することが大切です。
栄養・代謝パターン
失語症や嚥下機能障害により、経口摂取が困難な患者が多いです。嚥下スクリーニングテストを実施し、嚥下能力を評価してから、段階的に経口摂取を再開します。嚥下機能が回復しない場合は、経管栄養や経口流動食による栄養管理が行われます。血糖管理は脳梗塞の予後に影響するため、厳密に行う必要があります。
ストレス・対処パターン
急激な発症と重度の後遺症により、患者と家族は極度のストレスと喪失感を経験します。患者は、もし生き残っても身体機能や言語機能が失われることへの恐怖を抱きます。看護者の支持的で希望的な関わりが、患者の心理的適応を支援します。必要に応じて心理士や精神科の受診を勧めます。
ヘンダーソン14基本的ニード
1. 呼吸
脳梗塞が脳幹に及ぶ場合、呼吸中枢が侵されることがあります。呼吸が抑制されている場合は人工呼吸管理が行われます。嚥下機能の低下に伴う誤嚥による肺炎予防のため、定期的な吸引と体位ドレナージが重要です。
2. 栄養と水分
嚥下機能評価後、経口摂取を段階的に再開します。初期段階ではとろみ水から始め、段階的に常食に進めます。経管栄養が必要な場合は、栄養バランスの取れた栄養剤を投与し、栄養状態を維持します。脱水と過剰輸液の両方を回避するよう、水分出納を記録します。
3. 排泄
排尿困難に対しては、導尿管理や間欠的導尿が行われます。尿失禁がある場合は、定期的なトイレ利用や尿器・尿パッドの使用で対応します。便秘予防のため、十分な水分摂取と下剤使用により、毎日の排便を確保します。
4. 安全と防御
転倒リスクが極めて高いため、ベッド柵を固定し、床頭台やポータブルトイレを患者の側に置くなど、環境整備が重要です。また、脳梗塞の再発防止のため、血圧管理、抗血小板薬・抗凝固薬の確実な投与、危険因子の管理が必須です。
5. 睡眠と休息
脳梗塞後は疲労しやすくなるため、十分な睡眠と休息が必要です。夜間の睡眠環境を整え、昼間の過度な刺激を避けることが大切です。
6. 体温調節
発熱は脳の酸素消費を増加させ、梗塞領域を拡大させる可能性があるため、発熱の早期発見と対応が重要です。感染症の予防(特に誤嚥性肺炎、尿路感染症)に注力します。
看護計画・介入の内容
- 神経学的徴候を頻回に評価し(意識レベル、運動機能、感覚機能、言語機能など)、症状の悪化を敏感に察知して医師に報告する。特に発症後数時間は30分~1時間ごとの評価が必要です
- 嚥下スクリーニングテストを実施し、嚥下機能が回復するまでは経口摂取を控え、経管栄養や静脈栄養により栄養を維持する。嚥下機能回復後も、誤嚥のリスクに注意しながら段階的に経口摂取を再開する
- 血圧を定期的に測定し、医師の指示に従って厳密に管理する。過度な血圧低下は脳灌流を悪化させ、過度な高血圧は脳出血を引き起こすため、バランスが大切です
- 血糖値を定期的に測定し、高血糖を避ける。インスリンが投与される場合は、用量と投与時間を厳密に管理します
- 抗血小板薬・抗凝固薬が確実に投与されているか確認し、出血症状(鼻血、歯肉出血、血尿など)の有無を監視します
- 体温を毎日測定し、発熱があれば直ちに対応する。感染症予防のため、口腔ケア、導尿管理の衛生、定期的な体位変換などを実施します
- 転倒予防のため、床頭台、ポータブルトイレ、歩行器などを患者の側に置き、環境整備を徹底します。患者が動く際は見守りと支援を行い、無理な動きを止めます
- 失語症がある患者に対しては、ゆっくり簡潔な言葉で話しかけ、患者の応答を注意深く聞き、理解しようと努めます。コミュニケーション困難の状況を患者と家族に説明し、焦らず向き合うよう指導します
- 早期離床と段階的な活動拡大を支援し、理学療法・作業療法と連携してリハビリテーションを推進します
- 拘縮予防のため、関節可動域運動を継続的に実施し、患者の肢位を定期的に変えて、筋肉の萎縮を遅延させます
- 患者と家族の心理状態を常に評価し、不安や抑うつがあれば医師や心理士に相談する。患者の回復可能性について希望的に関わり、リハビリテーションへの参加を励まします
- 家族に疾患と治療、予後、生活制限について丁寧に説明し、在宅での危険因子管理(服薬遵守、食事療法、運動習慣など)について指導します
よくある疑問・Q&A
Q: 患者が「最近、つまりやすくなった」と言うのですが、これは何ですか?
A: これは一過性脳虚血発作(TIA)の可能性があります。症状は数分~数時間で消失しますが、脳梗塞の前兆信号です。いったん発生したら医師に直ちに報告し、精査と治療方針の決定をしてもらう必要があります。TIAは脳梗塞発症の強いリスク因子です。
Q: 失語症のある患者と、どのようにコミュニケーションをとれば良いですか?
A: 失語症の種類により異なりますが、基本は、ゆっくり簡潔な言葉で話しかけることです。患者が理解できない場合は、絵や身振りを使うことも有効です。患者の回答を急かさず、十分な時間を与えます。患者が言いたいことが理解できなくても、患者の努力を認めることが大切です。言語聴覚士のサポートを活用することも重要です。
Q: なぜ脳梗塞後の患者は、すぐにリハビリテーションを始めるのですか?
A: 脳は発症直後の可塑性(変わる能力)が最も高く、この時期に脳に刺激を与えることで、脳の他の領域が失われた機能を補う可能性があります。また、早期離床は筋力低下、拘縮、深部静脈血栓症などの合併症を予防します。ただし、患者の状態に応じて段階的に行うことが重要です。
Q: 抗血小板薬と抗凝固薬の違いは何ですか?
A: 抗血小板薬(アスピリン等)は血小板の凝集を抑えることで、アテローム性脳梗塞や小血管梗塞を予防します。一方、抗凝固薬(ワルファリン、DOACなど)は、血液凝固のプロセスそのものを抑え、特に心房細動に伴う血栓形成を予防します。患者の梗塞型と危険因子により、どちらが選択されるかが決まります。
Q: 患者が「もう、良くならないのか」と絶望的に言っています。看護者はどう対応すべきですか?
A: 患者の絶望感は、急激な機能喪失と将来への不安から生じた自然な反応です。看護者は、患者の気持ちを傾聴し、「今はこの状態でも、リハビリテーションにより回復の可能性がある」という希望的なメッセージを丁寧に伝えることが大切です。同時に、医師や心理士、患者会などのリソースを紹介し、患者が一人ではないことを伝えます。
まとめ
脳梗塞は、発症後の数時間が患者の運命を決める極めて時間に敏感な疾患です。看護学生が理解すべき最も重要なポイントは、「Time is brain」という原則を心に刻み、神経学的徴候の細微な変化を敏感に察知し、医師に迅速に報告する能力です。
医学的には、急性期の血栓溶解療法や機械的血栓除去術による血流再開通が患者の生命と予後を左右しますが、看護の役割も同様に重大です。神経学的評価、誤嚥予防、血圧・血糖管理、感染症予防、転倒予防といった基本的ながら極めて重要な看護実践が、患者の二次的害を防ぎ、回復をサポートします。
さらに重要なのが、患者と家族の心理的・社会的サポートです。脳梗塞により、患者は身体機能だけでなく、言語機能や認知機能、あるいは職業や役割さえも失うことがあります。この喪失感と向き合う患者に対して、看護者の支持的で希望的な関わりは、患者の適応と回復を促進する力となります。
実習では、患者の観察、コミュニケーション、リハビリテーションへの支援を通じて、脳梗塞患者の全人的な援助を学んでください。同時に、危険因子管理と予防の重要性も忘れず、社会的な健康教育の担い手としての看護者の役割を意識することが大切です。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
・正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません
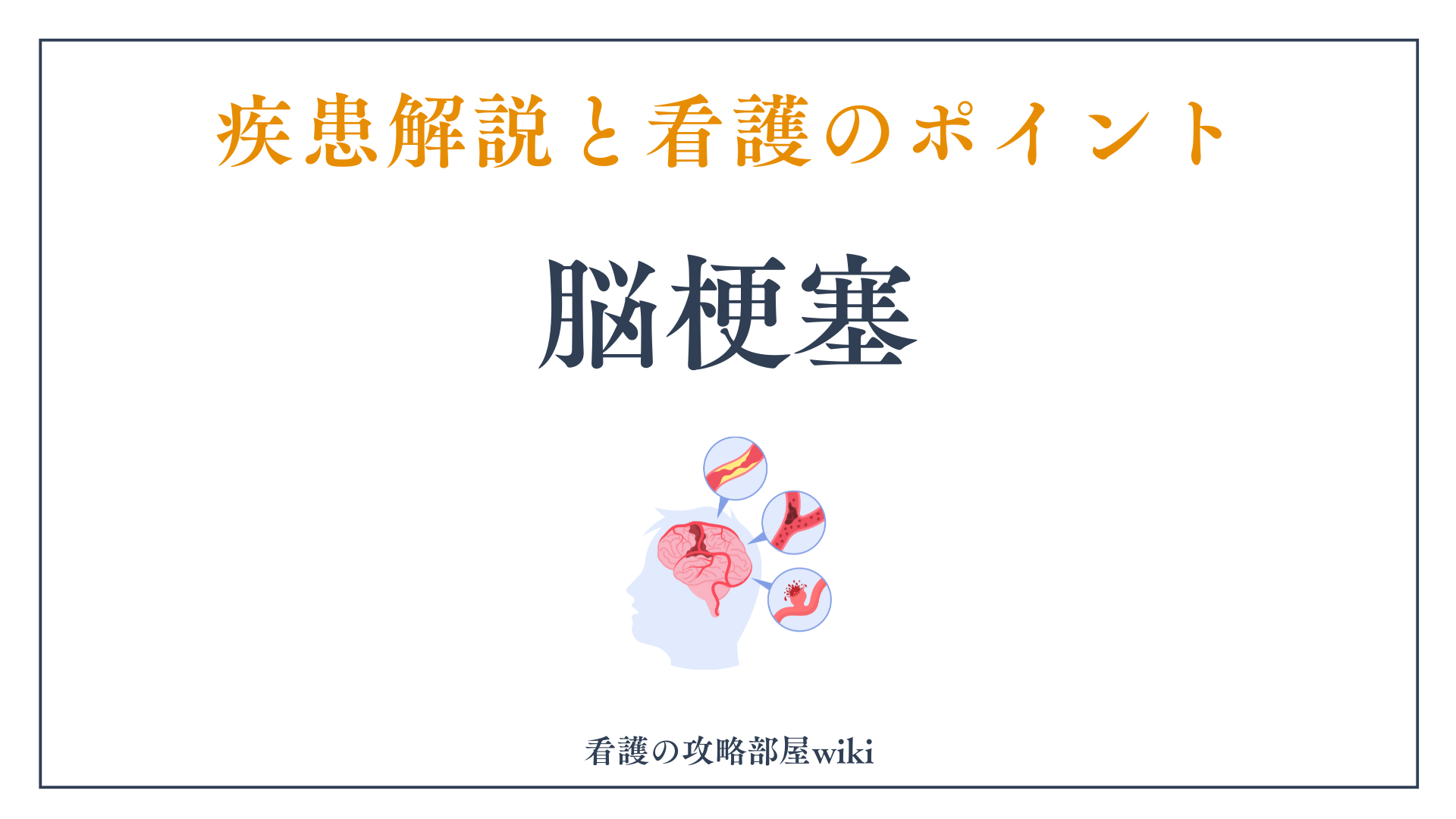
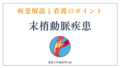

コメント