疾患概要
定義
くも膜下出血(Subarachnoid Hemorrhage; SAH)は、脳を覆う髄膜のうち、くも膜と軟膜の間の空間(くも膜下腔)に血液が流入する疾患です。この空間には脳脊髄液が流れており、脳血管や神経が通過しているため、出血により周囲組織に大きなダメージを与えます。突発的で重篤な脳血管障害であり、適切な診断と治療を行わないと死亡や重度の後遺症に至ることがある医学的緊急事態です。
疫学
日本におけるくも膜下出血の年間発症率は人口10万人あたり約18~20人で、脳卒中全体の約10~15%を占めます。発症年齢のピークは50~60歳代で、比較的若い年代での発症も少なくありません。性別では男性がやや多い傾向にありますが、女性の発症例も多数あります。発症の季節変動や時間帯では、冬季と早朝に発症することが多いとされています。致死率は高く、院外死亡を含めると約50%、入院後でも約10~15%の患者が死亡しています。また、生存者の約半数に何らかの神経学的後遺症が残ります。
原因
くも膜下出血の約85~90%は、脳動脈瘤の破裂が原因です。脳動脈瘤は脳の血管の一部が瘤状に拡張したもので、特に脳底部の動脈に多く見られます。その他の原因として、脳動静脈奇形の破裂、硬膜動脈瘤、外傷による血管損傷、凝固異常、抗凝固薬使用などが挙げられます。危険因子には高血圧、喫煙、多量飲酒、家族歴(特に一親等の親族に脳動脈瘤破裂の既往がある場合)、女性ホルモン関連因子などがあります。
病態生理
くも膜下出血の発症メカニズムは段階的に進行します。
初期段階では、脳動脈瘤が破裂することで、くも膜下腔に急激に血液が流入します。この時点で頭蓋内圧が急上昇し、脳血流が著しく低下します。同時に、脳脊髄液が血液で汚染されます。
二次的障害が続きます。出血直後から、脳血管が過剰に収縮する反応が始まり、脳血流がさらに悪くなります。これを血管攣縮(vasospasm)と呼び、発症後3~7日目がピークで、これにより脳梗塞が発生することがあります。同時に、血液中の鉄分やヘモグロビンが神経毒性を示し、神経細胞にダメージを与えます。さらに、脳脊髄液中に赤血球が混入することで、脳脊髄液循環が障害され、水頭症が発生することもあります。
炎症反応も重要です。出血により脳幹部が刺激され、著しい交感神経興奮が起こります。これにより血圧が急上昇し、心拍数が増加し、脳内圧がさらに上昇する悪循環が生じます。
症状・診断・治療
症状
くも膜下出血の症状は突発的かつ極めて重篤なのが特徴です。
患者は通常、これまで経験したことのない激しい頭痛を訴えます。患者自身が「バットで殴られたような」「頭が割れるような」と表現することが多く、その激しさは医学的に重要な信号です。同時に項部硬直(首の後ろが硬くなり、あごが胸に付かなくなる)、吐き気、嘔吐、けいれん、意識障害が見られます。
出血の部位や量により症状の程度は異なります。大量出血では意識がすぐに失われ、脳ヘルニアに至ることもあります。出血量が少ない場合でも、頭痛や軽度の意識混濁から始まり、数時間~数日後に症状が悪化することがあります。
神経学的合併症として、再出血(発症から48時間以内に約5~10%の患者で生じる)、血管攣縮に伴う脳梗塞(発症3~7日後)、水頭症などが起こります。これらは患者の転帰に大きな影響を与えます。
診断
診断の第一段階は頭部CT検査です。出血直後のCTでは、くも膜下腔に高吸収域(白く映る領域)が見られます。これは血液であり、出血の場所、量、分布を評価するのに極めて重要です。ただし、発症から時間が経つと、血液の吸収により所見が薄くなるため、早期の検査が必須です。
CTで明らかな出血が見られない場合でも、臨床症状が強く疑われる際は腰椎穿刺(ルンバール)を実施します。くも膜下出血があれば、脳脊髄液は血液で混濁しており、遠心分離後も黄色く変色するキサントクロミアが見られます。
出血源の同定と治療計画立案のため、脳血管造影(カテーテルによる造影検査またはCTA/MRA)が実施されます。脳動脈瘤の部位、大きさ、形態を把握することは、手術・血管内治療の方針決定に不可欠です。
発症後の経過観察では、脳水腫や脳梗塞の発生を監視するため、定期的なCT検査が行われます。
治療
くも膜下出血の治療は、出血源の閉塞と二次的障害の予防・軽減が柱になります。
出血源の治療として、クリッピング手術(脳動脈瘤の根部にクリップを装着する)または血管内コイル塞栓術(カテーテルを用いてコイルを瘤内に詰める)が行われます。治療の時期は、発症から数日以内の早期治療が再出血防止の観点から推奨されています。
対症療法と二次的障害予防が同時に進められます。脳血管攣縮の予防と軽減のため、カルシウム拮抗薬(ニモジピン)が投与され、脳脊髄液ドレナージが置かれることがあります。水頭症が発生した場合は、脳室ドレナージにより脳脊髄液を排液します。血圧管理も重要で、再出血防止のため過度な高血圧を避け、かつ脳灌流圧を維持するバランスが必要です。
急性期には集中治療が実施され、呼吸管理、循環動態管理、栄養管理などが行われます。けいれん予防のため抗けいれん薬が投与される場合もあります。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 急激な頭蓋内圧上昇に関連した脳灌流圧低下の危険性
- 再出血に関連した身体損傷の危険性
- 血管攣縮に伴う脳梗塞発症の危険性
- けいれんに関連した身体損傷の危険性
- 集中治療環境と疾患に関連した不安・恐怖
- 後遺症に対する適応困難
ゴードン機能的健康パターン
知覚・認知パターン
激しい頭痛は患者に極度の恐怖と不安をもたらします。患者の意識レベルを継続的に評価し、意識混濁の進行や悪化をいち早く検知することが生命維持に直結します。Glasgow Coma Scaleを用いた客観的評価が必須です。疾患と治療について、患者の理解度に応じて丁寧に説明する必要があります。集中治療中は患者の認知機能が低下しており、反復的で優しい説明が大切です。
活動・運動パターン
急性期の患者は安静が絶対的に必要です。用便時の力み、不用意な体動、急激な頭部の動きは、頭蓋内圧を上昇させ、再出血のリスクを高めます。ベッド上での活動制限を徹底し、患者が体動を控えるよう指導します。けいれんが起こった場合に備え、安全な環境を整備し、舌を噛まないよう対応の準備をします。回復期には段階的に活動を増やしていきますが、疲労を避けることが重要です。
排泄パターン
用便時は腹圧が上昇し、脳圧が上昇するため、患者の便秘予防が重要です。水分摂取と食物繊維、必要に応じて下剤により、毎日の緩い排便を維持します。尿が貯留しないよう、導尿管理または定期的なトイレ利用が必要です。排泄時の患者の動きを見守り、無理な力み込みを防ぐよう声掛けします。
栄養・代謝パターン
急性期は経口摂取が難しいため、経管栄養や中心静脈栄養により栄養を維持します。脳障害により嚥下機能が低下することもあるため、嚥下能力を評価してから経口摂取を始めることが大切です。脳の修復と回復を支援するため、タンパク質やビタミンを含むバランスの良い栄養管理が必要です。
ストレス・対処パターン
くも膜下出血は突然に起こり、患者と家族に極度のストレスと恐怖をもたらします。患者自身も、もし回復しても後遺症への不安があります。頻繁に声をかけ、患者の心情を傾聴し、医師や心理士との連携により、心理的サポートを提供することが重要です。家族への情報提供と精神的支持も看護の重要な役割です。
ヘンダーソン14基本的ニード
1. 呼吸
意識障害が深い患者では、気道確保が重要です。嘔吐があれば誤嚥を防ぐため、吸引を準備し、患者を側臥位に保つ必要があります。呼吸が抑制されている場合は、人工呼吸管理が行われます。常に呼吸音、酸素飽和度、呼吸パターンを監視します。
2. 栄養と水分
経口摂取が難しい場合は経管栄養や静脈栄養を用いて、十分なカロリーと栄養素を投与します。血糖管理も重要で、高血糖は脳浮腫を悪化させるため、インスリン投与により血糖をコントロールします。水分出納を正確に記録し、過剰輸液による脳浮腫を防ぎます。
3. 排泄
便秘は腹圧上昇により脳圧を高めるため、厳格に予防します。膀胱も尿による圧迫により脳圧を高めるため、導尿管理や定期的な排尿を行います。排尿・排便時の患者の様子を見守り、無理な力み込みを起こさないよう促します。
4. 安全と防御
最も重要なニードです。再出血防止のため、患者の安静と安全が絶対的です。ベッド柵をしっかり固定し、転倒を防ぎます。けいれんに備え、クッション材を配置し、頭部保護を準備します。けいれん発作時は、患者を動かさず気道を確保し、舌咬傷を防ぎます。点滴や導尿管、脳室ドレナージなどの医療機器の無意識の抜去を防ぐため、必要に応じて抑制帯を使用する場合もあります。
5. 睡眠と休息
急性期の患者は集中治療環境下にあり、継続的な監視とケアが必要なため、十分な睡眠が得難い状況にあります。できるだけ静かで暗い環境を作り、不必要な刺激を最小限にします。疲労が蓄積しないよう、看護ケアのタイミングを工夫し、患者が休息できる時間を確保します。
6. 体温調節
脳幹損傷が広範囲の場合、体温調節機能が失われることがあります。環境温度を調整し、患者の体温を正常範囲に保つよう努めます。
看護計画・介入の内容
- 神経学的徴候を30分~1時間ごとに評価し(意識レベル、瞳孔、運動・感覚機能、言語機能など)、悪化の兆候をいち早く検出して医師に報告する。変化をカルテに記録し、トレンドを把握する
- 脳圧低下のため、頭部を30度挙上させベッドに上げ、頭部を正中線に保ち、頸静脈圧迫を避ける。これにより脳静脈還流が促進される
- 再出血防止のため、患者の絶対安静を徹底する。用便時・体位変換時・吸引時など、脳圧が上昇する操作では、事前に医師に相談する
- 体温を厳密に管理する。発熱は脳の代謝を増加させ、脳圧を上昇させるため、高熱が出た場合は冷却や解熱薬により対応する
- 血圧・心拍・呼吸・酸素飽和度を継続的に監視し、異常があれば直ちに医師に報告する
- 脳脊髄液ドレナージ管が留置されている場合、管の閉塞や位置のズレがないか定期的に確認し、管理プロトコルに従う
- 尿量と色を毎時間記録し、排尿困難や尿量減少があれば医師に報告する。脱水と過剰輸液の両方を回避する
- けいれん予防のため、抗けいれん薬が処方されている場合は確実に投与し、けいれん発生時に備えてプロトコルを準備する
- 経管栄養中の患者では、嚥下機能回復後の段階的な食事再開を支援し、窒息・誤嚥を防ぐ
- 患者と家族の不安が大きいため、疾患と治療について、理解度に応じて繰り返し説明し、質問に丁寧に答える。医師の説明後には、患者の理解を確認し、疑問があれば医師に確認してもらう
- 回復期に向けて、リハビリテーション計画の立案に協力し、患者が前向きに取り組めるよう励まし支援する
よくある疑問・Q&A
Q: 患者が「頭が痛い」と訴える時、すぐに医師に報告すべきですか?
A: はい、極めて重要です。くも膜下出血では、再出血や水頭症の進行により突然に症状が悪化することがあります。頭痛の性質や程度の変化、新たな神経症状の出現は、深刻な事態を示す信号の可能性があります。迷わず医師に報告してください。
Q: なぜ血管攣縮が起こるのですか?
A: 血管攣縮の正確なメカニズムはまだ完全には解明されていませんが、出血により脳血管周囲の環境が変わり、血管平滑筋の収縮反応が異常に亢進することが関係しています。オキシヘモグロビンなどの物質が血管を刺激することも考えられています。このため、カルシウム拮抗薬の投与や脳脊髄液ドレナージにより、その発生や進行を予防・軽減する治療が行われます。
Q: 後遺症はどのような問題が残りますか?
A: 生存者の多くが、認知機能障害(記憶力低下、判断力低下)、性格変化、頭痛、易疲労性などの高次脳機能障害を経験します。また、片麻痺などの身体的後遺症が残る場合もあります。後遺症の程度は出血の範囲と量、治療のタイミングに影響されます。患者と家族は、回復プロセスが長く、段階的であることを理解し、心理的なサポートが必要です。
Q: 家族はどのような支援が必要ですか?
A: 家族は患者の予後について極度の不安を感じています。医師の説明を補足し、疾患の進行、治療の必要性、予想される経過について、わかりやすく繰り返し説明することが大切です。また、患者と一緒にいられる時間を確保し、患者への会話や触覚刺激の重要性について指導します。カウンセリングや家族会への参加など、心理的サポートの情報提供も有用です。
Q: 意識のない患者にも、声かけやケアは必要ですか?
A: はい、非常に重要です。意識がなくても患者は周囲の音や刺激を感知している可能性があります。看護ケアの時や医学的処置の前に、患者に対して「これからどのようなことをします」と説明しながら行うことで、患者の不安が軽減され、リラックス効果も期待できます。また、家族による会話や音楽なども、患者の回復を促進する可能性があります。
まとめ
くも膜下出血は、突発的で極めて重篤な脳血管障害であり、迅速な診断と治療が患者の生命と予後を左右する疾患です。看護学生が理解すべき最も重要なポイントは、神経学的徴候の微細な変化を敏感に察知し、医師に即座に報告する能力です。
医学的には、脳動脈瘤の根治治療(クリッピングやコイル塞栓)と、血管攣縮や水頭症などの二次的障害の予防・軽減が治療の中心です。しかし臨床現場では、患者の絶対安静の維持、脳圧管理、継続的な神経学的評価という看護実践が、患者の転帰に直結した形で貢献します。
加えて、生死の境界線にいる患者と、家族の極度の恐怖と不安に対して、看護者の支持的で誠実な関わりがもたらす心理的支援は、計り知れない価値があります。患者の回復を信じ、小さな改善も見逃さない観察眼と、患者・家族の気持ちに寄り添う姿勢を大切にしてください。
実習では、先輩看護師の実践を観察し、神経学的評価の方法、脳圧管理の理論的背景、患者・家族とのコミュニケーション方法など、実践的スキルを確実に身につけることが大切です。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
・正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません
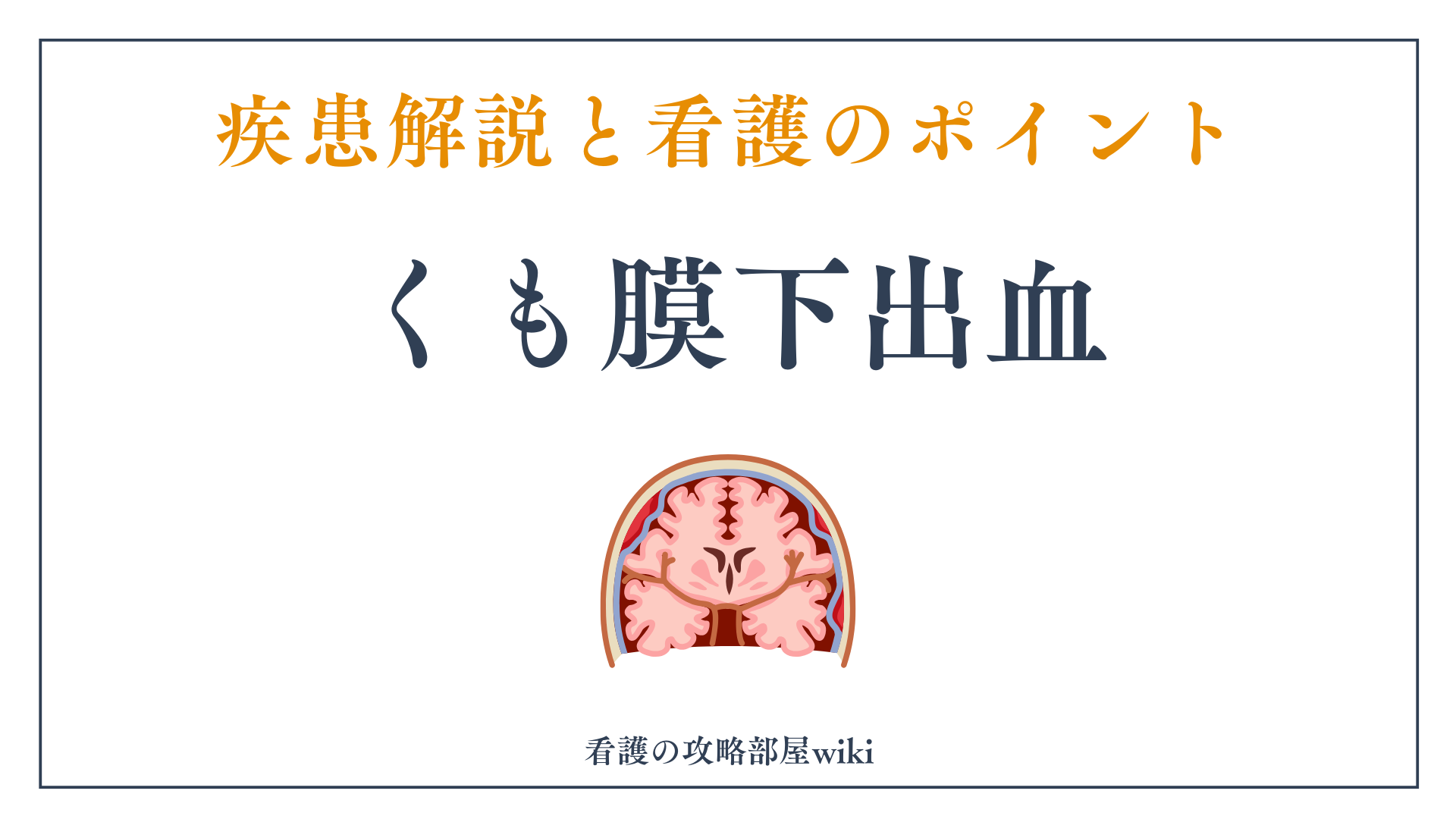
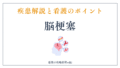
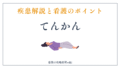
コメント