疾患概要
定義
てんかんは、脳の神経細胞が過剰に興奮して異常な電気信号を発生させることで、反復性の発作を起こす慢性神経疾患です。1回限りの発作ではなく、繰り返す発作が特徴で、発作がなくても診断されることもあります。国際抗てんかん連盟(ILAE)では、てんかんを「脳の慢性的な傾向で、反復する発作を起こしやすい素因を伴うもの」と定義しています。
疫学
日本では約100万人がてんかんに罹患しており、人口の約0.8~1.0%がこの疾患を持つといわれています。発症年齢は二峰性で、幼児期(特に0~5歳)と高齢者(65歳以上)での発症が多いのが特徴です。性別による大きな差はありませんが、小児期の発症が全体の約70%を占めます。発症の危険因子には、家族歴、脳外傷、脳卒中、脳腫瘍、中枢神経系感染症などが含まれます。
原因
てんかんの原因は大きく分けられます。症候性てんかんは脳の形態的異常(脳奇形、脳損傷、脳腫瘍など)が明らかなもので、特発性てんかんは脳画像に異常がなく原因が特定できないものです。また、遺伝的素因が関与する場合も多くあります。幼児期では熱性けいれんの既往、脳感染症、周産期の脳障害が原因となることがあり、成人では脳卒中や頭部外傷、高齢者では脳卒中が主な原因です。
病態生理
てんかんの発症メカニズムは、脳内の興奮性と抑制性のバランスの破綻によって生じます。
正常な脳では、グルタミン酸などの興奮性神経伝達物質とGABA(ガンマアミノ酪酸)などの抑制性神経伝達物質がバランスを保っています。てんかんではこのバランスが崩れ、抑制性神経伝達物質が低下したり、興奮性神経伝達物質が過剰になったりします。その結果、ニューロンが過剰に興奮し、異常な同期放電が生じるのです。
この異常放電が脳のどの部位に起こるか、どの程度の範囲に広がるかで、発作の型や症状が決まります。局所的な異常放電にとどまれば部分発作となり、全脳に広がれば全般発作となります。発作が繰り返されると、脳の神経ネットワークが変化し、さらに発作が起こりやすくなるという悪循環(てんかん形成)が生じます。
症状・診断・治療
症状
てんかんの症状は発作の分類により異なります。
全般発作では、意識喪失が急激に生じることが特徴です。強直間代発作(大発作)では、意識を失った後に全身の筋肉が硬直し(強直相)、その後全身が律動的にけいれんします(間代相)。この間、患者は悲鳴を上げたり、尿失禁、咬舌、泡沫状唾液分泌などが見られます。発作後は著しい疲労感と軽度の意識混濁(発作後朦朧状態)が数分~数十分続きます。
欠神発作(小発作)は主に小児に見られ、数秒間の意識消失があるだけで、けいれんはありません。周囲の反応が鈍くなり、虚ろな表情を呈します。
部分発作では意識は保たれることが多く、ジャッキング様の異常運動、異常感覚、不可思議な行動や情動の変化が見られます。
他の症状として、発作前の頭痛や気分の変化(前駆症状)、発作中の自動症(口をもぐもぐさせる、着衣をいじるなど)、発作後の頭痛や筋肉痛があります。重篤な状況としててんかん重積状態があり、発作が次々と繰り返されて意識が戻らない状態は、生命に関わる医学的緊急事態です。
診断
診断は臨床症状と脳波検査(EEG)が中心になります。脳波では棘波(spike)や棘徐波複合といった特異的な異常波形がみられ、発作間欠期(発作と発作の間)でも異常波形が検出されることが多いです。発作中の脳波記録が診断を確定させる最も確実な方法です。
脳画像検査(MRI、CT)は原因検索のため実施されます。MRIは脳の微細な異常を検出でき、特に側頭葉てんかんの診断に有用です。
患者の詳細な発作症状の聴取も重要です。発作の開始部位、進行経過、意識の有無、けいれんのパターンなどから、発作型や焦点部位が推定されます。
診断基準は国際分類に準じ、2回以上の発作があることが基本とされています。
治療
薬物療法が第一選択で、抗てんかん薬(AED)を用いて発作を予防します。主な薬剤にはフェニトイン、バルプロ酸、ラモトリジン、レベチラセタムなどがあります。患者の発作型、年齢、併用薬、副作用を考慮して選択されます。1種類の薬(単剤療法)から開始し、効果が不十分な場合は用量調整や他剤の追加を検討します。
規則的な血中濃度測定により、有効かつ安全な用量を維持することが重要です。抗てんかん薬の多くは肝代謝され、薬物相互作用の可能性があるため、他の薬剤との相互作用を確認する必要があります。
手術療法は、薬物抵抗性てんかん(3種類以上の抗てんかん薬が無効)の患者で、脳画像により焦点が限定できる場合に検討されます。焦点切除術、脳梁離断術などがあります。
生活指導として、十分な睡眠、ストレス管理、アルコール制限、発作誘発因子の回避が重要です。発作時の対応(安全な場所への移動、頭部保護など)についても患者と家族に指導します。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 発作に関連した身体損傷の危険性
- 疾患・治療に関連した知識不足
- 抗てんかん薬の副作用に関連した身体機能障害の危険性
- 疾患に対する不安・抑うつ
- 社会役割の変化に伴う自己概念の変容
ゴードン機能的健康パターン
知覚・認知パターン
発作時の意識消失により、発作自体を認識できない患者も多いです。発作の経験や内容について詳しく聴取し、患者の理解度を把握することが重要です。また、抗てんかん薬の副作用として認知機能障害が生じる場合があるため、学習能力や記憶力の変化に注意します。患者が疾患と治療について正しく理解し、セルフケアできるよう支援することが看護の重要な役割です。
活動・運動パターン
発作による受傷を防ぐため、患者の日常生活環境の安全性を評価します。階段利用の制限、浴槽での溺水防止、高所作業の回避など、生活上の制限について患者と相談します。抗てんかん薬による鎮静作用や運動失調が見られる場合は、転倒リスクが高まるため、活動レベルを調整する必要があります。また、発作によって身体機能が低下している場合は、リハビリテーションを検討します。
ストレス・対処パターン
てんかんは慢性疾患であり、長期の薬物治療と発作の不安から精神的ストレスが大きいです。患者の心理状態を常に観察し、不安や抑うつ症状の有無を評価します。患者が疾患と向き合い、適応できるようにカウンセリングや支持的態度で関わることが大切です。患者会や支援団体の情報提供も有効です。
ヘンダーソン14基本的ニード
1. 呼吸
発作中に舌根沈下や分泌物により気道が塞がれる危険があります。発作時は患者の気道確保に注意し、必要に応じて吸引を準備します。抗てんかん薬の副作用による呼吸抑制も監視します。
2. 栄養と水分
一部の抗てんかん薬は栄養の吸収に影響するため、栄養状態を監視します。葉酸欠乏予防のため、緑色野菜の摂取を勧めます。発作によるエネルギー消費は大きいため、バランスの良い栄養管理が重要です。
3. 排泄
発作中の尿失禁や便失禁は患者に大きなストレスとなります。発作の予兆があれば、トイレ利用を促すなどの配慮が必要です。一部の抗てんかん薬は便秘を引き起こすため、排便パターンを把握し、必要に応じて下剤を検討します。
4. 安全と防御
これが最も重要なニードです。発作時の受傷防止のため、ベッド周囲にクッション材を配置し、危険物を除去します。発作時には無理に口を開けようとせず、けいれんを止めようと力を加えてはいけません。発作が5分以上続く場合は、てんかん重積状態として緊急対応が必要です。
5. 睡眠と休息
十分な睡眠はてんかん患者にとって非常に重要で、睡眠不足は発作の誘発因子になります。夜間の睡眠環境を整え、安心して眠れるよう支援します。また、疲労がたまらないよう、日中の活動と休息のバランスを調整します。
6. 着衣と身繕い
部分発作で自動症が見られる場合、着衣を破損したり脱いだりすることがあります。患者の尊厳を守りながら、発作に備えた対応を準備します。
看護計画・介入の内容
- 発作時の対応マニュアルを患者と家族に説明し、安全な環境を整備する。ベッド柵、クッション材の準備と、発作時の適切な対応(気道確保、誤嚥防止、頭部保護)を実施する
- 抗てんかん薬の用法・用量、効果と副作用について患者に丁寧に説明し、飲み忘れ防止の工夫(お薬手帳、アラーム機能付き薬ケースなど)を一緒に検討する
- 定期的な血液検査により、抗てんかん薬の血中濃度と肝機能、腎機能を監視し、医師に報告する
- 発作誘発因子(睡眠不足、ストレス、女性ホルモン周期など)を患者と一緒に把握し、誘発因子の回避方法を指導する
- 患者の心理状態を常に観察し、不安や抑うつがあれば医師・心理士に相談し、必要に応じてカウンセリングや薬物療法を検討する
- 学生患者の場合は、学校への報告と発作時対応の事前打ち合わせをサポートする
- 運転免許取得や職業選択等の生活制限について、患者が納得できるよう丁寧に説明する
よくある疑問・Q&A
Q: 発作中に患者の口に何か詰めるべきですか?
A: いいえ、これは古い誤った対応です。口に物を詰めると、歯や顎が破損したり、詰めたものが気道に入ったりする危険があります。むしろ、横向きに寝かせて気道を確保し、嘔吐物が誤嚥されないようすることが大切です。
Q: 抗てんかん薬を飲み始めたら、一生飲み続けなければいけませんか?
A: 発作が完全にコントロールされ、医師の判断のもとで薬を減らせる場合もあります。特に小児の一部のてんかんは、成長とともに治癒することもあります。ただし、自己判断で中止すると重積状態を起こす危険があるため、必ず医師に相談してから減薬決定をしてください。
Q: てんかんのある患者は運転できませんか?
A: 発作がコントロールされていない場合は、法律で運転が禁止されています。一定期間発作がない状態が続けば、医師の診断書により運転再開が可能になる場合もあります。患者の安全と社会的役割のバランスについて、医療者は丁寧にサポートする必要があります。
Q: 抗てんかん薬には危険な副作用がありますか?
A: 薬剤によって異なりますが、一般的には眠気、めまい、運動失調などが見られます。重篤な副作用として、スティーブンス・ジョンソン症候群などの重症皮膚反応がまれに起こります。定期的な血液検査と自覚症状の聴取により、早期発見・対応が可能です。
Q: 月経周期とてんかん発作に関係がありますか?
A: はい、女性患者の約30~40%が月経周期と関連した発作パターン(月経関連発作)を経験します。これはホルモン変動により脳の興奮性が変わるためです。患者に月経周期と発作の関係を記録してもらうと、パターンが見えやすくなり、対応策を立てやすくなります。
まとめ
てんかんは脳の異常放電による慢性神経疾患で、患者の人生に大きな影響を与えます。看護学生が理解すべき最も重要なポイントは、発作時の安全確保と患者の心理社会的サポートです。
医学的には、抗てんかん薬による発作のコントロールが治療の中心ですが、患者にとって同じくらい大切なのは、疾患と向き合う心理的な適応と、社会参加の継続です。発作に対する恐怖心や社会的偏見から、患者は不安や抑うつに陥りやすいため、看護者の支持的な関わりが極めて重要です。
臨床実習では、患者の発作パターンの聴取、日常生活上の工夫、家族への指導など、実践的で個別的な看護を心がけてください。また、発作時の対応は冷静さと知識が生命を救う場面となり得るため、対応マニュアルを十分に理解し、いざという時に実行できる準備をしておくことが大切です。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
・正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません


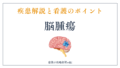
コメント