疾患概要
定義
肺水腫とは、肺胞内やその周囲の間質組織に異常に液体が貯留した状態を指します。本来、肺胞は空気で満たされているべきですが、何らかの原因で血管から液体成分が漏れ出し、肺胞内に水分が溜まってしまうことで、ガス交換が著しく障害されます。
肺水腫は大きく分けて心原性肺水腫と非心原性肺水腫の2つに分類されます。心原性肺水腫は心臓のポンプ機能低下により肺静脈圧が上昇して起こるもので、急性心不全の代表的な病態です。一方、非心原性肺水腫は肺の毛細血管透過性が亢進することで起こり、急性呼吸窮迫症候群(ARDS)などが含まれます。
疫学
肺水腫は主に心不全患者に多く見られ、日本における心不全患者数は約120万人と推定されています。高齢化に伴い心不全患者は増加傾向にあり、それに伴って心原性肺水腫の頻度も増えています。
急性心不全による入院患者の約30〜40%に肺水腫が認められるとされ、特に70歳以上の高齢者に多く発症します。男女比では、基礎疾患によって異なりますが、虚血性心疾患に起因する場合は男性にやや多く、弁膜症に起因する場合は女性にも多く見られます。
非心原性肺水腫は比較的まれですが、重症感染症、誤嚥、薬物中毒、高地での発症などさまざまな原因で起こり得ます。
原因
心原性肺水腫の主な原因
- 急性心筋梗塞による心機能低下
- 高血圧性心不全(血圧の急激な上昇)
- 心臓弁膜症(特に僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症)
- 拡張型心筋症などの心筋疾患
- 不整脈(特に心房細動の新規発症や頻脈)
- 過剰な輸液負荷
- 腎不全による体液過剰
非心原性肺水腫の主な原因
- 敗血症やARDSによる血管透過性亢進
- 誤嚥性肺炎
- 薬物中毒(ヘロイン、サリチル酸など)
- 高地肺水腫(急激な高所への移動)
- 神経原性肺水腫(頭部外傷、くも膜下出血後)
- 再膨張性肺水腫(気胸や胸水の急速な除去後)
病態生理
肺水腫の病態は、心原性と非心原性で異なるメカニズムで発症します。
心原性肺水腫のメカニズム
心臓のポンプ機能が低下すると、左心室から十分に血液を駆出できなくなり、左心房や肺静脈に血液が滞留します。その結果、肺静脈圧(肺毛細血管楔入圧)が上昇し、通常18mmHg以下に保たれている肺毛細血管圧が25mmHg以上に上昇すると、血管内の水分が血管外へ押し出されます。
最初は肺間質に液体が貯留し(間質性肺水腫)、さらに進行すると肺胞内にまで液体が漏出します(肺胞性肺水腫)。肺胞内に水分が溜まると、空気と血液のガス交換を行う場所が液体で満たされてしまうため、酸素化が著しく障害されます。
このプロセスは「Starlingの法則」に基づいており、血管内静水圧と膠質浸透圧のバランスが崩れることで液体の移動が起こります。健常な肺では、リンパ管が余分な間質液を排出していますが、急激な圧上昇や心不全の進行により、このリンパ排液能力を超えてしまうと肺水腫が発症します。
非心原性肺水腫のメカニズム
非心原性肺水腫では、肺静脈圧は正常であっても、肺毛細血管の透過性が亢進することで血管外へ液体が漏出します。炎症性サイトカインや細菌毒素などにより肺毛細血管内皮細胞が障害されると、血管壁のバリア機能が破綻し、タンパク質を含む血漿成分が肺胞内に流出します。
この液体はタンパク濃度が高く、肺サーファクタントの機能も障害されるため、肺胞が虚脱しやすくなり、無気肺を形成します。その結果、換気血流比の不均衡が生じ、重度の低酸素血症を引き起こします。
いずれのタイプでも、肺水腫が進行すると呼吸仕事量が増加し、呼吸筋疲労から呼吸不全に至る可能性があります。また、低酸素血症が持続すると多臓器不全につながる危険性もあるため、迅速な対応が求められます。
症状・診断・治療
症状
肺水腫の症状は急激に出現することが多く、生命に関わる緊急事態です。
主な症状
- 高度の呼吸困難:安静時でも息苦しさを訴え、会話も困難になります
- 起坐呼吸:横になると呼吸困難が増悪し、座位や前傾姿勢をとることで楽になります
- 頻呼吸と頻脈:呼吸数が25回/分以上、心拍数が100回/分以上に増加します
- ピンク色の泡沫状痰:肺胞内の液体と空気が混ざり、赤血球が混入した特徴的な痰が出ます
- チアノーゼ:低酸素血症により、口唇や爪床が紫色になります
- 冷汗と不安感:交感神経が亢進し、全身に冷汗をかき、強い不安や死の恐怖を感じます
- 湿性ラ音(水泡音):聴診で両肺野全体から細かい水泡音(crackles)が聴取されます
心原性肺水腫では、これらに加えて頸静脈の怒張、下腿浮腫、肝腫大などの心不全徴候を伴うことが多いです。非心原性肺水腫では、原疾患(敗血症、誤嚥など)の症状も同時に見られます。
診断
肺水腫の診断は、臨床症状、身体所見、画像検査、血液検査を総合的に評価して行われます。
胸部X線検査では、心原性肺水腫の場合、心拡大、肺門部の血管陰影増強(バタフライシャドウ)、Kerley B線(肺の下外側に見られる水平な線状陰影)、胸水貯留などが特徴的です。非心原性肺水腫では心拡大はなく、両側性のびまん性陰影が見られます。
心エコー検査は心原性か非心原性かの鑑別に有用で、左室駆出率(LVEF)の低下や弁膜症、壁運動異常などを評価します。
血液ガス分析では低酸素血症(PaO2低下)と呼吸性アルカローシス(PaCO2低下)が初期に見られ、進行すると呼吸性アシドーシスに転じることもあります。
BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)またはNT-proBNPは心原性肺水腫の診断に非常に有用で、心不全の重症度と相関します。BNPが100pg/mL以上、特に500pg/mL以上では心原性肺水腫の可能性が高くなります。
その他、心電図で心筋梗塞や不整脈の有無を確認し、胸部CT検査でより詳細な肺の状態を評価することもあります。
治療
肺水腫の治療は緊急性が高く、原因に応じた迅速な対応が必要です。
初期対応(ABC管理)
- 酸素療法:まず高濃度酸素投与を行い、SpO2を90%以上に維持します
- 体位管理:座位または半座位にして、静脈還流を減らし呼吸を楽にします
- 非侵襲的陽圧換気(NPPV):CPAP(持続陽圧呼吸)やBiPAPにより、肺胞を開いてガス交換を改善させます
- 挿管・人工呼吸管理:NPPVでも改善しない重症例では気管挿管が必要です
心原性肺水腫の薬物療法
- 利尿薬:フロセミド(ラシックス)などのループ利尿薬を静脈投与し、体液量を減らします
- 血管拡張薬:ニトログリセリンやニトロプルシドナトリウムにより前負荷・後負荷を軽減します
- 強心薬:心収縮力が著しく低下している場合、ドブタミンなどを使用します
- モルヒネ:不安を軽減し、血管拡張作用もあるため少量使用されることがあります
非心原性肺水腫の治療 原疾患の治療が中心となり、敗血症であれば抗菌薬投与と感染源コントロール、誤嚥であれば気道確保と抗菌薬投与などを行います。人工呼吸管理下で肺保護換気戦略を行い、肺損傷の進行を防ぎます。
原因疾患の治療 心筋梗塞であれば緊急カテーテル治療、弁膜症であれば手術的治療、高血圧性であれば降圧療法など、根本原因への対応も並行して行います。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- ガス交換障害:肺胞内液体貯留によるガス交換機能の低下
- 非効果的呼吸パターン:呼吸困難、頻呼吸による呼吸パターンの異常
- 活動耐性低下:低酸素血症と呼吸困難による日常生活動作の制限
- 不安:呼吸困難感と死への恐怖による強い不安
- 体液量過多(心原性の場合):心機能低下による体液貯留
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚-健康管理パターン 患者は突然の呼吸困難に強い不安を感じており、「死ぬかもしれない」という恐怖を訴えることが多いです。心不全の既往がある場合、服薬アドヒアランスや塩分・水分制限の遵守状況を確認することが重要です。急性発症の場合、前兆症状(息切れの増悪、浮腫の悪化、体重増加など)があったかを聴取し、今後の予防教育につなげます。
活動-運動パターン 重度の呼吸困難により、ほとんどの患者は安静時でも苦しく、体動することができません。起坐呼吸のため座位を保持していますが、長時間の座位により褥瘡のリスクも高まります。SpO2、呼吸数、呼吸パターン(浅速呼吸、努力呼吸の有無)、副雑音の聴診、チアノーゼの有無を継続的にモニタリングします。酸素療法やNPPVの装着状況、その効果も細かく観察します。
栄養-代謝パターン 呼吸困難により経口摂取が困難となり、栄養・水分摂取が制限されます。心原性肺水腫では体液過多の状態にあるため、厳密な水分管理が必要です。入院後は輸液量の調整と利尿薬投与により、1日の水分バランスをマイナスにコントロールします。体重測定、出入水分量の記録、浮腫の程度を毎日評価し、過剰な水分負荷を避けます。
睡眠-休息パターン 呼吸困難のため、横になって眠ることができず、座位や半座位での休息を余儀なくされます。夜間の睡眠が著しく障害されるため、不眠による疲労が蓄積します。症状が改善してくるまでは、安静と休息を優先し、ケアをまとめて実施するなど、睡眠を妨げない工夫が必要です。
認知-知覚パターン 低酸素血症により、意識レベルの変化や見当識障害が生じることがあります。特に高齢者では、せん妄のリスクが高まります。意識レベル(JCS、GCS)、見当識、指示への反応を定期的に評価し、低酸素血症の悪化や改善の指標とします。
ヘンダーソン14基本的ニード
1. 正常な呼吸 最も重要なニードであり、肺水腫患者では呼吸の維持が最優先課題です。起坐呼吸を取らせ、高濃度酸素投与やNPPV装着により呼吸を補助します。呼吸数、呼吸パターン、SpO2、チアノーゼの有無を継続的に観察し、悪化の兆候を早期に発見します。患者が呼吸に意識を集中しているため、穏やかな声かけと安心できる環境作りが大切です。
2. 適切な飲食 呼吸困難により経口摂取が困難なため、絶食または流動食で対応します。心原性肺水腫では水分制限が必要で、1日500〜1000mL程度に制限することが多いです。口渇を訴える場合は、氷片や湿らせたガーゼで口腔内を湿らせる工夫をします。症状改善後は、段階的に食事を再開し、塩分制限食(6g/日以下)の必要性を説明します。
3. 排泄 利尿薬投与により尿量が増加するため、尿量の正確な測定が必須です。心原性肺水腫では、体液過剰を改善するため、1日2000〜3000mL以上の尿量を目標とすることもあります。頻尿により患者は頻繁にトイレに行きたがりますが、呼吸困難があるため移動は困難です。尿器やポータブルトイレを活用し、安全にケアを提供します。
4. 体位の保持と変換 起坐呼吸のため、長時間の座位保持が必要ですが、褥瘡や筋肉疲労のリスクがあります。背もたれやクッションを使用し、快適な姿勢を保てるよう支援します。症状が軽快してきたら、徐々に体位変換を行い、肺の換気を促進させます。ただし、急激な体位変換は呼吸困難を増悪させるため、ゆっくりと行います。
8. 身体を清潔に保つ 呼吸困難と活動制限により、全身清拭や部分清拭で対応します。冷汗をかいているため、こまめに拭いて皮膚を清潔に保ちます。入浴やシャワーは症状が安定するまで控え、全身状態が改善してから段階的に再開します。清拭時は呼吸状態に注意し、疲労を最小限にするため短時間で効率的に行います。
9. 危険の回避 低酸素血症による意識レベルの変化や、利尿薬による起立性低血圧のため、転倒のリスクが高まります。ベッド周囲の環境を整え、ナースコールを手の届く位置に配置します。トイレ移動時は必ず付き添い、酸素チューブの管理にも注意します。NPPVマスクの装着により視野が制限されるため、安全な環境を確保します。
14. 学習 症状が落ち着いてきたら、肺水腫の再発予防についての患者教育を開始します。心不全の自己管理(毎日の体重測定、塩分・水分制限、服薬遵守、息切れや浮腫の悪化時の早期受診)について、具体的に説明します。退院後の生活指導や、家族も含めた教育が再入院予防につながります。
看護計画・介入の内容
- 呼吸状態の継続的モニタリング:呼吸数、SpO2、呼吸音、チアノーゼの有無を15〜30分ごとに観察し、急変の早期発見に努めます。酸素療法やNPPVの効果を評価し、効果が不十分な場合は医師に報告します
- 体位管理と安楽の提供:起坐呼吸を取らせ、前傾姿勢が楽な場合はオーバーテーブルに枕を置いてもたれさせるなど工夫します。長時間の同一体位による褥瘡予防のため、クッションで除圧し、可能な範囲で体位変換を行います
- 水分出納管理:入院後24時間の出入水分量を正確に記録し、利尿薬投与後の尿量増加を確認します。心原性肺水腫では水分バランスをマイナスに保つことが重要で、毎日の体重測定も実施します
- 不安の軽減:呼吸困難は強い不安を引き起こすため、穏やかな声かけと「そばにいますよ」という安心感を与えます。手を握る、背中をさするなどのタッチングも効果的です。深呼吸を促し、リラクゼーションを図ります
- 酸素療法・NPPV管理:酸素マスクやNPPVマスクの装着状態を確認し、皮膚トラブルや圧迫による痛みがないかチェックします。マスクのずれや酸素チューブの屈曲に注意し、効果的な酸素供給を維持します
- 循環動態の観察:血圧、心拍数、心電図モニタリングを継続し、不整脈や血圧変動に注意します。心原性肺水腫では血管拡張薬投与により血圧低下が起こることがあるため、過度な降圧に注意します
- バイタルサインの管理:体温、脈拍、血圧、呼吸数、SpO2を定期的に測定し、全身状態を評価します。発熱や頻脈は感染症や心不全の悪化を示唆するため、早期発見が重要です
- 口腔ケアと保湿:口呼吸や酸素投与により口腔内が乾燥しやすいため、定期的に口腔ケアを行い、保湿します。水分制限がある場合は、氷片や湿らせたガーゼで口渇を和らげます
- 感染予防:免疫力低下や侵襲的処置により感染リスクが高まるため、手指衛生を徹底し、清潔操作を守ります。発熱や痰の性状変化など、感染徴候の早期発見に努めます
- 患者・家族教育:症状が安定してきたら、心不全の自己管理方法について教育を開始します。毎日の体重測定、塩分・水分制限、服薬の重要性、症状悪化時の対応などを具体的に説明し、退院後の再発予防につなげます
よくある疑問・Q&A
Q: 肺水腫と心不全はどう違うのですか?
A: 肺水腫は心不全の一症状であり、重症の急性心不全で起こります。心不全とは心臓のポンプ機能が低下した状態全般を指し、慢性的に進行することが多いです。一方、肺水腫は心不全が急激に悪化して肺に水が溜まった緊急状態です。つまり、心不全の中でも特に重症で生命に関わる状態が肺水腫と言えます。ただし、心不全以外の原因(敗血症など)でも肺水腫は起こり得ます。
Q: 起坐呼吸はなぜ起こるのですか?横になると苦しくなる理由は?
A: 横になると重力により静脈血が心臓に戻りやすくなり、肺への血流が増加します。すでに肺水腫で肺がうっ血している状態では、さらに血流が増えることで呼吸困難が増悪します。座位や半座位では、重力により下半身に血液が貯留し、肺への血流が減少するため呼吸が楽になります。また、座位では横隔膜が下がり、肺が広がりやすくなる効果もあります。このため、肺水腫患者は自然と座った姿勢を好むようになります。
Q: ピンク色の泡沫状痰が出るのはなぜですか?
A: 肺胞内に溜まった液体が気道に押し出される際、呼吸により空気と混ざって泡立ちます。さらに、肺毛細血管から赤血球が漏出し、液体に混ざることでピンク色になります。この特徴的な痰は急性肺水腫の典型的な症状で、肺胞性肺水腫(重症)に進行した証拠です。大量に出ることもあり、気道閉塞のリスクもあるため、吸引などの処置が必要になります。
Q: 肺水腫の患者さんに水分制限をするのはなぜですか?どのくらい制限しますか?
A: 心原性肺水腫では、心臓が血液を十分に送り出せず、体内に水分が過剰に貯留している状態です。さらに水分を摂取すると体液量が増え、心臓の負担が増して肺水腫が悪化します。水分制限により体液量を減らし、心臓の負担を軽減させることが目的です。制限量は重症度により異なりますが、急性期は500〜1000mL/日程度に厳密に制限することが多く、症状改善後も1000〜1500mL/日程度の制限が継続されます。
Q: NPPVとはどのような治療法ですか?気管挿管とは違うのですか?
A: NPPV(非侵襲的陽圧換気)は、マスクを顔に装着して陽圧をかけることで呼吸を補助する治療法です。気管挿管のようにチューブを気道に入れる必要がないため「非侵襲的」と呼ばれます。CPAPやBiPAPがこれに含まれます。肺水腫では、陽圧により肺胞内の液体を押し出し、肺胞を開いた状態に保つことでガス交換を改善させます。NPPVで改善しない場合は気管挿管・人工呼吸管理が必要になりますが、まずはNPPVを試みることで挿管を避けられる患者も多くいます。
Q: 肺水腫の患者さんが急に落ち着かなくなったらどうすればいいですか?
A: 肺水腫患者の急な不穏や興奮は、低酸素血症の悪化や呼吸状態の増悪を示唆する重要なサインです。まずSpO2と呼吸状態を確認し、酸素投与が適切に行われているか、NPPVマスクがずれていないかをチェックします。意識レベルの変化も評価し、見当識障害やせん妄の有無を確認します。同時に、血圧や心拍数など全身状態を観察し、すぐに医師に報告します。患者には穏やかに声をかけ、安心感を与えることも大切ですが、急変の可能性を常に念頭に置き、迅速に対応する必要があります。
まとめ
肺水腫は肺胞内に液体が貯留してガス交換が障害される緊急性の高い病態であり、迅速な対応が患者の予後を左右します。心原性と非心原性に分類され、特に心原性肺水腫は急性心不全の代表的な症状として臨床でよく遭遇します。
病態の本質は、心臓のポンプ機能低下による肺静脈圧の上昇(心原性)、または肺毛細血管透過性の亢進(非心原性)により、血管内から液体が肺胞内へ漏出することです。この結果、重度の呼吸困難、起坐呼吸、ピンク色の泡沫状痰といった特徴的な症状が出現します。
看護の要点は、継続的な呼吸状態のモニタリングと迅速な対応です。SpO2、呼吸数、呼吸音、チアノーゼの観察を怠らず、酸素療法やNPPVの効果を評価します。起坐呼吸を取らせる体位管理、水分出納管理、不安の軽減も重要な看護介入です。
患者教育では、心不全の自己管理として毎日の体重測定、塩分・水分制限、服薬遵守、症状悪化時の早期受診の重要性を伝え、再発予防につなげます。
実習では、肺水腫患者の苦しそうな表情や呼吸困難の訴えに圧倒されるかもしれませんが、落ち着いて観察し、患者に寄り添う姿勢が大切です。病態を理解し、根拠に基づいた看護を提供することで、患者の回復を支援できます。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
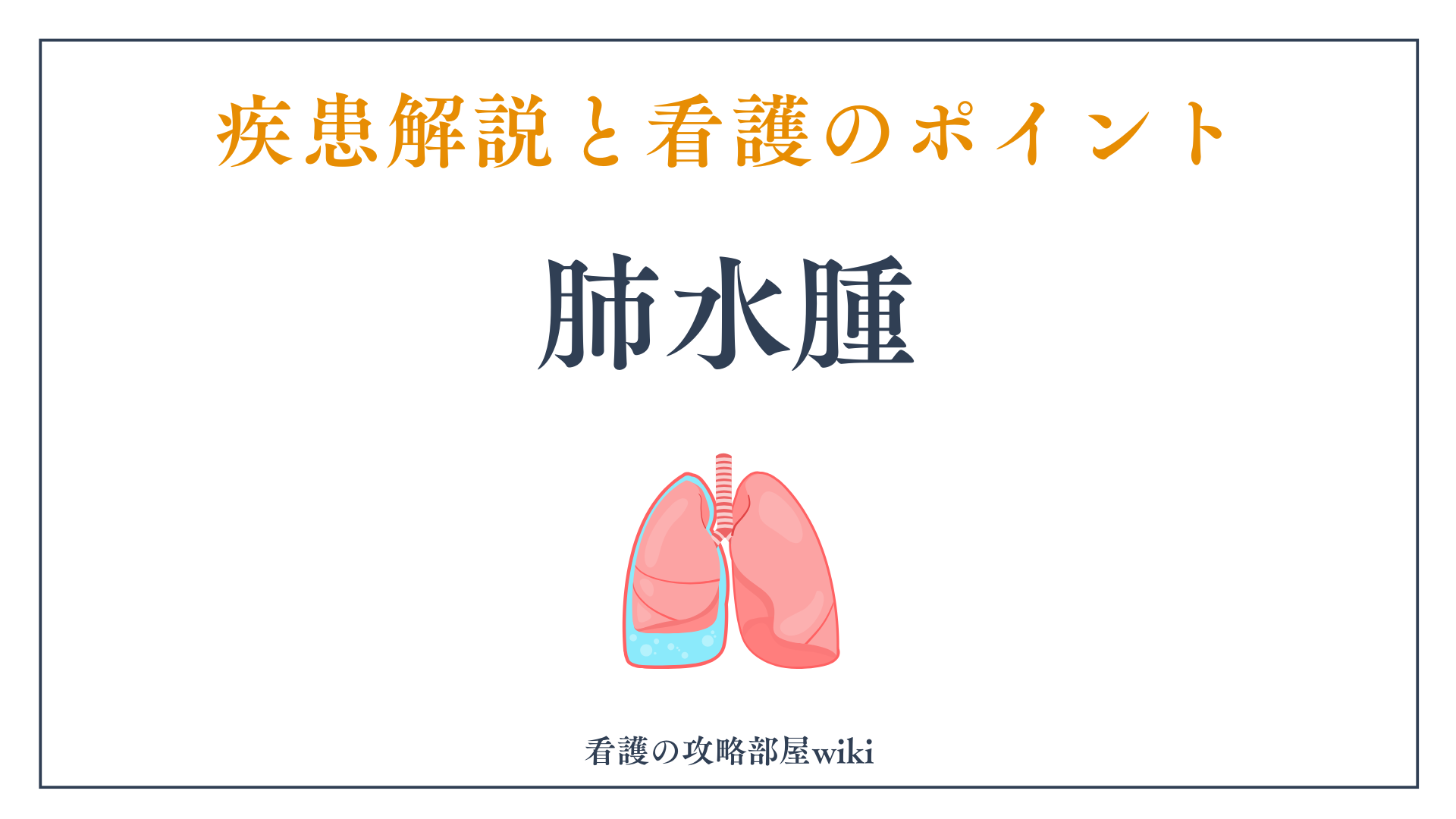
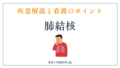

コメント