疾患概要
定義
肝炎とは、肝臓に炎症が起こり、肝細胞が破壊される疾患です。原因によってウイルス性肝炎、アルコール性肝炎、自己免疫性肝炎、薬剤性肝炎などに分類されます。また、経過により急性肝炎と慢性肝炎に分けられます。急性肝炎は6ヶ月以内に治癒するもので、慢性肝炎は6ヶ月以上炎症が持続し、進行すると肝硬変や肝癌へ移行する可能性があります。
疫学
日本において、ウイルス性肝炎は最も頻度の高い肝炎です。B型肝炎ウイルスのキャリアは約100〜130万人、C型肝炎ウイルスのキャリアは約150〜200万人と推定されています。年齢層では、B型肝炎は40〜50歳代、C型肝炎は60歳代以上に多い傾向があります。近年、C型肝炎の新規感染者は減少していますが、高齢のキャリアからの発症が問題となっています。A型肝炎は衛生環境の改善により国内感染は減少しましたが、海外渡航者での感染例がみられます。
アルコール性肝炎は、男性に多く、長期にわたる大量飲酒者に発症します。自己免疫性肝炎は中年以降の女性に好発し、比較的まれな疾患です。
原因
ウイルス性肝炎
肝炎ウイルスにはA型、B型、C型、D型、E型があります。日本で問題となるのは主にA型、B型、C型です。
A型肝炎ウイルスは経口感染し、急性肝炎を起こしますが慢性化することはありません。B型肝炎ウイルスは血液や体液を介して感染し、母子感染、性行為感染、医療行為での針刺し事故などが感染経路となります。成人が初感染した場合、多くは急性肝炎として治癒しますが、一部は慢性化します。C型肝炎ウイルスも血液を介して感染し、約70%が慢性化することが特徴です。
その他の原因
アルコール性肝炎は長期の過剰飲酒により発症します。目安として、日本酒換算で1日3合以上を10年以上継続すると発症リスクが高まります。自己免疫性肝炎は、自己の免疫系が肝細胞を攻撃することで起こります。薬剤性肝炎は、特定の薬剤による肝障害で、抗生物質、解熱鎮痛薬、抗てんかん薬などが原因となることがあります。
病態生理
肝炎の基本的な病態は、肝細胞の炎症と破壊です。しかし、その発症メカニズムは原因によって異なります。
ウイルス性肝炎では、ウイルスが肝細胞内に侵入して増殖します。興味深いことに、ウイルス自体が直接肝細胞を破壊するのではなく、ウイルスに感染した肝細胞を排除しようとする免疫反応が肝障害の主な原因となります。細胞傷害性T細胞がウイルス感染細胞を攻撃し、その過程で肝細胞が破壊されるのです。
肝細胞が破壊されると、細胞内にあった酵素が血液中に漏れ出します。これがAST(GOT)やALT(GPT)の上昇として検査値に現れます。特にALTは肝臓に特異的な酵素であり、肝障害の指標として重要です。
炎症が強いと、肝臓でのビリルビンの処理能力が低下します。ビリルビンは赤血球が分解される際に生成される黄色い色素で、通常は肝臓で処理されて胆汁中に排泄されます。しかし、肝機能が低下するとビリルビンが血液中に蓄積し、黄疸が出現します。黄疸は皮膚や眼球結膜が黄色くなる症状で、肝炎の重要な臨床徴候です。
急性肝炎の多くは、適切な安静と栄養管理により肝細胞が再生し、治癒します。しかし、B型肝炎やC型肝炎では慢性化することがあります。慢性肝炎では、持続的な炎症により肝細胞の破壊と再生が繰り返されます。この過程で、肝臓の線維化が徐々に進行し、最終的には肝硬変へと移行します。肝硬変になると肝機能が著しく低下し、さらに肝細胞癌の発生リスクも高まります。
劇症肝炎は、急性肝炎のうち極めて重症なもので、肝細胞の大量壊死により急速に肝不全に陥ります。意識障害(肝性脳症)、出血傾向、黄疸の急速な増悪などが特徴で、致死率が高い危険な状態です。
症状・診断・治療
症状
急性肝炎の症状
急性肝炎の初期症状は風邪に似ており、全身倦怠感、食欲不振、悪心、嘔吐、発熱などがみられます。これらの症状は非特異的で、患者さんは単なる風邪と思い込むこともあります。
数日から1週間後、黄疸が出現します。まず眼球結膜が黄色くなり、続いて皮膚全体が黄染します。黄疸とともに、尿の色が濃くなる(褐色尿、ビールのような色)ことも特徴的です。また、便の色が白っぽくなる(灰白色便)こともあります。これは、ビリルビンが胆汁として腸管に排泄されなくなるためです。
右上腹部痛や肝臓の腫大による圧迫感を訴えることもあります。一方、皮膚の掻痒感は、ビリルビンや胆汁酸が皮膚に沈着することで生じ、患者さんにとって非常に苦痛な症状です。
慢性肝炎の症状
慢性肝炎は、初期には自覚症状がほとんどありません。健康診断などで偶然発見されることが多いです。進行すると、全身倦怠感、易疲労感、食欲不振などが徐々に出現しますが、これらも非特異的な症状です。さらに進行して肝硬変に移行すると、腹水、浮腫、食道静脈瘤、肝性脳症などの重篤な症状が現れます。
診断
血液検査
肝炎の診断には血液検査が中心となります。肝機能検査では、AST、ALT、γ-GTP、ALP、ビリルビンなどを測定します。特にASTとALTの上昇は肝細胞の破壊を示し、急性肝炎では基準値の数十倍から数百倍に上昇することもあります。ALTの方がASTより高値を示すことが多いのが肝炎の特徴です。
ビリルビンは、直接ビリルビンと間接ビリルビンに分けられます。肝炎では主に直接ビリルビンが上昇します。また、肝臓でのタンパク質合成能を反映するアルブミンやプロトロンビン時間も重要な指標です。これらが低下すると肝機能の低下を意味します。
ウイルスマーカー
ウイルス性肝炎の診断には、各ウイルスに対する抗体や抗原の測定が必須です。B型肝炎ではHBs抗原、HBs抗体、HBe抗原、HBe抗体、HBc抗体などを測定します。C型肝炎ではHCV抗体とHCV-RNAを測定します。これらのマーカーパターンにより、感染の有無、病期、感染力の強さなどを判断します。
画像検査
腹部超音波検査やCTスキャンにより、肝臓の大きさ、形態、内部構造を評価します。慢性肝炎では肝臓の表面が粗く不整になり、肝硬変への進行度を評価できます。また、肝細胞癌の有無も確認します。
肝生検
必要に応じて、針を刺して肝組織を採取し、顕微鏡で観察する肝生検が行われます。炎症の程度、線維化の進行度、癌細胞の有無などを直接評価でき、確定診断や治療方針の決定に有用です。
治療
急性肝炎の治療
急性肝炎の基本は安静と栄養管理です。肝臓を休ませることが最も重要で、入院して安静を保ちます。食事は高カロリー・高タンパク質が推奨されますが、悪心や食欲不振が強い場合は輸液で栄養を補給します。
肝庇護薬(肝臓を保護する薬)が使用されることもありますが、特効薬はなく、対症療法が中心です。劇症肝炎に進行した場合は、集中治療が必要で、血漿交換、持続的血液濾過透析、場合によっては肝移植が検討されます。
慢性肝炎の治療
B型慢性肝炎では、抗ウイルス薬としてインターフェロンや核酸アナログ製剤が使用されます。核酸アナログ製剤はウイルスの増殖を抑制し、長期投与により肝炎の進行を抑えます。
C型慢性肝炎では、近年、直接作用型抗ウイルス薬(DAA)が登場し、治療成績が劇的に改善しました。8〜12週間の内服治療で、95%以上の患者さんでウイルスを排除できるようになりました。これはC型肝炎治療の革命的進歩です。
アルコール性肝炎では断酒が絶対的に必要です。自己免疫性肝炎ではステロイドや免疫抑制薬が使用されます。
すべての慢性肝炎患者さんに対して、定期的な血液検査と画像検査により、肝硬変や肝癌への進行を早期に発見することが重要です。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 活動耐性低下
- 栄養摂取消費バランス異常
- 皮膚統合性障害リスク状態
- 感染リスク状態
- 知識不足
ゴードン機能的健康パターン
栄養・代謝パターン
肝炎患者さんは食欲不振、悪心、嘔吐により栄養摂取が困難になることが多いです。しかし、肝細胞の再生には十分な栄養が必要です。摂取量、嗜好の変化、体重の推移を継続的にモニタリングします。急性期は輸液による栄養補給が中心ですが、症状が軽減したら経口摂取を促します。高カロリー・高タンパク質の食事が基本ですが、劇症肝炎や肝不全では逆にタンパク質制限が必要になるため、病態に応じた栄養管理が重要です。
黄疸や掻痒感により皮膚のケアも重要です。掻痒感は非常に苦痛で、不眠の原因にもなります。保湿剤の使用や冷却により症状を緩和し、爪を短く切って掻き傷を予防します。
活動・運動パターン
急性肝炎では安静が治療の基本です。特に黄疸が強い時期は、ベッド上安静が指示されることもあります。全身倦怠感が強く、活動耐性が著しく低下しているため、ADLの援助が必要です。しかし、長期臥床による廃用症候群を予防するため、症状の改善に合わせて段階的に活動を拡大していきます。
慢性肝炎では、過度な安静は不要ですが、過労を避け、適度な休息を取ることが大切です。患者さんの疲労度を評価し、生活リズムの調整を支援します。
排泄パターン
肝炎では、尿の色の変化(褐色尿)や便の色の変化(灰白色便)がみられます。これらは病態を反映する重要な観察ポイントです。尿量、排尿回数、尿の性状を観察し、脱水や腎機能障害の有無を評価します。
慢性肝炎が進行して肝硬変になると、腹水により尿量が減少することがあります。体重、腹囲、浮腫の有無を毎日チェックし、水分バランスを評価します。
ヘンダーソン14基本的ニード
正常に飲食する
食欲不振、悪心、嘔吐は肝炎患者さんの主要な症状です。少量頻回の食事、嗜好に合わせた食事内容の調整、食事時間の工夫などにより、摂取量の確保を図ります。悪心が強い場合は、制吐薬の使用も検討します。また、アルコール性肝炎では断酒指導、B型・C型肝炎では感染予防のための食事管理(食器の共用を避けるなど)も重要です。
正常に排泄する
前述の通り、尿と便の性状観察は病態把握に重要です。患者さん自身にも色の変化について説明し、異常があれば報告するよう指導します。また、掻痒感により夜間の睡眠が妨げられ、生活リズムが乱れることもあるため、排泄リズムへの影響も評価します。
身体の清潔を保ち、身だしなみを整え、皮膚を保護する
黄疸による掻痒感は、患者さんにとって非常に苦痛です。毎日の清拭や入浴により皮膚を清潔に保ち、掻痒感の軽減を図ります。ただし、熱い湯は掻痒感を増強させるため、ぬるめの温度が適しています。保湿剤を塗布し、皮膚の乾燥を防ぎます。掻き壊しによる感染を予防するため、爪を短く切り、必要に応じて手袋の着用も検討します。
働くこと、達成感を得ること
肝炎、特に慢性肝炎では、長期にわたる治療が必要となり、仕事や学業への影響が大きくなります。患者さんは「周囲に迷惑をかけている」「仕事を続けられるだろうか」といった不安を抱えます。病状に応じた就労や学業の調整について、患者さん、家族、医療チームで話し合い、社会復帰を支援します。また、偏見や差別を受けることへの不安もあるため、心理的サポートが重要です。
自分の感情、欲求、恐怖、あるいは気分を表現してコミュニケーションをとる
肝炎、特にウイルス性肝炎では、感染症であることへの不安、周囲への感染を心配する気持ち、偏見を受けるのではないかという恐れなど、多くの心理的負担があります。これらの感情を表出できる環境を整え、傾聴する姿勢が大切です。また、正しい知識を提供し、不必要な不安を軽減します。慢性肝炎では、長期にわたる治療や将来への不安もあるため、継続的な心理的サポートが必要です。
看護計画・介入の内容
- バイタルサインの監視: 発熱、脈拍、血圧を定期的に測定し、全身状態を評価する
- 黄疸の観察: 眼球結膜、皮膚の黄染の程度を毎日観察し、ビリルビン値と照らし合わせて評価する
- 尿・便の性状観察: 尿の色(褐色尿)、便の色(灰白色便)を観察し、変化を記録する
- 掻痒感のケア: 保湿剤の塗布、冷罨法、爪切り、必要に応じて制痒薬の使用を検討する。掻痒感の程度をスケールで評価する
- 栄養状態の評価: 食事摂取量、体重、血清アルブミン値を継続的にモニタリングし、栄養状態を評価する
- 安静度の管理: 病態に応じた適切な安静度を保ち、過労を避ける。回復期には段階的に活動を拡大する
- 検査データの確認: AST、ALT、ビリルビン、アルブミン、プロトロンビン時間などを定期的に確認し、肝機能の推移を評価する
- 感染予防: 劇症肝炎や重症例では易感染状態となるため、手指衛生を徹底し、感染兆候の早期発見に努める
- 出血傾向の観察: 肝機能低下により凝固因子の産生が低下するため、歯肉出血、皮下出血、血尿、タール便などの出血兆候を観察する
- 意識レベルの観察: 劇症肝炎では肝性脳症のリスクがあるため、意識レベル、見当識、羽ばたき振戦(アステリクシス)の有無を観察する
- 患者・家族教育: 疾患の理解促進、感染予防策(B型・C型肝炎)、断酒の重要性(アルコール性肝炎)、定期受診の必要性、肝癌スクリーニングの重要性について説明する
- 心理的サポート: 不安や恐れを傾聴し、偏見や差別への対処、社会復帰への支援を行う
よくある疑問・Q&A
Q: 肝炎の患者さんは入院中、なぜ安静が必要なのですか?
A: 肝細胞が炎症によりダメージを受けている状態では、肝臓に十分な血流を送り、エネルギーを肝細胞の修復・再生に集中させることが重要です。活動により全身の血流需要が増えると、肝臓への血流が相対的に減少し、肝細胞の回復が遅れてしまいます。また、活動によりエネルギーが消費されると、肝細胞の再生に必要なエネルギーが不足します。安静により肝臓を休ませ、回復を促進することが治療の基本なのです。ただし、症状が改善したら過度の安静は不要で、段階的に活動を拡大していきます。
Q: 黄疸が出ているとなぜ皮膚が痒くなるのですか?
A: 黄疸が出ると掻痒感を伴うことが多いのですが、そのメカニズムは完全には解明されていません。従来はビリルビン自体が原因と考えられていましたが、現在では胆汁酸が皮膚に沈着し、神経を刺激することが主な原因と考えられています。肝機能が低下すると、胆汁酸が血液中に増加し、皮膚に蓄積します。この掻痒感は非常に強く、患者さんの睡眠を妨げ、QOLを著しく低下させます。看護では、皮膚の保湿、冷罨法、爪の管理などにより掻痒感を軽減し、掻き壊しによる皮膚損傷を予防することが重要です。
Q: 急性肝炎と慢性肝炎の違いは何ですか? どちらが重症ですか?
A: 急性肝炎は6ヶ月以内に治癒する肝炎で、慢性肝炎は6ヶ月以上炎症が持続する肝炎です。急性肝炎は突然発症し、症状は強いですが、多くは数週間から数ヶ月で完全に回復します。ただし、まれに劇症肝炎という非常に重症な状態に進行することがあり、この場合は生命に関わります。一方、慢性肝炎は初期には自覚症状が乏しく、ゆっくりと進行しますが、放置すると肝硬変や肝癌へ移行するリスクがあります。どちらが重症かは一概には言えませんが、急性期の症状の強さは急性肝炎が上回り、長期的な予後への影響は慢性肝炎の方が深刻です。
Q: B型肝炎やC型肝炎の患者さんのケアで、看護師が感染しないために注意することは何ですか?
A: B型肝炎とC型肝炎は血液を介して感染するため、血液に直接触れないことが最も重要です。具体的には、採血や注射などの処置時に針刺し事故を起こさないよう、細心の注意を払います。使用済みの針は絶対にリキャップせず、専用の廃棄容器にすぐに捨てます。また、手袋を着用し、患者さんの血液が付着した器具や物品を扱う際は標準予防策を徹底します。もし針刺し事故が起きた場合は、直ちに流水で洗い、上司に報告し、医療機関の針刺し事故対応プロトコールに従います。B型肝炎に関しては、医療従事者はワクチン接種により予防できますので、未接種の方は接種を検討してください。日常的な接触(握手、会話、食器の共用など)では感染しませんので、患者さんを不当に隔離したり、差別的な対応をしないよう注意が必要です。
Q: アルコール性肝炎の患者さんに断酒指導をする際、どのように伝えればよいですか?
A: アルコール性肝炎では、断酒が唯一かつ最も重要な治療です。しかし、単に「お酒をやめなさい」と命令的に伝えるだけでは効果がありません。まず、患者さんの飲酒歴、飲酒に対する認識、飲酒の背景(ストレス、習慣、依存など)を丁寧に聴取します。その上で、アルコールが肝臓にどのようなダメージを与えているか、このまま飲酒を続けると肝硬変や肝癌に進行するリスクがあることを、検査データや画像を用いて具体的に説明します。しかし、説明だけでは不十分で、患者さんがなぜお酒を飲むのか、その理由に寄り添うことが大切です。アルコール依存症が疑われる場合は、専門医療機関への紹介や、家族を含めた支援体制の構築が必要です。断酒は患者さん一人では難しいことも多いため、継続的なフォローアップと励ましが重要です。
まとめ
肝炎は、肝臓に炎症が起こり肝細胞が破壊される疾患で、原因によりウイルス性、アルコール性、自己免疫性、薬剤性などに分類されます。日本ではB型・C型肝炎ウイルスによる慢性肝炎が多く、肝硬変や肝癌への進行が問題となります。
病態の本質は肝細胞の炎症と破壊であり、これにより肝機能が低下します。主な症状は、全身倦怠感、食欲不振、黄疸、掻痒感、褐色尿、灰白色便などです。診断には、AST・ALTなどの肝機能検査とウイルスマーカーが重要です。
看護のポイントは、急性期における安静と栄養管理、黄疸と掻痒感のケア、バイタルサインと検査データの継続的モニタリングです。特に掻痒感は患者さんのQOLを著しく低下させるため、保湿や冷罨法により症状を軽減します。
慢性肝炎では、抗ウイルス治療の確実な実施と、定期的な検査による肝硬変・肝癌への進行の早期発見が重要です。アルコール性肝炎では断酒指導が治療の要となります。
また、B型・C型肝炎は血液を介して感染するため、標準予防策の徹底と針刺し事故の予防が看護師自身を守るために必須です。一方で、日常的な接触では感染しないため、患者さんへの偏見や差別を避け、心理的サポートを提供することも重要な役割です。
実習では、患者さんの症状や検査データを丁寧に観察し、肝機能の変化を的確に捉えましょう。また、長期にわたる治療が必要な患者さんの不安に寄り添い、励まし続ける姿勢を大切にしてください。肝炎は適切な治療により改善が期待できる疾患です。根拠に基づいた


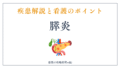
コメント