疾患概要
定義
副鼻腔炎は、頭蓋骨内にある副鼻腔(上顎洞、篩骨洞、前頭洞、蝶形骨洞)の粘膜に炎症が生じる疾患です。症状の持続期間により急性副鼻腔炎(4週間未満)、亜急性副鼻腔炎(4-12週間)、慢性副鼻腔炎(12週間以上)に分類されます。慢性副鼻腔炎はさらに好酸球性副鼻腔炎と非好酸球性副鼻腔炎に分けられ、それぞれ病態や治療法が異なります。俗に「蓄膿症」とも呼ばれます。
疫学
日本では約1,000万人が副鼻腔炎に罹患していると推定され、耳鼻咽喉科を受診する最も多い疾患の一つです。急性副鼻腔炎は小児から成人まで幅広い年齢層に発症し、特に上気道感染症の流行する秋から春にかけて頻度が増加します。慢性副鼻腔炎は成人に多く、男女差はあまりありません。近年、好酸球性副鼻腔炎の増加が注目されており、難治性で再発しやすい特徴があります。
原因
急性副鼻腔炎は上気道感染症(かぜ)に続発することが最も多く、原因菌として肺炎球菌、インフルエンザ菌、黄色ブドウ球菌などが挙げられます。慢性副鼻腔炎の原因は多因子性で、細菌感染、アレルギー、免疫異常、解剖学的異常(鼻中隔弯曲症、鼻茸など)が複合的に関与します。好酸球性副鼻腔炎はアスピリン不耐症、気管支喘息との合併が多く、アレルギー性機序が関与すると考えられています。その他の誘因として大気汚染、喫煙、歯性感染なども挙げられます。
病態生理
副鼻腔炎の発症には自然孔の閉塞が重要な役割を果たします。副鼻腔は自然孔を通じて鼻腔と交通しており、換気と排液が行われています。感染やアレルギーにより粘膜が腫脹すると自然孔が閉塞し、副鼻腔内の換気不良と分泌物の貯留が生じます。これにより細菌の増殖が促進され、炎症が持続・拡大します。慢性副鼻腔炎では粘膜の線毛機能が低下し、粘液の粘稠性が増加して排液障害が悪化します。好酸球性副鼻腔炎では好酸球浸潤により組織破壊が進行し、鼻茸形成や嗅覚障害が高頻度に認められます。
症状・診断・治療
症状
急性副鼻腔炎では膿性鼻汁、鼻閉、頭痛・顔面痛、嗅覚障害が主症状です。上顎洞炎では頬部痛、前頭洞炎では前頭部痛、篩骨洞炎では眼窩周囲痛が特徴的で、前屈位で疼痛が増強します。発熱や全身倦怠感を伴うこともあります。慢性副鼻腔炎では膿性または粘性鼻汁、鼻閉、後鼻漏(鼻汁がのどに流れ込む)、嗅覚・味覚障害が持続します。頭重感や集中力低下など、QOLに大きく影響する症状も認められます。好酸球性副鼻腔炎では嗅覚障害が高度で、鼻茸による著明な鼻閉を呈します。
診断
診断は症状、鼻鏡所見、画像検査により総合的に行われます。鼻鏡検査では鼻粘膜の腫脹、膿性分泌物、鼻茸の有無を観察します。CT検査は副鼻腔炎の診断における最も重要な検査で、副鼻腔の陰影、骨壁の肥厚、自然孔の閉塞状況を詳細に評価できます。内視鏡検査では鼻腔・副鼻腔の詳細な観察が可能で、鼻汁の性状や鼻茸の状態を確認できます。血液検査では好酸球数やIgE値を測定し、好酸球性副鼻腔炎の診断に役立てます。嗅覚検査では嗅覚障害の程度を客観的に評価します。
治療
急性副鼻腔炎では抗菌薬治療が基本で、ペニシリン系、マクロライド系、セフェム系抗菌薬が使用されます。対症療法として去痰薬、抗ヒスタミン薬、点鼻薬を併用します。慢性副鼻腔炎では14員環マクロライド系抗菌薬(クラリスロマイシン、エリスロマイシン)の少量長期投与が第一選択です。保存的治療で改善しない場合は内視鏡下鼻内副鼻腔手術(ESS)を考慮します。好酸球性副鼻腔炎ではステロイド薬(経口、点鼻)が有効で、生物学的製剤(抗IL-5抗体)も使用されるようになりました。鼻洗浄や去痰薬などの補助療法も重要です。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 急性疼痛:副鼻腔の炎症と圧迫に関連した頭痛・顔面痛
- 非効果的気道クリアランス:粘稠な分泌物と線毛機能低下に関連した鼻閉
- 感覚知覚変調(嗅覚・味覚):副鼻腔炎による嗅覚・味覚障害
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚・健康管理パターンでは患者の副鼻腔炎に対する理解度と治療への取り組み姿勢を評価します。慢性副鼻腔炎は長期治療が必要で、服薬アドヒアランスや生活習慣の改善が治療成果に大きく影響します。認知・知覚パターンでは嗅覚・味覚障害の程度と日常生活への影響を詳細にアセスメントします。食事の楽しみの減少や危険察知能力の低下(ガス漏れ、食品の腐敗)などの問題を把握します。活動・運動パターンでは鼻閉による呼吸困難感や睡眠障害の有無を評価し、日中の活動への影響を確認します。
ヘンダーソン14基本的ニード
正常な呼吸をするでは鼻閉の程度と口呼吸の頻度を評価し、効果的な鼻呼吸の回復を支援します。鼻洗浄や点鼻薬の適切な使用方法を指導し、気道クリアランスの改善を図ります。食べる・飲むでは嗅覚・味覚障害による食事摂取への影響を評価し、栄養状態の維持を支援します。眠る・休むでは鼻閉による睡眠の質の低下や睡眠時無呼吸症候群のリスクを評価し、良質な睡眠の確保を支援します。
看護計画・介入の内容
- 症状緩和・気道管理:適切な鼻洗浄方法の指導、点鼻薬の正しい使用法指導、加湿による鼻粘膜の保護、体位による症状軽減法の指導(頭部挙上位での睡眠)
- 服薬管理・指導:抗菌薬の適切な服薬方法と完遂の重要性説明、ステロイド薬使用時の副作用観察と対処法、点鼻薬の使用回数と期間の管理、薬剤の保管方法指導
- 生活習慣の改善支援:禁煙指導、アレルゲン回避のための環境整備、手洗い・うがいの励行、適切な鼻かみ方法の指導、ストレス管理の支援
よくある疑問・Q&A
Q: 副鼻腔炎は完全に治りますか?再発しやすいのでしょうか?
A: 急性副鼻腔炎は適切な治療によりほとんどの場合完治します。しかし、慢性副鼻腔炎は完治が困難で、症状のコントロールが治療目標となります。特に好酸球性副鼻腔炎は再発しやすく、長期的な管理が必要です。再発予防には適切な薬物療法の継続、生活習慣の改善、定期的な受診が重要です。手術治療を行った場合でも、術後の継続的な薬物療法により良好な状態を維持することができます。
Q: 鼻洗浄はどのように行えばよいですか?痛くないでしょうか?
A: 鼻洗浄は生理食塩水(0.9%食塩水)を使用して行います。市販の鼻洗浄器具を使用するか、清潔なスポイトやシリンジを用いて、片側の鼻孔から生理食塩水を注入し、反対側の鼻孔から流出させます。体温程度の温度にすることで痛みや不快感を軽減できます。最初は違和感がありますが、慣れれば痛みはありません。1日2-3回、特に朝と就寝前に行うと効果的です。水道水は避け、必ず生理食塩水を使用してください。
Q: 点鼻薬は長期間使用しても大丈夫ですか?
A: 点鼻薬の種類により使用期間が異なります。血管収縮薬(ナファゾリンなど)は連続使用を1週間以内に限定する必要があります。長期使用すると薬剤性鼻炎を引き起こし、かえって鼻閉が悪化します。一方、ステロイド点鼻薬は医師の指示に従えば長期間安全に使用できます。正しい点鼻方法(鼻孔を清潔にしてから使用、容器の先端を鼻に触れさせない)を守り、決められた回数・量を守ることが重要です。
Q: 嗅覚・味覚障害は回復しますか?日常生活で注意することはありますか?
A: 嗅覚・味覚障害の回復は副鼻腔炎の改善程度により異なります。急性副鼻腔炎による障害は炎症の改善とともに回復することが多いですが、慢性副鼻腔炎、特に好酸球性副鼻腔炎では回復が困難な場合があります。日常生活では安全面への注意が重要で、ガス漏れ、煙、食品の腐敗などの察知が困難になります。ガス警報器の設置、食品の消費期限確認、火の元の注意などの対策が必要です。また、食事の楽しみが減少するため、見た目や食感を重視した食事の工夫も大切です。
まとめ
副鼻腔炎は上気道の最も頻度の高い疾患の一つであり、急性から慢性まで幅広い病態を示します。病態の中心は自然孔の閉塞による換気・排液障害であり、これにより細菌感染や炎症の遷延化が生じます。近年、好酸球性副鼻腔炎など難治性の病型も増加しており、個々の病態に応じた治療選択が重要となっています。
看護の要点は症状マネジメントとセルフケア能力の向上です。特に鼻閉や疼痛などの不快症状の軽減は患者さんのQOL向上に直結します。鼻洗浄や点鼻薬の適切な使用法の指導は、症状改善と再発予防の両面で重要な看護介入となります。
また、嗅覚・味覚障害への対応も重要な看護の視点です。これらの障害は食事の楽しみを奪い、安全面でのリスクも生じるため、患者さんの生活全体への影響を包括的にアセスメントし、具体的な対策を提案することが必要です。
慢性副鼻腔炎では長期治療への支援が不可欠です。症状が改善してもすぐに治療を中断せず、医師の指示に従って継続することの重要性を説明し、患者さんのモチベーション維持を支援します。
実習では患者さんの症状の主観的評価と客観的な観察を組み合わせたアセスメントを心がけましょう。鼻閉の程度、分泌物の性状、疼痛の部位と程度などを詳細に把握し、個別性のある看護介入を計画することが大切です。また、予防教育を通じて再発防止に向けた生活習慣の改善を支援し、患者さんが疾患と上手に付き合いながら良好なQOLを維持できるよう支援していきましょう。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
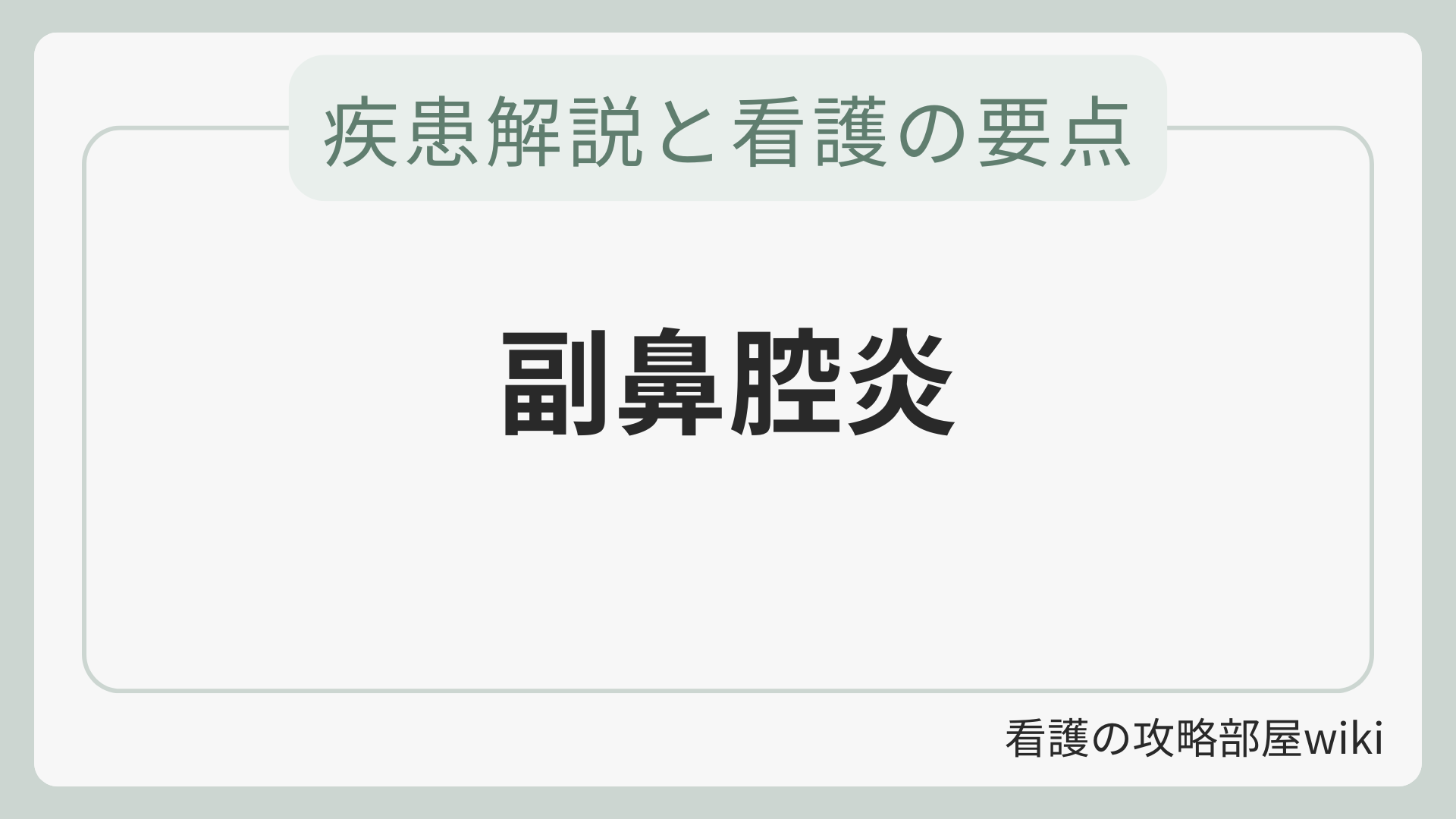
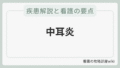
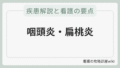
コメント