疾患概要
定義
肺がんとは、気管、気管支、肺胞などの肺組織から発生する悪性腫瘍です。日本におけるがん死亡原因の第1位であり、男性では最も多く、女性では大腸がんに次いで2番目に多いがんです。
肺がんは大きく分けて小細胞肺がんと非小細胞肺がんの2つに分類されます。この分類は治療方針を決定する上で非常に重要です。
非小細胞肺がん(約85%)は、さらに以下のように細分類されます:
- 腺がん(約60%):肺がん全体で最も多く、非喫煙者や女性に多い。肺の末梢部に発生しやすい
- 扁平上皮がん(約20%):喫煙との関連が強く、肺の中枢部(太い気管支)に発生しやすい
- 大細胞がん(約5%):増殖が速く、予後が悪い傾向がある
小細胞肺がん(約15%)は、増殖速度が非常に速く、早期から転移しやすい特徴があります。喫煙との関連が極めて強く、中枢部に発生することが多いです。
肺がんは進行度により病期(ステージ)I〜IV期に分類され、病期と組織型により治療方針が決定されます。
疫学
日本における肺がんの年間罹患者数は約13万人、死亡者数は約7万5千人に上り、がん死亡の約20%を占めます。罹患率、死亡率ともに増加傾向が続いています。
年齢では、60歳代から増加し、70歳代がピークです。しかし、近年は若年者(40〜50歳代)の肺がんも増加しています。
性別では、男性の方が女性より約2倍多く発症します。ただし、女性の肺がん(特に腺がん)は増加傾向にあり、女性のがん死亡原因では大腸がんに次いで第2位です。
組織型の変化として、かつては扁平上皮がんが最も多かったのですが、現在は腺がんが最多となっています。これは喫煙率の低下や低タール・フィルター付きタバコの普及により、煙が肺の奥深くまで到達するようになったことが一因と考えられています。
5年生存率は全体で約40%程度ですが、病期により大きく異なります。I期(早期)では約80%、II期で約50%、III期で約20%、IV期(遠隔転移あり)では約5%と、早期発見が予後を大きく左右します。
原因
肺がんの原因として、喫煙が最大のリスク因子です。
喫煙関連
- 喫煙者は非喫煙者に比べて、肺がんリスクが男性で4〜5倍、女性で3〜4倍高くなります
- 喫煙開始年齢が若いほど、喫煙期間が長いほど、喫煙本数が多いほど、リスクが高まります
- 受動喫煙も肺がんリスクを約1.3倍高めます
- 禁煙により、肺がんリスクは徐々に低下しますが、非喫煙者レベルには戻りません
その他のリスク因子
- 職業性曝露:アスベスト(石綿)、ラドン、クロム、ニッケル、ヒ素などへの曝露
- 大気汚染:PM2.5などの微小粒子物質
- 既往歴:COPD、肺線維症、結核などの慢性肺疾患
- 家族歴:肺がんの家族歴がある場合、リスクが1.5〜2倍になります
- 加齢:年齢とともにリスクが増加します
重要な点として、腺がんの約40〜50%は非喫煙者に発症します。特に女性の腺がんでは、非喫煙者の割合が高く、EGFR遺伝子変異などの遺伝子異常が関与していることが明らかになっています。
近年、ゲノム医療の進歩により、EGFR、ALK、ROS1、BRAF、MET、RET、NTRK、KRAS、HER2などの遺伝子異常(ドライバー変異)が同定され、これらに対する分子標的薬が開発されています。遺伝子変異の有無により治療方針が大きく変わるため、診断時に遺伝子検査が推奨されます。
病態生理
肺がんの発生から進展までの過程を理解することは、治療と看護の根拠を理解する上で重要です。
発がんのメカニズム
肺がんは、正常な気管支や肺胞の上皮細胞の遺伝子に複数の異常(変異)が蓄積することで発生します。喫煙や環境因子によりDNA損傷が繰り返されると、細胞の増殖や死をコントロールする遺伝子(がん遺伝子、がん抑制遺伝子)に異常が生じます。これにより、細胞が無秩序に増殖し、死ななくなり(不死化)、がん細胞が形成されます。
局所進展
がん細胞は増殖を続け、周囲の正常組織に浸潤していきます。肺がんが進行すると、以下の構造に浸潤します:
- 気管支:気道が狭窄し、閉塞性肺炎や無気肺を起こします
- 肺血管:血管に浸潤すると血痰や喀血を起こします
- 胸膜:胸膜に浸潤すると胸痛や胸水(癌性胸膜炎)が生じます
- 縦隔:食道、心臓、大血管に浸潤すると、嚥下困難や上大静脈症候群を起こします
- 胸壁:胸壁に浸潤すると激しい胸痛が生じます
- 横隔神経、反回神経:神経に浸潤すると、横隔膜麻痺や嗄声(声のかすれ)が生じます
リンパ節転移
肺がん細胞はリンパ管を通じて、まず肺門リンパ節、次に縦隔リンパ節へと転移していきます。さらに進行すると、鎖骨上リンパ節などの遠隔リンパ節にも転移します。
血行性転移
がん細胞が血管内に侵入すると、血流に乗って全身に運ばれ、遠隔臓器に転移します。肺がんの転移好発部位は:
- 脳(約30%):頭痛、けいれん、運動麻痺、意識障害などが出現
- 骨(約30%):骨痛、病的骨折、高カルシウム血症
- 肝臓(約20%):初期は無症状、進行すると肝機能障害、腹水
- 副腎(約10%):多くは無症状
- 反対側の肺:多発性肺転移
小細胞肺がんは特に早期から血行性転移を起こしやすく、診断時に約60〜70%が既に転移を伴っています。
がんの随伴症状(腫瘍随伴症候群)
肺がんは、がん自体が産生するホルモンや物質により、さまざまな全身症状を引き起こすことがあります:
- 高カルシウム血症:扁平上皮がんで多く、倦怠感、意識障害、腎障害を起こします
- SIADH(抗利尿ホルモン不適合分泌症候群):小細胞肺がんで多く、低ナトリウム血症により倦怠感、意識障害を起こします
- クッシング症候群:小細胞肺がんがACTH様物質を産生し、高血糖、浮腫、易感染性を起こします
- 肥厚性肺性骨関節症:関節痛、ばち指(指先が太鼓のばちのように丸く膨らむ)
- Lambert-Eaton症候群:小細胞肺がんで見られる筋力低下
これらの随伴症状は、時に肺がんの初発症状となることもあります。
病期分類(TNM分類)
肺がんの進行度は、T(原発腫瘍の大きさと浸潤範囲)、N(リンパ節転移の程度)、M(遠隔転移の有無)により評価され、これらを組み合わせて病期(I〜IV期)が決定されます。病期により治療方針と予後が大きく異なります。
症状・診断・治療
症状
肺がんの症状は、初期にはほとんど無症状であることが多く、進行してから症状が出現します。これが早期発見を困難にしている要因です。
呼吸器症状
- 咳:最も多い症状で、約50〜75%に見られます。気管支に浸潤すると、長引く乾性咳嗽や血痰を伴う咳が出現します。もともと咳があった喫煙者では、咳の性質の変化(増悪、血痰の出現)に注意が必要です
- 血痰・喀血:がんが血管に浸潤すると、血痰や喀血が生じます。少量の血痰から大量喀血まで程度はさまざまです
- 呼吸困難:腫瘍による気道狭窄、閉塞性肺炎、無気肺、胸水貯留、がん性リンパ管症などにより呼吸困難が生じます
- 喘鳴:気管や太い気管支が狭窄すると、ゼーゼーという呼吸音が聞こえます
- 胸痛:胸膜や胸壁に浸潤すると、持続的な鈍い痛みや鋭い痛みが生じます
局所進展による症状
- 嗄声(声のかすれ):反回神経に浸潤すると、声帯麻痺により嗄声が出現します
- 嚥下困難:食道に浸潤すると嚥下困難が生じます
- 上大静脈症候群:上大静脈が圧迫されると、顔面・上肢の浮腫、頸静脈怒張、呼吸困難が出現します
- Horner症候群:肺尖部の腫瘍(Pancoast腫瘍)が交感神経節に浸潤すると、縮瞳、眼瞼下垂、顔面の発汗低下が出現します
転移による症状
- 脳転移:頭痛、嘔気・嘔吐、けいれん、運動麻痺、意識障害、性格変化
- 骨転移:骨痛、病的骨折、脊髄圧迫による麻痺
- 肝転移:腹部膨満、黄疸、肝機能障害(進行時)
全身症状
- 体重減少:食欲不振とがんによる代謝亢進により、体重が減少します
- 全身倦怠感:進行がんでは強い倦怠感が出現します
- 発熱:閉塞性肺炎や腫瘍熱により発熱が続くことがあります
重要な点として、早期の肺がんは無症状であることが多いため、症状が出現した時点で既に進行していることが少なくありません。
診断
肺がんの診断は、画像検査と病理学的診断(組織診または細胞診)の組み合わせで行われます。
胸部X線検査
最も基本的な検査で、健康診断や人間ドックで肺がんが発見されることがあります。肺野に結節影や腫瘤影、無気肺、胸水などが見られます。ただし、早期の小さながんや心臓の陰に隠れたがんは見つけにくいことがあります。
胸部CT検査
肺がん診断の中心的な検査です。腫瘍の大きさ、位置、形態、周囲組織への浸潤、リンパ節腫大、遠隔転移の有無を詳細に評価できます。造影剤を使用することで、血管との関係や転移の評価がより正確になります。
PET-CT検査
がん細胞が正常細胞よりも多くのブドウ糖を取り込む性質を利用した検査です。全身のがんの広がり(リンパ節転移や遠隔転移)を一度に評価できます。ただし、炎症や感染でも集積するため、偽陽性に注意が必要です。
気管支鏡検査
気管支内視鏡を気管支に挿入し、腫瘍を直接観察し、生検(組織採取)や細胞診を行います。中枢型の肺がんの診断に有用ですが、末梢型では到達困難なこともあります。
経皮的肺生検
CTガイド下に、胸壁から針を刺して肺腫瘍の組織を採取します。末梢型の肺がんの診断に有用ですが、気胸や出血のリスクがあります。
喀痰細胞診
痰の中のがん細胞を顕微鏡で観察します。中枢型の肺がんで陽性率が高いですが、末梢型では陽性率が低くなります。非侵襲的な検査ですが、確定診断には組織診が必要です。
遺伝子検査(ゲノムプロファイリング)
非小細胞肺がんでは、EGFR、ALK、ROS1、BRAF、MET、RET、NTRK、KRAS、HER2などの遺伝子変異を調べます。遺伝子変異陽性の場合、それに対応する分子標的薬が使用できるため、治療方針決定に重要です。近年は、複数の遺伝子を同時に調べるがん遺伝子パネル検査が保険適用となっています。
腫瘍マーカー
CEA、CYFRA、ProGRP、SCC、NSEなどの腫瘍マーカーが測定されます。診断の補助、治療効果の判定、再発の早期発見に用いられますが、マーカーのみでは確定診断できません。
病期診断
診断確定後、CT、PET-CT、頭部MRI、骨シンチグラフィーなどにより、病期(ステージ)を決定します。病期により治療方針が大きく変わるため、正確な病期診断が重要です。
治療
肺がんの治療は、組織型(小細胞か非小細胞か)、病期、遺伝子変異の有無、患者の全身状態(PS: Performance Status)により決定されます。
非小細胞肺がんの治療
I〜II期(早期)
- 手術療法が第一選択です。肺葉切除+リンパ節郭清が標準術式で、早期であれば胸腔鏡下手術(VATS)が行われます。I期の5年生存率は約80%と良好です
- 術後補助化学療法:II期やIII期の一部では、再発予防のため術後に化学療法を行います
III期(局所進行)
- 手術可能な場合:手術+術前・術後化学療法または術後放射線療法
- 手術不可能な場合:化学放射線療法(抗がん剤と放射線を併用)、その後の免疫チェックポイント阻害薬による維持療法
IV期(遠隔転移あり)
- 遺伝子変異陽性の場合:分子標的薬が第一選択です
- EGFR変異陽性:ゲフィチニブ、エルロチニブ、オシメルチニブなどのEGFR-TKI
- ALK融合遺伝子陽性:アレクチニブ、クリゾチニブなどのALK-TKI
- その他の遺伝子変異に対する標的薬
- 遺伝子変異陰性の場合:化学療法+免疫チェックポイント阻害薬
- プラチナ製剤(シスプラチン、カルボプラチン)を含む2剤併用化学療法
- 免疫チェックポイント阻害薬(ペムブロリズマブ、アテゾリズマブなど)の併用または単剤
- 対症療法:緩和的放射線療法(骨転移、脳転移に対して)、症状緩和ケア
小細胞肺がんの治療
小細胞肺がんは増殖が速く、早期から転移するため、多くの場合化学療法が中心となります。
限局型(転移が片側胸腔内に限局)
- 化学放射線療法:シスプラチン+エトポシドなどの化学療法と胸部放射線療法を併用します
- 予防的全脳照射(PCI):脳転移予防のため、完全寛解が得られた場合に実施されることがあります
進展型(遠隔転移あり)
- 化学療法+免疫チェックポイント阻害薬:シスプラチン+エトポシド+アテゾリズマブまたはデュルバルマブ
- 二次化学療法:再発時にはアムルビシン、トポテカンなどが使用されます
放射線療法
- 根治的放射線療法:手術不能な局所進行肺がんに対して実施
- 緩和的放射線療法:骨転移の痛み、脳転移、上大静脈症候群、気道狭窄などの症状緩和
- 定位放射線治療(SBRT):早期肺がんで手術不能な場合、ピンポイントで高線量を照射
緩和ケア
進行がんでは、がんそのものの治療と並行して、早期から緩和ケアを導入することが推奨されています。痛み、呼吸困難、倦怠感などの症状緩和、精神的・社会的サポートを提供します。
新しい治療法
近年、免疫チェックポイント阻害薬(ペムブロリズマブ、ニボルマブ、アテゾリズマブなど)が登場し、一部の患者で劇的な効果を示しています。がん細胞が免疫細胞にかけているブレーキを外すことで、自己の免疫でがんを攻撃します。
また、がんゲノム医療の進歩により、個々の患者のがんの遺伝子異常を調べ、それに合った治療を選択する個別化医療が実現しつつあります。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- ガス交換障害:腫瘍による気道狭窄、閉塞性肺炎、胸水貯留による換気障害
- 非効果的気道浄化:咳嗽反射の低下、喀痰増加による気道クリアランスの低下
- 急性疼痛/慢性疼痛:がんの浸潤、骨転移による痛み
- 栄養摂取消費バランス異常:食欲不振、悪液質による栄養状態の悪化
- 不安・恐怖:がん診断、予後、治療への不安
- 非効果的コーピング:がん診断による心理的ストレス、将来への不安
- 活動耐性低下:呼吸困難、倦怠感、貧血による日常生活動作の制限
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚-健康管理パターン
肺がん診断は、患者にとって大きな衝撃です。多くの患者は「がん=死」というイメージを持っており、強い不安と恐怖を抱きます。診断の受け止め方は個人差が大きく、ショック、否認、怒り、抑うつなどさまざまな反応が見られます。患者がどの段階にいるのかを見極め、適切な心理的支援を提供することが重要です。
喫煙歴のある患者では、「タバコを吸っていたから肺がんになった」という自責の念を抱くことがあります。また、家族も「禁煙を勧めていれば」と後悔することがあります。患者や家族の罪悪感に配慮し、責めるような言動は避け、現在できる最善の治療に焦点を当てることが大切です。
治療方針、予後、療養場所について、患者・家族の希望や価値観を確認します。延命治療の希望、DNARの意思、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)についても、適切なタイミングで話し合いを持つことが推奨されます。
栄養-代謝パターン
肺がん患者の多くは、食欲不振と体重減少を認めます。がんによる炎症性サイトカインの産生、代謝亢進、味覚障害、抗がん剤や放射線療法の副作用(悪心、口内炎、食道炎)などが原因です。進行がんでは悪液質(cachexia)という状態になり、著しい体重減少と筋肉量低下が見られます。
栄養状態を評価するため、体重、BMI、血清アルブミン値、総リンパ球数を定期的にモニタリングします。食事摂取量を記録し、必要カロリーが摂取できているか確認します。
栄養管理として、高カロリー・高タンパクの食事を少量頻回で提供します。患者の嗜好を尊重し、食べやすい形態や温度を工夫します。経口栄養補助食品(ONS)も活用します。悪心が強い場合は制吐薬を適切に使用し、口内炎には口腔ケアと痛みの緩和を行います。
経口摂取が困難な場合は、経腸栄養や中心静脈栄養も検討しますが、終末期では患者の意思を尊重し、無理な栄養補給は避けることもあります。
活動-運動パターン
呼吸困難、倦怠感、疼痛により、活動耐性が著しく低下します。進行がんでは、ADL(日常生活動作)が制限され、セルフケア不足が生じます。Performance Status(PS)を評価し、患者の活動レベルに応じた援助を提供します。
呼吸状態の観察が最重要です。呼吸数、SpO2、呼吸パターン、呼吸困難の程度、チアノーゼの有無を定期的にモニタリングします。呼吸音を聴診し、喘鳴、副雑音の有無を確認します。喀痰の量や性状(血痰の有無)も観察します。
呼吸困難の緩和には、体位の工夫(半座位、前傾姿勢)、酸素療法、モルヒネなどのオピオイド、抗不安薬が有効です。患者が最も楽な体位を見つけられるよう支援します。
活動と休息のバランスを保ち、過度の安静は廃用症候群を招くため、可能な範囲で活動を促します。リハビリテーション(呼吸リハビリ、運動療法)も積極的に取り入れます。
睡眠-休息パターン
呼吸困難、咳、疼痛、不安により、睡眠が著しく障害されます。夜間の咳や呼吸困難で何度も覚醒し、不眠が続くと、日中の倦怠感が増強します。
睡眠環境を整え、静かで落ち着いた環境を提供します。就寝前の疼痛コントロールや抗不安薬の投与により、睡眠を確保します。必要に応じて睡眠薬も使用しますが、呼吸抑制に注意します。
認知-知覚パターン
疼痛管理は肺がん看護の中心的課題です。がんの浸潤、骨転移、神経浸潤により、激しい痛みが生じることがあります。痛みは患者のQOLを著しく低下させるため、積極的な疼痛コントロールが必須です。
疼痛アセスメントツール(NRS、VAS、フェイススケールなど)を用いて、痛みの強度、部位、性質、増悪因子、軽減因子を評価します。WHO三段階除痛ラダーに基づき、痛みの程度に応じて鎮痛薬を使用します:
- 軽度の痛み:非オピオイド鎮痛薬(アセトアミノフェン、NSAIDs)
- 中等度の痛み:弱オピオイド(トラマドール、コデイン)
- 高度の痛み:強オピオイド(モルヒネ、オキシコドン、フェンタニル)
オピオイドの副作用(便秘、悪心、眠気、呼吸抑制)に注意し、予防的に下剤を投与します。突出痛にはレスキュー薬を適切に使用します。
脳転移がある場合、頭痛、意識レベルの変化、けいれん、運動麻痺などの神経症状を観察します。ステロイドや浸透圧利尿薬による脳浮腫の軽減、放射線療法などが行われます。
コーピング-ストレス耐性パターン
肺がん診断は、患者と家族に多大な心理的ストレスをもたらします。予後不良ながんという認識、死への恐怖、家族への心配、経済的負担、役割の喪失など、さまざまな問題に直面します。
患者の心理的反応を理解し、傾聴の姿勢を持って接します。患者が自分の気持ちを表出できる安全な環境を提供します。怒りや否認も自然な反応であることを理解し、否定せずに受け止めます。
希望を支える関わりが重要です。「何もできることがない」のではなく、「今できることがある」という視点で支援します。小さな目標(家族との外出、孫の結婚式に出席など)を共有し、その実現を支援します。
必要に応じて、精神科医、臨床心理士、緩和ケアチーム、ソーシャルワーカー、がん相談支援センターなどの多職種と連携します。
役割-関係パターン
肺がんにより、患者はこれまでの役割(仕事、家庭内での役割)を失い、アイデンティティの喪失を感じることがあります。家族関係にも影響が及び、介護負担による家族の疲弊や、家族内の葛藤が生じることもあります。
患者と家族のコミュニケーションを促進し、互いの思いを伝え合える場を提供します。家族が患者にできることを一緒に考え、介護方法を指導します。家族の負担を軽減するため、レスパイトケア(一時的な介護からの解放)やデイケア、訪問看護などの社会資源を紹介します。
ヘンダーソン14基本的ニード
1. 正常な呼吸
肺がん患者にとって最も重要なニードです。腫瘍による気道狭窄、閉塞性肺炎、胸水貯留、がん性リンパ管症などにより、呼吸が著しく障害されます。
呼吸困難の緩和には:
- 体位の工夫:半座位、前傾姿勢(オーバーテーブルに枕を置いてもたれる)が楽なことが多いです
- 酸素療法:低酸素血症がある場合、適切な酸素流量を設定します
- 薬物療法:モルヒネは呼吸困難感を緩和します。抗不安薬も有効です
- 環境調整:室温、湿度を適切に保ち、換気を行います。扇風機で顔に風を当てるのも効果的です
- 呼吸法の指導:口すぼめ呼吸、腹式呼吸などのリラクゼーション呼吸法を指導します
気道の浄化も重要です。喀痰が増加している場合、体位ドレナージ、十分な水分摂取、去痰薬により喀出を促します。血痰や喀血がある場合は、量や頻度を観察し、大量喀血に備えます。
2. 適切な飲食
前述の通り、栄養状態の悪化は予後に直結します。食事摂取を促進するため:
- 嗜好を尊重し、食べたいものを食べられる時に提供します
- 少量頻回食とし、1回の食事量を減らします
- 高カロリー・高タンパクの食品を選択します
- 食欲が出る環境作り(好きな音楽、家族との食事)を工夫します
- 悪心がある場合は、制吐薬を食前に投与します
3. 排泄
オピオイド使用により便秘が必発します。予防的に下剤(酸化マグネシウム、センノシド)を投与し、排便コントロールを行います。3日以上排便がない場合は、浣腸や摘便も検討します。
脳転移や脊髄圧迫により、排尿障害や失禁が生じることもあり、尊厳を守りながら排泄介助を行います。
8. 身体を清潔に保つ
全身状態に応じて、入浴、シャワー浴、清拭を選択します。終末期では、清拭や部分浴で対応し、無理な入浴は避けます。清潔保持は患者の尊厳と快適さを保つために重要です。
9. 危険の回避
- 転倒予防:オピオイドによる眠気、脳転移による運動麻痺、全身衰弱により転倒リスクが高まります
- 感染予防:化学療法による骨髄抑制で易感染状態となります。手指衛生を徹底し、感染徴候を早期に発見します
- 出血予防:血小板減少により出血傾向が出現します。皮下出血、歯肉出血、喀血、血尿などに注意します
- 大量喀血への備え:血管に浸潤したがんでは、大量喀血の可能性があります。緊急時の対応を準備します
14. 学習
疾患、治療、予後についての情報提供を行いますが、患者の準備状態を見極め、希望に応じた情報提供を行います。「全てを知りたい」患者もいれば、「詳しくは知りたくない」患者もおり、個別性を尊重します。
治療の副作用(脱毛、悪心、倦怠感、骨髄抑制など)とその対処法について説明します。自宅での症状管理、緊急時の連絡先、利用可能な社会資源(訪問看護、介護保険、高額療養費制度など)についても情報提供します。
看護計画・介入の内容
- 呼吸状態の継続的モニタリング:呼吸数、SpO2、呼吸困難の程度、チアノーゼの有無を定期的に観察します。呼吸音を聴診し、喘鳴や副雑音を確認します。呼吸困難の増悪は、病状の進行や合併症を示唆するため、早期発見が重要です
- 疼痛管理:定期的に疼痛を評価し、鎮痛薬を適切に投与します。痛みは我慢させず、「痛みがあれば伝えてください」と患者に伝えます。突出痛にはレスキュー薬を使用し、ベースの鎮痛薬の調整も行います。オピオイドの副作用(便秘、悪心)に対する予防と対策を実施します
- 栄養管理:体重、食事摂取量を記録し、栄養状態を評価します。食欲を促進する工夫(嗜好の尊重、環境調整、少量頻回食)を行います。経口栄養補助食品を活用し、必要カロリーの確保に努めます
- 化学療法・放射線療法の副作用管理:治療前に副作用について説明し、不安を軽減します。悪心・嘔吐に対しては制吐薬を予防的に投与し、骨髄抑制に対しては定期的な血液検査でモニタリングします。脱毛への心理的サポートも提供します
- 心理的支援:患者の思いを傾聴し、感情の表出を促します。不安や恐怖を否定せず、受け止めます。希望を支える関わりを意識し、「今できること」に焦点を当てます。家族への心理的支援も行います
- 家族への支援:家族の不安や介護負担を理解し、サポートします。在宅療養の準備、介護方法の指導、社会資源の紹介を行います。家族の疲労やストレスにも配慮し、レスパイトケアを提案します
- 多職種連携:医師、薬剤師、栄養士、理学療法士、ソーシャルワーカー、緩和ケアチームなどと連携し、包括的なケアを提供します。定期的なカンファレンスで情報共有し、ケア方針を統一します
- 在宅療養支援:退院後の療養場所について、患者・家族と話し合います。在宅療養を希望する場合、訪問看護、訪問診療、訪問介護などの社会資源を調整します。緊急時の連絡先や対応方法について説明します
- アドバンス・ケア・プランニング(ACP):患者の価値観、人生の目標、医療に対する希望を確認します。終末期医療についての意思決定を支援し、患者の意思を尊重したケアを提供します
- 症状緩和:呼吸困難、疼痛、倦怠感、食欲不振、不安などの症状を総合的に緩和します。QOL(生活の質)の向上を目指し、患者が「その人らしく」過ごせるよう支援します
よくある疑問・Q&A
Q: 肺がんは早期発見できますか?どのような検査を受ければいいですか?
A: 肺がんの早期発見は難しいですが、胸部CT検査が最も有効です。胸部X線検査では小さながんや心臓の陰に隠れたがんを見逃すことがありますが、CTでは数mmの小さな結節も検出できます。
高リスク者(喫煙者、年齢50歳以上、喫煙指数400以上)では、低線量胸部CT検査による肺がん検診が推奨されています。この検査により、肺がんの死亡率が約20%減少することが報告されています。
ただし、CTで見つかる小結節のすべてががんではなく、良性結節も多いため、過剰診断や不要な検査・治療のリスクもあります。医師と相談の上、個々のリスクに応じた検診を受けることが重要です。
Q: タバコを吸わない人でも肺がんになるのですか?
A: はい、なります。実際、肺腺がんの約40〜50%は非喫煙者に発症しています。特に女性の肺がんでは、非喫煙者の割合が高いです。非喫煙者の肺がんは、EGFR遺伝子変異などの遺伝子異常が関与していることが多く、これらに対する分子標的薬が有効です。
受動喫煙、大気汚染、職業性曝露、遺伝的要因なども肺がんのリスク因子です。「タバコを吸わないから大丈夫」と安心せず、長引く咳や血痰などの症状があれば医療機関を受診することが大切です。
Q: 肺がんの治療はとても辛いと聞きました。副作用はどのようなものがありますか?
A: 治療の副作用は、治療法により異なります。
化学療法(抗がん剤)の主な副作用:
- 悪心・嘔吐:制吐薬により多くの場合コントロール可能です
- 脱毛:多くの抗がん剤で起こりますが、治療終了後に再生します
- 骨髄抑制:白血球減少(易感染)、血小板減少(出血傾向)、貧血
- 倦怠感:多くの患者が訴える症状です
- 末梢神経障害:手足のしびれや痛み
分子標的薬の主な副作用:
- 皮疹:EGFR-TKIで高頻度に見られますが、スキンケアで管理可能です
- 下痢:適切な下痢止めで対処します
- 間質性肺炎:まれですが重篤な副作用で、早期発見が重要です
免疫チェックポイント阻害薬の主な副作用:
- 免疫関連有害事象(irAE):間質性肺炎、大腸炎、肝障害、甲状腺機能障害、副腎機能不全など。自己免疫疾患のような症状が出現します
放射線療法の主な副作用:
- 放射線肺炎:治療後1〜3ヶ月で起こることがあります
- 食道炎:胸部照射により嚥下時の痛みが生じます
- 皮膚炎:照射部位の皮膚が赤くなり、痛みを伴うことがあります
副作用の多くは対処可能であり、医療チームと相談しながら管理していきます。我慢せずに症状を伝えることが重要です。
Q: 肺がんと診断されました。もうどのくらい生きられるのでしょうか?
A: 予後は、病期(ステージ)、組織型、遺伝子変異の有無、全身状態により大きく異なります。一般的な5年生存率は以下の通りですが、これはあくまで統計的な数字であり、個々の患者さんで異なります:
- I期(早期):約80%
- II期:約50%
- III期:約20%
- IV期(遠隔転移あり):約5%
ただし、近年の治療の進歩により、特に遺伝子変異陽性の肺がんでは、分子標的薬により長期生存が可能になってきています。また、免疫チェックポイント阻害薬が効く患者さんでは、劇的な効果が見られることもあります。
統計的な数字だけで判断せず、今できる最善の治療を受けること、そしてQOL(生活の質)を大切にすることが重要です。予後について知りたいと思うのは自然なことですが、同時に「どう生きるか」にも焦点を当てることが大切です。
Q: 家族が肺がんの終末期です。自宅で看取りたいのですが、可能ですか?
A: はい、可能です。多くの患者さんが「自宅で最期を迎えたい」と希望されており、在宅での看取りは十分に実現可能です。
在宅療養には以下のサポート体制があります:
- 訪問診療:医師が定期的に自宅を訪問し、症状管理や処方を行います
- 訪問看護:看護師が自宅を訪問し、症状観察、医療処置、療養指導を行います
- 訪問介護:ヘルパーが身体介護や生活支援を行います
- 24時間対応:多くの在宅医療機関は24時間連絡可能で、緊急時にも対応します
在宅での症状緩和も可能で、疼痛管理(オピオイドの使用)、呼吸困難の緩和、点滴などの医療処置も自宅で行えます。
ただし、家族の介護負担は大きいため、レスパイトケア(一時的に病院や施設で預かる)や、ショートステイの利用も検討します。また、「最期は病院で」と希望が変わることもあり、柔軟に対応することが大切です。
まずは、主治医、緩和ケアチーム、がん相談支援センター、地域の訪問看護ステーションなどに相談してみてください。
Q: 肺がん患者さんの呼吸困難が急に悪化したらどうすればいいですか?
A: まず呼吸状態を迅速に評価します。SpO2、呼吸数、呼吸パターン、チアノーゼの有無、意識レベルを確認し、バイタルサインを測定します。
以下のような原因を考えます:
- がんの進行による気道狭窄
- 閉塞性肺炎、無気肺
- 胸水の急速な貯留
- 気胸の合併
- 肺塞栓症
- 心不全の合併
応急処置:
- 患者を楽な体位(半座位、前傾姿勢)にします
- 酸素投与を開始または流量を上げます
- 穏やかに声をかけ、不安を軽減します
- 直ちに医師に報告し、指示を仰ぎます
医師の診察により原因が特定されれば、それに応じた治療(抗菌薬、胸水穿刺、気管支拡張薬、モルヒネなど)が行われます。
終末期の呼吸困難では、モルヒネによる呼吸困難感の緩和が有効です。モルヒネは呼吸抑制を心配されることがありますが、適切に使用すれば安全で、患者の苦痛を大幅に軽減できます。
まとめ
肺がんは、日本におけるがん死亡原因の第1位を占める重要な疾患です。小細胞肺がんと非小細胞肺がん(腺がん、扁平上皮がん、大細胞がん)に大別され、組織型により治療方針が異なります。
喫煙が最大のリスク因子ですが、非喫煙者でも発症し、特に腺がんでは遺伝子変異が関与しています。近年、EGFR、ALKなどの遺伝子変異に対する分子標的薬や、免疫チェックポイント阻害薬の登場により、治療成績が向上しています。
病態の本質は、がん細胞の無秩序な増殖と周囲組織への浸潤、遠隔転移です。脳、骨、肝臓への転移が多く、これらの転移により予後が大きく左右されます。
症状は、咳、血痰、呼吸困難、胸痛などの呼吸器症状に加え、転移による症状(頭痛、骨痛など)や全身症状(体重減少、倦怠感)が見られます。早期は無症状であることが多く、進行してから発見されることが課題です。
治療は、病期、組織型、遺伝子変異の有無により、手術、化学療法、放射線療法、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬を組み合わせて行われます。進行がんでは、早期からの緩和ケアが推奨されています。
看護の要点は、呼吸困難の緩和、疼痛管理、栄養管理、心理的支援です。呼吸状態を継続的にモニタリングし、体位の工夫、酸素療法、薬物療法により呼吸困難を緩和します。WHOの三段階除痛ラダーに基づく疼痛管理を行い、患者のQOLを維持します。
肺がん診断は患者と家族に大きな衝撃を与えます。傾聴の姿勢を持ち、患者の思いを受け止め、希望を支える関わりが重要です。多職種と連携し、包括的なケアを提供します。
患者教育では、疾患、治療、副作用、在宅療養、社会資源について情報提供します。アドバンス・ケア・プランニング(ACP)を通じて、患者の価値観を尊重した意思決定を支援します。
実習では、肺がん患者が抱える身体的・精神的苦痛に寄り添い、その人らしく生きることを支える看護を実践しましょう。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
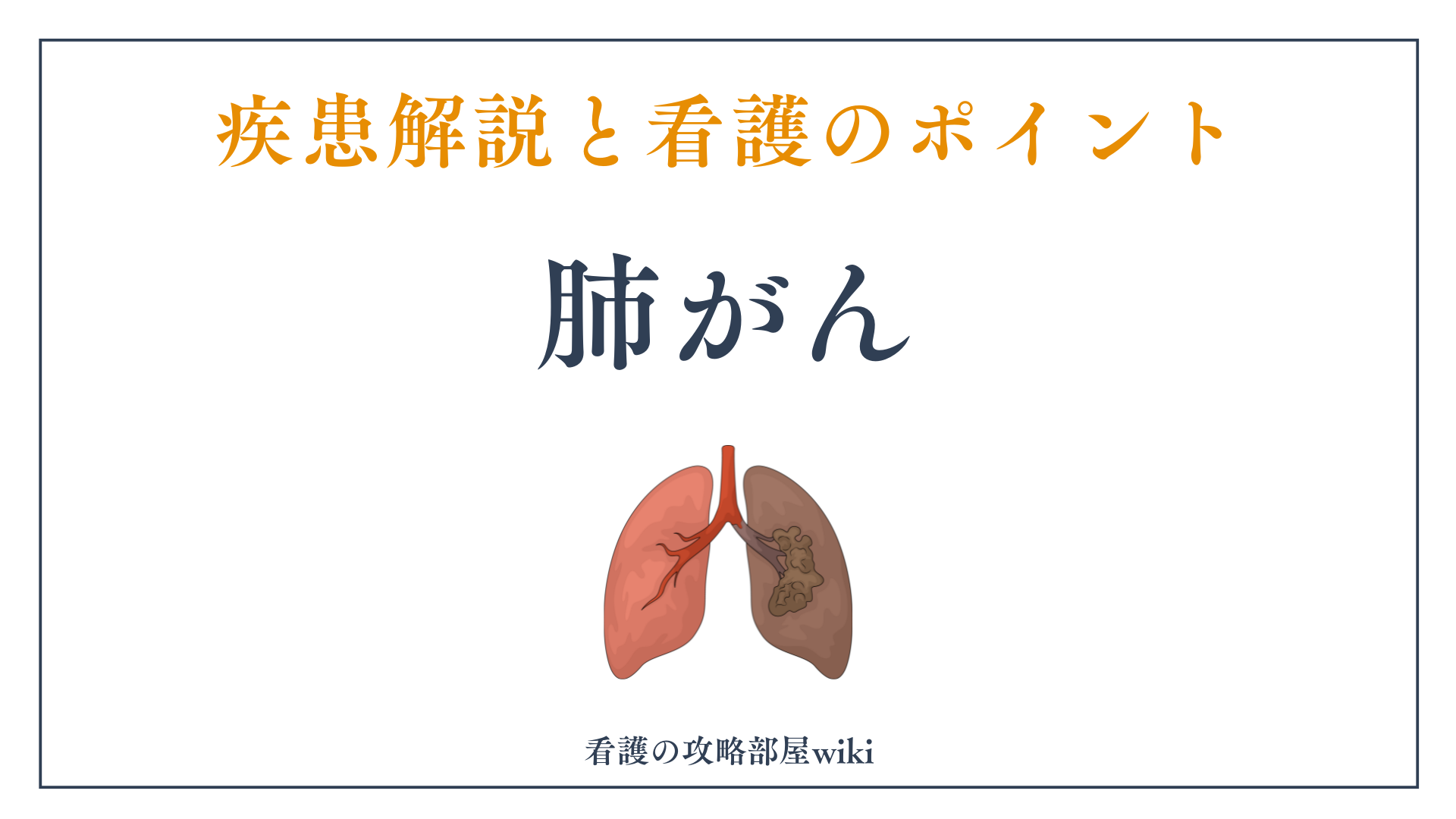
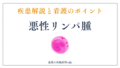
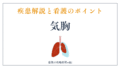
コメント