疾患概要
定義
悪性リンパ腫(Malignant Lymphoma)は、リンパ系組織から発生する悪性腫瘍の総称です。リンパ系組織とは、リンパ節、脾臓、胸腺、扁桃、骨髄などの免疫を担う組織のことで、これらの組織に存在するリンパ球(主にB細胞やT細胞)が腫瘍化して無制限に増殖します。悪性リンパ腫は大きくホジキンリンパ腫と非ホジキンリンパ腫の2つに分類されます。日本では非ホジキンリンパ腫が約90%を占め、ホジキンリンパ腫は約10%です。非ホジキンリンパ腫はさらに数十種類のサブタイプに分類され、それぞれ性質や治療法が異なります。
疫学
悪性リンパ腫は全年齢層に発症しますが、特に50〜70歳代に多く見られます。ただし、若年者にも発症することがあり、小児がんの中でも比較的頻度の高い疾患です。日本における年間発症率は人口10万人あたり約15人程度で、年間約3万人が新たに診断されています。近年、発症率は増加傾向にあります。男女比はやや男性に多く、約1.5:1程度です。非ホジキンリンパ腫の中では、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫(DLBCL)と濾胞性リンパ腫が最も多く、それぞれ全体の約30〜40%と約20%を占めます。
原因
悪性リンパ腫の明確な原因は多くの場合不明ですが、いくつかのリスク因子が知られています。
ウイルス感染が関与することがあり、成人T細胞白血病・リンパ腫(ATL)はHTLV-1ウイルス、バーキットリンパ腫はEBウイルス、胃のMALTリンパ腫はヘリコバクター・ピロリ菌の感染と関連しています。また、免疫不全状態(HIV感染、臓器移植後の免疫抑制療法、自己免疫疾患など)では発症リスクが高まります。
遺伝子異常も発症に関与しており、染色体転座や特定の遺伝子変異により、リンパ球が腫瘍化します。ただし、家族性の遺伝はほとんど見られず、遺伝する疾患ではありません。その他、加齢、化学物質への曝露、放射線被曝なども危険因子とされていますが、多くの症例では明確な原因は特定できません。
病態生理
悪性リンパ腫は、リンパ球が何らかの原因で腫瘍化し、無制限に増殖する疾患です。リンパ球にはB細胞、T細胞、NK細胞などがあり、どの細胞が腫瘍化するかによって病型が異なります。日本ではB細胞由来の非ホジキンリンパ腫が最も多く、全体の約80%を占めます。
リンパ腫細胞は主にリンパ節で増殖し、リンパ節の腫大を引き起こします。リンパ節は全身に存在するため、頸部、腋窩、鼠径部、縦隔、腹腔内など、様々な部位で腫瘤を形成します。また、リンパ腫は節外性(リンパ節以外の臓器)にも発生し、胃、腸管、肺、皮膚、中枢神経系、骨、精巣など、あらゆる臓器に病変を形成する可能性があります。
悪性リンパ腫は病期(ステージ)によって分類されます。Ann Arbor分類が広く用いられ、以下のように分類されます。
- I期:単一のリンパ節領域またはリンパ節外臓器に限局
- II期:横隔膜の同側に複数のリンパ節領域が侵される
- III期:横隔膜の両側にリンパ節病変がある
- IV期:リンパ節以外の臓器に広範に病変がある(肝臓、骨髄、肺など)
また、全身症状の有無により、A(全身症状なし)とB(全身症状あり)に分類されます。B症状とは、原因不明の発熱(38℃以上)、盗汗(寝汗)、6ヶ月で体重の10%以上の減少の3つを指します。
悪性リンパ腫は増殖速度によって低悪性度(ゆっくり進行)、中悪性度、高悪性度(急速に進行)に分類されます。低悪性度リンパ腫は進行が遅く、無症状で経過することも多いですが、治癒が難しく慢性経過をたどります。高悪性度リンパ腫は急速に進行しますが、化学療法に対する反応が良く、治癒が期待できることもあります。
腫瘍の増大により、周囲の臓器や組織を圧迫し、様々な症状を引き起こします。縦隔リンパ節の腫大では気道や上大静脈を圧迫し、腹腔内リンパ節の腫大では腸閉塞や水腎症を引き起こすことがあります。また、腫瘍細胞の急速な増殖と崩壊により、腫瘍崩壊症候群(高尿酸血症、高カリウム血症、高リン血症、低カルシウム血症)を引き起こすこともあります。
症状・診断・治療
症状
悪性リンパ腫の症状は、病変の部位や病型によって多様です。
リンパ節腫大が最も典型的な症状で、頸部、腋窩、鼠径部などに痛みのない腫瘤として触れます。通常は痛みを伴いませんが、急速に増大する場合は疼痛を感じることもあります。リンパ節は硬く、可動性がある(周囲組織と癒着していない)ことが多いですが、進行すると癒着して可動性が失われます。
B症状と呼ばれる全身症状は、予後に影響する重要な症状です。原因不明の発熱(38℃以上が持続)、夜間の大量の発汗(寝汗で着替えが必要なほど)、体重減少(6ヶ月で10%以上)が特徴的です。
その他の全身症状として、全身倦怠感、食欲不振、皮膚掻痒感などが見られることもあります。
圧迫症状は、腫大したリンパ節や腫瘤が周囲の臓器を圧迫することで生じます。縦隔リンパ節腫大では、咳嗽、呼吸困難、胸痛、上大静脈症候群(顔面や上肢の浮腫、静脈怒張)が出現します。腹腔内リンパ節腫大では、腹痛、腹部膨満、腸閉塞、水腎症などが生じます。
節外性病変の症状は、侵される臓器によって異なります。胃や腸管では腹痛、消化管出血、腸閉塞、脳では頭痛、嘔吐、痙攣、意識障害、皮膚では皮疹や結節、骨では骨痛や病的骨折などが見られます。
骨髄浸潤により貧血、白血球減少、血小板減少が生じることもあり、易感染性、出血傾向、倦怠感などの症状が出現します。
診断
診断には、病理組織学的検査が必須です。
リンパ節生検が最も重要で、腫大したリンパ節を摘出または針生検し、顕微鏡で腫瘍細胞の形態を観察します。免疫組織化学染色やフローサイトメトリーにより、腫瘍細胞の表面マーカーを調べ、B細胞性かT細胞性か、どのサブタイプかを同定します。遺伝子検査により、特定の染色体転座や遺伝子異常を検出することもあります。
血液検査では、LDH(乳酸脱水素酵素)の上昇が腫瘍量の指標となります。可溶性IL-2受容体も上昇することがあります。貧血、白血球増加または減少、血小板減少などが見られることもあります。肝機能、腎機能、電解質、尿酸値なども確認します。
画像検査により、病変の広がりや病期の評価を行います。CT検査(造影CT)で全身のリンパ節腫大や臓器病変を評価し、PET-CT検査では腫瘍の代謝活性を評価し、病変の範囲や治療効果の判定に有用です。MRI検査は脳や脊髄の病変の評価に優れています。
骨髄検査は、骨髄浸潤の有無を確認するために行われます。骨髄穿刺・生検により、骨髄中の腫瘍細胞の有無と割合を調べます。
病期診断は、これらの検査結果を総合してAnn Arbor分類に基づき判定されます。また、予後因子を評価する国際予後指標(IPI)も重要で、年齢、全身状態、LDH値、病期、節外病変の数により、予後を予測します。
治療
治療方針は、病型(ホジキンリンパ腫か非ホジキンリンパ腫か、そのサブタイプ)、病期、悪性度、年齢、全身状態、予後因子などを総合的に評価して決定されます。
化学療法が治療の中心です。非ホジキンリンパ腫の代表的なびまん性大細胞型B細胞リンパ腫では、R-CHOP療法(リツキシマブ、シクロホスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾロン)が標準治療です。リツキシマブは抗CD20モノクローナル抗体で、B細胞リンパ腫に対して特異的に作用します。通常、3週間ごとに6〜8サイクル投与します。
ホジキンリンパ腫ではABVD療法(ドキソルビシン、ブレオマイシン、ビンブラスチン、ダカルバジン)が標準的です。
低悪性度リンパ腫では、無症状で進行が遅い場合、無治療経過観察(Watch and Wait)を選択することもあります。症状が出現したり、病変が進行したりした時点で治療を開始します。
放射線療法は、限局期の病変や化学療法後の残存病変に対して行われます。また、緩和的治療として、圧迫症状のある部位に照射することもあります。
自家造血幹細胞移植は、再発・難治例や高リスク症例に対して行われます。大量化学療法後に、事前に採取しておいた自分の造血幹細胞を戻すことで、造血機能を回復させます。
分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬など、新しい治療薬も登場しています。再発・難治例に対して、CAR-T細胞療法(患者さん自身のT細胞を遺伝子改変して腫瘍を攻撃させる治療)も行われるようになっています。
支持療法も重要で、化学療法の副作用(悪心・嘔吐、骨髄抑制、口内炎など)に対する予防的治療、感染予防のための抗菌薬投与、腫瘍崩壊症候群の予防(アロプリノールやラスブリカーゼの投与、十分な輸液)などを行います。
治療成績は病型や病期により異なりますが、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の限局期では5年生存率が80〜90%、進行期でも60〜70%程度と比較的良好です。ホジキンリンパ腫も治療成績が良く、早期なら90%以上の治癒が期待できます。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 感染リスク状態(化学療法による骨髄抑制)
- 栄養摂取消費バランス異常(食欲不振、悪心・嘔吐)
- 活動耐性低下(貧血、全身倦怠感)
- 不安(診断、予後、治療への不安)
- ボディイメージ混乱(脱毛、体重変化、リンパ節腫大)
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚-健康管理パターン
悪性リンパ腫の診断は患者さんに大きな衝撃を与えます。がんという診断をどのように受け止めているか、治療への理解度や意欲、予後に対する認識などをアセスメントします。治療は長期にわたるため、患者さん自身が主体的に治療に参加できるよう支援することが重要です。
栄養-代謝パターン
化学療法の副作用(悪心・嘔吐、味覚障害、口内炎)や、B症状(発熱、盗汗)、腫瘍による代謝亢進により、食欲不振や体重減少が生じやすくなります。食事摂取量、体重変化、血清アルブミン値、BMIなどを評価し、栄養状態の維持に努めます。
排泄パターン
化学療法により便秘や下痢が生じることがあります。また、腹腔内リンパ節腫大により腸閉塞を起こすこともあります。排便状況、腹部症状を観察します。腫瘍崩壊症候群では高尿酸血症により腎機能障害が生じるため、尿量や尿の性状も重要です。
活動-運動パターン
貧血、全身倦怠感、B症状により活動耐性が低下します。ADLの自立度、活動時の症状(息切れ、動悸、めまいなど)を評価します。治療中は過度の安静は避け、可能な範囲で活動を維持することが望ましいですが、感染リスクや貧血の程度に応じた調整が必要です。
睡眠-休息パターン
B症状の盗汗により夜間の睡眠が妨げられることがあります。また、不安や入院環境、ステロイドの副作用により不眠が生じることもあります。睡眠時間、睡眠の質、日中の眠気などを評価します。
認知-知覚パターン
縦隔や腹腔内のリンパ節腫大による圧迫症状(胸痛、腹痛など)、化学療法の副作用(末梢神経障害によるしびれ、頭痛など)を評価します。中枢神経系に病変がある場合は、頭痛、嘔吐、意識障害、痙攣などの神経症状に注意が必要です。
自己知覚-自己概念パターン
化学療法による脱毛、ステロイドによる体重増加や満月様顔貌、リンパ節腫大による外見の変化などが、ボディイメージや自尊心に影響を与えます。特に若年者では、これらの変化が心理的負担となることが多いです。
役割-関係パターン
長期治療により、仕事や家庭での役割が変化します。また、周囲の人々にどのように病気を伝えるか、サポート体制はどうかなどを評価します。社会的孤立の予防も重要です。
性-生殖パターン
若年者では、化学療法による妊孕性(妊娠する能力)への影響が大きな問題となります。治療前に妊孕性温存(精子凍結、卵子凍結など)について説明を受けたか、性生活への影響についての懸念はないかを確認します。
ストレス-コーピングパターン
がんの診断、長期治療、再発への不安など、患者さんは大きなストレスを抱えています。ストレスへの対処方法、サポートシステムの有無、心理的サポートの必要性を評価します。
ヘンダーソン14基本的ニード
正常に呼吸する
縦隔リンパ節腫大による気道圧迫や上大静脈症候群では、呼吸困難が生じます。呼吸回数、呼吸音、SpO2、呼吸困難感を観察します。また、化学療法の副作用(ブレオマイシンによる肺毒性)にも注意が必要です。
適切に飲食する
栄養状態の維持が重要です。食事摂取量、体重、嗜好の変化を評価し、少量頻回食、高カロリー食品の活用、口内炎への対処などを行います。悪心・嘔吐に対しては、予防的制吐剤の投与が効果的です。
正常に排泄する
便秘や下痢の予防と対処が必要です。また、腫瘍崩壊症候群の予防のため、十分な水分摂取と尿量の確保が重要です。尿量、尿の色、排便状況を観察します。
身体の位置を動かし、またよい姿勢を保持する
活動耐性に応じて、適度な運動を促します。長期臥床による筋力低下や深部静脈血栓症を予防するため、早期離床や軽い運動が推奨されます。
睡眠と休息をとる
盗汗がある場合は、寝衣や寝具の交換により快適な睡眠環境を整えます。不眠に対しては、環境調整や必要に応じた睡眠薬の使用を検討します。
適当な衣類を選び、着たり脱いだりする
ADLの自立度に応じて、必要な介助を提供します。脱毛がある場合は、帽子やウィッグの使用を提案します。
体温を正常範囲内に保つ
B症状の発熱や、感染症による発熱に注意します。発熱時は、原因の鑑別(腫瘍熱か感染症か)が重要です。化学療法後の発熱性好中球減少症は緊急事態であり、速やかな対応が必要です。
身体を清潔に保ち、身だしなみを整える
感染予防のために清潔を保つことが重要です。特に好中球減少時は、口腔ケア、手洗い、陰部洗浄などを丁寧に行います。脱毛に対しては、ウィッグや帽子の情報提供を行います。
危険を回避する
化学療法による骨髄抑制時は、感染予防(手洗い、マスク、人混みを避ける)、出血予防(転倒防止、鋭利なものの取り扱い注意)が重要です。また、腫瘍崩壊症候群や上大静脈症候群などの緊急事態にも注意が必要です。
他者とコミュニケーションをもつ
患者さんや家族の不安や悩みを傾聴し、疾患や治療について十分に説明します。患者会やピアサポートの情報提供も有効です。
自分の信仰に従って礼拝する
がんの診断や予後への不安に対するスピリチュアルなサポートも必要な場合があります。
達成感をもたらすような仕事をする
治療中も可能な範囲での役割の継続を支援します。多くの患者さんは治療により寛解が得られ、仕事や社会生活に復帰できることを伝えます。
遊び、あるいはさまざまな種類のレクリエーションに参加する
体調に応じて、趣味や楽しみを継続できるよう支援します。QOLの維持が重要です。
学習する
疾患や治療、副作用への対処法、セルフケアなどについて、患者さんが十分に理解できるよう教育的支援を行います。
看護計画・介入の内容
- リンパ節腫大の観察:リンパ節の大きさ、硬さ、可動性、圧痛の有無を定期的に観察します。治療効果の評価にも重要です。
- 圧迫症状の観察:縦隔リンパ節腫大による呼吸困難、上大静脈症候群(顔面・上肢の浮腫、静脈怒張)、腹腔内リンパ節腫大による腹痛、腸閉塞症状などを観察します。症状が出現した場合は速やかに医師に報告します。
- B症状の観察と対処:発熱パターン、盗汗の程度、体重変化を記録します。盗汗がひどい場合は、寝衣や寝具の交換を頻回に行い、快適さを保ちます。
- 化学療法の副作用管理:
- 悪心・嘔吐:予防的制吐剤の投与、食事の工夫(少量頻回食、冷たいもの、においの少ないもの)
- 骨髄抑制:好中球、血小板、ヘモグロビン値のモニタリング、感染予防、出血予防
- 口内炎:口腔内観察、口腔ケアの徹底、痛みに応じた鎮痛薬や含嗽薬の使用
- 脱毛:治療前に脱毛について説明し、ウィッグや帽子の情報提供、心理的サポート
- 末梢神経障害:しびれや痛みの程度を評価、転倒予防、日常生活動作への影響を確認
- 感染予防と早期発見:化学療法後の好中球減少期は感染リスクが最も高くなります。手洗い・うがいの励行、マスク着用、人混みを避ける、生ものを避けるなどの指導を行います。発熱性好中球減少症(好中球500/μL未満で38℃以上の発熱)は緊急事態であり、速やかに抗生物質投与を開始する必要があります。発熱時は直ちに医師に報告します。
- 腫瘍崩壊症候群の予防と観察:化学療法開始時、特に腫瘍量が多い場合に発症リスクが高まります。十分な輸液(3L/日以上)、尿アルカリ化、アロプリノールやラスブリカーゼの投与により予防します。高尿酸血症、高カリウム血症、高リン血症、低カルシウム血症、腎機能障害の徴候(乏尿、浮腫)、不整脈、痙攣などを観察します。
- 栄養管理:食事摂取量の観察、体重測定、血清アルブミン値の確認を行います。食欲不振がある場合は、患者さんの嗜好に合わせた食事の提供、高カロリー食品の活用、経口栄養補助食品の利用を検討します。口内炎がある場合は、刺激の少ない柔らかい食事を提供します。
- 輸血療法の管理:貧血や血小板減少に対して輸血が行われます。輸血前の患者確認、輸血中のバイタルサイン測定、輸血副作用(発熱、蕁麻疹、アナフィラキシー、溶血反応など)の観察を行います。
- 心理的サポート:がんの診断や治療、予後への不安、外見の変化による苦痛などに対して、患者さんや家族の思いを傾聴します。正しい情報を提供し、希望を持って治療に取り組めるよう支援します。同じ疾患を持つ患者会の情報提供も有効です。
- 家族支援:患者さんだけでなく、家族も大きな不安や負担を抱えています。家族の思いも傾聴し、必要に応じてソーシャルワーカーや心理士との連携を図ります。
- 退院指導:感染予防の継続、副作用への対処法、緊急時の受診基準(発熱、出血、呼吸困難など)、定期的な受診の重要性、内服管理などを説明します。
- 社会資源の活用:高額療養費制度、障害年金、傷病手当金などの経済的支援制度について、ソーシャルワーカーと連携して情報提供します。治療費の負担は大きいため、利用できる制度を早期に案内することが重要です。
よくある疑問・Q&A
Q: 悪性リンパ腫は治る病気ですか?
A: はい、多くの悪性リンパ腫は治癒が期待できる疾患です。特にホジキンリンパ腫や、非ホジキンリンパ腫の中でもびまん性大細胞型B細胞リンパ腫などは、化学療法により高い治癒率が得られます。早期であれば80〜90%、進行期でも60〜70%程度の5年生存率が報告されています。ホジキンリンパ腫の早期では90%以上の治癒が期待できます。
ただし、病型によって予後は異なります。低悪性度リンパ腫(濾胞性リンパ腫など)は進行が遅く長期生存できますが、完全治癒は難しく、再発を繰り返しながら慢性経過をたどることが多いです。高悪性度リンパ腫は急速に進行しますが、化学療法に対する反応が良く、治癒が期待できます。
患者さんには、「がん=死」ではなく、適切な治療により多くの人が治癒し、元の生活に戻れることを伝え、希望を持って治療に取り組めるよう支援することが大切です。
Q: 化学療法後の発熱性好中球減少症とは何ですか?看護師として何に注意すべきですか?
A: 発熱性好中球減少症(Febrile Neutropenia:FN)は、化学療法による骨髄抑制で好中球が減少している時期に発熱を認める状態で、生命を脅かす緊急事態です。定義は、好中球数が500/μL未満(または1000/μL未満で今後500/μL未満に減少することが予測される)で、38℃以上の発熱です。
好中球は細菌感染と戦う重要な白血球で、これが極度に減少すると、わずかな感染でも急速に重症化し、敗血症性ショックに至る可能性があります。しかも、好中球が少ないため、通常の感染徴候(局所の発赤、腫脹、膿など)が現れにくく、発熱が唯一のサインであることが多いのが特徴です。
看護師として注意すべきポイントは以下の通りです。
- 化学療法後の好中球減少期を把握する:通常、化学療法後7〜14日頃に好中球が最も減少します(nadir:最低値)。この時期は特に注意が必要です。
- 体温測定を頻回に行う:1日4回程度の定期的な体温測定を行い、発熱の早期発見に努めます。
- 発熱時は直ちに医師に報告する:38℃以上の発熱を認めたら、速やかに医師に報告します。血液培養を採取し、直ちに広域抗生物質の投与を開始します。
- 感染源を探す:発熱の原因を探すため、口腔内、肺、尿路、皮膚、中心静脈カテーテル刺入部などを観察します。
- 予防的対応:手洗い・うがいの徹底、マスク着用、生ものの摂取制限、人混みを避ける、口腔ケアの徹底などを指導します。
FNは迅速な対応が予後を左右するため、化学療法を受ける患者さんには、退院前に「発熱したらすぐに連絡・受診する」ことを必ず指導しましょう。
Q: 化学療法で脱毛した患者さんへの心理的サポートで、どのような言葉がけが適切ですか?
A: 脱毛は、患者さん、特に女性や若年者にとって、最も辛い副作用の一つです。外見の変化は自尊心やボディイメージに大きな影響を与え、社会生活への参加を妨げることもあります。
まず大切なのは、患者さんの苦痛を否定せず、共感することです。「髪はまた生えますから」「命のほうが大事ですよ」といった励ましは、患者さんの気持ちを軽視しているように受け取られることがあります。「辛いですよね」「大切な髪を失うのは悲しいことですね」と、まず気持ちに寄り添いましょう。
その上で、以下のような情報やサポートを提供します。
- 具体的な情報提供:「治療終了後、数週間〜数ヶ月で髪は生え始めます。中には以前より良い髪質になったという方もいますよ」と、希望の持てる情報を伝えます。
- ウィッグや帽子の情報:「医療用ウィッグやおしゃれな帽子、スカーフなど、様々な選択肢があります。試着できる場所もありますよ」と具体的な対処法を提案します。
- 同じ経験をした人の話:「同じ治療を受けた方の多くが、工夫しながら乗り越えていますよ」と伝え、患者会などの情報を提供します。
- 個別性を尊重する:ある人は「帽子でいい」と考え、別の人は「高品質なウィッグが欲しい」と考えます。患者さんの価値観や希望を尊重し、その人に合った対処法を一緒に考えます。
また、家族や周囲の人が患者さんの外見の変化にどう反応するかも重要です。「家族には既に話していますか?どんな反応でしたか?」と尋ね、必要であれば家族への説明もサポートします。
Q: 腫瘍崩壊症候群はなぜ起こるのですか?どのような観察が必要ですか?
A: 腫瘍崩壊症候群(Tumor Lysis Syndrome:TLS)は、化学療法により腫瘍細胞が急速に破壊される際に、細胞内の物質が大量に血液中に放出されることで起こる代謝異常です。特に、腫瘍量が多い場合や、増殖スピードの速い高悪性度リンパ腫で起こりやすくなります。
腫瘍細胞が壊れると、細胞内に多く含まれるカリウム、リン、核酸(尿酸に代謝される)が血液中に大量に放出されます。その結果、以下の異常が生じます。
- 高尿酸血症:尿酸が腎臓の尿細管に沈着し、腎機能障害を引き起こします
- 高カリウム血症:致死的不整脈を引き起こす可能性があります
- 高リン血症:リンとカルシウムが結合して沈着し、低カルシウム血症を引き起こします
- 低カルシウム血症:痙攣やテタニーを引き起こします
これらが進行すると、急性腎不全、不整脈、痙攣、意識障害などの重篤な合併症を引き起こし、生命に関わることもあります。
看護師として必要な観察は以下の通りです。
- 尿量のモニタリング:乏尿(尿量が減少すること)は腎機能障害の初期サインです。時間尿量を測定し、減少があれば速やかに報告します。
- 電解質と腎機能の確認:血液検査で、カリウム、リン、カルシウム、尿酸、BUN、クレアチニンの値を定期的に確認します。
- 心電図モニタリング:高カリウム血症による不整脈(テント状T波、QRS幅の拡大など)を早期に発見します。動悸、胸部不快感などの症状にも注意します。
- 神経症状の観察:低カルシウム血症による痙攣、テタニー、しびれ、意識障害などを観察します。
- 十分な水分摂取の促進:輸液により尿量を確保し(3L/日以上)、尿酸や電解質の排泄を促進します。経口摂取も促します。
予防が最も重要で、化学療法開始前から十分な輸液、アロプリノール(尿酸生成抑制薬)やラスブリカーゼ(尿酸分解酵素)の投与を行います。リスクの高い患者さんでは、最初の化学療法は入院で行い、厳重な管理が必要です。
まとめ
悪性リンパ腫は、リンパ系組織から発生する悪性腫瘍の総称で、ホジキンリンパ腫と非ホジキンリンパ腫に大別されます。病態の核心は、リンパ球の腫瘍化による無制限な増殖であり、全身のリンパ節や様々な臓器に病変を形成します。
看護の要点は、化学療法の副作用管理(特に骨髄抑制による感染・出血リスク)、圧迫症状の観察、腫瘍崩壊症候群の予防と早期発見、栄養管理、そして心理的サポートです。特に発熱性好中球減少症は生命を脅かす緊急事態であり、早期発見と迅速な対応が不可欠です。
治療の進歩により、悪性リンパ腫の予後は大幅に改善しています。多くの病型で治癒が期待でき、適切な治療により元の生活に戻ることが可能です。ホジキンリンパ腫やびまん性大細胞型B細胞リンパ腫では、特に治療成績が良好です。
実習では、化学療法の副作用を見逃さないこと、感染徴候の早期発見、患者さんの不安や苦痛に寄り添うことを意識しましょう。悪性リンパ腫の患者さんは、がんという診断のショック、長期にわたる治療、脱毛などの外見の変化、再発への不安など、多くの心理的負担を抱えています。身体的ケアと心理的サポートの両面から、患者さんが希望を持って治療に取り組めるよう支援することが重要です。
また、若年者も多い疾患であるため、妊孕性の問題、仕事や学業への影響、ボディイメージの変化による苦痛など、年齢に応じた個別的なニーズにも配慮が必要です。多職種と連携しながら、患者さんとその家族を包括的に支えていきましょう。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
・正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません

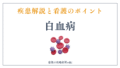
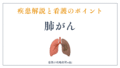
コメント