疾患概要
定義
腎結石とは、腎臓内で尿中の成分が結晶化して固まり、結石を形成した状態です。尿路結石症の一部であり、結石が腎臓内に留まっている状態を指します。結石の大きさは数mm程度の砂粒状のものから、数cmに及ぶものまで様々で、成分によってシュウ酸カルシウム結石、リン酸カルシウム結石、尿酸結石、シスチン結石などに分類されます。
疫学
日本における尿路結石症の生涯罹患率は約15%とされ、男性は女性の約2〜3倍の発症率です。年齢分布では30〜60歳代の働き盛りに多く発症しますが、近年は食生活の欧米化や高齢化に伴い、患者数は増加傾向にあります。また、再発率が高く、5年以内に約半数が再発するという特徴があります。地域差では、温暖な地域でやや発症率が高い傾向が見られ、これは発汗による脱水が関係していると考えられています。
原因
腎結石の形成には、尿の濃縮、結石形成物質の過剰排泄、結石形成抑制物質の減少という3つの要因が関与しています。
具体的な危険因子として、水分摂取不足による脱水、高カルシウム尿症、高尿酸血症、高シュウ酸尿症、遺伝的素因、尿路感染症、尿路の解剖学的異常などが挙げられます。食生活では、動物性タンパク質の過剰摂取、塩分の過剰摂取、シュウ酸を多く含む食品の過剰摂取などが関係しています。また、長期臥床による骨吸収の亢進も結石形成のリスクとなります。
病態生理
腎結石の形成メカニズムは、尿中の結石形成物質が過飽和状態になることから始まります。
正常な状態では、尿中にはクエン酸やマグネシウムなどの結石形成を抑制する物質が含まれていますが、何らかの要因でこのバランスが崩れると結石が形成されやすくなります。
具体的なプロセスとしては、まず尿中でカルシウムやシュウ酸、尿酸などの濃度が高まり、過飽和状態になります。すると、これらの物質が結晶として析出し始めます。結晶は腎乳頭部の集合管周辺で形成されることが多く、最初は微小な結晶核として存在します。
この結晶核に、さらに結石形成物質が付着・沈着していくことで、徐々に結石が成長していきます。成長した結石が腎盂や腎杯に留まると腎結石となります。結石が尿管に移動すると、尿管の狭い部分で詰まり、尿管閉塞を引き起こします。
尿管が閉塞すると、腎臓から尿が排出されなくなり、腎盂内圧が上昇します。この内圧上昇により腎被膜が伸展されると、激しい側腹部痛や腰背部痛が生じます。これが特徴的な疼痛発作である疝痛発作です。
また、結石による尿路粘膜の損傷により血尿が生じ、細菌感染を併発すると腎盂腎炎や敗血症に至るリスクがあります。長期間放置された結石による尿路閉塞は、水腎症や腎機能障害を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。
症状・診断・治療
症状
腎結石の症状は、結石のサイズや位置によって大きく異なります。
小さな結石が腎臓内に留まっている場合は、無症状のことも多く、健康診断などで偶然発見されることがあります。しかし、結石が移動して尿管に嵌頓すると、突然の激しい痛みが出現します。
最も特徴的な症状は疝痛発作と呼ばれる激痛で、側腹部から腰背部にかけて生じ、下腹部や鼠径部、外陰部へ放散することがあります。この痛みは波状に増強と軽減を繰り返し、患者さんは痛みのために体位を頻繁に変えたり、じっとしていられない様子が見られます。
疼痛に伴って、悪心・嘔吐、冷汗、顔面蒼白などの自律神経症状が現れることも多いです。また、結石による尿路粘膜の損傷により血尿が見られ、肉眼的血尿から顕微鏡的血尿まで程度は様々です。
尿路感染を合併している場合は、発熱、排尿時痛、頻尿、残尿感などの膀胱炎症状や、高熱と腰背部痛を伴う腎盂腎炎の症状が加わることがあります。
診断
診断は、詳細な問診と身体診察から始まります。疼痛の性質、部位、放散痛の有無などを確認し、肋骨脊椎角の叩打痛の有無をチェックします。
検査では、まず尿検査を行い、血尿の有無、尿pH、結晶成分などを確認します。血液検査では、腎機能を評価するために血清クレアチニンやBUNを測定し、炎症反応としてCRPや白血球数をチェックします。また、血清カルシウムや尿酸値も測定し、結石形成の原因を探ります。
画像診断では、腹部単純X線検査でカルシウム含有結石の約90%が描出されますが、尿酸結石はX線透過性のため写りません。超音波検査は非侵襲的で、水腎症の有無や結石の位置確認に有用です。
最も診断精度が高いのはCT検査で、結石の大きさ、位置、数、密度を正確に評価でき、尿酸結石も検出可能です。造影剤を使用しない単純CTでも十分な情報が得られるため、第一選択とされることが多いです。
治療
治療方針は、結石のサイズ、位置、症状の程度、腎機能の状態によって決定されます。
10mm以下の小さな結石では、自然排石が期待できるため、まず保存的治療を選択します。具体的には、水分摂取を1日2L以上に増やし、尿量を確保します。鎮痛薬や鎮痙薬で疼痛をコントロールしながら、排石促進薬を使用し、適度な運動を促します。
疝痛発作時には、NSAIDs系鎮痛薬の投与や、効果不十分な場合はペンタゾシンなどの強力な鎮痛薬を使用します。制吐薬も併用し、脱水予防のため点滴による輸液管理を行います。
10mmを超える結石や保存的治療で改善しない場合、尿路感染や水腎症を合併している場合は、積極的治療が必要です。現在の主流は体外衝撃波結石破砕術 (ESWL)で、体外から衝撃波を当てて結石を破砕し、自然排石を促します。侵襲が少なく、外来でも施行可能です。
より大きな結石や硬い結石には、経尿道的尿管砕石術 (TUL) や経皮的腎砕石術 (PNL) が選択されます。TULは尿道から内視鏡を挿入し、レーザーなどで結石を破砕します。PNLは背部から腎臓へ直接アプローチする方法で、大きな腎結石に有効です。
感染を合併している場合は、適切な抗菌薬投与が必要です。また、再発予防のため、結石成分分析に基づいた食事指導や生活指導が重要になります。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 急性疼痛:尿路結石による尿管閉塞と尿路攣縮に関連した激しい疼痛
- 体液量不足のリスク:疼痛による食事・水分摂取不良、悪心・嘔吐に関連
- 感染のリスク:尿路閉塞や尿停滞による細菌増殖の可能性
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚-健康管理パターン
結石形成の危険因子について患者さんがどの程度理解しているかを確認します。水分摂取習慣、食生活、既往歴、家族歴などを詳しく聴取し、再発予防に向けた健康管理への意識づけが重要です。患者さんが自身の生活習慣と結石形成の関係を理解し、改善への動機づけができるよう支援します。
栄養-代謝パターン
食事内容の詳細な聴取が必要です。特に動物性タンパク質、塩分、シュウ酸を多く含む食品の摂取状況を確認します。水分摂取量は1日2L以上が推奨されますが、実際の摂取量と患者さんの水分摂取習慣を把握します。悪心・嘔吐がある場合は、栄養・水分摂取が困難になるため、輸液管理と併せて摂取可能な食品を一緒に検討します。結石成分に応じた食事指導の必要性もアセスメントします。
排泄パターン
排尿回数、1回排尿量、尿の性状、色調を観察し、血尿の程度を確認します。結石排出の可能性があるため、排尿時には必ず尿をこし器やガーゼでこし、結石の有無を確認します。排出された結石は成分分析のため保存が必要です。また、尿量が維持されているか、尿路閉塞による無尿や乏尿がないかを注意深くモニタリングします。
活動-運動パターン
激しい疼痛により安静を保ちたくなりますが、適度な体動は結石の移動を促進します。疼痛コントロールが図れたら、無理のない範囲での歩行や軽い運動を促します。ただし、疼痛発作時は無理に動かず、安楽な体位を保つことを優先します。患者さんの疼痛の程度と活動可能な範囲を個別にアセスメントします。
ヘンダーソン14基本的ニード
正常に呼吸する
激しい疼痛により呼吸が浅く速くなることがあります。疼痛に伴う不安や恐怖も呼吸に影響を与えるため、深呼吸を促し、リラックスできる環境を整えます。また、疼痛コントロールが適切に行われているかを評価します。
適切に飲食する
疼痛や悪心・嘔吐により食事摂取が困難になりがちです。しかし、水分摂取は結石の排出促進と新たな結石形成予防のために非常に重要です。少量ずつでも摂取できるよう工夫し、経口摂取が困難な場合は点滴による水分補給を確実に行います。症状が改善してきたら、結石成分に応じた食事内容についての指導も開始します。
あらゆる排泄経路から排泄する
排尿状況の観察が最も重要です。排尿時痛や血尿の程度、排尿困難感の有無を確認します。必ず排尿時は尿をこし、結石排出の有無をチェックします。また、水腎症による腎機能低下のリスクがあるため、尿量を正確に測定し、適切な尿量が保たれているかを評価します。
身体の位置を動かし、またよい姿勢を保持する
疼痛により患者さんは落ち着きなく体位を変換することが多く見られます。これは自然な反応ですが、安楽な体位を一緒に探し、疼痛を最小限にする体位を見つける支援をします。側臥位や前傾姿勢が楽になることもあります。疼痛がコントロールされたら、適度な歩行を促し、結石の移動を促進します。
看護計画・介入の内容
- 疼痛コントロール:疼痛の程度を定期的にスケール評価し、鎮痛薬の効果を確認する。疼痛増強時は速やかに医師に報告し、追加の鎮痛薬投与を依頼する。温罨法が有効な場合もあるため、患者の希望に応じて実施する
- 水分出納管理:1日の水分摂取量2000ml以上を目標に、こまめな水分摂取を促す。経口摂取困難時は点滴による補液を確実に行い、摂取量と排泄量を正確に記録する
- 排尿観察と結石回収:すべての排尿をこし器でこし、結石の有無を確認する。血尿の程度を観察し、色調や混濁の変化を記録する。結石が排出された場合は、サイズ、形状、色を観察し、成分分析のため保存する
- 感染徴候の早期発見:体温測定を定期的に行い、発熱の有無を確認する。尿混濁や悪臭、排尿時痛の出現に注意し、感染徴候があれば速やかに報告する。白血球数やCRP値などの検査データもモニタリングする
- 悪心・嘔吐への対応:制吐薬を適切なタイミングで投与し、効果を評価する。嘔吐時は窒息予防のため、安全な体位を保持する。口腔内の清潔を保ち、不快感を軽減する
- 患者教育と再発予防指導:結石の成分が判明したら、成分に応じた食事指導を行う。カルシウム結石では過度なカルシウム制限は逆効果であること、動物性タンパク質や塩分の過剰摂取を避けることを説明する。シュウ酸を多く含む食品の摂り方についても指導する。水分摂取の重要性を繰り返し説明し、1日2L以上を習慣化できるよう支援する
- 活動促進:疼痛がコントロールされたら、結石の移動を促すため、適度な歩行や軽い運動を勧める。ただし、患者の状態に応じて無理のない範囲で実施する
- 心理的支援:激しい疼痛は患者に強い不安や恐怖を与える。疼痛が軽減すること、適切な治療により改善することを説明し、安心感を提供する。再発への不安に対しても、予防方法を具体的に伝えることで対処できるという認識を持ってもらう
よくある疑問・Q&A
Q: 疝痛発作が起きている患者さんが「じっとしていられない」と言って動き回っていますが、安静にさせた方がいいですか?
A: 尿路結石の疝痛発作時に患者さんが落ち着きなく動き回るのは、疼痛に対する自然な反応です。無理に安静を強いる必要はありません。むしろ、患者さんが楽だと感じる体位や動きを見つける手助けをすることが大切です。ただし、転倒のリスクがあるため、環境整備と見守りは必要です。また、動き回ることよりも疼痛コントロールが最優先なので、鎮痛薬の効果が不十分であれば速やかに医師に報告し、追加投与を検討してもらいましょう。
Q: 患者さんから「カルシウムを摂ると結石ができやすくなるのでは?」と質問されました。どう答えればよいですか?
A: これは非常によくある誤解です。実は、適度なカルシウム摂取は結石予防に効果的なのです。食事中のカルシウムは腸管内でシュウ酸と結合し、シュウ酸の吸収を減少させます。その結果、尿中のシュウ酸濃度が下がり、シュウ酸カルシウム結石のリスクが低下します。逆にカルシウムを制限しすぎると、シュウ酸の吸収が増え、結石形成のリスクが高まります。ただし、カルシウムサプリメントの過剰摂取は避けるべきで、食事から適量を摂取することが推奨されます。1日600〜800mg程度のカルシウム摂取を目安に、牛乳や乳製品、小魚などから摂るよう説明しましょう。
Q: 尿をこして結石を探すとき、どのくらいの大きさまで見つけられるものですか? 見逃さないコツはありますか?
A: 結石のサイズは数mm程度の砂粒状のものから1cm以上のものまで様々です。小さなものは砂のような細かい粒状で、見逃しやすいため注意が必要です。見逃さないコツとしては、まず採尿容器から直接こし器やガーゼに尿を注ぎ、水で薄まる前に観察することです。こし器を明るい場所で観察し、必要に応じてライトを当てると見つけやすくなります。また、尿の色が濃い場合は、こし器を水で軽く流しながら観察すると、結石が確認しやすくなります。結石は黄褐色から黒色、白色まで様々な色をしていますので、砂粒状の異物がないか丁寧に確認しましょう。発見した場合は、大きさや数、色、形状を記録し、成分分析のため必ず保存します。
Q: ESWLという治療を受ける患者さんの看護で注意すべきことは何ですか?
A: ESWL (体外衝撃波結石破砕術) は体外から衝撃波を当てて結石を破砕する治療法です。看護で注意すべき点として、まず術前には不整脈や出血傾向の有無を確認し、抗凝固薬を内服している場合は休薬の指示を確認します。術後は、破砕された結石の破片が排出される際に疼痛や血尿が生じることを説明し、水分摂取を十分に促します。排尿時は必ず尿をこし、結石の破片の排出を確認します。また、稀ですが、破砕された結石が尿管に詰まって尿路閉塞を起こすこともあるため、排尿状況や疼痛の増強に注意します。腎周囲の皮下血腫形成の可能性もあるため、側腹部痛や貧血徴候の出現に注意し、必要に応じて画像検査で確認します。
Q: 患者さんが「水を飲むのがつらい」と言います。どのように水分摂取を促せばよいですか?
A: 1日2L以上の水分摂取は確かに負担に感じる患者さんも多いです。工夫として、まず一度に大量に飲むのではなく、少量ずつこまめに飲む習慣をつけてもらいます。コップ1杯 (約200ml) を1日10回程度に分けて飲めば、2Lは達成できます。起床時、食事の前後、入浴前後など、タイミングを決めて飲む習慣をつけると継続しやすくなります。また、水だけでなく、お茶やスポーツドリンク、スープなども水分としてカウントできることを伝えましょう。ただし、シュウ酸を多く含む紅茶やコーヒーは過度に摂取しないよう注意が必要です。季節や活動量に応じて、発汗量が多い夏場や運動後はさらに水分を増やすよう説明します。尿の色が薄い黄色になることを水分摂取の目安にすることも伝えましょう。
まとめ
腎結石は、尿中の成分が結晶化して結石を形成し、激しい疝痛発作や血尿を引き起こす疾患です。病態の核心は、尿の濃縮と結石形成物質の過剰にあり、水分摂取不足や食生活が大きく影響します。
看護の要点は、第一に適切な疼痛コントロールです。疝痛発作時の激痛は患者さんに強い苦痛を与えるため、速やかな鎮痛薬投与と効果の評価が必要です。第二に、排尿観察と結石回収が重要です。すべての排尿をこし、結石の排出を確認し、成分分析のため保存します。第三に、水分出納管理です。1日2L以上の水分摂取を促し、尿量を確保することで結石の排出を促進し、新たな結石形成を予防します。
患者教育のポイントとして、再発予防のための生活習慣改善が不可欠です。結石成分に応じた食事指導、適切なカルシウム摂取の重要性、動物性タンパク質や塩分の過剰摂取を避けること、シュウ酸を多く含む食品の摂り方などを具体的に説明します。また、継続的な水分摂取習慣の確立が再発予防の鍵となることを強調しましょう。
実習での心構えとしては、激しい疼痛を訴える患者さんの苦痛を理解し、迅速に対応する姿勢が大切です。疼痛評価を適切に行い、患者さんが安楽に過ごせるよう環境調整や体位の工夫を行いましょう。また、結石回収は地道な作業ですが、成分分析により再発予防につながる重要な看護行為です。丁寧に観察する習慣をつけましょう。患者さんの生活習慣を詳しく聴取し、個別性を考慮した退院指導ができるよう、コミュニケーションを大切にしてください。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
- 一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
- 実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
- 記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
- 本記事を課題としてそのまま提出しないでください
- 正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません
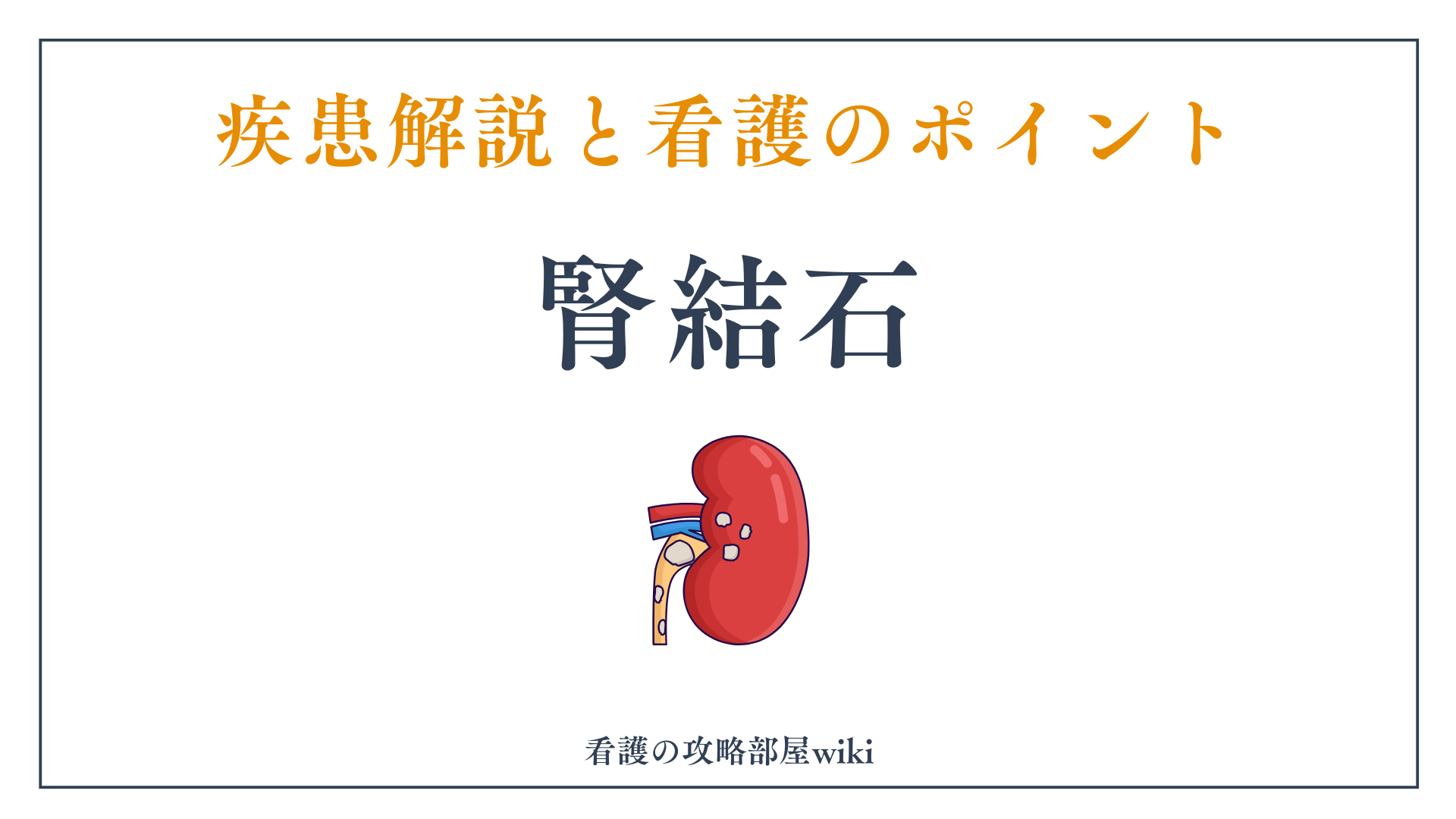
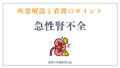
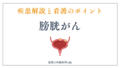
コメント