疾患概要
定義
膀胱がんとは、膀胱の粘膜から発生する悪性腫瘍です。膀胱は、腎臓で作られた尿を一時的に貯める袋状の臓器で、粘膜で覆われています。膀胱がんの約90%以上は尿路上皮がん(移行上皮がん)で、その他に扁平上皮がん、腺がんなどがあります。
膀胱がんは、がんの深達度により、表在性膀胱がん(筋層非浸潤性)と浸潤性膀胱がん(筋層浸潤性)に大別されます。表在性膀胱がんは、がんが粘膜または粘膜下層にとどまるもので、約70〜80%を占めます。浸潤性膀胱がんは、がんが筋層以深に浸潤したもので、予後が悪く、より積極的な治療が必要です。
疫学
膀胱がんは、日本において泌尿器科領域で最も多いがんです。年間約2万人が膀胱がんと診断されています。男女比は約3〜4:1で男性に多く、発症年齢のピークは70歳代です。高齢者に多いがんで、加齢とともに罹患率が上昇します。
欧米諸国に比べて日本は膀胱がんの罹患率が低いですが、近年、高齢化や生活習慣の変化に伴い、増加傾向にあります。早期発見により治療成績は良好で、5年生存率は約80%です。
原因
膀胱がんの発生には、環境因子が強く関与しています。
喫煙
最も重要な危険因子です。喫煙者は非喫煙者に比べて、膀胱がんのリスクが2〜4倍高まります。タバコに含まれる発がん物質が尿中に排泄され、膀胱粘膜に長時間接触することが原因と考えられています。膀胱がん患者さんの約50〜60%は喫煙者です。
職業性曝露
染料、ゴム、化学薬品などを扱う職業では、芳香族アミンなどの発がん物質に曝露され、膀胱がんのリスクが高まります。美容師、印刷工、塗装工、ゴム工業従事者などで多いとされています。
慢性膀胱炎
長期間の慢性炎症は、膀胱がんのリスクを高めます。特に、住血吸虫症による慢性膀胱炎では、扁平上皮がんが発生しやすくなります。
薬剤
抗がん剤のシクロホスファミドは、長期使用により膀胱がんのリスクを高めます。また、中国産のダイエット薬に含まれていたアリストロキア酸も、膀胱がんの原因となることが知られています。
その他
骨盤部への放射線治療歴、家族歴なども危険因子となります。
病態生理
膀胱がんの多くは、膀胱粘膜の尿路上皮から発生します。発がん物質が尿中に排泄され、膀胱粘膜に長時間接触することで、細胞のDNAが傷つき、がんが発生すると考えられています。
膀胱がんは、発育形態により、乳頭状腫瘍(表面がカリフラワー状に盛り上がる)と非乳頭状腫瘍(平坦または陥凹する)に分けられます。乳頭状腫瘍の方が多く、比較的予後良好です。
膀胱がんの進行度は、深達度(がんが膀胱壁のどこまで浸潤しているか)により決定されます。膀胱壁は、内側から、粘膜、粘膜下層、筋層、漿膜下層、漿膜で構成されています。
表在性膀胱がん(筋層非浸潤性)は、粘膜または粘膜下層にとどまるがんです。内視鏡的切除により治療できますが、再発率が高いのが特徴です。約50〜70%の患者さんで再発し、約10〜20%で浸潤性がんへ進行します。そのため、術後の定期的な膀胱鏡検査による経過観察が非常に重要です。
浸潤性膀胱がん(筋層浸潤性)は、がんが筋層以深に浸潤したものです。進行すると、周囲のリンパ節や遠隔臓器(肺、肝臓、骨など)に転移します。予後が悪く、膀胱全摘除術や化学療法などの積極的な治療が必要です。
膀胱がんの症状で最も多いのは無症候性血尿です。がん組織は脆く出血しやすいため、尿に血液が混じります。痛みを伴わない血尿が特徴で、間欠的に出現します。肉眼的血尿(目で見て分かる血尿)でも、痛みがないため放置されることがあり、注意が必要です。
症状・診断・治療
症状
血尿
膀胱がんの最も特徴的な症状は、痛みを伴わない肉眼的血尿です。約80〜90%の患者さんで血尿がみられます。尿全体が赤色やコーラ色になり、血の塊(血餅)が混じることもあります。痛みがないため、一度血尿が出ても自然に止まると、「大したことない」と放置されることがあります。しかし、痛みのない血尿は、膀胱がんの重要なサインです。血尿は間欠的に出現し、数日から数週間で消失しますが、がんが治ったわけではありません。
排尿症状
がんが進行すると、頻尿、排尿時痛、残尿感、尿意切迫感などの膀胱刺激症状が出現することがあります。ただし、早期がんでは、これらの症状は少ないです。
その他
進行すると、下腹部痛、腰痛、体重減少、貧血などの症状が出現します。リンパ節転移により下肢の浮腫が生じることもあります。
診断
尿検査
尿潜血反応により、顕微鏡的血尿(目で見えない血尿)を検出します。また、尿細胞診により、尿中のがん細胞を検出します。尿細胞診は、悪性度の高いがんでは感度が高いですが、悪性度の低いがんでは陽性率が低いという限界があります。
膀胱鏡検査
膀胱がんの診断に最も重要な検査です。尿道から膀胱鏡を挿入し、膀胱内を直接観察します。腫瘍の有無、部位、数、大きさ、形態を評価できます。腫瘍を発見したら、組織を採取して病理検査を行い、確定診断をします。
画像検査
CT検査、MRI検査により、がんの深達度、周囲臓器への浸潤、リンパ節転移、遠隔転移の有無を評価します。治療方針の決定に重要です。また、静脈性腎盂造影により、腎盂や尿管に病変がないかも確認します。
病期分類
膀胱がんは、TNM分類により病期が決定されます。TはTumor(腫瘍の深達度)、NはNode(リンパ節転移)、MはMetastasis(遠隔転移)を示します。病期は0期からIV期まであり、数字が大きいほど進行しています。
治療
膀胱がんの治療は、病期と患者さんの状態により異なります。
表在性膀胱がん(筋層非浸潤性)の治療
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT): 尿道から内視鏡を挿入し、電気メスで腫瘍を切除します。開腹せずに治療でき、膀胱機能を温存できます。最も一般的な治療法です。
膀胱内注入療法: TURBTの再発予防のため、膀胱内に抗がん剤(マイトマイシンC、アドリアマイシンなど)やBCG(結核菌ワクチン)を注入します。BCG膀胱内注入療法は、再発予防効果が高いことが知られています。週1回、計6〜8回注入し、その後維持療法として定期的に注入を続けます。
定期的な膀胱鏡検査: 表在性膀胱がんは再発率が高いため、術後は3ヶ月ごとに膀胱鏡検査を行い、再発の早期発見に努めます。
浸潤性膀胱がん(筋層浸潤性)の治療
膀胱全摘除術: 膀胱、前立腺(男性)、子宮・卵巣(女性)、周囲のリンパ節を一括して摘出します。膀胱を摘出するため、尿路変向術(尿を体外に排出する経路を作る手術)が必要です。尿路変向術には、以下の方法があります。
- 回腸導管: 回腸の一部を切除して導管を作り、一端を尿管につなぎ、もう一端を腹壁に開口させます。腹壁にストーマ(人工的な排泄口)を造設し、尿を体外に排出します。最も一般的な方法です。
- 新膀胱造設術: 腸管を使って新しい膀胱を作り、尿道につなぎます。自然排尿が可能ですが、手術が複雑で、術後の自己導尿が必要になることもあります。
- 尿管皮膚瘻: 尿管を直接腹壁に開口させます。
化学療法: 進行がんや転移がある場合、化学療法を行います。また、膀胱全摘除術の前後に補助化学療法を行うこともあります。シスプラチンを含む多剤併用療法(GC療法、MVAC療法など)が標準的です。
放射線療法: 手術が困難な場合や、膀胱温存を希望する場合、化学療法と併用して放射線療法を行うことがあります。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 急性疼痛(術後)
- 排尿障害
- ボディイメージ混乱(ストーマ造設時)
- 不安
- 感染リスク状態
- 皮膚統合性障害リスク状態(ストーマ周囲)
ゴードン機能的健康パターン
排泄パターン
膀胱がん患者さんの主要な症状は血尿です。血尿の程度、頻度、持続期間、随伴症状(痛み、血餅の有無)を詳細に観察します。TURBT後は、膀胱内に留置したカテーテルから持続的に膀胱洗浄を行い、血餅による閉塞を予防します。洗浄液の色、性状、量を観察し、記録します。
膀胱全摘除術後は、尿路変向術の方法により排尿管理が異なります。回腸導管を造設した場合は、ストーマからの尿の排泄となり、ストーマケアの習得が必要です。新膀胱造設術の場合は、自己導尿の指導が必要になることもあります。
栄養・代謝パターン
血尿による貧血により、食欲不振、全身倦怠感が出現することがあります。栄養状態を評価し、必要に応じて鉄剤の投与や輸血を検討します。術後は、腸蠕動の回復を待ちながら、段階的に経口摂取を再開します。
自己知覚・自己概念パターン
膀胱全摘除術により尿路変向術(特にストーマ造設)を行う場合、ボディイメージが大きく変化します。ストーマを受け入れ、セルフケアを習得し、社会復帰を果たすまでには時間がかかります。患者さんの心理的プロセスを理解し、継続的なサポートが必要です。
ヘンダーソン14基本的ニード
正常に排泄する
TURBT後は、尿道カテーテルが留置され、膀胱洗浄が行われます。洗浄液の流入と排出を確認し、カテーテルが閉塞していないか観察します。血餅により閉塞すると、膀胱内圧が上昇し、激しい痛みや出血を引き起こします。カテーテル抜去後は、排尿状況(回数、量、性状、血尿の程度)を観察します。
膀胱全摘除術後、回腸導管を造設した場合は、ストーマからの尿排泄となります。ストーマケアの方法を段階的に指導し、患者さんが自立してケアできるよう支援します。
身体を動かし、望ましい肢位を保持する
TURBT後は、早期離床が推奨されます。ただし、カテーテルが留置されているため、転倒や引っ張りに注意します。膀胱全摘除術後も、術後合併症の予防と回復促進のため、早期離床を促します。
身体の清潔を保ち、身だしなみを整え、皮膚を保護する
TURBT後は、尿道カテーテル挿入部の清潔管理が重要です。感染予防のため、陰部洗浄を行います。
回腸導管を造設した場合、ストーマ周囲の皮膚トラブルを予防することが非常に重要です。尿は常時排泄されるため、皮膚への刺激が大きく、びらん、潰瘍を起こしやすいです。適切な装具の選択と皮膚保護が必要です。
自分の感情、欲求、恐怖、あるいは気分を表現してコミュニケーションをとる
がんの診断、手術、ストーマ造設など、患者さんは多くのストレスにさらされます。特に、膀胱全摘除術によりストーマを造設する場合、ボディイメージの変化、性機能の喪失(男性)、社会生活への不安など、さまざまな感情を抱えます。これらの感情を表出できる環境を整え、傾聴する姿勢が大切です。
看護計画・介入の内容
- 術前オリエンテーション: 手術の流れ、術後の経過、カテーテル留置、膀胱洗浄、ストーマ造設(該当者)について説明し、不安を軽減する
- 血尿の観察: 血尿の程度、頻度、血餅の有無を観察し、記録する
- バイタルサインの監視: 体温、血圧、脈拍、呼吸数を定期的に測定し、術後合併症の早期発見に努める
- 疼痛コントロール: 痛みの部位、程度をペインスケールで評価し、鎮痛薬を確実に投与する
- 膀胱洗浄の管理(TURBT後): 持続的膀胱洗浄を行い、流入量と排出量を確認する。洗浄液の色、性状を観察し、血餅による閉塞に注意する。閉塞の徴候(排液の停止、下腹部痛、膀胱膨満)があれば、すぐに対応する
- カテーテル管理: カテーテルの固定を確認し、屈曲や閉塞を防ぐ。挿入部の清潔を保ち、感染を予防する
- 排尿状況の観察: カテーテル抜去後、排尿回数、量、性状、血尿の程度、残尿感の有無を観察する
- 腸蠕動の観察: 膀胱全摘除術後、排ガス、排便の有無、腹部膨満の程度、腸蠕動音を継続的に観察する
- 創部の観察: 創部の発赤、腫脹、浸出液、感染徴候を観察する
- 早期離床の促進: 術後の早期離床の重要性を説明し、患者さんのペースに合わせて歩行を支援する
- ストーマケアの指導(回腸導管造設者): ストーマケアの方法を段階的に指導する。装具の選択、交換方法、皮膚保護、トラブル時の対応、日常生活の工夫などを具体的に説明する
- ストーマ周囲皮膚の観察: ストーマ周囲の皮膚の状態を観察し、びらん、潰瘍、感染の有無を確認する。適切な皮膚保護剤を使用する
- 心理的サポート: 不安や恐怖を傾聴し、患者さんの尊厳を守る。ストーマ造設者には、ボディイメージの変化への適応を支援する
- 患者・家族教育: 疾患の理解促進、再発予防(禁煙)、定期受診の重要性、ストーマケア(該当者)、症状出現時の対応について説明する
- 退院調整: 退院後の生活環境を評価し、必要に応じて訪問看護やストーマ外来の紹介を行う
よくある疑問・Q&A
Q: 痛みのない血尿が出ましたが、すぐに止まりました。病院に行く必要がありますか?
A: はい、必ず病院を受診してください。痛みのない血尿は、膀胱がんの最も重要なサインです。血尿が自然に止まっても、がんが治ったわけではありません。膀胱がんによる血尿は、間欠的に出現し、数日から数週間で消失することがありますが、がんは進行している可能性があります。「痛くないから大丈夫」「自然に止まったから様子を見よう」と放置すると、がんが進行してしまいます。肉眼的血尿(目で見て分かる血尿)が一度でもあれば、必ず泌尿器科を受診し、膀胱鏡検査などの精密検査を受けることが重要です。早期発見により、内視鏡的切除だけで治療でき、膀胱を温存できる可能性が高まります。
Q: 膀胱全摘除術後、ストーマ(回腸導管)を造設すると、どのような生活になるのですか?
A: 回腸導管を造設すると、腹部にストーマ(尿の排泄口)ができ、尿が常時排泄されます。ストーマには括約筋がないため、尿を我慢することはできません。そのため、ストーマ装具(パウチ)を24時間装着し、尿を受け止めます。最初は戸惑いや不安を感じるかもしれませんが、適切なケアと工夫により、ほとんどの日常生活が可能です。入浴、旅行、スポーツなども楽しめます。ストーマ装具は、衣服の上からは分かりません。ただし、定期的な装具の交換が必要です。尿が常時出るため、夜間は足元にパウチを置き、長時間溜められるようにします。また、水分摂取が少ないと尿が濃縮され、ストーマ周囲の皮膚トラブルを起こしやすいため、十分な水分摂取が推奨されます。看護師は、患者さんがストーマを受け入れ、自立してケアできるよう、段階的に指導します。
Q: 表在性膀胱がんは、内視鏡で切除すれば治るのですか? 再発はしませんか?
A: 表在性膀胱がん(筋層非浸潤性)は、経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT)により内視鏡的に切除できます。開腹せずに治療でき、膀胱機能を温存できるため、患者さんにとって負担が少ない治療法です。しかし、再発率が非常に高いのが特徴です。約50〜70%の患者さんで再発し、約10〜20%で浸潤性がんへ進行します。再発の原因は、①切除時に取り残しがあった、②切除した部位に新たながんが発生した、③他の部位に新たながんが発生した、などです。そのため、術後は3ヶ月ごとに膀胱鏡検査を行い、再発の早期発見に努めます。また、再発予防のため、膀胱内に抗がん剤やBCGを注入する膀胱内注入療法を行うこともあります。定期的な膀胱鏡検査は、患者さんにとって負担ですが、再発の早期発見のために非常に重要です。
Q: 膀胱がんの予防のために、日常生活で気をつけることは何ですか?
A: 膀胱がんの最も重要な予防法は禁煙です。喫煙者は非喫煙者に比べて、膀胱がんのリスクが2〜4倍高まります。タバコに含まれる発がん物質が尿中に排泄され、膀胱粘膜に長時間接触することが原因です。禁煙により、膀胱がんのリスクは低下します。すでに膀胱がんと診断された方も、禁煙により再発のリスクを下げることができます。次に、十分な水分摂取が推奨されます。水分を多く摂ることで、尿量が増え、発がん物質が膀胱粘膜に接触する時間が短くなります。1日2リットル以上の水分摂取が目安です。また、職業性曝露のある方(染料、ゴム、化学薬品を扱う職業)は、適切な防護具を使用し、曝露を最小限にすることが大切です。さらに、痛みのない血尿があれば、必ず医療機関を受診することが、早期発見につながります。
Q: BCG膀胱内注入療法とは、どのような治療ですか? 副作用はありますか?
A: BCG膀胱内注入療法は、表在性膀胱がんの再発予防のための治療です。BCGとは、結核菌を弱毒化したワクチンで、膀胱内に注入すると、免疫反応が活性化され、がん細胞を攻撃します。抗がん剤による膀胱内注入療法よりも、再発予防効果が高いことが知られています。週1回、計6〜8回注入し、その後維持療法として定期的に注入を続けます。注入方法は、カテーテルで膀胱内にBCGを注入し、約2時間膀胱内に留めた後、排尿します。副作用として、膀胱刺激症状(頻尿、排尿時痛、血尿)、発熱、倦怠感などがみられます。まれに、重篤な副作用として、敗血症様症状を起こすことがあるため、注意深い観察が必要です。副作用が強い場合は、医師に相談し、投与を中止したり、薬剤を変更したりします。
まとめ
膀胱がんは、膀胱の粘膜から発生する悪性腫瘍で、泌尿器科領域で最も多いがんです。男性に多く、高齢者に好発します。最大の危険因子は喫煙で、禁煙が最も重要な予防法です。
最も特徴的な症状は、痛みを伴わない肉眼的血尿です。血尿が間欠的に出現し、自然に止まることもありますが、膀胱がんの重要なサインであり、必ず医療機関を受診することが必要です。診断には膀胱鏡検査が最も重要です。
膀胱がんは、深達度により、表在性膀胱がん(筋層非浸潤性)と浸潤性膀胱がん(筋層浸潤性)に大別されます。表在性膀胱がんは、経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT)により内視鏡的に切除でき、膀胱機能を温存できます。しかし、再発率が高い(50〜70%)ため、術後は3ヶ月ごとの膀胱鏡検査による経過観察が必要です。再発予防のため、膀胱内注入療法(抗がん剤、BCG)を行います。
浸潤性膀胱がんでは、膀胱全摘除術が標準治療です。膀胱を摘出するため、尿路変向術が必要で、多くの場合回腸導管が造設されます。ストーマからの尿排泄となるため、ストーマケアの習得が必要です。
看護のポイントは、血尿の観察、TURBT後の膀胱洗浄管理(血餅による閉塞予防)、カテーテル管理、ストーマケアの指導、心理的サポートです。特に、ストーマを造設した患者さんには、ボディイメージの変化への適応を支援し、セルフケア能力の獲得を段階的に支援することが重要です。
TURBT後の膀胱洗浄では、洗浄液の流入と排出を確認し、血餅によるカテーテル閉塞に注意します。閉塞すると膀胱内圧が上昇し、激しい痛みや出血を引き起こすため、早期発見が重要です。
回腸導管を造設した場合、尿は常時排泄されるため、ストーマ周囲の皮膚トラブル(びらん、潰瘍)を起こしやすく、適切な皮膚保護が必要です。患者さんが自立してストーマケアを行えるよう、装具の選択、交換方法、皮膚保護、日常生活の工夫などを段階的に指導します。
また、がんの診断やストーマ造設により、患者さんは大きな心理的ショックを受けます。不安や恐怖、ボディイメージの変化、性機能の喪失(男性)への悲しみなどに寄り添い、継続的な心理的サポートを提供することが大切です。
実習では、痛みのない血尿の重要性を理解し、患者さんや家族への啓発の重要性を学びましょう。また、TURBT後の膀胱洗浄管理の実際を観察し、血餅による閉塞の予防と早期発見のポイントを把握してください。ストーマケアについては、患者さんの心理的プロセスを理解し、尊厳を守りながら段階的に指導する姿勢を学ぶことが大切です。
膀胱がんは、早期発見により良好な予後が期待できる疾患です。再発率は高いものの、定期的な膀胱鏡検査により早期に発見でき、再発しても内視鏡的治療で対応できることが多いです。患者さんが希望を持って治療を継続し、再発予防のための定期受診を守れるよう、根拠に基づいた看護を実践していきましょう。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
・正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません
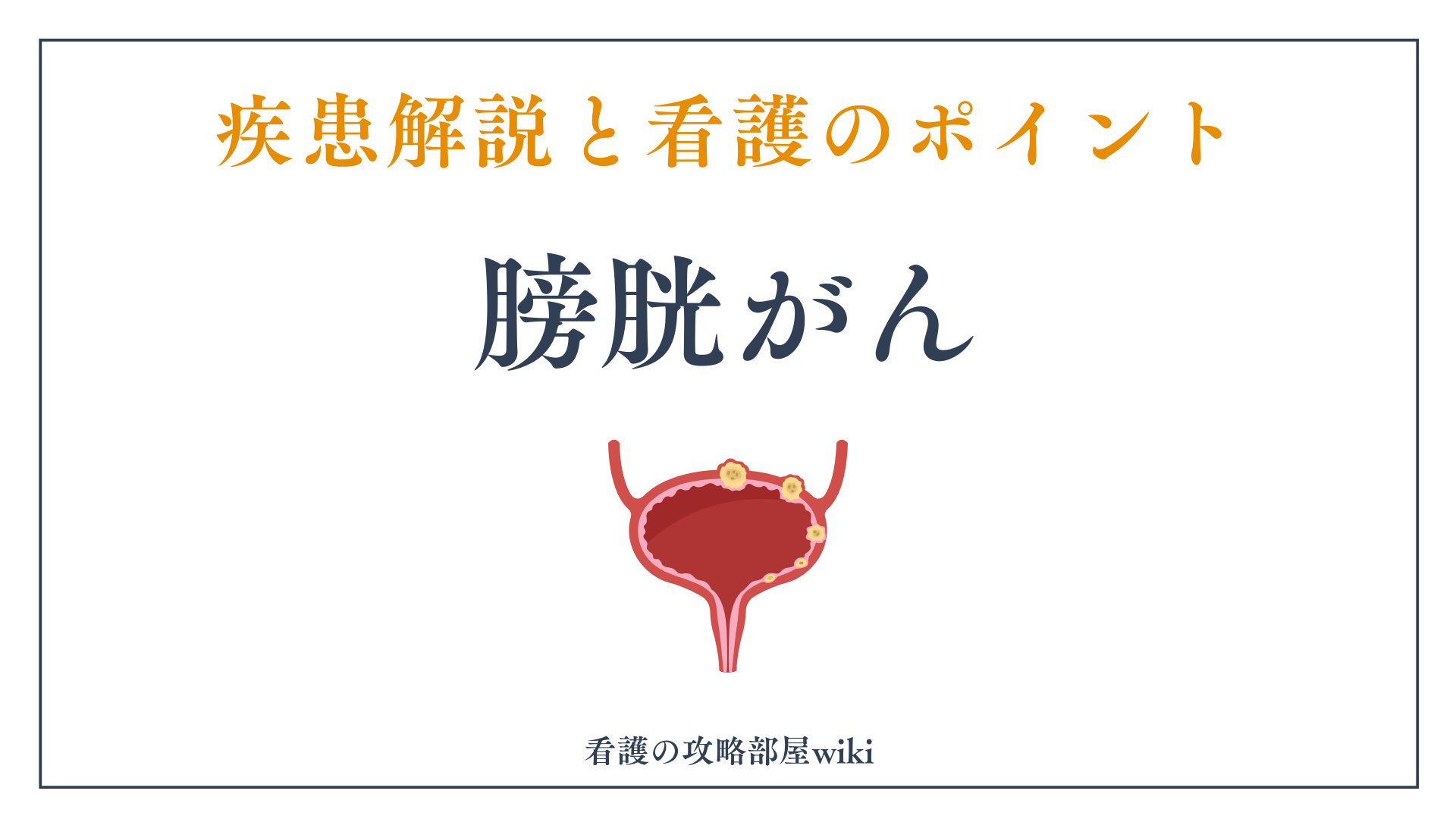
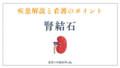

コメント