疾患概要
定義
急性腎不全とは、数時間から数日という短期間に腎機能が急激に低下し、老廃物の排泄や体液・電解質バランスの調節ができなくなった状態です。近年では、急性腎障害(AKI:Acute Kidney Injury)という用語が用いられることが多くなっています。AKIの診断基準は、血清クレアチニン値の上昇(48時間以内に0.3mg/dL以上の上昇、または7日以内にベースラインの1.5倍以上)または尿量の減少(6時間で0.5mL/kg/時以下)です。
急性腎不全は、適切な治療により腎機能が回復する可能性がある点で、慢性腎不全と異なります。しかし、重症例では透析治療が必要となり、死亡率も高い重篤な病態です。
疫学
急性腎不全は、入院患者の約5〜7%に発症するとされ、集中治療室(ICU)では約30〜50%と高頻度でみられます。高齢者、糖尿病患者、慢性腎臓病患者、心不全患者などでリスクが高まります。
急性腎不全を発症した患者さんの死亡率は約20〜50%と高く、特に多臓器不全を伴う場合は予後不良です。しかし、適切な治療により腎機能が回復する患者さんも多く、早期発見と迅速な対応が重要です。
原因
急性腎不全の原因は、発生部位により腎前性、腎性、腎後性の3つに分類されます。
腎前性(約55〜60%)
腎臓への血流が減少することで起こります。腎臓自体には障害がなく、血流を改善すれば腎機能は回復します。原因として、脱水(嘔吐、下痢、出血、熱傷)、心不全、ショック(敗血症、心原性、出血性)、肝硬変などがあります。最も頻度が高いタイプです。
腎性(約35〜40%)
腎臓自体が障害されることで起こります。原因として、急性尿細管壊死(ATN:虚血、薬剤、造影剤など)、急性間質性腎炎(薬剤性)、急性糸球体腎炎、横紋筋融解症などがあります。腎前性が持続すると、腎性に移行することがあります。
腎後性(約5%)
尿路が閉塞することで起こります。原因として、尿管結石、前立腺肥大症、前立腺癌、膀胱癌、後腹膜線維症などがあります。両側の尿路閉塞、または単腎の場合に発症します。
病態生理
急性腎不全の病態は、原因により異なりますが、共通するのは糸球体濾過量(GFR)の急激な低下です。
腎前性急性腎不全
腎臓への血流が減少すると、糸球体での濾過圧が低下し、GFRが減少します。初期には、腎臓は自己防御機能により糸球体の濾過圧を維持しようとしますが、血流減少が続くと代償機能が破綻し、急性腎不全に至ります。この段階では、腎臓の細胞自体は障害されていないため、血流を回復させれば腎機能は速やかに改善します。しかし、腎前性が持続すると、腎虚血により尿細管細胞が壊死し、腎性(急性尿細管壊死)に移行します。
腎性急性腎不全(急性尿細管壊死)
虚血や薬剤により尿細管細胞が障害されると、尿細管での再吸収や分泌機能が低下します。壊死した細胞が剥がれ落ちて尿細管内腔を閉塞し、濾過された尿が尿細管間質に漏れ出すこともあります。その結果、GFRが著しく低下します。尿細管細胞は再生能力があるため、数日から数週間で回復することが多いですが、重症例では完全には回復せず、慢性腎臓病に移行することもあります。
腎後性急性腎不全
尿路が閉塞すると、尿が排泄できずに腎盂に貯留し、腎盂内圧が上昇します。その圧力が糸球体に逆行し、濾過圧が低下してGFRが減少します。早期に閉塞を解除すれば腎機能は回復しますが、長期間続くと腎実質が障害され、不可逆的な腎障害となります。
急性腎不全による全身への影響
GFRが低下すると、以下のような変化が起こります。
老廃物の蓄積: 尿素窒素(BUN)、クレアチニンなどの老廃物が体内に蓄積し、尿毒症の症状(悪心、嘔吐、意識障害、けいれんなど)が出現します。
電解質異常: カリウムが排泄されず、高カリウム血症となります。高カリウム血症は致死的不整脈を起こす危険があります。また、リンの蓄積、カルシウムの低下、代謝性アシドーシスも生じます。
体液過剰: 水分が排泄されず、体液過剰となり、浮腫、肺水腫、心不全を起こします。
貧血: エリスロポエチンの産生低下により貧血が進行します。
症状・診断・治療
症状
急性腎不全の症状は、原因疾患と腎機能低下の程度により異なります。
尿量の変化
多くの急性腎不全では、乏尿(1日の尿量が400mL以下)または無尿(100mL以下)となります。しかし、約30〜50%の患者さんでは尿量が保たれる非乏尿性急性腎不全もあります。尿量の減少は、急性腎不全の重要なサインです。
浮腫・体重増加
水分が排泄されず体内に貯留するため、全身性の浮腫(特に下肢)、体重増加がみられます。肺に水分が貯留すると、呼吸困難、起坐呼吸、咳嗽、ピンク色の泡沫状痰などの肺水腫の症状が出現します。
尿毒症症状
老廃物の蓄積により、悪心、嘔吐、食欲不振、全身倦怠感、意識障害、けいれん、出血傾向などが出現します。
電解質異常による症状
高カリウム血症: 脱力感、しびれ、不整脈(徐脈、心室細動)。重症では心停止に至ります。
代謝性アシドーシス: 深く速い呼吸(クスマウル呼吸)、意識障害。
低カルシウム血症: テタニー、筋肉のけいれん。
原因疾患の症状
脱水症状、ショック症状、発熱、腹痛、血尿、排尿障害など、原因疾患に特有の症状もみられます。
診断
血液検査
BUN、クレアチニン: 上昇します。BUN/クレアチニン比が20以上の場合、腎前性を疑います。
電解質: カリウム、リン、尿酸の上昇、カルシウムの低下がみられます。
血液ガス分析: 代謝性アシドーシス(pH低下、HCO3-低下)がみられます。
尿検査
尿量、尿比重、尿浸透圧、尿中Na濃度、尿蛋白、尿潜血、尿沈渣などを評価します。腎前性では尿が濃縮され(尿比重高値、尿浸透圧高値、尿中Na低値)、腎性では尿が希釈されます(尿比重低値、尿浸透圧低値、尿中Na高値)。
画像検査
腹部超音波検査、CT検査により、腎臓の大きさ、水腎症の有無、尿路閉塞の有無を評価します。腎後性急性腎不全では、水腎症や尿路閉塞が確認されます。
原因検索
病歴聴取、身体診察、各種検査により、原因を特定します。脱水の有無、薬剤使用歴、造影剤使用歴、感染症の有無、尿路閉塞の有無などを確認します。
治療
急性腎不全の治療は、原因の除去、腎機能の保護、合併症の管理が柱となります。
原因の除去
腎前性: 輸液により循環血液量を回復させます。心不全が原因の場合は、利尿薬や強心薬を使用します。
腎性: 原因薬剤を中止します。造影剤腎症では、事前の十分な輸液が予防に重要です。
腎後性: 尿路閉塞を速やかに解除します。尿道カテーテル留置、経皮的腎瘻造設、尿管ステント留置などを行います。
腎機能の保護
適切な輸液管理により腎血流を維持します。ただし、過剰な輸液は肺水腫を引き起こすため、注意が必要です。利尿薬(フロセミド)により尿量を確保しようとすることもありますが、腎機能自体を改善する効果はありません。
合併症の管理
高カリウム血症: カリウム制限食、カリウム吸着薬、グルコン酸カルシウム静注(心保護作用)、グルコース・インスリン療法、炭酸水素ナトリウム投与などを行います。重症例では緊急透析が必要です。
体液過剰: 水分・塩分制限、利尿薬投与を行います。肺水腫がある場合は、酸素投与、必要に応じて人工呼吸管理を行います。
代謝性アシドーシス: 重症例では炭酸水素ナトリウムを投与します。
尿毒症: 低タンパク質食により老廃物の産生を抑えます。症状が強い場合は透析を検討します。
血液浄化療法(透析)
以下の場合、血液透析または持続的血液濾過透析を行います。
- 高カリウム血症(K 6.5mEq/L以上)で内科的治療に反応しない場合
- 重度の体液過剰、肺水腫
- 重度の代謝性アシドーシス
- 重度の尿毒症症状
- BUN 100mg/dL以上
透析により、過剰な水分、電解質、老廃物を除去できます。急性腎不全の透析は、腎機能が回復するまでの一時的な治療です。
栄養管理
適切なカロリー摂取(30〜35kcal/kg/日)を確保し、タンパク質は制限します(0.6〜0.8g/kg/日)。カリウム、リン、水分も制限します。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 体液量過剰
- 体液量不足リスク状態(腎前性の場合)
- ガス交換障害(肺水腫を伴う場合)
- 栄養摂取消費バランス異常
- 活動耐性低下
- 不安
ゴードン機能的健康パターン
栄養・代謝パターン
急性腎不全患者さんは、尿毒症による悪心、嘔吐、食欲不振により食事摂取が困難になります。しかし、腎臓に負担をかけないよう、タンパク質、カリウム、リン、水分の制限が必要です。これらの制限により、さらに食事の楽しみが減り、栄養状態が悪化することもあります。栄養士と連携し、制限内で患者さんが食べられる食事を工夫します。
浮腫の評価のため、毎日同じ時間に体重を測定します。体重の急激な増加は、体液過剰を示します。
排泄パターン
尿量の正確な測定と記録が、急性腎不全の管理において最も重要です。尿量は1時間ごとに測定し、乏尿(400mL/日以下)や無尿(100mL/日以下)の有無を評価します。尿量と水分摂取量のバランス(水分出納)を毎日計算し、体液過剰や脱水を評価します。
透析を行っている場合は、透析による除水量も記録します。
活動・運動パターン
急性腎不全患者さんは、貧血、尿毒症、電解質異常により、著しい倦怠感と活動耐性の低下がみられます。重症例では、集中治療室で厳重な管理が必要です。ベッド上安静が基本ですが、長期臥床による合併症(肺炎、深部静脈血栓症、筋力低下など)を予防するため、状態が安定したら早期離床を検討します。
認知・知覚パターン
尿毒症による意識障害、見当識障害、けいれんが出現することがあります。意識レベル、見当識、不穏の有無を継続的に評価します。高カリウム血症によるしびれや脱力感にも注意します。
ヘンダーソン14基本的ニード
正常に飲食する
水分制限、塩分制限、カリウム制限、リン制限、タンパク質制限など、多くの制限があり、患者さんにとって非常に苦痛です。制限の理由を丁寧に説明し、理解を促します。また、制限内で患者さんの嗜好に合わせた食事を提供できるよう、栄養士と連携します。
口渇感が強い場合は、氷片を与えたり、レモン汁で口を潤したりして、不快感を軽減します。
正常に排泄する
尿量測定は、1時間ごとに正確に行います。尿道カテーテルが留置されている場合は、感染予防のため清潔管理を徹底します。腎後性で尿路閉塞を解除した後は、利尿期に大量の尿が排泄されることがあり、脱水に注意します。
正常に呼吸する
体液過剰により肺水腫が生じると、呼吸困難が出現します。呼吸数、呼吸音(水泡音)、酸素飽和度を観察し、必要に応じて酸素投与や人工呼吸管理を行います。起坐呼吸がある場合は、ファウラー位(上半身を起こした体位)により呼吸を楽にします。
身体の清潔を保ち、身だしなみを整え、皮膚を保護する
尿毒症により皮膚の掻痒感が出現することがあります。皮膚を清潔に保ち、保湿剤を使用して乾燥を防ぎます。浮腫により皮膚が脆弱になっているため、圧迫や摩擦による皮膚損傷に注意します。
透析を行っている場合は、シャント(血液透析のための血管)や透析カテーテルの管理が重要です。感染予防のため、清潔操作を徹底します。
自分の感情、欲求、恐怖、あるいは気分を表現してコミュニケーションをとる
急性腎不全の診断は、患者さんに大きな不安と恐怖をもたらします。「腎不全」という言葉への恐れ、透析への不安、将来への心配など、さまざまな感情が生じます。これらの感情を表出できる環境を整え、傾聴する姿勢が大切です。また、急性腎不全の多くは回復可能であることを説明し、希望を持てるよう支援します。
看護計画・介入の内容
- 尿量の厳密な測定: 1時間ごとに尿量を測定し、正確に記録する。乏尿・無尿の有無を評価する
- 水分出納の管理: 飲水量、輸液量、尿量、不感蒸泄、その他の排泄物を記録し、1日の水分バランスを計算する
- 体重測定: 毎日同じ時間、同じ条件で体重を測定し、体液過剰や脱水を評価する
- バイタルサインの監視: 血圧、脈拍、呼吸数、体温、酸素飽和度を定期的に測定し、循環動態と呼吸状態を評価する
- 浮腫の観察: 全身の浮腫の程度、特に下肢、顔面、手指、腰部の浮腫を観察する。圧痕の有無も確認する
- 呼吸状態の観察: 呼吸困難、起坐呼吸の有無、呼吸音(水泡音、ラ音)を聴取し、肺水腫の早期発見に努める
- 意識レベルの観察: 尿毒症による意識障害、見当識障害、不穏、けいれんの有無を継続的に評価する
- 電解質異常の観察: 高カリウム血症の症状(脱力感、しびれ、不整脈)、低カルシウム血症の症状(テタニー、筋肉のけいれん)を観察する
- 心電図モニタリング: 高カリウム血症による致死的不整脈を早期発見するため、持続的に心電図をモニタリングする。T波の増高、QRS幅の延長に注意する
- 検査データの確認: BUN、クレアチニン、電解質(特にカリウム)、血液ガス分析、ヘモグロビン値を定期的に確認し、病態を評価する
- 水分・塩分制限の管理: 医師の指示に従い、適切な水分・塩分制限を実施する。患者さんに制限の理由を説明し、協力を得る
- 食事制限の支援: カリウム、リン、タンパク質の制限食を提供する。栄養士と連携し、患者さんの嗜好に合わせた食事を工夫する
- 透析の管理: 透析中は、血圧、脈拍、不整脈、不均衡症候群(頭痛、悪心、嘔吐、意識障害)の有無を観察する。シャントやカテーテルの感染予防に努める
- スキンケア: 浮腫部位の皮膚保護、掻痒感の軽減、褥瘡予防を行う
- 感染予防: 尿道カテーテル、透析カテーテル、中心静脈カテーテルなどの挿入部の清潔管理を徹底する
- 患者・家族教育: 疾患の理解促進、水分・食事制限の必要性、透析について、症状出現時の対応について説明する
- 心理的サポート: 不安や恐怖を傾聴し、急性腎不全の多くは回復可能であることを説明し、希望を持てるよう支援する
よくある疑問・Q&A
Q: 急性腎不全と慢性腎不全の違いは何ですか?
A: 急性腎不全(急性腎障害)は、数時間から数日という短期間に腎機能が急激に低下した状態で、適切な治療により腎機能が回復する可能性があります。原因を取り除き、適切な治療を行えば、多くの患者さんで腎機能は元に戻ります。一方、慢性腎不全(慢性腎臓病)は、数ヶ月から数年かけて徐々に腎機能が低下していく状態で、不可逆的です。一度低下した腎機能は元に戻らず、進行すると末期腎不全となり、永続的な透析療法や腎移植が必要になります。急性腎不全でも、適切な治療が遅れたり、重症だったりすると、完全には回復せずに慢性腎臓病に移行することもあります。早期発見と迅速な対応が、腎機能の回復には非常に重要です。
Q: 高カリウム血症はなぜ危険なのですか? どのような症状が出ますか?
A: カリウムは、心臓の電気的活動に重要な役割を果たしています。血液中のカリウム濃度が正常範囲(3.5〜5.0mEq/L)に保たれているときは問題ありませんが、高カリウム血症(5.5mEq/L以上)になると、心臓の電気的活動が乱れ、致死的不整脈を起こす危険があります。初期症状は、脱力感、しびれ、悪心などですが、これらの症状は必ずしも現れるわけではありません。カリウム値が6.5mEq/L以上になると、心電図変化(T波の増高、QRS幅の延長)が出現し、7.0mEq/L以上では徐脈、心室細動、心停止に至る可能性があります。症状が乏しいまま突然心停止を起こすこともあるため、非常に危険です。そのため、急性腎不全患者さんでは、カリウム値を頻回に測定し、心電図モニタリングを行い、高カリウム血症を早期に発見して治療することが極めて重要です。
Q: 急性腎不全の患者さんに、なぜ水分制限が必要なのですか? どのくらい制限するのですか?
A: 急性腎不全では、腎臓の機能が低下しているため、水分を尿として排泄できません。水分を摂りすぎると、体内に水分が貯留し、体液過剰となります。体液過剰になると、全身性の浮腫、肺水腫、心不全を起こし、呼吸困難や生命の危険をもたらします。そのため、水分制限が必要なのです。水分制限の目安は、前日の尿量+不感蒸泄(約500mL)です。例えば、前日の尿量が300mLであれば、その日の水分摂取量は300mL+500mL=800mLに制限します。ただし、発熱や発汗がある場合は、不感蒸泄が増加するため、制限を緩めます。水分制限は、患者さんにとって非常に苦痛です。口渇感が強い場合は、氷片を与えたり、レモン汁で口を潤したりして、不快感を軽減します。また、制限の理由を丁寧に説明し、理解と協力を得ることが大切です。
Q: 急性腎不全で透析が必要になるのは、どのような場合ですか? 透析は一生続けなければならないのですか?
A: 急性腎不全で透析が必要になるのは、内科的治療だけでは生命の危険がある以下のような場合です:高カリウム血症(6.5mEq/L以上)で内科的治療に反応しない場合、重度の体液過剰・肺水腫、重度の代謝性アシドーシス、重度の尿毒症症状、BUN 100mg/dL以上などです。急性腎不全の透析は、腎機能が回復するまでの一時的な治療です。透析により、過剰な水分、電解質、老廃物を除去し、生命を維持しながら、腎臓が回復するのを待ちます。多くの患者さんでは、適切な治療により腎機能が回復し、透析から離脱できます。透析が必要な期間は、数日から数週間程度のことが多いです。ただし、腎障害が重症で完全には回復しなかった場合や、元々慢性腎臓病があった場合は、永続的な透析が必要になることもあります。急性腎不全の透析は、あくまで一時的なサポートであり、慢性腎不全の永続的な透析とは異なることを理解しておくことが大切です。
Q: 急性腎不全の患者さんの看護で、最も重要なことは何ですか?
A: 急性腎不全の看護で最も重要なのは、尿量の厳密な測定と水分出納の管理です。尿量は、腎機能の最も直接的な指標であり、1時間ごとに正確に測定する必要があります。乏尿(400mL/日以下)や無尿(100mL/日以下)の早期発見が、迅速な治療介入につながります。また、飲水量、輸液量、尿量、その他の排泄物を正確に記録し、1日の水分バランスを計算します。体重も毎日測定し、体液過剰や脱水を評価します。次に重要なのは、高カリウム血症による致死的不整脈の早期発見です。カリウム値を頻回に確認し、心電図を持続的にモニタリングします。T波の増高、QRS幅の延長などの変化を見逃さないよう注意します。さらに、肺水腫の早期発見も重要です。呼吸数、呼吸困難の有無、呼吸音の聴取、酸素飽和度の測定を継続的に行います。これらの観察を通じて、生命に関わる合併症を早期に発見し、迅速に対応することが、急性腎不全看護の要です。
まとめ
急性腎不全(急性腎障害:AKI)は、数時間から数日という短期間に腎機能が急激に低下し、老廃物の排泄や体液・電解質バランスの調節ができなくなった状態です。原因により腎前性(約55〜60%)、腎性(約35〜40%)、腎後性(約5%)に分類されます。
腎前性は腎臓への血流減少により起こり、適切な輸液により改善します。腎性は腎臓自体の障害で、急性尿細管壊死が代表的です。腎後性は尿路閉塞により起こり、早期の閉塞解除が重要です。
主な症状は、乏尿・無尿、浮腫・体重増加、尿毒症症状、高カリウム血症などです。高カリウム血症は致死的不整脈を起こす危険があり、最も注意すべき合併症です。体液過剰により肺水腫を起こすと、呼吸困難が出現し、生命に関わります。
診断には、血液検査(BUN、クレアチニン、電解質)、尿検査、画像検査が用いられます。治療は、原因の除去、腎機能の保護、合併症の管理が柱です。高カリウム血症、重度の体液過剰、重度の尿毒症などでは、血液透析が必要となります。
看護のポイントは、尿量の厳密な測定、水分出納の管理、体重測定、電解質異常の観察、心電図モニタリング、呼吸状態の観察です。尿量は1時間ごとに正確に測定し、水分バランスを毎日計算します。高カリウム血症による不整脈を早期発見するため、心電図を持続的にモニタリングします。肺水腫の早期発見のため、呼吸状態を継続的に観察します。
また、水分・食事制限の管理も重要です。水分は前日の尿量+不感蒸泄(約500mL)に制限します。カリウム、リン、タンパク質の制限食を提供します。これらの制限は患者さんにとって非常に苦痛であるため、制限の理由を丁寧に説明し、理解と協力を得ることが大切です。
急性腎不全は、適切な治療により腎機能が回復する可能性があります。透析が必要になっても、多くは一時的なもので、腎機能の回復とともに透析から離脱できます。患者さんと家族に、回復の可能性を伝え、希望を持てるよう支援することも看護の重要な役割です。
実習では、尿量測定と水分出納計算を正確に行う技術を身につけましょう。また、検査データ(特にカリウム値)と心電図変化を結びつけて理解し、危険な状態を早期に発見する力を養ってください。急性腎不全は重篤な病態ですが、早期発見と迅速な対応により、多くの患者さんで腎機能の回復が期待できます。根拠に基づいた的確な観察と看護介入を実践していきましょう。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
・正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません
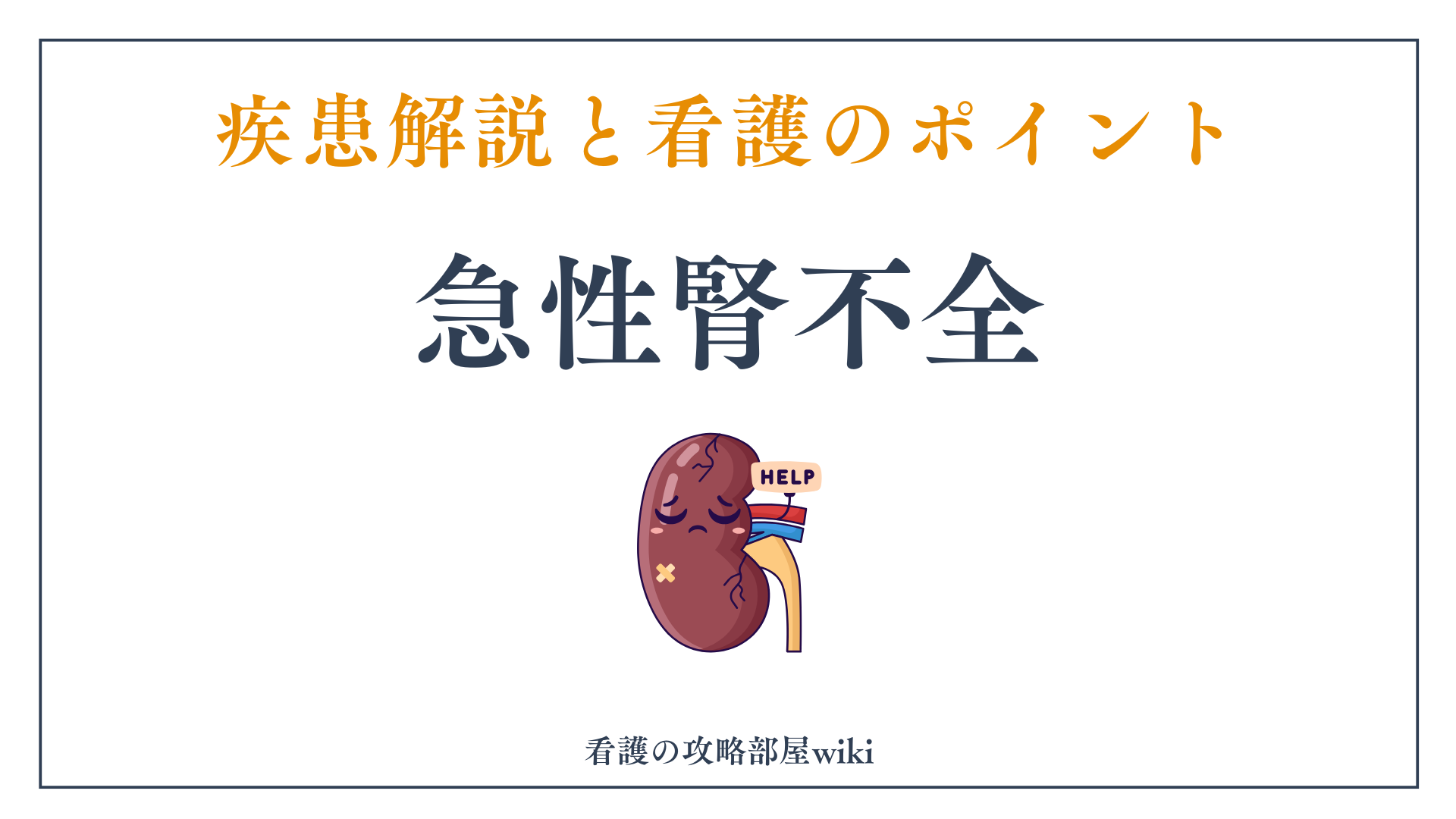
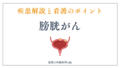

コメント