疾患概要
定義
血小板減少症(Thrombocytopenia)は、血液中の血小板数が正常範囲より減少した状態を指します。血小板は止血に重要な役割を果たす血液成分で、血管が傷ついた時に傷口に集まって血栓を作り、出血を止める働きがあります。正常な血小板数は15〜40万/μL程度ですが、10万/μL未満になると血小板減少症と診断されます。血小板数が減少すると、出血しやすくなったり、出血が止まりにくくなったりします。血小板減少症は単独の疾患ではなく、様々な原因によって引き起こされる症候群であり、原因疾患の特定が重要です。
疫学
血小板減少症の発症頻度は原因によって大きく異なります。最も多い原因の一つである特発性血小板減少性紫斑病(ITP)は、年間10万人あたり2〜4人程度が発症するとされています。小児と成人の両方に見られますが、小児では急性型が多く自然治癒することもある一方、成人では慢性化しやすい傾向があります。性別では、成人ITPは女性に多く、男女比は1:2〜3程度です。その他、薬剤性、感染症、自己免疫疾患、血液疾患、肝疾患など、多様な原因で血小板減少が起こるため、臨床現場では比較的よく遭遇する病態です。
原因
血小板減少症の原因は、大きく分けて以下の3つのメカニズムに分類されます。
血小板産生の低下では、骨髄での血小板の産生が減少します。原因として、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、白血病などの骨髄疾患、抗がん剤や放射線治療による骨髄抑制、巨赤芽球性貧血(ビタミンB12や葉酸欠乏)、骨髄への腫瘍浸潤などがあります。
血小板破壊の亢進では、血小板が通常より早く壊されてしまいます。特発性血小板減少性紫斑病(ITP)が代表的で、自己抗体が血小板に結合し、脾臓で破壊されます。その他、薬剤性(ヘパリン、キニーネ、抗生物質など)、感染症(ウイルス感染、敗血症など)、自己免疫疾患(SLE、抗リン脂質抗体症候群など)、血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)、溶血性尿毒症症候群(HUS)なども血小板破壊を引き起こします。
血小板分布の異常では、血小板が脾臓に溜まってしまい、循環血液中の血小板が減少します。肝硬変などによる脾腫が原因となります。また、播種性血管内凝固症候群(DIC)では、血小板が過剰に消費されることで減少します。
病態生理
血小板は、骨髄の巨核球という細胞から産生され、通常7〜10日程度の寿命を持っています。血小板の主な役割は一次止血(血管が傷ついた際に、傷口に集まって血小板血栓を形成し、出血を一時的に止めること)です。
血小板減少症では、この血小板数が減少することで止血機能が低下します。血小板数と出血リスクの関係は以下のようになります。
10万/μL以上では、通常は出血症状は見られません。ただし、手術や外傷時には出血リスクが高まる可能性があります。
5〜10万/μLでは、日常生活では問題ないことが多いですが、大きな外傷や手術では出血傾向が見られることがあります。
2〜5万/μLでは、軽度の外傷でも皮下出血(紫斑、点状出血)が出現しやすくなります。抜歯などの小手術でも出血に注意が必要です。
1〜2万/μLでは、明らかな出血傾向が見られます。自然出血(鼻出血、歯肉出血、月経過多、消化管出血など)のリスクが高まります。
1万/μL未満では、重篤な出血のリスクが非常に高くなります。特に頭蓋内出血は生命を脅かす最も危険な合併症です。
特発性血小板減少性紫斑病(ITP)の病態を例に取ると、自己抗体(主にIgG型抗体)が血小板膜の糖タンパク質(GPIIb/IIIaやGPIb/IXなど)に結合します。抗体が結合した血小板は、脾臓のマクロファージに捕捉され破壊されます。これにより血小板の寿命が通常の7〜10日から数時間〜数日に短縮されます。骨髄は代償的に血小板産生を増加させようとしますが、破壊のスピードに追いつかず、血小板減少が生じます。
薬剤性血小板減少症では、薬剤が抗原となって抗体が産生され、薬剤-抗体複合体が血小板に結合して破壊を引き起こします。薬剤の中止により通常は改善します。
血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)では、ADAMTS13という酵素の欠損または阻害により、異常に大きなvon Willebrand因子が血中に蓄積し、血小板が凝集して微小血栓を形成します。これにより血小板が消費され、同時に微小血管障害性溶血性貧血、腎障害、神経症状、発熱を呈する重篤な病態です。
症状・診断・治療
症状
血小板減少症の症状は、血小板数の程度によって異なります。
皮膚・粘膜の出血症状が最も特徴的です。点状出血(petechiae:針先で突いたような1〜2mm程度の赤い点状の出血斑)は、重力の影響を受けやすい下肢に多く見られます。紫斑(purpura:3〜10mm以上の青紫色の出血斑)は、軽い打撲でも出現し、大きさや色が様々です。出血斑は押しても消えないのが特徴です。
粘膜出血として、鼻出血、歯肉出血、口腔内出血がよく見られます。女性では月経過多が問題となることがあります。消化管出血では、吐血、下血、血便が出現し、重篤な場合は貧血を伴います。
重症の場合の症状として、肉眼的血尿、喀血、関節内出血などが見られることもあります。最も危険なのは頭蓋内出血で、頭痛、嘔吐、意識障害、痙攣、片麻痺などの神経症状が出現します。これは生命に関わる緊急事態です。
無症状のことも多く、健康診断や他の疾患の検査で偶然発見されることもあります。原因疾患によっては、特有の症状を伴うこともあります。例えば、ITPでは出血症状以外に特徴的な症状はありませんが、TTPでは発熱、意識障害、黄疸などを伴います。
診断
診断は、血液検査、骨髄検査、原因検索のための各種検査を組み合わせて行われます。
血液検査では、血小板数の減少を確認します。血液塗抹標本で血小板の形態や凝集の有無を観察します。凝固検査(PT、APTT)は通常正常ですが、DICなどでは異常を示します。網状赤血球の増加は溶血を示唆します。
骨髄検査は、血小板産生の状態を評価するために重要です。ITPでは巨核球(血小板を作る細胞)の数は正常または増加していますが、骨髄疾患では減少します。骨髄の形態や細胞の割合を詳しく評価します。
原因検索として、薬剤歴の詳細な聴取、ウイルス抗体検査(HIV、HCV、CMVなど)、自己抗体検査(抗核抗体、抗リン脂質抗体など)、腹部超音波検査(肝脾腫の有無)、CT検査などを行います。ITPの診断は除外診断で、他の原因を除外した上で診断されます。
重症度評価として、出血症状の程度、血小板数、患者さんの活動性や出血リスク因子(高齢、高血圧、抗凝固薬使用など)を総合的に評価します。
治療
治療は、原因、血小板数、出血症状の有無、患者さんの状態を総合的に評価して決定されます。
原因治療が最も重要です。薬剤性であれば原因薬剤の中止、感染症であれば抗生物質や抗ウイルス薬の投与、基礎疾患がある場合はその治療を行います。
ITPの治療では、血小板数や出血症状に応じて治療方針が決まります。血小板数が3万/μL以上で出血症状がない場合は、経過観察のみで治療しないこともあります。
第一選択は副腎皮質ステロイド(プレドニゾロン)です。血小板に対する自己抗体産生を抑制し、マクロファージによる血小板破壊を抑制します。通常、投与開始後数日〜2週間で血小板数が増加します。効果が得られたら徐々に減量しますが、減量に伴い再発することもあります。
ステロイドが効かない、または副作用で使用できない場合は、トロンボポエチン受容体作動薬(エルトロンボパグ、ロミプロスチム)を使用します。これらは骨髄での血小板産生を促進する薬剤です。
その他の治療として、免疫グロブリン大量療法(重症例や緊急時に速やかに血小板を増やす必要がある場合)、脾臓摘出術(薬物療法が無効な慢性ITPに対して)、免疫抑制薬(リツキシマブ、シクロスポリンなど)があります。
TTPの治療は緊急を要し、血漿交換療法が第一選択です。ステロイドや免疫抑制薬も併用されます。
DICの治療は、原因疾患の治療と、凝固因子や血小板の補充、ヘパリンなどの抗凝固療法を組み合わせて行います。
支持療法として、重症の出血時には血小板輸血を行いますが、ITPでは輸血した血小板もすぐに破壊されるため、効果は一時的です。頭蓋内出血などの生命に関わる出血時の緊急措置として行われます。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 出血リスク状態(血小板減少による)
- 皮膚統合性障害リスク状態(点状出血、紫斑)
- 活動耐性低下(出血への恐怖、安静の必要性)
- 不安(出血への恐怖、疾患の予後)
- 知識不足(疾患管理、出血予防に関する)
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚-健康管理パターン
患者さんが自身の病態をどのように理解しているか、出血リスクについてどの程度認識しているかをアセスメントします。慢性化している場合は、長期的な疾患管理の必要性や、治療へのアドヒアランスを評価します。
栄養-代謝パターン
歯肉出血や口腔内出血により、食事摂取が困難になることがあります。消化管出血による貧血の有無、ステロイド治療による食欲亢進や体重増加、高血糖などにも注意します。皮膚の出血斑の観察も重要です。
排泄パターン
血尿、下血、黒色便などの出血徴候を観察します。女性では月経過多の有無と程度を確認します。便秘は排便時のいきみで出血を誘発する可能性があるため、予防が重要です。
活動-運動パターン
出血リスクのため活動が制限されることがあります。特に重症例では転倒や打撲を避ける必要があります。一方で、過度の安静は深部静脈血栓症のリスクを高めるため、血小板数と出血症状に応じた適切な活動レベルの設定が重要です。
睡眠-休息パターン
不安や入院環境により睡眠が妨げられることがあります。また、ステロイド治療による不眠にも注意が必要です。
認知-知覚パターン
頭蓋内出血の徴候(頭痛、嘔吐、意識障害、視覚障害など)を見逃さないことが最も重要です。また、出血部位の疼痛や腹痛(消化管出血を示唆)の有無を評価します。
自己知覚-自己概念パターン
特に若年者や女性では、皮膚の紫斑による外見の変化がボディイメージの変化や自尊心の低下につながることがあります。ステロイド治療による顔貌の変化(満月様顔貌)も同様です。
役割-関係パターン
入院や活動制限により、仕事や家庭での役割が変化します。特に慢性化した場合は、長期的な影響を考慮する必要があります。
ストレス-コーピングパターン
出血への恐怖、疾患の予後への不安、治療の副作用などのストレスにどう対処しているかを評価します。
ヘンダーソン14基本的ニード
正常に呼吸する
喀血や肺出血の有無を観察します。貧血が進行している場合は、呼吸困難や頻呼吸が見られることもあります。
適切に飲食する
口腔内出血や歯肉出血により食事が困難な場合は、柔らかい食事や刺激の少ない食事を提供します。消化管出血がある場合は、絶食が必要になることもあります。
正常に排泄する
血尿、下血、黒色便などの出血徴候を注意深く観察します。月経過多がある場合は、経血量や貧血症状を評価します。
身体の位置を動かし、またよい姿勢を保持する
転倒や打撲を避けるため、環境整備や移動時の見守りが必要です。ただし、過度の安静は避けます。
睡眠と休息をとる
不安や環境、ステロイドの副作用による不眠に対して、環境調整や必要に応じた睡眠薬の使用を検討します。
適当な衣類を選び、着たり脱いだりする
きつい衣類や圧迫する下着は皮下出血を引き起こす可能性があるため、ゆったりとした衣類を推奨します。
体温を正常範囲内に保つ
感染症による発熱の有無を観察します。TTPでは発熱が見られることがあります。
身体を清潔に保ち、身だしなみを整える
歯磨きは柔らかい歯ブラシを使用し、優しく行うよう指導します。ひげ剃りは電気シェーバーを推奨します。入浴時は転倒に注意し、身体を強くこすらないようにします。
危険を回避する
出血予防が最も重要です。転倒・外傷予防、鋭利なものの取り扱い注意、抗凝固薬やNSAIDsの使用制限などを指導します。
他者とコミュニケーションをもつ
患者さんや家族の不安を傾聴し、疾患や治療について十分に説明します。
自分の信仰に従って礼拝する
重篤な出血のリスクや予後への不安に対するスピリチュアルなサポートも必要な場合があります。
達成感をもたらすような仕事をする
活動制限の中でも、可能な範囲での役割の継続を支援します。
遊び、あるいはさまざまな種類のレクリエーションに参加する
安全な範囲での趣味や楽しみの継続を支援し、QOLの維持を図ります。
学習する
疾患や治療、出血予防、緊急時の対応などについて、患者さんが十分に理解できるよう教育的支援を行います。
看護計画・介入の内容
- 出血徴候の観察:皮膚(点状出血、紫斑、斑状出血)、粘膜(鼻出血、歯肉出血、口腔内出血)、尿(血尿)、便(下血、黒色便)、月経(過多)などを注意深く観察します。新たな出血斑の出現や既存の出血斑の拡大をチェックします。
- 頭蓋内出血の早期発見:頭痛、嘔吐、意識レベルの変化、見当識障害、瞳孔不同、視覚障害、痙攣、片麻痺などの神経症状を見逃さないよう、定期的に神経学的観察を行います。これらの症状が出現した場合は直ちに医師に報告します。
- バイタルサインの観察:出血による循環血液量減少を早期に発見するため、血圧、脈拍、呼吸数を定期的に測定します。頻脈、血圧低下、蒼白、冷汗などの出血性ショックの徴候に注意します。
- 血小板数のモニタリング:定期的な血液検査の結果を確認し、血小板数の推移を把握します。治療効果の評価にも重要です。
- 外傷・打撲の予防:ベッド柵の使用、床の整理整頓、滑り止めマットの使用、十分な照明の確保などの環境整備を行います。移動時は見守りや介助を提供します。
- 出血予防の生活指導:
- 歯磨きは柔らかい歯ブラシで優しく行う
- デンタルフロスは慎重に使用する
- 鼻をかむ時は優しく行う
- ひげ剃りは電気シェーバーを使用する
- きつい衣類や下着を避ける
- 便秘を予防する(いきみによる出血を避けるため)
- 激しい運動やコンタクトスポーツを避ける
- 禁止事項の説明:
- アスピリンやNSAIDsなどの抗血小板作用のある薬剤の使用禁止
- 筋肉注射の制限(皮下出血のリスクが高い)
- 抗凝固薬の使用制限
- アルコールの過剰摂取の制限
- 安全な日常生活動作の指導:転倒や外傷のリスクを減らしながら、可能な範囲で活動を維持します。血小板数2万/μL未満の重症例では、より厳重な活動制限が必要です。
- 薬物療法の管理:ステロイドの副作用(感染症、高血糖、消化性潰瘍、骨粗鬆症、精神症状など)の観察と予防を行います。内服のアドヒアランスを確認し、自己判断での中止を防ぎます。
- 血小板輸血の管理:重症の出血時には血小板輸血が行われます。輸血前の患者確認、輸血中のバイタルサイン測定、輸血副作用(発熱、蕁麻疹、アナフィラキシーなど)の観察を行います。
- 心理的サポート:出血への恐怖、疾患の予後への不安、長期治療への負担などに対して、患者さんや家族の思いを傾聴します。正しい情報を提供し、不安の軽減を図ります。
- 退院指導:出血予防の生活指導、緊急時の対応(重大な出血や頭蓋内出血が疑われる症状が出現した場合は直ちに受診)、定期的な受診の重要性、内服管理などを説明します。
よくある疑問・Q&A
Q: 血小板減少症の患者さんに筋肉注射や静脈注射をしても大丈夫ですか?
A: 静脈注射や静脈採血は可能ですが、穿刺後の圧迫止血を通常より長めに(5〜10分程度)しっかりと行うことが重要です。細い針を使用し、一発で成功させるよう心がけましょう。一方、筋肉注射は原則避けるべきです。筋肉内出血のリスクが高く、血腫を形成する可能性があります。どうしても必要な場合は、血小板数を確認し、医師と相談の上、最も出血リスクの低い部位を選択し、穿刺後は十分に圧迫します。可能であれば、皮下注射や静脈注射に変更できないか検討しましょう。
Q: 血小板数が何万/μL以下になったら入院が必要ですか?
A: 一概には言えませんが、一般的には血小板数が2万/μL未満、または血小板数が3〜5万/μLでも出血症状が強い場合は入院を検討します。特に、粘膜出血(鼻出血、歯肉出血など)が頻繁に見られる、消化管出血や血尿がある、高齢者や高血圧などの出血リスク因子がある場合は、より慎重な判断が必要です。また、血小板数が急速に減少している場合や、初めて診断された場合も、経過観察のために入院することがあります。頭蓋内出血は血小板数1万/μL未満で特にリスクが高まるため、この値を下回る場合は入院管理が強く推奨されます。
Q: 点状出血と紫斑の違いは何ですか?また、観察時のポイントは?
A: 点状出血(petechiae)は1〜2mm程度の針先で突いたような小さな赤い点状の出血斑で、紫斑(purpura)は3〜10mm以上の青紫色の出血斑です。どちらも押しても消えないのが特徴で、これにより血管拡張による発赤(押すと消える)と鑑別できます。
観察のポイントとしては、まず分布を確認します。点状出血は重力の影響を受けやすく、下肢や足背に多く見られます。次に新旧の判別が重要で、新しい出血斑は鮮紅色、古いものは青紫色から黄褐色へと変化します。毎日同じ時間に観察し、新たな出血斑の出現や既存の出血斑の拡大をチェックします。出血斑の写真を撮っておくと、経時的な変化を評価しやすくなります。また、出血斑の大きさや数の増加は病状の悪化を示唆するため、医師に速やかに報告します。粘膜(口腔内、眼球結膜)の出血斑も見逃さないよう注意しましょう。
Q: 患者さんから「いつになったら普通の生活に戻れますか?」と聞かれたら、どう答えたらよいですか?
A: これは患者さんが最も気になる質問の一つです。答えは原因や重症度、治療への反応によって大きく異なります。
急性ITP(特に小児)の場合、多くは数週間〜数ヶ月で自然治癒または治療により改善し、普通の生活に戻れることを伝えられます。
慢性ITP(成人に多い)の場合は、「血小板数が安定し、出血症状がコントロールされれば、ほぼ普通の生活が送れます。ただし、定期的な通院や内服治療の継続が必要で、激しいスポーツや出血リスクの高い活動には注意が必要です」と説明します。多くの患者さんは、治療により血小板数が安定すれば、仕事や日常生活を問題なく送れるようになります。
薬剤性の場合は、原因薬剤の中止により通常は数日〜数週間で改善することを伝えます。
重要なのは、「普通の生活」の定義を患者さんと共有することです。「どんな生活に戻りたいですか?」と尋ね、具体的な目標(仕事復帰、旅行、スポーツなど)を一緒に考えます。そして、血小板数や治療の進行状況に応じて、「今はここまでできます」「もう少し血小板が増えたらこれもできます」と段階的な目標を示すことで、希望を持って治療に取り組めるよう支援します。「完全に元通り」を約束することはできませんが、「疾患と上手に付き合いながら、充実した生活を送ることは十分可能です」というメッセージを伝えることが大切です。
まとめ
血小板減少症は、血液中の血小板数が減少し、出血傾向を示す病態です。原因は多岐にわたり、血小板産生の低下、破壊の亢進、分布の異常に大きく分類されます。最も重要なのは原因の特定と適切な治療です。
看護の要点は、出血徴候の早期発見、頭蓋内出血などの重篤な合併症の予防、外傷・打撲の予防、そして患者・家族への教育的支援です。特に血小板数が2万/μL未満の重症例では、わずかな外傷でも重大な出血につながる可能性があるため、細心の注意が必要です。
観察のポイントとして、点状出血や紫斑の分布・程度・新旧の評価、粘膜出血の有無、血尿や下血などの内出血の徴候、そして最も重要な頭蓋内出血を示唆する神経症状を見逃さないことが求められます。これらの観察は定期的かつ系統的に行い、異常があれば速やかに医師に報告する必要があります。
治療は原因により異なりますが、ITPではステロイド療法やトロンボポエチン受容体作動薬が主体となります。治療により多くの患者さんで血小板数の改善が得られ、通常の社会生活を送ることが可能になります。ただし、慢性化する例もあり、長期的な疾患管理が必要となることもあります。
実習では、出血徴候を見逃さないための系統的な観察、患者さんの安全を守るための環境整備、そして出血への恐怖や不安に寄り添う姿勢を大切にしましょう。血小板減少症の患者さんは、「いつ出血するかわからない」という恐怖を常に抱えています。その不安を理解し、適切な情報提供と心理的サポートを提供することで、患者さんが安心して治療に取り組めるよう支援することが看護師の重要な役割です。
また、日常生活での出血予防の具体的な方法を患者さんと一緒に考え、実践可能な形で提案することも大切です。「何もできない」という制限ではなく、「こうすれば安全にできる」という前向きな指導を心がけましょう。患者さんが疾患と上手に付き合いながら、自分らしい生活を送れるよう、長期的な視点で支援していくことが求められます。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
・正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません


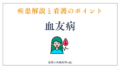
コメント