疾患概要
定義
胃潰瘍・十二指腸潰瘍は、胃液(胃酸とペプシン)により胃や十二指腸の粘膜が傷つき、粘膜下層以深に達する深い欠損ができた状態です。両者を合わせて消化性潰瘍と呼びます。粘膜までの浅い欠損はびらんといい、潰瘍とは区別されます。潰瘍は粘膜筋板を超えて粘膜下層まで達しており、治癒しても瘢痕が残ります。
胃潰瘍と十二指腸潰瘍は、発生メカニズムや症状に違いがあります。胃潰瘍は胃の出口付近(幽門前庭部)や胃体部に多く、十二指腸潰瘍は十二指腸球部に好発します。
疫学
日本における消化性潰瘍の患者数は、近年減少傾向にあります。これは、ヘリコバクター・ピロリ菌の感染率低下と除菌治療の普及、胃酸分泌抑制薬の発達によるものです。しかし、高齢者における非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)による潰瘍は増加傾向にあります。
十二指腸潰瘍は20〜40歳代の若年者に多く、男性に多い傾向があります。一方、胃潰瘍は50歳代以降に多く、男女差は比較的少ないです。十二指腸潰瘍の方が胃潰瘍より若年発症が多いのが特徴です。
原因
消化性潰瘍の発生には、攻撃因子(胃酸、ペプシン)と防御因子(粘液、粘膜血流、粘膜の修復能力)のバランスが崩れることが関与します。攻撃因子が強まったり、防御因子が弱まったりすると、潰瘍が形成されます。
ヘリコバクター・ピロリ菌感染
消化性潰瘍の最大の原因です。胃潰瘍患者の約70%、十二指腸潰瘍患者の約90〜95%がピロリ菌に感染しています。ピロリ菌は胃粘膜に炎症を起こし、粘膜の防御機能を低下させます。また、十二指腸では胃酸分泌を増加させる働きもあります。ピロリ菌を除菌すると、潰瘍の再発率が劇的に低下します。
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)
アスピリン、イブプロフェン、ロキソプロフェンなどのNSAIDsは、胃粘膜の保護に重要なプロスタグランジンの合成を抑制し、粘膜の防御機能を低下させます。高齢者、長期服用者、高用量使用者でリスクが高まります。近年、高齢者の増加とNSAIDsの使用増加に伴い、NSAIDs潰瘍が問題となっています。
ストレス
重度の外傷、熱傷、手術、脳血管障害、重症感染症などの強いストレスにより、急性潰瘍(ストレス潰瘍)が形成されることがあります。これは、ストレスにより胃粘膜の血流が低下し、防御機能が低下するためです。
その他
喫煙は胃粘膜の血流を低下させ、潰瘍の治癒を遅らせます。過度のアルコール摂取も胃粘膜を傷つけます。また、胃酸分泌を促進するガストリン産生腫瘍(ゾリンジャー・エリソン症候群)などの稀な疾患もあります。
病態生理
消化性潰瘍の病態の本質は、攻撃因子と防御因子のバランスの崩れです。
胃は、食物を消化するために強力な胃酸とペプシンを分泌します。胃酸は非常に強い酸性(pH1〜2程度)で、タンパク質を分解するペプシンも含まれています。これらは本来、自分の胃を消化してしまうほど強力です。しかし、正常な状態では、粘液による保護、豊富な粘膜血流による栄養供給、傷ついた粘膜の迅速な修復により、胃は自己消化から守られています。
十二指腸潰瘍の病態
十二指腸潰瘍では、胃酸の過剰分泌が主な原因です。ピロリ菌感染により、胃の出口付近(幽門前庭部)の炎症が起こると、胃酸分泌を抑制するホルモンの分泌が低下し、胃酸分泌が増加します。過剰な胃酸が十二指腸に流入し、十二指腸粘膜を傷つけます。十二指腸は胃ほど強力な防御機能を持たないため、胃酸により容易に潰瘍が形成されます。
胃潰瘍の病態
胃潰瘍では、胃酸の過剰分泌よりも、粘膜の防御機能の低下が主な原因です。ピロリ菌感染により胃粘膜に炎症が起こると、粘液分泌が低下し、粘膜血流が悪化し、粘膜の修復能力が低下します。その結果、通常の胃酸でも粘膜が傷つきやすくなり、潰瘍が形成されます。NSAIDsによる潰瘍も、粘膜の防御機能低下が主な原因です。
合併症
潰瘍が深くなると、以下の重大な合併症を起こすことがあります。
出血: 潰瘍底の血管が破れると、消化管出血を起こします。吐血や下血(黒色便)がみられ、大量出血ではショック状態となります。
穿孔: 潰瘍が胃壁や十二指腸壁を貫通すると、消化液が腹腔内に漏れ出し、急性腹膜炎を起こします。激しい腹痛、筋性防御、ショック症状を呈し、緊急手術が必要です。
狭窄: 潰瘍が繰り返し治癒する過程で瘢痕化し、幽門部や十二指腸が狭くなると、食物の通過障害を起こします。悪心、嘔吐、体重減少などの症状が出現します。
症状・診断・治療
症状
消化性潰瘍の症状は、腹痛が最も特徴的です。しかし、胃潰瘍と十二指腸潰瘍では、痛みの特徴が異なります。
十二指腸潰瘍の症状
空腹時痛が特徴的です。空腹時や夜間に上腹部痛(心窩部痛)が出現し、食事を摂ると痛みが軽減します。これは、空腹時に胃酸が十二指腸に流入し、潰瘍を刺激するためです。食事により胃酸が中和されると、痛みが和らぎます。また、季節性があり、春や秋に症状が悪化しやすい傾向があります。
胃潰瘍の症状
食後痛がみられることが多いです。食事を摂ると上腹部痛が出現したり、増悪したりします。これは、食事により胃酸分泌が刺激され、潰瘍を刺激するためです。ただし、胃潰瘍でも空腹時痛を訴えることもあり、症状だけで区別することは困難です。
共通する症状
腹痛の他に、悪心、嘔吐、食欲不振、胸やけ、腹部膨満感などがみられます。無症状の場合もあり、特に高齢者やNSAIDs使用者では、症状が乏しいまま突然出血や穿孔を起こすことがあり、注意が必要です。
合併症の症状
出血: 吐血(コーヒー残渣様、または鮮血)、下血(黒色便、タール便)、貧血症状(動悸、息切れ、めまい)が出現します。大量出血では、ショック症状(血圧低下、頻脈、冷汗、意識障害)を呈します。
穿孔: 突然の激しい上腹部痛で発症します。痛みは持続的で、徐々に腹部全体に広がります。腹部は板のように硬くなり(板状硬)、筋性防御がみられます。発熱、頻脈、血圧低下などのショック症状も出現します。
狭窄: 悪心、嘔吐(特に食後)、腹部膨満感、体重減少がみられます。
診断
上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)
消化性潰瘍の診断に最も有用な検査です。潰瘍を直接観察でき、部位、大きさ、深さ、活動性、出血の有無などを評価できます。また、組織を採取して、ピロリ菌の感染の有無を調べたり、悪性腫瘍を除外したりすることもできます。特に胃潰瘍では、胃がんとの鑑別が重要であり、必ず生検を行います。
上部消化管造影検査(バリウム検査)
バリウムを飲んでX線撮影を行い、潰瘍による粘膜の陥凹(ニッシェ)を確認します。しかし、内視鏡検査に比べて診断精度が劣るため、現在は主に内視鏡検査が行われます。
ヘリコバクター・ピロリ菌検査
ピロリ菌感染の有無を調べます。内視鏡検査時に採取した組織で調べる方法(迅速ウレアーゼ試験、培養、組織検査)と、内視鏡を使わない方法(尿素呼気試験、血清抗体、便中抗原)があります。
血液検査
貧血の有無、炎症反応などを評価します。出血性潰瘍では、ヘモグロビン値やヘマトクリット値の低下がみられます。
治療
消化性潰瘍の治療は、薬物療法が中心です。多くの潰瘍は、適切な薬物療法により治癒します。
薬物療法
プロトンポンプ阻害薬(PPI): オメプラゾール、ランソプラゾールなど。胃酸分泌を強力に抑制し、潰瘍の治癒を促進します。現在、消化性潰瘍治療の第一選択薬です。
H2受容体拮抗薬: ファモチジン、ラニチジンなど。胃酸分泌を抑制しますが、PPIほど強力ではありません。
防御因子増強薬: レバミピド、テプレノンなど。胃粘膜の防御機能を高め、粘膜の修復を促進します。
制酸薬: 胃酸を中和します。症状の緩和に用いられます。
ヘリコバクター・ピロリ菌除菌療法
ピロリ菌感染が確認された場合、除菌療法を行います。PPI、アモキシシリン、クラリスロマイシンの3剤を1週間服用します。除菌成功率は約70〜90%で、失敗した場合は二次除菌を行います。除菌により、潰瘍の再発率が劇的に低下します(年間再発率:除菌前60〜80%→除菌後0〜5%)。
生活指導
禁煙、NSAIDsの中止または変更、規則正しい食事、ストレス管理、過度のアルコール摂取を避けるなどの生活習慣の改善が重要です。
内視鏡的止血術
出血性潰瘍では、内視鏡下に止血術を行います。出血部位をクリップで止める、焼灼する、薬剤を注入するなどの方法があります。
手術療法
現在では、薬物療法の進歩により、手術が必要となることは稀です。しかし、以下の場合は手術を検討します。
- 内科的治療で改善しない難治性潰瘍
- 繰り返す大量出血で、内視鏡的止血が困難な場合
- 穿孔
- 幽門狭窄
手術方法は、潰瘍の切除、迷走神経切断術、胃切除術などがあります。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 急性疼痛
- 栄養摂取消費バランス異常
- 悪心
- 不安
- 出血リスク状態
- 知識不足(疾患管理)
ゴードン機能的健康パターン
栄養・代謝パターン
消化性潰瘍患者さんは、腹痛や悪心により食事摂取が困難になることがあります。特に胃潰瘍では、食後に痛みが増悪するため、食事を避ける傾向があります。食事摂取量、体重変化を評価し、必要な栄養が確保できるよう支援します。
かつては、潰瘍食として牛乳やおかゆなどの消化のよい食事が推奨されていましたが、現在では、特別な食事制限は不要とされています。ただし、香辛料の強い食事、アルコール、カフェイン、炭酸飲料など、胃を刺激する食品は控えるよう指導します。規則正しい食事、ゆっくりよく噛んで食べることが大切です。
睡眠・休息パターン
十二指腸潰瘍では、夜間の空腹時痛により睡眠が妨げられることがあります。就寝前の軽食や、医師の指示による胃酸分泌抑制薬の服用により、夜間痛を軽減できます。
認知・知覚パターン
腹痛は、患者さんの主要な訴えです。痛みの部位、性質、程度、増悪・軽減因子を詳細に聴取します。食事との関連(空腹時痛、食後痛)、時間帯(夜間痛)なども確認します。痛みのパターンから、胃潰瘍か十二指腸潰瘍かを推測することもできます。
ストレス・コーピングパターン
ストレスは消化性潰瘍の増悪因子です。患者さんの生活背景、ストレスの原因、対処方法を評価します。仕事上のストレス、人間関係の悩み、経済的問題などが関与していることもあります。ストレスマネジメントの方法を一緒に考え、必要に応じて心理的サポートを提供します。
ヘンダーソン14基本的ニード
正常に飲食する
腹痛や悪心により、食事摂取が困難になることがあります。少量頻回の食事、嗜好に合わせた食事内容の調整により、必要な栄養を確保します。また、過度な食事制限は不要であることを説明し、バランスの取れた食事を摂るよう指導します。
正常に排泄する
出血性潰瘍では、黒色便(タール便)がみられます。便の色と性状を観察し、消化管出血の有無を評価します。患者さんにも便の色の変化に注意するよう説明します。
働くこと、達成感を得ること
消化性潰瘍は、仕事やストレスとの関連が強い疾患です。過労やストレスが症状を悪化させることを説明し、仕事と休息のバランスを考えるよう支援します。必要に応じて、職場環境の調整や、休職についても相談に乗ります。
自分の感情、欲求、恐怖、あるいは気分を表現してコミュニケーションをとる
患者さんは、痛みへの不安、治療期間の長さへの焦り、再発への恐れなど、さまざまな感情を抱えています。これらの感情を表出できる環境を整え、傾聴する姿勢が大切です。
看護計画・介入の内容
- 疼痛のアセスメント: 痛みの部位、性質、程度、食事との関連、時間帯を詳細に聴取し、記録する
- バイタルサインの監視: 体温、血圧、脈拍を定期的に測定し、出血やショックの徴候を早期発見する
- 腹部症状の観察: 腹痛の程度、悪心・嘔吐の有無、腹部膨満、筋性防御(穿孔の徴候)を観察する
- 出血徴候の観察: 吐血、下血、黒色便、貧血症状(動悸、息切れ、めまい)を観察する。便の色を確認する
- 薬物療法の支援: 処方された薬を確実に服用できるよう支援する。PPIは食前に服用することが効果的であることを説明する
- ピロリ菌除菌療法の指導: 除菌療法の重要性を説明し、3剤を1週間確実に服用するよう指導する。途中で中断すると除菌に失敗することを強調する
- 食事指導: 規則正しい食事、よく噛んで食べる、胃を刺激する食品(香辛料、アルコール、カフェインなど)を控えることを指導する。特別な食事制限は不要であることも伝える
- 禁煙指導: 喫煙が潰瘍の治癒を遅らせ、再発リスクを高めることを説明し、禁煙を支援する
- ストレスマネジメント: ストレスが潰瘍の増悪因子であることを説明し、リラクゼーション法、趣味の活用、休息の取り方などを一緒に考える
- NSAIDsの使用について: NSAIDsが潰瘍の原因となることを説明し、必要な場合は医師に相談するよう指導する。市販の鎮痛薬にもNSAIDsが含まれることを伝える
- 症状出現時の対応: 激しい腹痛、吐血、黒色便、冷汗、めまいなどの症状が出現した場合は、すぐに医療機関を受診するよう指導する
- 定期受診の重要性: 症状が改善しても自己判断で薬を中止せず、医師の指示に従うこと、定期的な受診により潰瘍の治癒を確認し、再発を予防することの重要性を説明する
- 患者・家族教育: 疾患の理解促進、薬の正しい使用方法、生活習慣の改善、再発予防の方法について説明する
よくある疑問・Q&A
Q: 胃潰瘍と十二指腸潰瘍の症状の違いは何ですか? 自分でどちらか分かりますか?
A: 一般的に、十二指腸潰瘍は空腹時痛、胃潰瘍は食後痛が特徴的とされています。十二指腸潰瘍では、空腹時や夜間に上腹部痛が出現し、食事を摂ると痛みが軽減します。胃潰瘍では、食事を摂ると痛みが出現したり増悪したりすることが多いです。ただし、これはあくまで典型的なパターンであり、個人差があります。胃潰瘍でも空腹時痛を訴えることもありますし、症状だけでは確実に区別することはできません。また、無症状の潰瘍も存在します。症状から自己判断せず、必ず医療機関を受診し、胃カメラによる確定診断を受けることが重要です。特に胃潰瘍では、胃がんとの鑑別が必要なため、内視鏡検査と生検が不可欠です。
Q: ピロリ菌を除菌すると、潰瘍は再発しなくなるのですか?
A: はい、ピロリ菌の除菌に成功すると、潰瘍の再発率は劇的に低下します。除菌前の年間再発率は60〜80%と非常に高いのですが、除菌後は0〜5%程度に減少します。これは、ピロリ菌が消化性潰瘍の最大の原因であるためです。除菌療法は、PPI、アモキシシリン、クラリスロマイシンの3剤を1週間服用する方法で、成功率は70〜90%です。除菌が成功したかどうかは、除菌治療終了後、少なくとも4週間以上経過してから判定検査を行います。もし除菌に失敗した場合は、薬剤を変更して二次除菌を行います。ただし、除菌後も、NSAIDsの使用、喫煙、ストレスなどにより潰瘍が発生する可能性はあるため、生活習慣の改善も重要です。
Q: 消化性潰瘍の治療中、食事で気をつけることはありますか? 特別な食事制限が必要ですか?
A: 以前は、潰瘍食として牛乳やおかゆなどの消化のよい食事が推奨されていましたが、現在の考え方は変わってきています。特別な厳しい食事制限は不要とされています。ただし、以下の点に注意することが推奨されます。まず、規則正しい食事を心がけ、1日3食をほぼ同じ時間に摂ります。よく噛んでゆっくり食べることも大切です。早食いは胃に負担をかけます。また、胃を刺激する食品、具体的には、香辛料の強い食事、熱すぎる・冷たすぎる食事、アルコール、カフェイン、炭酸飲料などは控えめにします。脂肪の多い食事も消化に時間がかかるため、控えめにした方がよいでしょう。一方、バランスの取れた多様な食事を摂ることは、栄養状態の維持と粘膜の修復に重要です。過度な食事制限はかえってQOLを低下させるため、医師や栄養士と相談しながら、自分に合った食事を見つけることが大切です。
Q: 消化性潰瘍の薬は、いつまで飲み続ければよいのですか? 症状がなくなったらやめてもいいですか?
A: 症状が改善しても、自己判断で薬を中止してはいけません。潰瘍の治癒には時間がかかり、症状が消失してもまだ潰瘍が完全に治っていないことがあります。十二指腸潰瘍では通常4〜6週間、胃潰瘍では6〜8週間の治療が必要です。医師の指示に従い、処方された期間はきちんと服薬を続けることが重要です。途中で薬を中止すると、潰瘍が再発したり、治癒が遅れたりします。ピロリ菌の除菌療法では、3剤を1週間確実に服用することが非常に重要で、途中で中断すると除菌に失敗し、薬剤耐性菌が出現する可能性があります。治療終了後は、内視鏡検査により潰瘍の治癒を確認します。その後、ピロリ菌を除菌していれば、多くの場合、薬の継続は不要です。ただし、NSAIDsを継続使用する必要がある場合などは、胃酸分泌抑制薬を継続することもあります。定期的に医師の診察を受け、相談しながら治療を進めることが大切です。
Q: 消化性潰瘍の穿孔とはどのような状態ですか? なぜ緊急手術が必要なのですか?
A: 穿孔とは、潰瘍が深くなって胃壁や十二指腸壁を貫通し、穴が開いた状態です。穴が開くと、胃や十二指腸の内容物(食物、胃酸、消化酵素、細菌など)が腹腔内に漏れ出します。これにより、急性腹膜炎という非常に重篤な状態になります。症状としては、突然の激しい上腹部痛で発症し、痛みは持続的で、徐々に腹部全体に広がります。腹部は板のように硬くなり(板状硬)、筋性防御がみられます。発熱、頻脈、血圧低下などのショック症状も出現します。腹膜炎が進行すると、敗血症や多臓器不全に至り、生命に関わります。そのため、緊急手術が必要です。手術では、穿孔部を縫合閉鎖したり、場合によっては潰瘍部を切除したりします。また、腹腔内を洗浄し、ドレーンを留置します。穿孔は消化性潰瘍の重大な合併症であり、予防のためには、適切な薬物療法の継続、定期受診、危険な兆候(激しい腹痛)が出現した場合の早期受診が重要です。
まとめ
胃潰瘍・十二指腸潰瘍は、胃液により胃や十二指腸の粘膜が深く傷つく疾患で、両者を合わせて消化性潰瘍と呼びます。病態の本質は、攻撃因子(胃酸、ペプシン)と防御因子(粘液、粘膜血流、修復能力)のバランスの崩れです。
最大の原因はヘリコバクター・ピロリ菌感染で、胃潰瘍患者の約70%、十二指腸潰瘍患者の約90〜95%が感染しています。その他、NSAIDs、ストレス、喫煙、過度のアルコール摂取なども原因となります。
典型的な症状として、十二指腸潰瘍では空腹時痛、胃潰瘍では食後痛がみられますが、個人差があり、症状だけでは確実な診断はできません。診断には胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)が最も有用です。
治療は薬物療法が中心で、プロトンポンプ阻害薬(PPI)による胃酸分泌抑制が第一選択です。ピロリ菌感染が確認された場合は、除菌療法を行います。除菌に成功すると、潰瘍の年間再発率が60〜80%から0〜5%程度へ劇的に低下します。
重大な合併症として、出血、穿孔、狭窄があります。特に穿孔は急性腹膜炎を起こし、緊急手術が必要となる生命に関わる状態です。
看護のポイントは、疼痛のアセスメント(痛みの部位、性質、食事との関連)、出血徴候の観察(吐血、黒色便、貧血症状)、穿孔の早期発見(激しい腹痛、筋性防御)、薬物療法の支援、生活指導です。
特に重要なのは、ピロリ菌除菌療法の確実な実施です。3剤を1週間確実に服用することが除菌成功の鍵であり、途中で中断すると除菌に失敗することを患者さんに理解してもらう必要があります。
また、生活習慣の改善も重要です。禁煙、NSAIDsの適切な使用、規則正しい食事、ストレスマネジメントなどを指導します。現在では、特別な厳しい食事制限は不要とされていますが、胃を刺激する食品(香辛料、アルコール、カフェインなど)は控えめにするよう助言します。
実習では、患者さんの腹痛の特徴を詳細に聴取し、胃潰瘍と十二指腸潰瘍の違いを理解する力を養いましょう。また、便の色の観察により消化管出血を早期発見する重要性を学んでください。さらに、ピロリ菌除菌の意義と方法について、患者さんに分かりやすく説明できるよう知識を深めましょう。
消化性潰瘍は、適切な治療により治癒が期待でき、ピロリ菌除菌により再発も予防できる疾患です。患者さんが安心して治療を継続し、生活習慣を改善できるよう、根拠に基づいた看護を実践していきましょう。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
・正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません
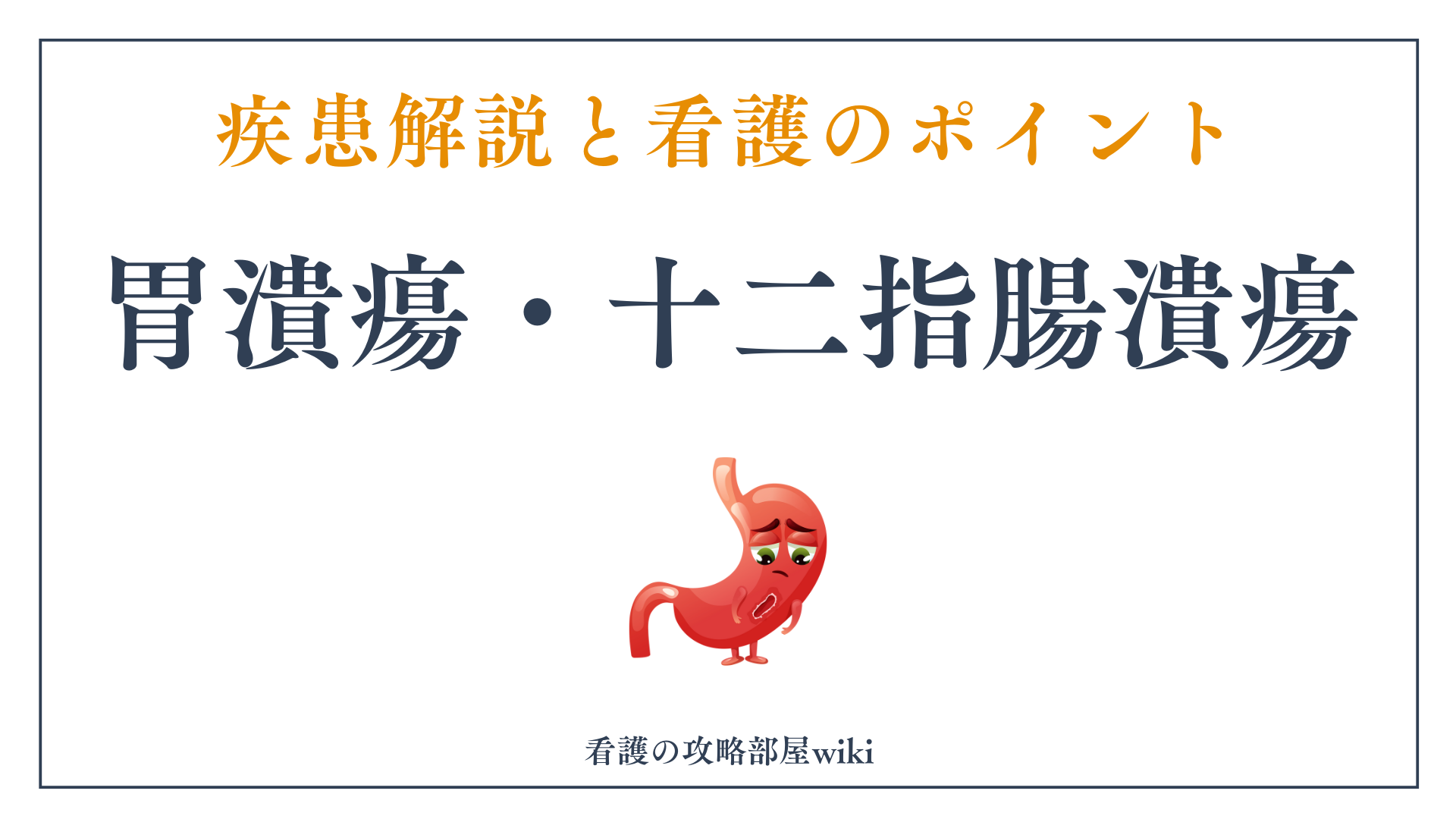
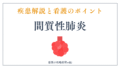

コメント