疾患概要
定義
RSウイルス感染症(Respiratory Syncytial Virus:RSV感染症)は、RSウイルスによる急性呼吸器感染症です。乳幼児の細気管支炎・肺炎の主要な原因であり、特に生後6ヶ月未満の乳児では重症化しやすい疾患です。年長児や成人では軽症の上気道炎として経過することが多いですが、高齢者や基礎疾患のある患者では重篤化することがあります。強い感染力を持ち、接触感染や飛沫感染により急速に拡散するため、医療機関や保育施設での院内感染対策が重要な疾患です。
疫学
RSウイルス感染症は乳幼児において最も重要な呼吸器感染症の一つです。2歳までにほぼ100%の小児が感染し、そのうち約25-40%が下気道感染(細気管支炎・肺炎)を発症します。入院を要する乳幼児呼吸器感染症の約50-80%を占めます。季節性があり、日本では秋から春(9月-3月)にかけて流行し、特に11月-1月がピークとなります。男児の方が重症化しやすく、早産児、先天性心疾患、慢性肺疾患、免疫不全、生後6ヶ月未満では特に重症化リスクが高くなります。再感染も頻繁に起こりますが、初回感染時が最も重症となります。
原因
RSウイルスはRNAウイルス(パラミクソウイルス科)で、A型とB型に大別されます。A型の方が重症化しやすいとされています。感染経路は接触感染(汚染された手指、玩具、タオルなど)と飛沫感染が主で、空気感染は起こりません。ウイルスは環境中で数時間生存し、手指では約30分間感染力を保持します。潜伏期間は2-8日(平均4-6日)で、排ウイルス期間は通常1-3週間ですが、乳児や免疫不全者では数ヶ月間持続することがあります。再感染は生涯にわたって起こりますが、年齢とともに症状は軽症化します。
病態生理
RSウイルスは気道上皮細胞に感染し、細胞融合を引き起こして多核巨細胞を形成します。下気道感染では細気管支(直径2mm以下)の炎症と閉塞が特徴的で、細気管支炎の病態となります。炎症により気道粘膜が腫脹し、粘液分泌が亢進して気道内腔が狭小化します。換気血流比不均等により低酸素血症が生じ、呼吸困難、多呼吸、陥没呼吸が出現します。免疫応答によりTh2型反応が優位となり、好酸球浸潤やIgE上昇を認めることがあります。重症例では無気肺、気胸を合併し、呼吸不全に至ることがあります。
症状・診断・治療
症状
初期症状は鼻汁、咳嗽、くしゃみ、微熱などの上気道炎症状から始まります。下気道感染に進展すると多呼吸、呼吸困難、陥没呼吸、喘鳴が出現します。乳児では特徴的症状として哺乳困難、不機嫌、睡眠障害、無呼吸発作を認めます。身体所見では努力呼吸、鼻翼呼吸、チアノーゼ、聴診での fine crackles、expiratory wheezeを聴取します。重症例では意識レベル低下、脱水、哺乳量減少が見られ、CO2ナルコーシスや呼吸停止に至ることもあります。年長児や成人では軽症の感冒様症状で終わることが多いですが、高齢者では肺炎に進展することがあります。
診断
診断は臨床症状と流行状況から推定されます。確定診断には迅速抗原検査(鼻腔・咽頭拭い液)、RT-PCR法、ウイルス分離、血清抗体価測定が用いられます。迅速抗原検査は15-30分で結果が得られ、外来診療で有用ですが、感度は60-80%程度です。RT-PCR法は感度・特異度が高く、確定診断に用いられます。胸部X線では過膨張、肺紋理増強、無気肺を認めることがあります。血液検査では軽度の白血球増多または減少、CRP軽度上昇を認めます。鑑別診断では細菌性肺炎、マイコプラズマ肺炎、百日咳、気管支喘息などを除外します。
治療
RSウイルス感染症に対する特異的な抗ウイルス薬はなく、対症療法が中心となります。軽症例では十分な水分摂取、安静、鼻汁吸引により経過観察します。中等症以上では酸素療法、輸液療法、呼吸理学療法を行います。重症例では人工呼吸管理、ECMOが必要になることもあります。気管支拡張薬(β2刺激薬)やステロイド薬の効果は限定的です。リバビリンは重症例に使用されることがありますが、効果は議論が分かれています。予防ではパリビズマブ(抗RSV単クローン抗体)の筋注により、高リスク児での重症化予防が可能です。支持療法として栄養管理、感染症予防も重要です。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 非効果的呼吸パターン:細気管支の炎症・閉塞による呼吸困難
- 栄養摂取不足:呼吸困難による哺乳・摂食困難
- 感染拡大リスク:強い感染力による院内感染の危険性
ゴードン機能的健康パターン
呼吸パターンでは呼吸数、呼吸様式(陥没呼吸、鼻翼呼吸)、酸素飽和度、喘鳴の有無を継続的に評価します。栄養・代謝パターンでは哺乳量・摂食量の減少、体重変化、脱水の兆候を詳細にアセスメントします。乳児では特に哺乳時の呼吸困難に注意が必要です。活動・運動パターンでは呼吸困難による活動制限、睡眠・休息パターンでは呼吸困難による睡眠障害、夜間の症状増悪を評価します。健康知覚・健康管理パターンでは家族の感染に対する理解と予防行動を把握します。
ヘンダーソン14基本的ニード
正常な呼吸をするでは効果的な呼吸を維持するための体位管理、酸素療法、気道クリアランスが最優先となります。食べる・飲むでは呼吸困難による哺乳・摂食困難に対して、少量頻回授乳、適切な体位での授乳を支援します。清潔で健康な皮膚を維持し、衣服で身体を守るでは感染拡散防止のための手指衛生、個人防護具の適切な使用が重要です。安全で健康的な環境を維持し、他者に危険が及ばないようにするでは標準予防策と接触予防策の徹底を行います。
看護計画・介入の内容
- 呼吸管理・酸素化改善:呼吸状態の継続的モニタリング、酸素療法の適切な実施、体位管理(半座位、側臥位)、鼻汁・痰の吸引、加湿による気道粘膜の保護
- 栄養・水分管理:哺乳・摂食状況の評価、少量頻回授乳の指導、脱水の予防と早期発見、体重変化のモニタリング、必要に応じた輸液管理
- 感染管理・予防対策:標準予防策と接触予防策の実施、手指衛生の徹底、個人防護具の適切な使用、環境清拭・消毒、面会制限の実施、退院後の感染予防教育
よくある疑問・Q&A
Q: RSウイルス感染症はどのようにうつりますか?予防方法を教えてください
A: RSウイルスは接触感染と飛沫感染で広がります。接触感染では汚染された手指、玩具、タオル、ドアノブなどを介して感染し、飛沫感染では咳やくしゃみの飛沫により感染します。予防方法として、①手洗い・手指消毒の徹底(石鹸と流水で20秒以上)、②マスク着用(2歳以上)、③咳エチケット、④玩具や環境の消毒、⑤人混みを避ける、⑥感染者との接触回避が重要です。ウイルスは環境中で数時間生存するため、定期的な清拭・消毒が効果的です。兄弟姉妹がいる場合は特に注意が必要で、隔離が困難でも可能な限り接触を制限してください。
Q: 入院が必要なのはどのような場合ですか?家で様子を見ても大丈夫でしょうか?
A: 入院適応は、①呼吸困難(多呼吸、陥没呼吸、鼻翼呼吸)、②酸素飽和度低下(95%未満)、③哺乳困難(普段の半分以下)、④脱水(尿量減少、ぐったり)、⑤無呼吸発作、⑥高リスク児(早産児、先天性心疾患、慢性肺疾患、生後3ヶ月未満)などです。家庭での観察ポイントとして、呼吸の速さ(2ヶ月未満:60回/分以上、2-12ヶ月:50回/分以上)、哺乳量、機嫌、尿量を確認してください。緊急受診が必要な症状は、呼吸困難の悪化、顔色不良、ぐったりしている、哺乳できない、けいれん、無呼吸です。軽症例でも症状は急速に変化することがあるため、注意深い観察が重要です。
Q: 兄弟姉妹がいます。感染を防ぐにはどうすればよいですか?
A: 兄弟姉妹への感染予防は非常に重要です。家庭内での対策として、①可能な限りの隔離(別室での過ごし方)、②手洗いの徹底(接触前後に必ず実施)、③マスク着用(保護者・年長児)、④玩具の共有回避、⑤タオル・食器の分離、⑥定期的な環境消毒を行います。完全な隔離は困難ですが、感染児のケア後は必ず手洗いし、清潔な衣服に着替えることが重要です。保育園・幼稚園では感染児は症状消失後も数日間は登園を控えることが推奨されます。妊婦や新生児がいる場合は特に注意が必要で、可能な限り接触を避けるか、十分な感染対策を講じてください。
Q: 薬で治療できないのでしょうか?自然に治るまで待つしかないのですか?
A: RSウイルス感染症には特効薬がなく、対症療法が中心となります。しかし、自然治癒を待つだけではありません。積極的な支持療法により症状を和らげ、合併症を予防することができます。具体的な治療として、①酸素療法による呼吸支援、②輸液による脱水予防、③鼻汁吸引による気道クリアランス、④栄養管理、⑤感染症予防などがあります。重症例では人工呼吸管理も行います。抗生物質は細菌感染の合併がない限り効果がなく、気管支拡張薬の効果も限定的です。予防薬としてパリビズマブ(シナジス)が高リスク児に使用されます。適切な支持療法により多くの患児が後遺症なく回復します。
まとめ
RSウイルス感染症は乳幼児の重要な呼吸器感染症として、特に生後6ヶ月未満の乳児では生命に関わる重篤な経過をたどる可能性がある疾患です。特異的治療法がないため、早期発見と適切な支持療法、そして感染拡散防止が看護の重要な役割となります。
看護の要点は呼吸状態の継続的観察と感染管理の徹底です。乳幼児では呼吸状態が急速に変化する可能性があるため、呼吸数、呼吸様式、酸素飽和度の継続的モニタリングと、陥没呼吸、鼻翼呼吸などの努力呼吸の早期発見が重要です。無呼吸発作は特に危険な徴候であり、24時間の厳重な観察が必要です。
栄養・水分管理では、呼吸困難による哺乳困難が脱水や栄養不良につながる可能性があるため、哺乳量の詳細な観察と体重変化のモニタリングが重要です。少量頻回授乳や適切な体位での授乳により、呼吸への負担を最小限に抑えながら栄養摂取を支援します。
感染管理では、RSウイルスの強い感染力を考慮し、標準予防策と接触予防策を徹底することが重要です。手指衛生、個人防護具の適切な使用、環境の清拭・消毒により、院内感染の拡散を防止します。面会制限も感染拡散防止の重要な対策です。
家族支援も重要な看護の視点です。特効薬がないことへの不安、重症化への恐怖、感染拡散への心配など、家族は多くの不安を抱えています。疾患の正しい理解、症状の経過、家庭での観察ポイントについて分かりやすく説明し、家族の不安軽減を図ることが重要です。
退院指導では、症状悪化時の受診基準、感染予防方法、兄弟姉妹への感染対策について具体的に指導し、家族が安心して在宅ケアを継続できるよう支援します。再感染の可能性についても説明し、継続的な予防の重要性を伝えます。
予防教育では、パリビズマブによる予防の適応、手洗い・消毒の重要性、流行期の外出制限など、予防可能な対策について指導します。特に高リスク児を持つ家族には、より厳重な感染予防対策について教育することが重要です。
実習では患児の年齢と重症度に応じたアプローチを心がけましょう。乳児では非言語的サインの観察が重要で、不機嫌、哺乳不良、活気低下などの微細な変化を見逃さないよう注意深く観察することが大切です。また、家族の不安に共感的に対応し、チーム一体となった包括的ケアを提供することで、患児と家族が安心して治療を受けられるよう支援していきましょう。RSウイルス感染症は適切な管理により多くの患児が後遺症なく回復する疾患であることを忘れずに、希望を持った看護を提供することが重要です。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
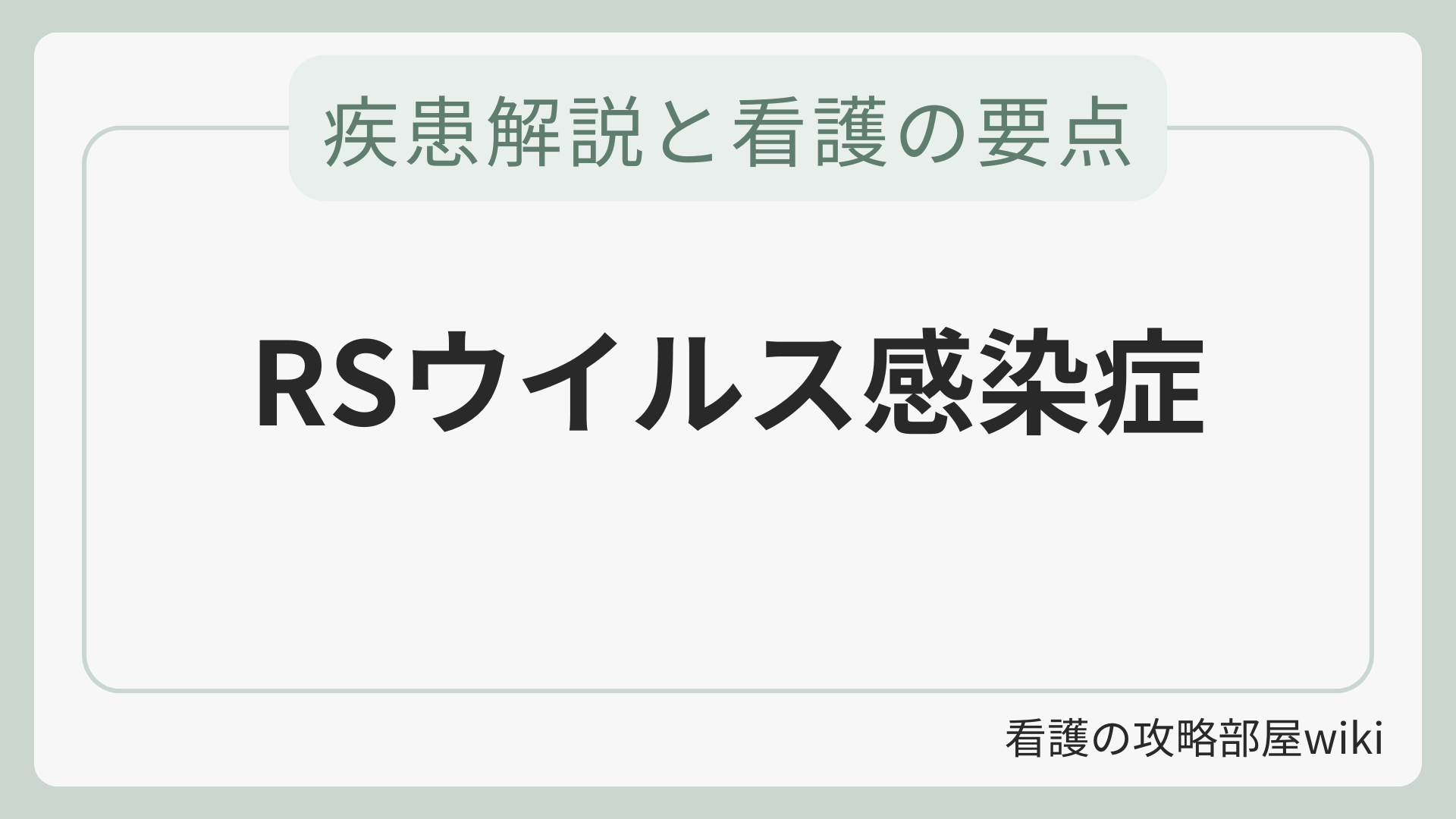
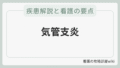
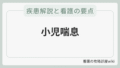
コメント