疾患概要
定義
咽頭炎・扁桃炎は上気道感染症の代表的な疾患で、咽頭および扁桃に炎症が生じる状態です。咽頭炎は咽頭粘膜全体の炎症、扁桃炎は主に口蓋扁桃の炎症を指しますが、実際には併発することが多く、まとめて咽頭扁桃炎と呼ばれることもあります。症状の持続期間により急性(2週間未満)と慢性(3ヶ月以上)に分類され、急性扁桃炎では炎症の程度によりカタル性扁桃炎と陥窩性扁桃炎に分けられます。
疫学
咽頭炎・扁桃炎は最も頻度の高い上気道感染症で、年間を通じて発症しますが、特に秋から春にかけて多く見られます。小児から成人まで幅広い年齢層に発症し、小児では溶血性連鎖球菌による急性扁桃炎が多く、成人ではウイルス性咽頭炎の頻度が高くなります。慢性扁桃炎は10-30歳代に多く、反復性の急性扁桃炎により扁桃組織の線維化が進行した状態です。集団生活や乾燥した環境では感染拡大のリスクが高まります。
原因
ウイルス性(約70-80%)と細菌性(約20-30%)に大別されます。ウイルス性ではアデノウイルス、エンテロウイルス、EBウイルス、インフルエンザウイルスなどが原因となります。細菌性ではA群β溶血性連鎖球菌(溶連菌)が最も重要で、特に小児の急性扁桃炎の原因として頻度が高く、適切な抗菌薬治療が必要です。その他の細菌として黄色ブドウ球菌、インフルエンザ菌なども原因となります。誘因として過労、ストレス、免疫力低下、喫煙、乾燥した環境などが挙げられます。
病態生理
咽頭・扁桃は外界からの病原体に対する第一の防御機構として機能していますが、病原体の侵入により炎症反応が惹起されます。急性期には血管透過性の亢進により組織の腫脹、発赤、疼痛が生じます。扁桃では陥窩(クリプト)に膿性分泌物が貯留し、白苔として観察されます。溶連菌感染では毒素産生により全身症状が強く現れ、適切な治療を行わないとリウマチ熱や急性糸球体腎炎などの続発症を引き起こす可能性があります。慢性扁桃炎では反復する炎症により扁桃組織の線維化が進行し、細菌の温床となって病巣感染の原因となることがあります。
症状・診断・治療
症状
急性咽頭炎・扁桃炎では咽頭痛、嚥下痛、発熱が主症状です。咽頭痛は安静時にも持続し、嚥下により増強します。溶連菌感染では38-39℃の高熱、頭痛、倦怠感、時として嘔吐を伴い、咽頭・扁桃の著明な発赤と白苔付着、頸部リンパ節腫脹が特徴的です。小児では腹痛を訴えることもあります。ウイルス性では比較的軽症で、鼻汁、咳嗽などの上気道症状を伴うことが多くなります。慢性扁桃炎では軽度の咽頭痛、咽頭違和感、口臭、微熱などの軽微な症状が持続します。
診断
診断は臨床症状と咽頭所見により行われます。視診では咽頭・扁桃の発赤、腫脹、白苔や膿栓の有無、頸部リンパ節の腫脹を確認します。溶連菌感染の鑑別が重要で、迅速診断キット(15分程度で結果判明)や咽頭培養検査により確定診断を行います。血液検査では白血球数、CRP、ASO値(抗ストレプトリジンO抗体価)などを測定します。Centor criteria(発熱、扁桃白苔、前頸部リンパ節腫脹、咳嗽なし)により溶連菌感染の可能性を評価することもあります。重症例では血液培養や画像検査も考慮されます。
治療
ウイルス性では対症療法が基本で、解熱鎮痛薬、含嗽薬、トローチなどを使用します。十分な休息と水分摂取が重要です。細菌性、特に溶連菌感染では抗菌薬治療が必須で、ペニシリン系抗菌薬(アモキシシリン)が第一選択です。治療期間は通常10日間で、症状改善後も処方された薬剤を完全に服用することが重要です。ペニシリンアレルギーがある場合はマクロライド系やセフェム系抗菌薬を使用します。慢性扁桃炎で反復する場合や病巣感染が疑われる場合は扁桃摘出術が考慮されます。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 急性疼痛:咽頭・扁桃の炎症に関連した咽頭痛・嚥下痛
- 体液量不足リスク状態:嚥下痛による水分摂取不足の危険性
- 感染拡大リスク:病原体の飛沫感染による感染拡大の危険性
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚・健康管理パターンでは患者・家族の疾患理解度と感染予防に対する意識を評価します。特に溶連菌感染では完全な抗菌薬治療の重要性と感染拡散防止の必要性について十分な説明が必要です。栄養・代謝パターンでは嚥下痛による食事摂取量の減少と脱水のリスクを詳細にアセスメントします。食事の形態、摂取量、水分バランス、体重変化を継続的に観察します。活動・運動パターンでは発熱や全身倦怠感による活動制限の程度を評価し、適切な安静度を設定します。
ヘンダーソン14基本的ニード
食べる・飲むでは嚥下痛による摂食・嚥下困難を詳細に評価し、栄養・水分摂取の維持を支援します。食事の温度、形態、摂取方法を工夫し、脱水や栄養不良の予防に努めます。コミュニケーションをとるでは咽頭痛による発声困難や音声の変化を評価し、効果的なコミュニケーション方法を検討します。安全で健康的な環境を維持し、他者に危険が及ばないようにするでは感染拡散防止のための隔離予防策と家族・周囲への感染予防指導を行います。
看護計画・介入の内容
- 疼痛管理・症状緩和:適切な鎮痛薬の使用指導、冷たい飲み物や氷片による局所冷却、含嗽による咽頭の清浄化、加湿による咽頭粘膜の保護
- 栄養・水分管理:嚥下しやすい食事形態の提供(ゼリー、プリン、スープなど)、十分な水分摂取の励行、電解質バランスの維持、体重・尿量の観察
- 感染管理・予防:標準予防策と飛沫予防策の実施、手指衛生の徹底指導、マスク着用の指導、適切な咳エチケットの指導、家族・接触者への感染予防教育
よくある疑問・Q&A
Q: 咽頭炎と扁桃炎の違いは何ですか?治療は異なりますか?
A: 咽頭炎は咽頭粘膜全体の炎症、扁桃炎は主に扁桃の炎症を指しますが、実際には同時に起こることが多く、症状や治療法に大きな違いはありません。重要なのはウイルス性か細菌性かの鑑別で、細菌性(特に溶連菌)の場合は抗菌薬治療が必要です。症状の程度や原因菌により治療方針が決定されるため、医師による適切な診断と治療が重要です。
Q: 溶連菌感染はなぜ抗菌薬での完全治療が重要なのですか?
A: 溶連菌感染を不完全に治療すると、続発症のリスクが高まります。主な続発症にはリウマチ熱(心臓弁膜症を引き起こす可能性)、急性糸球体腎炎(腎機能障害)、PANDAS(小児の強迫性障害)などがあります。症状が改善しても処方された抗菌薬は10日間完全に服用することで、これらの重篤な合併症を予防できます。また、完全治療により感染性もなくなり、他者への感染拡散も防げます。
Q: いつから学校や職場に復帰できますか?
A: ウイルス性の場合は発熱がなく全身状態が良好であれば復帰可能です。溶連菌感染の場合は抗菌薬治療開始から24時間経過後で発熱がなければ復帰できます。ただし、全身状態や咽頭痛の程度も考慮して判断します。復帰後もマスク着用と手指衛生を徹底し、他者への感染拡散防止に努めることが重要です。学校や職場の規則がある場合はそれに従ってください。
Q: 家族への感染を防ぐにはどうすればよいですか?
A: 飛沫感染が主な感染経路のため、マスク着用と咳エチケットが最も重要です。患者と家族の手指衛生を徹底し、タオルや食器の共用を避けます。患者の使用した食器は熱湯消毒し、部屋の換気を十分に行います。特に高齢者、妊婦、免疫力の低下した家族は感染リスクが高いため、可能な限り接触を避けるか、接触時は必ずマスクを着用してください。溶連菌の場合は抗菌薬治療開始24時間後まで特に注意が必要です。
まとめ
咽頭炎・扁桃炎は最も身近な感染症の一つでありながら、適切な診断と治療が重要な疾患です。特に溶連菌感染の鑑別は重篤な続発症の予防のために不可欠であり、迅速かつ正確な診断に基づく適切な抗菌薬治療が求められます。
看護の要点は症状マネジメントと感染拡散防止です。特に嚥下痛による水分・栄養摂取不足は脱水や栄養不良につながるため、個別性のある摂食支援が重要となります。疼痛緩和では薬物療法と非薬物療法を組み合わせ、患者さんの苦痛軽減を図ります。
また、感染管理の徹底は患者さん自身の回復促進と同時に、家族や地域社会への感染拡散防止の観点からも重要です。特に溶連菌感染では完全な抗菌薬治療の重要性を患者・家族に十分説明し、服薬アドヒアランスの向上を支援することが続発症予防につながります。
患者教育では疾患の特徴、治療の必要性、感染予防方法について分かりやすく説明し、患者・家族が安心して治療に取り組めるよう支援します。特に小児の場合は保護者の理解と協力が治療成功の鍵となります。
実習では患者さんの年齢や発達段階に応じたアプローチを心がけましょう。小児では遊びを通じた関わりや保護者との連携が重要で、成人では自己管理能力の向上を支援します。症状の観察では咽頭痛の程度、嚥下状態、水分摂取量、全身状態を継続的にアセスメントし、個別性のある看護介入を提供することで、患者さんの早期回復と合併症予防に貢献していきましょう。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
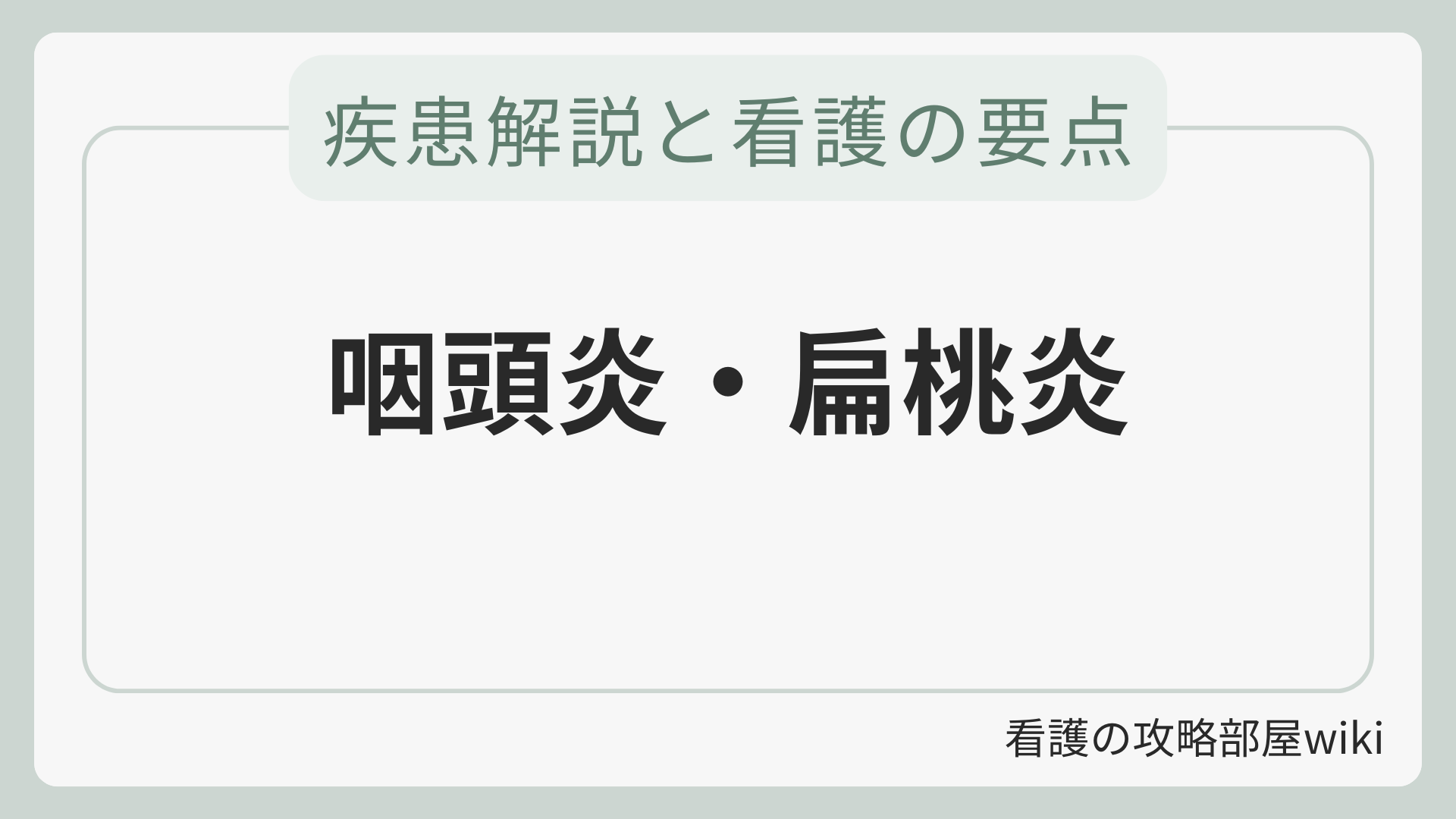
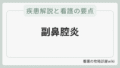
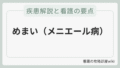
コメント