疾患概要
定義
子宮がんは、発生部位により子宮頸がんと子宮体がんに大きく分けられます。子宮頸がんは子宮の入り口である子宮頸部に発生し、そのほとんどが扁平上皮がんです。子宮体がんは子宮内膜から発生する腺がんで、子宮内膜がんとも呼ばれます。両者は発症年齢、原因、症状、治療法が異なる別の疾患として扱われます。
疫学
子宮頸がんは年間約1万1千人が罹患し、30〜40代の若い世代に多く発症します。近年は若年化と罹患率の増加が問題となっており、20〜30代の女性では発症するがんの中で最も多い疾患です。一方、子宮体がんは年間約1万7千人が罹患し、50〜60代の閉経前後に多く発症します。食生活の欧米化や出産回数の減少により、子宮体がんの罹患率は増加傾向にあります。子宮頸がんは検診による早期発見が可能で、早期治療により予後は良好です。
原因
子宮頸がんの原因の約90%以上はヒトパピローマウイルス(HPV)感染です。HPVは性交渉により感染し、多くの場合は自然に排除されますが、持続感染すると数年から十数年かけて前がん病変を経てがん化します。特にハイリスク型HPV(16型、18型など)の感染が重要です。一方、子宮体がんの主な原因はエストロゲンの過剰刺激です。肥満、糖尿病、高血圧、出産経験がない、初経が早い、閉経が遅いなどがリスク因子となります。また、タモキシフェンの長期使用も子宮体がんのリスクを高めます。
病態生理
子宮頸がんは、HPV感染により子宮頸部の細胞に異形成が生じ、軽度異形成→中等度異形成→高度異形成→上皮内がん→浸潤がんと段階的に進行します。この過程には通常数年以上かかるため、検診による早期発見が可能です。浸潤がんになると周囲組織に広がり、リンパ節転移や遠隔転移を起こします。子宮体がんは、エストロゲンの持続的刺激により子宮内膜が過剰に増殖し、異型増殖症を経てがん化します。筋層への浸潤が深いほど、リンパ節転移や遠隔転移のリスクが高くなります。転移は骨盤内リンパ節、傍大動脈リンパ節へと進み、血行性には肺、肝臓、骨などに転移します。
症状・診断・治療
症状
子宮頸がんの初期はほとんど無症状で、進行すると不正性器出血(特に性交後出血)が最も多い症状です。その他、おりものの増加や悪臭、下腹部痛、腰痛などが見られます。さらに進行すると膀胱や直腸への浸潤により血尿や血便、下肢の浮腫などが出現します。子宮体がんの最も特徴的な症状は不正性器出血で、特に閉経後の出血は重要なサインです。その他、おりものの増加、下腹部痛、腹部膨満感などが見られます。進行例では貧血症状や体重減少も伴います。
診断
子宮頸がんの診断には、まず子宮頸部細胞診(パップテスト)を行い、異常があればコルポスコープ検査で病変部位を観察し、組織診で確定診断します。HPV検査も併用されることが多いです。子宮体がんの診断には経腟超音波検査で子宮内膜の厚さを評価し、子宮内膜細胞診または組織診で確定診断します。両者とも、がんと診断された場合はMRI検査やCT検査で病変の広がりや転移の有無を評価し、FIGO分類による進行期分類を行います。腫瘍マーカーでは、子宮頸がんでSCC、子宮体がんでCA125が参考になります。
治療
子宮頸がんの治療は進行期により異なります。初期(IA期まで)では円錐切除術により妊孕性温存が可能な場合もあります。IB〜IIA期では広汎子宮全摘出術と骨盤リンパ節郭清が標準治療です。IIB期以降は放射線療法と化学療法の同時併用療法が標準となります。子宮体がんの治療は手術療法が基本で、単純子宮全摘出術、両側付属器切除術、骨盤リンパ節郭清を行います。リスク因子に応じて術後に化学療法や放射線療法を追加します。進行例や再発例ではホルモン療法(黄体ホルモン製剤)が有効な場合もあります。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 不安:がん診断、治療、妊孕性喪失、死への不安
- セクシュアリティパターン変調:子宮摘出による性機能や女性性への影響
- 知識不足:疾患や治療、予防に関する知識不足
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚-健康管理パターンでは、特に子宮頸がんではHPVワクチンや定期検診の重要性について理解度を評価します。多くの患者は「自分ががんになるとは思わなかった」と語るため、予防や早期発見の意識づけが重要です。自己知覚-自己概念パターンでは、子宮摘出による女性性やアイデンティティへの影響を評価します。特に若年者や妊娠を希望していた患者では、深い喪失感や悲嘆を経験します。性-生殖パターンでは、妊孕性の喪失、性機能の変化、パートナーシップへの影響について、プライバシーに配慮しながら丁寧に評価することが必要です。
ヘンダーソン14基本的ニード
正常に排泄するニードでは、術後の排尿障害や放射線療法による膀胱炎、直腸炎への対応が重要です。広汎子宮全摘出術後は自律神経障害により排尿困難や便秘が生じやすいため、自己導尿や排便コントロールの指導が必要となります。安全なニードでは、化学療法や放射線療法による副作用管理、骨盤内リンパ節郭清後の下肢リンパ浮腫予防について指導します。学習のニードでは、HPV感染予防やワクチンの重要性、定期検診の必要性について教育します。
看護計画・介入の内容
- 心理的支援:がん告知後の心理的ケア、妊孕性喪失への悲嘆ケア、女性性への影響に対する支援、必要に応じて生殖医療相談や心理カウンセリングへの橋渡し
- 術後管理:創部管理、ドレーン管理、疼痛管理、排尿障害への対応(自己導尿指導含む)、早期離床の促進
- 放射線療法の副作用管理:皮膚炎のケア、膀胱炎・直腸炎の症状管理、腟狭窄予防のためのダイレーター使用指導
よくある疑問・Q&A
Q: 子宮頸がんはどうすれば予防できますか?
A: 子宮頸がんの予防にはHPVワクチン接種と定期的な子宮頸がん検診が最も有効です。HPVワクチンは感染前に接種することで高い予防効果があります。また、コンドームの使用はHPV感染のリスクを減らすことができます。検診は20歳から2年に1回受けることが推奨されています。
Q: 子宮を摘出すると女性ホルモンが出なくなりますか?
A: いいえ、女性ホルモンは主に卵巣から分泌されるため、子宮のみを摘出した場合はホルモン分泌に影響はありません。ただし、卵巣も同時に摘出した場合は、閉経前の女性では更年期症状が出現します。この場合はホルモン補充療法を検討することがあります。
Q: 手術後も性生活は可能ですか?
A: 子宮摘出術後も性生活は可能です。術後6〜8週間程度で創部が治癒すれば、医師の許可を得て再開できます。ただし、放射線療法を受けた場合は腟の狭窄や乾燥が起こりやすいため、潤滑剤の使用やダイレーターによる腟拡張が必要な場合があります。
Q: 閉経後の不正出血は必ず受診すべきですか?
A: はい、閉経後の不正出血は子宮体がんの重要なサインですので、必ず婦人科を受診してください。出血量が少量でも、また一度だけの出血でも受診が必要です。早期発見により治療成績は大きく向上します。
Q: HPVは一度感染したら治りませんか?
A: いいえ、HPVに感染しても多くの場合(約90%)は2年以内に自然に排除されます。ただし、排除されずに持続感染すると前がん病変やがんに進行するリスクがあるため、定期的な検診が重要です。
Q: 若い年代でも子宮頸がんになりますか?
A: はい、子宮頸がんは30〜40代に最も多く、20代でも発症します。近年は若年化が進んでおり、20〜30代の女性では最も多いがんの一つです。性交渉の経験がある方は、年齢に関係なく定期的な検診が重要です。
まとめ
子宮がんは子宮頸がんと子宮体がんという異なる疾患の総称であり、それぞれ発症年齢、原因、症状が異なります。子宮頸がんはHPV感染が原因で若年者に多く、ワクチン接種と検診による予防が可能です。子宮体がんはエストロゲン過剰が原因で閉経前後に多く、閉経後の不正出血が重要なサインとなります。
看護師は早期発見の重要性を啓発し、特に若い世代へのHPVワクチン接種の推奨や定期検診の受診勧奨を行う役割を担います。また、検診を受けることへの心理的抵抗を軽減するための情報提供も重要です。
患者の多くは妊孕性の喪失や女性性への影響に深い悲しみを感じるため、十分な心理的支援が必要です。特に若年患者では、妊孕性温存の可能性について医師と十分に相談できるよう、意思決定支援を行うことが大切です。
治療においては、広汎子宮全摘出術後の排尿障害や放射線療法後の腟狭窄など、特有の合併症への対応が重要となります。これらは患者のQOLに大きく影響するため、具体的なセルフケア方法を指導し、長期的にフォローアップする必要があります。
実習では、患者の年齢や背景を考慮した個別的なケアを心がけ、特にデリケートな問題については、プライバシーに十分配慮しながら共感的な態度で接することが大切です。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
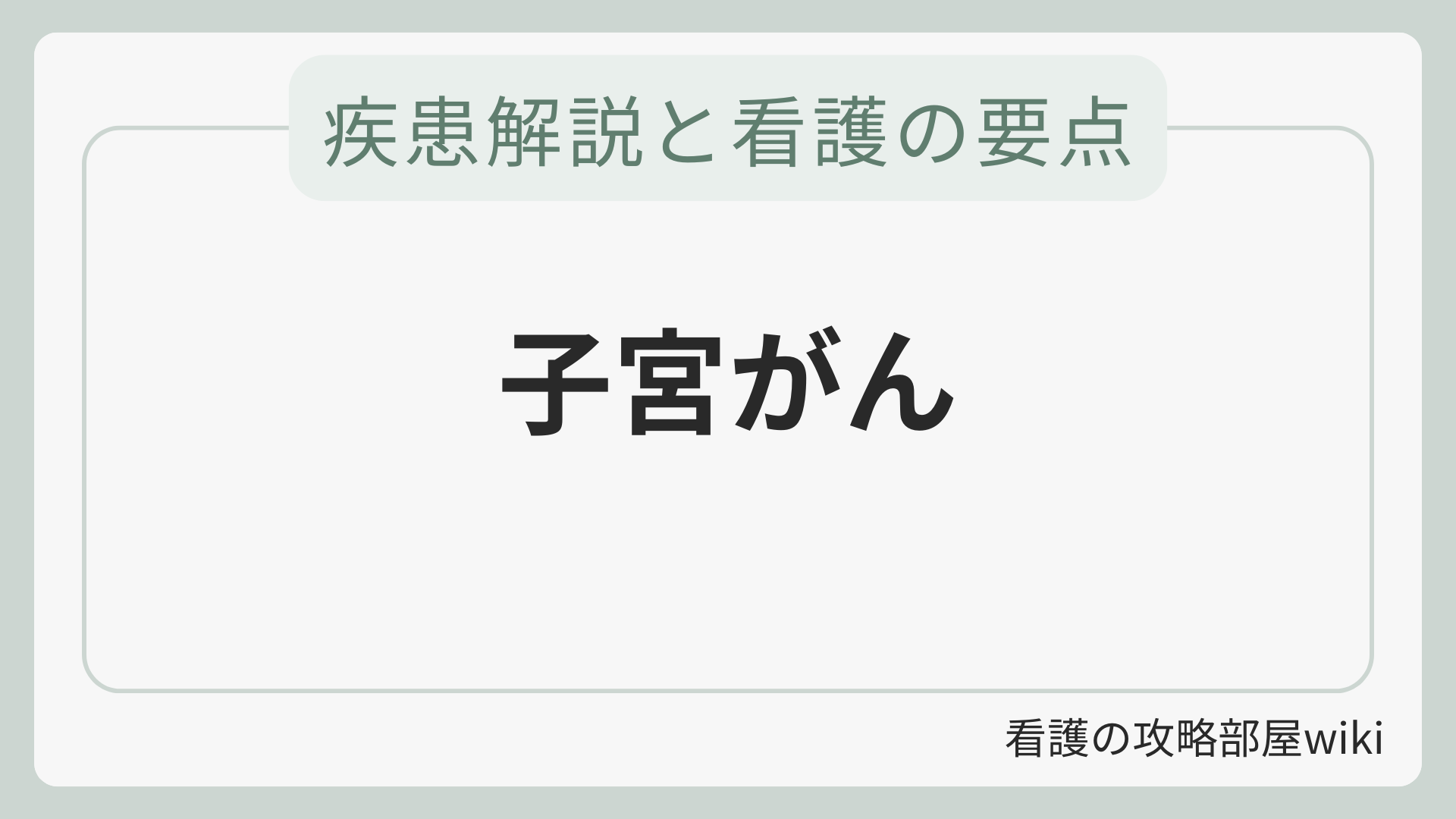
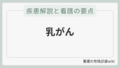
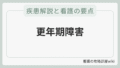
コメント