疾患概要
定義
血管性認知症とは、脳の血管が障害されることにより、脳への血液供給が不足し、脳神経細胞が傷つき、認知機能が低下する疾患です。脳梗塞や脳出血などの脳血管疾患により、脳組織が損傷を受け、その結果として認知障害が起こることが特徴です。
血管性認知症は、アルツハイマー病に次いで、認知症の第2位の原因とされていますが、アルツハイマー病と異なり、血管疾患の治療と予防により、進行を遅延させたり、改善させたりすることが可能な点が極めて重要です。
つまり、血管性認知症は、「治療・予防の可能性がある認知症」として、特に注目されている疾患です。
疫学
日本では、認知症患者さんは約600万人と推計されており、そのうち約20~25%が血管性認知症とされています。つまり、認知症患者さんの約100~150万人が血管性認知症ということになります。
血管性認知症の発症率は、60代後半以降で急速に増加し、特に75歳以上の高齢者で高いとされています。男女差では、男性の方が若干高い発症率を示します。
脳梗塞や脳出血などの脳血管疾患の既往がある患者さんでは、血管性認知症の発症リスクが著しく高くなります。また、高血圧、脂質異常症、糖尿病、喫煙などの血管疾患の危険因子を有する患者さんでも、リスクが高いとされています。
発症形式として、段階性認知症(脳梗塞などの脳血管疾患発症に伴い、急激に認知機能が低下する)と緩徐性認知症(血管性病変が徐々に蓄積して、ゆっくり認知機能が低下する)の2つのパターンがあります。
原因
血管性認知症の原因は、脳血管障害です。具体的には以下のようなメカニズムが関与します。
大血管梗塞:太い脳動脈(中大脳動脈、前大脳動脈など)が血栓により閉塞し、広い範囲の脳梗塞が起こります。その結果、その領域の脳神経細胞が壊死し、認知機能が急激に低下します。
小血管梗塞:脳の細い血管(穿通枝)が障害され、多数の微小梗塞が脳全体に散在して起こります(ラクナ梗塞)。これにより、脳白質が傷つき、認知機能が徐々に低下します。
脳出血:脳血管が破裂して、脳内に血液が流出します。その結果、脳組織が損傷され、認知機能が低下します。特に、脳幹や小脳などの重要な領域に出血が起こった場合は、深刻な認知障害が起こります。
白質病変:脳の白質(神経線維)が虚血により障害され、脳神経細胞間の接続が断たれ、認知機能が低下します。これは、脳梗塞として明らかな損傷がなくても、累積的に起こります。
血管型認知症を引き起こす危険因子として、高血圧、脂質異常症、糖尿病、喫煙、心房細動(脳塞栓症のリスク)などが挙げられます。これらの危険因子により、脳血管が傷つき、血栓が形成されやすくなり、脳梗塞や脳出血のリスクが高まります。
病態生理
血管性認知症の発症メカニズムは、脳血管障害→脳組織の虚血・壊死→神経細胞死→認知機能低下という流れです。
第1段階:脳血管の損傷
高血圧や脂質異常症などの危険因子により、脳血管の内膜が傷つき、動脈硬化性プラークが形成されます。また、血液凝固能が亢進して、血栓が形成されやすくなります。
第2段階:脳血流の低下または途絶
プラークが形成された脳血管が、さらに血栓により閉塞されると、その先の脳組織への血液供給が途絶えます。あるいは、脳血管が完全には閉塞されなくても、著しく狭窄することで、脳への血流が低下します。
第3段階:脳組織の虚血と梗塞
脳血流が途絶えた領域の脳組織は、酸素とグルコース(栄養)の供給が絶たれます。脳は、全身の臓器の中で最もエネルギーを消費する臓器であり、虚血に非常に敏感です。
虚血から数分以内に、神経細胞のエネルギー代謝が破綻し、細胞内のカリウムイオンが流出し、カルシウムイオンが流入します。細胞膜の機能が失われ、細胞が膨張(細胞性浮腫)します。
虚血から数時間が経過すると、神経細胞は不可逆的に壊死し、その領域の脳組織は永遠に失われます。
第4段階:脳神経回路の破壊
脳梗塞により脳神経細胞が死滅すると、その細胞が形成していた脳神経回路が破壊されます。特に、認知機能に関わる脳領域(前頭葉の前頭前野、頭頂葉、側頭葉など)が障害される場合、認知機能の低下が顕著になります。
一方、脳血管の疾患は段階的に蓄積することも重要です。1回の脳梗塞では症状が軽度でも、複数の脳梗塞が蓄積すると、脳の予備能力が枯渇し、認知機能が低下するという現象(multi-infarct dementia)が起こります。
第5段階:脳の可塑性と代償機構
重要なのは、脳には可塑性という性質があり、障害された脳領域の機能が、他の脳領域により代償される可能性があります。特に、若年者やリハビリテーション早期に、リハビリテーションにより、ある程度の機能回復が期待できます。
つまり、血管性認知症は、アルツハイマー病と異なり、脳血管の状態を改善させることで、認知機能の改善や進行の停止が期待できるという特徴があります。
症状・診断・治療
症状
血管性認知症の症状は、脳梗塞や脳出血が起こった場所と範囲により、多様です。
認知機能の低下:記憶障害(特に最近の出来事を覚えられない)、注意散漫、判断力の低下、計算能力の低下などが起こります。アルツハイマー病と異なり、段階的に、あるいは急激に認知機能が低下することが特徴です。
階段状の低下:複数の脳梗塞が蓄積した場合、脳梗塞が起こるたびに、認知機能が段階的に低下していく、という特徴的なパターンを示すことがあります。患者さんや家族は「ここまでは大丈夫だったのに、急に悪くなった」と訴えることが多いです。
脳卒中の後遺症:脳梗塞や脳出血により、片麻痺(片側の身体の麻痺)、失語症(言葉が出ない)、失行症(行為ができない)などの神経学的後遺症が起こることがあります。
気分の変化:感情的になりやすい、怒りっぽい、泣きやすくなるという情動不安定性が起こることが多いです。これは、脳の感情調整中枢が障害されるためです。
脳血管型認知症に特徴的な症状として「突発的感情表現障害」がある:患者さんが理由なく泣いたり、笑ったり、怒ったりする症状が起こることがあります。これは、脳幹の領域が障害されることにより起こります。
物忘れ:アルツハイマー病の物忘れは、自分が何かをしたことを完全に忘れてしまう(例えば、昼食を食べたことを全く覚えていない)のに対して、血管性認知症では、昼食を食べたことは覚えているが、何を食べたかが思い出せないという型の物忘れが特徴的です。
日中の眠気:脳血流が低下することにより、日中の眠気が強くなることがあります。これは、アルツハイマー病では見られない特徴です。
歩行障害:脳の運動中枢や小脳が障害される場合、歩行が困難になることがあります。「小刻みに歩く」「バランスが悪い」などの症状が起こります。
診断
血管性認知症の診断には、認知機能検査と脳画像検査が組み合わせられます。
認知機能検査:
MMSE(ミニメンタルステート検査)やMoCA(Montreal Cognitive Assessment)などの認知機能スクリーニング検査により、認知機能低下の程度を評価します。
詳細な神経心理学的検査により、どの認知領域が障害されているか(記憶、注意、言語、視空間認識など)を詳細に評価します。
脳画像検査は、血管性認知症の診断に最も重要です。
頭部CT検査:脳梗塞(低吸収域)や脳出血(高吸収域)、白質病変などを認識できます。ただし、微小梗塞や白質病変の評価には限界があります。
頭部MRI検査:T2強調画像やFLAIR画像により、脳梗塞や白質病変をより詳細に評価できます。拡散強調画像(DWI)により、急性梗塞を検出できます。
3D-TOF MRA(磁気共鳴血管造影):脳血管の形態と狭窄の程度を評価できます。
PET検査やSPECT検査:脳の血流や代謝を評価し、認知症の原因部位を同定するのに役立ちます。
脳脊髄液検査:タウ蛋白やアミロイドβを測定し、アルツハイマー病との鑑別に役立つことがあります。
血液検査:危険因子(血糖値、コレステロール、血圧など)と、他の認知症の原因(ビタミンB12欠乏、甲状腺機能異常など)を調べます。
診断基準:
国際的には、DSM-5やICD-11などの診断基準が使用されており、以下の基準により血管性認知症と診断されます。
- 認知機能低下が存在する
- 脳画像検査により、脳梗塞や脳出血などの脳血管病変が認識される
- 認知機能低下と脳血管病変の分布が一致している(またはその関連性が合理的である)
治療
血管性認知症の治療は、一次予防と二次予防が中心です。
危険因子の管理:
血管性認知症の進行を遅延させるために、最優先となるのは、脳梗塞や脳出血の再発予防です。
高血圧の管理:血圧を適切にコントロールすることが、最も重要です。目標血圧は、通常140/90mmHg未満とされていますが、患者さんの状態により調整されます。降圧薬(ACE阻害薬、ARB、カルシウム拮抗薬など)が用いられます。
脂質異常症の管理:LDLコレステロールを低下させるため、スタチン系薬剤が用いられます。
糖尿病の管理:血糖値を適切にコントロールすることが重要です。
喫煙の中止:喫煙は、脳梗塞のリスクを著しく高めるため、禁煙が必須です。
抗血小板薬と抗凝固薬:
脳梗塞の再発予防のため、アスピリンなどの抗血小板薬が用いられます。
心房細動などにより脳塞栓症のリスクがある場合は、抗凝固薬(ワルファリンやDOAC)が用いられます。
認知機能改善薬:
アルツハイマー病治療薬(ドネペジル、リバスチグミン、ガランタミンなど)が、血管性認知症に対しても効果を示すことがあります。ただし、効果は限定的です。
脳代謝改善薬:イデベノン、アルセルカなどの薬剤が、血流低下による脳ダメージを軽減させるために用いられることがあります。
リハビリテーション:
理学療法や認知リハビリテーションにより、脳の可塑性を活用して、失われた機能の一部を回復させることが期待できます。特に、脳梗塞直後のリハビリテーションが重要です。
その他の対症療法:
認知症に伴う行動心理症状(BPSD:Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)に対する治療として、抗精神病薬や抗うつ薬が用いられることがあります。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 知識不足:疾患、危険因子管理、生活管理について
- 記憶障害と見当識障害に伴う混乱と不安
- 身体的能力の低下と自己管理困難
- 脳梗塞再発に対する不安
- 家族との関係変化と心理的苦痛
- 感情的不安定性(突発的感情表現障害)への対応
- 危険行動と転倒・転落のリスク
- 薬物療法と危険因子管理の継続困難
- 社会的孤立感
ゴードン機能的健康パターン
健康知覚-健康管理パターンでは、患者さん自身が認知機能低下を自覚しているかどうかが重要です。多くの場合、患者さんは自分の認知障害を十分に認識せず、家族の訴えを否定することがあります。一方、患者さんが自分の障害を認識している場合は、それに伴う不安や絶望感が強いこともあります。
栄養-代謝パターンでは、認知機能低下により、患者さんが「食べること」を忘れたり、食事の準備ができなくなったりするため、栄養管理が課題になります。
活動-運動パターンでは、脳画像で脳梗塞や白質病変が認識されても、患者さんが過度に活動を制限していないか、一方で危険な活動をしていないかの両面から評価が必要です。
認識-認知パターンでは、患者さんの認知機能低下の程度、および患者さんが自分の障害をどの程度認識しているかが極めて重要です。
ストレス-対処パターンでは、患者さんが自分の認知障害に対してどのように対処しようとしているか、そして家族との関係がどのように変化しているかを評価します。
自己認識-自己概念パターンでは、患者さんが自分の人生と役割の変化をどのように受け止めているかを評価します。
ヘンダーソン14基本的ニード
認識と判断は、血管性認知症患者さんにおいて、最も重要で障害されやすいニードです。患者さんが、環境や自分の状態を正確に認識できず、正確な判断ができなくなっていく過程を理解することが、看護ケアの基盤です。
栄養と水分では、患者さんが「食べることを忘れる」「何を食べるか判断できない」ため、家族や介護者が食事を準備し、患者さんが栄養を摂取できるよう支援することが重要です。
排泄では、認知機能低下により、トイレの場所がわからなくなったり、使用方法を忘れたりするため、環境工夫と介助が必要です。
活動と運動では、患者さんが転倒のリスクが高くなるため、安全な環境設定と監視が重要です。同時に、適度な活動により、脳機能の維持が期待できるため、患者さんが安全に行える活動の提案が重要です。
個人の衛生と身だしなみでは、患者さんが衛生管理を忘れたり、失禁に対応できなくなったりするため、家族や介護者のサポートが重要です。
危機的状況への安全として、脳梗塞や脳出血の再発への警戒が重要です。また、患者さんが危険な行動(ガスの火を付けたまま忘れる、無断外出など)をする可能性があるため、環境設定と監視が重要です。
看護計画・介入の内容
- 血管性認知症の疾患教育と危険因子管理の重要性の強調:患者さんと家族に対して、「血管性認知症は、脳血管障害により起こる認知症であり、脳梗塞や脳出血の危険因子を管理することで、進行を遅延させたり、改善させたりすることが可能」という重要なメッセージを伝えることが極めて重要です。これにより、患者さんと家族が、治療と管理に前向きに取り組む動機づけが高まります。
- 高血圧、脂質異常症、糖尿病などの危険因子管理の具体的支援:患者さんと家族に対して、各危険因子が認知症の進行を招く仕組みを説明し、薬物療法の継続と生活習慣改善の重要性を強調します。特に、認知機能が低下している患者さんの場合は、家族による薬物療法の管理が重要になります。
- 禁煙支援:喫煙は脳梗塞のリスクを著しく高めるため、患者さんが喫煙している場合は、禁煙の強力な支援が必要です。患者さんの認知機能が低下している場合は、家族による環境工夫(たばこを置かない、喫煙の機会を作らない)が重要です。
- 認知機能低下に対する患者さんと家族への心理的サポート:患者さんが自分の認知障害を認識している場合は、それに伴う不安や絶望感が強いことがあります。患者さんと家族に対して、「多くの認知症患者さんが、社会的サポートと適切な管理により、充実した生活を送っている」という情報提供と、精神保健専門家による心理的サポートが重要です。
- 患者さんの安全な環境設定:認知機能低下により、患者さんが転倒したり、危険な行動をしたりするリスクが高まります。自宅環境を安全にする工夫(段差の除去、手すりの設置、ガスコンロの安全装置、鍵のかけ方など)が重要です。また、患者さんが無断外出して迷子になるリスクもあるため、必要に応じてGPS機器の使用も検討されます。
- 日常生活活動(ADL)の支援と介助方法の指導:患者さんが、着替え、入浴、排泄など、日常生活活動が困難になっていく過程を、患者さんと家族が受け入れるのを支援することが重要です。介助の際には、患者さんの自尊心を傷つけないような方法が重要です。
- 記憶補助と見当識改善のための工夫:患者さんが記憶障害を有している場合、メモ、カレンダー、時計、写真などの視覚的な補助が、患者さんの見当識維持に役立つことがあります。
- 感情的不安定性への対応:血管性認知症患者さんが突発的感情表現障害(理由なく泣く、笑う、怒る)を示す場合は、家族がその原因を追究せず、落ち着いて対応することが重要です。また、これが脳の損傷による症状であることを家族に説明し、患者さんを責めないよう指導することが重要です。
- 抗血小板薬と抗凝固薬の継続管理:脳梗塞の再発予防のため、アスピリンなどの抗血小板薬、または心房細動がある場合は抗凝固薬の継続が生命を守る重要な課題です。患者さんの認知機能が低下している場合は、家族による薬物療法の管理が重要です。
- 定期的な医師の診察と脳画像検査による進行の監視:血管性認知症は進行性疾患であり、定期的な医師の診察と脳画像検査により、新たな脳梗塞や白質病変の進行を監視することが重要です。患者さんと家族に対して、定期受診の重要性を繰り返し強調することが必要です。
- 脳梗塞再発の前兆症状の認識教育:患者さんや家族が「片麻痺、言語障害、顔面神経麻痺」などの脳梗塞の前兆症状を認識し、これらの症状が出現した場合に即座に医師に報告することの重要性を強調します。
- 栄養管理と食事の工夫:患者さんが「食べることを忘れる」「何を食べるか判断できない」ため、家族が食事を準備し、患者さんが栄養を摂取できるよう支援することが重要です。また、患者さんが独居している場合は、配食サービスなどの社会的リソースの活用が重要です。
- 家族への教育とサポート体制の構築:認知症患者さんの家族は、患者さんのケアに伴う身体的・心理的負担が大きいため、家族自身の心理的ケアと、利用可能な社会的リソース(デイサービス、ショートステイ、認知症カフェなど)に関する情報提供が重要です。
- リハビリテーションの促進:脳梗塞直後のリハビリテーションが、失われた機能の回復に最も有効です。患者さんと家族に対して、リハビリテーションの重要性を強調し、継続的な取り組みを支援することが重要です。
よくある疑問・Q&A
Q: 血管性認知症と診断されました。治りますか?
A: 血管性認知症は、脳梗塞により失われた脳組織は回復しないため、完全には治りません。しかし、脳血管疾患の再発を予防することで、認知機能の低下をそれ以上進めない、あるいは一部の機能を回復させることは可能です。つまり、血管性認知症は、「完全には治らないが、管理により進行を遅延させることができる認知症」です。
Q: 認知症が進行していることを患者さん自身に伝えるべきですか?
A: これは、患者さんの認知機能低下の程度、そして患者さんと家族の希望により異なります。患者さんが自分の障害をある程度認識している場合は、正直で思いやりのある情報提供が重要です。一方で、患者さんが自分の障害を全く認識していない場合は、無理に認識させる必要はありません。重要なのは、患者さんの尊厳と心理的安定を保つことです。
Q: 血管性認知症の患者さんが、自分が認知症であることを否定しています。何ができますか?
A: 多くの認知症患者さんは、自分の認知障害を認識することの心理的苦痛から、無意識のうちに否定することがあります。患者さんの否定を否定するのではなく、患者さんの現在の状態を受け入れ、できることに焦点を当てることが重要です。同時に、家族に対して、患者さんの否定の背景にある心理的苦痛を理解させることが重要です。
Q: 血管性認知症の患者さんが、脳梗塞を繰り返しています。何ができますか?
A: 脳梗塞の繰り返しは、血管疾患の危険因子が十分にコントロールされていない可能性があります。医師に相談して、以下の対策を検討することが重要です。高血圧の厳格なコントロール、脂質異常症の管理、糖尿病の管理、抗血小板薬または抗凝固薬の用量調整、喫煙の中止。
Q: 血管性認知症の患者さんが、アルツハイマー病の治療薬を処方されています。効果がありますか?
A: アルツハイマー病治療薬(アセチルコリンエステラーゼ阻害薬など)が、血管性認知症に対しても一定の効果を示すことがあります。ただし、血管性認知症は脳血管障害による認知症であり、アルツハイマー病の病態とは異なるため、効果は限定的です。最も重要なのは、脳梗塞再発予防のための危険因子管理です。
Q: 血管性認知症の患者さんが、感情的に不安定です。泣いたり、怒ったり、笑ったりします。これは何ですか?
A: これは、突発的感情表現障害と呼ばれる症状で、血管性認知症に特に多い症状です。脳の感情調整中枢が脳梗塞により障害される場合に起こります。これは、患者さんの意思によるものではなく、脳の損傷による症状です。家族に対して、患者さんを責めないこと、そして患者さんの感情表現に落ち着いて対応することが重要です。
Q: 血管性認知症の患者さんが、独居しています。安全ですか?
A: 認知機能が著しく低下している場合、患者さんが独居することは、安全上のリスクが高いです。患者さんが火をつけたまま忘れたり、ガスを付けたまま忘れたり、無断外出したりする可能性があります。家族や医療チームと相談して、以下の選択肢を検討することが重要です。配食サービス、デイサービス、ショートステイ、施設入所、家族との同居、など。
Q: 血管性認知症の患者さんが、脳梗塞の前兆症状を示しています。何をしたらよいですか?
A: 「片麻痺、言語障害、顔面神経麻痺、視野障害」などの脳梗塞の前兆症状が出現した場合は、躊躇なく119番通報して医師の診察を受けることが重要です。脳梗塞は、発症から数時間以内の治療開始が予後を大きく左右するため、初期対応が極めて重要です。
Q: 血管性認知症と診断されてから、患者さんの性格が変わりました。何が起こっているのですか?
A: 脳梗塞により、人格や感情を調整する脳領域が障害される場合があります。この結果、患者さんの性格が変わることがあります。例えば、「温厚だった人が、怒りっぽくなった」「社交的だった人が、内向的になった」などのような変化です。これは、患者さんの本質が変わったのではなく、脳の損傷による症状です。家族に対して、この変化が患者さんの脳の損傷によるものであることを説明し、患者さんへの対応方法をアドバイスすることが重要です。
Q: 血管性認知症の患者さんが、配偶者に暴力を振るいます。何ができますか?
A: 認知症患者さんの暴力や暴言は、多くの場合、認知症に伴う行動心理症状(BPSD)です。患者さんが意図的に暴力を振るっているのではなく、脳の損傷による症状です。配偶者が身の危険を感じる場合は、以下の対策が重要です。医師に相談して、薬物療法(抗精神病薬など)の検討、環境設定の工夫、カウンセリング、必要に応じて一時的な分離(デイサービス、ショートステイなど)。配偶者自身の心理的ケアも重要です。
まとめ
血管性認知症は、アルツハイマー病に次いで、認知症の第2位の原因であり、かつ最も予防・改善の可能性がある認知症です。
脳血管疾患の危険因子(高血圧、脂質異常症、糖尿病、喫煙)を適切に管理することで、脳梗塞や脳出血の再発を予防し、認知症の進行を遅延させることが可能です。この点が、アルツハイマー病と異なり、極めて重要です。
看護の役割は、患者さんと家族に対して、「血管性認知症は治療・予防が可能な認知症である」という希望を持たせ、継続的な危険因子管理と医学的フォローアップに取り組ませることです。
患者さんが認知機能低下により、自分で薬を飲むことや、危険因子の管理ができなくなった場合は、家族による支援が極めて重要になります。看護師は、患者さんだけでなく、家族に対する教育と支援が重要です。
認知症に伴う行動心理症状(感情的不安定性、暴力、無断外出など)への対応は、患者さんの脳の損傷による症状であることを家族に理解させ、患者さんを責めないよう指導することが重要です。
患者さんが認知機能低下により、日常生活活動が困難になっていく過程において、患者さんの尊厳と自尊心を保つための支援が重要です。同時に、家族が患者さんのケアに伴う身体的・心理的負担を経験しないよう、社会的リソース(デイサービス、ショートステイ、認知症カフェなど)の活用と、家族自身の心理的ケアが不可欠です。
実習では、認知症患者さんの認知機能低下の多様な現れ方を理解し、患者さんが尊厳を保ちながら社会との関係を保つための支援をすることの重要性を学ぶ貴重な機会になるでしょう。
免責事項
・本記事は教育・学習目的の情報提供です。 ・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません。 ・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください。 ・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります。 ・本記事を課題としてそのまま提出しないでください。 ・正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
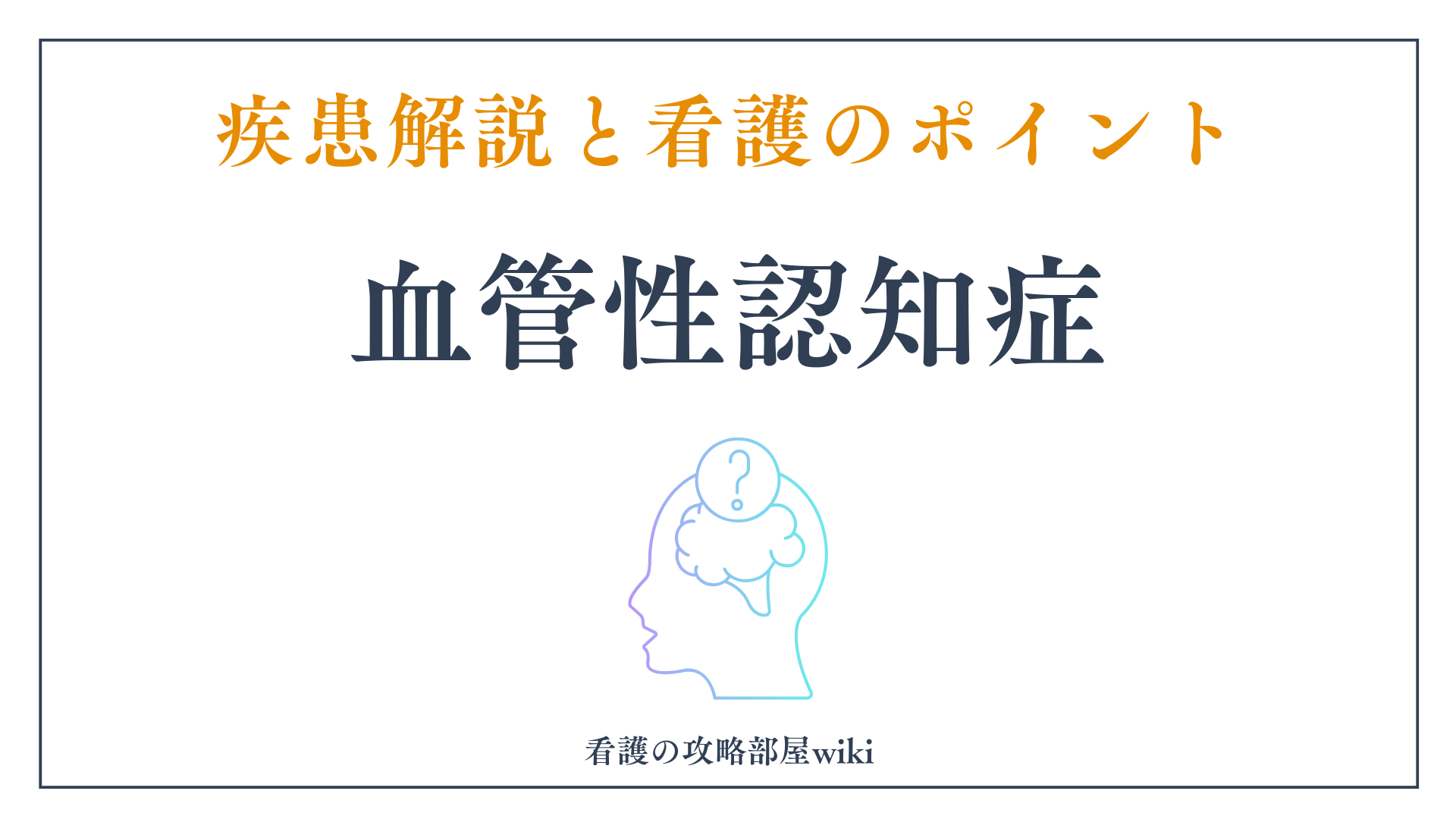
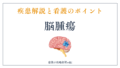
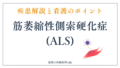
コメント