疾患概要
定義
発達障害は、脳機能の発達の偏りにより、乳幼児期から認知、言語、社会性、運動などの発達に持続的な困難を示す状態です。自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習症(LD)が主要な障害として分類されます。生来の脳の機能的特性であり、病気ではなく特性として理解されます。適切な理解と支援により、その人らしい社会参加と自立した生活が可能となる状態です。早期発見・早期支援により、二次的な問題の予防と適応能力の向上が期待できます。
疫学
発達障害の有病率は全人口の約6-10%とされ、決して稀な状態ではありません。自閉スペクトラム症は約1-2%、ADHDは約3-7%、学習症は約2-10%の有病率です。男女比は障害により異なり、ASDとADHDは男性に多く(3-4:1)、学習症でも男性にやや多い傾向があります。近年、診断基準の変更と社会の理解向上により診断例が増加していますが、これは真の増加というより適切な診断がなされるようになったと考えられています。成人期の診断も増加しており、生涯にわたる特性として認識されています。
原因
発達障害の原因は多因子性で、遺伝的要因と環境要因の相互作用により生じます。遺伝的要因では複数の遺伝子の組み合わせが関与し、家族内発症率は一般人口より高くなります。脳画像研究では前頭前野、側頭葉、小脳などの構造・機能異常が報告されています。環境要因では周産期の問題(低出生体重、早産、仮死など)、感染症、外傷などが関与する可能性が示唆されていますが、決定的な原因は特定されていません。ワクチン接種との関連性は科学的に否定されており、親の育て方が原因という考えも誤りです。
病態生理
発達障害では脳の神経ネットワークの発達に偏りが生じます。自閉スペクトラム症では社会的認知に関わる脳領域(側頭葉、前頭前野)の機能異常により、他者の心の理解、非言語コミュニケーション、社会的相互作用に困難が生じます。ADHDでは実行機能に関わる前頭前野の機能低下により、注意制御、衝動抑制、作業記憶に問題が生じます。学習症では特定の認知機能(音韻処理、視覚認知、作業記憶など)の障害により、読み書き、計算などの学習に困難が生じます。これらは神経発達の多様性として理解され、病的状態ではなく脳の個性と捉えられています。
症状・診断・治療
症状
自閉スペクトラム症では①社会的コミュニケーションの困難(視線が合わない、身振り・表情の理解困難、友人関係の形成困難)、②限定的・反復的行動(特定の興味への執着、ルーティンへのこだわり、感覚過敏・鈍麻)が主症状です。ADHDでは①不注意(集中困難、忘れ物が多い、課題の完遂困難)、②多動性(じっとしていられない、しゃべりすぎ)、③衝動性(順番を待てない、行動の結果を考えない)が認められます。学習症では読字症(文字の読み困難)、書字症(文字の書き困難)、算数症(計算困難)などの特定領域の学習困難が見られます。二次的な問題として自己肯定感の低下、不安・うつ、行動上の問題が生じることがあります。
診断
診断は発達歴、行動観察、心理検査、医学的評価を総合して行われます。DSM-5やICD-11の診断基準に基づき、多職種チーム(小児精神科医、臨床心理士、言語聴覚士、作業療法士)による評価が重要です。発達検査では新版K式発達検査、田中ビネー知能検査、WISC-IVなどにより認知プロフィールを評価します。自閉症評価ではADOS-2、ADI-R、ADHD評価ではConners評価尺度、ADHD-RSなどの標準化された評価ツールを使用します。医学的評価では神経学的検査、聴力検査、必要に応じた脳画像検査により器質的疾患を除外します。早期診断(1歳半-3歳)により早期療育が可能となります。
治療
発達障害の根本的治療法はありませんが、療育・支援により適応能力の向上が期待できます。療育では応用行動分析(ABA)、構造化教育(TEACCH)、社会的スキル訓練(SST)、認知行動療法(CBT)などが用いられます。薬物療法はADHDの注意欠如・多動性に対する刺激薬(メチルフェニデート)、非刺激薬(アトモキセチン)、二次的な問題(不安、うつ、睡眠障害)に対する薬物が使用されます。多職種連携により個別支援計画を策定し、医療、教育、福祉、家族が協働して支援を行います。環境調整(構造化、視覚的支援、感覚調整)により本人の特性に配慮した環境を整備します。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 社会的相互作用の障害:社会的コミュニケーション能力の困難
- 成長発達の変調:発達の偏りによる年齢相応の発達課題達成困難
- 家族過程の機能不全:診断受容と長期的支援による家族の負担
ゴードン機能的健康パターン
認知・知覚パターンでは認知機能の強みと弱み、学習スタイル、感覚処理の特徴(過敏・鈍麻)を詳細にアセスメントします。役割・関係パターンでは社会的スキル、対人関係能力、集団適応状況を評価し、自己概念・自己認識パターンでは自己理解、自己肯定感、将来への希望を把握します。対処・ストレス耐性パターンでは環境変化への適応能力、ストレス反応、問題行動の出現状況を評価し、価値・信念パターンでは本人・家族の障害受容、支援に対する考え方を理解します。
ヘンダーソン14基本的ニード
コミュニケーションをとるでは本人に適したコミュニケーション方法(視覚的支援、構造化、明確な指示)を見つけ、効果的な意思疎通を支援します。学習するでは本人の認知特性に配慮した学習方法、環境調整、個別支援計画の実施を支援します。遊び、レクリエーション活動に参加するでは本人の興味・関心を活かした活動参加、社会参加の機会提供を支援します。働くこと、達成感を得るでは将来の自立に向けた職業準備、就労支援、社会参加の促進を支援します。
看護計画・介入の内容
- 個別性の理解・強みの発見:本人の認知特性と感覚特性の詳細評価、強みと興味の発見、個別支援計画の策定、本人中心の支援体制構築
- コミュニケーション支援:本人に適したコミュニケーション方法の確立、視覚的支援ツールの活用、構造化されたコミュニケーション環境の整備、社会的スキルの段階的習得支援
- 家族支援・環境調整:家族の障害理解と受容支援、家族のストレス軽減、兄弟姉妹への配慮、学校・地域との連携、長期的な支援体制の構築
よくある疑問・Q&A
Q: 発達障害は治る病気ですか?将来普通に生活できるようになりますか?
A: 発達障害は病気ではなく脳の個性・特性であり、治すものではありません。しかし、適切な理解と支援により大幅な改善が期待でき、多くの方が自立した社会生活を送っています。重要なのは本人の特性を理解し、強みを活かした支援を行うことです。早期からの療育により社会適応能力は向上し、就学・就労・結婚を経験している方も多くいます。完全に定型発達と同じになることは困難ですが、その人らしい充実した人生を送ることは十分可能です。個人差が大きいため、本人のペースに合わせた長期的な支援が重要です。
Q: 薬を飲めば症状は改善しますか?副作用はありませんか?
A: 発達障害の根本的な特性を変える薬はありませんが、ADHDの注意欠如・多動性に対しては有効な薬物があります。刺激薬(コンサータ、リタリン)や非刺激薬(ストラテラ、インチュニブ)により集中力向上、多動性・衝動性の軽減が期待できます。副作用として食欲低下、睡眠障害、成長への影響などがありますが、適切な管理により多くは対処可能です。薬物療法は補助的手段であり、療育・環境調整との組み合わせが重要です。二次的な問題(不安、うつ、睡眠障害)に対する薬物も使用されることがあります。定期的な効果判定と副作用チェックにより安全な治療が可能です。
Q: 普通学級と支援学級、どちらが良いのでしょうか?
A: 教育環境の選択は本人の特性、支援ニーズ、将来目標を総合的に考慮して決定します。普通学級では同年齢集団との交流、多様な学習機会がメリットですが、個別支援が不十分になる可能性があります。支援学級では個別的な配慮、スモールステップの学習、構造化された環境が提供されますが、社会性の学習機会が限定される場合があります。通級指導や合理的配慮により普通学級での学習も可能です。本人の特性(知的レベル、社会性、感覚特性)を詳細に評価し、教育チーム(保護者、教師、専門職)で十分検討することが重要です。選択は固定的ではないため、状況に応じて変更も可能です。
Q: 将来就職できますか?どのような職業に向いているのでしょうか?
A: 発達障害のある方の就職率は向上しており、多様な職業で活躍されています。障害者雇用では法定雇用率(2.3%)により雇用機会が確保され、就労移行支援、ジョブコーチなどの支援制度も充実しています。向いている職業は個人の特性により異なりますが、ASDでは規則性のある作業、専門性を活かせる仕事(IT、研究、図書館業務)、ADHDでは創造性を活かせる仕事(デザイン、営業、接客)が向いている場合があります。就労準備としてソーシャルスキル訓練、職業訓練、インターンシップなどが有効です。継続就労のためには職場の理解、適切な配慮、定期的な支援が重要で、就労定着支援制度も活用できます。
まとめ
発達障害は脳機能の発達の偏りによる生来の特性として、病気ではなく個性の一つとして理解されています。適切な理解と支援により、多くの方がその人らしい社会参加と自立した生活を実現しており、現在では決して特別なことではない状態として認識されています。
看護の要点は個別性の理解と強みに焦点を当てた支援です。発達障害は一人ひとり特性が大きく異なるため、詳細なアセスメントにより本人の認知特性、感覚特性、コミュニケーションスタイルを理解することが支援の出発点となります。欠点の修正ではなく強みの発見と活用により、本人の自己効力感と生活の質を向上させることが重要です。
コミュニケーション支援では、本人に適した視覚的支援、構造化、明確で具体的な指示により、効果的な意思疎通を図ります。感覚過敏・鈍麻への配慮、環境の構造化、予測可能なルーティンの提供により、本人が安心して過ごせる環境を整備することが大切です。
発達支援では、本人の発達段階と認知特性に応じた個別支援計画を策定し、多職種チームによる包括的な支援を提供します。社会的スキルの段階的習得、学習方法の工夫、将来の自立に向けた準備を継続的に行うことが重要です。
家族支援は発達障害支援の重要な柱です。診断時のショック、将来への不安、日々の育児ストレス、兄弟姉妹への影響など、家族が抱える多様な問題に包括的に対応し、正確な情報提供と継続的な励ましにより、家族が希望を持って支援に取り組めるよう支援します。
社会資源の活用では、療育機関、教育機関、福祉サービス、就労支援機関など、ライフステージに応じた適切なサービスの利用を支援し、切れ目のない支援体制を構築することが重要です。
啓発・理解促進も重要な看護の役割です。発達障害に対する正しい理解の普及、偏見の解消、インクルーシブな社会の実現に向けて、地域や職場での理解促進活動に参画することが大切です。
実習では本人のユニークな特性を理解し、その人らしさを大切にする視点が重要です。発達障害は多様性の一つであり、異なる脳の働き方を持つ人々です。定型発達に近づけるのではなく、その人の特性を活かした支援により、豊かで充実した人生を送ることができることを理解し、希望と可能性に満ちた看護を提供していきましょう。発達障害のある方々は社会に多様な価値をもたらす存在であり、インクルーシブな社会の実現に向けて私たち看護職の果たす役割は大きいのです。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
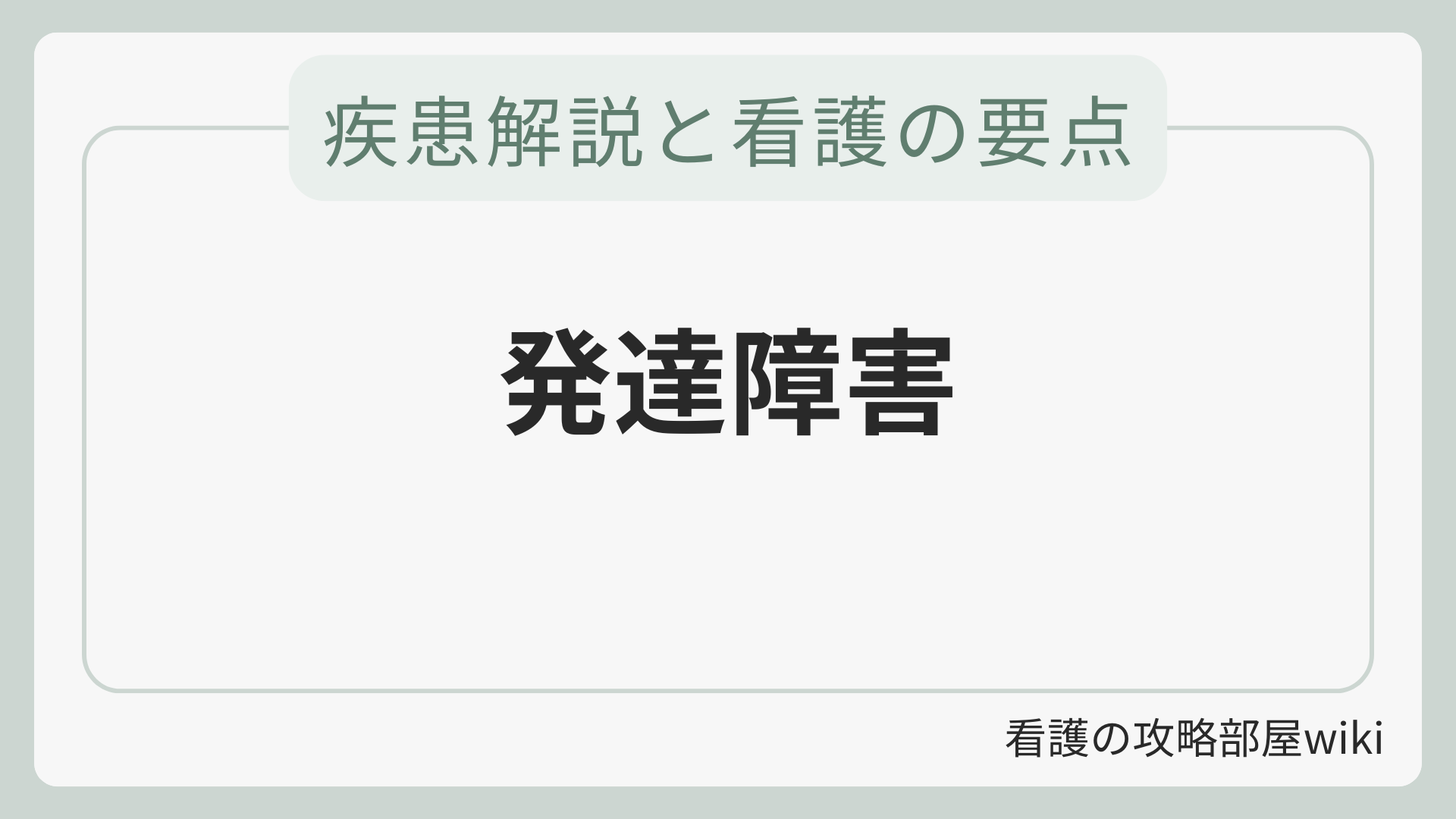
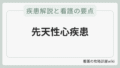
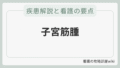
コメント