本記事では、看護師の思考プロセスを詳しく解説します。
実際の臨床では患者さんごとに状況が異なりますが、「わたしならどう考えるか」を具体的に示すことで、あなた自身の考える力を育てることを目指します。
この記事を参考に思考プロセスを学び、看護過程が得意になってもらえたら嬉しいです。
それでは、見ていきましょう。
看護学習や実習に役立つブログも運営しています✨️
ぜひ参考にしてみてくださいね!
https://kango-kouryaku.com/
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。事例は完全なフィクションであり、個別の診断・治療の根拠ではありません。実際の看護実践は患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください。本記事をそのまま課題として提出しないでください。内容の完全性・正確性は保証できず、本記事の利用により生じた損害について一切の責任を負いません。
基本情報
A氏、7歳、女児、身長119cm、体重21kg。父(38歳)、母(36歳)、弟(4歳)の4人家族で、キーパーソンは母である。小学校2年生で、学校では活発に活動しているが、体育の授業では疲れやすさを訴えることがある。性格は人懐っこく明るいが、やや内気な面もあり、初対面の人には緊張する傾向がある。感染症はなし、アレルギーは卵白に軽度のアレルギーがあり食事制限をしている。認知力は年齢相応で、会話によるコミュニケーションは良好である。
病名
完全型心房中隔欠損症(secundum型)。10月16日に開心術による心内修復術(パッチ閉鎖術)の予定である。
既往歴と治療状況
1歳6か月児健診で心雑音を指摘され、精密検査の結果、心房中隔欠損症と診断された。欠損孔の大きさは約15mmで、当初は自然閉鎖の可能性を考慮し経過観察となっていた。しかし5歳時の心エコー検査で欠損孔の縮小傾向が認められず、右心系の拡大と左右短絡率の増加が確認された。6歳時には軽度の肺高血圧症も認められ、今後の成長や心機能への影響を考慮し、7歳での手術が推奨された。これまで特に内服治療は行っておらず、年2回の定期受診で経過観察を継続していた。
入院から現在までの情報
10月13日に手術目的で小児循環器科に入院した。入院時は運動時の息切れと易疲労感を主訴としており、母によると「体育の授業の後はぐったりしている」「友達と遊んでいてもすぐに疲れて休憩する」とのことであった。入院後は術前検査として心電図、心エコー、胸部レントゲン、血液検査が実施された。10月14日には心臓カテーテル検査が全身麻酔下で施行され、肺動脈圧や短絡率の詳細な評価が行われた。検査後は問題なく経過し、同日夕方には歩行も可能となった。本人は入院や手術に対して不安を示しており、「痛いのは嫌だ」「早くおうちに帰りたい」と訴えることがある。母は付き添い入院をしており、父と弟は面会時間に訪れている。10月15日には麻酔科診察と術前オリエンテーションが実施され、プレパレーションとして絵本やパンフレットを用いた手術の説明が行われた。看護師が手術室や集中治療室の見学を提案したが、本人は「怖い」と拒否し、母と一緒に写真を見ながら説明を受けることを選択した。現在は明日の手術に向けて、21時以降は絶飲食の指示が出ており、点滴ルートは確保されていない。
バイタルサイン
来院時のバイタルサインは、体温36.8℃、血圧98/62mmHg、脈拍92回/分(整)、呼吸数22回/分、SpO2 96%(room air)であった。現在(10月15日17時)のバイタルサインは、体温36.5℃、血圧102/64mmHg、脈拍88回/分(整)、呼吸数20回/分、SpO2 97%(room air)であり、安定している。軽度の運動負荷では脈拍が110回/分程度まで上昇し、SpO2は94%まで低下するが、休息により速やかに回復する。
食事と嚥下状態
入院前は普通食を摂取しており、食事摂取量は良好で偏食はほとんどない。ただし卵白アレルギーがあるため、卵を含む食品は除去している。嚥下機能は正常で、誤嚥のリスクはない。食事は1日3回規則正しく摂取しており、間食は適度に取っている。入院後も小児食(卵除去食)を提供され、摂取量は8割程度である。母によると「病院のご飯は少し苦手みたい」とのことで、好きなおかずは完食するが、苦手なものは残すことがある。喫煙と飲酒の経験はない。
排泄
入院前の排泄状況は自立しており、排尿は日中5〜6回、夜間は0〜1回である。排便は1日1回、普通便であり、便秘や下痢の傾向はない。入院後も排泄パターンに大きな変化はなく、トイレでの排泄が自立している。カテーテル検査後は一時的に安静が必要であったが、尿器を使用して排泄することができた。下剤の使用はない。
睡眠
入院前の睡眠時間は21時から6時半頃までで、約9時間半の睡眠を取っている。睡眠の質は良好で、中途覚醒や早朝覚醒はほとんどない。入院後は環境の変化や手術への不安から、入眠に時間がかかることがあり、「眠れない」と訴える日もあった。母の付き添いにより安心感は得られているが、23時頃まで起きていることもある。夜間の睡眠時間は約7〜8時間で、やや不足気味である。眠剤等の使用はない。
視力・聴力・知覚・コミュニケーション・信仰
視力は両眼ともに1.0で、矯正は不要である。聴力も正常で、日常会話に支障はない。知覚は正常で、痛みや温度感覚の異常はない。コミュニケーション能力は年齢相応で、自分の気持ちや症状を言葉で表現することができる。ただし、初対面の医療者には緊張して口数が少なくなることがある。母や担当看護師とは良好な関係を築いており、笑顔で話すことができる。信仰は特にない。
動作状況
歩行、移乗、排尿、排泄、入浴、衣類の着脱はすべて自立している。ADLは年齢相応で、日常生活に介助は不要である。ただし、運動耐容能はやや低下しており、体育の授業や長時間の歩行では疲労感が強く出現する。階段昇降は可能であるが、数階分上ると息切れを訴える。転倒歴はなく、バランス感覚や運動機能に問題はない。
内服中の薬
現在、定期的に内服している薬はない。
検査データ
| 検査項目 | 入院時(10/13) | 最新(10/15) | 基準値 |
|---|---|---|---|
| WBC | 6800 /μL | 7200 /μL | 4000-9000 |
| RBC | 4.52 ×10⁶/μL | 4.48 ×10⁶/μL | 4.00-5.50 |
| Hb | 13.2 g/dL | 13.0 g/dL | 11.5-15.0 |
| Ht | 39.8 % | 39.2 % | 35.0-45.0 |
| PLT | 28.5 ×10⁴/μL | 27.8 ×10⁴/μL | 15.0-35.0 |
| TP | 7.1 g/dL | 7.0 g/dL | 6.5-8.0 |
| Alb | 4.3 g/dL | 4.2 g/dL | 3.8-5.0 |
| AST | 28 U/L | 26 U/L | 10-40 |
| ALT | 18 U/L | 16 U/L | 5-35 |
| BUN | 12 mg/dL | 13 mg/dL | 8-20 |
| Cr | 0.42 mg/dL | 0.40 mg/dL | 0.30-0.70 |
| Na | 140 mEq/L | 139 mEq/L | 135-145 |
| K | 4.2 mEq/L | 4.0 mEq/L | 3.5-5.0 |
| Cl | 104 mEq/L | 103 mEq/L | 98-108 |
| CRP | 0.08 mg/dL | 0.06 mg/dL | <0.30 |
| BNP | 82 pg/mL | – | <18.4 |
服薬管理は不要である。BNPの軽度上昇は心房中隔欠損症による容量負荷を反映しているが、臨床的に許容範囲内である。
今後の治療方針と医師の指示
10月16日8時30分に手術室入室予定で、開心術による心内修復術(パッチ閉鎖術)を施行する。手術時間は約4〜5時間を予定しており、術後は小児集中治療室(PICU)に入室し、人工呼吸器管理と循環動態の管理を行う。術後1〜2日で人工呼吸器から離脱し、状態が安定すれば術後3〜4日で一般病棟に転棟する予定である。術前の指示として、10月15日21時以降は絶飲食、手術当日朝は前投薬(ミダゾラムシロップ)を内服し、点滴ルート確保は手術室で実施する。術前の清潔ケアとして、10月15日夜に入浴または清拭を実施し、手術当日朝は臍処置とうがいを行う。母の付き添いは手術室入室まで可能で、面会は術後PICUで短時間可能となる予定である。
本人と家族の想いと言動
本人は「手術は痛いの?」「いつおうちに帰れるの?」と繰り返し尋ねており、手術や入院に対する不安が強い様子である。プレパレーション時には「頑張る」と言うものの、表情は硬く緊張している。「ママと一緒がいい」「弟に会いたい」との発言もあり、家族と離れることへの不安も感じられる。一方で、「手術したら元気になるんだよね」「たくさん走れるようになる?」と前向きな発言もあり、手術の必要性について一定の理解を示している。母は「この子のためだとわかっていても、やっぱり不安で仕方ない」「小さい体にメスを入れるのは辛い」と涙ぐみながら話すことがある。しかし、「先生たちを信じて、娘も頑張るって言ってるから親も頑張らないと」と前向きに捉えようとしている。父は「仕事の都合で付き添えないのが申し訳ない」「妻と娘を支えたい」と話し、面会時には娘を励まし、明るく接している。弟は「お姉ちゃん早く帰ってきて」と言いながらも、入院中の姉のために絵を描いてプレゼントするなど、家族全体で手術を乗り越えようとする姿勢が見られる。
ゴードン11項目アセスメント解説
1. 健康知覚-健康管理パターンのポイント
このパターンでは、A氏と家族が心房中隔欠損症という疾患をどのように認識し、手術という大きな治療にどう向き合っているかを評価します。7歳という発達段階を考慮しながら、本人の理解度と家族の疾患管理能力の両面からアセスメントすることが重要です。
どんなことを書けばよいか
健康知覚-健康管理パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 疾患についての本人・家族の理解度(病態、治療、予後など)
- 疾患や治療に対する受け止め方、受容の程度
- 現在の健康状態や症状の認識
- これまでの健康管理行動(受診行動、服薬管理、生活習慣など)
- 疾患が日常生活に与えている影響の認識
- 健康リスク因子(喫煙、飲酒、アレルギー、既往歴など)
本人の疾患認識と手術への理解
A氏は7歳という年齢から、疾患の病態生理を詳細に理解することは困難ですが、「手術したら元気になるんだよね」「たくさん走れるようになる?」という発言から、手術が自分の体を良くするためのものであるという基本的な理解を示していることに着目するとよいでしょう。一方で「痛いのは嫌だ」「早くおうちに帰りたい」という訴えは、手術や入院がもたらす苦痛や不安への率直な感情表現であり、学童期の子どもとして自然な反応です。プレパレーション時に「頑張る」と言いながらも表情が硬く緊張している様子は、理解と感情の間にギャップがあることを示しており、その点を踏まえて心理的支援の必要性を考えるとよいでしょう。
家族の受容状況と疾患管理
母は「この子のためだとわかっていても、やっぱり不安で仕方ない」「小さい体にメスを入れるのは辛い」と涙ぐみながらも、「先生たちを信じて、娘も頑張るって言ってるから親も頑張らないと」と前向きに捉えようとしています。この両価的な感情は、手術の必要性を理解しつつも我が子への侵襲的治療に対する葛藤を示しており、家族の心理的サポートの必要性を考える上で重要な情報となります。1歳6か月健診での心雑音指摘から現在まで年2回の定期受診を継続していることは、家族の健康管理能力が高く、医療者との協力関係が良好であることを示しており、術後の生活指導を考える上でも重要な強みとなるでしょう。
症状の認識と日常生活への影響
母による「体育の授業の後はぐったりしている」「友達と遊んでいてもすぐに疲れて休憩する」という観察は、A氏の運動耐容能低下を具体的に示しており、家族が症状の影響を適切に認識していることがわかります。本人も運動時の息切れと易疲労感を訴えており、自分の体の状態について一定の自覚があることを踏まえてアセスメントするとよいでしょう。ただし、7歳という年齢では症状と疾患の因果関係を完全に理解することは難しく、「なぜ疲れやすいのか」について発達段階に応じた説明が必要かもしれません。
健康リスク因子とアレルギー管理
卵白に軽度のアレルギーがあり、食事制限を実施していることは、家族がアレルギー管理を適切に行っていることを示しています。入院後も小児食(卵除去食)が提供され、安全に管理されている点を確認するとよいでしょう。現在は定期内服薬がなく、これまで特別な治療介入なく経過観察できていたことは、家族の負担が比較的少なかったことを意味しますが、術後は服薬管理や創部管理など新たな健康管理行動が必要になる可能性があり、その点も視野に入れて記述することが大切です。
アセスメントの視点
A氏と家族の健康知覚を評価する際は、本人の発達段階に応じた理解度、家族の疾患受容と健康管理能力、そして手術という大きなストレスイベントへの準備状態という3つの側面から統合的に捉えることが重要です。これまでの定期受診の継続やアレルギー管理の適切さは家族の強みとして評価でき、一方で手術への不安や環境変化への適応という課題も明確です。
ケアの方向性
発達段階に応じたプレパレーションの継続、家族の不安に寄り添いながら手術への準備を支援すること、そして術後の健康管理について家族の理解を深める教育的支援を計画することが重要となります。
2. 栄養-代謝パターンのポイント
このパターンでは、A氏の成長発達に見合った栄養状態、卵白アレルギーという制限がある中での食事管理、そして術前絶飲食から術後回復期の栄養管理への移行という一連の流れを評価します。小児の場合、成長に必要な栄養素の確保が特に重要となります。
どんなことを書けばよいか
栄養-代謝パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 食事と水分の摂取量と摂取方法
- 食欲、嗜好、食事に関するアレルギー
- 身長・体重・BMI・必要栄養量・身体活動レベル
- 嚥下機能・口腔内の状態
- 嘔吐・吐気の有無
- 皮膚の状態、褥瘡の有無
- 栄養状態を示す血液データ(Alb、TP、RBC、Ht、Hb、Na、K、TG、TC、HbA1c、BSなど)
成長発達と栄養状態の評価
A氏は7歳で身長119cm、体重21kgであり、この数値が成長曲線のどの位置にあるかを確認することが重要です。血液データではTP 7.0 g/dL、Alb 4.2 g/dL、Hb 13.0 g/dLといずれも基準値内にあり、栄養状態は良好に保たれていることがわかります。RBC 4.48×10⁶/μL、Ht 39.2%も正常範囲であり、心房中隔欠損症による循環動態の変化がありながらも、貧血などの栄養関連の問題は生じていないことを踏まえてアセスメントするとよいでしょう。
食事摂取状況とアレルギー管理
入院前は普通食を摂取しており、食事摂取量は良好で偏食はほとんどないという情報は、A氏の食習慣が良好であることを示しています。卵白アレルギーがあるため卵を含む食品を除去していますが、この制限下でも適切な栄養状態を維持できていることは、家族の食事管理能力の高さを示していると考えられます。入院後は小児食(卵除去食)を8割程度摂取しており、母によると「病院のご飯は少し苦手みたい」とのことですが、好きなおかずは完食するという情報から、極端な食欲低下ではなく環境変化による一時的な摂取量減少と捉えることができるでしょう。
術前絶飲食と水分・電解質バランス
10月15日21時以降は絶飲食の指示が出ており、手術当日朝まで約11時間の絶飲食期間となります。現在のNa 139 mEq/L、K 4.0 mEq/L、Cl 103 mEq/Lは正常範囲内であり、電解質バランスは保たれています。7歳児の場合、成人に比べて体液量が体重に占める割合が高く、絶飲食による脱水のリスクを考慮する必要があります。現時点では点滴ルートは確保されていませんが、手術室で確保予定であり、術前の水分・電解質管理をどう評価するか考えるとよいでしょう。
嚥下機能と誤嚥リスク
嚥下機能は正常で誤嚥のリスクはなく、7歳という年齢相応の摂食嚥下能力を有しています。この情報は術後の経口摂取再開時期を考える上で重要であり、呼吸器系の合併症がなければ比較的早期に経口摂取を開始できる可能性を示唆しています。口腔内の状態についても特記すべき問題はなく、術後の栄養摂取を妨げる要因は少ないと考えられます。
皮膚の状態と創傷治癒力
栄養状態が良好であることは、術後の創傷治癒にも有利に働くと考えられます。Albが4.2 g/dLと正常範囲にあることは、タンパク質の貯蔵が十分であり、組織修復のための材料が確保されていることを意味します。褥瘡のリスクについては、ADLが自立しており、自分で体位変換ができることから低リスクと評価できるでしょう。
アセスメントの視点
A氏の栄養-代謝パターンを評価する際は、現時点での良好な栄養状態を確認するとともに、術前絶飲食期間の管理、術後の経口摂取再開プロセス、そして成長期にある小児として継続的な栄養確保の必要性という時間軸を持って考えることが重要です。卵白アレルギーという制限がある中でも適切な栄養状態を維持できている点は、家族の食事管理能力の高さを示しており、退院後の生活指導の際の強みとなります。
ケアの方向性
術前の絶飲食期間の安全な管理、術後の経口摂取再開時期の適切な判断、卵白アレルギーに配慮した食事提供の継続、そして退院後の成長に必要な栄養摂取について家族への教育的支援を計画することが重要となります。
続きはnoteで公開中です✨️
ゴードンの続きとヘンダーソン・関連図・看護計画について解説しています😊
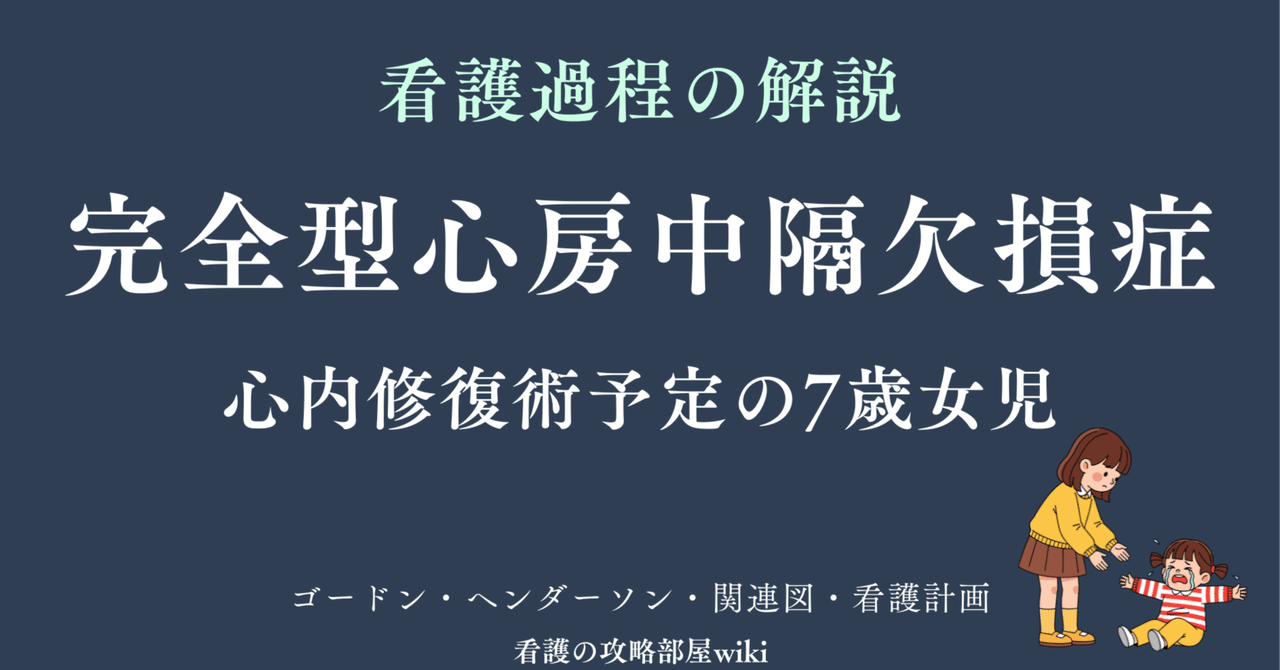
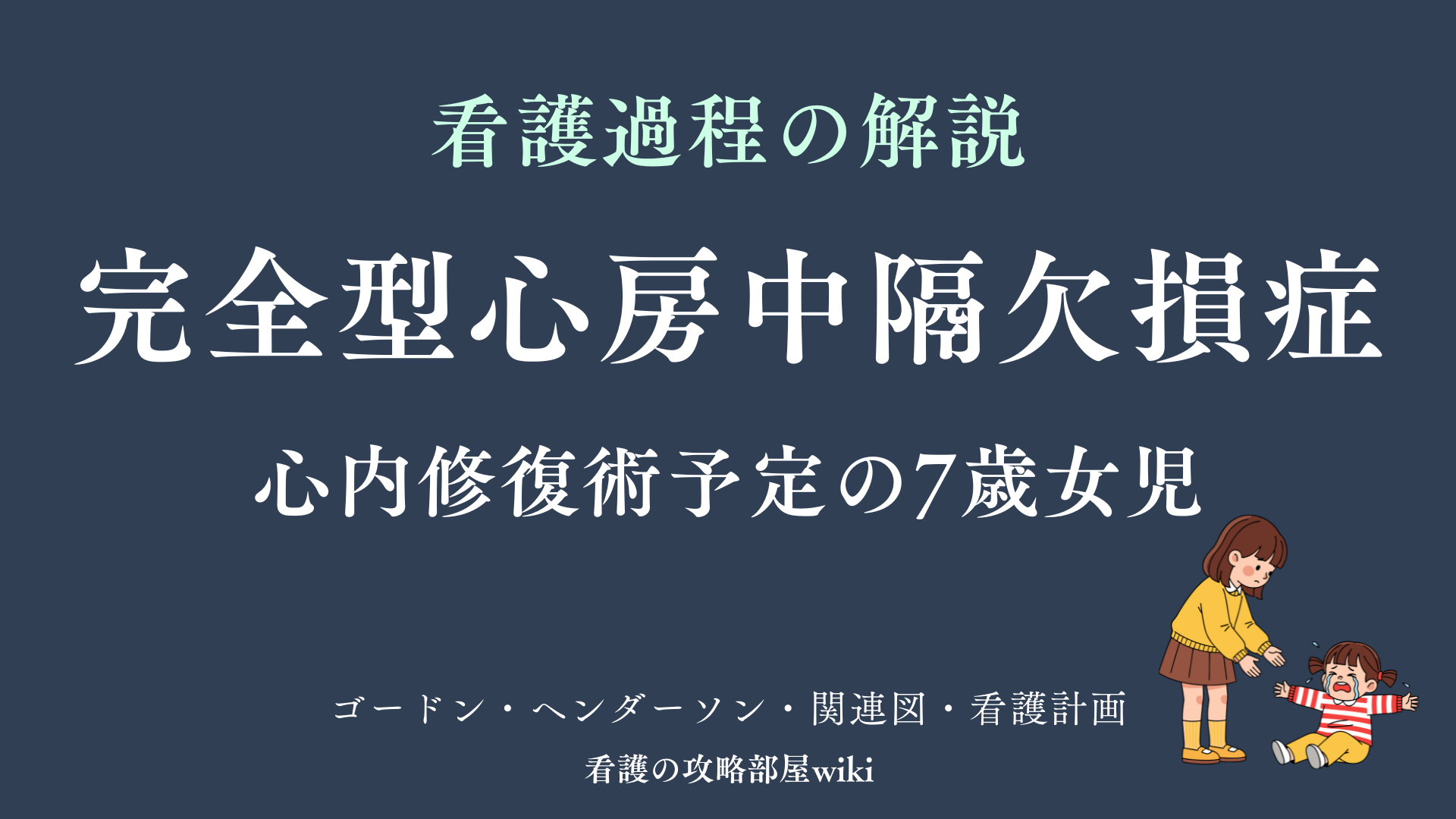


コメント