本記事では、看護師の思考プロセスを詳しく解説します。
実際の臨床では患者さんごとに状況が異なりますが、「わたしならどう考えるか」を具体的に示すことで、あなた自身の考える力を育てることを目指します。
この記事を参考に思考プロセスを学び、看護過程が得意になってもらえたら嬉しいです。
それでは、見ていきましょう。
看護学習や実習に役立つブログも運営しています✨️
ぜひ参考にしてみてくださいね!
https://kango-kouryaku.com/
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。事例は完全なフィクションであり、個別の診断・治療の根拠ではありません。実際の看護実践は患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください。本記事をそのまま課題として提出しないでください。内容の完全性・正確性は保証できず、本記事の利用により生じた損害について一切の責任を負いません。
今回の事例
基本情報
A氏は83歳の女性で、身長148cm、体重42kgである。現在は長男夫婦と3人暮らしで、キーパーソンは同居している長男の妻である。夫は2年前に他界している。職業は30年間小学校教諭として勤務し、退職後は趣味の園芸を楽しんでいた。性格は温厚で几帳面であり、教師時代は生徒思いで信望が厚かった。感染症の既往はなく、花粉症のアレルギーがある。認知機能については、HDS-Rの点数が3年前22点、2年前18点、1年前15点、直近(1月)では12点と進行性の低下を示している。
病名
アルツハイマー型認知症、誤嚥性肺炎、パーキンソニズム
既往歴と治療状況
5年前にアルツハイマー型認知症と診断され、ドネペジルの内服を開始している。認知症の進行に伴い行動・心理症状が出現し、2年前からクエチアピンの投与が開始された。また、1年前からパーキンソニズムに対してレボドパ・カルビドパ配合錠による治療が行われている。高血圧症に対して降圧薬を内服中である。服薬管理については、当初は本人が管理していたが、内服忘れや重複服用があったため、入院前は長男の妻が管理していた。現在は看護師が管理しており、内服時は確実に服用できているか確認している。
入院から現在までの情報
1月15日に自宅で転倒し救急搬送された。入院後は環境の変化により見当識障害が増悪し、「ここは学校?」「授業の準備をしないと」などの発言が頻回にみられるようになった。入院3日目より発熱と呼吸状態の悪化を認め、誤嚥性肺炎と診断された。抗生剤投与が開始されたが、食事摂取量は著しく低下し、拒否的な態度もみられている。入院7日目の現在も誤嚥性肺炎の治療を継続中である。
バイタルサイン
来院時は体温36.8℃、脈拍78回/分・整、血圧142/88mmHg、呼吸数18回/分、SpO2 96%(室内気)であった。現在(入院7日目)は体温37.8℃、脈拍92回/分・整、血圧136/82mmHg、呼吸数24回/分、SpO2 93%(酸素2L/分 経鼻カニューレ)である。呼吸音は両側下肺野で湿性ラ音を聴取している。
食事と嚥下状態
入院前は長男の妻が準備した食事を自力で摂取していたが、食事の途中で忘れてしまうことや、むせ込みが時々みられていた。嚥下機能の低下により、食事形態は常食から一口大に変更されていた。現在は認知機能低下と誤嚥性肺炎の影響により、全介助での食事摂取となっている。食事形態はミキサー食で、とろみ剤を使用し、一回量を少なくして時間をかけて摂取している。摂取量は3割程度で、拒否がみられることもある。喫煙歴、飲酒歴はない。
排泄
入院前は日中のトイレ動作は自立していたが、夜間は失禁がみられることがあった。現在はベッド上での安静が必要であり、オムツを使用している。排便コントロールは良好で、下剤の使用はない。
睡眠
入院前は夕方からの帰宅願望や夜間の不穏があり、「家に帰りたい」「主人が待っているの」との訴えが強く、不眠がみられていた。クエチアピンの内服により、不穏は若干改善していた。現在は日中の覚醒が悪く、夜間も環境の変化により睡眠リズムが乱れている。眠剤は使用していない。
視力・聴力・知覚・コミュニケーション・信仰
視力は軽度の老眼があり、読書時には眼鏡を使用している。聴力は年齢相応で、普通の会話は可能である。知覚に関して、温痛覚や触覚に異常はない。コミュニケーションについては、簡単な質問への応答は可能だが、内容の一貫性を欠くことが多い。特に教師時代の長期記憶は保たれており、その時期の話をすると表情が明るくなる。信仰は特にない。
動作状況
入院前は室内での歩行は自立していたが、パーキンソニズムの影響で小刻み歩行がみられ、屋外では杖を使用していた。移乗動作は自立していたものの、動作が緩慢で見守りを要していた。排泄は日中であれば自力でトイレまで移動し、動作も可能であった。入浴は長男の妻の介助のもと、週3回自宅の浴室で行っていた。更衣は自立していたが、着る順番を間違えることがあり、見守りを要していた。転倒歴については、今回の入院の3ヶ月前に自宅で転倒し、右膝を打撲している。現在は誤嚥性肺炎の治療のため、ベッド上での安静が必要な状態である。
内服中の薬
- ドネペジル錠5mg 1回1錠 1日1回 朝食後
- クエチアピン錠25mg 1回1錠 1日1回 夕食後
- レボドパ・カルビドパ配合錠 1回1錠 1日3回 毎食後
- アムロジピン錠5mg 1回1錠 1日1回 朝食後
- セフトリアキソン注射用1g 1回1g 1日2回 点滴静注(肺炎治療のため)
検査データ
| 検査項目 | 基準値 | 入院時(1/15) | 現在(1/22) |
|---|---|---|---|
| WBC | 3300-8600/μL | 12500 | 10800 |
| RBC | 386-492×10⁴/μL | 389 | 382 |
| Hb | 11.6-14.8g/dL | 10.8 | 10.2 |
| Ht | 35.1-44.4% | 32.5 | 31.8 |
| Plt | 15.8-34.8×10⁴/μL | 22.5 | 24.2 |
| TP | 6.6-8.1g/dL | 6.2 | 5.8 |
| Alb | 4.1-5.1g/dL | 3.2 | 2.8 |
| AST | 13-30U/L | 28 | 25 |
| ALT | 7-23U/L | 18 | 16 |
| BUN | 8-20mg/dL | 26 | 28 |
| Cre | 0.46-0.79mg/dL | 0.68 | 0.72 |
| Na | 138-145mEq/L | 140 | 138 |
| K | 3.6-4.8mEq/L | 4.2 | 4.0 |
| Cl | 101-108mEq/L | 104 | 102 |
| CRP | 0-0.14mg/dL | 3.8 | 2.6 |
| 血糖 | 73-109mg/dL | 98 | 102 |
現在の薬剤は看護師による管理である。
今後の治療方針と医師の指示
誤嚥性肺炎に対する抗生剤治療を継続しながら、安全な経口摂取の確立を目指している。医師からは、誤嚥予防のため30度以上のギャッジアップを保持すること、食事は必ずとろみ剤を使用し、一回量を少なくして時間をかけて摂取することとの指示が出ている。SpO2が90%以下となった場合は酸素流量を3L/分まで調整可能である。また、認知機能維持と生活リズム調整のため、日中の覚醒を促し、リハビリテーション科と連携してベッドサイドでの運動を実施することとなっている。退院後の療養環境について、介護保険サービスの利用拡大や施設入所も含めた検討が必要との見解が示されており、来週に多職種カンファレンスを予定している。
本人と家族の想いと言動
本人は「ここは学校?」「授業の準備をしないと」といった発言が多く、現状を十分に理解できていない様子である。時折、「家に帰りたい」「主人が待っているの」と不安な様子を見せる一方で、教師時代の思い出を語る際は表情が明るくなる。家族については、長男の妻が「できるだけ家で看たいのですが、夜も眠れず体力的に厳しくなってきました」と介護の限界を訴えている。また、「認知症が進んでしまって、どう接していいのか分からなくなることがあります」と不安を口にしており、今後の療養方針について具体的な助言を求めている。長男は仕事が忙しく、平日の面会は難しい状況だが、週末は必ず来院し、母の状態を心配している。
ゴードン11項目アセスメント解説
1. 健康知覚-健康管理パターンのポイント
健康知覚-健康管理パターンでは、患者本人と家族が疾患や治療をどのように理解し、どのように健康管理を行ってきたかを評価します。特に認知症患者の場合、本人の病識と家族の疾患理解や管理能力の両面からアセスメントすることが重要です。
どんなことを書けばよいか
健康知覚-健康管理パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 疾患についての本人・家族の理解度(病態、治療、予後など)
- 疾患や治療に対する受け止め方、受容の程度
- 現在の健康状態や症状の認識
- これまでの健康管理行動(受診行動、服薬管理、生活習慣など)
- 疾患が日常生活に与えている影響の認識
- 健康リスク因子(喫煙、飲酴、アレルギー、既往歴など)
本人の疾患認識と病識
A氏は認知症の進行により、現在の健康状態を十分に理解できていない状況にあります。「ここは学校?」「授業の準備をしないと」という発言からは、入院という状況や自身の疾患について適切な認識を持つことが困難な状態であることが読み取れます。HDS-Rが直近で12点という結果は、見当識障害や記憶障害が著明であることを示しており、疾患に対する病識の欠如がどのように療養行動に影響するかという視点でアセスメントすることが重要です。特に誤嚥性肺炎の治療において、安静の必要性や食事摂取の重要性を理解できないことが、治療の妨げとなる可能性を考慮するとよいでしょう。
家族の疾患理解と健康管理能力
キーパーソンである長男の妻は、入院前から服薬管理を担当しており、食事形態の調整やむせ込みへの対応も行っていたことから、一定の健康管理能力を持っていると考えられます。しかし「認知症が進んでしまって、どう接していいのか分からなくなることがあります」という発言には、認知症の進行に伴う対応の困難さと、具体的なケア方法についての知識不足が表れています。さらに「できるだけ家で看たいのですが、夜も眠れず体力的に厳しくなってきました」という訴えからは、介護負担が限界に達していることが読み取れます。家族の疾患理解と管理能力、そして介護継続の可能性を総合的にアセスメントする必要があります。
これまでの健康管理行動
A氏は5年前にアルツハイマー型認知症と診断されて以降、ドネペジルの内服を継続しており、行動・心理症状に対するクエチアピン、パーキンソニズムに対するレボドパ・カルビドパ配合錠、高血圧に対する降圧薬と、複数の疾患に対して適切に治療を受けてきたことがわかります。当初は本人が服薬管理をしていましたが、認知機能低下により内服忘れや重複服用が生じたため、家族が管理に移行したという経過は、疾患の進行に応じて健康管理体制を調整してきたことを示しています。この家族の対応能力と柔軟性は、退院後の療養計画を考える上で重要な強みとなります。
健康リスク因子
A氏には喫煙歴・飲酒歴はなく、これらのリスク因子は認められません。花粉症のアレルギーがありますが、現在の入院治療に直接影響する要因ではないと考えられます。むしろ、認知症の進行そのものが最大の健康リスク因子となっており、見当識障害による転倒リスク、嚥下機能低下による誤嚥リスク、服薬管理困難によるアドヒアランス低下など、多面的なリスクをもたらしていることを認識する必要があります。
アセスメントの視点
本人の病識欠如と家族の疾患理解・管理能力のギャップに着目することが重要です。A氏自身は疾患を認識できていないため、治療への協力を得ることが困難ですが、家族は一定の健康管理能力を持ちつつも、介護負担の増大により継続が困難になってきています。これまでの健康管理行動の実績と現在の限界、そして今後必要となる支援体制をバランスよく評価することが求められます。
ケアの方向性
家族の疾患理解を深めるための教育的支援と、介護負担軽減のための社会資源活用が重要です。本人への直接的な疾患説明は困難ですが、日々のケアの中で安心感を提供し、治療への協力を引き出す工夫が必要です。また、退院後の服薬管理や誤嚥予防など、家族だけでは対応困難な部分について、訪問看護や介護サービスの導入を検討する必要があります。
2. 栄養-代謝パターンのポイント
栄養-代謝パターンでは、食事摂取状況と嚥下機能、そして栄養状態を総合的に評価します。誤嚥性肺炎を発症した高齢認知症患者の場合、嚥下機能低下と認知機能低下が相互に影響し合い、栄養状態の悪化をもたらす可能性があることを意識してアセスメントする必要があります。
どんなことを書けばよいか
栄養-代謝パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 食事と水分の摂取量と摂取方法
- 食欲、嗜好、食事に関するアレルギー
- 身長・体重・BMI・必要栄養量・身体活動レベル
- 嚥下機能・口腔内の状態
- 嘔吐・吐気の有無
- 皮膚の状態、褥瘡の有無
- 栄養状態を示す血液データ(Alb、TP、RBC、Ht、Hb、Na、K、TG、TC、HbA1c、BSなど)
食事摂取状況の変化
入院前のA氏は、長男の妻が準備した食事を自力で摂取していましたが、食事の途中で忘れてしまうことがあり、認知機能低下が食事行動に影響を与えていたことがわかります。現在は誤嚥性肺炎の影響により、摂取量が3割程度まで低下し、拒否的な態度もみられています。この摂取量の著しい低下は、入院という環境変化、誤嚥性肺炎による全身状態の悪化、認知症の進行による食事認識の困難さなど、複数の要因が関連していると考えられます。3割という摂取量が、必要栄養量と比較してどの程度不足しているのか、また拒否がどのような状況で生じるのかを詳しく観察し、記述するとよいでしょう。
嚥下機能の低下
入院前から嚥下機能の低下によりむせ込みがみられ、食事形態も常食から一口大に変更されていました。現在はミキサー食にとろみ剤を使用し、一回量を少なくして時間をかけて摂取するという対応が取られています。入院3日目に誤嚥性肺炎を発症したという事実は、入院による環境変化や見当識障害の増悪が、さらなる嚥下機能の低下や誤嚥リスクの増大につながった可能性を示しています。嚥下機能低下の程度、むせの頻度、食事中の体位、介助方法など、誤嚥を予防するための具体的な観察事項を含めて記述することが重要です。
栄養状態の評価
身長148cm、体重42kgからBMIを計算すると約19.2となり、BMI18.5以上25未満という基準範囲内ではありますが、高齢者としては決して十分とは言えない値です。血液データではAlb 3.2→2.8 g/dL、TP 6.2→5.8 g/dLと入院後に低下しており、低栄養状態が悪化していることが明らかです。Albの基準値が4.1-5.1 g/dLであることを考えると、2.8 g/dLという値は著明な低栄養状態を示しています。さらにHb 10.8→10.2 g/dL、Ht 32.5→31.8%と貧血も持続しており、これらは食事摂取量の低下と関連していると考えられます。低栄養状態は免疫機能の低下、創傷治癒の遅延、感染リスクの増大などをもたらすため、栄養状態の改善が治療上の重要な課題となることを認識する必要があります。
皮膚の状態と褥瘡リスク
事例には皮膚の状態について直接的な記載はありませんが、現在ベッド上安静が必要であること、低栄養状態であること、貧血があることなどから、褥瘡発生のリスクが高い状態にあると推測されます。特にAlb 2.8 g/dLという低値は、皮膚の脆弱性を示唆しており、圧迫による組織損傷が生じやすい状態です。褥瘡の有無、皮膚の状態、圧迫部位の発赤の有無など、詳細な観察が必要であることを記述に含めるとよいでしょう。
アセスメントの視点
栄養状態の悪化は、誤嚥性肺炎の治癒を遅らせ、免疫機能の低下により感染リスクを高めるという悪循環を生み出します。現在の食事摂取量3割という状態が継続すれば、さらなる栄養状態の悪化が予測されます。嚥下機能低下と認知機能低下の両方が食事摂取を困難にしているという複合的な問題を理解し、安全性と栄養確保のバランスを考慮したアプローチが必要です。
ケアの方向性
安全な経口摂取を確立するために、適切な食事形態、食事介助方法、誤嚥予防の体位の確保が必要です。認知症による食事認識の困難さに対しては、声かけの工夫や環境調整により、食事への意欲を引き出す支援が求められます。経口摂取のみで必要栄養量を確保することが困難な場合は、栄養補助食品の使用や、場合によっては経腸栄養の検討も必要となる可能性があります。栄養状態の改善は誤嚥性肺炎の治療にも直結するため、多職種で連携したアプローチが重要です。
続きはnoteで公開中です✨️
ゴードンの続きとヘンダーソン・関連図・看護計画について解説しています😊
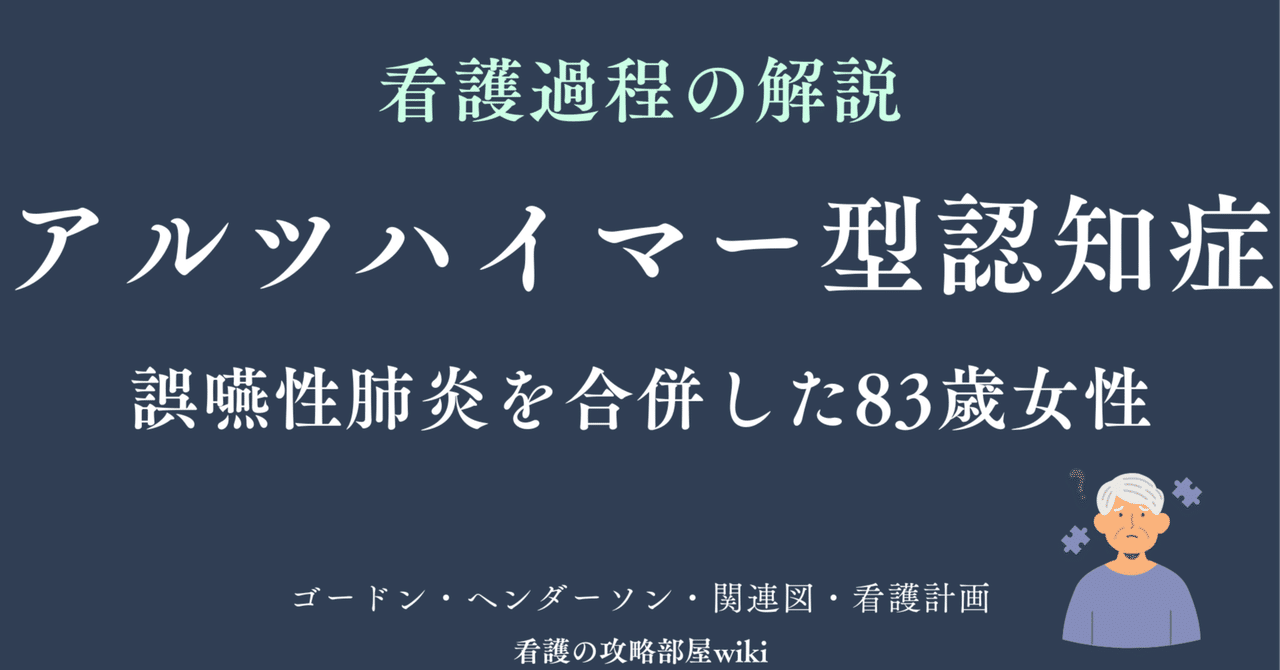
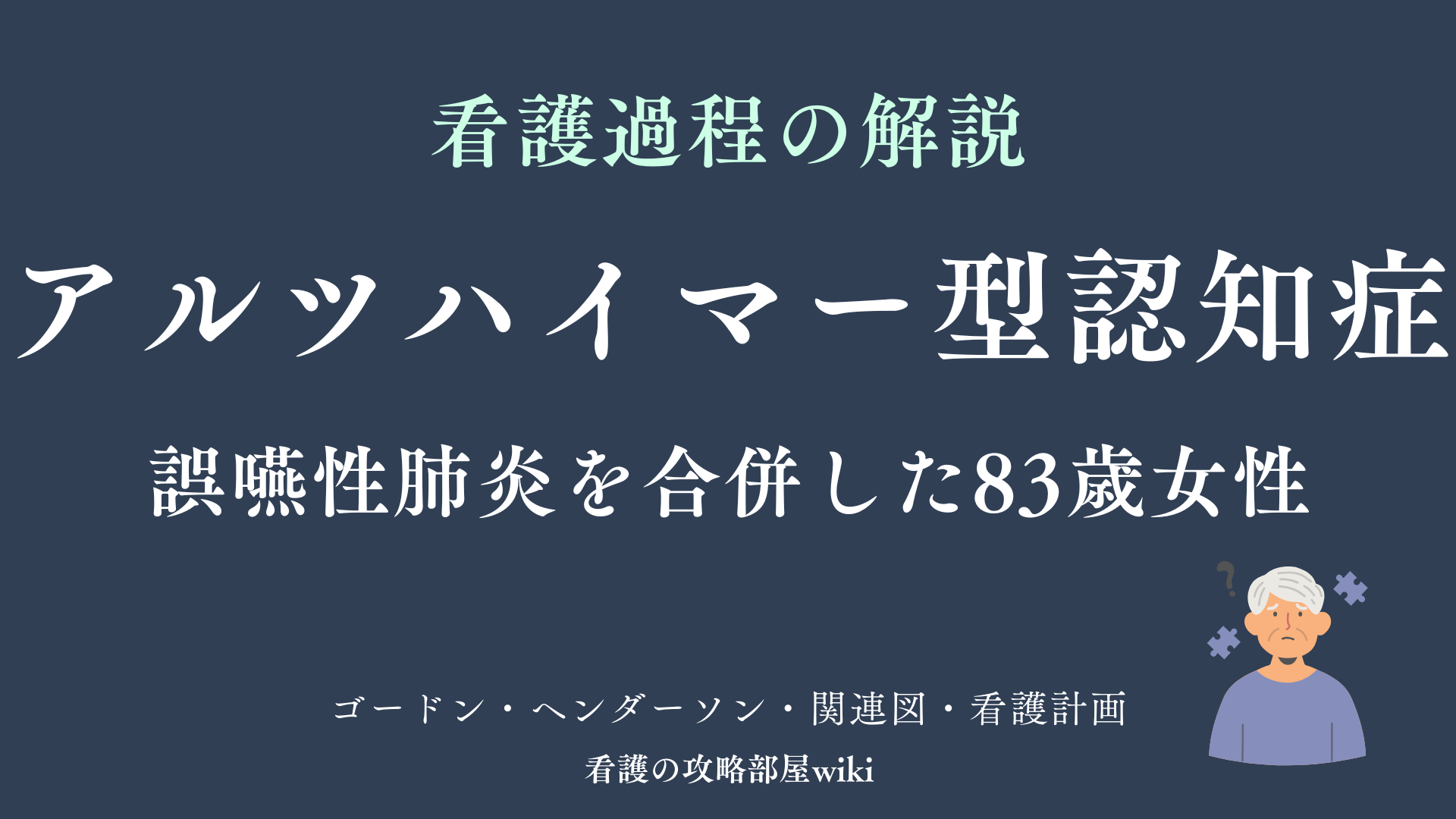

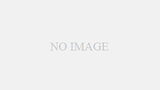
コメント