本記事では、看護師の思考プロセスを詳しく解説します。
実際の臨床では患者さんごとに状況が異なりますが、「わたしならどう考えるか」を具体的に示すことで、あなた自身の考える力を育てることを目指します。
この記事を参考に思考プロセスを学び、看護過程が得意になってもらえたら嬉しいです。
それでは、見ていきましょう。
看護学習や実習に役立つブログも運営しています✨️
ぜひ参考にしてみてくださいね!
https://kango-kouryaku.com/
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。事例は完全なフィクションであり、個別の診断・治療の根拠ではありません。実際の看護実践は患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください。本記事をそのまま課題として提出しないでください。内容の完全性・正確性は保証できず、本記事の利用により生じた損害について一切の責任を負いません。
今回の事例
基本情報
A氏、50歳、女性、身長158cm、体重56kg。家族構成は夫(52歳)と長女(22歳・社会人)、次女(19歳・大学生)の4人家族で、キーパーソンは夫である。職業は事務職で、性格は几帳面で真面目、やや心配性な傾向がある。HBs抗原陰性、HCV抗体陰性、梅毒陰性で感染症はなく、アレルギーも特にない。認知力は正常で、見当識も保たれている。
病名
右卵巣粘液性嚢胞腺腫。9月17日に腹腔鏡下右卵巣腫瘍摘出術を施行した。
既往歴と治療状況
35歳時に帝王切開による次女の出産歴がある。40歳時に子宮筋腫を指摘されたが経過観察中で、現在も月経時の過多月経があるものの特に治療は行っていない。45歳頃から高血圧を指摘され、降圧薬を内服中である。その他に特記すべき既往歴はない。
入院から現在までの情報
8月下旬から下腹部の違和感と膨満感を自覚し、9月初旬に近医を受診したところ、超音波検査で右卵巣に約8cmの腫瘤性病変を指摘された。精査目的で当院婦人科を紹介受診し、造影CTとMRI検査の結果、右卵巣粘液性嚢胞腺腫と診断された。悪性の可能性は低いものの、腫瘍径が大きく茎捻転のリスクもあるため、手術適応と判断され9月15日に入院となった。入院時は特に自覚症状は強くなく、バイタルサインも安定していた。
9月16日に術前検査と麻酔科診察を実施し、9月17日に全身麻酔下で腹腔鏡下右卵巣腫瘍摘出術を施行した。手術時間は2時間45分、出血量は少量で、術中所見では腫瘍は右卵巣から発生しており、周囲臓器への浸潤や腹水貯留は認めなかった。右卵巣のみを摘出し、左卵巣と子宮は温存された。術後は帰室後より経過観察を行い、術後1日目(9月18日)から離床を開始した。疼痛は術後から継続しているが、鎮痛薬でコントロール可能な範囲である。術後2日目(9月19日)から食事を開始し、排ガスも確認された。術後3日目(9月20日)にドレーンを抜去し、創部の状態も良好である。
現在は術後5日目(9月22日)で、疼痛は軽減傾向にあり、歩行も自立している。創部の発赤や腫脹はなく、感染徴候も認めていない。退院に向けて日常生活動作の確認と退院指導を進めている段階である。
バイタルサイン
来院時のバイタルサインは、体温36.4℃、血圧128/78mmHg、脈拍72回/分で整、呼吸数16回/分、SpO2 98%(室内気)であった。現在(術後5日目、9月22日)のバイタルサインは、体温36.8℃、血圧120/74mmHg、脈拍68回/分で整、呼吸数18回/分、SpO2 97%(室内気)であり、すべて正常範囲内で安定している。
食事と嚥下状態
入院前は自宅で普通食を摂取しており、1日3食規則正しく食べていた。食欲は良好で、嚥下障害もなかった。喫煙歴はなく、飲酒は月に1〜2回程度ビールをグラス1杯程度飲む程度であった。
現在は術後食(常食)を提供されており、食事摂取量は8割程度である。術後の疼痛や緊張から食欲がやや低下しているが、少しずつ改善傾向にある。嚥下状態は良好で、水分摂取も問題なく行えている。
排泄
入院前は自宅のトイレで自立して排泄しており、排便は1日1回、普通便であった。下剤等の使用はなく、排尿も日中5〜6回程度で特に問題はなかった。
術後は尿道カテーテルを留置していたが、術後1日目(9月18日)に抜去された。抜去後は自力排尿が可能となり、残尿感や排尿痛はない。排尿回数は日中6〜7回程度で、夜間は1回程度である。排便は術後3日目(9月20日)に初回排便があり、やや硬めの便であったが、その後は1日1回のペースで普通便が出ている。下剤の使用はしていない。
睡眠
入院前は自宅で23時頃に就寝し、6時頃に起床する生活パターンで、睡眠時間は約7時間であった。寝つきは良好で、中途覚醒もなく、熟睡感もあり、眠剤等の使用はなかった。
入院後は病院の環境に慣れないことと術後の疼痛から、やや入眠困難と中途覚醒が見られた。術後2日目(9月19日)と3日目(9月20日)は眠剤(ゾルピデム5mg)を使用したが、術後4日目(9月21日)からは眠剤なしでも入眠できるようになり、現在は睡眠時間約6時間確保できている。
視力・聴力・知覚・コミュニケーション・信仰
視力は両眼とも1.0で、眼鏡やコンタクトレンズは使用していない。聴力も正常で、補聴器等の使用はない。知覚については、四肢の感覚障害はなく、痛覚・触覚・温度覚ともに正常である。コミュニケーション能力は良好で、日本語での会話に問題はなく、意思疎通もスムーズに行える。特定の信仰は持っていない。
動作状況
入院前は日常生活動作すべてにおいて自立しており、歩行、移乗、排泄、入浴、衣類の着脱はすべて介助なく行えていた。転倒歴もなかった。
術後は手術当日から術後1日目午前中までベッド上安静であったが、術後1日目(9月18日)午後から離床を開始し、看護師付き添いのもとで歩行を開始した。術後2日目(9月19日)からは病棟内を自立歩行しており、トイレへの移動も自立している。移乗や排泄、衣類の着脱も自立して行えている。入浴はまだ許可されていないが、清拭は自分で行えている。転倒のリスクは低く、術後の回復は順調である。
内服中の薬
- アムロジピン錠5mg 1錠 1日1回朝食後(降圧薬)
- ロキソプロフェンナトリウム錠60mg 1錠 1日3回毎食後(鎮痛薬、術後疼痛管理のため追加)
- レバミピド錠100mg 1錠 1日3回毎食後(胃粘膜保護薬、ロキソプロフェンの副作用予防)
検査データ
| 項目 | 入院時(9/15) | 術後3日目(9/20) | 基準値 |
|---|---|---|---|
| WBC(白血球) | 6,800 /μL | 9,200 /μL | 3,300-8,600 /μL |
| RBC(赤血球) | 4.25 ×10⁶/μL | 3.98 ×10⁶/μL | 3.86-4.92 ×10⁶/μL |
| Hb(ヘモグロビン) | 13.2 g/dL | 11.8 g/dL | 11.6-14.8 g/dL |
| Ht(ヘマトクリット) | 39.5 % | 36.2 % | 35.1-44.4 % |
| Plt(血小板) | 268 ×10³/μL | 312 ×10³/μL | 158-348 ×10³/μL |
| CRP(C反応性蛋白) | 0.08 mg/dL | 1.52 mg/dL | 0.00-0.14 mg/dL |
| TP(総蛋白) | 7.2 g/dL | 6.8 g/dL | 6.6-8.1 g/dL |
| Alb(アルブミン) | 4.3 g/dL | 3.9 g/dL | 4.1-5.1 g/dL |
| AST | 22 U/L | 28 U/L | 13-30 U/L |
| ALT | 18 U/L | 24 U/L | 7-23 U/L |
| BUN(尿素窒素) | 14.2 mg/dL | 16.8 mg/dL | 8-20 mg/dL |
| Cr(クレアチニン) | 0.68 mg/dL | 0.72 mg/dL | 0.46-0.79 mg/dL |
| Na(ナトリウム) | 140 mEq/L | 138 mEq/L | 138-145 mEq/L |
| K(カリウム) | 4.1 mEq/L | 4.3 mEq/L | 3.6-4.8 mEq/L |
| Cl(クロール) | 103 mEq/L | 102 mEq/L | 101-108 mEq/L |
服薬は看護師管理で行っており、毎食後に看護師が配薬し、内服確認を行っている。
今後の治療方針と医師の指示
病理検査の結果は良性の粘液性嚢胞腺腫であり、悪性所見は認められなかった。術後経過は順調で、創部の治癒状態も良好であるため、9月24日(術後7日目)の退院を予定している。退院後は外来でフォローアップを行い、術後2週間後に抜糸を予定している。その後は3ヶ月後、6ヶ月後、1年後に定期受診し、超音波検査で左卵巣の状態と術後の経過観察を行う方針である。日常生活については、退院後1週間は重いものを持つことや激しい運動は避け、徐々に活動量を増やしていくよう指導されている。職場復帰は術後3週間後を目安としている。
本人と家族の想いと言動
A氏は「最初に腫瘍と言われたときは癌かもしれないと思って不安でいっぱいでしたが、良性だとわかって本当に安心しました」と話している。また、「手術の傷も思ったより小さくて、回復も早いと言われて嬉しいです。早く家に帰って普通の生活に戻りたいです」と退院を楽しみにしている様子が見られる。一方で、「左の卵巣にも何か起きないか心配です。定期的に検査を受けて、早めに異常を見つけられるようにしたいです」と今後の健康管理に対する意識も高い。
夫は「妻が手術を受けると聞いて心配でしたが、無事に終わって本当に良かったです」と安堵の表情を見せている。また、「退院後はしばらく家事などを手伝って、妻に無理をさせないようにします。娘たちにも協力してもらうつもりです」と退院後のサポート体制についても前向きに考えている。長女と次女も面会に訪れ、「お母さん、無理しないでね。家のことは私たちも手伝うから」と声をかけており、家族全体でA氏の回復を支えようとする姿勢が見られる。
ゴードン11項目アセスメント解説
1. 健康知覚-健康管理パターンのポイント
このパターンでは、A氏が卵巣腫瘍という診断をどのように受け止め、健康管理にどう取り組んできたか、今後の健康維持に向けてどのような意識を持っているかを評価します。特に婦人科疾患という特性上、女性特有の健康問題への認識や、今後の定期検診への姿勢が重要となります。
どんなことを書けばよいか
健康知覚-健康管理パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 疾患についての本人・家族の理解度(病態、治療、予後など)
- 疾患や治療に対する受け止め方、受容の程度
- 現在の健康状態や症状の認識
- これまでの健康管理行動(受診行動、服薬管理、生活習慣など)
- 疾患が日常生活に与えている影響の認識
- 健康リスク因子(喫煙、飲酒、アレルギー、既往歴など)
疾患の早期発見と受診行動
A氏は8月下旬に下腹部の違和感と膨満感を自覚した際、9月初旬には近医を受診しており、自覚症状に対する感度が高く、適切な受診行動をとれていることがわかります。この早期受診により約8cmの腫瘤性病変が発見され、茎捻転などの合併症を起こす前に手術治療につなげることができました。A氏の几帳面で真面目な性格が、身体の変化を見逃さず適切に対処する行動につながったと考えられ、この点を健康管理能力の強みとして記述するとよいでしょう。
疾患の受容と心理的適応
「最初に腫瘍と言われたときは癌かもしれないと思って不安でいっぱいでした」というA氏の言葉から、診断当初は悪性を疑い強い不安を抱いていたことが読み取れます。しかし病理検査で良性と確定した後は「本当に安心しました」と安堵を表現しており、診断結果を適切に理解し受け止められていることがわかります。また「手術の傷も思ったより小さくて、回復も早いと言われて嬉しいです」という発言からは、腹腔鏡手術の低侵襲性についても理解し、前向きに受け止めている様子が見られます。これらの発言から、A氏の疾患受容のプロセスと現在の心理状態を踏まえてアセスメントするとよいでしょう。
既往歴と健康管理の継続性
A氏は45歳頃から高血圧を指摘され、降圧薬を内服中であり、慢性疾患の管理を継続できています。また40歳時に子宮筋腫を指摘されて経過観察中であることから、婦人科疾患への関心もあったと考えられます。喫煙歴がなく、飲酒も月に1〜2回程度と節制していることから、日頃から健康的な生活習慣を心がけていたことがわかります。入院中も服薬は看護師管理下で確実に行われており、内服アドヒアランスも良好と考えられます。これらの情報から、A氏の日常的な健康管理能力を評価するとよいでしょう。
今後の健康管理への意識
「左の卵巣にも何か起きないか心配です。定期的に検査を受けて、早めに異常を見つけられるようにしたいです」という発言から、今後の健康管理に対する意識の高さが読み取れます。右卵巣を摘出したことで、残存する左卵巣への関心が高まっており、定期検診の必要性を自ら認識しています。やや心配性な性格傾向もあり、過度な不安につながる可能性も考慮しつつ、この健康意識の高さを退院後のフォローアップ継続の動機づけとして活用できると考えられます。3ヶ月後、6ヶ月後、1年後の定期受診計画が立てられていることを踏まえて記述するとよいでしょう。
アセスメントの視点
A氏は自覚症状への感度が高く、適切な受診行動がとれること、慢性疾患の管理も継続できていることから、基本的な健康管理能力は良好と評価できます。疾患の受容も段階的に進んでおり、良性との診断後は前向きな姿勢を示しています。今後の健康管理への意識も高く、定期検診への意欲も見られます。ただし、やや心配性な性格傾向があることから、過度な不安を軽減しながら、適切な健康管理行動を継続できるよう支援する視点が重要となります。
ケアの方向性
A氏の健康管理能力の高さを活かし、退院後の生活指導や定期検診の重要性について理解を深められるよう支援します。左卵巣への過度な不安には共感的に対応しつつ、定期的な検診で早期発見が可能であることを説明し、安心感を提供することが大切です。また高血圧の継続的な管理や、子宮筋腫の経過観察も含めた包括的な健康管理の視点を持てるよう支援するとよいでしょう。
2. 栄養-代謝パターンのポイント
このパターンでは、A氏の栄養状態、術前後の食事摂取状況、創傷治癒に必要な栄養素の充足状況を評価します。50歳という年齢や、術後の回復過程における栄養管理の重要性を意識してアセスメントすることが大切です。
どんなことを書けばよいか
栄養-代謝パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 食事と水分の摂取量と摂取方法
- 食欲、嗜好、食事に関するアレルギー
- 身長・体重・BMI・必要栄養量・身体活動レベル
- 嚥下機能・口腔内の状態
- 嘔吐・吐気の有無
- 皮膚の状態、褥瘡の有無
- 栄養状態を示す血液データ(Alb、TP、RBC、Ht、Hb、Na、K、TG、TC、HbA1c、BSなど)
術前の栄養状態
A氏の身長158cm、体重56kgからBMIを計算すると約22.4となり、標準体重範囲内にあります。入院前は自宅で1日3食規則正しく普通食を摂取しており、食欲も良好でした。入院時の検査データでは、TP 7.2g/dL、Alb 4.3g/dL、Hb 13.2g/dLといずれも基準値内であり、術前の栄養状態は良好と評価できます。喫煙歴がなく、飲酒も月に1〜2回程度と節制していることも、良好な栄養状態の維持に寄与していたと考えられます。これらの情報から、A氏の術前の栄養基盤を評価するとよいでしょう。
術後の食事摂取状況
術後2日目(9月19日)から食事を開始し、現在(術後5日目)は術後食(常食)を提供されており、食事摂取量は8割程度となっています。術後の疼痛や緊張から食欲がやや低下しているものの、少しずつ改善傾向にあるという記載から、術後の一時的な食欲低下は認められるものの、回復に向かっていることがわかります。嚥下状態は良好で水分摂取も問題なく行えており、経口摂取に支障はありません。食事摂取量8割という状態を、術後5日目の経過として妥当と評価できるか、さらなる摂取量増加が必要かを検討するとよいでしょう。
術後の栄養状態と創傷治癒
術後3日目(9月20日)の検査データでは、TP 6.8g/dL、Alb 3.9g/dLとやや低下していますが、これは術後の侵襲や輸液の影響として理解できる範囲です。Hb 11.8g/dLへの低下も、手術時の出血(少量ではあったものの)や術後の血液希釈の影響と考えられます。創部の発赤や腫脹はなく、感染徴候も認めておらず、術後3日目にドレーンを抜去できていることから、創傷治癒は順調に進んでいると評価できます。これらの所見を総合して、現在の栄養状態が創傷治癒に及ぼす影響をアセスメントするとよいでしょう。
水分出納バランス
術後の尿道カテーテルは術後1日目に抜去され、その後は自力排尿が可能となっています。排尿回数は日中6〜7回程度、夜間1回程度で、残尿感や排尿痛もありません。水分摂取も問題なく行えており、電解質データもNa 138mEq/L、K 4.3mEq/L、Cl 102mEq/Lと正常範囲内にあることから、水分・電解質バランスは保たれていると考えられます。In-Outバランスの観点から、術後の体液管理が適切であるかを評価するとよいでしょう。
アセスメントの視点
A氏の術前の栄養状態は良好であり、これが術後の回復を支える基盤となっています。術後5日目の時点で食事摂取量は8割程度ですが、改善傾向にあり、嚥下機能や水分摂取に問題はありません。栄養状態を示す血液データは術後のやや低下を示していますが、創傷治癒は順調に進んでおり、現時点で栄養上の大きな問題はないと評価できます。ただし、退院後の日常生活への復帰に向けて、さらなる栄養状態の改善が望ましいと考えられます。
ケアの方向性
食欲の改善傾向を支持し、摂取量を段階的に増やせるよう支援します。疼痛コントロールを適切に行い、食事に影響する要因を軽減することが大切です。創傷治癒を促進するために、タンパク質やビタミンを含む食品の摂取を意識できるよう、退院指導の中で栄養に関する情報提供を行うとよいでしょう。また、退院後も規則正しい食生活を継続し、体力回復を図れるよう支援します。
続きはnoteで公開中です✨️
ゴードンの続きとヘンダーソン・関連図・看護計画について解説しています😊
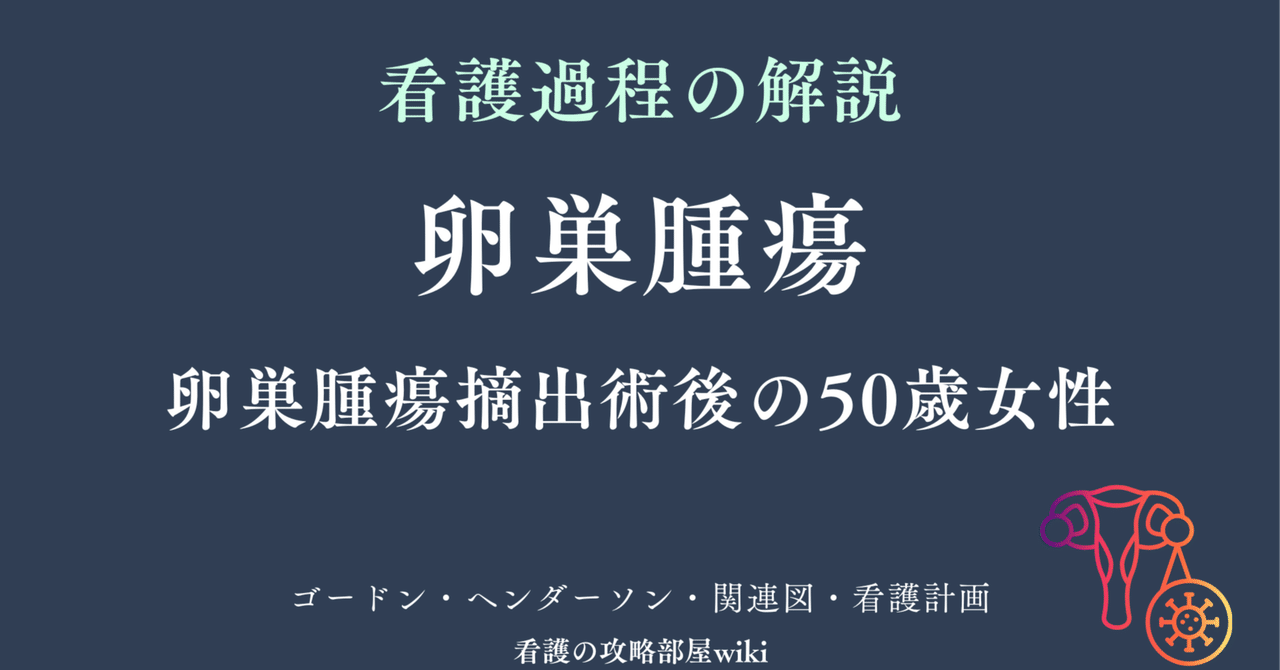
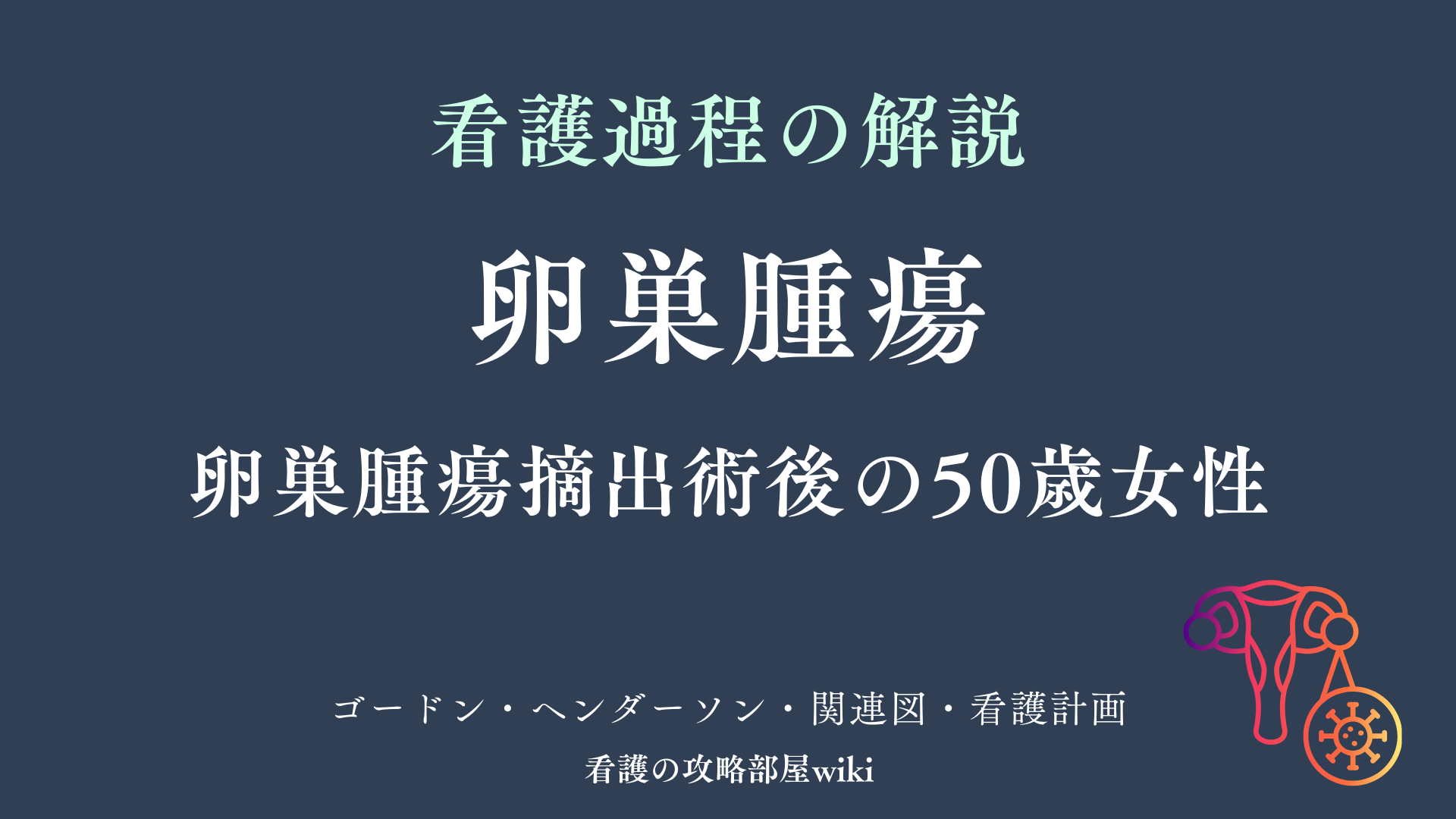


コメント