本記事では、看護師の思考プロセスを詳しく解説します。
実際の臨床では患者さんごとに状況が異なりますが、「わたしならどう考えるか」を具体的に示すことで、あなた自身の考える力を育てることを目指します。
この記事を参考に思考プロセスを学び、看護過程が得意になってもらえたら嬉しいです。
それでは、見ていきましょう。
看護学習や実習に役立つブログも運営しています✨️
ぜひ参考にしてみてくださいね!
https://kango-kouryaku.com/
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。事例は完全なフィクションであり、個別の診断・治療の根拠ではありません。実際の看護実践は患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください。本記事をそのまま課題として提出しないでください。内容の完全性・正確性は保証できず、本記事の利用により生じた損害について一切の責任を負いません。
基本情報
A氏は74歳の女性で、身長152cm、体重48kgである。家族構成は夫との二人暮らしで、キーパーソンは長女(県外在住)である。職業は元小学校教員で、現在は年金生活をしている。性格は几帳面で真面目、他者への気遣いが強い傾向がある。感染症は特になく、アレルギーは卵に対する軽度の食物アレルギーがある。認知力は良好で、MMSE 28点、HDS-R 27点と正常範囲内である。
病名
急性腎盂腎炎(右側)
既往歴と治療状況
既往歴として5年前に子宮筋腫で子宮全摘術を受けており、3年前には尿路感染症で入院加療の経験がある。また、10年前から高血圧症と脂質異常症に対して内服治療を継続している。現在は急性腎盂腎炎に対して抗菌薬治療を行っており、血圧と脂質のコントロールも継続中である。
入院から現在までの情報
10月1日に38.5℃の発熱と右側腹部痛、悪寒戦慄を主訴に近医を受診し、急性腎盂腎炎と診断され即日入院となった。入院時の尿検査で白血球と細菌が多数検出され、血液検査ではCRP 12.8mg/dLと著明な炎症反応の上昇を認めた。セフトリアキソンの点滴治療を開始し、入院3日目には解熱、5日目には炎症反応の改善傾向が見られた。入院7日目(10月7日)に経口抗菌薬へ切り替え、10月9日に退院となった。退院時のCRPは3.2mg/dLまで低下していた。退院後は自宅で療養しており、10月10日から訪問看護サービスを週2回(月曜日と木曜日)利用している。現在は全身状態が安定しており、日常生活動作も徐々に回復している段階である。
バイタルサイン
来院時のバイタルサインは体温38.5℃、血圧158/92mmHg、脈拍102回/分・整、呼吸数22回/分、SpO2 96%(室内気)であった。現在(10月15日、訪問看護14日目)のバイタルサインは体温36.8℃、血圧138/82mmHg、脈拍76回/分・整、呼吸数18回/分、SpO2 98%(室内気)と安定している。
食事と嚥下状態
入院前は1日3食を規則正しく摂取しており、主に和食中心の食事内容であった。食事摂取量は通常の8割程度で、嚥下機能に問題はなかった。喫煙歴はなく、飲酒は月に1~2回程度、日本酒を1合飲む程度であった。入院中は発熱と食欲不振により摂取量が5割程度に低下したが、解熱後は徐々に改善した。現在は自宅で常食を摂取しており、食事摂取量は通常の7~8割程度まで回復している。嚥下状態は良好で、水分摂取も問題なく行えている。医師からは1日1500mL以上の水分摂取を指示されており、本人も意識的に水分を摂るよう心がけている。現在は禁酒を継続している。
排泄
入院前の排泄状況は、排尿は日中5~6回、夜間1回程度で自立していた。排便は2日に1回程度で、軟便傾向があったが自力排便が可能であった。下剤の使用はなかった。入院中は尿道カテーテルが挿入され、尿の性状は混濁していたが、治療により徐々に清明化した。退院前にカテーテルは抜去され、自力排尿が可能となった。現在は排尿回数が日中7~8回、夜間2~3回とやや頻尿傾向が見られるが、残尿感や排尿時痛はない。尿の性状は清明で、色調も正常である。排便は2~3日に1回程度で、便秘傾向が見られるため、水分摂取と軽い運動を心がけている。下剤は現在使用していないが、必要時には使用可能な処方を受けている。
睡眠
入院前は23時頃就寝、6時頃起床で、睡眠時間は約7時間であった。途中覚醒は夜間1回程度で、睡眠の質は比較的良好であった。眠剤の使用はなかった。入院中は環境の変化と発熱により睡眠が浅く、途中覚醒が頻回であった。現在は自宅での生活に戻り、23時頃就寝、6時半頃起床で睡眠時間は約7時間半である。しかし、夜間の排尿のために2~3回起きることがあり、睡眠の質がやや低下している。日中の傾眠傾向は見られず、眠剤は使用していない。
視力・聴力・知覚・コミュニケーション・信仰
視力は両眼とも老視があり、日常生活では老眼鏡を使用している。新聞や本を読む際には問題なく読むことができる。聴力は軽度の加齢性難聴があるが、日常会話には支障はない。知覚は正常で、温痛覚、触覚ともに異常は見られない。コミュニケーション能力は良好で、会話は明瞭であり、意思疎通に問題はない。自分の症状や気持ちを適切に表現することができる。信仰は特にないが、年に数回は神社への参拝を行っている。
動作状況
歩行は入院前は杖なしで自立していたが、退院直後は体力低下により家の中では壁や家具につかまりながら歩行していた。現在は徐々に体力が回復し、屋内は自立歩行が可能となっているが、屋外歩行はまだ不安定さが見られる。移乗動作は自立しており、ベッドから車椅子、トイレへの移乗は問題なく行える。排尿と排泄はトイレで自立して行っており、介助は不要である。入浴は退院後1週間は清拭で対応していたが、現在はシャワー浴を自立して行っている。ただし、疲労を考慮して長時間の入浴は避けている。衣類の着脱は自立している。転倒歴は3年前に自宅の階段で1回転倒したことがあるが、骨折などの重大な外傷はなかった。
内服中の薬
- レボフロキサシン錠500mg:1日1回朝食後、10日間(残り4日分)
- アムロジピン錠5mg:1日1回朝食後
- ロスバスタチン錠2.5mg:1日1回夕食後
- レバミピド錠100mg:1日3回毎食後
- 酸化マグネシウム錠330mg:1日2回朝夕食後(頓用)
検査データ
| 検査項目 | 入院時(10月1日) | 退院時(10月9日) | 最新(10月14日) | 基準値 |
|---|---|---|---|---|
| WBC(白血球) | 14,200/μL | 8,600/μL | 7,200/μL | 3,500-9,000 |
| RBC(赤血球) | 398万/μL | 405万/μL | 412万/μL | 380-500万 |
| Hb(ヘモグロビン) | 12.2g/dL | 12.5g/dL | 12.8g/dL | 11.5-15.0 |
| Plt(血小板) | 25.8万/μL | 26.2万/μL | 27.1万/μL | 15-35万 |
| CRP | 12.8mg/dL | 3.2mg/dL | 1.2mg/dL | 0-0.3 |
| BUN(尿素窒素) | 28.5mg/dL | 18.2mg/dL | 15.8mg/dL | 8-20 |
| Cr(クレアチニン) | 1.35mg/dL | 0.98mg/dL | 0.92mg/dL | 0.5-1.0 |
| eGFR | 35.2mL/分/1.73㎡ | 50.8mL/分/1.73㎡ | 54.2mL/分/1.73㎡ | 60以上 |
| Na(ナトリウム) | 138mEq/L | 140mEq/L | 141mEq/L | 135-145 |
| K(カリウム) | 4.2mEq/L | 4.0mEq/L | 4.1mEq/L | 3.5-5.0 |
| 尿蛋白 | (3+) | (±) | (-) | (-) |
| 尿潜血 | (2+) | (±) | (-) | (-) |
| 尿白血球 | 多数 | 5-9/HPF | 1-4/HPF | 1-4/HPF |
| 尿細菌 | 多数 | 少数 | (-) | (-) |
服薬は現在自己管理で行っており、配偶者の見守りのもと確実に内服できている。訪問看護時には服薬状況の確認と残薬チェックを行っている。
今後の治療方針と医師の指示
抗菌薬治療は10月19日まで継続し、終了後は10月22日に外来でフォローアップを行う予定である。腎機能は改善傾向にあるが、慢性腎臓病(CKD)ステージG3aの状態であるため、今後も定期的な腎機能のモニタリングが必要である。水分摂取を1日1500mL以上確保し、尿路感染症の再発予防に努めることが指示されている。また、排尿後は陰部を清潔に保つこと、便秘を避けること、過労を避けて十分な休息をとることが指示されている。血圧管理も継続し、家庭血圧測定を1日2回(朝・夕)行うよう指示されている。体力回復のために軽い散歩などの運動を徐々に開始することが推奨されている。発熱、側腹部痛、排尿時痛、尿混濁などの症状が出現した場合は速やかに受診するよう指導されている。
本人と家族の想いと言動
A氏は「また感染症になるのではないかと不安です」と訴えており、再発への恐怖を抱いている。また「水をたくさん飲まなければいけないのは分かっているのですが、トイレが近くなって夜も眠れないのが辛いです」と睡眠の質の低下について訴えている。「早く元気になって、また友人と旅行に行きたい」という前向きな発言も聞かれる。一方で「夫に迷惑をかけて申し訳ない」と配偶者への気遣いを示す発言も多く見られる。配偶者は「妻が急に高熱を出したときは本当に心配しました。今は少しずつ元気になってきて安心しています」と述べており、協力的な姿勢を見せている。ただし「自分も高齢なので、どこまで介護ができるか不安です」とも話している。長女は電話で「仕事があるのですぐには帰れませんが、必要があればいつでも帰ります。訪問看護を利用できて本当に助かっています」と述べており、遠方からのサポート体制を整えている。
ゴードン11項目アセスメント解説
1. 健康知覚-健康管理パターンのポイント
このパターンでは、A氏が自身の健康状態をどう認識し、どのように健康管理を行っているかを評価します。特に急性腎盂腎炎という疾患に対する理解度と、再発予防に向けた健康管理行動の実施状況を把握することが重要です。
どんなことを書けばよいか
健康知覚-健康管理パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 疾患についての本人・家族の理解度(病態、治療、予後など)
- 疾患や治療に対する受け止め方、受容の程度
- 現在の健康状態や症状の認識
- これまでの健康管理行動(受診行動、服薬管理、生活習慣など)
- 疾患が日常生活に与えている影響の認識
- 健康リスク因子(喫煙、飲酒、アレルギー、既往歴など)
疾患に対する認識と不安
A氏は「また感染症になるのではないかと不安です」と訴えており、3年前にも尿路感染症で入院した経験があることから、再発への強い恐怖を抱いていることが分かります。この不安は疾患の再発リスクを認識していることの表れともいえますが、同時に過度な不安が生活の質に影響を与えている可能性も考慮する必要があります。再発予防に関する正しい知識と具体的な実践方法を理解しているか、またその不安が適切な健康管理行動につながっているかという視点でアセスメントすることが重要です。
服薬管理と医療者の指示の遵守状況
現在の服薬は自己管理で行っており、配偶者の見守りのもと確実に内服できていることから、基本的な健康管理能力は保たれていると考えられます。また、医師から1日1500mL以上の水分摂取を指示されており、本人も意識的に水分を摂るよう心がけているという点は、医療者の指示を理解し実践しようとする姿勢の表れです。ただし「水をたくさん飲まなければいけないのは分かっているのですが、トイレが近くなって夜も眠れないのが辛いです」という発言から、指示の遵守と生活の質のバランスに葛藤を抱えていることが読み取れます。この葛藤をどう解決していくかという視点も含めて記述するとよいでしょう。
既往歴と健康リスク因子
5年前の子宮全摘術、3年前の尿路感染症入院歴に加えて、10年前から高血圧症と脂質異常症で内服治療を継続していることから、長期的な健康管理の必要性を理解している可能性があります。現在は禁酒を継続しており、喫煙歴もないことは健康リスクの低減につながっています。一方で、卵アレルギーがあることは食事指導の際に配慮が必要な情報です。これらの既往歴や生活習慣が現在の疾患管理にどう影響しているか、またA氏自身がこれらの関連性をどの程度理解しているかという点を押さえておくとよいでしょう。
アセスメントの視点
A氏は基本的な健康管理能力を持ち、医療者の指示を理解し実践しようとする姿勢が見られます。しかし、再発への不安が強く、水分摂取と睡眠のバランスに葛藤を抱えている状況です。既往歴から長期的な健康管理の経験があることは強みとなりますが、今回の急性腎盂腎炎の再発予防に必要な具体的な知識と実践方法について、どの程度理解し実行できているかを多角的に評価することが重要です。
ケアの方向性
再発予防に向けた具体的で実践可能な健康管理方法の指導が必要です。特に水分摂取のタイミングや方法について工夫を提案し、睡眠の質を保ちながら適切な水分摂取ができるよう支援することが求められます。また、過度な不安を軽減し、自信を持って健康管理を継続できるよう、正しい知識の提供と心理的サポートが重要です。
2. 栄養-代謝パターンのポイント
このパターンでは、入院による食事摂取量の低下から回復過程にある状況を評価します。水分摂取が疾患管理の重要な要素となっているため、栄養と水分のバランスを総合的に捉えることが必要です。
どんなことを書けばよいか
栄養-代謝パターンでは、以下のような視点からアセスメントを行います。
- 食事と水分の摂取量と摂取方法
- 食欲、嗜好、食事に関するアレルギー
- 身長・体重・BMI・必要栄養量・身体活動レベル
- 嚥下機能・口腔内の状態
- 嘔吐・吐気の有無
- 皮膚の状態、褥瘡の有無
- 栄養状態を示す血液データ(Alb、TP、RBC、Ht、Hb、Na、K、TG、TC、HbA1c、BSなど)
食事摂取状況の経時的変化
入院前は1日3食を規則正しく摂取しており、和食中心で通常の8割程度の摂取量であったことから、もともと規則正しい食習慣を持っていたことが分かります。入院中は発熱と食欲不振により摂取量が5割程度に低下しましたが、解熱後は徐々に改善し、現在は7~8割程度まで回復しています。この回復傾向は治療効果の表れといえますが、入院前の8割から現在の7~8割という摂取量が、体力回復に十分かどうかという視点でアセスメントすることが重要です。
水分摂取と疾患管理の関連
医師から1日1500mL以上の水分摂取を指示されており、本人も意識的に水分を摂るよう心がけています。水分摂取は急性腎盂腎炎の再発予防において最も重要な要素の一つです。現在の水分摂取量が実際にどの程度確保できているか、どのようなタイミングで摂取しているか、水分の種類は何かといった具体的な情報も含めて記述するとよいでしょう。また「トイレが近くなって夜も眠れない」という訴えから、水分摂取のタイミングが睡眠に影響を与えている可能性があります。
体格と栄養状態の評価
身長152cm、体重48kgからBMIを計算すると約20.8となり、標準範囲内です。血液データではRBCが412万/μL、Hb12.8g/dLと基準範囲内に改善しており、貧血はありません。電解質もNa141mEq/L、K4.1mEq/Lと正常範囲内で、水分・電解質バランスは保たれています。これらのデータから、現在の栄養状態は概ね良好と考えられますが、体力回復のためにはさらなる摂取量の増加が必要かどうかを検討する必要があります。
食物アレルギーへの配慮
卵に対する軽度の食物アレルギーがあることは、食事指導や献立を考える際に配慮が必要な情報です。たんぱく質源として卵が制限される場合、他の良質なたんぱく質源を確保する必要があります。高齢者の体力回復にはたんぱく質が重要な役割を果たすため、アレルギーに配慮しながら適切な栄養摂取を実現する方法を考える視点が求められます。
アセスメントの視点
食事摂取量は回復傾向にあり、血液データからも栄養状態は概ね良好です。水分摂取は疾患管理上重要ですが、夜間頻尿による睡眠障害との兼ね合いで本人に葛藤があります。卵アレルギーへの配慮をしながら、体力回復に必要な栄養を確保できているか、水分摂取が適切に行えているかを総合的に評価することが大切です。
ケアの方向性
水分摂取のタイミングを工夫し、夜間の摂取を控えめにするなど、睡眠の質を保ちながら必要量を確保できる方法を一緒に考えることが重要です。また、卵アレルギーに配慮した栄養バランスの良い食事について、本人の嗜好や生活習慣を踏まえて具体的に提案していく必要があります。体力回復のためには、現在の摂取量で十分か評価を続けることも大切です。
続きはnoteで公開中です✨️
ゴードンの続きとヘンダーソン・関連図・看護計画について解説しています😊
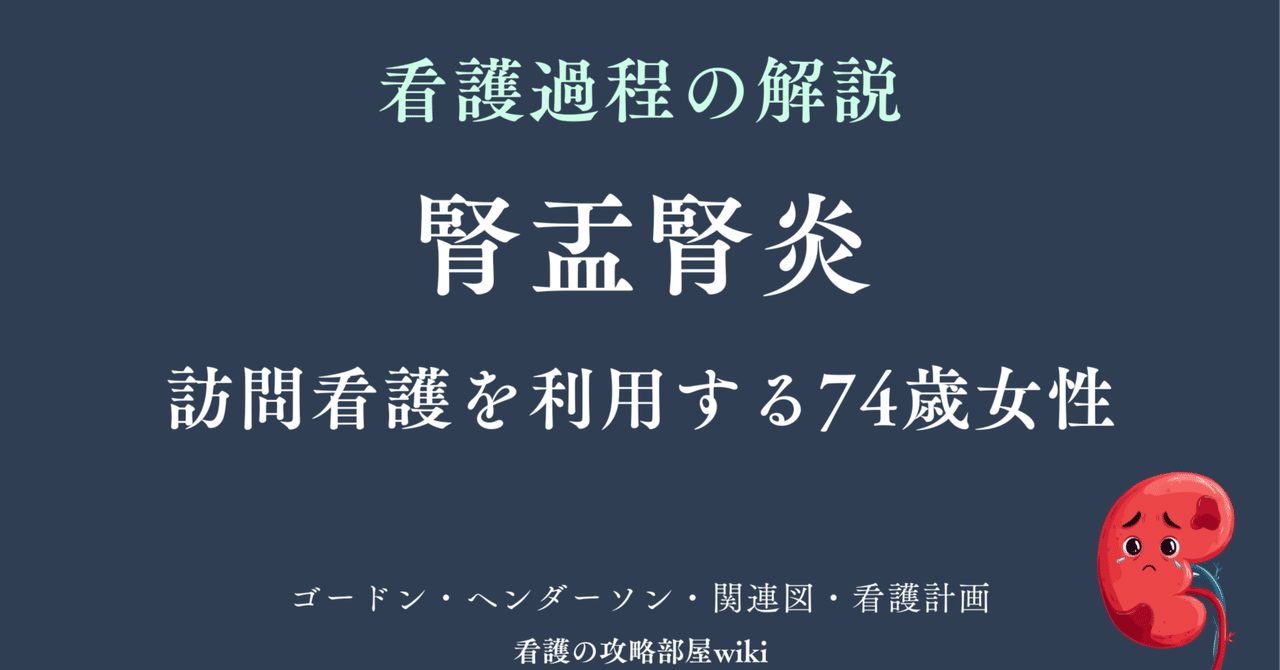
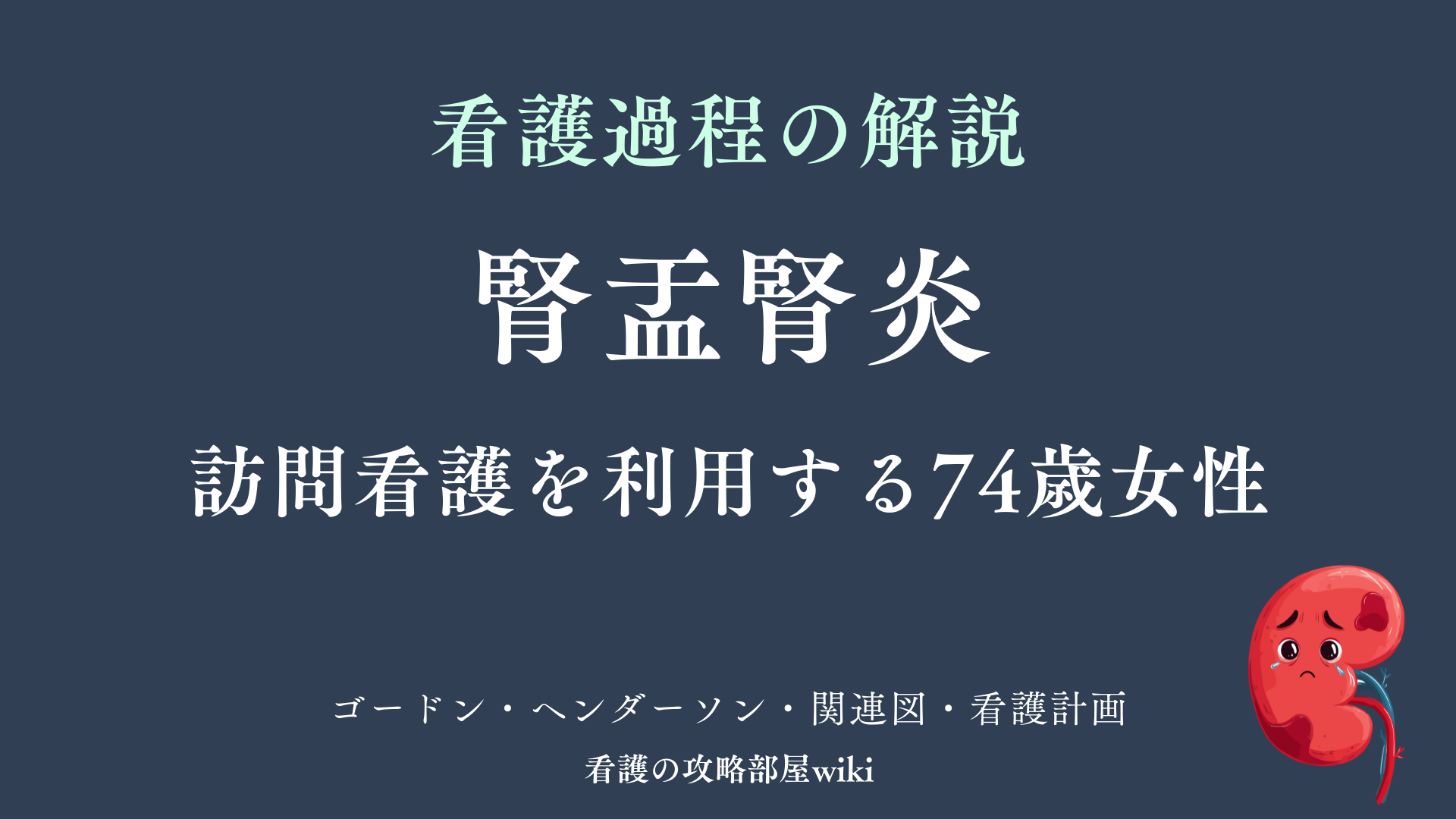


コメント