疾患概要
定義
加齢黄斑変性(Age-related Macular Degeneration:AMD)は、網膜の中心部である黄斑部に加齢に伴う変化が生じ、中心視力の低下をきたす疾患です。萎縮型(ドライ型)と滲出型(ウェット型)に大別され、滲出型では脈絡膜新生血管の形成により急激な視力低下が生じます。50歳以上の中途失明原因の上位を占め、高齢化社会の進展とともに患者数が急増している重要な眼疾患です。
疫学
日本では50歳以上の約1.3%(約70万人)が加齢黄斑変性に罹患していると推定されます。男性に多く(男女比約2:1)、加齢とともに有病率が上昇し、70歳以上では約5%に達します。欧米では萎縮型が多い(約90%)のに対し、日本人では滲出型の割合が高い(約70%)という特徴があります。片眼発症後、5年以内に約10-15%で対側眼にも発症し、両眼発症例では日常生活に著しい支障をきたします。近年、食生活の欧米化や喫煙率の影響により患者数は増加傾向にあります。
原因
加齢黄斑変性の原因は多因子性で、加齢が最も重要な危険因子です。遺伝的素因も重要で、補体系遺伝子(CFH、C3など)の多型が発症リスクに関与します。環境因子では喫煙が最も強い危険因子で、喫煙者の発症リスクは非喫煙者の2-3倍に上昇します。その他の危険因子として強い光曝露、肥満、高血圧、動脈硬化、酸化ストレスなどが挙げられます。栄養因子では抗酸化物質(ルテイン、ゼアキサンチン、ビタミンC、E)や亜鉛の不足、オメガ3脂肪酸の不足が関与するとされています。
病態生理
加齢黄斑変性の病態は網膜色素上皮(RPE)の機能低下から始まります。RPEの老化により老廃物の処理能力が低下し、ドルーゼン(老廃物の蓄積)が形成されます。萎縮型ではRPEと視細胞の萎縮が徐々に進行し、中心視野の暗点が拡大します。滲出型では脈絡膜新生血管が網膜色素上皮下や網膜下に侵入し、血管透過性亢進により浮腫や出血が生じます。新生血管は脆弱で破綻しやすく、出血や瘢痕形成により急激な視力低下をきたします。血管内皮増殖因子(VEGF)の過剰産生が新生血管形成の主要因となっています。
症状・診断・治療
症状
萎縮型では緩徐な中心視力低下が主症状で、読書困難、細かい作業の困難、顔の認識困難などが徐々に進行します。滲出型では急激な視力低下、変視症(直線が波打って見える、歪んで見える)、中心暗点(見ようとする部分が見えない)、小視症(物が小さく見える)が特徴的です。アムスラーグリッドを用いた自己チェックにより変視症の早期発見が可能です。両眼性の場合は読書、運転、階段昇降、人の顔の認識などの日常生活動作に著しい支障をきたし、中心視力依存の活動が困難となります。
診断
診断は眼底検査、光干渉断層計(OCT)、蛍光眼底造影検査により行われます。眼底検査ではドルーゼン、色素沈着、萎縮巣、出血、浮腫を観察します。OCTは非侵襲的で反復検査が可能なため、黄斑部の詳細な構造評価と経過観察に重要です。網膜下液、網膜内浮腫、脈絡膜新生血管の活動性を評価できます。フルオレセイン蛍光眼底造影(FA)とインドシアニングリーン蛍光眼底造影(IA)により脈絡膜新生血管の部位、範囲、活動性を詳細に評価し、治療方針決定に用いられます。アムスラーグリッド検査は患者の自覚症状評価と経過観察に有用です。
治療
萎縮型に対する根本的治療法は現在のところありませんが、抗酸化サプリメント(AREDS2処方:ルテイン、ゼアキサンチン、ビタミンC、E、亜鉛、銅)により進行抑制効果が期待されます。滲出型では抗VEGF薬硝子体注射が第一選択治療で、ラニビズマブ、アフリベルセプト、ベバシズマブなどが使用されます。初回治療では導入期として月1回を3回連続投与し、その後は病状に応じて維持期治療を行います。光線力学療法(PDT)は特定の病型に対して考慮され、レーザー光凝固術は中心窩外の病変に限定的に使用されます。補助的治療として視覚補助具(拡大鏡、電子ルーペ)の活用も重要です。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 感覚知覚変調(視覚):黄斑変性に関連した中心視力低下・変視症
- セルフケア不足:中心視力低下に関連した日常生活動作の困難
- 社会的孤立:視覚障害による外出困難と社会参加の減少
ゴードン機能的健康パターン
認知・知覚パターンでは中心視力低下と変視症の程度を詳細にアセスメントし、読書、テレビ視聴、手芸、料理などの具体的な活動への影響を評価します。特にアムスラーグリッドを用いた自己チェック能力と、症状変化の早期発見能力を確認します。活動・運動パターンでは中心視力低下による歩行、階段昇降、外出頻度への影響を評価し、転倒リスクや活動制限の程度を把握します。役割・関係パターンでは視覚障害による家族関係や社会的役割の変化、孤立感の有無を評価し、必要な支援体制を検討します。
ヘンダーソン14基本的ニード
学習するでは中心視力低下が情報収集や学習活動に与える影響を評価し、拡大鏡や音声機器などの視覚補助具の活用方法を指導します。食べる・飲むでは調理や食事摂取への影響を評価し、安全で自立した食事管理を支援します。遊び、レクリエーション活動に参加するでは趣味活動や社会参加への影響を把握し、視覚障害に適応した楽しみの発見を支援します。働くこと、達成感を得るでは就労への影響と職場環境の調整、あるいは役割の再構築について支援します。
看護計画・介入の内容
- 視機能評価・症状観察:中心視力と変視症の程度評価、アムスラーグリッド自己チェック指導、症状変化の早期発見教育、定期受診の重要性説明、両眼視機能の活用指導
- 日常生活適応支援:視覚補助具(拡大鏡、電子ルーペ、音声機器)の選択と使用指導、安全な生活環境の整備、調理・家事動作の工夫指導、外出時の安全対策
- 心理社会的支援:視覚障害による喪失感への共感的対応、残存視機能の活用と希望の維持、視覚障害者支援制度の紹介、家族の理解促進と協力体制構築、同病者との交流機会の提供
よくある疑問・Q&A
Q: 加齢黄斑変性は治る病気ですか?進行を止めることはできますか?
A: 現在のところ完全な治癒は困難ですが、滲出型では抗VEGF薬治療により視力の維持や改善が期待できます。約30-40%の患者さんで視力改善、約90%で視力悪化の抑制効果が認められています。萎縮型でも抗酸化サプリメントにより進行の遅延が可能です。早期発見・早期治療により、多くの患者さんで実用的な視力を保持できるため、定期的な眼科受診と適切な治療継続が重要です。新しい治療法の開発も進んでおり、将来的にはさらに効果的な治療が期待されます。
Q: 抗VEGF薬の注射はどのくらい続ける必要がありますか?
A: 治療期間は個人差がありますが、多くの患者さんで長期間の治療が必要です。初回は月1回を3回連続投与し、その後は病状に応じて1-3ヶ月間隔で継続します。治療により病変が安定すれば注射間隔を延長でき、一部の患者さんでは治療を中止できる場合もあります。しかし、治療中止後に再燃することも多いため、定期的なOCT検査による慎重な経過観察が必要です。治療の継続により視力保持効果が持続するため、医師と相談しながら適切な治療計画を立てることが大切です。
Q: 日常生活で気をつけることはありますか?予防法はありますか?
A: 禁煙が最も重要な予防法で、喫煙は発症リスクを2-3倍に増加させます。抗酸化物質を豊富に含む食品(緑黄色野菜、魚類、ナッツ類)の摂取を心がけ、紫外線対策(サングラス、帽子の着用)も重要です。アムスラーグリッドによる定期的な自己チェック(週1-2回)で変視症の早期発見に努めてください。片眼発症の場合、対側眼への発症リスクが高いため、定期的な眼科受診(3-6ヶ月ごと)を継続することが重要です。適度な運動と体重管理も推奨されます。
Q: 見えづらくなった場合、どのような支援がありますか?
A: 様々な視覚補助具と支援制度があります。拡大鏡、電子ルーペ、音声読み上げソフト、大きな文字の書籍・新聞などが利用できます。身体障害者手帳の取得により、税制優遇、交通費割引、補助具購入費助成などのサービスを受けられます。ロービジョンケアでは眼科医、視能訓練士、歩行訓練士などの専門チームが残存視機能の最大活用を支援します。地域の視覚障害者支援団体では日常生活訓練、外出支援、同病者との交流機会を提供しています。一人で悩まず、積極的に支援を求めることが大切です。
まとまり
加齢黄斑変性は高齢化社会における重要な視覚障害として、患者さんの生活の質に深刻な影響を与える疾患です。特に中心視力の障害という特徴により、読書、運転、人の顔の認識など、日常生活の根幹となる活動が困難となります。
看護の要点は早期発見の支援と視覚障害への適応促進です。アムスラーグリッドによる自己チェックの指導は、滲出型への移行や症状悪化の早期発見につながり、適切なタイミングでの治療介入を可能にします。患者さんが継続的に自己観察を行えるよう、分かりやすい指導と動機づけを行うことが重要です。
抗VEGF薬治療では長期間の通院と注射が必要となるため、治療継続への支援が重要となります。治療効果や副作用について正確な情報提供を行い、患者さんが安心して治療を継続できるよう支援します。また、注射後の注意事項や異常時の対応についても十分に指導することが必要です。
視覚障害への適応支援では、患者さんの残存視機能を最大限活用できるよう、個別性のある指導を行います。視覚補助具の選択と使用方法の習得、安全な生活環境の整備、効果的な照明の活用など、具体的で実践可能な方法を提案することが大切です。
心理的支援では、中心視力の喪失による絶望感や将来への不安に対して共感的に関わり、希望を維持できるよう支援することが重要です。視覚障害があっても充実した生活を送っている人々の体験談や、利用可能な支援制度の紹介により、患者さんが前向きに適応できるよう励まします。
実習では患者さんの視機能の詳細な評価と個別的なニーズの把握を重視しましょう。中心視力低下の程度、変視症の有無、両眼の状態、使用している補助具などを総合的にアセスメントし、その人らしい生活の継続を支援する看護計画を立案することが重要です。また、家族への教育も含めた包括的なアプローチにより、患者さんが加齢黄斑変性とうまく付き合いながら豊かな人生を送れるよう支援していきましょう。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
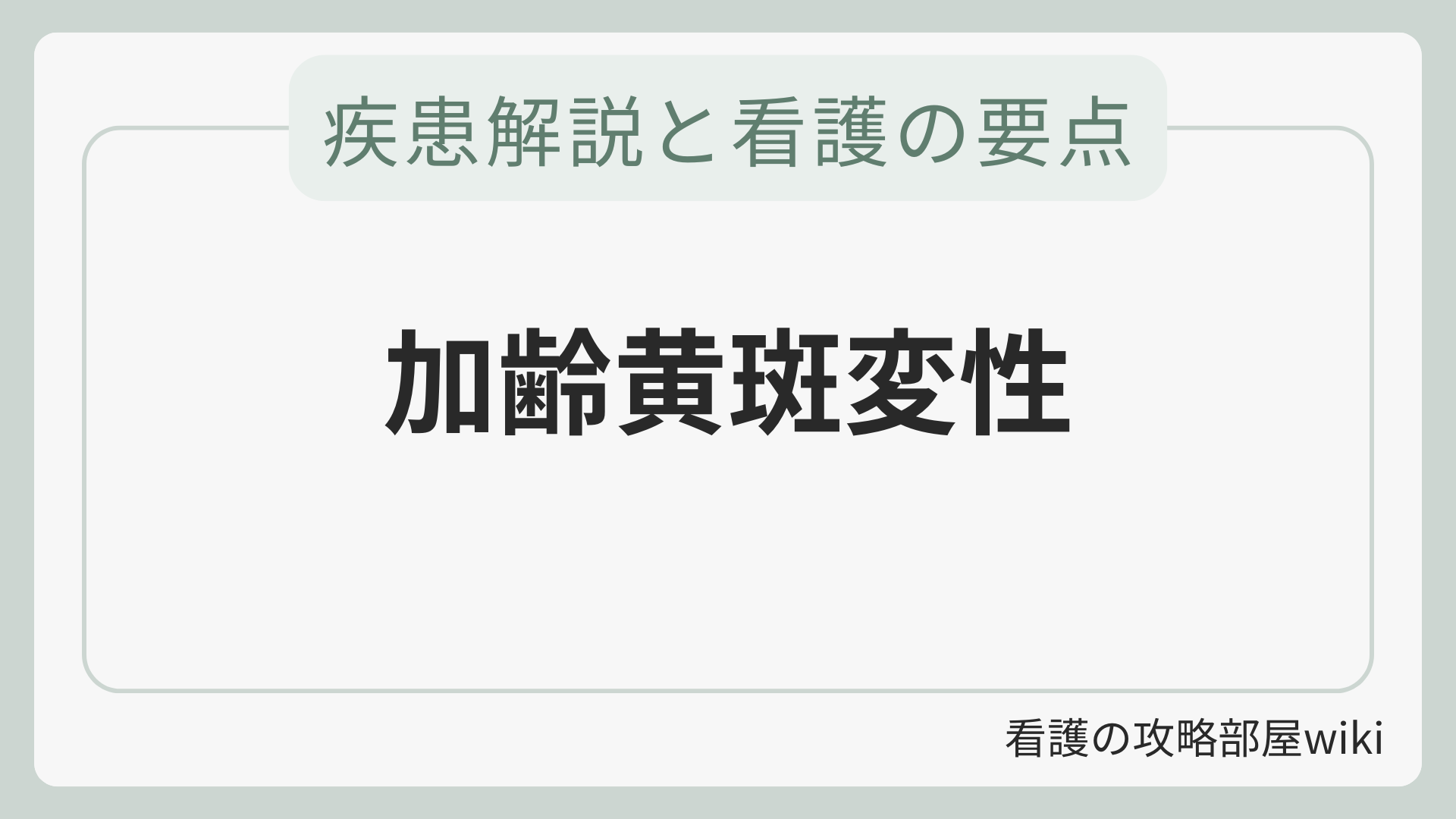
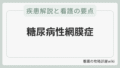
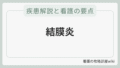
コメント