病態の概要
定義
せん妄とは、急性に発症し変動する意識障害を主体とした症候群のことですね。注意力の低下、認知機能の障害、知覚の異常が特徴的で、数時間から数日の間で症状が変動するのが大きな特徴です。医学的には「急性錯乱状態」とも呼ばれ、入院患者さんの10-30%に発症するとされています。
原因
せん妄の原因は非常に多岐にわたりますが、大きく分けて以下のような要因があります。
直接的要因(誘発因子)としては、感染症(特に尿路感染症、肺炎)、脱水、電解質異常(ナトリウム、カリウムの異常)、低酸素血症、薬物(特に抗コリン薬、ベンゾジアゼピン系薬物)、アルコール離脱、疼痛、便秘などがあります。
素因(準備因子)としては、高齢、認知症の既往、重篤な疾患、感覚器障害(視力・聴力低下)、睡眠不足、環境の変化などが挙げられますね。
病態生理
正常な状態
正常な意識状態では、脳の様々な部位が協調して働いています。大脳皮質が情報処理を行い、視床が意識レベルを調整し、脳幹が覚醒状態を維持しています。また、神経伝達物質のバランス(アセチルコリン、ドパミン、GABAなど)が適切に保たれることで、清明な意識と正常な認知機能が維持されているのです。
異常が起こる過程
せん妄では、神経伝達物質のバランスが崩れることが根本的な病態です。特に重要なのは、アセチルコリンの相対的な減少とドパミンの相対的な増加ですね。
感染症や脱水などのストレスが加わると、炎症性サイトカインが放出され、血液脳関門の透過性が亢進します。これにより脳内に炎症物質が侵入し、神経伝達に異常をきたすのです。また、低酸素や電解質異常は直接的に神経細胞の機能を障害します。
高齢者では、加齢による脳の予備能力の低下により、わずかなストレスでも容易にせん妄を発症しやすくなっています。「コップの水があふれるように」少しの負荷でも症状が現れるのが特徴的ですね。
症状
現れる症状とその理由
せん妄の症状は非常に多彩で、活動性の違いにより3つのタイプに分類されます。
過活動型せん妄では、興奮、攻撃性、幻覚、妄想が主な症状として現れます。これは脳内のドパミン活性が亢進することで起こり、患者さんは落ち着きがなく、大声を出したり、点滴を抜去しようとしたりする行動が見られますね。
低活動型せん妄では、活動性の低下、傾眠、反応の鈍化が特徴です。これはアセチルコリンの機能低下が主体となって起こり、一見すると「おとなしい」ため見過ごされやすいのが問題です。
混合型せん妄では、上記の症状が混在して現れます。
共通する症状として、注意力の障害(集中できない、すぐ気が散る)、見当識障害(時間、場所、人物がわからなくなる)、記憶障害(新しいことを覚えられない)、睡眠-覚醒リズムの障害(昼夜逆転)、知覚異常(幻視、幻聴)などがあります。
これらの症状が日内変動を示すのがせん妄の大きな特徴で、一般的に夕方から夜間にかけて症状が悪化する「日没症候群」と呼ばれる現象がよく見られます。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
・急性錯乱状態
・転倒リスク状態
・セルフケア不足
・睡眠パターン混乱
・暴力リスク状態
・家族の対処困難
ゴードンのポイント
健康知覚-健康管理パターンでは、患者さん自身が自分の状態を正しく認識できないため、安全確保が最優先となります。転倒や医療器具の自己抜去のリスクアセスメントが重要ですね。
睡眠-休息パターンでは、昼夜逆転や不眠が頻繁に見られるため、睡眠環境の整備と生活リズムの調整が必要です。
認知-知覚パターンでは、見当識障害や幻覚の有無、程度を詳細にアセスメントし、現実見当識を高める介入が重要となります。
ヘンダーソンのポイント
安全で清潔な環境の維持が最も重要で、転倒防止、医療器具の管理、環境の整備が必要です。
学習、発見、好奇心の充足では、現実見当識を高めるために、時計やカレンダーの設置、家族写真の活用、継続的な声かけが効果的ですね。
睡眠と休息では、適切な睡眠-覚醒リズムの確立のため、日中の活動促進と夜間の睡眠環境整備が重要です。
看護計画・介入の内容
・24時間の継続的な観察と症状の記録
・転倒防止対策(ベッド柵、センサーマット、付き添い)
・現実見当識の促進(時計、カレンダー、声かけ)
・適切な照明の確保(日中は明るく、夜間は暗く)
・家族の面会促進と協力依頼
・原因疾患の治療への協力
・薬物療法の適切な実施と副作用観察
・水分・栄養状態の管理
・感染予防対策
・安全で安心できる環境の提供
よくある疑問・Q&A
Q: せん妄と認知症はどう違うのですか?
A: せん妄は急性に発症し症状が変動するのに対し、認知症は慢性・進行性で症状が比較的安定しています。せん妄は原因を取り除けば改善可能ですが、認知症は基本的に不可逆的な変化です。ただし、認知症の方はせん妄を発症しやすいため、両者が合併することもよくありますね。
Q: なぜ高齢者にせん妄が多いのですか?
A: 高齢者では脳の予備能力が低下しており、わずかなストレスでも容易にバランスが崩れてしまうからです。また、多くの薬剤を服用していることが多く、薬物相互作用のリスクも高くなります。感覚器障害や基礎疾患も多いため、せん妄の素因を多く持っているのです。
Q: せん妄の患者さんへの声かけのコツはありますか?
A: ゆっくり、はっきり、短い言葉で話しかけることが基本です。患者さんの名前を呼んでから話し始め、「今日は○月○日です」「ここは○○病院です」など具体的な情報を繰り返し伝えます。否定的な言葉は避け、安心感を与える言葉がけを心がけましょう。
Q: 家族にはどのように説明すればよいですか?
A: せん妄は一時的な状態で治療可能であることを強調し、「本来の人格ではない」ことを理解してもらいます。家族の協力が回復に重要であることを説明し、面会時の対応方法もアドバイスしましょう。家族自身のストレスケアも忘れずに配慮することが大切ですね。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
看護の攻略部屋wiki
看護過程の個別サポート
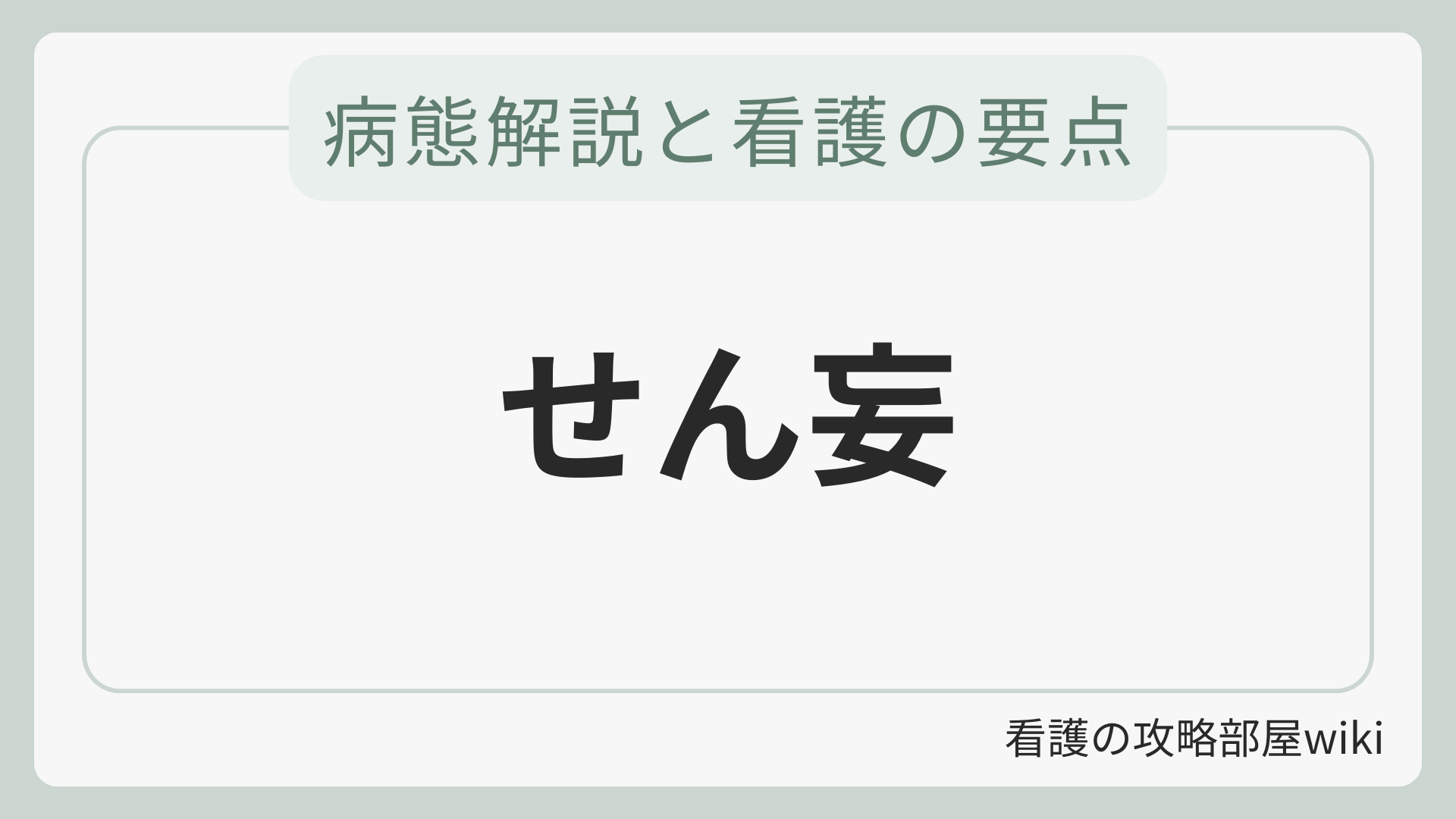
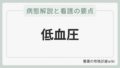
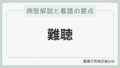
コメント