疾患概要
定義
誤嚥性肺炎とは、口腔内や咽頭に存在する細菌が唾液や食物とともに気道に侵入(誤嚥)し、肺に炎症を引き起こす疾患です。通常、健康な人では咳反射や嚥下反射によって気道への異物侵入が防がれていますが、これらの防御機能が低下することで発症します。
高齢者や神経疾患を持つ患者さんに多く見られ、市中肺炎や院内肺炎の重要な原因となっています。特に、夜間の不顕性誤嚥(むせを伴わない誤嚥)によって発症するケースが多いことが特徴です。
疫学
日本における肺炎死亡者の約7割が75歳以上の高齢者であり、その多くが誤嚥性肺炎と考えられています。特に80歳以上では肺炎全体の約70〜80%を誤嚥性肺炎が占めるとされています。
男性に多い傾向があり、これは男性の方が脳血管疾患の罹患率が高いことや、喫煙歴による気道のダメージが関連していると考えられています。また、施設入所者や寝たきりの高齢者では特に発症リスクが高く、誤嚥性肺炎は繰り返し発症しやすいという特徴があります。
原因
誤嚥性肺炎の発症には、主に以下の要因が関与しています。
嚥下機能の低下が最も重要な要因です。加齢に伴う筋力低下、脳血管疾患による嚥下障害、神経筋疾患(パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症など)、認知症などが嚥下機能を低下させます。
咳反射・咽頭反射の低下も重要です。これらの防御反射が減弱すると、誤嚥した物質を排出できず、肺に到達してしまいます。特に脳血管疾患後や高齢者では、これらの反射が著しく低下していることがあります。
口腔内の衛生状態の悪化は、誤嚥する物質に含まれる細菌量を増加させます。歯周病菌や口腔内常在菌が増殖した状態で誤嚥が起こると、肺炎を発症しやすくなります。
その他、胃食道逆流症、意識レベルの低下、鎮静薬や睡眠薬の使用、体位(臥床時間が長い)、栄養状態の不良なども危険因子として挙げられます。
病態生理
誤嚥性肺炎の発症メカニズムは、防御機能の破綻→病原体の侵入→炎症反応という流れで説明できます。
まず、嚥下時に本来食道に送られるべき食物や唾液が、嚥下反射の低下により誤って気管に入ってしまいます。健康な状態では、喉頭蓋が気管を閉鎖し、誤嚥を防いでいますが、この機能が低下すると防御が不十分になります。
特に問題となるのが不顕性誤嚥(silent aspiration)です。これは、誤嚥してもむせや咳などの症状が現れない状態で、本人も周囲も気づかないうちに繰り返し誤嚥が起こります。夜間の睡眠中に唾液を誤嚥するケースが多く、これが誤嚥性肺炎の主要な原因となっています。
気道に侵入した物質には、口腔内や咽頭の常在菌(嫌気性菌、グラム陰性桿菌、肺炎球菌など)が含まれています。これらの細菌が肺の末梢まで到達すると、肺胞や気管支で増殖を始めます。
細菌の侵入に対して、身体は炎症反応を起こします。白血球が集まり、炎症性サイトカインが放出され、肺胞内に滲出液が貯留します。この結果、ガス交換が障害され、低酸素血症が生じます。
高齢者では免疫機能も低下しているため、細菌の排除が遅れ、炎症が遷延しやすくなります。また、繰り返す誤嚥により慢性的な炎症が持続し、肺の線維化や呼吸機能の低下を招くこともあります。
症状・診断・治療
症状
誤嚥性肺炎の症状は、通常の細菌性肺炎と比べて非典型的で緩徐に進行することが多いのが特徴です。
典型的な症状としては、発熱、咳嗽、痰の増加、呼吸困難感などがありますが、高齢者では発熱が明確でないことも多く、37度台の微熱や平熱のこともあります。咳や痰も軽度であることが多く、見逃されやすいです。
むしろ、全身状態の変化に注意が必要です。食欲低下、活動性の低下、意識レベルの変化、傾眠傾向、せん妄などが初発症状となることがあります。「いつもと様子が違う」という変化を見逃さないことが重要です。
身体所見としては、頻呼吸、SpO2の低下、湿性ラ音(痰がからむようなゴロゴロとした呼吸音)などが認められます。重症例では、チアノーゼ、呼吸補助筋の使用、意識障害などが出現します。
診断
診断は、臨床症状、身体所見、画像検査、血液検査を総合的に評価して行います。
画像検査では、胸部X線検査やCT検査で肺炎像を確認します。誤嚥性肺炎では下葉や背側に陰影が出現しやすいという特徴があります。これは、臥床時に重力の影響で誤嚥物がこれらの部位に流れ込みやすいためです。
血液検査では、白血球数の増加(特に好中球の増加)、CRP(C反応性蛋白)の上昇など、炎症反応の亢進を示す所見が見られます。ただし、高齢者では炎症反応が弱く、これらの数値が正常範囲内のこともあります。
喀痰検査では、原因菌の同定と薬剤感受性の確認を行います。誤嚥性肺炎では、複数の菌が混在する混合感染が多いことも特徴です。
嚥下機能の評価も重要です。嚥下造影検査(VF)や嚥下内視鏡検査(VE)によって、誤嚥の有無や嚥下のメカニズムを詳しく評価することができます。また、ベッドサイドでの水飲みテストや反復唾液嚥下テスト(RSST)なども有用です。
治療
治療の基本は、抗菌薬療法、呼吸管理、誤嚥の予防、栄養管理の4つです。
抗菌薬療法では、口腔内常在菌をカバーできる広域抗菌薬を選択します。ペニシリン系やセフェム系の抗菌薬に、嫌気性菌をカバーするためのクリンダマイシンやメトロニダゾールなどを併用することもあります。治療期間は通常2週間程度ですが、患者さんの状態により調整されます。
呼吸管理では、低酸素血症に対して酸素療法を行います。必要に応じて、ネーザルカニューラ、酸素マスク、場合によっては人工呼吸管理を行うこともあります。また、去痰薬の投与や吸引によって気道内の分泌物を除去し、換気を改善します。
誤嚥予防が最も重要です。食事時の姿勢調整(30度以上のギャッジアップ、頸部前屈位)、食形態の調整(とろみ付け、ペースト食など)、食事介助方法の工夫、口腔ケアの徹底などを行います。
栄養管理も欠かせません。経口摂取が困難な場合は、経鼻胃管や胃瘻からの経管栄養、場合によっては静脈栄養を検討します。ただし、経管栄養でも胃食道逆流による誤嚥は起こり得るため、注意が必要です。
リハビリテーションとして、嚥下訓練(直接訓練・間接訓練)、呼吸リハビリテーション、離床の促進なども重要な治療の一環です。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 非効果的気道浄化(喀痰の貯留、咳嗽反射の低下に関連した)
- ガス交換障害(肺炎による換気障害に関連した)
- 誤嚥リスク状態(嚥下機能低下に関連した)
- 低栄養リスク状態(嚥下困難、食欲不振に関連した)
- 感染リスク状態(免疫機能低下、口腔内衛生状態の悪化に関連した)
ゴードン機能的健康パターン
栄養・代謝パターンが最も重要なアセスメントポイントです。
嚥下機能の評価では、実際の食事場面を観察することが大切です。むせの有無だけでなく、食事中の姿勢、食べるペース、咀嚼の様子、飲み込むまでの時間、食後の声の変化(湿性嗄声)などを細かく観察します。水分でむせやすいのか、固形物が難しいのか、食事の種類によって違いがあるかも確認しましょう。
口腔内の状態も詳しく観察します。歯の状態、義歯の適合性、口腔粘膜の乾燥、舌苔の付着、口臭の有無などから、口腔衛生状態を評価します。口腔内に多量の細菌が存在すると、誤嚥時の肺炎リスクが高まります。
栄養状態については、食事摂取量、体重変化、血液データ(アルブミン値など)、皮膚の状態などから総合的に判断します。低栄養は免疫機能を低下させ、肺炎の回復を遅らせます。
活動・運動パターンでは、呼吸状態と活動能力を評価します。
呼吸状態は、呼吸数、呼吸パターン、SpO2値、呼吸音、チアノーゼの有無などを観察します。特に、食事前後や体位変換時のSpO2の変動に注意が必要です。誤嚥が起こると、食後にSpO2が低下することがあります。
活動能力については、ADLの自立度、離床の状況、1日の臥床時間などを確認します。長時間の臥床は誤嚥性肺炎のリスクを高めるため、可能な範囲で離床を促すことが重要です。
認知・知覚パターンも見逃せません。
意識レベルの変化は、肺炎の悪化のサインであると同時に、誤嚥リスクを高める要因でもあります。特に高齢者では、肺炎によってせん妄を起こしやすく、そのことがさらに誤嚥を引き起こす悪循環となります。
認知機能の低下がある患者さんでは、食事への注意力、指示理解力、安全な食事方法の遵守などが困難になることがあります。個々の認知レベルに応じた支援が必要です。
ヘンダーソン14基本的ニード
「正常な呼吸」のニードが最も中心的です。
呼吸状態の観察では、安静時だけでなく、体動時や食事時の呼吸状態の変化に注目します。誤嚥のリスクが高い時間帯(食事中、食後30分、夜間)は特に注意深く観察が必要です。
気道浄化の援助として、適切な吸引、体位ドレナージ、咳嗽介助などを行います。吸引は必要ですが、頻回すぎると粘膜を傷つけるため、タイミングと方法に配慮が必要です。
「適切な飲食」のニードも重要です。
安全な食事の提供のためには、患者さんの嚥下機能に合わせた食形態の選択が必要です。水分にとろみをつける程度、食事の硬さやまとまりやすさなど、言語聴覚士や栄養士と連携しながら調整します。
食事環境の整備も大切です。静かで落ち着いた環境、適切な照明、食事に集中できる雰囲気を作ります。テレビをつけたまま、話しかけながらの食事は誤嚥リスクを高めます。
「身体の清潔保持と皮膚の保護」に関連して、口腔ケアは誤嚥性肺炎予防の要です。
口腔ケアは、食後だけでなく、起床時、就寝前にも実施します。特に就寝前の口腔ケアは夜間の不顕性誤嚥対策として重要です。舌や口腔粘膜、義歯の清掃を丁寧に行い、口腔内の細菌数を減らします。
口腔内の保湿も忘れずに行います。乾燥していると細菌が繁殖しやすく、また粘膜も傷つきやすくなります。
看護計画・介入の内容
- 誤嚥予防の徹底: 食事時は30〜60度のギャッジアップを保ち、頸部をやや前屈させた姿勢で摂取してもらう。食後も30分以上はこの姿勢を維持する。ベッド上での食事介助では、介助者の位置は患者さんの真正面か、やや下方から行うことで、頸部前屈位を保ちやすくなる
- 食事環境と方法の調整: 一口量を少なめにし、ゆっくりとしたペースで食事を進める。急がせたり、話しかけながらの食事は避ける。食事中に疲労が見られたら、一旦休憩を入れる。嚥下を確認してから次の一口を提供することが重要
- 口腔ケアの実施: 毎食後および就寝前に実施する。特に夜間の不顕性誤嚥予防のため、就寝前のケアは丁寧に行う。歯ブラシだけでなく、スポンジブラシや口腔ケア用ウェットティッシュなども活用し、舌や頬の内側、口蓋もケアする。義歯は外して洗浄し、夜間は外しておく
- 呼吸状態のモニタリング: SpO2、呼吸数、呼吸音を定期的に観察する。特に食事前後、体位変換後、夜間帯は注意深く観察する。SpO2が普段より2〜3%低下したり、呼吸数が増加した場合は医師に報告する
- 適切な吸引の実施: 口腔内・咽頭部に分泌物が貯留している場合は、食事前に吸引を行う。吸引は必要最小限とし、1回の吸引は10〜15秒以内とする。吸引圧は成人で150mmHg程度を目安とし、粘膜損傷に注意する
- 離床の促進: 可能な範囲で離床を促し、座位時間を増やす。臥床時間が長いと分泌物が貯留しやすく、また嚥下筋も弱くなる。車椅子への移乗や、ベッドサイドでの座位保持など、患者さんの状態に合わせた活動を検討する
- 栄養状態の管理: 摂取量を記録し、体重測定を定期的に行う。経口摂取量が不足する場合は、栄養補助食品の追加や、場合によっては経管栄養の併用を検討する。ただし、無理な経口摂取は誤嚥リスクを高めるため、安全性を最優先する
- 意識レベルの観察: 意識レベルの低下は誤嚥リスクを高めるため、定期的にJCSやGCSで評価する。せん妄の兆候(不穏、見当識障害など)にも注意し、早期発見・早期対応を心がける
- 家族への教育と支援: 誤嚥予防の重要性、適切な食事介助方法、口腔ケアの方法などを家族にも説明し、退院後も継続できるよう指導する。また、家族の不安や疲労にも配慮し、サポート体制を整える
よくある疑問・Q&A
Q: 不顕性誤嚥はどうやって見つけるのですか?
A: 不顕性誤嚥は、むせや咳などの明らかな症状がないため、見つけにくいのが特徴です。ただし、いくつかのサインがあります。食後に声質が変わる(湿性嗄声)、食後にSpO2が低下する、原因不明の発熱を繰り返す、食事中に集中力が続かない、などの変化に注意しましょう。また、水飲みテストや反復唾液嚥下テストなどのスクリーニング検査も有用です。リスクが高いと判断された場合は、嚥下造影検査で詳しく評価することができます。実習では、「いつもと何か違う」という微細な変化を見逃さない観察力を養うことが大切です。
Q: とろみをつける際の注意点を教えてください
A: とろみの濃度は、患者さんの嚥下機能に合わせて調整する必要があります。濃すぎると口腔内に残留しやすく、薄すぎると誤嚥のリスクが高まります。一般的に、「薄いとろみ」「中間のとろみ」「濃いとろみ」の3段階がありますが、その人に合った濃度を見つけることが重要です。また、とろみ剤を混ぜた後は、十分に時間をおいて(通常1〜2分)、とろみが安定してから提供します。時間が経つと濃度が変わる製品もあるため、作り置きは避け、都度調整することが望ましいです。お茶や水だけでなく、薬を飲む時の水分にもとろみが必要な場合があることを忘れずに。
Q: 経鼻胃管や胃瘻があれば誤嚥性肺炎は予防できますか?
A: いいえ、経管栄養でも誤嚥性肺炎のリスクはあります。胃食道逆流によって胃内容物が逆流し、それを誤嚥することがあるためです。特に、注入速度が速すぎる場合や、注入後すぐに臥位にした場合にリスクが高まります。予防策としては、注入時は30〜45度のギャッジアップを保つ、注入後も30分〜1時間は同じ姿勢を維持する、注入速度を適切に保つ(通常100〜150ml/時間程度)などが重要です。また、経管栄養中でも口腔ケアは必須です。唾液の誤嚥は経管栄養の有無に関わらず起こるため、口腔内の細菌数を減らすことが誤嚥性肺炎予防につながります。
Q: 呼吸音の「湿性ラ音」とはどのような音ですか?
A: 湿性ラ音は、気道内に分泌物や滲出液がある時に聴取される、ゴロゴロ、プツプツといった水泡音です。痰が絡んだような音と表現されることもあります。聴診器で聴くと、呼吸に合わせて「ブクブク」「ゴボゴボ」という音が聞こえます。誤嚥性肺炎では、特に肺の下部(下葉)で聴取されやすいのが特徴です。実習で聴診する際は、まず静かな環境で、患者さんに深呼吸をしてもらいながら、左右対称に複数箇所を聴診します。健常な肺音との違いを感じ取るためには、正常な呼吸音もしっかり聴いて比較することが大切です。指導者に「聴いてみてください」とお願いすることも良い学習になります。
Q: 食事介助で一番気をつけることは何ですか?
A: 最も重要なのは、患者さんのペースに合わせることです。急がせると誤嚥リスクが高まります。一口量は患者さんの嚥下能力に合わせて調整し、前の一口を完全に飲み込んだことを確認してから次を提供します。姿勢も重要で、頸部がやや前屈する位置でスプーンを口に運びます。また、食事中は話しかけず、患者さんが嚥下に集中できる環境を作ります。食事の進行中に疲労の兆候(食べるペースが落ちる、むせが増える、集中力が低下する)が見られたら、無理せず休憩を入れることも大切です。「完食すること」よりも「安全に食べること」を優先する姿勢を持ちましょう。
まとめ
誤嚥性肺炎は、嚥下機能や咳反射の低下により、口腔内細菌を含む唾液や食物が気道に入ることで発症する肺炎です。高齢者に多く、繰り返しやすいという特徴があります。
病態の本質は、不顕性誤嚥による口腔内細菌の気道侵入と、免疫機能低下による細菌排除の遅延にあります。夜間の唾液誤嚥が主要な原因となることを理解しておくことが重要です。
看護の要点は、第一に誤嚥の予防です。適切な体位保持、食形態の調整、ペースを守った食事介助、そして口腔ケアの徹底が欠かせません。特に就寝前の口腔ケアは、夜間の不顕性誤嚥予防に重要な役割を果たします。
第二に、呼吸状態のモニタリングと早期発見です。SpO2の変動、呼吸数の増加、湿性ラ音の出現などの変化を見逃さず、早期に対応することで重症化を防ぐことができます。
第三に、全身状態の観察です。高齢者では典型的な肺炎症状が現れにくく、「いつもと違う」という微細な変化が唯一のサインであることも多いため、日々の観察が非常に重要になります。
患者教育では、誤嚥予防の具体的な方法、口腔ケアの重要性、早期受診のタイミングなどを、患者さんと家族の両方に分かりやすく伝えることが大切です。
実習での心構えとしては、「むせがないから安全」とは限らないことを常に意識しましょう。不顕性誤嚥の存在を念頭に置き、多角的な視点で患者さんを観察する姿勢が求められます。また、食事介助の場面では、安全性を最優先し、患者さんのペースを尊重する姿勢を忘れないでください。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
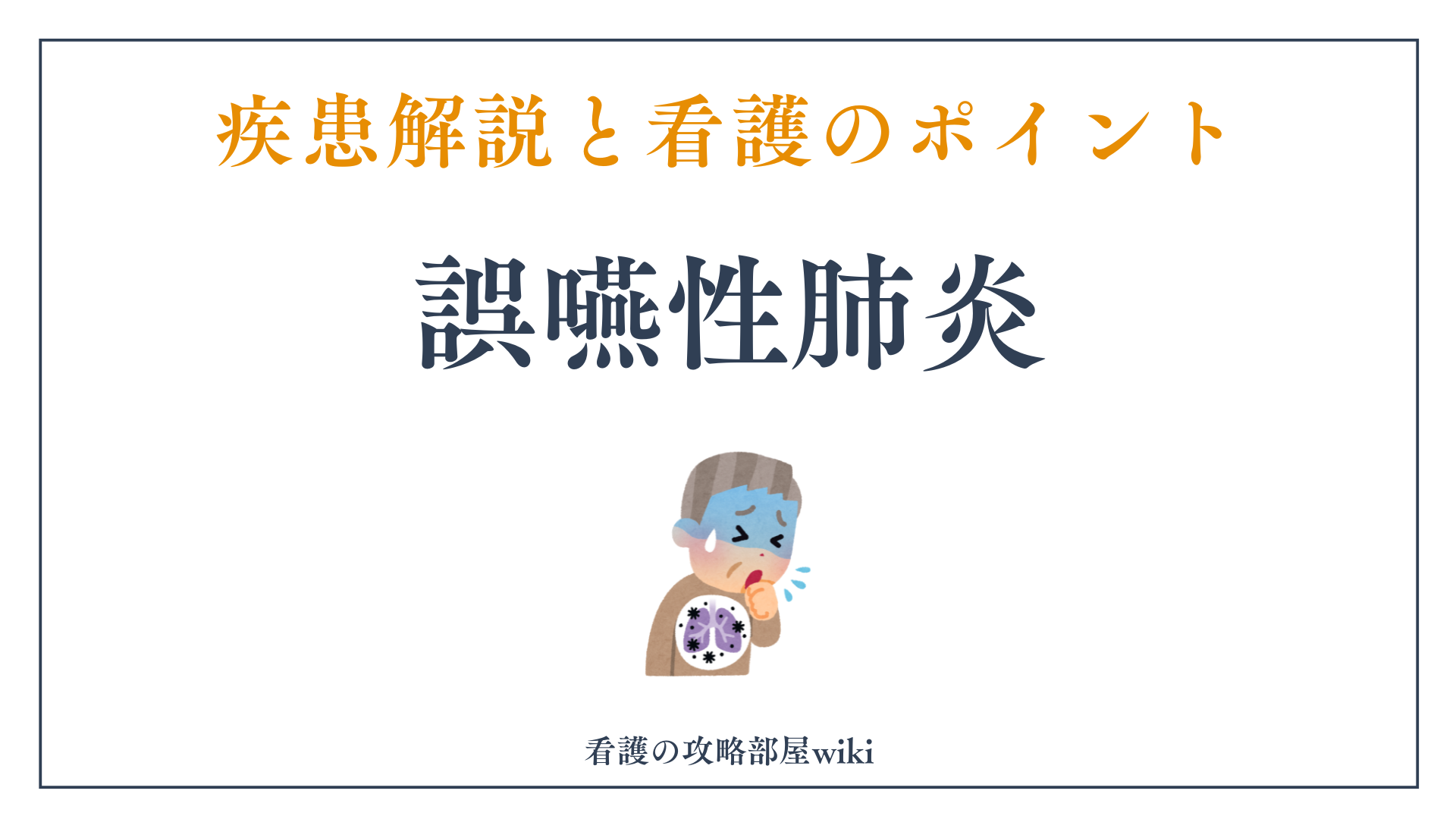
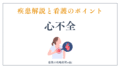
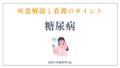
コメント