疾患概要
定義
うつ病は、持続的な抑うつ気分と興味・関心の喪失を主症状とする精神疾患です。WHO(世界保健機関)の診断基準では、これらの中核症状に加えて、思考・認知機能の低下、精神運動性の変化、身体症状(食欲・睡眠障害、疲労感)、希死念慮などの症状が2週間以上持続する状態と定義されます。単なる一時的な気分の落ち込みではなく、日常生活に著しい支障をきたす疾患であり、適切な治療により回復が期待できる病気です。
疫学
日本におけるうつ病の生涯有病率は約4-5%で、約500万人が罹患していると推定されます。女性の発症率は男性の約2倍で、特に20-40歳代の女性に多く見られます。初回発症年齢は20-30歳代が最多ですが、高齢者うつ病や青年期うつ病も増加傾向にあります。再発率は約60%と高く、複数回のエピソードを経験することが多い疾患です。近年、職場でのストレス増大、社会情勢の変化、COVID-19パンデミックの影響により患者数は増加傾向にあり、現代社会の重要な健康問題となっています。
原因
うつ病の原因は多因子性で、生物学的要因、心理学的要因、社会的要因が複合的に関与します。生物学的要因では脳内神経伝達物質(セロトニン、ノルアドレナリン、ドパミン)の機能異常、視床下部-下垂体-副腎系(HPA軸)の過活動、遺伝的素因が関与します。心理学的要因では認知の歪み、学習性無力感、性格特性(完璧主義、依存性)が影響します。社会的要因では重大なライフイベント(死別、離婚、失職)、慢性的ストレス、社会的支援の不足、経済的困窮などが誘因となります。
病態生理
うつ病の病態生理はモノアミン仮説が代表的で、セロトニン、ノルアドレナリン、ドパミンなどの神経伝達物質の機能低下が中核となります。セロトニン系の機能低下により抑うつ気分、不安、睡眠障害が生じ、ノルアドレナリン系の機能低下により意欲低下、集中力低下、疲労感が出現します。HPA軸の過活動によりコルチゾール分泌が亢進し、海馬の萎縮や前頭前野の機能低下が生じます。炎症性サイトカイン(IL-1β、TNF-α、IL-6)の増加も抑うつ症状に関与するとされています。近年、神経可塑性の低下やBDNF(脳由来神経栄養因子)の減少も注目されています。
症状・診断・治療
症状
中核症状として抑うつ気分(憂うつ、悲しい、空虚感)と興味・関心の喪失(アンヘドニア)があります。認知症状では思考制止、集中力低下、決断困難、記憶力低下、自責感、罪悪感、無価値感を認めます。身体症状として睡眠障害(入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒)、食欲低下、体重減少、疲労感、精神運動制止または焦燥が出現します。重篤な症状として希死念慮、自殺念慮、精神病症状(妄想、幻覚)を認めることがあります。日内変動では午前中に症状が強く、夕方に軽減する傾向があります。仮面うつ病では身体症状が前景に立ち、抑うつ気分が目立たないこともあります。
診断
診断はDSM-5やICD-11の診断基準に基づいて行われます。主要抑うつエピソードの診断には、抑うつ気分または興味・関心の喪失のいずれかを含む5つ以上の症状が2週間以上持続し、機能の著しい低下を伴うことが必要です。重症度評価にはハミルトンうつ病評価尺度(HAM-D)、ベック抑うつ質問票(BDI)、患者健康質問票(PHQ-9)などが用いられます。鑑別診断では双極性障害、適応障害、不安障害、器質性精神障害、薬物性うつ病などを除外します。身体検査と血液検査により甲状腺機能低下症、貧血、電解質異常などの身体疾患を除外することも重要です。
治療
治療は薬物療法と精神療法を組み合わせて行います。薬物療法ではSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)、SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)が第一選択薬となります。効果発現まで2-4週間を要し、6-8週間の十分な期間を経て効果判定を行います。精神療法では認知行動療法(CBT)、対人関係療法(IPT)が有効性が確立されています。重症例では修正型電気けいれん療法(mECT)も考慮されます。維持治療では再発予防のため6ヶ月から1年以上の薬物療法継続が推奨されます。心理社会的介入として社会復帰支援、家族教育、環境調整も重要な治療要素です。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 自殺リスク状態:抑うつ気分と希死念慮に関連した自殺の危険性
- 非効果的個人コーピング:ストレス対処能力の低下に関連した適応困難
- 社会的孤立:抑うつ症状による対人関係の回避と社会参加の減少
ゴードン機能的健康パターン
認知・知覚パターンでは思考制止、集中力低下、記憶力低下、判断力低下の程度を評価し、日常生活への影響を把握します。自責感や罪悪感の程度、現実検討能力、病識の有無も重要な評価項目です。睡眠・休息パターンでは睡眠の質・量・パターンを詳細にアセスメントし、日内変動との関連を評価します。対処・ストレス耐性パターンではストレス要因、従来の対処方法、支援システム、危機対処能力を評価し、自殺リスクを継続的にアセスメントします。
ヘンダーソン14基本的ニード
安全で健康的な環境を維持し、他者に危険が及ばないようにするでは自殺リスクの評価と安全確保が最優先となります。希死念慮の有無、自殺計画の具体性、手段へのアクセス、制止要因を継続的に評価します。コミュニケーションをとるでは抑うつ症状による意思疎通の困難さを評価し、効果的なコミュニケーション方法を検討します。働くこと、達成感を得るでは職業機能への影響を評価し、段階的な社会復帰を支援します。
看護計画・介入の内容
- 自殺予防・安全確保:継続的な自殺リスクアセスメント、安全な環境の提供、希死念慮の表出促進、危険物の除去、24時間の見守り体制確立、家族・医療チームとの情報共有
- 治療的関係性の構築:受容的・共感的態度での関わり、治療的コミュニケーション技法の活用、患者の思いや感情の表出支援、小さな変化への気づきと肯定的フィードバック
- 日常生活支援・活動促進:基本的生活リズムの確立支援、段階的な活動拡大、達成可能な目標設定、服薬管理と副作用観察、栄養・睡眠・運動の改善支援
よくある疑問・Q&A
Q: うつ病は治る病気ですか?薬は一生飲み続けなければならないのでしょうか?
A: うつ病は適切な治療により改善が期待できる疾患です。約70-80%の患者さんで薬物療法により症状の改善が見られます。薬物療法は急性期治療で2-3ヶ月、継続治療で4-9ヶ月、維持治療で6ヶ月から1年以上継続することが推奨されますが、一生服薬が必要というわけではありません。初回エピソードで十分に改善した場合は段階的に減薬・中止が可能です。ただし、再発を繰り返す場合は長期間の維持治療が必要になることもあります。医師と相談しながら個別に治療計画を立てることが重要です。
Q: 抗うつ薬を飲むと依存になったり、性格が変わったりしませんか?
A: 抗うつ薬は依存性がなく、性格を変える薬でもありません。抗うつ薬は脳内の神経伝達物質のバランスを整えることで、うつ病により低下した脳の機能を本来の状態に戻す働きをします。「薬に頼りたくない」という気持ちは理解できますが、うつ病は脳の病気であり、適切な薬物治療は回復に必要です。副作用への心配がある場合は医師に相談し、薬の種類や量を調整することで多くの場合改善できます。精神療法との併用により、より効果的な治療が可能です。
Q: 家族や職場の人にはどう説明すればよいでしょうか?
A: うつ病は脳の病気であり、「気持ちの問題」や「甘え」ではないことを理解してもらうことが重要です。風邪や糖尿病と同じように治療が必要な病気であることを説明し、十分な休養と治療により回復が期待できることを伝えます。職場では産業医や人事担当者と相談し、必要に応じて診断書を提出して適切な配慮を求めます。段階的な復職や勤務時間の調整などの支援を受けることができます。家族には病気への理解と適切な支援方法について説明し、過度な励ましや批判的態度は避けてもらうよう依頼します。
Q: 再発を防ぐにはどうすればよいですか?日常生活で気をつけることはありますか?
A: 再発予防には薬物療法の継続、ストレス管理、生活習慣の改善が重要です。規則正しい生活リズムを保ち、十分な睡眠(7-8時間)、適度な運動、バランスの取れた食事を心がけてください。ストレス対処法を身につけ、完璧主義的な考え方を見直すことも大切です。社会的支援(家族、友人、同僚)を活用し、一人で抱え込まないようにします。認知行動療法で学んだ技法を日常生活で実践し、早期警告サイン(睡眠障害、食欲低下、意欲低下)に気づいたら早期に医療機関を受診してください。定期的な通院により病状を医師と共有することも重要です。
まとめ
うつ病は現代社会における重要な健康問題として、適切な理解と治療により回復が期待できる疾患です。脳の機能異常による病気であり、患者さんの意志の弱さや性格の問題ではないことを理解することが支援の出発点となります。
看護の中核は治療的関係性の構築と自殺予防です。患者さんの苦痛に共感し、受容的・非批判的な態度で関わることで、安心して治療に取り組める環境を提供することが重要です。自殺リスクアセスメントは継続的に行い、安全確保を最優先とした看護介入が求められます。
薬物療法の支援では、効果発現までに時間がかかることや副作用について十分に説明し、治療継続への動機づけを行うことが重要です。精神療法(特に認知行動療法)の効果についても患者さんに伝え、多角的なアプローチの必要性を理解してもらいます。
社会復帰支援では、患者さんのペースに合わせた段階的なアプローチが重要です。過度な期待や圧力は症状悪化につながるため、小さな改善を評価し、達成可能な目標設定を支援することが大切です。
家族教育も重要な看護の視点です。家族の理解と適切な支援は患者さんの回復に大きく影響するため、疾患の正しい知識、接し方のポイント、再発予防の方法について指導する必要があります。
実習では患者さんの個別性を重視し、その人の価値観や生活背景を理解した上で看護計画を立案することが重要です。うつ病は回復に時間がかかる疾患ですが、適切な治療と支援により多くの患者さんが社会復帰を果たしています。希望を持って治療に取り組めるよう、患者さんと家族を支援し、その人らしい生活の再構築に向けて包括的なケアを提供していきましょう。
この記事の執筆者

・看護師と保健師
・プリセプター、看護学生指導、看護研究の経験あり
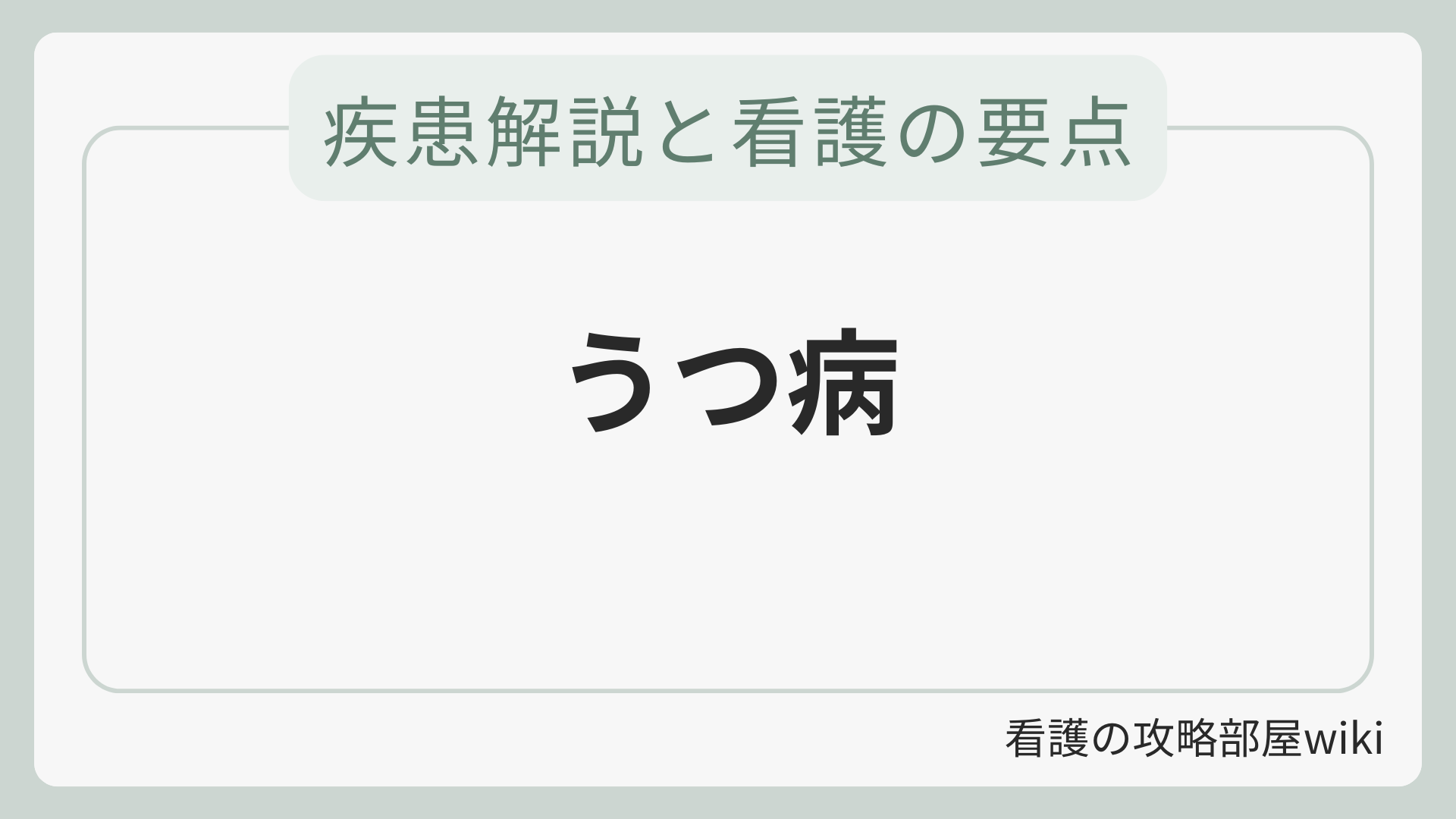
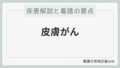
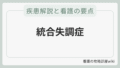
コメント