疾患概要
定義
大腸がんとは、大腸(結腸と直腸)の粘膜から発生する悪性腫瘍です。大腸は、盲腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸、直腸に分けられ、部位により結腸がんと直腸がんに大別されます。大腸がんの約60%はS状結腸と直腸に発生します。多くは腺腫というポリープから発生し、数年かけて徐々にがん化すると考えられています。
疫学
大腸がんは、日本において最も罹患者数が多いがんです。年間約15万人が大腸がんと診断され、死亡者数は年間約5万人で、がんによる死亡原因の第2位となっています。男女比はやや男性に多く、発症年齢のピークは60〜70歳代ですが、近年は若年者の発症も増加傾向にあります。
欧米諸国に比べて日本は大腸がんの罹患率が低かったのですが、食生活の欧米化に伴い、1990年代以降急増しています。早期発見により治癒率が高いがんであり、検診の重要性が強調されています。
原因
大腸がんの発生には、環境因子と遺伝因子の両方が関与しています。
環境因子(生活習慣)
食生活が最も重要な危険因子です。高脂肪・高タンパク質の食事、特に赤身肉や加工肉の過剰摂取は大腸がんのリスクを高めます。一方、食物繊維の摂取不足も危険因子となります。その他、肥満、運動不足、喫煙、過度のアルコール摂取などもリスクを高めます。
遺伝因子
大腸がん患者さんの約5〜10%は遺伝性です。家族性大腸腺腫症やリンチ症候群などの遺伝性疾患では、若年で大腸がんを発症するリスクが非常に高くなります。また、血縁者に大腸がんの患者さんがいる場合、そうでない人に比べて2〜3倍リスクが高まります。
その他
潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患は、長期間にわたる慢性炎症により大腸がんのリスクが高まります。
病態生理
大腸がんの多くは、腺腫(良性のポリープ)から発生すると考えられています。これを腺腫-癌連続説といいます。正常な粘膜から腺腫が形成され、それが数年から十数年かけて徐々にがん化していきます。腺腫のすべてががんになるわけではありませんが、大きな腺腫ほどがん化のリスクが高くなります。
大腸がんは、粘膜から発生し、粘膜下層、固有筋層、漿膜下層、漿膜へと徐々に深く浸潤していきます。がんの進行度は、この浸潤の深さ(深達度)とリンパ節転移の有無、遠隔転移の有無により決定されます。
がん細胞が大腸壁を越えて周囲のリンパ節に転移すると、リンパ節転移となります。大腸がんは、まず腸管の近くのリンパ節に転移し、次第に遠くのリンパ節へ広がっていきます。
さらに進行すると、血流に乗ってがん細胞が全身に運ばれ、遠隔転移を起こします。大腸がんの遠隔転移で最も多いのは肝臓です。これは、大腸からの血液が門脈を通って肝臓に流れ込むためです。次いで肺、腹膜、骨などに転移します。
大腸がんによる症状は、腫瘍の大きさ、部位、進行度により異なります。右側結腸がんは腸管の内腔が広いため、かなり大きくなるまで症状が出にくく、貧血や腹部腫瘤で発見されることが多いです。左側結腸がんやS状結腸がん、直腸がんは、内腔が狭いため、比較的早期から便通異常や血便などの症状が出現します。
腫瘍が大きくなると、腸管の内腔を狭窄させ、便の通過障害を起こします。完全に閉塞すると腸閉塞となり、緊急手術が必要です。また、腫瘍表面は脆く出血しやすいため、血便の原因となります。
症状・診断・治療
症状
早期大腸がん
早期の大腸がんは、ほとんど自覚症状がありません。検診の便潜血検査や、他の疾患の検査で偶然発見されることが多いです。これが、検診が重要な理由です。
進行大腸がん
症状は、がんの部位により異なります。
右側結腸がん(盲腸、上行結腸): 腸管の内腔が広いため、かなり進行するまで症状が出ません。慢性的な出血により貧血(ふらつき、動悸、息切れ)で発見されることが多いです。また、右下腹部に腹部腫瘤を触れることもあります。
左側結腸がん(下行結腸、S状結腸): 腸管の内腔が狭いため、比較的早期から症状が出ます。便通異常(便秘と下痢の繰り返し)、便が細くなる、血便、腹痛、腹部膨満感などがみられます。
直腸がん: 最も多い症状は血便です。鮮血便や粘血便がみられます。痔と間違えやすいため、注意が必要です。その他、便が細くなる、残便感(排便後もすっきりしない感じ)、排便時の痛み、頻回の便意などがあります。
共通する症状
進行すると、全身症状として体重減少、食欲不振、全身倦怠感が出現します。腸閉塞を起こすと、激しい腹痛、嘔吐、排便・排ガスの停止がみられます。遠隔転移がある場合、肝転移では右上腹部痛や黄疸、肺転移では咳や血痰などの症状が出現することもあります。
診断
便潜血検査
大腸がん検診で最も一般的な検査です。便に混じった微量の血液を検出します。陽性の場合、大腸内視鏡検査などの精密検査が必要です。ただし、便潜血検査が陰性でも、大腸がんがないとは言い切れません。
大腸内視鏡検査
肛門から内視鏡を挿入し、大腸全体を観察する検査です。大腸がんの確定診断に最も有用です。腫瘍を直接観察でき、同時に組織を採取して病理検査(生検)を行うことで、がんの確定診断ができます。また、早期がんやポリープであれば、内視鏡で切除することも可能です。
注腸造影検査
バリウムを肛門から注入し、X線で大腸の形態を観察する検査です。近年は大腸内視鏡検査が主流となり、行われる機会は減っています。
CT検査・MRI検査
がんの進行度、周囲臓器への浸潤、リンパ節転移、遠隔転移の有無を評価します。治療方針の決定に重要です。直腸がんでは、骨盤MRIにより腫瘍の深達度や周囲組織への浸潤を詳細に評価できます。
腫瘍マーカー
血液検査でCEA(癌胎児性抗原)やCA19-9などの腫瘍マーカーを測定します。診断の補助や、治療効果の判定、再発の早期発見に用いられます。ただし、早期がんでは上昇しないことも多く、診断のための検査としては限界があります。
病期分類
大腸がんは、TNM分類とStage分類により病期が決定されます。Tは腫瘍の深達度、Nはリンパ節転移の程度、Mは遠隔転移の有無を示します。病期は0期からIV期まであり、数字が大きいほど進行しています。病期により治療方針と予後が大きく異なります。
治療
大腸がんの治療は、手術、化学療法、放射線療法を組み合わせて行います。
手術療法
大腸がんの根治的治療の中心は手術です。早期がんであれば、内視鏡的切除が可能です。内視鏡的粘膜切除術や内視鏡的粘膜下層剥離術により、開腹せずに治療できます。
進行がんでは、開腹手術または腹腔鏡下手術により、がんを含む腸管とリンパ節を切除します。結腸がんでは、がんの部位に応じて右半結腸切除術、左半結腸切除術、S状結腸切除術などが行われます。直腸がんでは、肛門からの距離により、前方切除術(肛門を温存)または直腸切断術(人工肛門造設)が選択されます。
近年、腹腔鏡下手術が普及し、傷が小さく、術後の回復が早いという利点があります。また、直腸がんでは、肛門温存を目指した肛門括約筋温存手術が積極的に行われています。
化学療法
進行がんや再発がん、遠隔転移がある場合に行われます。術後の再発予防(術後補助化学療法)としても用いられます。5-FU、オキサリプラチン、イリノテカン、分子標的薬(ベバシズマブ、セツキシマブなど)などが使用されます。
放射線療法
大腸がんでは、放射線療法は主に直腸がんに対して行われます。術前に照射して腫瘍を縮小させたり、術後の局所再発予防のために行われたりします。また、骨転移による痛みの緩和など、症状緩和目的でも使用されます。
人工肛門(ストーマ)
直腸がんで肛門に近い位置にがんがある場合や、腸閉塞で緊急手術を行った場合、人工肛門が造設されることがあります。一時的なストーマ(後に閉鎖予定)と永久的なストーマがあります。ストーマ造設後は、ストーマケアの指導とセルフケア能力の獲得が重要です。
看護アセスメント・介入
よくある看護診断・問題
- 急性疼痛
- 栄養摂取消費バランス異常
- 下痢/便秘
- ボディイメージ混乱(ストーマ造設時)
- 不安
- 感染リスク状態
- 皮膚統合性障害リスク状態(ストーマ周囲)
ゴードン機能的健康パターン
栄養・代謝パターン
大腸がん患者さんは、腫瘍による消化管症状や、がんに伴う代謝亢進により栄養状態が悪化します。術前は、貧血や低栄養の改善が必要です。食事摂取量、体重、血清アルブミン値、ヘモグロビン値を評価し、必要に応じて栄養補助食品や輸液による栄養補給を検討します。
術後は、腸管の機能回復を待ちながら、段階的に経口摂取を再開します。最近では、術後早期から飲水や経口摂取を開始するERAS(術後回復力強化)プログラムが導入されています。ストーマを造設した場合は、食事による便の性状への影響を観察し、適切な食事指導を行います。
排泄パターン
大腸がんの主要な症状の一つが排便異常です。便秘、下痢、血便、細い便、残便感などを詳細に聴取します。排便回数、便の量、性状、色、血液の混入の有無を観察し、記録します。
術後は、腸蠕動の回復を確認します。排ガス、排便の有無、腹部膨満の程度、腸蠕動音を観察します。ストーマを造設した場合は、ストーマからの排泄物の量、性状、色を観察し、記録します。
活動・運動パターン
貧血や全身倦怠感により、活動耐性が低下します。術前の貧血の程度を評価し、必要に応じて輸血を検討します。
術後は、早期離床が推奨されます。術後合併症(肺炎、深部静脈血栓症、腸閉塞など)の予防と、腸蠕動の回復促進のため、術後早期から歩行を促します。ただし、疼痛により活動が制限されることもあるため、鎮痛薬の適切な使用と、患者さんのペースに合わせた離床支援が必要です。
自己知覚・自己概念パターン
大腸がんの診断は、患者さんに大きな心理的衝撃を与えます。「がん」という言葉への恐怖、治療への不安、将来への心配など、さまざまな感情が生じます。特に、ストーマを造設する場合、ボディイメージの変化により自尊感情が低下し、社会復帰への不安が増大します。患者さんの感情を傾聴し、心理的サポートを提供することが重要です。
ヘンダーソン14基本的ニード
正常に飲食する
腫瘍による腸管狭窄や食欲不振により、食事摂取が困難になることがあります。少量頻回の食事、嗜好に合わせた食事内容の調整により、必要な栄養を確保します。腸閉塞のリスクがある場合は、消化のよい低残渣食を提供します。
術後の経口摂取再開時は、水分から開始し、流動食、三分粥、五分粥、全粥と段階的に進めます。摂取後の腹部症状(腹痛、腹部膨満、嘔吐など)を観察します。
正常に排泄する
前述の通り、排便状況の観察が重要です。血便は、大腸がんの重要な症状ですが、痔と間違えやすいため、注意深く観察します。
術後は、腸蠕動の回復を促すため、早期離床と歩行を促します。ストーマを造設した場合は、ストーマケアの方法を指導し、患者さんが自立してケアできるよう支援します。ストーマ装具の選択、交換方法、皮膚保護、トラブル時の対応などを段階的に指導します。
身体を動かし、望ましい肢位を保持する
術後の早期離床は、合併症予防と腸蠕動回復のために非常に重要です。しかし、術後の疼痛や、ストーマ造設による不安から、患者さんは動くことを躊躇することがあります。鎮痛薬を適切に使用し、創部やストーマを保護しながら体位変換や歩行を支援します。
身体の清潔を保ち、身だしなみを整え、皮膚を保護する
術後は、創部の観察とケアが重要です。創部の発赤、腫脹、浸出液、離開の有無を確認し、感染徴候の早期発見に努めます。
ストーマを造設した場合、ストーマ周囲の皮膚トラブルを予防することが非常に重要です。排泄物による皮膚の浸軟、びらん、潰瘍を防ぐため、適切な装具の選択と皮膚保護が必要です。また、患者さんがストーマを受け入れ、セルフケアできるよう、段階的に指導します。
自分の感情、欲求、恐怖、あるいは気分を表現してコミュニケーションをとる
がんの診断、手術、ストーマ造設など、患者さんは多くのストレスにさらされます。不安、恐怖、悲しみ、怒りなど、さまざまな感情を抱えています。これらの感情を表出できる環境を整え、傾聴する姿勢が大切です。また、ストーマ造設者の会(オストメイト)を紹介し、同じ経験をした人との交流の機会を提供することも有効です。
看護計画・介入の内容
- 術前オリエンテーション: 手術の流れ、術後の経過、痛みのコントロール方法、早期離床の重要性などを説明し、不安を軽減する
- 栄養状態の評価: 食事摂取量、体重、血清アルブミン値、ヘモグロビン値を測定し、栄養状態を評価する
- 排便状況の観察: 排便回数、便の性状、血便の有無を詳細に観察し、記録する
- バイタルサインの監視: 体温、血圧、脈拍、呼吸数を定期的に測定し、術後合併症の早期発見に努める
- 疼痛コントロール: 痛みの部位、程度をペインスケールで評価し、鎮痛薬を確実に投与する。患者自己調節鎮痛法(PCA)を使用する場合は、使用方法を指導する
- 腸蠕動の観察: 術後、排ガス、排便の有無、腹部膨満の程度、腸蠕動音を継続的に観察する
- 創部の観察: 創部の発赤、腫脹、浸出液、離開、感染徴候を観察する。ドレーンがある場合は、排液の量、性状、色を観察し、記録する
- 早期離床の促進: 術後の早期離床の重要性を説明し、患者さんのペースに合わせて歩行を支援する。深呼吸や咳嗽の指導も行い、呼吸器合併症を予防する
- 経口摂取の再開支援: 医師の指示に従い、水分摂取から開始し、段階的に食事を進める。摂取後の腹部症状を観察する
- ストーマケアの指導: ストーマ造設者には、ストーマケアの方法を段階的に指導する。装具の選択、交換方法、皮膚保護、トラブル時の対応、日常生活の工夫などを具体的に説明する
- ストーマ周囲皮膚の観察: ストーマ周囲の皮膚の状態を観察し、びらん、潰瘍、感染の有無を確認する。適切な皮膚保護剤を使用する
- 心理的サポート: 不安や恐怖を傾聴し、患者さんの尊厳を守る。ストーマ造設者には、ボディイメージの変化への適応を支援する
- 患者・家族教育: 疾患の理解促進、術後の生活管理、食事の注意点、ストーマケア(該当者)、症状出現時の対応、定期受診の重要性について説明する
- 退院調整: 退院後の生活環境を評価し、必要に応じて訪問看護やストーマ外来の紹介を行う
よくある疑問・Q&A
Q: 大腸がんと痔の血便は、どのように見分けるのですか?
A: 血便は、大腸がんの重要な症状ですが、痔でも血便が出るため、見分けが難しいことがあります。一般的に、痔による出血は、排便時に鮮やかな赤い血が便の表面に付着したり、トイレットペーパーに付いたりします。排便時の痛みを伴うことが多く、出血は排便に関連しています。一方、大腸がんによる血便は、血液が便に混じっていることが多く、暗赤色や黒っぽい色をしていることもあります。排便時の痛みは少なく、便通異常(便秘と下痢の繰り返し、便が細くなるなど)を伴うことがあります。ただし、これらはあくまで目安であり、自己判断せずに医療機関を受診することが重要です。「痔だと思っていたら大腸がんだった」というケースは少なくありません。血便があれば、必ず大腸内視鏡検査などの精密検査を受けるべきです。
Q: ストーマ(人工肛門)を造設すると、どのような生活になるのですか?
A: ストーマを造設すると、腹部に排泄口ができ、ストーマ装具(パウチ)を装着して便を受け止めます。最初は戸惑いや不安を感じるかもしれませんが、適切なケアと工夫により、ほとんどの日常生活が可能です。入浴、旅行、スポーツなども楽しめます。ストーマ装具は、目立たない薄型のものが開発されており、衣服の上からは分かりません。ただし、便の排泄をコントロールできないため、定期的な装具の交換が必要です。また、食事により便の性状が変化するため、ガスや臭いが気になる食品は控えるなどの工夫が必要です。看護師は、患者さんがストーマを受け入れ、自立してケアできるよう、段階的に指導します。また、ストーマ造設者の会(オストメイト)では、同じ経験をした仲間との交流や情報交換ができ、心理的なサポートも得られます。
Q: 大腸がんは遺伝するのですか? 家族に大腸がんの人がいたら、自分もなりやすいですか?
A: 大腸がんの約5〜10%は遺伝性です。家族性大腸腺腫症やリンチ症候群などの遺伝性疾患では、若年で大腸がんを発症するリスクが非常に高くなります。また、遺伝性疾患でなくても、血縁者に大腸がんの患者さんがいる場合、そうでない人に比べて2〜3倍リスクが高まるとされています。特に、若年で発症した血縁者がいる場合や、複数の血縁者が大腸がんになっている場合は、リスクが高まります。ただし、大腸がんの多く(約90〜95%)は遺伝ではなく、生活習慣などの環境因子が主な原因です。家族歴がある方は、より若い年齢から定期的な大腸がん検診を受けることが推奨されます。また、禁煙、適度な運動、バランスの取れた食事など、生活習慣の改善によりリスクを下げることができます。
Q: 大腸がんの手術後、どのくらいで普通の生活に戻れますか?
A: 回復のスピードは、手術の方法、がんの進行度、患者さんの年齢や全身状態により異なります。腹腔鏡下手術の場合、開腹手術に比べて侵襲が少ないため、回復が早い傾向があります。一般的に、入院期間は7〜14日程度です。退院後は、徐々に日常生活に戻りますが、完全に回復するには1〜3ヶ月かかることもあります。軽い家事や散歩は退院後すぐに始められますが、重い物を持つ、激しい運動をするなどは、医師の許可が出るまで控えます。仕事復帰の時期は、仕事の内容により異なりますが、デスクワークであれば術後1ヶ月程度、肉体労働であれば2〜3ヶ月程度が目安です。ストーマを造設した場合は、ストーマケアに慣れるまで時間がかかることもあります。焦らず、自分のペースで回復を目指すことが大切です。
Q: 大腸がんを予防するために、日常生活で気をつけることは何ですか?
A: 大腸がんの予防には、生活習慣の改善が重要です。食生活では、赤身肉や加工肉の摂取を控え、食物繊維を多く含む野菜、果物、全粒穀物を積極的に摂ることが推奨されます。また、適度な運動(週に150分以上の中程度の運動)は、大腸がんのリスクを下げることが分かっています。肥満もリスク因子なので、適正体重を維持することが大切です。禁煙と節度あるアルコール摂取(1日あたり純アルコール換算で約20g以下)も重要です。そして、最も重要なのは定期的な検診です。40歳以上の方は、年に1回の便潜血検査を受けることが推奨されます。便潜血検査が陽性の場合や、血便などの症状がある場合は、必ず大腸内視鏡検査を受けましょう。大腸がんは、早期発見により治癒率が非常に高いがんです。検診を受けることが、最も効果的な予防法といえます。
まとめ
大腸がんは、日本で最も罹患者数が多いがんですが、早期発見により治癒率が高い疾患です。多くは腺腫というポリープから発生し、数年かけて徐々にがん化します。主な原因は、高脂肪・高タンパク質の食事、食物繊維不足、肥満、運動不足などの生活習慣です。
症状は、がんの部位により異なりますが、血便、便通異常、便が細くなる、腹痛、貧血などがみられます。ただし、早期がんは無症状のことが多いため、定期的な検診が非常に重要です。便潜血検査と大腸内視鏡検査により診断します。
治療の中心は手術療法です。早期がんでは内視鏡的切除、進行がんでは開腹手術または腹腔鏡下手術により、がんを含む腸管とリンパ節を切除します。直腸がんでは、肛門に近い場合、人工肛門(ストーマ)が造設されることがあります。進行がんや転移がある場合は、化学療法や放射線療法も行われます。
看護のポイントは、術前の栄養状態の改善、術後の疼痛コントロール、早期離床の促進、腸蠕動の回復の観察、創部管理です。ストーマを造設した場合は、ストーマケアの指導と心理的サポートが非常に重要となります。患者さんがストーマを受け入れ、自立してケアできるよう、段階的に支援します。
また、がんの診断を受けた患者さんの心理的ショックは大きく、不安や恐怖に寄り添うケアが重要です。特にストーマ造設者は、ボディイメージの変化により自尊感情が低下することがあるため、継続的な心理的サポートが必要です。
実習では、患者さんの排便状況を詳細に観察し、便の性状や血便の有無を正確に記録する力を養いましょう。また、術後の腸蠕動の回復を評価し、早期離床を促進する看護介入の重要性を理解してください。ストーマを造設した患者さんには、尊厳を守りながら、セルフケア能力の獲得を支援する姿勢が大切です。大腸がんは、適切な治療により良好な予後が期待できる疾患です。患者さんが希望を持って治療に臨めるよう、根拠に基づいた看護を実践していきましょう。
免責事項
本記事は教育・学習目的の情報提供です。
・一般的な医学知識の解説であり、個別の患者への診断・治療の根拠ではありません
・実際の看護実践は、患者の個別性を考慮し、指導者の指導のもと行ってください
・記事の情報は公開時点のものであり、最新の医学的知見と異なる場合があります
・本記事を課題としてそのまま提出しないでください
・正確な情報提供に努めていますが、内容の完全性・正確性を保証するものではありません
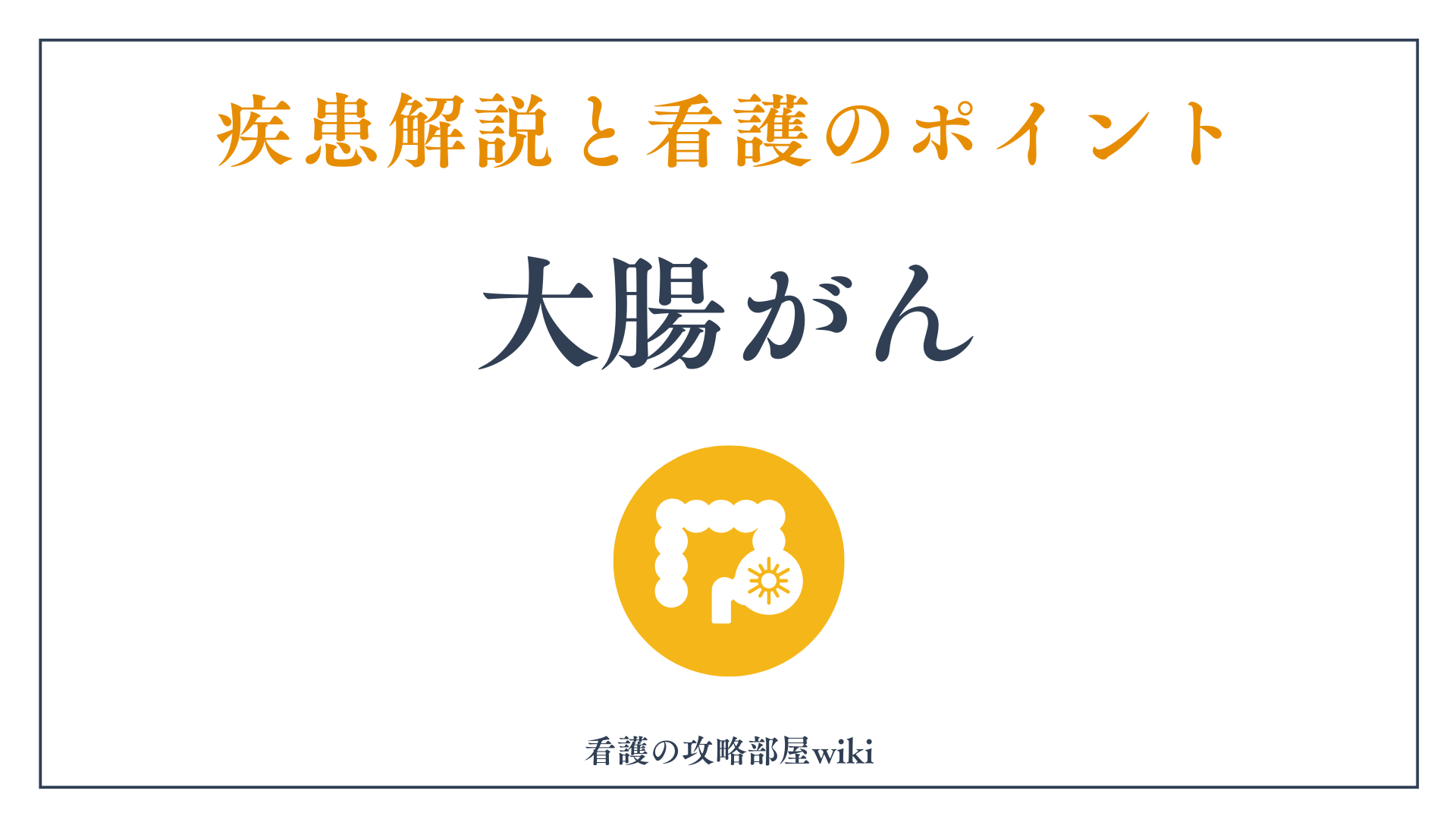


コメント